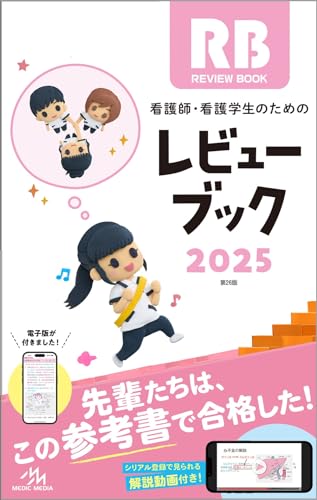【2025年】「精神疾患」のおすすめ 本 161選!人気ランキング
- 明日からできる訪問看護管理 改訂2版: これだけはおさえておきたい
- ~1日10分で自分を浄化する方法~マインドフルネス瞑想入門
- 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え
- 精神疾患にかかわる人が最初に読む本
- 在宅ケアナースポケットマニュアル
- 精神科の薬がわかる本 第4版
- 精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本 "横綱級"困難ケースにしないための技と型
- 双極性障害 第3版: 病態の理解から治療戦略まで
- 訪問看護業務の手引 令和4年4月版
- DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引
この本は、マインドフルネス瞑想を通じて心を整え、ストレスや不安を軽減し、自己変革を促す方法を紹介しています。内容は、瞑想の始め方や実践のコツ、瞑想の仕組み、日常生活でのマインドフルな過ごし方に分かれています。著者は瞑想とヨガの講師で、世界各国での経験を基にしています。
本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。
10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。
『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。
この書籍は、精神医学の基本知識をイラストを用いてわかりやすく解説した入門書です。精神症状や疾患を理解し、他者との関わりを改善するための内容が含まれています。目次には、精神症状の分類、主要な精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症など)、および治療法(環境調整、精神療法、薬物療法)が示されています。著者の西井重超は、日本精神神経学会の専門医で、精神医学教育に携わっています。
双極性障害に関する包括的な入門書の改訂第3版で、歴史、疫学、症状、診断、治療、薬理、ゲノム研究、病態仮説などの情報を網羅。症例を交えつつ、読みやすく理解しやすい内容となっており、双極性障害の全体像を把握できる一冊。
『訪問看護ステーション必携』は、訪問看護ステーションの運営に必要な介護保険と医療保険の業務を解説したガイドです。ステーションの開設から訪問看護の実施、請求手続きまでを図表を用いてわかりやすくまとめています。また、業務に関連する様式や法令、通知を網羅しており、介護保険制度の概要やサービスコード表も含まれています。
創業から15年で年間売上30億円、社員数600人超! 訪問看護のパイオニアは、いかにして急成長を遂げたのか。 独自の高品質サービスで高収益を生み出し、 東京都城南エリアで最大規模の在宅医療事業者へ拡大した ソフィアメディ株式会社の創業者が明かす事業成功の秘訣。 地域シェアNo.1を獲得するための営業戦略、マーケティングの判断基準、 女性スタッフが輝く職場環境づくり、長期事業計画の立て方など、 在宅医療・介護サービスの経営者・従事者が知りたい経営ノウハウが満載! 第1章 訪問看護の業界事情と事業成功の基本条件 1 経営の実務目線 2 ソフィアメディ創業時の経営戦略 3 質の高さは利益に直結する 4 儲かる訪問看護ステーション3つの秘訣 5 スケールメリットで経営の安定化を図る 6 専門職との一体感・人間関係バランスの取り方 7 商圏の考え方と市場占有率の特性 第2章 訪問看護ステーションの立ち上げ方 安定・成功への方策 1 マーケティングの判断基準 2 競合の実情把握と手の打ち方 3 売上配分比率と概算損益計算書で経営のパターンを検討する 4 次年度の売上配分を検討する3つのモデルケース 5 訪問看護ステーションにおける訪問リハビリの考え方とリスクヘッジ 6 内装や什器、備品、IT設備などデコレーションのこだわり 7 女性8割の医療職集団のマネジメント要領 第3章 地域シェアNo.1を実現するための社長の営業・販売姿勢 1 社長自らがお客様のところを回る 2 お客様の要求を掴む(お客様や紹介先、地域活動からの情報収集等) 3 得意先をABC分析に基づき判断する 4 ランチェスター戦略を踏まえた営業戦略 5 営業方法を駆使して差別化 清掃ボランティアの恩恵 6 クレーム処理とトラブル対処の徹底 第4章 内部体制づくりと現場環境整備の要諦 1 内部体制のつくり方 2 人事・総務部門の体制づくりにおけるポイント 3 組織体制と現場環境の整備 4 訪問看護・リハビリにもICT化の波 5 ソフィアメディにおける問題解決の実務 第5章 訪問看護ステーションの繁栄に向けた社長の経営計画 1 ただの熱い想い、粗野な望み、漠然とした夢を経営理念に昇華させる 2 戦略を構成する経営思想と実務の概念化 3 訪問看護ステーションの超簡略長期事業計画のつくり方 第6章 ソフィア経営塾で将来の幹部・起業家を育成 1 健全経営を継続できる経営者を育成する 2 弟子の成長が何よりうれしい
著者は13年間うつ病に苦しんだ後、双極性障害と診断され、治療を通じて回復に向かう。彼の経験をもとに、双極性障害の理解や日常生活のコツを伝えるピアサポートブックを執筆。内容は、双極性障害の症状や治療法、上手に付き合う方法などを含む。著者は現在、ピアサポート活動にも積極的に取り組んでいる。
本書は、脳内科医が「脳の使い方」を改善する方法を紹介しています。悩みやストレスを軽減するために「脳の練習」が重要であり、具体的な行動例として、視線の動かし方や反対の手を使うこと、複数の散歩コースを持つことなどが挙げられています。著者は、脳の機能を活性化させることで、やる気や記憶力、対人関係の改善を図る方法を提案しています。
本書は、精神医学の基礎知識をわかりやすく解説した入門書で、研修医や看護師向けに精神疾患の患者への初期対応を説明しています。著者の森皆ねじ子は、イラストを用いて精神科治療が必要な患者を適切に見つけ、専門家に繋げるための知識を提供します。内容は、心の病の概念や各種精神疾患(統合失調症、躁うつ病、うつ病、神経症、人格障害、子どもの精神障害、依存症)についての解説が含まれています。
精神保健福祉の制度やサービスをわかりやすく解説。初めて精神科で働く人や学生におすすめ。2024年施行の改正法に対応した最新版 精神科領域の全体像をつかんで現場の支援に活かす!改正精神保健福祉法(2023年・2024年施行)に対応した最新版!精神疾患・精神障害の種類や症状は患者さんごとに多種多様。多くの場合、治療は長期に及ぶため、症状と付き合いながら仕事をしたり、いくつもの課題を抱えながら生活している方が少なくありません。そのため、薬や心理療法などの医療的ケアとともに、様々な支援制度やサービスを患者さんの状況に合わせて活用することが重要です。こころの病や問題には、医師をはじめ、看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、作業療法士など様々な専門職が関わります。それぞれの専門領域の違いから、「症状や治療の知識は豊富だが、制度やサービスについては詳しくない」「精神保健福祉士の常駐がない現場で、患者さんからの制度や法律に関する質問に対応できない」ということもあります。本書は、主に精神科にかかわる専門職や患者さんを支える家族などに向けて、精神保健福祉に関する制度・サービスをわかりやすく整理して紹介。2023年4月、2024年4月施行の改正精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)にも対応しています。精神疾患や精神障害の基礎知識もまとめており、初めて精神科に勤務する人や学生にも入門書としておすすめ。病院以外の場所で、課題を抱えて生活する人を支援する上でも役立ちます。【目次】第1章:精神保健福祉法の基本第2章:精神科の対象とは?第3章:精神科に関わる専門職第4章:精神疾患の治療法第5章:入院・医療制度の実際第6章:働く人のための精神保健福祉第7章:日常生活で活用できる支援制度【編著者】■二本柳 覚(にほんやなぎ・あきら)京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科講師。日本福祉大学福祉社会開発研究所客員研究所員。修士(福祉マネジメント:日本福祉大学)。社会福祉士、精神保健福祉士。【著者】■石井 佳葉(いしい・かよう)就実大学教育学部教育心理学科講師。博士(教育学:京都大学)。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。公認心理師、臨床心理士。■茂本 由紀(しげもと・ゆき)武庫川女子大学心理・社会福祉学部講師。博士(心理学:同志社大学)。公認心理師、臨床心理士。 はじめに第1章 精神保健福祉法の基本 ・そもそも精神保健福祉法ってどんな法律? ・精神障害者をめぐる法制度〈明治~昭和中期〉 ・精神障害者をめぐる法制度〈宇都宮病院事件~現在〉 ・精神保健に課題を抱える者も市町村の相談支援の対象に ・人権に配慮した精神科の入院制度 ・適切な精神科医療を実施するための制度 ・自傷他害の恐れのある状態の人を医療につなげる ・緊急入院が必要なのに拒否する患者さんへの対応 ・都道府県における精神保健福祉の中核機関 ・適切な医療や保護がなされているかを審査 ・各種支援を受けるための証明書 ・精神科病院での虐待防止のための取り組みを推進 COLUMN|依存症問題は「隣の家の話」ではありません第2章 精神科の対象とは? ・そもそも精神疾患って何? ・DSMとICDは何が違う? ・精神科と神経内科、心療内科はどう違う? ・成長過程で見えてくるつまずきの総称 ・統合失調症は脳と心の統合機能の障害 ・「落ち込む」「やる気が出ない」はうつ病のサイン? ・躁とうつの状態を繰り返す双極性障害 ・100人に1人がかかるパニック障害 ・おかしいと思っても止められない強迫性障害 ・PTSDの苦しみは千差万別 ・摂食障害は食行動を通じた心の叫び ・神経系に生じた異常はもとに戻らない ・医療領域以外の支援が欠かせない高次脳機能障害 ・認知症のタイプや進行度により症状は異なる ・人との関わりで問題を抱えやすいパーソナリティ障害 ・「疾患」ではないが、不随する不調には医療が必要 ・いつ生じるかわからない発作との付き合い方が重要 COLUMN|医療事務スタッフとの連携は欠かせない第3章 精神科に関わる専門職 ・様々な専門職と連携して治療にあたる司令塔 ・患者さんの心に寄り添う精神科看護師 ・地域生活をサポートし、疾病・再発の予防にも尽力 ・精神科医療と社会のパイプ役 ・心の安定を支える専門性の高い心理資格 ・心と身体のリハビリテーションで患者さんをサポート ・服薬指導で患者や家族をサポートする薬物治療の要 ・食事を通じて患者さんの心身をケア COLUMN|心理士・師は実際にどんな風に対応しているの?第4章 精神疾患の治療法 ・薬物療法は精神疾患で最初に行われる治療法 ・社会生活機能の訓練を行う精神科デイケア ・社会生活で必要なスキルを獲得するトレーニング ・無意識に着目し治療を進める心理療法 ・思考を受け入れ自分らしい人生を送るために ・家族を一つのシステムとして捉える心理療法 ・あるがままの姿勢を獲得していく日本独自の心理療法 ・その人の能力の状態を知って生活に生かす ・その人のパーソナリティを捉えて治療に生かす ・心理療法の効果とそのエビデンスの確認方法 COLUMN|改善が難しい疾病医に対する治療法第5章 入院・医療制度の実際 ・精神科に入院する際に必ず行われる「告知」 ・精神科病院への入院の中で最も基本的な形態 ・医療保護入院では、「家族等」の同意が必要 ・医療保護入院の入院期間に上限が定められた ・退院後のことを入院時から考えるシステム ・入院が長期化した場合に退院支援に向けた会議を開催 ・緊急な医療を必要とした時の相談・受診システム ・自傷他害の恐れのある場合に知事の命令で行われる入院 ・入院しても面会や電話は自由にできる? ・入院の医療費は手続きによって減額可能 ・患者さんの回復と社会復帰を目指して専門職が協働 ・「退院」だけではなく、「退院に至る過程」が大事 ・再発を防ぎ社会生活を続けるための継続的ケア ・心神喪失及び心神耗弱により罪を犯した人への司法精神医療 COLUMN|専門職が質の高い支援を継承し続けるために第6章 働く人のための精神保健福祉 ・職場でのメンタルヘルスへの取り組みが求められる時代 ・自身のメンタルヘルスの状況がわかる ・社員の悩みの解決を会社全体の利益につなげる ・社員の身体的・精神的健康を支援する医師 ・社内に相談できる仕組みがない場合はどうする? ・病気やケガで働けない場合にもらえるお金 ・精神疾患も労災認定される可能性がある ・休職中の過ごし方や、復職に向けた取り組みとは? ・部下の調子が悪い時、上司はどう対応する? ・復職するまでと、復職してからの社員へのサポート ・障害者雇用枠で就業するという選択 COLUMN|短時間労働の法定雇用率の算定見直しで広がる雇用機会第7章 日常生活で活用できる支援制度 ・障害により生活や仕事に制限を受けた場合の年金制度 ・精神障害者保健福祉手帳で受けられる様々なサービス ・社会復帰に向けた様々なサービスを規定した法律 ・家以外の居場所が欲しい時には? ・「また働きたい」と思った時に受けられる支援は? ・地域生活で困った時には社会福祉協議会へ ・急な出費など、お金の問題に対応する制度 ・生活保護はセーフティネットとして大事な制度 ・大事な財産を守るための制度 ・同じような体験をした人たちとの関わりで得られること COLUMN|精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを目指して
この書籍は、1年目の看護師が臨床現場での不安を乗り越えるためのコツをまとめたもので、Instagramで人気の看護師しゅーぞーさんが執筆しています。基礎的な看護技術や心の持ち方、日々の勉強法から急変時の対応まで、イラストや図解を用いてわかりやすく解説しています。また、先輩看護師にも役立つ指導方法についてのアドバイスも提供しています。全体を通じて、1年目の看護師の成長をサポートする内容となっています。
この書籍は、訪問看護ステーションの開設・運営・評価に必要な最新情報を網羅しており、2021年の介護報酬改定に対応しています。経営関連の内容が刷新され、感染症や災害対応に関する業務継続計画(BCP)やICTセキュリティ対策についても新たに取り上げています。また、科学的介護情報システム(LIFE)の活用についても触れています。新規開設を含む全ての訪問看護ステーションにとって必携の一冊です。
本書では、マリリン・モンローやアンディ・ウォーホル、ダイアナ妃など、歴史的な偉人12人が抱えていた心の問題を現代医学の視点から探求しています。彼らは各分野で偉業を成し遂げながらも、境界性パーソナリティー障害やうつ病、強迫性障害などの精神的な苦悩に悩まされていました。著者は、これらの偉才たちの人生を通じて、人間の心の複雑さと「生きづらさ」を浮き彫りにしています。
本書は、心理学の基本概念を生徒と先生の対話形式でわかりやすく解説する入門書です。心の働きが日常の行動や判断にどのように影響するかを科学的に理解することを目指しています。目次には性格、社会心理学、感情、記憶、臨床心理学などが含まれています。著者は東京大学の教授で、臨床心理学を専門としています。
この書籍は、訪問看護に関する包括的なガイドで、アセスメントから生活ケア、基本的な看護技術、病気別のケアまでを豊富な写真を用いて視覚的に解説しています。患者や家族の気持ちに寄り添い、医療チームと連携して最良のケアを提供するためのポイントが示されています。内容は、生活全体のアセスメント、医療の視点からの生活ケア、在宅での看護技術、病気に応じたケアに分かれています。著者は訪問看護の専門家であり、経験豊富な管理者です。
精神医学の多様な方法論を解説した定番教科書が2023年に改訂され、DSM-5-TR日本語版に準拠。発達障害や物質関連障害などの記載が更新され、具体的な症例やイラストが豊富に含まれ、学習や臨床実習、試験対策に役立つ実用的な一冊。
本書は、大坂なおみを世界一に導いたコーチ、サーシャ・バインが日本人向けに書いたメンタル教本です。ビジネスマンや学生、育児中の親など、夢を追う全ての人に向けて、心を強くする方法やプレッシャーへの対処法を紹介しています。内容には、自信の高め方や感情の扱い方、ストレスのリセット方法などが含まれ、エピローグでは大坂との別れについても触れています。著者は、テニスだけでなくビジネスにも役立つメンタルの重要性を強調しています。
本書は、双極性障害(双極症)の性格や対処法について解説したロングセラーの第2版です。双極性障害は統合失調症と並ぶ重大な精神疾患で、患者は長期間にわたって抑うつ症状を抱えることが多く、社会的なハンディキャップも生じやすいです。著者は臨床と研究の専門家で、最新の研究成果や豊富なQ&Aを通じて、診断や治療、患者との向き合い方を説明しています。目次は対処と治療、症状や経過、治療法、原因など多岐にわたります。
この本は看護師が行う基本的な手技「吸引・排痰法」について深く掘り下げ、臨床での実践に役立つ情報を提供しています。特に教科書には記載されていない具体的な困りごとの解決法を詳しく解説し、看護師や介護職、家族にも役立つ内容です。各レッスンでは、痰や吸引の技術、排痰法、体位ドレナージなどが紹介されており、実践的な知識を得ることができます。また、著者は看護師YouTuberとしても活動しており、学びを通じて看護の楽しさを伝えています。
本書は、ストレスフルな環境で心が不安定になりがちな人々に向けて、心を軽くするための実践的な方法やノウハウを提供します。休み方や「ひとり時間」の楽しみ方、ストレスを減らす雑談のコツ、簡単なレシピなどが紹介されており、日常に取り入れやすい内容です。各パートは1日1分から始められる実践的なアプローチで構成されています。
精神科医Tomyの著書は、心の負担を軽くするための「手放す」方法を提案し、シリーズ累計33万部を突破しています。彼の言葉は多くの人々に感銘を与え、心の悩みを解決する助けとなっています。書籍は、他人との関係や不安の捉え方、こだわりの減少などをテーマにし、実用的なアドバイスを提供。読者からは感謝の声が寄せられ、心の支えとなる一冊と評判です。
本書は、グーグルやフェースブックなどの企業が導入しているマインドフルネスについて、メリットとデメリットを考察し、実践のヒントを提供します。著者にはダニエル・ゴールマンやエレン・ランガーなどの著名人が含まれ、職場での導入理由や効果、簡単なテクニックも紹介されています。マインドフルネスの科学的根拠や歴史、リスクについても触れられています。
本書は、双極性障害(躁うつ病)の新しい対処法を提案しています。対人関係や社会リズムのトラブルに悩む人々に向けて、薬物療法以外のアプローチとして「対人関係・社会リズム療法(IPSRT)」を紹介。著者は精神医学の専門家で、対人関係療法の普及に尽力してきた水島広子氏です。内容は双極性障害の理解や療法の進め方について詳述されています。
本書は、メンタルを強化するためにやめるべき13の思考習慣を紹介しています。著者エイミー・モーリンは、人生の厳しい試練を乗り越えるためにこれらの習慣を捨てることを決意しました。全米で1000万人が読んだこのメソッドを通じて、読者は「最高で最強の自分」になるための心の訓練を学ぶことができます。内容は、自己哀れみや過去への執着、リスク回避など、メンタルの強さを妨げる習慣をやめることに焦点を当てています。
この入門書は、文系学生向けに心理学における統計の重要性と基本的手法を分かりやすく解説しています。内容は、統計の基礎から始まり、実践的な手法を学び、さらに深い理解へと進む3つのステップで構成されています。著者たちは心理学や神経科学の専門家であり、学生の視点を考慮した親切な学習ガイドです。
本書は、人気の産婦人科医である高尾美穂が、女性たちの心と体に寄り添いながら自己実現や人間関係、性に関する悩みなどに答える内容です。全9章構成で、自己理解や不安への対処法、コミュニケーション、女性の体についての知識、性の悩み、家族やパートナーシップのあり方、キャリア、人生の目標について語ります。また、著者の半生を綴ったエッセイも収録されています。
著者・安冨歩が五年かけて現代語訳した『老子の教え あるがままに生きる』は、抽象的な内容ながらも生きるための実践的な知恵を提供する書である。『老子』は変化と動的な世界観を重視し、固定観念の危険性を指摘。読者が日常生活を通じてその言葉の意味を理解し、豊かな生き方を見出す手助けをする。著者は、言葉に縛られず、変化を受け入れることの重要性を強調している。
この書籍は、訪問看護を始めたい看護師に向けて、在宅ケアのニーズが高まる中で「新人でもできる」ことに焦点を当てており、ステップごとに成長を実感できる構成でわかりやすく解説されています。
著者KAGAYAによる星景写真集は、月虹やオーロラ、天の川などの美しい瞬間を捉えた作品で、至高の「星景写真集」として紹介されています。KAGAYAは埼玉県出身の星景写真家で、デジタルペインティングの先駆者としても知られ、プラネタリウム映像クリエイターとしても活動しています。彼の作品は広く評価され、小惑星にも名が付けられています。
アート・ウルフの未発表作品集『電気を消したら、見えてくる景色』は、夜の世界に潜む美しい光景を捉えたネイチャー写真集です。モロッコの夜市やバリのファイヤーダンサー、南極の夕陽など、普段は見えない動物や人間、自然の姿を美しい構図で記録しています。目次には「星々と影」「夜に生きるもの」「夜を抱いて」「光の照らすもの」が含まれ、ウルフの60年にわたる写真家としてのキャリアが反映されています。
「ナースのメモ帳」は、累計35,000部を突破した人気の書籍で、20万人のフォロワーを持つ内容を集約しています。128種類の薬剤を見開きで比較し、患者の状態に応じた使い分けを分かりやすく解説。ナースや薬剤師が協力し、後輩指導にも役立つ情報が詰まったお守りのような一冊です。
この書籍は、訪問看護ステーションの運営に必要な介護報酬と診療報酬について詳しく解説しています。内容は3部構成で、第1部では訪問看護制度の概要と報酬改定について、第2部では実務に役立つQ&A形式で運営や指示、記録に関する疑問を解消し、第3部では関連法令や通知を収載しています。全体で500項目以上のQ&Aが収められ、初心者からベテランまで活用できる内容です。
読みながら行動や考えを改められ、少しずつ自身に変化を感じられる素晴らしい書籍です!
誰もが知る名著なので一度は目を通しておくべきだが、内容は冗長で個人的にはあまりはまらなかった。重要度×緊急度のマトリクスの話が一番重要で、そこだけ理解しておけばいい気がする。緊急度は低いが重要度が高いタスクになるべく長期的な視点で取り組めるようになるべき。
【精神疾患のある人へのチームアプローチがこの1冊でわかる!】 精神疾患のある人を地域で、チームで、支えるための知識・方法をわかりやすく解説。豊富な事例により、理解が深まります。 ◇かかわりのポイントがわかる 疾患・症状を丁寧に解説 統合失調症やうつ病、パーソナリティ障害など10の疾患・症状の特徴とそれをふまえた各疾患のある人へのかかわり方を詳しくまとめています。 ◇家族関係の読み解き方をやさしく理解 家族を「システム」としてとらえる考え方を、具体例を織り交ぜながらわかりやすく説明しています。 ◇利用者主体の多職種連携がわかる 3つの実践事例を通じて、ケアマネジャー、訪問看護師、相談支援専門員等多職種における役割分担や情報共有の方法を具体的に理解できます。 ◇精神疾患のある人を支える具体的なアプローチ方法も掲載 オープンダイアローグやTIC(トラウマ・インフォームドケア)といったかかわりの手法や考え方もわかりやすく解説しています。
本書は、ドイツの著名な心理学者シュテファニー・シュタールによる、心の奥底の「無意識のトリガー」にアプローチし、思考や行動パターンをリセットする方法を解説しています。著者は、過去の経験が現在の自分に与える影響を探り、内なる子供の声に耳を傾けることの重要性を強調。150万部以上の売上を誇るこのベストセラーは、自己理解を深め、人間関係や自己価値感の問題を解決する手助けをする内容となっています。
この書籍は、ストーリーを通じて心理テクニックを学ぶことができる内容です。目次には、日常生活や友人、対人関係、仕事、ビジネス、恋愛、自分を変える方法など、様々な心理学の応用が紹介されています。著者は精神科医のゆうきゆうで、心理学に関する多くの活動を行っています。
本書は、現役ナースが解剖生理学を1000点以上のイラストを用いてわかりやすく解説した入門書です。解剖学の基本から臨床で役立つ知識まで幅広く網羅しており、楽しく学べる内容になっています。看護学生や医療従事者におすすめで、基礎医学を学ぶ際に役立つ情報や豆知識も豊富に含まれています。著者は看護師でイラストレーターの角野ふち、監修には医学部教授や助教が関わっています。
著者の鍵井靖章は1971年兵庫県生まれの水中写真家で、大学在学中に伊藤勝敏氏に師事。1993年からオーストラリア、伊豆、モルディブで活動し、1998年に帰国してフリーランスとして独立。受賞歴には第15回アニマ賞や2003年の日本写真協会新人賞などがある。
この入門書は、日常生活で「怒り」に悩む人々に向けて、怒りの感情を理解し、上手にコントロールする方法「アンガーマネジメント」をわかりやすく解説しています。著者の安藤俊介は、日本にこの技術を普及させた第一人者で、実践的な手法を通じて読者が自分の感情をプラスに活かす手助けをします。目次では、怒りの仕組みや感情の抑え方、記録による「見える化」などが紹介されています。
この文章は、ICD-10における「精神および行動の障害」の分類についての注釈や診断カテゴリーのリストを示しています。具体的には、器質性精神障害、精神作用物質使用障害、統合失調症、気分障害、神経症性障害、パーソナリティ障害、知的障害、発達障害、行動および情緒の障害などが含まれています。また、臨床記述と診断ガイドライン、関連する他のICD-10項目のリストも付録として提供されています。著者は東京医科歯科大学や長崎大学の名誉教授など、専門家たちです。
この写真集は、カメラマン小林廉宜が世界20か国と国内7か所の森を撮影したもので、約220点の迫力ある写真を通じて人類共通の自然の財産を伝えています。著者は「楽園」の写真集で知られる三好和義の弟子であり、森との対峙をテーマにした旅の記録でもあります。
精神科で働く人向けの実践的アドバイス集の第3版。クレーマー対策や援助者のアイデンティティ維持、当事者や家族との接し方など、役立つ情報が満載で、初心者の不安を解消します。
統合失調症の方の回復力を高める、心穏やかに暮らすための接し方の工夫やヒントが満載!最強コンビによる集大成、遂に刊行! 第1章 統合失調症の人の気持ちを理解する 第2章 回復力を高める接し方 第3章 サポートの方法
「かんテキ」は、看護やコメディカル向けに循環器疾患の理解を深めるための実用書です。1,500点以上のイラストや図解を用いて、患者の病態や必要な対応を視覚的にわかりやすく解説しています。難しい医学用語を使わず、実際の臨床で役立つ知識を提供し、患者への説明や観察ポイントも明確にしています。具体的な症例や会話例を通じて、実践的なケアのイメージを持つことができる内容です。
この書籍は、肩こりや腰痛、ストレスなどの心身の不調を軽減するための運動が苦手な人向けに、簡単に続けられるヨガやストレッチを紹介しています。内容は、自律神経の解説をはじめ、リラックスや元気を出すポーズ、リフレッシュするためのエクササイズ、そしておすすめのメニューが含まれています。著者はイラストレーターの崎田ミナと医学博士の福永伴子です。
この書籍は、人間の行動を進化論の観点から解明する入門書であり、自然淘汰、性による繁殖、性淘汰、心の適応反応、心の病、脳の進化、知能の進化などのテーマを扱っています。著者は進化心理学や科学史の専門家であり、進化論に基づく人間の行動理解を深める内容となっています。
この書籍は「訪問看護が支える がんの在宅ターミナルケア」の改訂版で、がんだけでなく非がん疾患への支援や意思決定支援、がん疼痛アセスメント、看取りに関する内容を追加しています。訪問看護師にとって必携の一冊で、在宅医療やターミナルケアの動向、法的知識、プロセス、症状緩和、エンゼルケア、入退院支援、地域の連携など、幅広いトピックが網羅されています。
本書は、解剖学を熟知したストレッチトレーナーによるストレッチガイドで、効果的なストレッチをお悩み別に紹介しています。全32種目と3つのルーティーンストレッチの動画がQRコードで視聴可能で、詳細な解剖イラストとともに筋肉の役割や効果を解説。体が硬い人向けの「EASY」ストレッチも収録されています。ストレッチを習慣化することで、柔軟性向上や肩こり・腰痛の改善が期待でき、生活の質を向上させる内容です。著者は人気のストレッチ専門家、なぁさんです。
本書は、疾患や患者、看護、観察について感覚的に理解できる医療スタッフ向けの教科書です。ナースや医療従事者が臨床現場で必要な知識を視覚的に学べるよう、解剖イラストやケアの4コママンガが豊富に掲載されています。消化器疾患に特化し、患者対応や薬剤知識も詳しく解説。医師がナースの疑問に答えるQ&Aコラムもあり、実践的な知識を身につけることができます。難しい用語を使わず、図解やイラストで理解しやすくまとめられています。
この書籍は、自閉症とアスペルガー症候群を「自閉症スペクトラム」として一つの連続した状態として捉え、対人関係の苦手さや特有のこだわりなどの特徴を解説しています。10人に1人が抱える「生きづらさ」の原因を探り、早期発見や支援方法についても多角的に説明しています。著者は発達障害の専門家であり、臨床と研究に長年従事してきた精神科医です。
◆第1巻の特徴◆ 鮮度の高い事例や普遍的なハウツーを盛り込みながら,どの研究法にも共通する基盤的知識を解説。研究倫理も手厚く扱う。実証に基づく科学としての心理学が「なるほど!」と理解できて,もっと研究したくなる入門書。 第1部では,心理学研究に着手する技能や技術を身につけるにあたって,最低限知っておきたい知識を解説。第2部では,心理学研究に必要な技能や技術についてのハウツーを述べる。効果量や検定力分析,ベイズ統計学の基本的考え方などについても鮮度高く解説。 第3部では,研究を「公表する」にあたって研究者が心がけるべき倫理について手厚く解説。仮説の後づけ(HARKing), p値ハッキング(p-hacking)など問題のある研究実践(QRPs)への警鐘をならし,モラル違反を抑止する策について述べる。 ◆第1巻 主なもくじ◆ 序章 心理学とは何か ―第1部 心理学を「研究する」ということ― 第1章 心理学のなりたち:心理学史 第2章 研究の準備:心理学研究の基礎知識 第3章 研究の準備:先行研究の探し方 ―第2部 心を「測定する」ということ― 第4章 研究の基礎:研究法概説 第5章 研究の基礎:人間を対象とする測定における諸問題 第6章 データの中身を知る:記述統計 第7章 データから対象を見通す:推測統計 ―第3部 研究を「公表する」ということ― 第8章 研究倫理:研究者として「なすべきこと」 第9章 研究倫理:研究者として「やってはいけないこと」 第10章 研究倫理:モラル違反を抑止するシステム 第11章 研究成果の公表:心理学論文の書き方 終章 よりよい心理学研究のために ◆◆◆『心理学ベーシック』全5巻-シリーズ監修 三浦 麻子-◆◆◆ 心のはたらきを科学的に見つめるまなざしを養い,「自らの手で研究すること」に力点をおいたシリーズ 第1巻 なるほど! 心理学研究法 三浦麻子 著 第2巻 なるほど! 心理学実験法 佐藤暢哉・小川洋和 著 第3巻 なるほど! 心理学調査法 大竹恵子 編著 第4巻 なるほど! 心理学観察法 佐藤 寛 編著 第5巻 なるほど! 心理学面接法 米山直樹・佐藤 寛 編著 ◆「心理学ベーシック」シリーズ刊行にあたって(一部抜粋)◆ 「心理学を学ぶこと」をめぐる状況は,2015年に国家資格「公認心理師」の制度化が決まったことによって大きな岐路に立った。-略- しかしわれわれは,心理職としての現場での実践を有為なものとするためには,何よりもまず,心理学諸領域の基礎的な知見や理論を学び,それらをふまえて自らテーマを設定して研究を計画し,収集したデータを分析・考察するという一連の科学的実証手続きを遂行するためのスキルとテクニックを習得することが必要だという強い確信をもっている。 「心理学ベーシック」シリーズ刊行にあたって はしがき 序章 心理学とは何か 1節 心理学の定義 2節 心理学を研究することの難しさ 3節 心理学を研究することの面白さ ―第1部 心理学を「研究する」ということ― 第1章 心理学のなりたち:心理学史 1節 心理学と哲学 2節 心理学と医学 3節 心理学と生物学 4節 近代心理学の創始とその発展 5節 第二次大戦後の心理学 6節 日本の心理学 第2章 研究の準備:心理学研究の基礎知識 1節 概念的定義と操作的定義 2節 信頼性と妥当性 3節 相関と因果 4節 さまざまな変数 第3章 研究の準備:先行研究の探し方 1節 リサーチ・クエスチョン 2節 巨人の肩の上に立つということ 3節 先行研究レビューの意義 4節 先行研究の収集法:概論 5節 心理学の研究論文に触れる 6節 心理学の研究テーマを知る 7節 さあ,歩きはじめよう ―第2部 心を「測定する」ということ― 第4章 研究の基礎:研究法概説 1節 実験法 2節 調査法 3節 観察法 4節 面接法 第5章 研究の基礎:人間を対象とする測定における諸問題 1節 参加者効果 2節 実験者効果 3節 努力の最小限化 4節 生態学的妥当性との両立 第6章 データの中身を知る:記述統計 1節 数値データの利点 2節 尺度 3節 記述統計 第7章 データから対象を見通す:推測統計 1節 推測統計とは 2節 標本抽出に伴う結果の変動 3節 統計的仮説検定 4節 統計的仮説検定における2種類の誤り 5節 効果量と検定力分析 6節 ベイズ統計学の基本的考え方 ―第3部 研究を「公表する」ということ― 第8章 研究倫理:研究者として「なすべきこと」 1節 エシックスの基本的な考え方 2節 最小限のコストやリスク 3節 説明責任 4節 個人情報・データの保護 5節 成文化されたエシックス 6節 倫理審査 第9章 研究倫理:研究者として「やってはいけないこと」 1節 モラルとしての研究倫理 2節 研究者が陥るかもしれない「地獄」 3節 仮説の後づけ(HARKing) 4節 p値ハッキング(p-hacking) 5節 蔓延するQRPs 第10章 研究倫理:モラル違反を抑止するシステム 1節 研究結果の再現可能性 2節 心理学界で起こった問題 3節 システムの整備 4節 心理学研究の「パラダイムシフト」 第11章 研究成果の公表:心理学論文の書き方 1節 論文のアウトライン 2節 論文の文章表現 3節 図表 4節 全体的なチェック [付録] 心理科学実験実習 レポート作成 チェックリスト 終章 よりよい心理学研究のために 1節 「研究」するということ 2節 よい研究とは何か 3節 心理学研究への船出 引用文献/索 引
訪問看護の新入職者向けの入門書で、就職活動から実際の業務、事例までを網羅。先輩のアドバイスや豊富なイラストを通じて、不安を解消し、訪問看護のやりがいを理解できる内容。書類や疑問の解決にも役立つ。
「かんテキ」は、医療従事者向けに患者の肺に優しい換気の仕組みをわかりやすく解説した本です。人工呼吸に関する重要な知識を、独自の視点と豊富なビジュアルを使って丁寧に説明しています。モードや波形の基本、人工呼吸管理のポイント、肺保護換気の理解を深める内容が含まれており、医師やナースはもちろん、すべての医療従事者に役立つ一冊です。
内面のドラマともいうべき、無意識的な心の変遷過程をたどる。ユング思想の全体を浮かびあがらせる絶好の入門書。 集合的無意識の概念を紹介し、個性化過程の考えを打ちだし、ユング心理学の基礎を築き上げた初期代表作。内面のドラマともいうべき、無意識的な心の変遷過程を個々の例を挙げながら分りやすく説くという点で、ユング思想の全体像を浮かびあがらせる入門書。 第一部 意識におよぼす無意識の諸作用 第一章 個人的無意識と集合的無意識 第二章 無意識の同化作用のおこす後続現象 第三章 集合的心の一部としてのペルソナ 第四章 集合的心からの個性解放の試み A ペルソナの退行的復元 B 集合的心との同一化 第二部 個性化 第一章 無意識の機能 第二章 アニマとアニムス 第三章 自我と無意識の諸形象とを区別する技術 第四章 マナ=人格 訳者解説 無意識とユング
「KANAMI式バーオソル」は、バレエダンサー向けに開発された身体矯正メソッドで、日本人の体の特性に合わせてアレンジされています。このプログラムは、体幹を強化し柔軟性を高めることで、骨格の歪みを整え、姿勢や脚、ヒップを美しくする効果があります。続けることで自信を持てるようになり、心と体の調和を促進します。女優・比嘉愛未さんも推薦しています。
「かんテキ」は、看護師や医療従事者向けに脳神経疾患の患者対応を視覚的に理解できるようにまとめた書籍です。1,200点以上のイラストや図解を用いて、発症から退院までの流れをストーリー形式で解説。難しい医学用語を使わず、わかりやすく、実践的な知識を提供します。各疾患の重要ポイントや観察項目も明確に示されており、実際の臨床現場で役立つ内容となっています。
自分の言葉で心理学を思考し、心を観察し、今そこにある問題を考える。簡潔な文章と多彩なイラストでヒトの心の不可解に迫る入門書 簡潔な文章と多彩なイラストで一読である程度理解できる「簡潔性」、知識の詰め込みではなく考える材料になる「思考促進性」、現代人が抱える悩みや課題にこたえる「現在性」に留意したたいへん読みやすい一冊。入門書に最適。 読むだけである程度理解できる「簡潔性」、知識の詰め込みではなく考える材料になる「思考促進性」、現代人が抱える悩みや課題にこたえる「現在性」に留意したたいへん読みやすい一冊。教科書としてだけではなく一般書としても読み応え十分。一読すれば、いまそこにある心の問題が見えてくる。 はじめに 心理学を学ぶ喜びと意義 1章 荒川歩 心理学とは:心理学に何を期待するのか? コラム1 フェヒナーの精神物理学と感覚の尺度化 2章 三星宗雄・荒川歩 知覚:人の目はカメラとどう違うのか? コラム2 騒色公害の系譜とその解決 3章 三星宗雄・荒川歩 知覚の障害:私たちに見える世界は共通か? コラム3 ユニバーサルデザインとカラーユニバーサルデザイン 4章 浅井千絵 記憶と学習:人はどのように学ぶのか? コラム4 感情と色彩 5章 浅井千絵 認知:人はどのように世界を理解するのか? コラム5 絵画・デザイン制作の認知科学 6章 荒川歩 感情:感情は何のためにあるのか? コラム6 無意識 7章 荒川歩 自己:私はどこにあるのか? コラム7 アイデンティティ拡散と回復 8章 荒川歩・河野直子 発達:それぞれの年代において人はどんな課題とむきあうか? コラム8 子どもの絵の発達 コラム9 氏か育ちか、氏も育ちも 9章 遠藤架児 発達の障害:障害なのか? 個性なのか? コラム10 サヴァン症候群 10章 桂 瑠以 性格と社会的認知:何が人の性格や態度を決めるのか? コラム11 心理(性格)検査って何? 11章 桂 瑠以 人間関係 : 人と人とは、どう関わるか? コラム12 コミュニケーションメディアの使い分け 12章 桂 瑠以 社会的影響と集団:集団はどのような影響を及ぼすか? コラム13 商品開発と心理学 コラム14 広告と心理学 13章 河野直子・荒川歩 心と脳:心はどのような脳内メカニズムに支えられているか? コラム15 心とからだ コラム16 アフォーダンス 14章 河野直子・尾崎紀夫 病理:精神疾患とどう付き合っていくか? コラム17 病跡学:作品や人物を精神病理で理解する コラム18 芸術療法:アートと心理学のもう1つの関係 引用文献 索引
本書は、イギリス発の人気マンダラぬりえブックで、発売3か月で7万部を売り上げ、フランスでも好評を得ています。作品は手描きの花をモチーフにした美しいマンダラが40点収録されており、癒しと集中をもたらす内容です。また、ぬりえのテクニックや道具の紹介もあり、初心者からプロまで楽しめる工夫が施されています。造本設計にもこだわり、色を塗る環境を重視した作りになっています。著者は、花をテーマにしたデザインを得意とするシンシア・エマリーです。
バーテンダーを目指す歩がバー「セブン」での出会いを通じて成長する物語。彼女の人生観を変えたのは「7つの習慣」で、各習慣を通じて主体性や優先事項、相互理解、シナジーの重要性を学ぶ。著者はまんが家の小山鹿梨子。
名著「7つの習慣」について漫画で分かりやすく学べる!7つの習慣は名著だけどボリューム多く読破するのつらいのでまずこの漫画版読んで面白ければオリジナルを読むのもあり。
本書は、循環器科のナース向けに心電図の判読を解説したもので、基本波形や異常波形の見分け方を図版や症例を用いて詳しく説明しています。ドクターコールのポイントや患者への対応方法も紹介されており、臨床現場での適切な対応をサポートします。モニター心電図から12誘導心電図までを網羅した内容で、心電図のバイブルとされています。著者は心電図の教育に長年携わっている医師です。
このノートは、気持ちが沈んだり不安を感じたりする人のためのサポートツールです。毎日少しずつ読むことで、考え方や視点が変わり、憂うつや不安が軽減されます。内容は認知療法の理解から始まり、ストレスの認識や問題解決、人間関係の改善などを扱っています。著者は大野裕で、精神医学の専門家です。
訪問看護の現場での実践的な看護技術やアイデアを集めた本です。経験の浅い看護師でも学べるよう、役立つ物品や写真、エピソードが豊富に掲載されています。具体的なコツや他職種・家族とのコミュニケーションに関する知恵もシェアされており、現場の視点からベテラン看護師の経験が反映されています。
本書『キレイはこれでつくれます』は、現代人が抱える様々な問題(鬱病、肥満、不眠など)が実は共通の根本原因から来ていることを指摘し、総合的なアプローチで解決策を提供します。著者の鈴木祐は、科学的根拠に基づき、文明病から脱却し本来の自分を取り戻す方法を解説しています。目次には、炎症、腸、ストレスなどのテーマが含まれており、進化医学の視点から最高のコンディションを実現するための知識が紹介されています。
「かんテキ」は、妊産婦や患者ケアに特化した医療スタッフ向けの一冊で、疾患や生理を視覚的に理解できる内容です。妊娠・分娩から婦人科疾患まで幅広い知識を美しいイラストと簡潔な解説で提供し、初期研修にも役立つ内容となっています。重要なポイントや「ヤバサイン」などの実践的な情報も含まれており、基本を素早く把握できる構成です。
だるい、重い、つらい……。日々の不調はストレスよりも「質的栄養失調」が原因!? 毎日の食事では何よりタンパク質と鉄が重要。そして糖質減。薬に頼らず、うつを振り払う、栄養療法メソッドです! はじめに 第1章 うつ消しごはん――肉をたくさん食べなさい タンパク質をたっぷり摂りなさい ・タンパク質は生命活動の“第一人者” ・毎日分解と合成を繰り返すタンパク質 ・動物性のタンパク質が効率的 ・プロテインスコアで比較せよ 女性は鉄をどんどん摂りなさい ・女性のうつ・パニックは「鉄不足」が原因 ・日本人女性の鉄不足の現状 ・欧米などの他国では鉄分補給対策がある ・鉄不足が深刻な日本女性 ・鉄分をほうれん草には頼れない ・さまざまな鉄の働き 肉は何をどのように摂ればいいか ・肉は少なくとも200g毎日食べる ・肉は体に悪い? ・牛肉はタンパク質と鉄がたっぷり ・豚肉100g~で1日分のビタミンB1が摂れる ・鶏肉は消化がいい ・ラム肉や馬肉、ジビエにもタンパク質が豊富 第2章 うつ消しごはん――明るい食事の習慣術 質的な栄養失調から抜け出す方法 ・肉の安全性について ・食品添加物は神経質になりすぎない ・卵は完全栄養食、毎日2~5個食べよう ・卵かけご飯はNG ・マグロ、カツオ、赤身の魚が効率的 ・アサリ、シジミ等の貝類も大切 ・バター、生クリーム、MCTオイルもしっかり摂る ・生クリームをおやつに ・塩や砂糖の味付けについて ・日々のヒント「まごわやさしい」 サプリ活用で効果倍増 ・足りない分は鉄剤やプロテインで補う ・ヘム鉄神話からキレート鉄へ ・キレート鉄はキケン? ・女性はしっかりプロテインでタンパク質を補給 ・体重の1/2グラムのプロテインを摂る ・BUN20を目標にタンパク質摂取 ・どうしてもプロテインを摂れない 第3章 うつ消しごはん――糖質と悪い脂質を減らす 精製された糖は減らしなさい ・精製糖質(白米、小麦粉、砂糖)はインスリンを分泌させるので避ける ・砂糖は特に「減らす」食べ物 ・タンパク不足があると糖質制限がうまくいかない ・精製糖質の過剰摂取はがん、うつを引き起こす ・鉄不足の人は甘いものを欲しがる ・甘いものの過食に苦しむ方へ 狂った脂肪は即やめなさい ・トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニング)はNG ・サラダ油もできるだけ減らす 質の悪い野菜は意味がない ・コンビニ野菜の栄養はわずか ・インスリン分泌が少ない全粒粉の小麦粉、イモ類等の根菜類はOK ・野菜ジュース、果物ジュースはNG 第4章 メガビタミン療法のすすめ――ATPブーストセットがあなたを救う ATPセットの効果 ・ATPをつくり出すためのエネルギー代謝 ・ATPはどのようにつくられるのか ・ATPブースト(激増)サプリメント4点セット ・鉄・タンパク不足の女性にATPブースト4点セットは有効 ・ADHD+LDの男の子がATPセットでこれだけ1年でよくなった ・過食症にはプロテイン+ATPセットが最強 ・ようやく三石巌先生と同じ治療ができるように メガビタミン療法について ・医学界の権威によるビタミンへの攻撃 ・もし私がメガファーマの新薬担当責任者だったら ・心身共に快適に過ごすための自己管理法 ・参考 私の日々の食事とサプリメント 第5章 栄養改善による症例集 症例が意味すること ・きちんと患者を診ているからいえること ・症例の血液検査が示す数値について ・フェリチン値について 完治への道 ・【症例】「高タンパク/低糖質食+鉄」でうつ病は完治する ・【症例】「職場の人間関係で体調が悪い」と訴える人は、実は栄養状態が悪い ・【症例】最も典型的。鉄・タンパク不足を伴うパニック障害 ・【症例】鉄・タンパク不足で頭が回らない女性もすっかり回復 ・【症例】パニック発作に苦しむ女性がプロテインで回復 ・【症例】ADHD傾向の4歳の男の子、3カ月で落ち着いてきた ・【症例】本を読んで受診した貧血+うつ病女性、1年弱でほぼ完治 ・【症例】学習障害(LD)の男の子、6カ月で優等生になった ・【症例】産後の鉄・タンパク不足にはATPセットが最強 ・【症例】プロテインと鉄剤を飲んでいても妊娠すると鉄・タンパク不足になる ・【症例】プロテイン+ATPセットで家庭崩壊の危機を救う ・【症例】中年の単身男性で糖質ばかり摂取 ・【症例】中高年の単身男性では鉄・タンパク不足になる ・【症例】起立性調節障害(OD)で不登校となった中学生、3カ月で元気になった あとがき 参考文献
誰も教えてくれなかった”基礎の一歩先”がコンパクトにわかり,実臨床でも武器になる“正確に,秒で読む”鑑別力がつく必携書! 心電図検定1級合格を目指すために必要な判読スキルを身につけるために,上級者も悩ませる梗塞部位特定,軸偏位・ブロック・起源・変行伝導の攻略を主眼に解説。表面的な理解にとどまっていたり,単なる暗記で対応しがちな基礎メカニズムを上級問題に対応できるよう学び直し,“正確に,秒で読む”ためのエッセンスがわかる。本番を想定した模擬問題100問で力試しでき,各問題から基礎章をおさらいできるリンケージ付き。 1章 講義編 ①はじめに ②心電図検定受験の心構え 心電図検定とは/心電図検定の各級/検定当日の注意点 ③心電図の基礎 まずは波形と心拍数を考える/正常と異常を見分ける ④P波に異常をきたす疾患 異所性心房調律/右房性P波/左房負荷/上室期外収縮(PAC)/PACの起源を探る/洞不全症候群 ⑤PQに異常をきたす疾患 房室ブロック/房室ブロックのまとめ ⑥QRS波に異常をきたす疾患 変行伝導/脚ブロック初級編〜興奮の流れで理解を深める/脚ブロック上級編〜脚は2本ではなく3本である/心室期外収縮(PVC)/PVCの起源を探る ⑦STに異常をきたす疾患 急性冠症候群(ACS)/冠動脈の障害部位を探る/Brugada症候群/不整脈原性右室心筋症(ARVC)/早期再分極症候群,J波(オズボーン波) ⑧T波に異常をきたす疾患 陰性T波をきたす疾患(虚血性心疾患,左室肥大,肥大型心筋症)/たこつぼ型心筋症 ⑨QTに異常をきたす疾患 QT延長症候群/QT短縮症候群/電解質異常 ⑩発作性上室頻拍 房室回帰性頻拍(AVRT)/房室結節リエントリー頻拍(AVNRT)/心房頻拍(AT) ⑪WPW症候群におけるケント束付着部位の推定 ケント束とは/なぜデルタ波ができるのか/WPW症候群とタイプ一覧/ケント束付着部位 ⑫頻脈性不整脈(心房細動,心房粗動,心房頻拍) 心房細動(AF)/心房粗動(AFL)/心房頻拍(AT) ⑬頻脈性不整脈(心室頻拍,心室細動) 心室頻拍(VT)/心室細動(VF) ⑭肺動脈血栓塞栓症 ⑮心膜炎・心筋炎 ⑯植込み型心臓電気デバイス 植込み型心臓電気デバイスとは/ペーシング波形の特徴/ペーシング位置による波形の違い/デバイスの誤作動/プログラマーからみる心電図/ホルター心電図 ⑰薬物による心電図異常 ジギタリス中毒/抗不整脈薬(薬剤性QT延長症候群,Ⅰcフラッター) ⑱心筋症 心アミロイドーシス/心サルコイドーシス/拡張型心筋症 ⑲小児の心電図(先天性心疾患) 胸部誘導の陰性T波/心房中隔欠損症/房室中隔欠損症/右胸心 ⑳電極の付け間違い 2章 問題編 [模擬問題] 第1回目“Hard” [模擬問題] 第2回目“Extreme”
著者のとがわ愛は、運動が苦手でリバウンドを繰り返していましたが、5ヶ月で10キロの減量に成功しました。自宅で10分でできる「やせ筋」に特化した簡単なトレーニングを紹介しており、初心者でも楽しく取り組める内容です。イラストを用いたわかりやすい解説が特徴で、効果的なトレーニング法やストレッチ、食事のアドバイスも含まれています。ダイエットを続けられなかった人でも楽しめる筋トレ本です。
はじめてのやせ筋トレは、特に女性向けに考えられた筋トレメニューがたくさん載ってます!筋トレ初心者でも無理なくスタートできるシンプルなメニューが揃っていて、筋肉をつけながらスッキリ痩せたい人におすすめ。著者のかわいいイラストとわかりやすい説明もポイントで、筋トレが楽しく続けられる工夫が満載です。
この本は、心理学の全体像を俯瞰できる入門書で、各分野を豊富なカラーイラストと写真を用いて解説しています。基礎から学べるステップアップ形式で構成されており、初学者に最適です。目次には心理学の歴史や学習、知覚、認知、社会、人格、臨床、発達、神経心理学などが含まれています。著者は心理学と工学的アプローチを融合させた研究を行う専門家です。
この書籍は、発達障害のある子どもを育てるための実践的なアプローチを提供しています。「しかる・ほめる・慣れさせる」方法では効果が薄いとし、親や教師がどのように接すればよいかのヒントが詰まっています。内容は、発達障害についての理解、幼稚園や学校でのサポート事例、家庭での支援方法、学校と家庭の連携の重要性などを網羅しています。著者は、発達障害に関する専門知識を持つ医師と教育者です。
「経済からのアプローチ」、「知覚からのアプローチ」「感情・直観からのアプローチ」といった章を新たに立て、構成を大幅に刷新。 「経済からのアプローチ」、「知覚からのアプローチ」「感情・直観からのアプローチ」といった章を新たに立て、構成を大幅に刷新。心理学の知識がなくても読みやすく、幅広い読者におすすめできる1冊。教科書にも最適。 意思決定研究の基礎はこれで学べる! 行動経済学を生み、医療や科学技術のリスコミにも欠かせないリスクと意思決定の基礎知識が満載! 好評入門書の第3版! ▼学界で好評を得た「行動的意思決定」の入門書を10年ぶりに改版! 「意思決定とリスク」に関わる概念・理論についての心理学的知見の蓄積と最新の動向をいち早く紹介した入門書の第3版。行動経済学やリスクコミュニケーションが注目される今、「経済からのアプローチ」をはじめ、「知覚からのアプローチ」「感情・直観からのアプローチ」といった章を新たに立て、構成を大幅に刷新。心理学の知識がなくても読みやすく、幅広い読者におすすめできる1冊。教科書にも最適。 はじめに 改訂版によせて 第3版刊行にあたって 第Ⅰ章 意思決定、不確実性と心理学 Ⅰ―1 意思決定とは Ⅰ―2 ギャンブルと不確実性 Ⅰ―3 事故・災害、環境問題のリスク Ⅰ―4 医療意思決定、その他領域での展開 Ⅰ―5 集団での行動、意思決定と生産性 Ⅰ―6 リスクと不確実性、曖昧性 Ⅰ―7 曖昧さは嫌われる? 第Ⅱ章 認知からのアプローチ Ⅱ―1 不確実性下での意思決定と期待効用 Ⅱ―2 経済学における意思決定(1)効用逓減と期待効用理論 Ⅱ―3 経済学における意思決定(2)期待効用理論の侵犯 Ⅱ―4 代表性ヒューリスティック(1) Ⅱ―5 代表性ヒューリスティック(2)基準比率の無視 Ⅱ―6 利用可能性ヒューリスティック Ⅱ―7 係留と調整ヒューリスティック Ⅱ―8 感情ヒューリスティック、適応的ヒューリスティック Ⅱ―9 枠組み効果 Ⅱ―10 プロスペクト理論 Ⅱ―11 意思決定の二重過程モデル Ⅱ―12 ヒューリスティックス&バイアス研究への批判 Ⅱ―13 その他の認知的意思決定理論 第Ⅲ章 知覚からのアプローチ Ⅲ―1 ランダムネスの知覚と生成 Ⅲ―2 共変関係の知覚 Ⅲ―3 錯誤相関 Ⅲ―4 原因帰属理論 Ⅲ―5 制御幻想 Ⅲ―6 抑うつのリアリズム Ⅲ―7 自信過剰 第Ⅳ章 感情・直観からのアプローチ Ⅳ―1 感情が判断や意思決定に与える影響 Ⅳ―2 ストレスと意思決定 Ⅳ―3 決定後の心理:認知的不協和の低減 Ⅳ―4 単純接触効果 Ⅳ―5 選択と理由 Ⅳ―6 後悔 Ⅳ―7 予測と経験 第Ⅴ章 行動からのアプローチ Ⅴ―1 動物の選択行動 Ⅴ―2 迷信行動とギャンブル行動 Ⅴ―3 動物行動研究から見た遅延割引 Ⅴ―4 自己制御(セルフコントロール)と衝動性 Ⅴ―5 ヒトの価値割引研究への展開 Ⅴ―6 選択行動研究とマッチングの法則 Ⅴ―7 行動生態学 第Ⅵ章 社会からのアプローチ Ⅵ―1 集団の影響 Ⅵ―2 集団の問題解決 Ⅵ―3 集団の意思決定と合議(1) Ⅵ―4 集団の意思決定と合議(2) Ⅵ―5 集団の意思決定と合議(3)集合知 Ⅵ―6 リスク心理研究(1) Ⅵ―7 リスク心理研究(2)リスクコミュニケーション Ⅵ―8 科学情報のコミュニケーション Ⅵ―9 リスクリテラシー 第Ⅶ章 経済からのアプローチ Ⅶ―1 行動経済学(1)需要供給分析 Ⅶ―2 行動経済学(2)無差別曲線分析 Ⅶ―3 心の会計とサンクコスト効果 Ⅶ―4 保有効果と現状維持バイアス Ⅶ―5 行動ファイナンス Ⅶ―6 神経経済学 引用文献一覧 索 引 BOX 目次 ( )内は執筆者 1 Blue seven 現象(坂上) 2 選択肢は多いほどよいか?(山田) 3 平均への回帰(増田) 4 様々な合理性の見解(広田) 5 マーフィーの法則を科学する(増田) 6 好物は後で? 上昇選好(井垣) 7 終わり良ければすべてよし? ピーク・エンドの法則(井垣) 8 競合分割効果(広田) 9 時間と意思決定(広田) 10 飛行爆弾は狙って打ち込まれたか?(増田) 11 読みやすい名前は好かれる?(森) 12 最高を求めると不幸になる?(森) 13 誠意のコスト(森) 14 自己制御の技術(坂上) 15 動物も不公平を嫌う?(石井) 16 ただ乗り問題と共有地の悲劇 社会的ジレンマ(広田) 17 1円はどこへ消えた?(広田) 18 「直観」が全てを知っている?! 現実場面での意思決定(三田地) 19 デフォルト(山田) 20 貨幣錯覚(井垣) 21 ソマティックマーカー仮説(石井)
医療や福祉に携わる方やカウンセラーなどの専門職を目指す方向けに、こころの病気の原因と種類、治療法、患者を支える社会制度など、精神医学の基礎と最新情報をやさしく解説。やさしい文章とイラストを使った図解、丁寧な用語解説で、はじめて学ぶ方もすんなり読めるようになっています。国際的な診断基準であるDSM-5に対応しながら、近年使用されている薬や精神療法、患者と家族を支援する法制度など、最新情報を網羅しました。
気楽に読み進めながら自然と精神科薬物療法の「基本知識」や「考え方」が身につくことをめざして企画された本書は、これから精神科治療薬について学ぼうとしている研修医や、臨床心理士・看護師などのコメディカル・スタッフを主な読者対象とした、精神科薬物療法の「技」を磨くための一冊! 第1講 抗精神病薬 第2講 抗うつ薬 第3講 気分安定薬 第4講 抗不安薬 第5講 睡眠薬 第6講 中枢刺激薬とノルアドレナリン再取り込み阻害薬 第7講 抗てんかん薬 第8講 漢方薬
この文章は、アドラー心理学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、基本理論、自分との付き合い方、人間関係、仕事、親子・家族関係、人生を豊かにする方法についての章が示されています。著者は岩井俊憲で、アドラー心理学のカウンセリング指導者であり、中小企業診断士としての経歴を持ちます。
精神神経科疾患を図示化し,要点をまとめた書籍.より平易で,正確に,より具体的に,をコンセプトにまとめた一冊. 総論では解剖や構造を可視化し,各論では原因,症状・臨床所見,検査・分類・診断,治療という日々の診療の流れに沿って,病態理解を容易にするためのイラスト,シェーマ,画像写真などを取り入れて解説.総論と各論を対応させて大局的な理解が可能.
「認識」について,実験の醍醐味に触れながら,基礎的な内容から新しい知見までをカバーした,コンパクトで読みやすい入門書。 人間は世界をどのように認識しているのか。当たり前になしえている「認識」の背後にからみ合う複雑な営みを,1つ1つ解き明かしていく実証的・科学的手法の醍醐味を堪能してほしい。初版刊行後の新しい知見も盛り込んだ,コンパクトで読みやすい入門書。 第1章 認知心理学の誕生と変貌――情報工学から機能的生物学へ=道又 爾 第2章 知覚の基礎――環境とのファーストコンタクト=北〓崎充晃 第3章 高次の知覚――見ることから理解することへ=道又 爾 第4章 注 意――情報の選択と資源の集中=大久保街亜・道又 爾 第5章 表 象――こころの中身,その形式=大久保街亜 第6章 記 憶――過去・現在・未来の自己をつなぐ=今井久登 第7章 言 語――成長する心の辞書システム=山川恵子 第8章 問題解決と推論――普遍性と領域固有性の間で=黒沢 学
本書は、精神科の薬の処方に関する解説書で、著者の吉尾隆教授が多くの症例をもとに、精神疾患(大うつ病性障害、双極性障害、神経症性障害、統合失調症、認知症)の処方意図を明らかにします。薬剤師が処方の意図を理解しやすくするために、各疾患に関連する薬物療法の概要と具体的な症例(全33例)を紹介しています。
この文章は、ジュエリーやアクセサリーに関する目次を示しており、ピアス・イヤリング、ブレスレット、ネックレス、リング、ヘアアクセサリー、チャーム・ブローチの6つのカテゴリに分かれています。
論文の読み方入門書。『心理学論文の書き方』の姉妹篇。論文読破に必要となる概説的な知識や論文の形式・ルールをやさしく解説。 「書く」のためには,まずは「読む」ことから!『心理学論文の書き方』の姉妹篇。論文を読むことは学問という知的な世界を旅することである。論文読破に必要となる概説的な知識や形式・ルールをやさしい筆致でコンパクトにまとめた,論文ビギナー必携の入門書。 プロローグ 論文を読もうとする人に Step1 論文を読む前に 第1章 なぜ論文を読むのか 第2章 論文の作法を知る 第3章 読む前に大切なこと Step2 論文を読む 第4章 論文の構造をつかむ 第5章 いろいろな読み方を試してみる 第6章 読むときに役立つこと 第7章 図表を読む 第8章 統計の結果を読む 第9章 読んだ後にすべきこと 第10章 英語論文を読む 第11章 論文を探すコツ エピローグ 論文の読み方を極める
著者が18年間の看護経験を基に作成した「看護のメモ帳」は、看護師が知りたい情報をポケットサイズでまとめたものです。13のテーマと92項目にわたり、看護技術や処置、急変対応、検査、薬剤などの具体的な内容を詳細に記載しています。正確な知識が求められる現場で役立つ一冊で、医学監修による専門的なアドバイスも含まれています。
本書は、悩みを「消す」方法として、ブッダの教えを日常生活に活かす方法を紹介しています。著者は独立派の出家僧で、原始仏教を基にした実用的な教えを提供。内容は、理解を深めること、判断を避けること、マイナス感情を管理すること、他人の目からの自由、正しい競争、考える基準を持つことなど、日常生活に役立つ6つの章で構成されています。著者の草薙龍瞬は、様々な経験を経て実用的な仏教を広める活動をしています。
パニック障害とはどんな病気か。最新の薬物療法と精神療法。発作への対処法とメンタルケア。 第1章 パニック障害ではどのようなことが起こるか 第2章 パニック障害とはどのような病気か 第3章 パニック障害の診断・治療の進め方 第4章 回復に近づくための日常生活のケア 第5章 家族や周囲の人は患者さんをどう支えるか 第6章 症例集…回復のプロセス
「かんテキ」は、看護師やコメディカル向けに、整形外科の疾患や患者対応の重要ポイントを視覚的にまとめた実践的なテキストです。新人ナースや研修医が必要な知識を短時間で習得できるよう、1ページに要点を凝縮し、1,500点以上のイラストを用いて理解を助けます。難しい医学用語は使わず、図解や箇条書きで情報を整理し、臨床現場で自信を持って対応できるように設計されています。
これまでの心理学は、とかく人間の欠けているところ、できない部分に注目してそれを克服することに着目しがちでしたが、これからは人間のポジティブな側面にもっと注目し、人間の本来もつ強さを引き出すことによって個人や社会を支えるような学問を目指すべきだ、とする考え方が生まれています。本書は、スポーツ心理学、健康心理学に、新たに確立してきたポジティブ心理学をあわせて、積極的な人生追求のためのこころのサイエンスの最前線を紹介する入門書です。 目次 ●もくじ はじめに 第1部 スポーツ心理学 中込四郎 1‐1 スポーツ心理学 スポーツと心理学が出会う 1‐2 タレント発掘 早期トレーニングの功と罪 1‐3 青年期とスポーツ スポーツで「自己」を体験する 1‐4 アスリートのパーソナリティ スポーツによってパーソナリティをつくる 1‐5 こころの強化 スポーツメンタルトレーニングの今 1‐6 ピークパフォーマンス 実力発揮につながる心理的世界を知る 1‐7 積極的思考 弱気から強気に変える 1‐8 イメージトレーニング イメージをうまく活用する 1‐9 スポーツ・モニタリング・トレーニング こころと体の動きを知る 1‐10 ソーシャルサポート まわりの人的資源を活用する 1‐11 スランプ いくらやっても上達しない 1‐12 アスリートの燃え尽き 努力する割には報われない 1‐13 心因性動作失調 こころが動きを縛る 1‐14 スポーツセラピー スポーツでこころを癒やす 1‐15 運動の継続 運動の継続を妨げるもの 第2部 健康心理学 石崎一記 2‐1 健 康 心身ともにその人らしくいること 2‐2 健康心理学 健康をこころと体の結びつきの面から科学する 2‐3 健康の査定 健康ってはかれるの? 2‐4 生涯発達 一生変化し続けるもの 2‐5 QOL 人生の質、生活の質 2‐6 生きがい 生きる意味が感じられること 2‐7 ストレス ストレスって本当に悪いもの? 2‐8 ストレス・コーピング ストレスとの上手な付き合い方 2‐9 感 情 人を心底から動かすもの 2‐10 グループと自然の癒やし効果 人や自然と関わることで健康づくり 第3部 ポジティブ心理学 外山美樹 3‐1 ポジティブ心理学とは 人間のもつ「強さ」から考える 3‐2 学習性無力感 説明スタイルの違いから謎を解く 3‐3 楽観主義 自分の将来を楽観的に考える 3‐4 悲観主義ネガティブ思考のポジティブなパワー 3‐5 フロー経験 夢中になる 3‐6 目 標 自分の未来を導く 3‐7 自尊感情 揺れ動く自己 3‐8 認知的複雑性 物事を多面的に見る能力 3‐9 ネガティブ感情とポジティブ感情 感情の凹凸 3‐10 笑 い 人は幸福だから笑うのではない 3‐11 気晴らし 気晴らしにもコツがいる 3‐12 自己開示 こころをオープンにすると健康になる? 3‐13 アサーション 自己表現によってよりよい人間関係を築く 3‐14 ハーディネス ストレスに強い性格とは 3‐15 認知療法 考え方の癖を見ぬく 人名索引 事項索引 文 献
じつは難しいうつ病の診断。典型的なうつ病から非定型うつ病、誤診されやすい病気まで。原因、症状、治療法を“初歩”から徹底図解! 本書は、好評だった既刊『入門うつ病のことがよくわかる本』(2010 年7 月刊行)の新版。近年、うつ病の治療法や病気の研究が進んでいます。治療の指針となる、新しい分類(DSM−5による)をはじめ、うつ病と見分けづらい心の病気、新薬など最新の情報を盛り込みました。そもそもうつ病は、どんな病気なのか、どのように診断されるのか、治るのか。うつ病の原因から治療法まで丸ごとわかる「入門書」の決定版です。 ひと目でわかるイラスト図解 《講談社 健康ライブラリーイラスト版》 【典型的なうつ病から薬の効かないうつ病まで】 うつ病の患者さんは年々増えつづけています。なかなか治らず慢性化している例も多くあります。ほかの病気と誤診されていたり、心の病を合併したりしていることも、うつ病を治りにくくしている大きな原因です。また、近年では、うつ病の治療法や病気の研究が進んでいます。 本書は、好評だった既刊『入門うつ病のことがよくわかる本』(2010 年7 月刊行)に治療の指針となる、新しい分類(DSM−5による)をはじめ、うつ病と見分けづらい心の病気、新薬など最新の情報を盛り込みました。 TVの健康番組やネット情報も氾濫する中、うつ病の本も数多く出版されていて、どれを選ぶか迷うほどです。本書はその中でも「入門書」として図解でわかりやすい、うつ病の原因から治療法まで丸ごとわかる決定版です! 【本書の内容構成】 第1章 発病には多くの要因が重なっている 第2章 じつはむずかしい、うつ病の診断 第3章 治療法のメニューを決める 第4章 うつになりやすい考え方を変える 第5章 新しい生活リズムをつくる
この書籍は、フィジカルアセスメントの基本知識や手技、症状別のアセスメントと急変対応を解説し、在宅での実践に役立つ視点を提供しています。目次には基礎知識、Q&A、実践事例が含まれており、具体的なケーススタディを通じて看護ケアの方法を学ぶことができます。
ストレス要因の解決策がたっぷり詰まった1冊。日常的な悩みをカテゴリごとに分け、一つ一つ解決策が書かれているので読みやすい。過去の実験結果をもとに書かれているから説得力があるし、簡単に実践できるものが多いので良い!最近気持ちが晴れないなと思っている人におすすめ。私もこの本に助けられた人のうちの1人!
初心者向けの刺しゅう教科書で、川畑先生が監修。基本的な刺しゅうの技術や失敗を避けるコツを紹介し、580種類のかわいい図案や刺しゅう小物の作り方も掲載。基本のステッチの詳細な解説があり、実用的なアドバイスが豊富に含まれています。著者は刺しゅう作家の川畑杏奈で、教室も運営しています。
このポケットブックは、持ち運びに便利なサイズで、各科共通の重要情報やスケール・データを簡単に参照できる。北里大学病院の認定看護師・専門看護師の臨床視点も含まれており、第2版では新人・若手看護師向けの新しい項目が追加されている。
「精神疾患」に関するよくある質問
Q. 「精神疾患」の本を選ぶポイントは?
A. 「精神疾患」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「精神疾患」本は?
A. 当サイトのランキングでは『明日からできる訪問看護管理 改訂2版: これだけはおさえておきたい』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで161冊の中から厳選しています。
Q. 「精神疾患」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「精神疾患」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

































![『双極性障害[第2版] (ちくま新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41R6YXm1uxL._SL500_.jpg)


![『おかねをまなぶ・つかう・たのしい! 知育コインケース ニコニコイン わくわくおかねワークブック ([バラエティ])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51eYeLL8MIL._SL500_.jpg)



![『マインドフルネス (ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51jDEkgJ2YL._SL500_.jpg)