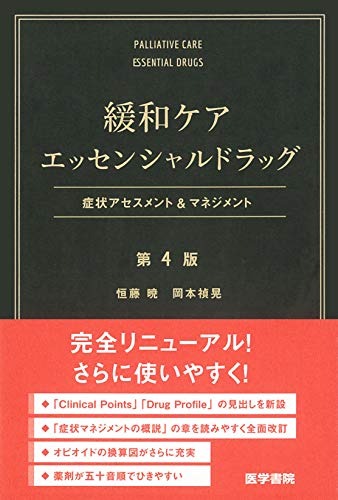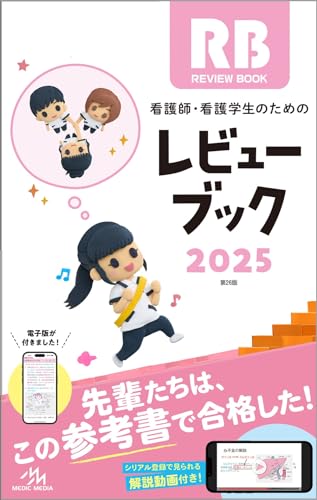【2025年】「緩和ケア」のおすすめ 本 93選!人気ランキング
- ここが知りたかった緩和ケア(改訂第3版)
- 米国緩和ケア医に学ぶ医療コミュニケーションの極意
- 緩和ケアレジデントマニュアル
- 緩和ケアレジデントマニュアル 第2版
- 患者・家族とのコミュニケーション (ようこそ緩和ケアの森)
- 緩和ケア 即戦力ノート: あなたにもできる、やさしい緩和ケア
- がんがみえる 第1版
- がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2020年版
- がん患者の精神症状はこう診る 向精神薬はこう使う
- がんになった親が子どもにしてあげられること
『ここが知りたかった 緩和ケア』の改訂版が出版され、薬剤の使い方やケアのコツがわかりやすく解説されています。新しい治療薬や臨床の進歩が反映され、実際のケアで役立つ情報が満載です。著者の経験から、読者は具体的な悩みの解決に役立つ内容を得られ、看護師や医師にとっても有用な一冊です。多様な読者に対応しており、緩和ケアに携わる人々に推薦されています。
『病気がみえる』シリーズの姉妹本として、腫瘍学に特化したテキストが登場。がんの基礎から診断・治療までを豊富なイラストと共にわかりやすく解説しており、がんに関わる全ての職種に役立つ情報が満載の一冊です。
本書は、がんを患う親とその子どもへのサポートをテーマにしたもので、年間5万6143人の子を持つがん患者に希望を与える内容です。がん患者の4人に1人が子どもを持ち、子どもにがんのことをどう伝えるかが大きな課題となっています。著者は、専門家としての視点から、がん患者が子どもにできることや、適切な伝え方、周囲のサポートの求め方、遺すべきものについてアドバイスしています。著者は医療ソーシャルワーカーであり、がん患者の支援活動を行っています。
「亡くなる過程(natural dying process)を科学する」という視点を国内で初めて提供した書籍の第2版。今改訂では、初版刊行以降の国内外における新たな研究知見をふんだんに盛り込み、著者自身の経験に根差したわかりやすい解説とともに、新たな知見がどのように臨床に役立つのかにも重点が置かれている。「死亡直前と看取り」に携わるすべての医療職者に向けた待望の改訂版、ここに堂々の刊行!
この書籍は、緩和ケアにおける患者と家族の葛藤や、医療現場での「もやもや事例」を扱っています。著者である緩和ケア医の森田達也と生命倫理学者の田代志門が往復書簡形式で、臨床の課題を探求し、文系と理系の視点を交えて深く考察しています。
この書籍は、1年目の看護師が臨床現場での不安を乗り越えるためのコツをまとめたもので、Instagramで人気の看護師しゅーぞーさんが執筆しています。基礎的な看護技術や心の持ち方、日々の勉強法から急変時の対応まで、イラストや図解を用いてわかりやすく解説しています。また、先輩看護師にも役立つ指導方法についてのアドバイスも提供しています。全体を通じて、1年目の看護師の成長をサポートする内容となっています。
この本は看護師が行う基本的な手技「吸引・排痰法」について深く掘り下げ、臨床での実践に役立つ情報を提供しています。特に教科書には記載されていない具体的な困りごとの解決法を詳しく解説し、看護師や介護職、家族にも役立つ内容です。各レッスンでは、痰や吸引の技術、排痰法、体位ドレナージなどが紹介されており、実践的な知識を得ることができます。また、著者は看護師YouTuberとしても活動しており、学びを通じて看護の楽しさを伝えています。
「ナースのメモ帳」は、累計35,000部を突破した人気の書籍で、20万人のフォロワーを持つ内容を集約しています。128種類の薬剤を見開きで比較し、患者の状態に応じた使い分けを分かりやすく解説。ナースや薬剤師が協力し、後輩指導にも役立つ情報が詰まったお守りのような一冊です。
迷い多き緩和医療の現場…でも大丈夫!患者さんがモルヒネは嫌だ、と拒絶したら?終末期の口の渇き(口渇)にどう対応しよう?患者さんに抗がん剤治療の中止をどう伝えよう?「鎮静」をご家族にどう説明すればいいんだろう?などなど、身近な難問をエビデンスで解決。 1 疼痛(とりあえずモルヒネ増量…? レスキューの使用回数が多いから、ベースアップでOK? ほか) 2 疼痛以外の身体症状(呼吸困難にモルヒネ? 腹水の処置、どうしよう? ほか) 3 精神的サポートとコミュニケーション(抗がん剤治療の中止をどう伝えるか? 緩和ケア病棟をどう紹介するか? ほか) 4 終末期ケア(予後をどうやって予測するか? 看取りの時期に入ったら? ほか)
本書は、現役ナースが解剖生理学を1000点以上のイラストを用いてわかりやすく解説した入門書です。解剖学の基本から臨床で役立つ知識まで幅広く網羅しており、楽しく学べる内容になっています。看護学生や医療従事者におすすめで、基礎医学を学ぶ際に役立つ情報や豆知識も豊富に含まれています。著者は看護師でイラストレーターの角野ふち、監修には医学部教授や助教が関わっています。
「かんテキ」は、看護やコメディカル向けに循環器疾患の理解を深めるための実用書です。1,500点以上のイラストや図解を用いて、患者の病態や必要な対応を視覚的にわかりやすく解説しています。難しい医学用語を使わず、実際の臨床で役立つ知識を提供し、患者への説明や観察ポイントも明確にしています。具体的な症例や会話例を通じて、実践的なケアのイメージを持つことができる内容です。
本書は、疾患や患者、看護、観察について感覚的に理解できる医療スタッフ向けの教科書です。ナースや医療従事者が臨床現場で必要な知識を視覚的に学べるよう、解剖イラストやケアの4コママンガが豊富に掲載されています。消化器疾患に特化し、患者対応や薬剤知識も詳しく解説。医師がナースの疑問に答えるQ&Aコラムもあり、実践的な知識を身につけることができます。難しい用語を使わず、図解やイラストで理解しやすくまとめられています。
「かんテキ」は、看護師や医療従事者向けに脳神経疾患の患者対応を視覚的に理解できるようにまとめた書籍です。1,200点以上のイラストや図解を用いて、発症から退院までの流れをストーリー形式で解説。難しい医学用語を使わず、わかりやすく、実践的な知識を提供します。各疾患の重要ポイントや観察項目も明確に示されており、実際の臨床現場で役立つ内容となっています。
「かんテキ」は、妊産婦や患者ケアに特化した医療スタッフ向けの一冊で、疾患や生理を視覚的に理解できる内容です。妊娠・分娩から婦人科疾患まで幅広い知識を美しいイラストと簡潔な解説で提供し、初期研修にも役立つ内容となっています。重要なポイントや「ヤバサイン」などの実践的な情報も含まれており、基本を素早く把握できる構成です。
「かんテキ」は、看護師やコメディカル向けに、整形外科の疾患や患者対応の重要ポイントを視覚的にまとめた実践的なテキストです。新人ナースや研修医が必要な知識を短時間で習得できるよう、1ページに要点を凝縮し、1,500点以上のイラストを用いて理解を助けます。難しい医学用語は使わず、図解や箇条書きで情報を整理し、臨床現場で自信を持って対応できるように設計されています。
「かんテキ」は、医療従事者向けに患者の肺に優しい換気の仕組みをわかりやすく解説した本です。人工呼吸に関する重要な知識を、独自の視点と豊富なビジュアルを使って丁寧に説明しています。モードや波形の基本、人工呼吸管理のポイント、肺保護換気の理解を深める内容が含まれており、医師やナースはもちろん、すべての医療従事者に役立つ一冊です。
本書は、循環器科のナース向けに心電図の判読を解説したもので、基本波形や異常波形の見分け方を図版や症例を用いて詳しく説明しています。ドクターコールのポイントや患者への対応方法も紹介されており、臨床現場での適切な対応をサポートします。モニター心電図から12誘導心電図までを網羅した内容で、心電図のバイブルとされています。著者は心電図の教育に長年携わっている医師です。
妻の末期ガン闘病中、家族は会話もしなくなり最悪の状態に。そんな中、モデルでデザイナーの雅姫さんに保護犬を飼うことをすすめられ出会ったのが「福」だった。「福」との出会いと日々を「福」の写真とともに綴った家族の物語。 はじめに......2 悪性胸水......12 抗がん治療開始......19 終わりの見えない苦しみ......23 私、もう長く生きられないでしょ......29 犬を飼うと毎日が絶対楽しくなるよ......37 セラピードッグを知る......48 アンズとの出会い......54 アンズを我が家へ......63 アンズから福へ......72 困り顔の新しい家族......78 外が怖い......84 冬空の下で根くらべ......94 深夜のお散歩......102 ペッカとキップル ......110 父と娘の関係......117 福の心がとけたとき......122 留守番中のいたずら......128 日常におきた変化......134 犬らしくない犬......139 はじめてのキャンプ......143 カリスマトレーナーとの出会い......152 犬と幸せに暮らす方法55......159 セカンドオピニオン......170 残された時間でできること......178 ドーナツ......182 犬は夢を見る......186 手作りおやつの日々......188 旅行へ......193 福井へ......200 8月の朝散歩......206 マグロのごはんのこと......210 夏の終わり......214 緩和ケア病棟......220 季節外れの花火大会......226 成人式の前撮りに参加......232 退院そして自宅療養......239 保護犬を飼うということ......244 おわりに......252
誰も教えてくれなかった”基礎の一歩先”がコンパクトにわかり,実臨床でも武器になる“正確に,秒で読む”鑑別力がつく必携書! 心電図検定1級合格を目指すために必要な判読スキルを身につけるために,上級者も悩ませる梗塞部位特定,軸偏位・ブロック・起源・変行伝導の攻略を主眼に解説。表面的な理解にとどまっていたり,単なる暗記で対応しがちな基礎メカニズムを上級問題に対応できるよう学び直し,“正確に,秒で読む”ためのエッセンスがわかる。本番を想定した模擬問題100問で力試しでき,各問題から基礎章をおさらいできるリンケージ付き。 1章 講義編 ①はじめに ②心電図検定受験の心構え 心電図検定とは/心電図検定の各級/検定当日の注意点 ③心電図の基礎 まずは波形と心拍数を考える/正常と異常を見分ける ④P波に異常をきたす疾患 異所性心房調律/右房性P波/左房負荷/上室期外収縮(PAC)/PACの起源を探る/洞不全症候群 ⑤PQに異常をきたす疾患 房室ブロック/房室ブロックのまとめ ⑥QRS波に異常をきたす疾患 変行伝導/脚ブロック初級編〜興奮の流れで理解を深める/脚ブロック上級編〜脚は2本ではなく3本である/心室期外収縮(PVC)/PVCの起源を探る ⑦STに異常をきたす疾患 急性冠症候群(ACS)/冠動脈の障害部位を探る/Brugada症候群/不整脈原性右室心筋症(ARVC)/早期再分極症候群,J波(オズボーン波) ⑧T波に異常をきたす疾患 陰性T波をきたす疾患(虚血性心疾患,左室肥大,肥大型心筋症)/たこつぼ型心筋症 ⑨QTに異常をきたす疾患 QT延長症候群/QT短縮症候群/電解質異常 ⑩発作性上室頻拍 房室回帰性頻拍(AVRT)/房室結節リエントリー頻拍(AVNRT)/心房頻拍(AT) ⑪WPW症候群におけるケント束付着部位の推定 ケント束とは/なぜデルタ波ができるのか/WPW症候群とタイプ一覧/ケント束付着部位 ⑫頻脈性不整脈(心房細動,心房粗動,心房頻拍) 心房細動(AF)/心房粗動(AFL)/心房頻拍(AT) ⑬頻脈性不整脈(心室頻拍,心室細動) 心室頻拍(VT)/心室細動(VF) ⑭肺動脈血栓塞栓症 ⑮心膜炎・心筋炎 ⑯植込み型心臓電気デバイス 植込み型心臓電気デバイスとは/ペーシング波形の特徴/ペーシング位置による波形の違い/デバイスの誤作動/プログラマーからみる心電図/ホルター心電図 ⑰薬物による心電図異常 ジギタリス中毒/抗不整脈薬(薬剤性QT延長症候群,Ⅰcフラッター) ⑱心筋症 心アミロイドーシス/心サルコイドーシス/拡張型心筋症 ⑲小児の心電図(先天性心疾患) 胸部誘導の陰性T波/心房中隔欠損症/房室中隔欠損症/右胸心 ⑳電極の付け間違い 2章 問題編 [模擬問題] 第1回目“Hard” [模擬問題] 第2回目“Extreme”
著者が18年間の看護経験を基に作成した「看護のメモ帳」は、看護師が知りたい情報をポケットサイズでまとめたものです。13のテーマと92項目にわたり、看護技術や処置、急変対応、検査、薬剤などの具体的な内容を詳細に記載しています。正確な知識が求められる現場で役立つ一冊で、医学監修による専門的なアドバイスも含まれています。
このポケットブックは、持ち運びに便利なサイズで、各科共通の重要情報やスケール・データを簡単に参照できる。北里大学病院の認定看護師・専門看護師の臨床視点も含まれており、第2版では新人・若手看護師向けの新しい項目が追加されている。
看護学生向けの「クイックノートシリーズ」の「看護技術」編が発売されました。この本は、実習でよく行う看護技術を学生の要望に基づいて厳選し、ポイントや根拠を豊富な写真やイラストとともにまとめています。ポケットサイズで持ち運びやすく、実習時に必要な情報をいつでも確認できる便利なガイドです。
看護学生に人気の『看護技術がみえるvol.2』がリニューアルされ、注射や採血などの侵襲的技術を豊富なイラストと写真で解説しています。臨床現場での技術のコツや注意点、手順の根拠が詳述されており、最新のガイドラインにも対応しています。また、実習用の「基準値早見表」も追加されています。
『フィジカルアセスメントがみえる』が『看護がみえる』シリーズとしてリニューアルされ、看護学生や新人看護師に役立つ内容となっています。特徴として、豊富なイラストや写真を用いて身体の評価を解説し、解剖生理や病態に関する情報も充実。新たに動画やROMシミュレーターなどの付録が追加され、身体計測の章も設けられました。各章にはアセスメントの目的が明記され、異常所見の写真も増え、より実践的でわかりやすい内容になっています。
『看護がみえる』シリーズから新たに登場した本書は、看護実習に役立つアセスメントに焦点を当てており、患者の個別性を考慮した理解を促進します。発達段階や健康状態、治療、療養の場に基づいたアセスメントのポイントをイラストで解説し、家族や地域社会のニーズも考慮しています。全ページにQRコードがあり、特典コンテンツとしてクイズも提供され、知識の定着を助けます。
この書籍は、看護現場でのコミュニケーションに役立つ会話術を紹介しており、患者の症状や状況に応じた250の具体的な言葉がけの実例を提供しています。目次には、基本フレーズや処置時のコミュニケーション、患者タイプ別の対応、ご家族への接し方、困った時の対応、スタッフとのコミュニケーションが含まれています。著者は看護の専門家で、看護師のキャリア支援や教育プログラムの企画運営にも携わっています。
この書籍は、「週刊医学界新聞」の人気連載を基に、医療コミュニケーションの方法論を実践的に学ぶために書かれています。21のテーマを通じて、エビデンスに基づくコミュニケーションスキルを習得できる内容です。目次は、医療者の倫理観、基本的なコミュニケーションスキル、状況に応じたコミュニケーション法、共感力を高める方法に分かれています。著者は中島俊氏で、医療コミュニケーションや心理療法の専門家です。
この書籍は、ケア従事者向けの対話スキルを向上させるための実践書です。著者はクリニカルサイコロジストで、対話の「型」としてA(Assessment)、B(Be with the Patient)、C(Clinical Questioning)、D(Direction & Decision)の4ステップを解説しています。各ステップで使用できるスキルを練習課題を通じて磨くことができ、対話の目的や順序を学ぶことができます。
本書は、認知症の人とのコミュニケーションを改善するための具体的な「言いかえ」フレーズを紹介しています。著者は認知症研究の第一人者で、認知症の人の心を理解し、伝わりやすい言葉を使うことで、家族のストレスを軽減できることを提案しています。具体的な事例を挙げ、感情を考慮した優しい声かけが重要であることを強調。また、認知症の基礎知識や家族の悩みに対するQ&Aも掲載されており、実用的なガイドとして活用できます。
物語で学ぶ,医療者と患者側の誤解と心理.意思決定支援のコツが楽しく身につく実践書. 哲学と医療行動経済学という多方面の知識を用いてがん患者の意思決定支援を解説した前著は,その難しさの要因を紐解き,解決の糸口を紹介して好評を博した.本書は,その待望の「実践編」である.医療者と患者側の誤解と心理を,7つの物語をベースに検証し,成功の秘訣を語っている.各物語には意思決定支援に必要な知識が散りばめられており,自然に大事なことが頭に入るように工夫した.楽しく学べる新たなかたちの実践書だ. 目 次 1st ストーリー 診療の経過 解説 ハーバード交渉術 方法の原理 現在バイアス コミットメント Step-Up <3Dハーバード流交渉術> 1st ストーリーの続き 解説 アンガーマネジメント 2nd ストーリー 診療の経過 解説 現状維持バイアス 正常化バイアス 実現可能性と論理的可能性 行動変容を促す「動機付け」 Step-Up <ナッジとその倫理性> 2nd ストーリーの続き Step-Up <ラポール形成> 3rd ストーリー 診療の経過 解説 ヘルス・リテラシーとバイアス 緊急ACP(Advance Care Planning) 3rd アナザーストーリー「音読みでなく訓読みで」 4th ストーリー 診療の経過 解説 遺伝子検査とがん治療 セルフ・マネジメントの必要性(とくにタイム・マネジメント) Step-Up 遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC) 4th ストーリーの続き 解説 がん相談支援センター 担当医にできること(戦略的ニヒリズム) 5th ストーリー 診療の経過 解説 医療者が持つ責務と家族が持つ責務の違い 人がそうするには理由がある~肯定ファーストの姿勢 Step-Up 「関心相関性と表の関心・裏の関心」 5th アナザーストーリー エビデンスはどうやって作られているのか? 高齢者がん診療ガイドライン 5th ストーリーの続き 在宅療養への障壁(キーパーソンが抱える責務,社会規範と市場規範) 市場規範と社会規範の併存を実現する「方法の原理」 6th ストーリー 診療の経過 解説 重篤な病気をもつ患者との話し合い(Serious illness conversation program) がんは予防できるのか? Step-Up <がん教育> 6th ストーリーの続き 解説 システム1とシステム2 確証バイアス プロスペクト理論 7th ストーリー 診療の経過 もやもやのすすめ 7th ストーリーの続き 肯定ファースト 意思決定能力 代理意思決定 Step-Up <事前指示とDNAR(Do Not Attempt Resuscitation)> 7th ストーリーのその後 Step-Up <臨床倫理の4分割法> おわりに 索引
この書籍は、治癒を目指さない精神医療のアプローチを探求し、神社のおフダやシイタケの原木を利用した独自の実践を通じて、精神症状の理解や患者との関係性の構築を提案しています。著者は、精神看護の専門家であり、ACT(包括型地域生活支援プログラム)を通じて、精神疾患を病ではなく苦悩の一形態と捉え、支援のあり方を変革する重要性を論じています。全体を通して、精神医療の専門性を再考し、社会生活へのシフトを促す内容となっています。
この書籍は、発達障害についての基礎知識や重要な情報を提供する「発達障害の教科書」です。編集者・ライターが専門家13人にインタビューし、発達障害の理解を深める内容をまとめています。主なポイントとして、発達障害は「脳の個性」であり、治療よりも対応が重要、ADHDの薬は効果的であること、二次障害のリスク、発達障害の診断が自尊感情を守る役割を果たすことなどが挙げられています。また、特別支援学校の意義や仕事選びの注意点についても触れています。
本書は、子どもが直面する6つのつまずきに対する100種類以上の遊びを紹介し、感覚統合の視点から問題を解決する方法を提案しています。内容は、ボディイメージやバランス感覚、触覚、協調運動、感覚欲求、ゲームを通じた感覚統合のアプローチに分かれており、実践しやすい遊びが満載です。著者の藤原里美氏は、発達障害のある子どもへの支援を行い、子どもが楽しく遊ぶことで自然に発達を促すことを目指しています。全ページカラーで、視覚的にもわかりやすく工夫されています。
本書は脳神経外科看護に必要な知識をビジュアルで解説し、先輩ナースの経験を基にしたケアのコツや注意点を紹介しています。新人や異動ナース向けに、解剖生理や神経症状、外科手術、治療法、重要薬剤、ドレーン・シャント管理などをコンパクトにまとめた内容です。理解度確認のためのWEBテストも付属しています。著者は名古屋市立大学の講師です。
この書籍は、田淵仁志先生が実践する心理的安全性の高い組織作りをテーマにしたもので、オンラインセミナーを基にしています。ミスが起こっても責めずにチームで改善し、成長する職場環境の重要性を示しています。内容は、心理的安全性の定義からリーダーシップ、認知バイアス、ライフ・サイクル理論、チームの目的との関連まで多岐にわたります。著者は医療マネジメントの専門家であり、実践的なQ&Aも含まれています。
「緩和ケア」に関するよくある質問
Q. 「緩和ケア」の本を選ぶポイントは?
A. 「緩和ケア」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「緩和ケア」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ここが知りたかった緩和ケア(改訂第3版)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで93冊の中から厳選しています。
Q. 「緩和ケア」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「緩和ケア」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。