【2025年】「国際情勢」のおすすめ 本 174選!人気ランキング
- (247)歴史で読み解く!世界情勢のきほん (ポプラ新書 247)
- 地政学でわかるわたしたちの世界: 12の地図が語る国際情勢 (評論社の児童図書館・絵本の部屋)
- 世界史と時事ニュースが同時にわかる 新 地政学 (だからわかるシリーズ)
- 恐怖の地政学 ―地図と地形でわかる戦争・紛争の構図
- 地政学 ー地理と戦略ー
- 歴史で読み解く!世界情勢のきほん 中東編 (ポプラ新書 269)
- 日英対訳 英語で話す世界情勢
- 大人の学参 まるわかり近現代史 (文春新書 1393)
- この一冊でわかる世界経済の新常識2023
- 「女性目線」のマーケティング入門
本書は、地形が国の歴史や政治に与える影響を探る絵本形式の作品で、12枚の地図を通じて国際情勢を解説します。貧富の差や戦争の理由、アメリカの強さなどを豊富なイラストと詳細な解説で説明し、地政学的視点から世界を理解する手助けをします。著者はジャーナリストのティム・マーシャル氏で、翻訳は大山泉氏が担当しています。
本書は、地政学の観点から戦争や紛争の原因を探求し、地理的要因が国家に与える影響を考察しています。中国やロシアの動向、アメリカの地理的優位性の変化などを通じて、国際情勢の複雑さを明らかにします。20枚の地図を用いて、地球上の危機と平和を分析し、地形、歴史、宗教、人種、文化がどのように絡み合っているかを示しています。著者は国際情勢の取材経験が豊富なジャーナリスト、ティム・マーシャルです。
日 本 を 担う国 家 のリーダー たち へ 「日本の国家安全保障は大丈夫なのか?」 本書には、きっとなんらかのヒントがある。 地政学の原点。幻の名著。ついに完全版が復刊! 奥山真司 完訳 「古典地政学」から「批判地政学」へ 本書は「戦略学系の地政学研究の論文集」という日本ではまったく紹介されたことのない、かなり珍しいジャンルの本である。(奥山真司談) 第1章 なぜ地政学なのか 第2章 ハルフォード・マッキンダー卿 -ハートランド理論の流れ- 第3章 地政学者アルフレッド・セイヤー・マハン 第4章 エアパワー、スペースパワー、地理 第5章 宇宙時代の地政戦略-アストロポリティクスによる分析- 第6章 批判地政学の理解のために-地政学とリスク社会- 第7章 地政学 戦いの場としての国境 第8章 インフォメーションーパワー-戦略、地政学と第五次元- 第9章 逃れられない地理 第10章 帆船時代における天候、地理、そして海軍力 第11章 地理と戦争の関係について 第12章 ドイツ地政学-ハウスホーファー、ヒトラー、そしてレーベンスラウム 第13章 ロシアの地政学における事実と幻想 訳者解説◆奥山真司 地政学の「三位一体」
この本は、子どもと大人が知るべき世界の仕組みを「地政学」を通じて楽しく学ぶ内容です。高校生と中学生の兄妹が年齢不詳の男「カイゾク」との会話を通じて、歴史問題や国際ニュースの背景、国同士の駆け引きが理解できるようになります。著者は国際政治記者の田中孝幸で、複雑な国際情勢を物語形式でわかりやすく解説しています。
この書籍は、ナチス侵攻から太平洋戦争までの主要な戦闘とその経過を詳細に解説したアトラスです。時間軸と地図を連動させ、戦場や戦況の変化を視覚的に理解できるように構成されています。地図100点、総図版278点を収録し、真珠湾攻撃や沖縄戦など、日本の戦いも詳述。著者は歴史家のピーター・スノウとリチャード・オウヴァリーで、両者は歴史に関する豊富な著作を持つ専門家です。
この書籍は、戦争の危機がなぜ続くのかという問いに対し、国際政治の現実を分析する入門書です。著者は、軍縮、経済交流、国際機構などを具体的に検討し、国家利益やイデオロギーの絡み合いを踏まえた議論を展開しています。国際関係を単純化せず、現実的な視点から平和の実現を探求しています。著者は高坂正堯で、国際政治学の専門家です。
本書は、イギリスの政治家ウィンストン・チャーチルによる第二次世界大戦に関する記録であり、彼の強力な指導力と歴史観に基づいています。内容は1919年から1940年5月10日までの出来事を描写しており、特にヒトラーの台頭や国際情勢の変化に焦点を当てています。著者のチャーチルはノーベル文学賞を受賞した歴史家でもあり、彼の視点からの戦争の理解を深めることができます。
本書は、第二次世界大戦におけるドイツ軍(空軍、海軍、陸軍、武装親衛隊)と政府の失敗を分析し、なぜ史上最強と謳われたドイツ軍が滅亡したのかを探る戦争学の新しい視点を提供する。著者は、過去の戦争からの教訓を無視した小失敗や、戦闘車両・空軍・海軍の技術的問題を考察し、ドイツ軍の優れた点も紹介している。著者の三野正洋は日本大学の講師で、現代史の執筆にも取り組んでいる。
池上彰氏が監修した本書は、新社会人や就活中の学生に向けて、政治、経済、国際情勢の基礎知識をわかりやすく解説しています。イラストや漫画、チャートを多用し、重要なポイントを一目で理解できる内容となっており、社会人としての常識を身につけるための実用ガイドブックです。180ページにわたり、政治の仕組み、経済の基礎、国際情勢について詳しく学べます。
この書籍は、フランス革命から始まる近代史の重要な出来事を描いており、ナポレオンの生涯や、ロシア、イタリア、ドイツの近代化、アメリカの歴史、中国の屈辱の歴史、二つの世界大戦の経緯とその後の世界情勢を追っています。各章では、18世紀から21世紀までの歴史的な変革や運動がまとめられています。著者は歴史学者の綿引弘、漫画家の小杉あきら、ほしのちあきです。
国際政治学を専攻する3人の著者が,各人の得意分野を生かし,総花的であるよりも深く掘り下げようと心がけて書き上げた教科書。 国際政治を歴史的観点からとらえる,社会科学としての国際政治学を基本的研究手法とする,理論的枠組みをふまえつつ国際政治の諸側面について実証分析を行う,という著者3人が,各人の得意分野を生かし,総花的であるよりも深く掘り下げようと心がけた教科書。 序 章 分析枠組みとしての国際政治学 第1章 国際政治学の見取り図 第2章 国際政治の歴史的視角 第3章 対外政策の選択 第4章 国際秩序 第5章 安全保障 第6章 国際政治経済 第7章 越境的世界 引用文献 事項索引 人名索引
現代世界を理解するためには,それを形作ってきた歴史を把握することが必要不可欠である.16世紀から第二次世界大戦終結に至る国際関係史を,ヨーロッパからアメリカ大陸,アジア,アフリカ,中東まで広く視野に入れ,平易かつ丁寧に描いた決定版通史. 第I章 ヨーロッパの勢力拡張開始期の世界 第II章 大西洋圏の諸革命とウィーン体制 第III章 イギリスの経済的優越と新たな国民国家の登場 第IV章 帝国主義の時代の国際関係 第V章 帝国主義世界とヨーロッパの大国間関係 第VI章 第一次世界大戦と国際情勢の新展開 第VII章 パリ講和と戦後世界の混乱 第VIII章 相対的な安定の回復 第IX章 国際秩序の崩壊と戦争の勃発 第X章 地球規模の戦争としての第二次世界大戦 終章 国際関係史の中の第二次世界大戦 参考文献/年表
主権国家体系の成立と展開に着目し歴史的な観点から国際政治の歩みを辿る。宗教改革からトランプ大統領の誕生までをこの一冊で。 現代の世界は,どのようにして成り立ってきたのか。主権国家の成立とその地理的拡大,そしてその部分的な変容に着目し,歴史的な観点から国際政治の歩みをたどる。宗教改革からトランプ大統領の誕生までの約500年間の国際政治の大きな流れをつかむ。 序 章 なぜ国際政治史を学ぶのか 第1部 主権国家体系の誕生と展開 第1章 近代主権国家体系の生成 第2章 勢力均衡とナショナリズム 第3章 帝国主義の時代 第2部 2度の世界大戦 第4章 第一次世界大戦の衝撃 第5章 第一次世界大戦後の国際秩序 第6章 国際秩序の崩壊 第3部 冷 戦 第7章 冷戦の起源と分断体制の形成 第8章 グローバル化する冷戦 第9章 冷戦体制の変容 第10章 冷戦終結への道 第4部 主権国家体系を超えて 第11章 湾岸戦争とソ連解体 第12章 EUの誕生と深化・拡大 第13章 冷戦後の地域紛争・民族紛争 第14章 新興国の台頭 第15章 21世紀の国際政治
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
本書は、1914年に始まったバルカン戦争がどのようにしてヨーロッパの戦争、さらには第一次世界大戦へと拡大したのかを考察しています。近年の研究を基に、戦史、技術進展、社会変化、国際体制の変化などを分析し、帝国から国民国家への移行や女性の社会進出、福祉国家化に与えた影響を探ります。著者は木村靖二で、ドイツ近現代史を専門とし、東京大学名誉教授です。
本書は、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教、仏教、ヒンドゥー教、神道など、主要な宗教の重要ポイントを図版を用いてわかりやすく解説しています。池上解説スタイルで、宗教に関連するニュースを理解しやすくすることを目的としています。
20世紀とはいかなる時代であったのか? 帝国主義、2つの大戦、冷戦、地域紛争の惨禍を経験した激動の世紀の実像を手際よく描き出し、多元主義的国際社会実現の可能性を考える。豊富な図版・資料とともに、現代の国際政治の流れを新たな叙述で描き切った信頼のテキスト。 序 章 20世紀と国際政治 1 「国際社会」 と 「国際政治」 2 20世紀はどんな時代であったか 第Ⅰ部 2つの世界大戦の時代 第1章 帝国主義の時代と第一次世界大戦 1 帝国主義の時代 2 第一次世界大戦と各国の戦争目的 第2章 第一次世界大戦後の国際体制 1 ロシア革命とウィルソンの14カ条 2 大戦の終結とヴェルサイユ講和会議 3 ヴェルサイユ=ワシントン体制 第3章 1930年代危機と第二次世界大戦の起源 1 世界恐慌と国際体制の崩壊 2 ファシズム諸国の対外侵略と宥和政策 3 第二次世界大戦への道 第4章 第二次世界大戦 1 枢軸国の攻勢と戦線の拡大 2 反ファシズム連合の形成 3 ヨーロッパ第二戦線問題 第5章 第二次世界大戦の終結と戦後秩序 1 戦後秩序の形成 2 大戦の終結と諸結果 第Ⅱ部 冷戦と地域紛争の時代 第6章 冷戦の起源とヨーロッパの分裂 1 米、ソの戦後政策と冷戦の起源 2 ヨーロッパ分断への政治過程 第7章 冷戦と超大国の支配 1 覇権システムとしての冷戦体制 2 アジアと冷戦 第8章 冷戦の諸相 1 冷戦と核兵器体系 2 デタントから冷戦終結へ 第9章 冷戦後の世界と地域紛争 1 「冷戦後」 と地域紛争 2 民族・宗教と地域紛争 —— ユーゴスラヴィア 第10章 中東紛争と湾岸戦争 1 中東紛争と大国の歴史的責任 2 湾岸戦争とその遺産 第11章 テロとの戦争 —— アフガニスタンとイラク 1 9.11事件とアフガニスタン戦争 2 イラク戦争と国際秩序 終 章 21世紀の国際社会と国際政治 1 その後の国際社会 2 21世紀の課題 付 録 : 国際連合憲章
本書『サクッとわかるビジネス教養 地政学』は、急速にグローバル化が進む中でビジネスパーソンが世界情勢を理解するための地政学の重要性を解説しています。著者の奥山真司氏が、特別な図解を用いて地政学の基本概念や国際関係をわかりやすく説明し、最新の国際情勢に基づいた情報を提供しています。具体的には、パレスチナ・イスラエル戦争やロシアのウクライナ侵攻などのトピックを取り上げ、地政学的視点からの理解を深める内容となっています。初心者でも簡単に地政学を学べるよう工夫されており、会話や説明ができるレベルに達することを目指しています。
いま世界では、パンデミックの混乱がつづくなか、ロシアのウクライナ侵攻や切迫する台湾有事、北朝鮮のミサイル発射など、物騒なニュースがたえません。なぜこうした問題が起きているのかを考えるとき、さまざまな解釈の方法があるでしょう。 「地政学」とは、地図をもとにその国の政治や軍事を考えていく学問です。軍事理論でもあるため、戦後の日本では封印されていました。 地理というのは、時代が変わっても変わりません。ですから、変わらない地理をもとにすることで、それぞれの国や地域がとる戦略というのは自ずと決まってくる、と考えられます。となると、いくら世界情勢が混沌としてきても、その国がとるべき一貫した正しい戦略があるはずだ、となります。地政学ではこう考えるわけです。 混沌として先の見えない時代です。だからこそ、普遍的な知である地政学的視点をもつことが大切です。それによって、より自信をもって世界と向き合うことができるはずです。 (「はじめに」より)
政治と経済の相互作用に着目し,理論と歴史/事例分析/展望の3部構成で現代の国際社会が抱える問題を解説するテキスト第3版。 政治と経済の相互作用に着目し,「理論と歴史」「事例分析」「展望」の3部構成で現代の国際社会が抱える問題を解説する。新版以降の国際社会と国際政治経済学の変化をふまえ,各章をヴァージョンアップするとともに,新たに「金融」「移民」の章を設けた。 第3版はしがき 序 章 「経済」の論理と「政治」の論理 第1部 国際政治経済学の理論と歴史 第1章 国際政治経済の見方 第2章 力の構造と国際経済体制 第3章 冷戦とブレトンウッズ体制 第2部 国際政治経済体制の動態 第4章 安全保障と経済 第5章 保護貿易をめぐる政治と経済 第6章 金融グローバル化の構図 第7章 科学技術と現代国際関係 第8章 移民をめぐる政治と経済 第9章 経済発展と人権,民主化 第10章 地球環境をめぐる政治経済 第3部 国際政治経済秩序の模索 第11章 グローバル・レベルの国際秩序の模索 第12章 リージョナル・レベルの国際秩序の模索 第13章 ナショナル・レベルからの国際秩序の模索 終 章 国際政治経済学の未来像 補 論 研究の手引き
本書『裏切られた自由』は、アメリカの第31代大統領フーバーの著作を基に、第二次世界大戦の新たな解釈を提示するものである。著者はフーバーの感情を抑え、資料を通じて戦争の不可解さを探求。従来の「正義の戦争」という視点から脱却し、ヒトラーやルーズベルトの行動、外交の失敗を分析し、日米開戦の背景を考察する。目次にはフーバーの生い立ちや、戦争準備の過程、連合国首脳の協議内容が含まれている。
池上彰氏による20世紀の歴史を映像で解説したDVDブックです。日露戦争や関東大震災、真珠湾攻撃などの貴重な映像をもとに、歴史的瞬間をわかりやすく紹介しています。全15回分の内容を収録し、カラーMAPも付いており、歴史ファンや学生に最適な教材となっています。20世紀が21世紀に与えた影響を映像で確認できる一冊です。
この書籍は、小学生向けに日本の自然、文化、社会、経済について易しく解説しています。池上彰氏が著者で、イラストや写真を多用したビジュアル中心の構成で、総ルビと平易な文章により、低学年から理解できる内容です。全56項目を4つのジャンルに分け、クイズや思考を促すメッセージも含まれています。また、最新の情報に修正可能なウェブサイトも提供されています。
国際関係論の理論を用いて,国際社会の現実のとらえ方を解説するテキスト。事例のアップデートを図り,新版化した。 国際関係論の理論を用いて,国際社会における現実のとらえ方を解説する好評テキストを,事例のアップデートを図り,新版化した。第Ⅰ部では,国際関係の主要な理論を整理し,わかりやすく説明を行い,第Ⅱ部では,具体的事例を理論に基づいて分析・解説する。 序 章 世界を分析する四つの見方 第Ⅰ部 国際関係の見方 第1章 リアリズム 第2章 リベラリズム 第Ⅱ部 国際社会のすがた 第3章 安全保障 第4章 国際経済関係 第5章 地球環境 第6章 人 権 終 章 世界のゆくえと理論的な見方
本書は、地政学をまんがと図解で解説し、世界の紛争や政争の背景を理解するための内容です。著者は、地政学の基本を学びながら、主要国の戦略や利害関係を分析します。主人公の高校生・八嶋七海が、ロシア人の同僚との経験を通じて、地政学的思考や交渉の重要性を学んでいく様子が描かれています。著者は国際関係の専門家であり、地政学の視点から現代の世界情勢を考察しています。
この書籍は、お金と社会の仕組みを理解し、賢くお金を使うための知識を楽しく学ぶことを目的としています。目次には、お金の起源、賢い使い方、銀行の役割、稼ぎ方・増やし方、ニュースの理解を深める方法が含まれています。著者はジャーナリストの池上彰で、教育やメディアの分野で豊富な経験を持っています。
この書籍は、ユートピアニズムとリアリズムの対立を通じて、20世紀の国際政治を分析した重要な作品です。内容は、国際政治学の基本概念、ユートピア的理想と現実の関係、国際的危機における利益調和、リアリズムの批判、政治の本質、権力と道義、国際法の役割、平和的変革の必要性など多岐にわたります。最終的には、新しい国際秩序の展望について考察しています。この本は、戦争や平和、国際問題を理解するための必読書とされています。
「地政学」とは、地図をもとに政治や軍事を考えていく学問です。軍事理論でもあるため、戦後の日本では封印されていました。 地理というのは、時代が変わっても変わりません。ですから、変わらない地理をもとにすることで、それぞれの国や地域がとる戦略というのは自ずと決まってくる、と考えられます。となると、いくら世界情勢が混沌としてきても、その国がとるべき一貫した正しい戦略があるはずだ、となります。地政学ではこう考えるわけです。 混沌として先の見えない時代だからこそ、普遍的な知である地政学的視点をもつことが大切です。それによって自信をもって世界と向き合うことができるはずです。
人口世界一、GDPは世界第5位。新興国のリーダーとも見られるインドの政治、経済、ビジネス、社会、外交戦略をわかりやすく解説。 人口で中国を抜き世界一に、GDPでも英仏を抜き第5位に。近年では「グローバル・サウス」と呼ばれる新興国のリーダーとして見られることも増えたインド。複雑化する国際政治のなかで展開する独自外交も注目されている。長くインドを研究する経済学者が、財閥の盛衰やIT産業の強さの理由といったビジネス面から、米・中・ロとの外交の検証、さらには格差問題の現状まで幅広く解説するインド入門書の決定版。
本書は、気候変動という人類共通の課題に対し、2015年のパリ協定に合意した各国の取り組みを考察しています。しかし、2017年にトランプ米大統領が協定から脱退し、中国やインドなど新興国が条件を巡る争いを始めたことで、国際協調が揺らいでいます。著者は米国、欧州、新興国の利害関係を産業、貿易、金融、エネルギーの視点から分析し、国家間対立の解消に向けた世界と日本の進むべき道を探ります。
本書は、ノモンハン事件から真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、スターリングラード戦など、第二次世界大戦の全体像を網羅した通史です。著者アントニー・ビーヴァーは、各国の指導者や軍司令官の視点を中心に、一般市民や兵士の視点も交えながら詳細に描写しています。日本軍の行動についても最新の研究を基に厳しく論じており、歴史認識を深めるための必読書とされています。世界24カ国で出版され、高い評価を受けています。
本書は国際開発学の学際性を追求し、開発学と開発政策の全体像を示すテキストで、経済学、政治学、社会学を基盤にした多学問的研究を構築しています。初学者向けに「貧困」「ガバナンス」「グローバリゼーション」「農村」「教育」「環境」「平和」といった主要課題を取り上げ、新政治経済学としての学際的アプローチを提示しています。文献やインターネットリソースガイドも付いています。著者は名古屋大学の教授陣で、各分野の専門家です。
本書は、国際政治学の古典的名著であり、ハンス・J・モーゲンソーの現実主義に基づいています。内容は三部構成で、第一部では国際政治の理論と実践、第二部では権力闘争のメカニズム、第三部では国力の本質とその要素を探求しています。モーゲンソーは、人間の本性に基づく権力と国益の概念を通じて、国際平和の実現を主張しています。
本書は、ロシアのウクライナ侵攻を契機に生じた物資不足や供給網の混乱、気候変動がもたらす物価高騰に焦点を当て、21の重要物資に関する国際情勢を解説しています。統計データや地図を用いて、各国のパワーバランスや利害、紛争の影響をわかりやすく示し、日本の輸出入事情や国内流通状況も考察しています。内容は、世界経済のしくみ、国際貿易、地政学、鉱物資源、食料資源、産業資源に分かれ、重要物資が人々の生活やビジネスに与える影響を深く理解する手助けをします。著者は小山堅氏で、エネルギー経済の専門家です。
この増補・改訂版の書籍は、ロシアのウクライナ侵攻を地政学的視点から分析し、冷戦後の新たな覇権時代を探る内容です。主なポイントには、専制主義と民主主義の対立、米国の影響力の低下と中露の連携、インド太平洋地域における日本と英国の関係、日本の地政戦略などが含まれています。著者は国際的な安全保障の専門家であり、豊富な取材経験を持っています。
センセイの最期 西日の渡り廊下で 想像力は無限だ 歌の時間 先生がくれた、光 先生は…… 大切な「症状」 手紙 柔道とは? 中学・高校生に願うこと 巨大な疑問符を与えてくれた 実はすごい、日本の教育 「抗う」こと 学びの同志おっちゃん 八〇歳を超えた中学生 紅茶の味 ことばの裏にある子どもの声を聴く 「消費者的感覚」に立ち向かう 作る、壊す、作る 人生最初の「先生!」は…… 逃げろ、逃げろ! 先生と子どもの関係 色えんぴつ 詩が開いた心の扉 自分の物差し とらわれちゃだめだ 学問を武器にして生徒とわかりあう
この書籍は、脱グローバル経済が日本や世界に与える影響について論じており、特にアメリカの役割の変化とその結果としての無秩序時代の到来を警告しています。著者のピーター・ゼイハンは、経済や政治の野蛮化、人口減少の課題、資源調達の難しさ、そして日本が直面する食糧危機などを詳細に分析し、未来の厳しい現実を描いています。この内容は全米で大きな反響を呼び、地政学的視点からの鋭い洞察が評価されています。
「達成される政策目標」として「平和」をとらえ,国際紛争の時代の「平和政策」を体系的にまとめた初めてのテキスト。 「達成されるべき政策目標」として「平和」をとらえ,国際紛争の時代の「平和政策」を体系的にまとめた初めてのテキスト。国際政治の基礎理論,国際紛争の実態,平和構築の実際について第一級の執筆陣が的確に分析・考察する。国際紛争や国際関係の初学者に最適。 序 章 政策としての平和=藤原帰一 第Ⅰ部 国際紛争をどうとらえるか 第1章 国際紛争はどうとらえられてきたのか=藤原帰一/第2章 現代紛争の構造とグローバリゼーション=遠藤誠治/第3章 国際法と国際組織の役割=山田哲也/第4章 地域機構は役に立つのか=坪内 淳/第5章 紛争と国際経済組織=大芝 亮 第Ⅱ部 現代国際紛争の実態 第6章 植民地支配の遺産と開発途上国=半澤朝彦/第7章 兵器はどう規制されてきたか=佐渡紀子/第8章 核軍拡と核軍縮=水本和実/第9章 人の移動と難民保護=栗栖薫子/第10章 テロリズムとテロ対策=宮坂直史 第Ⅲ部 平和構築の実際 第11章 軍事介入=星野俊也/第12章 平和構築における政治・法制度改革=篠田英朗/第13章 紛争後選挙と選挙支援=上杉勇司/第14章 国際犯罪と刑法=〓山佳奈子/第15章 開発協力=広瀬 訓/第16章 平和構築とジェンダー=竹中千春/第17章 NGOと市民社会=大西健丞 終 章 国際紛争をこえて=山田哲也
この書籍は、地政学の祖マッキンダーによる「ハートランドの戦略論」を詳述したもので、国際関係を動態的に理解することを目指しています。内容は、社会の動向や帝国の興亡、自由の概念など多岐にわたり、補遺として歴史的事件や地理学の視点も含まれています。著者マッキンダーは地理学の専門家であり、現代地政学の基礎を築いた人物です。
この文章は、国際政治学の古典的名著についての内容紹介です。著者モーゲンソーは、国家間の権力闘争を中心に、バランス・オブ・パワーや国際道義、国際世論、国際法などの抑制要因がどの程度機能するかを考察しています。目次では、国家権力の制限に関する複数の部が示され、バランス・オブ・パワーの評価、国際道義、世界世論、国際法、主権の問題、現代の国際政治の動向などが扱われています。全体として、現代世界の国際政治の本質を明らかにする内容となっています。
この書籍は、地政学についての解説を提供し、国家戦略を考える上での重要な知識を集積しています。地政学は、指導者や安全保障担当者が自国の安全や優位を確保するために用いる地理に基づく思考パターンを指します。著者は、地政学の巨人たちの思考法、シーパワーとランドパワーの違い、戦略的なルートやチョークポイント、グランド・ストラテジー、バランス・オブ・パワー、戦争の目的について解説しています。著者は国際地政学研究所の上席研究員であり、戦略学の専門家です。
増刷決定! 新装完全版の登場! “リアル・ポリティクス、攻撃的現実主義の教科書" 「ウクライナ紛争の責任はアメリカが持たなければならない! 」 国際政治学の第一人者による、意見表明(YouTube)に世界が驚いた。 今、最も注目すべきミアシャイマー(シカゴ大学終身教授)の主著。 原著オリジナル版に書き下ろし「日本語版に寄せて」を加え、 「中国は平和的に台頭できるか?」の章を収載。 訳者奥山真司による解説、注釈も充実。 米中の衝突を確実視し、世界各国の外交戦略を揺るがす、“攻撃的現実主義(オフェンシヴ・リアリズム)"とは!? 過去200年間の世界史的事実の検証から、きわめて明晰、冷徹、論理的に国際システムの構造を分析、北東アジアの危機と日本の運命も的確に予測する。 ミアシャイマーによる北東アジアの将来の見通しはあまり華やかなものではなく、むしろ彼自身が認めているように「悲劇的」なのだ。そしてこの「悲劇」は、モーゲンソーの言うような「人間の愚かさ」にあるのではなく、国際社会(国際システム)の構造による、人間の意志ではコントロールできないところで引き起こされるものだ。......本書のタイトルが『大国政治の“悲劇"』である理由は、まさにここにある。(「訳者解説」より) 《内容紹介》 ■改訂版のまえがき / 日本語版に寄せて ■はじめに ■第1章〈イントロダクション〉 (オフェンシヴ・リアリズム(攻撃的現実主義) / リベラリズム 対 リアリズム / リベラルなアメリカにおける権力政治(パワー・ポリティクス)) ■第2章〈アナーキーとパワーをめぐる争い〉 (国家はなぜパワーを求めるのか / 覇権の限界 / パワーと恐怖 / 国家目標の優先順位 / 世界秩序の創造 / 国家間の協力) ■第3章〈富とパワー〉 (パワーの物質的な基盤 / 人口と富:軍事力の根源 / 軍事力の経済的基礎 / 軍事的潜在力と軍事力のギャップ) ■第4章〈ランドパワーの優位〉 (征服 対 強制 / 独立シーパワーの限界 / 戦略エアーパワーの限界 / 陸軍の圧倒的な影響力 / 水の制止力 / 核兵器とバランス・オブ・パワー / 軍事力の計測の仕方) ■第5章〈生き残りのための戦略〉 (実践的な国家の目標 / パワー獲得のための戦略 / 侵略国を抑止するための戦略 / 避けるべき戦略 / リアリスト的な理由によるパワーの譲歩) ■第6章〈大国の実際の行動〉 (日本 1868〜1945年 / ドイツ 1862〜1945年 / ソヴィエト連邦 1917〜91年 / イタリア 1861〜1943年 / 自滅的な行動? / 核武装競争) ■第7章〈イギリスとアメリカ:オフショア・バランサー〉 (アメリカのパワーの勃興 1800〜1900年 / アメリカとヨーロッパ 1900〜90年 / アメリカと北東アジア1900〜90年 / イギリスのグランドストラテジー 1792〜1999年) ■第8章〈バランシング 対 バック・パッシング〉 (どのような時に国家はバック・パッシングをするのか / 革命・ナポレオン時代のフランス 1789〜1815年 / ビスマルク時代のプロイセン 1862〜70年 / ヴィルヘルム皇帝時代のドイツ 1890〜1914年 / ナチス・ドイツ 1933〜41年 / 冷戦 1945〜90年) ■第9章〈大国間戦争の原因〉 (構造(structure)と戦争 /「二極システム」対「多極システム」/「安定した多極システム」対「不安定な多極システム」/ 近代ヨーロッパの大国間戦争 1792〜1990年 / 分析と結論) ■第10章〈中国は平和的に台頭できるか?〉 (オフェンシヴ・リアリズムのまとめ / アメリカの覇権の追求 / サムおじさんの後を追って / 来るべきバランシング同盟 / 戦争は起こるか? / 平和的台頭の希望) ■原注 ■訳者解説とあとがき
ついに全面新改訂! 国と人を守る論理──初版刊行以来、読者の圧倒的な支持を得てきた定番が、11年目にして大改訂を施した。執筆陣も若返り、アップ・ツー・デートな問題意識で「いま問われるべき課題群」に切り込んだ。教科書に、討論の刺激剤に、そして安全保障的思考の訓練に使える一冊。 新訂第4版へのはしがき 初版へのはしがき 第1部 安全保障学入門 第1章 安全保障の概念 1 普遍的定義の欠如 2 伝統的な安全保障概念とその変容 3 新しい安全保障の諸概念 第2章 戦争と平和の理論 1 国際システムからみた国家間戦争の生起 2 二国間関係からみた国家間戦争の生起 3 国家からみた国家間戦争の生起 4 内戦の発生原因 第3章 国際安全保障体制論 1 国際安全保障体制とは 2 覇権モデル 3 勢力均衡モデル 4 集団安全保障モデル 5 集団防衛モデル 6 協調的安全保障モデル 7 「共通の安全保障」モデル 8 ポスト冷戦時代の安全保障体制 第4章 安全保障とパワー 1 ハードパワー・ソフトパワー・スマートパワー 2 パワー行使の諸形態 3 軍事力と安全保障 4 情報と安全保障 5 科学技術と安全保障 第5章 核と安全保障 1 核兵器国の核戦略 2 核拡散の動向 3 核兵器と国際政治 第6章 軍備管理・軍縮 1 軍縮と軍備管理の概念 2 軍備管理・軍縮の諸形態 3 「軍備管理・軍縮」から「軍縮・不拡散」へ 第7章 政軍関係論 ── シビリアン・コントロール 1 現代の軍事組織 2 軍事専門職主義 3 シビリアン・コントロール 第8章 現代紛争の管理 1 紛争の諸形態 2 紛争の予防と管理 3 人道的介入 4 信頼醸成措置 5 危機管理 6 紛争解決 第9章 安全保障の非軍事的側面 1 非軍事的安全保障の概念的枠組み 2 非軍事的安全保障の諸目的 3 安全保障の非軍事的手段 第10章 非伝統的脅威と安全保障 1 「非伝統的脅威」とは何か 2 テロリズム 3 海賊 4 越境組織犯罪 5 大量破壊兵器の拡散 第11章 国連と安全保障 1 集団安全保障機構としての国連 2 冷戦と国連の集団安全保障の空洞化 3 国連平和維持活動(PKO)の発達 4 冷戦の終結と国連の平和機能の活性化 5 『平和の課題』 6 ガリ構想の実践と挫折 7 『平和への課題への追補』 8 ブラヒミ・レポート 9 国連平和機能強化の限界 第12章 1 国際法の法的性質 2 集団安全保障 3 武力紛争法 第13章 ポスト九・一一の安全保障 1 冷戦の終結 2 秩序構想の不在と現実の先行 3 脅威の性格の変化と安全保障への二種類のアプローチ 4 安全保障環境の地域的不均質性 5 九・一一テロ・世界秩序・米国の役割 6 平和と軍事力に関する発送転換の進行 7 安全保障工具の新次元 第2部 日本の安全保障政策の基礎知識 Ⅰ 戦後日本の安全保障政策 Ⅱ 防衛計画の大綱 Ⅲ 日本の安全保障政策の原則 Ⅳ 日本の安全保障関連法制 Ⅴ 日米同盟 Ⅵ 集団的自衛権 Ⅶ 日本の国際平和協力活動 Ⅷ 日本の地域安全保障協力 Ⅸ 日本の軍縮・不拡散政策 Ⅹ 日本の危機管理体制 ⅩⅠ 日本のテロ対策 ⅩⅡ ミサイル防衛 ⅩⅢ 非伝統的安全保障への取り組み 参考文献 執筆者紹介
この書籍は、日本人が第一次世界大戦の重要性を理解していないことを指摘し、戦争の背景や影響を広範な視点から解説する入門書です。著者は、覇権国と新興国の対立や技術革新、グローバリゼーションの進展など、WW1と現代の共通点を示しつつ、戦争技術や国民国家意識、経済的側面などを詳細に探ります。目次には、戦争の発端から日本の参戦、経済影響、戦後の残留物までが含まれています。著者は作家であり、経済の専門家でもあります。
本書は、第二次世界大戦の欧州大戦を、ヒトラー、スターリン、チャーチルの戦略や誤算を通じて描き、19カ国の「周辺国」の視点から多面的に検証するものです。連合国と枢軸国の間で繰り広げられた占領と奪取の歴史を、各国の政治的・軍事的状況を通じて明らかにし、戦闘の詳細や諜報活動も含めた広範な分析を提供します。著者は戦史研究家の山崎雅弘氏です。
E・H・カーから、ヴァンダナ・シヴァまで。変容し続ける国際関係の現実を批判的に乗り越え、オルタナティブを目指すための30冊。 第1部 「現実」をめぐって 第2部 法・規範と自由 第3部 資本と配分的正義 第4部 主権と権力 第5部 ヘゲモニーと複数性 第6部 「周辺」からの声と政治
池上彰氏の著書は、行動経済学をわかりやすく解説し、人間の心理がどのように経済行動に影響を与えるかを探る内容です。主なテーマには、選択肢の数が売上に与える影響(例:二択より三択)、損切りができない理由(サンクコスト効果)、イケアの家具への愛着、政治におけるバンドワゴン効果、人間の非合理的行動、直感による意思決定、そして「ナッジ」理論が含まれています。行動経済学はビジネスや日常生活に役立つ知見を提供します。
本書『インド太平洋戦略』は、自由で開かれたインド太平洋秩序を維持するための挑戦に焦点を当て、地政学的な視点から日米豪印の戦略的競争を分析しています。著者たちは、地域の主要アクターや国際的な視点を交え、地政学の新たな複雑性に対処するためのリソースを提供します。また、安倍元首相の序文や重要な演説も収録されています。著者は国際関係や安全保障の専門家であり、幅広い知見をもとに議論を展開しています。
本書は、第一次世界大戦がどのように始まったのかを、バルカン半島の紛争から詳細に描写しています。著者クラークは、多数の史料を基に、19世紀末から1914年までのヨーロッパの状況を分析し、戦争の原因を探求しています。第一次世界大戦は20世紀の災厄の起源とされ、現在の政治的危機にも影響を与えています。全2巻から成る本書は、国際的に高く評価されています。
この書籍は、1945年以降の世界の動向をマンガ形式でわかりやすく解説した現代史の教科書です。著者は国際関係の専門家で、マンガと要点を押さえた文章を組み合わせることで、視覚的に理解しやすい内容になっています。歴史上の重要人物を通じて、現代の世界情勢やその背景を楽しく学ぶことができ、歴史を復習したい人や新たに知りたい人に最適です。
国際・地域レジームにおける外交構想や理念,交渉戦略を対象に,日本とアメリカの外交を従来とは異なる観点から検討する。 いかなる国の政策も国内では完結しないため,おかれた国際環境を整えようと働き掛ける。WTOやAPEC,FTAといった国際・地域レジームをめぐって,日米はどのような外交構想や交渉戦略を展開しているのか。両国の外交を従来とは異なる観点から分析する。 序 章 国際・地域レジームと複層政治過程 第Ⅰ部 変容する国際レジーム 第1章 WTOの危機?――新ラウンドをめぐるアメリカ政府の陥穽 第2章 法化したWTOと日本の受容――日米リンゴ紛争・WTO裁定の波紋 第3章 TRIPsへの道程――コンピュータ・プログラム問題をめぐる政府間交渉と民間対話 第4章 貿易紛争における「歴史」問題の影――日韓繊維紛争の非政治化の試み 第Ⅱ部 アジア太平洋・地域レジームの模索 第5章 日本によるAPEC提案――通産省の構想とアジアン・ウェイ 第6章 アメリカのAPEC政策の文脈――国内基盤と地域関与の境界 第7章 EVSLをめぐる衝突――乖離する日米のAPEC構想 第8章 FTAAPへの展開――アメリカのAPEC回帰 第Ⅲ部 FTAの選択と地域レジーム化 第9章 日本の政策転換――アメリカ型FTAの「学習」 第10章 アメリカのFTA政策――「先端」と「遅れ」 第11章 競合する広域FTA構想――EAFTA・CEPEA・FTAAP 終 章 交錯する変化と持続の力学
国連は創設60年を迎え改革論議が活発化し,EUは拡大と憲法の批准拒否に揺れ,他の地域的機構やNGOは多様な展開を見せるなど,国際機構は大きなうねりの中にある.国際機構の全体像を示し現代世界におけるその存在意義を問うテキスト,待望の全面改訂. 第1章 国際機構小史 第2章 国際連合 第3章 国連改革 第4章 地域的国際機構 第5章 国際機構創設の動因 第6章 構造・機能・意思決定 第7章 国際機構論の方法 第8章 国際機構の理論化
この書籍は、国際社会における平和の問題を探求し、軍縮、安全保障、司法的解決、国際統治などの視点から平和を実現する方法を論じています。著者モーゲンソーは、外交の役割を強調し、国益の調整を通じて平和を築く重要性を示しています。内容は、制限、変革、調整による平和のアプローチを中心に構成されており、外交の未来についても考察しています。
アジアにおける「地域」構築の試みが,いかにしてアジアの安定と繁栄に寄与するのか。地域「構築」の展開を精緻に分析する。 ASEANなどさまざまな地域制度が重層的に設立されているアジアにおいて,地域「構築」の試みが重要性を増している。諸国家が,内部に対立を抱えつつも,共同で安定と繁栄を実現させようと政策協調や協力を進める姿に,日本への示唆を見る。 序 章 アジアにおける重層的「地域」への着目 第1章 「地域」形成の論理とアジア 第2章 重層的「地域」の萌芽 第3章 「アジア太平洋」対「東アジア」 第4章 「東アジア」と「拡大東アジア」 第5章 「東南アジア」と「北東アジア」 第6章 変容する重層的「地域」 終 章 重層的「地域」としてのアジア─課題と展望
この書籍は、2024年の国際政治の転換点に関連する情報を提供し、政治や政策に関心のある人々や投資家、海外ビジネスに関わる人々に有益な内容を含んでいます。基本的な政治用語や概念を解説し、各地域の政治状況や政党の特徴を詳述しています。目次には、北米、西欧、東欧、北欧、ロシア、中国、中東、ラテンアメリカ、アフリカの政治的な背景と課題が含まれています。著者は山中俊之で、国際的な視点から世界情勢についての執筆活動を行っています。
この本は、ビジネスや学習に役立つ基本的な情報を30~60分で得られる内容を提供しています。地理や歴史、経済に関するテーマを地図や図解を用いてわかりやすく解説し、大人の学び直しや子供の学習意欲を高めることを目的としています。具体的には、ロシアのウクライナ侵攻や米中対立、パレスチナ問題、中国の一帯一路構想など、国際情勢や経済の動きを地政学的に分析しています。著者は地理の予備校講師で、地理を通じて国際情勢の理解を深めることを提唱しています。
戦史イラストレーター、渡辺信吾による飛行機大図鑑!第二次大戦に活躍した軍用機256機、その構造と戦績を余すところなくイラス… 第二次大戦期の軍用機250機以上を掲載する空前の飛行機大図鑑!戦場の空を彩った世界各国の軍用機たち、その構造、性能、戦績の全てがカラーイラストとなって甦ります。手がけるのは気鋭の戦史イラストレーター渡辺信吾! 第二次世界大戦期の軍用機256機を掲載する空前の飛行機大図鑑!零戦、マスタング、Bf109といった世紀の傑作機から歴史の影に埋もれた失敗作にいたるまで、戦場の空を彩った世界各国の軍用機たちがカラーイラストとなって甦ります。第二次大戦中、国家の存亡をかけて戦った軍用機の数々は、いかなる思想の元設計されたのか?その性能は?戦績は?気になる疑問をわかりやすく解説。手がけるのは気鋭の戦史イラストレーター渡辺信吾!
まるで劇を観ているような感覚で楽しく詳しく学べるシリーズ第5弾。第一次世界大戦の展開をドラマティックに描いていきます。 世界史における重要な局面を、劇を見ているような感覚で楽しく詳しく学べるシリーズ第5弾です。第一次世界大戦は戦争の常識を塗り替え、20世紀の世界に多大な影響を与えた避けることのできないテーマです。本書では第一次世界大戦の原因から結果までをヨーロッパ戦線を中心に扱い、近代兵器が続々と登場して、これまでにない惨禍をもたらした戦の内容をドラマティックに描いていきます。臨場感あふれる解説と“歴史が見える”イラストで学べる、まったく新しい歴史教養書! 第1章 第一次世界大戦前夜 第2章 1914年 第3章 1915年 第4章 1916年 第5章 1917年 第6章 1918年 第7章 パリ講和会議
池上彰が選んだ6つのテーマ(地図、お金、宗教、資源、文化、情報)を通じて、現代の世界を解説する本です。格差や対立の背景を具体的に理解する手助けをし、「高校1年生にわかるように話す」スタイルで大人にも読みやすく構成されています。著者は、現地取材で得た知識を基にした授業を行い、今後は国や地域別にテーマを深掘りするシリーズを展開予定です。
本書は、地政学を通じて国際情勢や戦争の歴史を体系的に学ぶことを目的としています。イスラエルとパレスチナの紛争やロシアのウクライナ侵攻、日本の米軍基地の意義など、様々な国際問題を地政学的視点から考察。具体的には、パックス・ブリタニカ、パックス・アメリカーナ、中国やロシアの影響、アジアにおける日本の地政学などを扱い、最新のビジネス教養を提供します。著者は一橋大学の教授で、国際関係学の専門家です。
中央政府の存在しない国際社会において,国家の枠を超える問題はどう解決されるのか.現代世界を理解し,運営していくキー・ワードとして注目される「グローバル・ガヴァナンス」概念の可能性と限界に包括的に接近しながら,政府なき秩序の可能性を模索する. 序章 グローバル・ガヴァナンスの射程(渡辺昭夫・土山實男) 第1部 現代国際関係理論とグローバル・ガヴァナンス 第1章 グローバル・ガヴァナンスの理論(オラン・R・ヤング) 第2章 グローバリゼーション論批判(スティーブン・D・クラズナー) 第3章 制度,覇権,グローバル・ガヴァナンス(G・ジョン・アイケンベリー) 第4章 アナーキー下のグローバル・ガヴァナンス(土山實男) 第2部 国際社会の制度化とグローバル・ガヴァナンス 第5章 国際法の視点(柘山堯司) 第6章 国際行政(城山英明) 第7章 国際機構(星野俊也) 第8章 国際機構におけるリーダーシップ(飯田敬輔) 第3部 争点領域とグローバル・ガヴァナンス 第9章 安全保障(山本吉宣) 第10章 国際経済(古城佳子) 第11章 国内政治からの分析(河野勝) 第12章 地球環境問題(太田宏)
理論・歴史・規範 グローバル・ガバナンス グローバル・ガバナンス論再考 国際秩序と権力 グローバル・ガバナンスと民主主義 グローバル・ガバナンスとしてのサミット 覇権システムとしての冷戦とグローバル・ガバナンスの変容 イギリス帝国からのコモンウェルスへの移行と戦後国際秩序 「開発」規範のグローバルな普及とリージョナル・アプローチ 戦争とグローバル・ガバナンス 貿易自由化ガバナンスにおける多角主義と地域主義 ウクライナ危機とブダペスト覚書 国連海洋法条約と日本外交 日本による人間の安全保障概念の普及
まるで劇を見ているような感覚で、世界史の一大局面が学べる人気シリーズ。ナチスドイツの動きを軸に、欧米各国の熾烈な争いを描く。 まるで劇を見ているような感覚で、世界史の一大局面が学べる人気シリーズ。ナチスドイツの動きを軸に、欧米各国の熾烈な争いを描く。 「まるで劇を観ているような感覚で、楽しみながら世界史の一大局面が学べる」まったく新しい教養書シリーズ! 本書では、ナチスが政権を奪取した直後から戦争終結まで、ナチスドイツの動きを軸に、第二次世界大戦のヨーロッパでの熾烈な争いを描きます。なぜ第二次世界大戦は避けられなかったのか? なぜドイツは敗れたのか? ヨーロッパ諸国の政治と軍事の動きを追いながらその真相に迫ります。“歴史が見える”イラストパネルと臨場感あふれる解説で、歴史を“体感”できる一冊となっています。 第1章 ヒトラー野心沸騰 第1幕 アメとムチ 第2幕 孤立への道 第3幕 狼の囁き 第4幕 禁断の一歩 第5幕 2つ目の穴 第6幕 雪辱を晴らす賭け 第7幕 東西からの危機 第8幕 独裁を決定づけた奇蹟 第9幕 第二次世界大戦の前哨戦 第2章 大戦前夜 第1幕 破滅の入口 第2幕 平和への生贄 第3幕 ヒトラーの確信 第4幕 故国滅亡の署名 第5幕 飽くなき野望 第6幕 国際均衡崩壊 第7章 “欧州情勢は複雑怪奇なり” 第3章 ドイツ快進撃 第1幕 第二次世界大戦の幕開け 第2幕 望まぬ戦い 第3幕 アルデンヌの森を抜けて 第4幕 我々の敗北は最終的か!? 第5幕 史上最大の空中戦 第4章 形勢逆転 第1幕 ローマ帝国の復興を我が手で! 第2幕 ムッソリーニの尻拭い 第3幕 積水なきバルバロッサ 第4幕 チャーチルの思惑 第5幕 -42℃の紅蓮地獄 第6幕 史上最大の市街戦 第5章 枢軸軍崩壊 第1幕 ロンメルの奮闘と失望 第2幕 唐突な“無条件降伏”発言 第3幕 署名なき宣言 第4幕 終局への約束 第5幕 パリは燃えているか? 第6幕 密談の末に 最終幕 “奇蹟”は起きず
この書籍は、現代史を理解するための基礎知識を提供するもので、民族紛争やテロ、領土問題などの背景にある歴史を解説しています。著者の池上彰が、豊富なビジュアルとわかりやすい説明で、冷戦後の主要な出来事を取り上げ、ニュースをより鮮明に理解できるようにしています。最新情報も加筆され、現代史入門の決定版として文庫化されています。
本書は、対中半導体輸出規制などの「経済の武器化」が進む中で、国際社会における「パワー」の本質を探求しています。目に見えない権力、例えば通信ネットワークの管理や通貨のコントロールが地政学的な力として重要であることを示し、米中対立の中でも米国が超大国としての地位を維持する理由を解明しています。さらに、米国の地経学的パワーを再評価し、その持続的な発揮のための国際秩序のあり方を提案しています。
主体・地域・新領域 国際連合 地域集団防衛から安全保障グローバル・ガバナンスへ BRICSと国際金融ガバナンス NGOと子ども人権ガバナンス イスラーム世界のグローバル・ガバナンス グローバル・ガバナンスにおけるEUと国連 ASEANと国連 国連とOSCEの東部欧州ガバナンス 人の移動をめぐるガバナンス グローバル・エイズ・ガバナンスとアフリカ サイバーセキュリティ テロリズムの原因と対策 地球を覆い尽くすガバナンス体系
戦争の時代に逆戻りした今こそ、現実主義の視点から二度の世界大戦と冷戦を振り返る必要がある。国際政治学者の幻の名講演を書籍化。 「戦争の世紀」が再来した今こそ、高坂史観が役に立つ――! 「〈いい人〉の政治家が戦争を起こすことがある」「ロシアに大国をやめろと強制することはできない」――戦争の時代に逆戻りした今、現実主義の視点から「二度の世界大戦」と「冷戦」を振り返る必要がある。世界恐慌、共産主義、大衆の台頭、文明の衝突……国際政治学者の「幻の名講演」を初の書籍化【解題・細谷雄一】。
日本の領土のうち「北方領土」と「竹島」は、それぞれロシア、韓国の実効支配をゆるしています。「尖閣諸島」は中国が実効支配を狙っています。 日本が「歴史的にも国際法上も日本固有の領土」といくら正論を述べたところで、彼らは日本の領土を明け渡すことはありません。 いま必要なことは、現実的な思考ではないでしょうか。日本の周辺国がどのような戦略をもっているのか? それに対して日本はどのような戦略をとるべきか? しっかりとした戦略をもってのぞまないと日本の領土は守れません。 このような現実的な思考をするためのツールの1つが「地政学」です。「地政学」とは、地図をもとにその国の政治や軍事を考えていく学問です。 ロシアのウクライナ侵攻や台湾有事の危機が報じられるなか、領土問題に対する関心が高まっています。本書が日本の領土について考える一助となれば幸いです。
本書は、相互依存関係における敏感性と脆弱性を多角的に検証し、国際政治に新たな視点を提供する相互依存論の名著を日本語に翻訳したものです。目次は、相互依存の理解、海洋と通貨の政治、米加・米豪関係、アメリカの相互依存への対処、グローバリズムと情報時代、理論と政策の再考に分かれています。著者は、ロバート・コヘインとジョセフ・ナイで、いずれも著名な国際関係の学者です。
大人気の歴史系YouTuber「いつかやる社長」が初の著書を出版。世界情勢を簡単に解説し、ウクライナや台湾、北朝鮮の問題を含む現代のニュースをわかりやすく説明。かわいい動物キャラを使って、地政学や国際情勢を学ぶことができる内容で、小中学生や新社会人に人気。地政学の基本や各国の考え方をイラスト付きで紹介し、学校では教わらない「世界のカラクリ」を理解できる入門書となっている。
「国際情勢」に関するよくある質問
Q. 「国際情勢」の本を選ぶポイントは?
A. 「国際情勢」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「国際情勢」本は?
A. 当サイトのランキングでは『(247)歴史で読み解く!世界情勢のきほん (ポプラ新書 247)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで174冊の中から厳選しています。
Q. 「国際情勢」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「国際情勢」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。








































![『[図解]池上彰の 世界の宗教が面白いほどわかる本 (中経の文庫 い 17-3)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Mx64mLtHL._SL500_.jpg)











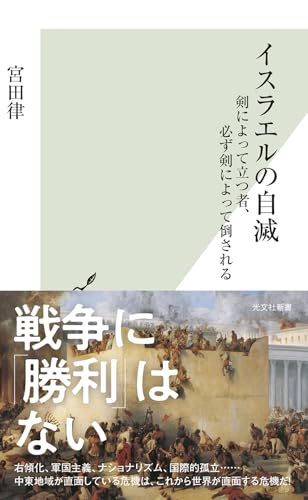



















































































































![『[図説]ユーラシア「帝国」の地政学 ロシア・中国の行動原理がわかる』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51HrohSWJ+L._SL500_.jpg)

















