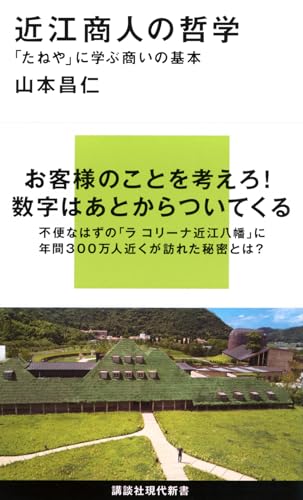【2025年】「ヨーロッパ史」のおすすめ 本 211選!人気ランキング
- 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
- 北の十字軍 「ヨーロッパ」の北方拡大 (講談社学術文庫 2033)
- 中世ヨーロッパ全史 上: 王と権力
- 詳説世界史研究
- 図説 中世ヨーロッパの商人 (ふくろうの本/世界の歴史)
- 今さら聞けない! 世界史のキホンが2時間で全部頭に入る
- 論点・西洋史学
- 中世ヨーロッパの歴史
- 366日の西洋美術 (366日の教養シリーズ)
- 独ソ戦 絶滅戦争の惨禍 (岩波新書)
この本は、現役教師が書いた新感覚の世界史教科書で、YouTubeでの授業動画が話題となり、50万部を突破しています。一般的な教科書とは異なり、年号を使わずに世界史を一つのストーリーとして解説し、読者が自然に知識を身につけられるよう工夫されています。高校生から社会人まで幅広い層に向けた内容で、歴史を数珠つなぎに学ぶ新しいアプローチを提案しています。著者は福岡県立高校の教諭で、YouTubeでの授業動画が多くの支持を得て「神授業」として評判です。
本書は、1998年度サントリー学芸賞を受賞した作品で、11世紀の十字軍や中世の「北の十字軍」に焦点を当て、特にドイツ騎士修道会の残虐行為を正当化する思想を探求しています。著者は、これらの活動がヨーロッパの形成と拡大において重要な役割を果たしたことを考察し、ゲルマンとスラブの対立から大航海時代に至るまでの歴史的背景を分析します。全体を通じて、ヨーロッパ史の未開拓な側面を切り開き、現代世界の理解を深めることを目指しています。
この書籍は、古代ローマ帝国の崩壊から宗教改革までの中世の歴史を新たな視点で描いています。内容は二部構成で、第一部ではローマ帝国や蛮族、ビザンツ帝国、アラブ帝国を扱い、第二部ではフランク人や修道士、騎士、十字軍戦士に焦点を当てています。著者は歴史家ダン・ジョーンズで、彼は多くのベストセラーを執筆し、テレビ番組の制作にも関わっています。翻訳はダコスタ吉村花子が担当しています。
『詳説世界史』に基づき、10年ぶりに全面改訂された世界通史のロングセラー。内容は先史時代から現代までを網羅し、オリエント、地中海、アジア、ヨーロッパの発展や帝国主義、世界大戦、冷戦などを詳述。著者は東京大学名誉教授の木村靖二、岸本美緒、お茶の水女子大学教授と小松久男。
本書は、西洋の歴史に関する様々な「論点」を集め、真実を求める主張がどのように対立しているかを探求するテキストです。各項目は「史実」「論点」「歴史学的に考察するポイント」の3パートから成り、豊富な語句説明やクロスリファレンスにより、世界史の知識がなくても理解しやすい内容となっています。著者は歴史学の専門家であり、古代から現代に至る西洋史の主要な論点を取り上げています。
本書は、ミケランジェロやダ・ヴィンチなどの名画を366作品紹介し、1日5分で美術の基礎知識を学べる内容です。1週間で7つのテーマ(美術史、主題、ジャンル、画家の逸話、技法、謎・フェイク、周辺)を通じて西洋美術の見方を深めることができます。著者は美術評論家の瀧澤秀保氏で、長年にわたり美術教育に携わってきました。
本書は、ヒトラーが「絶滅戦争」と呼んだ独ソ戦の実態を描写し、その惨禍を明らかにする。歴史修正主義の歪みを正し、戦争の本質を探求することで、21世紀の平和の礎を築くことを目指している。著者はドイツ現代史や国際政治史の専門家であり、独ソ戦の多様な側面を軍事史的に解説している。
時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。 時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。 オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。 時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。 オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。
この図説は、ただの資料集ではありません。ページをめくるたびに、時代が鮮やかに蘇る感覚を味わえます。「時代の流れと地域のつながり」をここまで直感的に理解できる資料集は他にないのではないでしょうか。特に、特集ページは圧巻で、例えば「シルクロードの交易路」や「冷戦下の国際関係」の図解は感動的なほど分かりやすい。細部まで描き込まれた地図や年表は、まるで壮大な歴史ドラマを観ているかのような没入感を与えてくれます。歴史を「学ぶ」だけでなく「体感する」資料集です!
この書籍は、人類の1000万年の歴史を網羅した内容で、先史時代から現代までの各時代を章ごとに解説しています。著者は歴史学者のジェレミー・ブラックで、彼はイギリスのエクセター大学の教授です。また、藤崎衛と下田明子も関与しており、藤崎は西洋中世史の専門家、下田は翻訳者として活動しています。
中世ヨーロッパ文明への視角 キリスト教化と西欧世界の形成 ローマ・カトリック教会の発展 中世後期の宗教生活 戦争の技術と社会 貴族身分と封建制 文書と法による統治 西欧的農業の誕生 都市という環境 ラテン・ヨーロッパの辺境と征服・入植運動 衣服とファッション 融合する食文化 都市と農村の住居 知の復興と書物の変容 見えないものへのまなざしと美術 ヨーロッパ音楽の黎明
ハプスブルク家の650年にわたる歴史を描いた本で、スイスの豪族から神聖ローマ帝国皇帝に上り詰めた家系の波乱に満ちた物語を紹介しています。著者は、愛や権力争いの中で運命に翻弄された皇帝や王妃たちを名画と共に描写し、彼らの魅力的な人生を探ります。著者はドイツ文学と西洋文化史を専門とする中野京子です。
ヨーロッパ史に「近世」は存在するか。主権国家と複合国家の相克という視点から、中世でも近代でもないその独自性に迫る画期的試み。 ヨーロッパ史において近世とはいかなる時代か。宗教、経済、帝国、戦争という四つの特質に注目し、主権国家と複合国家の相克という観点からその全貌を描き出す。 ヨーロッパ史において「近世」とはいかなる時代か。宗教改革からフランス革命にかけてのこの時期は、ときに「近代」の準備段階とみなされ、ときに「長い中世」の一部とされてきた。だが近年、複合国家論などが提唱されるなかで、中世とも近代とも異なる独自の時代として近世を位置づける動きが広がっている。では、その独自性とは何か。近世を多様な地域が複雑に絡み合う歴史的空間と捉え、人やモノのグローバルな移動に注目することで、これまで教科書などでは十分に語られてこなかったその複雑なうねりをダイナミックに描き出す。 【目次】 はしがき――「中世」でも「近代」でもない時代 序章 ヨーロッパ近世の二つの顔――主権国家と複合国家 ヤヌスの二つの顔/教科書の中のヨーロッパ近世史/現代ヨーロッパの光景から/「地域」から考える/「複合国家」とは何か/本書の論点と構成 第一部 ヨーロッパ近世の構成要素 第1章 宗教と複合国家 「宗教改革」とは何か/ルターと「プロテスタント」の誕生/ツヴィングリとブツァー/カルヴァンの宗教改革/宗教改革と主権国家/宗教改革と神聖ローマ帝国の分裂 第2章 経済と地域社会 地域の経済活動/ヨーロッパ近世の重商主義/地域から見た価格革命と物価騰貴/サースクの局地的経済論/一七、一八世紀イングランドの毛織物工業 第3章 帝国と複合国家 大航海時代/ポルトガルとスペインの植民地貿易/大航海時代と主権国家/帝国建設と複合国家/君主による帝国建設/会社組織による植民地建設 第4章 戦争と講和条約 近世の戦争と主権国家/近世初期のイタリア戦争/パーカーの軍事革命論/三〇年戦争/ウェストファリア条約/「ウェストファリアの神話」/主権国家論の問題点 第二部 ヨーロッパ大陸の複合君主政国家 第5章 神聖ローマ帝国と地域――複合国家としての帝国 近世初頭の複合国家/「怪物のような国家」/近世の神聖ローマ帝国/神聖ローマ帝国の「まとまり」と合意形成/ウェストファリア条約以降の帝国存続/オーストリアとプロイセン 第6章 スペインの国家と地域――カスティーリャとアラゴン カルロス一世とフェリペ二世/スペイン複合君主国/スペインの統合政策の問題点/フランスとの比較/スペインの財政的負担/アラゴン連合王国の抵抗理念/一七世紀スペインの衰退 第7章 フランスの国家と地域――パリと周辺地域 フランス近世の歩み/フランス絶対王政の確立/フランスの統合政策の問題点/フランス絶対王政の評価/二つの顔を持つフランス近世 第8章 オーストリアとプロイセン――神聖ローマ帝国内の主導権争い 神聖ローマ帝国の国制/神聖ローマ帝国をめぐる主導権争い/マリア・テレジア期の集権化と分権化/プロイセン近世史の評価/複合国家プロイセン/神聖ローマ帝国の中のプロイセン 第三部 オランダとイギリスの複合国家 第9章 オランダの国家と地域――ネーデルラントの南部と北部 ネーデルラント独立戦争/オランダの繁栄/一七世紀オランダは「中世」か「近代」か/複合国家オランダの「紐帯」/宗教と経済活動という「紐帯」 第10章 一六世紀イギリスの複合国家と地域――イングランドとウェールズ ブリテン諸島を結んだ「紐帯」/一六世紀イングランドの集権化と宗教改革/エリザベス女王の時代/ネーデルラントの亡命者と技術移転/スコットランドとアイルランドの動き/イングランドとウェールズの合同/ウェールズの社会と文化/ウェールズ政策とアイルランド政策 第11章 ピューリタン革命と複合国家の危機――スコットランドとアイルランド 一七世紀の危機/ジェイムズ一世とブリテン統合/チャールズ一世の国教会強制とピューリタン/ピューリタンの「避難所」オランダ/スコットランドとアイルランドの反発/スコットランド暴動から長期議会へ/スコットランド契約派の改革/アイルランド反乱の衝撃/内戦の勃発と議会軍の勝利/セクトと平等派 第12章 ピューリタン革命から名誉革命へ――イギリス複合国家の確立 国王なき時代へ/共和政の実験/アイルランドとスコットランドの征服/複合国家の形成/ヒュー・ピーターの提言/指名議会とプロテクター政権/「近世」的な革命が「近世」を変えた/王政復古から名誉革命へ/再度のアイルランド征服/イングランドとスコットランドの合同 第四部 複合国家の変質と存続 第13章 宗教的亡命者と複合国家の思想 近世における変化の兆し/宗教的迫害と移民/スペインの宗教迫害とユダヤ人/フランスの宗教迫害とユグノー/亡命者を受け入れたイングランド/イングランドのカトリック差別/「獲得によるコモンウェルス」を説くホッブズ/複合国家の思想家ハリントン 第14章 商業・貿易とイギリス産業革命 商業や貿易という「紐帯」/バーボンの『交易論』/イングランドの商業革命/フランスの経済発展/「イングランド帝国」から「ブリテン帝国」へ/産業革命と奴隷貿易/長期にわたる産業革命 第15章 英仏抗争とアメリカ独立戦争 「紐帯」を強化する戦争/戦時の「紐帯」としての国王/商人や一般人にとっての戦争/「財政軍事国家」の登場/フランスの財政破綻を招いた英仏戦争 第16章 啓蒙思想とフランス革命 啓蒙思想とフランス革命の関係/啓蒙思想の宗教的寛容論/啓蒙思想の奴隷制批判/東欧・ロシアでの啓蒙思想普及/アメリカとフランスを結ぶ大西洋革命/国民国家の形成と地方主義 終章 比較と展望のヨーロッパ近世史 本書のまとめ/近世の二つの政治組織モデル/日本近世との比較/現代への展望 あとがき――「歴史総合」から除外されたヨーロッパ近世史 参考文献
本書は、絵画をより深く理解し楽しむための指南書です。著者は、絵の「意味」と「形」の二本柱からアプローチし、特に造形面に焦点を当てています。読者は、名画の主役やバランス、色の使い方、構図などを学びながら、絵を観察する力を養うことができます。理系の人や理論を好む人にも適しており、絵をパズルのように読み解く楽しさを提供します。最終的に、名画が名画たる理由を理解し、個々の感想と客観的な分析を結びつけることを目指します。
この書籍は、農業革命と国家形成に関する新たな視点を提供し、定住と穀物栽培が人類や動植物に与えた影響を探求しています。著者は、古代国家が形成される過程で非エリート層がどのような負担を強いられたのか、また農業国家の強制手法やその脆弱性について考察しています。最新の考古学や人類学の成果を基に、従来の歴史観を覆す壮大な仮説が展開されています。著者はイェール大学の教授であり、農民の抵抗に関する研究を行っています。
本書は、16世紀以降の戦闘を「補給」の観点から分析し、補給が戦いの勝敗を決定する要因であることを明確に論じた名著の第二版。ナポレオン戦争や二度の世界大戦における補給計画や実施、戦闘への影響を具体的な数値と計算に基づいて解説している。著者はマーチン・ファン・クレフェルトで、石津朋之による翻訳と新たな解説が付されている。
本書は、ギリシアの思想とヘブライの信仰がヨーロッパ哲学の基盤であることを探求する。第1部ではギリシアの思想、特にホメロスや哲学の発展を扱い、第2部では旧約・新約聖書を通じてヘブライの信仰を考察。第3部では中世から近現代の哲学の流れを分析し、これらの源泉がどのように現代思想に影響を与えているかを明らかにする。著者は岩田靖夫で、古代ギリシア哲学を専門とする教授である。
この書籍は、美術史を洞窟壁画から現代美術までの視点で物語のように描き出しており、絶えず変化しながらも繋がっている美術の流れを紹介しています。目次には、先史時代や古代文明、ギリシャ・ローマ時代、ビザンティン、イスラム、中国など多様な文化の美術が含まれています。著者エルンスト・H・ゴンブリッチは20世紀の著名な美術史家であり、彼の作品は明瞭で説得力があり、美術への深い愛情が表れています。
この書籍は、フランスの歴史をわかりやすく解説しており、ガリア時代からフランス革命、ナポレオン戦争、ベル・エポック、パリ解放までの変革を取り上げています。また、コラム「そのころ、日本では?」を通じてグローバルな視点も提供します。著者は福井憲彦で、フランスを中心とした西洋近現代史の専門家です。
騎士団、武器と甲冑、騎士道――中世ヨーロッパの花である騎士の、実はとらえにくいその実像を、多数図版とともに第一人者が解説。 騎士団、武器と甲冑、騎士道、馬――中世ヨーロッパの花、騎士が導く豊潤な世界。実はとらえにくいその実像を、多数図版とともに多様な視点から第一人者が解説する、必携の一冊!
小説で読む、世紀の独裁者アドルフ・ヒトラーの生涯。全3巻、刊行開始!! Ⅰでは、ヒトラーの幼少期、ミュンヘン一揆までを描く。 小説で読む、世紀の独裁者アドルフ・ヒトラーの生涯。全3巻、刊行開始!! 「邪悪な独裁者」といわれた男の生涯を描いた初めての歴史小説! 「人間」ヒトラーの実像とは? 知られざる総統の初恋⁉ ユダヤ人はなぜ大虐殺されたのか? 世界大戦はなぜ起きたのか? ヒトラーの「愛」と「憎しみ」と「野望」を描く! Ⅰ(第一回配本)では、ヒトラーの幼少期から不遇の青年期を経て、ナチ党に入党し、演説で頭角を現して人々の注目を集め、そしてミュンヘン一揆の失敗で自殺を図ろうとするまでを描く。 ※第二回配本「Ⅱ―ヨーロッパの覇者への道」、第三回配本「Ⅲ―破滅への道』5 月・6 月刊行予定 第1章 愛憎――アロイスとクララ 第2章 恋――シュテファニー 第3章 帝都――ウィーン 第4章 鉄十字章――ソンム 第5章 国民社会主義ドイツ労働者党――ナチス 第6章 ミュンヘン一揆――クーデター
本書は、東京藝大美術館の館長が厳選した23作品を通じて、西洋絵画の「革命」を解説し、絵画鑑賞の常識を変える内容です。ルネサンスからポップ・アートまでの西洋美術の歴史を探りながら、知的教養を深める方法や美術館の楽しみ方を紹介しています。著者は、東京生まれの美術館長で、アートライターとしても活動してきた秋元雄史氏です。
本書は、宮崎市定による唐と宋の間の時代変革を論じた通史で、平易な文章と明確な論旨が特徴です。上巻では歴史の定義や時代区分を紹介し、古代から近世までの歴史的特徴を概観し、夏殷周から唐五代に至る内容を扱っています。全2冊から成ります。
イギリスの伝説的英雄アーサー王と円卓の騎士団の物語は、15世紀の無頼の騎士によってまとめられ、同時期にイギリスの初の印刷業者によって印刷・刊行された。特に評価の高いW.キャクストン版による「アーサー王の死」が紹介されている。
本書は、著者である海軍の参謀がシーレーン確保の戦略を綴った貴重な体験記であり、現代日本の防衛においても重要な記録です。日本は資源を海外に依存しているため、海上交通線の問題は非常に重要です。著者は戦争中にさまざまな戦略や困難な状況を経験し、その詳細を各章にわたって述べています。著者、大井篤は海軍大佐として終戦まで海上護衛総司令部で活動し、戦後は戦史研究家や評論家としても知られています。
「A Short Guide to Writing About Art」(第7版)の日本語版は、美術に関する文章を書くための必携書で、学生や美術ブロガーなど幅広い読者に向けて、美術を言葉で表現するテクニックを解説しています。内容は、作品の見方や具体的な文章技術に至るまで多岐にわたり、レポートや論文、展覧会レビューなどの執筆方法を詳しく説明しています。著者は美術史に詳しいバーネットと竹内順一で、各章には美術を書くための具体的な指針が示されています。
この書籍は、人類の始まりから現代までの歴史を85項目に分け、図解でわかりやすく解説しています。主要なテーマは「始まり」、「拡大」、「侵略」、「混迷」で、各章では重要な出来事や人物が紹介されており、パラパラとめくるだけで時代の雰囲気を理解できます。受験やビジネスの教養にも役立つ内容です。著者は歴史や古典文学に詳しい福田智弘、イラストは塩浦信太郎が手がけています。
この書籍は、中世から第二次世界大戦までのヨーロッパの戦争を、戦術だけでなく社会、経済、技術の発展との関連性を考慮しながら概観したもので、2009年に改訂された日本初訳です。目次には、封建騎士、傭兵、商人、専門家、革命、民族、技術者の戦争に関する章が含まれています。著者は、戦争史の権威であるマイケル・ハワードをはじめ、戦後の日本で歴史を学んだ奥村房夫と奥村大作です。
本書『室内画の世界』は、美しい部屋の情景を描いた366点の「室内画」を紹介し、フェルメールやマティスなどの巨匠から知られざる名作まで幅広く取り上げています。著者の海野弘氏が各作品のテーマや画家について楽しく解説し、絵画の見方や知識を深める内容です。1日1作を楽しむ形式で、画家たちの自邸に招かれたような体験が提供されます。
1789年。フランス王国は破産の危機に瀕していた。大凶作による飢えと物価高騰で、苦しむ民衆の怒りは爆発寸前。財政立て直しのため、国王ルイ16世は170余年ぶりに全国三部会を召集する。貴族でありながら民衆から絶大な支持を得たミラボーは、平民代表として議会に乗り込むが、想像もしない難題が待ち受けていた-。男たちの理想が、野望が、歴史を変える!一大巨編、ここに開幕。
本書は、地政学の観点から戦争や紛争の原因を探求し、地理的要因が国家に与える影響を考察しています。中国やロシアの動向、アメリカの地理的優位性の変化などを通じて、国際情勢の複雑さを明らかにします。20枚の地図を用いて、地球上の危機と平和を分析し、地形、歴史、宗教、人種、文化がどのように絡み合っているかを示しています。著者は国際情勢の取材経験が豊富なジャーナリスト、ティム・マーシャルです。
この本は、スウェーデン発の子ども向けに書かれた人類史の入門書で、楽しいイラストを交えながら「ホモ・サピエンス」がどのように世界を形成してきたかを探ります。人類の進化や農業の始まり、文化の交流、科学の発展、経済の仕組みについて解説し、SDGsの重要性も理解できる内容です。小学校高学年以上向けで、漢字にはルビがついており、朝読にも適しています。著者は子ども向けの科学書を多く手掛ける作家とイラストレーターです。
小説や漫画など物語創作に役立つ中世ヨーロッパの知識をイラストと図解で解説。世界観を作る上で欠かせない知識やコツを多数掲載。 小説や漫画など物語創作に役立つ、中世ヨーロッパの知識をイラストと図解でわかりやすく解説した書籍です。中世の世界観を作る上で欠かせない知識やコツを多数掲載。クリエイターの知りたい情報をまとめた一冊です。 <物語創作に大活躍!これ一冊で中世ヨーロッパの世界観がわかる!>近年、Web小説や漫画アプリなどで注目されている多くは、歴史系ファンタジー作品です。その中でも優美で洗練された印象のある中世ヨーロッパの世界観をイメージした作品は、特に人気を集めています。人気とともに、このジャンルに挑戦する書き手も増えていますが、中世時代の制度や人々の暮らしについてある程度知識を持っていないと、ストーリーを考えるのが難しいジャンルです。本書は創作系クリエイターの方が、そのようなファンタジーや歴史作品を書くときに役立つ中世ヨーロッパの制度や人々の暮らし、貴族の爵位などをイラストと図解でわかりやすく解説します。また、物語創作におけるコツについても掲載しており、クリエイターにとって使いやすい工夫を豊富に盛り込んだ一冊です。ご自身の作品をつくる際に、活用していただけたら、嬉しく思います。 はじめに 物語創作で役立つ「中世ヨーロッパ」の基礎知識 中世の世界観をつくるなら押さえておきたい「封建制度」 統治形態&権力構造を知れば物語のクオリティが格段に上がる [本書の見方]3つの要点で中世ヨーロッパの仕組みがわかる! PART.1 権力者たちの暮らしとしくみ Column.1 身分違いの恋の行方 騎士と王家の結婚は許されたのか PART.2 一般市民の暮らしとしくみ Column.2 世にも恐ろしい「人狼」は実在した!? PART.3 中世ヨーロッパ社会のルールと概念 Column.3 裁判には動物も出廷させられた PART.4 中世ヨーロッパの施設と住まい Column.4 封建社会から主権国家へ PART.5 中世ヨーロッパを舞台に物語を創作してみよう! 知っておくと便利!中世ヨーロッパ年表
内戦で萌芽し、独ソ戦を勝利に導き、冷戦時、アメリカと伍した、最強のソフト。現代用兵思想の要、「作戦術」とは何か? ソ連の軍事思想研究、独ソ戦研究の第一人者が解説する名著、待望の初訳。 作戦術(Operational Art)とは? ソ連は、第二次世界大戦前に、画期的な用兵概念である「作戦術(Operational Art)」を世界で初めて明確に定義し言語化することに成功。この作戦術は、独ソ戦においてソ連軍の勝利に貢献した。そしてアメリカ陸軍も、ベトナム戦争での敗北を機に、この「作戦術」の概念を自軍の軍事ドクトリンに導入。湾岸戦争で勝利を収める大きな原動力となった。 現在、世界の主要国の軍隊では、この「作戦術」という用兵概念はすでに常識となっている。 前書き(米陸軍参謀総長 カール・E・ヴオノ) 序文(サンドハースト王立陸軍士官学校 クリストファー・ドネリー) 著者による序文 第一章 ソ連の戦争研究 歴史と戦争/軍事ドクトリン/ミリタリー・サイエンス/ミリタリー・アート/軍事戦略/作戦術/戦術 第二章 作戦術の特質 作戦術の起源 作戦術の発展 縦深作戦の出現 戦争によるテスト 軍事における革命と作戦 作戦レベルの再現出と縦深作戦の再生 第三章 作戦の枠組み 任務(使命) 領域 行動 部隊 作戦戦略級大規模部隊-正面軍/作戦級大規模部隊-軍/作戦戦術級大規模部隊-軍団/作戦級中規模部隊/作戦戦術級中規模部隊/戦術級中規模部隊 結論 第四章 ソ連作戦術の形成期〔一九一七~一九四一年〕 導入 内戦とレーニン主義に基づく軍事ドクトリン〔一九一七~一九二一年〕 情況/ドクトリン/戦略/作戦/戦術 社会主義者の軍事ドクトリンの進化〔一九二一~一九二九年〕 情況/ドクトリン/戦力組成/戦略/作戦術/戦術 軍隊の技術的再建と縦深作戦の理論〔一九二九~一九三七年〕 情況/ドクトリン/戦略/作戦術/戦術/戦力組成 ソ連軍幹部の危機〔一九三七~一九四一年〕 情況/戦略/作戦術/戦術/戦争前夜 第五章 大祖国戦争と作戦術の成熟〔一九四一~一九四五年〕 陸軍の悲劇と再生〔一九四一~一九四二年〕 情況/戦力組成/ドクトリン/戦略/作戦術/戦術/結論 転換期の陸軍〔一九四三年〕 情況/戦力組成/戦略/作戦術/戦術/結論 戦勝〔一九四四~一九四五年〕 情況/戦力組成/ドクトリン/戦略/作戦術/戦術/結論 第六章 作戦術と軍事における革命 最後のスターリン時代〔一九四三~一九五三年〕 情況/ドクトリン/戦力組成/戦略/作戦術/戦術/結論 核の時代と軍における革命〔一九五三~一九六八年〕 情況/ドクトリン/戦力組成/戦略〔一九五三~一九六〇年〕/作戦術と戦術〔一九五三~一九六〇年〕/戦略〔一九六〇~一九六八年〕/作戦術〔一九六〇~一九六八年〕/戦術〔一九六〇~一九六八年〕/結論 第七章 軍事における革命の改善 背景 戦力組成 軍事ドクトリン 軍事戦略 作戦術-正面軍と軍による作戦 戦術-軍と師団の作戦 結論 第八章 将来に関する見通し 背景 軍事戦略 作戦術・戦術 戦力組成 結論 本書紹介 長く読まれるべき現代用兵思想の古典 田村尚也(軍事ライター) 解説 「作戦術」の系譜学――半世紀にわたる、軍事研究の成果 三浦一郎 訳者後書き 戦力組成表の出典に関する註 写真の出典に関する註 索引
この文章は、イギリスの歴史を時代ごとにまとめた目次と著者情報を提供しています。目次では、ブリタニアの創成からブレグジットへの道までの主要な歴史的出来事が列挙されています。著者は君塚直隆で、イギリス政治外交史を専門とし、いくつかの著書を持つ教授です。
この書籍は、戦争と平和の関係を「世界史」を通じて探求し、人類が戦争を回避しようとした歴史を振り返る内容です。ロシアのウクライナ侵攻を受けて加筆・更新された最新版で、米中露や日本を含む多極化する世界の覇権争いも解説。著者は、戦争の起源や国際法の限界、21世紀の東アジアの未来についてわかりやすく学べるように構成しており、戦争観を見直すきっかけを提供します。著者は歴史を教える講師であり、読者にとって必読の一冊です。
本書は、美術鑑賞の入門書であり、ギリシャ美術から現代美術までの歴史を簡潔にまとめています。専門用語や美術の概念をQ&A形式でわかりやすく解説し、学芸員の対話や猫の素朴な質問を通じて読者の理解を深めます。美術館での作品鑑賞をより楽しむための知識を提供し、特に海外旅行前に読むことで美術館体験が豊かになることを目的としています。
ポルトガル史を体系的に学習する小学校5、6年生用の教科書の翻訳。ローマの征服やイスラームの半島支配に対する抵抗にスペインからの「再独立」など国家形成や独立の維持、さらに海外進出の歴史に1974年の「革命」まで、国家形成や独立の維持を柱に豊富な図版・資料で描き出した通史。現代史を重視し、困難の上に成り立つ現在の民主体制を維持する大切さを生徒に理解させる内容となっている。
パートナーたちは画家の生涯と作品にどのような影響を及ぼしたか。そこには様々な葛藤やドラマがあった。印象派を中心とした15人。 画家たちのパートナーに焦点を当てながら、彼らが画家の生涯と作品にどのようにかかわり、影響を及ぼしたかを探ってゆく。そこには実にさまざまな葛藤やドラマがある。印象派を中心とするフランスの著名画家ら15人を取り上げる。 はじめに 1 ヴィジェ=ルブラン──王妃マリー・アントワネットに愛された美貌の女流画家 2 カウフマン──名声と失意の女流〝歴史画家〟 3 グルーズ──悪妻に悩まされ続けた風俗画家 4 ダヴィド──激動の時代に君臨した巨匠 5 アングル──保守・伝統主義を貫いた〝良き夫〟 6 マ ネ──フランス近代絵画の先駆けとなったパリジャン 7 モ ネ──生活の苦しさ、創作の苦しさを支えたふたりの妻 8 ルノワール──多くの女性を愛し描いた「バラ色の人生」の画家 9 モリゾ──男社会での制約に悩みながらも、〝最も純粋な印象派〟を貫いた紅一点 10 ピサロとシスレー ピサロ──長年貧困に苦しんだ、印象派の「農民画家」 シスレー──終始不遇な人生だった〝晴の日〟の画家 11 モローとシャヴァンヌ モロー──ひとり〝象牙の塔〟に生きた世紀末の隠者 シャヴァンヌ──名家出身の貴婦人との遅すぎる結婚 12 セザンヌ──絵画において人もリンゴも同価値と見做した〝不器用な天才〟 13 ゴーガン──都会を捨て、未開の〝楽園〟に創造の源泉をもとめて おわりに 主要参照文献
「赤毛のエイリークのサガ」と「グリンランド人のサガ」についての情報が記載されている。著者は山元正憲で、1947年に宮崎県生まれの前大学教授。ブリティッシュ・コロンビア・アイスランド・クラブの会員であり、以前は日本中世英語英文学会にも所属していた。
古代・中世 「古代帝国」の時代 縄文文化 弥生時代の交流結節点・原の辻遺跡 時空を超える『楚辞』 乾燥世界における人びとの暮らしとシルクロード ローマ帝国 巨大古墳と東アジア 巨大前方後円墳の築造 ローマの崩壊とゲルマン人の移動 中部ユーラシアを動く イスラーム国家の出現とアフロ・ユーラシアへの拡大 国際都市平城京 上総の「望陀布」 訳経僧霊仙 世界につながる唐帝国 イスラームの拡大とキリスト教世界 ヴァイキングの時代 古代の秋田城 円仁の旅 アッバース朝イスラーム帝国の統治体制 武士と騎士の誕生 平氏政権と唐物 日宋貿易と森林資源 硫黄島 十字軍と「キリストの騎士」 映画『キングダム・オブ・ヘブン』 モンゴルの世界帝国 鷹島海底遺跡 モンゴル帝国と日本 「透頂香」を生んだヒト・モノの連関 マルコ・ポーロとラシード・アッディーン 世界の一体化への助走 日明貿易と硫黄 津軽安藤氏の交易世界 13~15世紀のアイヌの北方交易 万国津梁の琉球王国 中世日本のジェンダー関係 イブン・バットゥータと鄭和 オスマン帝国のユダヤ教徒
近代と向き合い、格闘し、支えた思想家たちの思考のエッセンスを平易に解説、自由と公共をめぐる思想的遺産を縦横に論じて、現代社会をよりよく考える基盤を指し示す。政治・経済・哲学の枠を超え、近代社会の通奏低音をなす思想の姿を浮かび上がらせた、刺激に満ちた最良の道案内。 序 章 社会思想とは何か 1 社会思想の歴史とは何か 2 社会思想史の方法 3 「時代」 と 「思想」 の文脈 4 社会思想の基本問題 —— 「自由」 と 「公共」 の相関 第1章 マキアヴェリの社会思想 1 「時代」 の文脈 —— 市場経済の復活と近代国家の胎動 2 「思想」 の文脈 —— イタリア・ルネサンスの人文主義 3 マキアヴェリの 「問題」 4 『君主論』 の人間観 5 『ディスコルシ』 の共和制論 6 マキアヴェリにおける 「自由」 と 「公共」 第2章 宗教改革の社会思想 1 「時代」 の文脈 —— 近代国家の出現と市場経済の発展 2 「思想」 の文脈 —— ルネサンスから宗教改革へ 3 宗教改革思想の 「問題」 4 ルターの信仰義認論と万人司祭主義 5 カルヴァンの予定説と資本主義の精神 6 宗教改革思想における 「自由」 と 「公共」 第3章 古典的 「社会契約」 思想の展開 1 「時代」 の文脈 —— 国際商業戦争の幕開け 2 「思想」 の文脈 —— 科学革命から自然法学へ 3 社会契約思想の 「問題」 4 ホッブズの機械論的人間観と絶対主権の理論 5 ロックの理性的人間観と政治社会論 6 社会契約思想における 「自由」 と 「公共」 第4章 啓蒙思想と文明社会論の展開 1 「時代」 の文脈 —— 文明社会の発展 2 「思想」 の文脈 —— フランスとスコットランド 3 啓蒙思想の 「問題」 4 フランス啓蒙の文明社会像 —— ヴォルテールから重農主義まで 5 スコットランド啓蒙の文明社会像 —— ハチソンとヒューム 6 啓蒙思想における 「自由」 と 「公共」 第5章 ルソーの文明批判と人民主権論 1 「時代」 の文脈 —— 文明社会の危機 2 「思想」 の文脈 —— 啓蒙から文明批判へ 3 ルソーの 「問題」 4 『社会契約論』 における一般意志と人民主権 5 ルソーにおける 「自由」 と 「公共」 第6章 スミスにおける経済学の成立 1 「時代」 の文脈 —— 文明社会の危機を超えて 2 「思想」 の文脈 —— 啓蒙から社会科学へ 3 スミスの 「問題」 4 『道徳感情論』 における共感と道徳秩序 5 『国富論』 における分業・市場・富裕 6 スミスにおける 「自由」 と 「公共」 第7章 「哲学的急進主義」 の社会思想 —— 保守から改革へ 1 「時代」 の文脈 —— 二重革命のはじまり 2 「思想」 の文脈 —— バークとマルサス 3 哲学的急進主義の 「問題」 4 功利主義の思想 —— ベンサムとジェームズ・ミル 5 古典派経済学の思想 —— リカードウの 『経済学原理』 6 哲学的急進主義における 「自由」 と 「公共」 第8章 近代自由主義の批判と継承 —— 後進国における 「自由」 1 「時代」 の文脈 —— 二重革命の光と影 2 「思想」 の文脈 —— カント、フィヒテ、ロマン主義における自我の発見 3 ヘーゲルの 「問題」 4 ヘーゲルの学問論と市民社会論 5 ヘーゲルにおける 「自由」 と 「公共」 第9章 マルクスの資本主義批判 1 「時代」 の文脈 —— 資本主義の危機 2 「思想」 の文脈 —— マルクス以前の社会主義 3 マルクスの 「問題」 4 哲学批判 —— 『経済学・哲学草稿』 から 『ドイツ・イデオロギー』 へ 5 『資本論』 の資本主義批判 6 マルクスにおける 「自由」 と 「公共」 第10章 J・S・ミルにおける文明社会論の再建 1 「時代」 の文脈 —— 資本主義の変化と民主主義の進展 2 「思想」 の文脈 —— 哲学的急進主義の再検討 3 ミルの 「問題」 4 哲学と道徳の革新 5 社会主義の可能性 6 ミルにおける 「自由」 と 「公共」 第11章 西欧文明の危機とヴェーバー 1 「時代」 の文脈 —— 帝国主義と大衆社会 2 「思想」 の文脈 —— 実証主義の諸潮流 3 ヴェーバーの 「問題」 4 『職業としての学問』 と近代合理主義の起源 5 『職業としての政治』 と民主主義の運命 6 ヴェーバーにおける 「自由」 と 「公共」 第12章 「全体主義」 批判の社会思想 —— フランクフルト学派とケインズ、ハイエク 1 「時代」 の文脈 —— 世界大戦、ロシア革命、大恐慌 2 「思想」 の文脈 —— 全体主義批判の諸相 3 全体主義批判の 「問題」 4 『啓蒙の弁証法』 の資本主義文明批判 5 ケインズとハイエクにおける2つの自由主義 6 全体主義批判における 「自由」 と 「公共」 第13章 現代 「リベラリズム」 の諸潮流 1 「時代」 の文脈 —— 社会主義体制の成立と崩壊 2 「思想」 の文脈 —— 「歴史の終わり」 か 「文明の衝突」 か 3 現代リベラリズムの 「問題」 4 ハーバーマスとロールズ 5 ロールズにおける公正としての正義 6 現代リベラリズムにおける 「自由」 と 「公共」 終 章 社会思想の歴史から何を学ぶか 1 方法からの問い 2 現代における 「自由」 と 「公共」 の可能性
本書は、「天使と悪魔」「天国と地獄」をテーマにした絵画を集め、魅惑的なビジュアルと共にその背景にある伝説や文学を紹介しています。内容は「最後の審判」の特集を含む三章構成で、天国と地獄、天使と悪魔の系譜を探求。美術作品を通じてキリスト教の神秘的な世界を楽しむことができる一冊です。元は2015年に刊行された書籍の再編集版です。
この本は、ドイツの歴史をわかりやすく解説し、敗戦を乗り越えたそのたくましさを探る内容です。目次には、フランク王国の始まりから近代ドイツ帝国、ワイマール共和国、ナチスドイツ、そして連邦共和国と民主共和国に至るまでの歴史が含まれています。著者は関眞興で、歴史に関する著書が多数あります。
この書籍は、軍事や戦争に関する基本的な概念とその背後にある思想を考察する内容で、古典的な軍事概念から現代の用語、戦略、指揮、そして日本や他国の軍事について詳述しています。著者は戦史・用兵思想史の研究家、片岡徹也氏です。
この書籍は、4000年にわたる西洋美術の歴史を時代や特徴ごとに紹介しています。各時代(エジプト、ギリシャ、ローマ、ルネサンス、バロック、印象派など)について、見開き2ページでテーマを解説し、代表的な作品を幅広く紹介。美術館巡りの前に全体像を把握するのに役立つ内容です。著者は美術史の専門家とライターたちです。
ナチスによる支配体制下で、人間と食をめぐる関係には何が生じたのか? 家事労働、レシピ、エネルギーなどから、「台所」空間の歴史と文化をつぶさに検証した「第1回河合隼雄学芸賞」受賞作の増補決定版。 国民社会主義(ナチス)による支配体制下で、人間と食をめぐる関係には何が生じたのか? この強烈なモティーフのもと、竃(かまど)からシステムキッチンへ、近代化の過程で変容する、家事労働、レシピ、エネルギーなどから、「台所」という空間のファシズムをつぶさに検証し、従来のナチス研究に新たな一歩を刻んだ画期的な成果。第1回(2013年度)河合隼雄学芸賞を受賞した、著者の代表作。 序章 台所の環境思想史 1、歴史の基層としての台所 2、テイラー・システムとナチズム 3、台所の変革者たち 4、 台所をどうとらえるか──定義とアングル 第1章 台所空間の「工場」化──建築課題としての台所 1、ドイツ台所小史──「煙と煤」から「ガスと電気」へ 2、ドイツ台所外史──「キッチンの集団化」という傍流 3、第一次世界大戦の衝撃──集団給食の登場 4、フランクフルト・キッチン──「赤いウィーン」から来た女性建築家 5、考えるキッチン──エルナ・マイヤーの挑戦 6、ナチス・キッチン? 7、労働者、約一名の「工場」 第2章 調理道具のテクノロジー化──市場としての台所 1、電化される家族愛──快適、清潔、衛生的 2、台所道具の進歩の背景 3、ニュアル化する台所仕事──人間から道具へ 4、市場化する家事──消費者センター「ハイバウディ」の歴史 5、報酬なきテイラー主義の果てに 第3章 家政学の挑戦 1、家政学とは何か 2、家政学の根本問題──『家政年報』創刊号 3、家政学の可能性と限界──『家政年報』1928—1932 4、家政学のナチ化──『家政年報』1933—1935 5、家政学の戦時体制化──『家政年報』1939—1944 6、家政学が台所に与えた影響 第4章 レシピの思想史 1、ドイツ・レシピ小史 2、読み継がれる料理本──食の嗜好の変化のなかで 3、企業のレシピ──ナチズムへの道 4、栄養素に還元される料理 第5章 台所のナチ化──テイラー主義の果てに 1、台所からみたナチズム 2、「第二の性」の戦場 3、「主婦のヒエラルキー」の形成──母親学校、更生施設、そして占領地へ 4、無駄なくせ闘争 5、残飯で豚を育てる──食糧生産援助事業 6、食の公共化の帰結 終章 来たるべき台所のために 1、労働空間、生態空間、信仰の場 2、台所の改革者たちとナチズム 3、ナチスのキッチンを超えて 註 参考文献 「食べること」の救出に向けて──あとがきにかえて 針のむしろの記──新版のあとがきにかえて --------- 付録1 ベストセラーの料理本 付録2 ダヴィディス著『日常的かつ洗練された料理のための実用的料理本』の版別レシピ構成 付録3 ハーン著『市民の台所のための実用的料理本』の版別レシピ構成 人名索引 477
本書は、広義の「東洋史」をテーマに、アフロ・ユーラシア地域の歴史的論点を158項目にわたり解説したものです。各項目は背景、論点、探究のポイントに分かれており、語句説明やクロスリファレンスも豊富で、歴史研究の魅力を伝える内容となっています。著者は東京大学の吉澤誠一郎教授で、学生や研究者にとって必携の一冊です。
本書は東京藝術大学の講義に基づく西洋美術の入門書で、著者が選んだ個々の作品を通じてそのメッセージをわかりやすく解説します。ビジュアルを多用し、読者が楽しみながら鑑賞眼を鍛えることを目的としています。全15回の講義形式で構成され、作品同士の関連性を示しながら、美術鑑賞の実践的なアプローチを提案。著者は東京藝大の准教授で、美術史の専門家です。
本書は、古代から20世紀までの代表的な戦略思想家50人の生涯や業績を詳述した事典です。内容は、戦略研究の歴史、近代の思想家たち、日本の戦略思想に関する章で構成されています。著者は陸軍航空士官学校卒の前原透と、社会学専攻の片岡徹也です。
パンデミック到来!街には死体があふれ出した!ウイルスと人間との攻防を描いた17世紀ペストの記録小説を現代新訳で。 パンデミック到来!街には死体があふれ出した!ウイルスと人間との攻防を描いた17世紀ペストの記録小説を現代新訳で。 パンデミック到来! 自粛するしか手立てはないのか! ウイルスと人間との攻防を描いた17世紀の記録小説が現代新訳に。 “自粛する”しか手立てはないのか! 17世紀、ロンドンで10万人の死者を出したペスト。都市は閉鎖され、政府は自粛を要請、それでも感染はとまらない。病院は死体であふれだす。ウイルスという見えない敵に恐怖する人々。公文書や膨大な記録を基に再現されたあまりにも現代的な記録小説が、平易でわかりやすい現代語訳で登場! 18世紀に書かれた現代の予言書!
『イラストでサクッと理解! 流れが見えてくる日本史図鑑』の第2弾で、豊富なイラストを通じて世界史の流れを理解できる内容です。横長のワイド判で時間軸が見やすく、大人の復習や中高生の学習に適しています。各章は中国・東アジア、ヨーロッパ、中東・イスラーム、その他の地域、テーマ別に分かれています。
秦王政が中国を統一するまでには550年にわたる長い道のりがあった。中国史の原点となるこの春秋戦国時代を臨場感ある解説で描く。 秦王政が中国を統一するまでには550年にわたる長い道のりがあった。中国史の原点となるこの春秋戦国時代を臨場感ある解説で描く。 紀元前221年、秦王政は斉を滅ぼし、史上はじめて中国を統一しました。それまで中国は、各諸侯が分立抗争する状態にあり、中国全土を一人の王のもとで支配されることはなかったのです。そのような中国はいかにして統一に向かっていったのでしょうか。 本書ではその過程にあたる春秋戦国時代を、臨場感あふれる解説で詳しく描いていきます。この時代には、歴史の展開や思想など、その後の中国史の原型となる要素が詰まっており、中国の歴史を理解するためには避けて通れません。中国史をこれから学ぶ方にもおすすめです。まるで劇を見ているような感覚で歴史を体感できる一冊! 第1章 春秋時代(前期) 第1幕 笑わない王妃?/ 第2幕 最初の覇者/ 第3幕 一枚肋の屈辱/ 第4幕 三舎避かせて猪を捌く/ 第5幕 仮痴不癲の王 第2章 春秋戦国(後期) 第1幕 孔子と老子/ 第2幕 血塗られた玉座/ 第3幕 名君にして暗君/ 第4幕 主客逆転 第3章 戦国の幕開け 第1幕 「鉄」の衝撃/ 第2幕 銭の力/ 第3幕 戦国時代の幕開け/ 第4幕 法家vs抵抗勢力 第4章 秦の抬頭 第1幕 法を為すの弊、一ここに至るか/ 第2幕 魁より始めよ/ 第3幕 鶏鳴狗盗/ 第4幕 離間の計に落つ/ 第5幕 刎頸の交わり/ 第6幕 “便所の屈辱”を晴らさん!/ 第7幕 破滅の足音/ 第8幕 青二才の大失態/ 第9幕 一振りの剣 第5章 天下布武 第1幕 奇貨居くべし/ 第2幕 完全なる粛清/ 第3幕 “才ある者”の死/ 第4幕 牛は牛連れ、馬は馬連れ/ 第5幕 届かぬ匕首/ 第6幕 逸を以て労を持ち、飽を以て饑を持つ/ 最終幕 天下統一
この書籍は、歴史学の重要性や社会的役割について探求する内容です。著者は、歴史がどのように個人や社会に役立つのかを問い、歴史教科書の限界や相対主義・構造主義の批判に対して、歴史学が提供する「知の技法」の価値を示します。具体的には、歴史小説と歴史書の違いや従軍慰安婦論争を例に挙げ、歴史学の実用性や教育の意義を考察します。著者は社会経済史を専門とする東北大学の助教授です。
「新世界」に投影された諸観念が合衆国を作り、社会に根づき、そして数多の運動を生んでゆく――。アメリカ思想の五〇〇年間を通観する新しい歴史。 「新世界」に投影された諸観念が合衆国を作り、社会に根づき、そして数多の運動を生んでゆく――。アメリカ思想の五〇〇年間を通観する新しい歴史。 === 発端において、アメリカは、ヨーロッパの探検者たちが「新世界」に投影した一群の諸観念であった。それらはいかにして合衆国を築き、どのような運動を生み出していったか――。本書は、アメリカ人たちが紡いできた思想的生の物語を、国や時間や文化の境界を越える横断の歴史として描く。思想史とは、時代の問題と向きあった人びとの行為選択から彼らの知的背景を読みとること、そして彼らが生きた経験へ近づくことである。ピューリタニズムからポストモダニズムまで、あるいはトマス・ジェファソンからリチャード・ローティまで、アメリカ史に作用した観念の力を概説する画期的思想史入門。 === 【目次】 日本語版への序文 序文 第1章諸帝国の世界――コンタクト以前から一七四〇年まで 第2章アメリカと環大西洋啓蒙―― 一七四一年から一八〇〇年まで 第3章リパブリカンからロマンティックへ―― 一八〇〇年から一八五〇年まで 第4章思想的権威をめぐる諸抗争―― 一八五〇年から一八九〇年まで 第5章モダニズムの諸反乱―― 一八九〇年から一九二〇年まで 第6章ルーツと根なし草―― 一九二〇年から一九四五年まで 第7章アメリカ精神の開始―― 一九四五年から一九七〇年まで 第8章普遍主義に抗して―― 一九六二年から一九九〇年代まで エピローグ グローバリゼーションの時代のアメリカ再考、あるいは会話の継続 謝辞 訳者あとがき 原註 さらに学ぶためのブックリスト 索引
この本は、ストーンヘンジからエリザベス2世までのイギリスの歴史を整理し、伝統的な国の魅力を楽しく学べる内容です。目次では、アーサー王伝説、百年戦争、テューダー朝、絶対王政、ピューリタン革命、産業革命、大英帝国の繁栄、第一次世界大戦など、重要な歴史的出来事が取り上げられています。
人名や年号は減らし、「像を結ぶ」「因果関係や背景がわかる」世界史を読み解く。入試の副読本にも使える画期的な教科書。 人名や年号は極力減らす、「像を結ぶ」「因果関係や背景がわかる」説明を目指す、要所に学習者への問いかけを挟むなど様々な工夫をして、歴史に親しむ習慣を養う。市民向けや入試の副読本にも使える画期的な教科書。 カリキュラムの矛盾や入試問題に災いされて、高校生の歴史認識は後退している。本書はそのような現状を跳ね返し、歴史を学ぶ意義や面白さを知ってもらうことをモットーに、全国の高校教員と協力して作られた。人名や年号は極力減らす、「像を結ぶ」「因果関係や背景がわかる」説明を目指す、要所に学習者への問いかけを挟むなど様々な工夫をして、歴史に親しむ習慣を養う。市民向けや入試の副読本にも使える画期的な教科書。 序章 なぜ世界史を学ぶのか 1.21世紀の世界で歴史を学ぶ意味 2.世界史の入り口で 第1章 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 1.文明の誕生と国家の出現 2.遠距離の移動と交流 3.諸地域世界の成立と古代帝国の栄華 4.古代帝国の解体と紀元後3〜5世紀のユーラシア動乱 第2章 地域世界の再編 1.中央ユーラシアの発展と東アジアの再編 2.「唐宋変革」と「中央ユーラシア型国家」の時代 3.ユーラシア西方の変動と新しい地域世界の成立 4.ユーラシア南方の変容 第3章 海陸の交流とモンゴル帝国 1.海陸のネットワークの連鎖 2.モンゴル帝国とアフロ・ユーラシアの「グローバル化」 3.14世紀の危機と大崩壊 4.モンゴルの遺産・記憶とその後のユーラシア 第4章 近世世界のはじまり 1.明を中心とする国際秩序 2.西アジア・南アジアの近世帝国 3.ルネサンスと西ヨーロッパ「近代」の胎動 第5章 大航海時代 1.ヨーロッパ人の世界進出と「近代世界システム」の形成 2.銀と火器による東アジアの激動 3.17世紀の全般的危機 第6章 アジア伝統社会の成熟 1.東アジア諸国の「鎖国」 2.18世紀東アジア諸国の成熟の日中の大分岐 3.東南アジア・インド洋世界の変容 第7章 ヨーロッパの奇跡 1.イギリスとフランスの覇権争奪 2.イギリスの工業化 3.環太平洋革命の展開 第8章 近代化の広がり 1.「パクス・ブリタニカ」の成立 2.欧米の国民国家建設と工業化 3.近代化と大衆社会の萌芽 第9章 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 1.イスラーム世界の苦悩 2.南アジアの植民地化 3.東南アジアの植民地時代 4.東アジアの衝撃と模索 5.「アジア間貿易」とアジアの工業化 第10章 帝国主義とアジアのナショナリズム 1.帝国主義と第一次世界大戦 2.アジアのナショナリズム 第11章 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 1.「戦間期」の繁栄と世界恐慌 2.日中「15年」戦争 3.第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 第12章 冷戦と民族独立の時代 1.戦後の国際秩序と「冷戦」「熱戦」 2.脱植民地化と新興国の国民国家建設 3.「平和共存」と高度経済成長 4.ベトナム戦争とアメリカの覇権の動揺 5.中ソ対立と社会主義の行き詰まり 第13章 現代世界の光と影 1.新自由主義と冷戦の終結 2.開発と民主化 3.イスラームの復興と挑戦 4.グローバル化と反グローバル化 終章 どのように世界史を学ぶか 1.歴史学とはどんな学問か、どのように発展してきたか 2.世界史をさらに学びたい人のために あとがき 図版典拠一覧 索引
「西洋美術史」の決定版が刊行され、古代から現代アートまでの通史を全11章で学べる内容です。700点以上のビジュアルを用い、重要項目を見開きで紹介することで、読みやすさを追求しています。美術系大学でも教科書として採用されており、第一線の研究者11名による最新の視点から解説されています。美術を学ぶ初心者にも、知識を深めたい人にも適した一冊です。
「魔女の社会」は実在したのだろうか? 資料を精確に読み解き、「魔女」にまつわる言説がどのように形成されたのかを明らかにする。解説 黒川正剛 「魔女の社会」は実在したのだろうか? 資料を精確に読み解き、「魔女」にまつわる言説がどのように形成されたのかを明らかにする。解説 黒川正剛 === 「幼児を殺して貪り喰い、近親相姦を行い、十字架に唾をかけ、魔王を崇拝する」――近世のキリスト教世界において激しく非難された「魔女の社会」は、すべてが捏造されたものにすぎない。では、それらの言説はどのような伝統を持ち、いかにして「魔女たち」と結びつき、そして「魔女狩り」に寄与してきたのか。厳密な資料読解を通して、排除と迫害が生み出される条件とその仕組みを明らかにする。また、近代の魔女狩り研究が、どのようにその過ちを増幅し流通させることになったのかについても徹底的に検証する。(解説 黒川正剛) === 排除と迫害と虐殺のメカニズム 「魔女の社会」は、 如何に捏造されたか。 === 【目次】 序文 謝辞 第一章 古代における序幕 第二章 悪魔とその力にかんする見解の変化 第三章 中世の異端の悪霊化(一) 第四章 中世の異端の悪霊化(二) 第五章 テンプル騎士団の壊滅 第六章 儀礼的魔術の実在 第七章 悪霊を崇拝する魔術師は存在しなかった 第八章 魔女の社会は実在しなかった 第九章 民衆の想像の中での夜の魔女 第十章 魔女狩りの開始についての誤った通説 第十一章 魔女狩りは実際に、どのように始まったのか(一) 第十二章 魔女狩りは実際に、どのように始まったのか(二) 訳者あとがき 文庫版解説 学際的な魔女狩り研究を切り開いた先駆者 黒川正剛 書誌的註解 序文 謝辞 第一章 古代における序幕 第二章 悪魔とその力にかんする見解の変化 第三章 中世の異端の悪霊化(一) 第四章 中世の異端の悪霊化(二) 第五章 テンプル騎士団の壊滅 第六章 儀礼的魔術の実在 第七章 悪霊を崇拝する魔術師は存在しなかった 第八章 魔女の社会は実在しなかった 第九章 民衆の想像の中での夜の魔女 第十章 魔女狩りの開始についての誤った通説 第十一章 魔女狩りは実際に、どのように始まったのか(一) 第十二章 魔女狩りは実際に、どのように始まったのか(二) 訳者あとがき 文庫版解説 学際的な魔女狩り研究を切り開いた先駆者 黒川正剛 書誌的註解
最新の科学の成果に基づいて138億年前のビッグバンから未来にわたる長大な時間の中に「人間」の歴史を位置づけ、それを複雑性が増大する「8つのスレッショルド=大跳躍=」という視点を軸に読み解いていく。宇宙論、生物学、化学などの自然科学と歴史学、地理学、社会学などの人文社会学が融合した「新しい学問」、ビッグヒストリーのオリジナルテキスト。 序章 ビッグヒストリーの概要と学び方 第1章 第1・第2・第3スレッショルド:宇宙、恒星、新たな化学元素 第2章 第4スレッショルド:太陽、太陽系、地球の誕生 第3章 第5スレッショルド:生命の誕生 第4章 第6スレッショルド:ホミニン、人間、旧石器時代 第5章 第7スレッショルド:農業の起源と初期農耕時代 第6章 小スレッショルドを経て:都市、国家、農耕文明の出現 第7章 パート1 農耕文明時代のアフロユーラシア 第8章 パート2 農耕文明時代のアフロユーラシア 第9章 パート3 農耕文明時代のその他のワールドゾーン 第10章 スレッショルド直前:近代革命に向けて 第11章 第8のスレッショルドに歩み入る:モダニティ(現代性)へのブレークスルー 第12章 アントロポシーン:グローバリゼーション、成長と持続可能性 第13章 さらなるスレッショルド?:未来のヒストリー 「ビッグヒストリー」を味わい尽す[長沼毅]
東京大学の講義をベースにした『まなざしのレッスン 1西洋伝統絵画』の続篇.印象派以降,伝統的な絵画の枠組みが崩れていくなか,画家たちは何をめざしたのか.難解な近現代絵画を解きほぐし,まったく新しい視点から実践的に読み解く.美術館に行くのが楽しくなる決定版テキスト第2弾. 第1章 西洋近現代絵画をいかに見るか 第1部 主題とテーマ 第2章 物語表現の変容 第3章 現実の表象I 近代都市の諸相 第4章 現実の表象II 人間と自然の新たな表現 第5章 幻視の世界 第2部 造形と技法 第6章 空間と平面 第7章 色彩と筆触 第8章 抽象と超越性 第9章 引用と遊戯性 第3部 受容と枠組み 第10章 制度と運動 第11章 異文化の受容,逸脱の系譜 第12章 絵画という枠組み 掲載図版一覧 画家名索引
多文化主義・地域統合・安全保障・複合国家論・国民国家論・エスニシティ等あらゆる現代社会科学の研究テーマに波及する。 そこはなぜドイツになり、そしてなぜドイツではなくなったのか? 周辺各国の地理・歴史だけでなく、多文化主義・地域統合・安全保障・複合国家論・国民国家論・エスニシティ等あらゆる現代社会科学の研究テーマに波及する。 そこはなぜドイツになり、そしてなぜドイツではなくなったのか? 周辺各国の地理・歴史だけでなく、多文化主義・地域統合 安全保障・複合国家論・国民国家論・エスニシティ等 あらゆる現代社会科学の研究テーマに波及する ●カラーで紋章・旗・歴史観光ガイド ●膨大な量のドイツ時代の古写真 ●時代ごとの境界・国境変遷地図 ●現統治国言語名とドイツ名を必ず併記 ■オストプロイセン 歴代君主の戴冠地ケーニヒスベルクを擁すプロイセンの中核 ■ヴェストプロイセン ポーランド分割後にプロイセンと一体化させられた係争地 ■シュレージエン ピァスト朝・ハプスブルクを経て、工業化を果たした言語境界地域 ■ポーゼン プロイセンによって「ドイツ化」の対象となった「ポーランド揺籃の地」 ■ヒンターポンメルン スウェーデン支配を経て保守派の牙城となったバルト海の要衝 ■北シュレースヴィヒ 普墺戦争からドイツ統一、デンマーク国民国家化への足掛かり ■エルザス=ロートリンゲン 独仏対立の舞台から和解の象徴、欧州連合の中心地に ■オイペン・マルメディ ベルギーの中のドイツ語共同体と、線路で分断された飛び地 ◦カシューブ人、ルール・ポーランド人、オーバーシュレージエン独立運動などマニアックなコラムも 目次 はじめに 2 「分断された歴史叙述」─なぜ今、旧ドイツ領なのか 2 地理概念について 5 本書の構成 5 目次 7 地名表記と地図について 14 凡例 16 旗・紋章 17 歴史観光ガイド 20 オストプロイセン 20 ヴェストプロイセン 28 シュレージエン 36 ポーゼン 44 ヒンターポンメルン 48 北シュレースヴィヒ 54 エルザス=ロートリンゲン 60 オイペン・マルメディ 68 序章 「旧ドイツ領」史概観 73 中・東ヨーロッパにおける国家形成(9-12世紀頃) 74 ポーランド=リトアニアの台頭と宗教改革(13-16世紀) 75 ポーランド=リトアニア共和国の展開と三十年戦争(16-17世紀) 78 ポーランド分割と中・東ヨーロッパの再編(18世紀) 79 ウィーン体制と1848・49年革命(19世紀前半) 83 ドイツ統一(1871-1914年) 85 第一次世界大戦下の中・東ヨーロッパ(1914-1918年) 88 第一次世界大戦の戦後処理・領土問題(1918-1924年頃) 89 戦間期の中・東ヨーロッパ(1918-1933年) 91 ナチ・ドイツと第二次世界大戦(1933-1945年) 95 第二次世界大戦末期の避難と戦後の領土変更にともなう「追放」・「送還」(1945-1950年頃) 99 戦後の中・東ヨーロッパ(1945-1991年頃) 102 第1章 オストプロイセン 歴代君主の戴冠地ケーニヒスベルクを擁すプロイセンの中核 107 ドイツ領となるまで 111 ・プルーセン族 111 ・ドイツ騎士団の到来と移住政策 113 ・プロイセン諸身分とホーエンツォラーン家の対立 116 ・プロイセン王国の成立 117 ・ナポレオンによる占領 120 ・近代オストプロイセンの住民と言語 121 ドイツ領の中のオストプロイセン 124 ・帝政下の言語政策 124 ・政治・経済 126 ・第一次世界大戦 127 ・アレンシュタインでの住民投票とメーメルの分離 128 ・戦間期の苦境 131 ・第二次世界大戦とオストプロイセン 134 ・オストプロイセンからの避難 137 その後 140 ・ソ連領カリーニングラード州 140 ・ポーランド領ヴァルミア・マズーリィ地域 143 テーマ史 146 ・「ゲルマン対スラヴ」─騎士団・東方移住の評価と東方研究 146 ・「ゲルマン対スラヴ」─2つのタンネンベルク 148 ・アルベルトゥス大学ケーニヒスベルクと「ケーニヒスベルクの世紀」 150 著名出身者 152 第2章 ヴェストプロイセン ポーランド分割後にプロイセンと一体化させられた係争地 157 ドイツ領となるまで 161 ・十三年戦争と王領プロイセンの成立 161 ・王領プロイセンの展開 162 ・共和国の没落と第一次ポーランド分割 164 ・プロイセン王国領ヴェストプロイセン 167 ・ナポレオンによる占領と「自由国家」ダンツィヒ 168 ・19世紀前半のヴェストプロイセン 170 ドイツ領の中のヴェストプロイセン 172 ・ドイツ帝国におけるヴェストプロイセン 172 ・「ポーランド回廊」と「自由市」ダンツィヒの承認 174 その後 176 ・自由市ダンツィヒ 176 ・第二次世界大戦の勃発とダンツィヒ=ヴェストプロイセン大管区 179 ・第二次世界大戦後の「ヴェストプロイセン」 183 テーマ史 187 ・ 「ヴェストプロイセン」における言語的少数派カシューブ人 187 著名出身者 189 第3章 シュレージエン ピァスト朝・ハプスブルクを経て、工業化を果たした言語境界地域 195 ドイツ領となるまで 199 ・シロンスク・ピァスト家 199 ・モンゴル軍の襲来と東方移住の開始 201 ・ボヘミア王国の下での繁栄 203 ・ハプスブルク家・宗教改革・三十年戦争 203 ・シュレージエン戦争 207 ・フリードリヒ2世の改革 209 ・ナポレオン戦争とウィーン会議 211 ・シュレージエンにおけるドイツ民族主義の登場と展開 213 ・工業化の時代 214 ・19世紀シュレージエンの言語状況 215 ドイツ領の中のシュレージエン 218 ・文化闘争とポーランド民族運動の興隆 218 ・第一次世界大戦期のシュレージエン 219 ・オーバーシュレージエン問題と住民投票 221 ・ヴァイマル共和国とポーランド共和国の狭間で 226 ・ナチ期のシュレージエン 229 ・第二次世界大戦 231 ・シュレージエンからの避難と追放・送還 234 その後 237 ・「ピァストの地域」 237 テーマ史 240 ・シロンスクの世界遺産 240 ・ ブンツラウ陶器はなぜボレスワヴィエツ陶器(ポーランド陶器)になったのか 244 ・オーバーシュレージエンでの独立運動と集団的帰属意識 246 著名出身者 248 第4章 ポーゼン プロイセンによって「ドイツ化」の対象となった「ポーランド揺籃の地」 255 ドイツ領となるまで 259 ・ピァスト朝黎明の地「ヴィエルコポルスカ」 259 ・ヴィエルコポルスカ公領─束の間の独立 260 ・ポーランド王冠への統合 262 ・ポーランド黄金時代のポズナニ県・カリシュ県・イノヴロツワフ県 264 ・第二次ポーランド分割によるヴィエルコポルスカの割譲 267 ・プロイセン領ポーゼン州の成立とポーランド人問題の浮上 269 ・1848年革命とポーゼン州におけるポーランド人問題 271 ドイツ領の中のポーゼン 273 ・ビスマルクによるポーゼン州のポーランド人問題への対応 273 ・第一次世界大戦と戦後のヴィエルコポルスカ蜂起 275 その後 279 ・ポーランドの戦間期とその破局 279 ・第二次世界大戦における「ヴァルテラント大管区」 282 ・戦後のヴィエルコポルスカ周辺地域 284 テーマ史 287 ・ルール・ポーランド人 287 ・第二次世界大戦期の「民族ドイツ人」入植政策 290 著名出身者 292 第5章 ヒンターポンメルン スウェーデン支配を経て保守派の牙城となったバルト海の要衝 297 ドイツ領となるまで 301 ・ポモラニアの黎明 301 ・ポモージェ公領の成立と展開 302 ・東方移住による人口動態・社会構造の変化 303 ・ポンメルンにおける宗教改革 304 ・スウェーデンによる占領とポンメルン公領の分割 305 ・プロイセンによるヒンターポンメルンの再統合 308 ・ナポレオン戦争とウィーン会議 309 ・プロイセン領ポンメルン州と1848年革命 311 ドイツ領の中のヒンターポンメルン 314 ・帝政期のポンメルン 314 ・ヴァイマル期─保守派の牙城 316 ・ナチ期と第二次世界大戦 319 ・ポンメルンにおけるドイツ人の避難 321 その後の「ヒンターポンメルン」 323 ・「ステティンからトリエステまで」─ポーランド領シュチェチン県の誕生 323 ・シュチェチンと戦後ポーランド 325 テーマ史 327 ・スウェーデン領ポンメルン 327 ・フルトン演説におけるシュチェチンの位置 329 著名出身者 331 第6章 北シュレースヴィヒ 普墺戦争からドイツ統一、デンマーク国民国家への足掛かり 335 ドイツ領となるまで 339 ・スレースヴィの黎明 339 ・スレースヴィ公領の成立とシャウエンブルク家の台頭 341 ・分割されるシュレースヴィヒ=ホルシュタイン 343 ・宗教改革の波及と三十年戦争 344 ・近代スレースヴィの言語状況 345 ・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン(南ユラン)問題 347 ・1848年革命と第一次スレースヴィ戦争 350 ・ヘールスタートの挫折と第二次シュレースヴィヒ戦争 352 ドイツ領の中のシュレースヴィヒ 356 ・ドイツ帝国における北シュレースヴィヒ問題 356 ・第一次世界大戦下のシュレースヴィヒと戦後の住民投票 359 その後 365 ・戦間期の民族問題 365 ・第二次世界大戦と戦後 366 テーマ史 369 ・デンマークとスカンディナヴィア主義 369 ・デュブル砦の戦い 371 ・著名出身者 373 第7章 エルザス=ロートリンゲン 独仏対立の舞台から和解の象徴、欧州連合の中心地に 377 ドイツ領となるまで 381 ・キリスト教の浸透と神聖ローマ帝国による支配 381 ・三十年戦争による荒廃とフランスへの併合 383 ・フランス王国領「アルザス州」 387 ・フランス革命以後のフランス領アルザスとロレーヌ 389 ドイツ領の中のエルザス=ロートリンゲン 392 ・普仏戦争の帰結とドイツ帝政下のエルザス=ロートリンゲン 396 ・第一次世界大戦とエルザス=ロートリンゲンの行方 396 その後 401 ・戦間期におけるアルザス・ロレーヌのフランス化と自治運動 401 ・第二次世界大戦 402 ・第二次世界大戦後のアルザス・ロレーヌ 405 テーマ史 408 ・アルザスとロレーヌの言語 408 ・ エルザス=ロートリンゲン邦国・共和国構想 410 著名出身者 412 第8章 オイペン・マルメディ周辺地域 ベルギーの中のドイツ語共同体と、線路で分断された飛び地 419 ドイツ領となるまで 423 ・ガリア族の支配地域と大修道院領 423 ・中近世のオイペン 425 ・フランスによる支配とウィーン会議 426 ドイツ領の中のオイペン・マルメディ 429 ・オイペン・マルメディでの言語政策とフェン鉄道の開通 429 ・第一次世界大戦とパリ講和会議でのオイペン・マルメディ帰属問題 431 ・国際連盟による暫定統治と住民調査 432 その後 436 テーマ史 439 ・ベルギーのドイツ語共同体 439 ・ワロン語(方言)の歴史と標準化への取り組み 440 著名出身者 441 参考文献・ウェブサイト一覧 442 索引 459 あとがき 462
スコットランド独立の住民投票、EU離脱など、近年話題の絶えないイギリスだが、その背景には何があるのか。古代から現代までの膨大な歴史を50のトピックで切り取り、通史でありつつも各時代のポイントを絞って記述。読み物としても楽しめるイギリス史入門。 はじめに 第Ⅰ部 先史・古代 1 ブリテン島のケルト人――いまも辺境に生きる伝統文化 [コラム1]ストーンヘンジ 2 ブリテン島のローマ人――ローマ文明との出会い [コラム2]ハドリアヌスの防壁 [コラム3]ロンドンの誕生 [コラム4]バース 3 アングロ・サクソン人のイングランド――ヴァイキング来寇以前のアングロ・サクソン諸王の行状 4 アングロ・サクソン・イングランド統一への道――ヴァイキングに翻弄された王朝 5 英語のルーツと変遷――アングロ・サクソン民族の言語から国際語へ 6 キリスト教の伝播――西欧文化圏への帰属 第Ⅱ部 中世 7 ノルマン・コンケスト――論争を生み続ける「イングランド史の転換点」 [コラム5]アングロ・サクソン人を睥睨したノルマン式の城 8 アンジュー帝国――中世英仏関係史の中で 9 マグナ・カルタ――国制基本文書説の再検討 10 大陸からの撤退と島国国家の誕生――中世から18世紀まで 11 百年戦争――島国イギリスの誕生 [コラム6]パブリック・スクール 12 バラ戦争――命運を握っていたのは女性 第Ⅲ部 近世 13 テューダー王朝の始まり――王領地拡大による王権強化 14 ヘンリー8世と宗教改革――その後のイングランドを大きく変えた王の離婚 15 支配されるウェールズ――イングランドによるウェールズの併合を中心として 16 エリザベス朝の社会――格差の拡大とイングリッシュネスの誕生 17 無敵艦隊(アルマダ)の戦い・ドーヴァー沖海戦――無謀なる遠征の果てに 18 東インド会社――世界商業の始まり 19 ピューリタン革命から王政復活へ――回転した革命 20 奴隷貿易と奴隷貿易廃止――「人道主義の帝国」前史 [コラム7]『ピープスの日記』 21 名誉革命――議会中心の体制へ [コラム8]博物学の黄金時代 22 七年戦争――イギリス帝国の形成 23 財政軍事国家の成立――近世国家の歴史的役割 24 イングランドとスコットランドの議会合同――現代までくすぶり続ける政治課題 25 重商主義帝国とは何か――産業革命以前の帝国 26 産業革命――世界で最初の工業国家の誕生 [コラム9]鉄道の発祥と産業革命 27 偉大なる宰相ウォルポール――政権批判に苦しんだ初めての首相 第Ⅳ部 近代 28 アメリカ独立戦争――代表されずして課税なし 29 フランス革命・ナポレオン戦争――最初の「総力戦」とそのインパクト [コラム10]フランス革命の衝撃とパンフレット戦争 30 ジョージ3世と摂政時代――保守と改革 近代の幕開け 31 アイルランド併合・連合王国成立――グローバル帝国主義の助走 32 ヴィクトリア時代――イギリスの黄金時代 33 アヘン戦争――名誉か? 商売か? 34 インド帝国創建――現代インドへの道 [コラム11]イギリスが育んだスポーツ 35 ボーア戦争――「光栄ある孤立」を破棄する大事件 [コラム12]東西を結んだ日英同盟 第Ⅴ部 現代 36 女性参政権――思想と運動の長い営み 37 20世紀の秘密情報機関――連戦連勝の基となった機関 38 覇権国イギリスの第一次世界大戦――帝国の総力戦体制 39 イースター蜂起――共和国殉教神話の誕生 40 イギリス帝国からコモンウェルス――パッチワークの帝国からグローバルな国家クラブへ 41 「至上の時」の神話――イギリスの第二次世界大戦経験 [コラム13]対日戦戦勝記念日(V-Jデー) 42 ウィンストン・チャーチル――コモンセンスを信奉するファイター 43 「ゆりかごから墓場まで」――福祉国家の後は? 44 イギリスの民衆運動――接続する民衆運動 45 イギリスとヨーロッパ統合――終わらない困難な関係 46 サッチャリズム――政策・思想とスコットランド・LGBTから見る 47 ブレア労働党政権――ニュー・レイバー登場 48 イギリスの議会――議院内閣制とポピュリズム 49 現代の移民事情――歴史がつくった多人種社会 50 イギリスにおける人種差別問題――寛容と排除の歴史? 参考文献 歴代首相一覧 歴代国王一覧 年表
アジア史の観点から世界史を一望。西洋中心の歴史観を覆し、「来るべき」世界史を提示する。歴史認識を大胆に刷新する試み。 アジア史の観点から世界史を一望。そのとき「ヨーロッパの奇跡」「日本の近代化」はどう位置づけられるのか。西洋中心の歴史観を覆し「来るべき」世界史をえがく。
本書は、西洋美術の誕生と発展を歴史的背景とともに解説したもので、名作の誕生に関する時代背景をビジュアル年表を用いて詳述しています。古代から現代までの美術と歴史の関係を300点以上の名作を通じて探り、当時の社会や人々の暮らしについても触れています。美術史に興味がある人に最適な内容です。著者は美術史家の池上英洋とライターの青野尚子です。
「ヨーロッパ史」に関するよくある質問
Q. 「ヨーロッパ史」の本を選ぶポイントは?
A. 「ヨーロッパ史」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「ヨーロッパ史」本は?
A. 当サイトのランキングでは『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで211冊の中から厳選しています。
Q. 「ヨーロッパ史」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「ヨーロッパ史」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。











![『大学で学ぶ西洋史[古代・中世]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/610jwOnRctL._SL500_.jpg)








![『大学で学ぶ西洋史[近現代]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/61ZvMdHGljL._SL500_.jpg)

























![『帝国書院 新詳 世界史B [世界史B312] 高校教科書』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51nOJkoTe7L._SL500_.jpg)

































































![『[ヴィジュアル版]中世ヨーロッパ攻城戦歴史百科』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51v+G9hUP-L._SL500_.jpg)













![『詳説世界史B 改訂版 [世B310] 文部科学省検定済教科書 【81山川/世B310】』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51pHmv0qPjL._SL500_.jpg)













![『[決定版]ナチスのキッチン: 「食べること」の環境史』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51fr02EeGOL._SL500_.jpg)