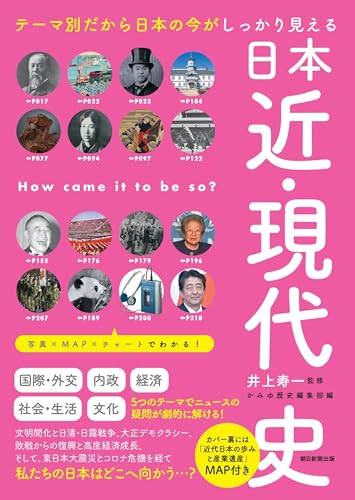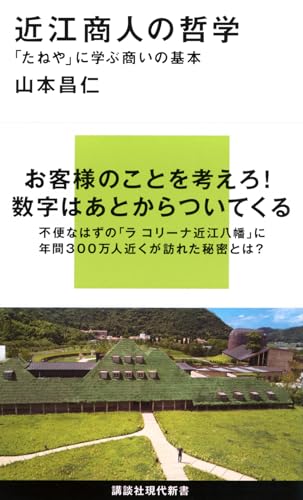【2026年】「現代史」のおすすめ 本 168選!人気ランキング
- 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた
- 読むだけですっきりわかる日本史 (宝島社文庫)
- 300点の写真とイラストで大図解 世界史
- 最新世界史図説タペストリー 十九訂版
- 詳説世界史研究
- 読むだけですっきりわかる世界史 完全版 (宝島SUGOI文庫)
- 今さら聞けない! 世界史のキホンが2時間で全部頭に入る
- 世界史 上 (中公文庫 マ 10-3)
- 教養としての「世界史」の読み方
- 日本近現代史講義-成功と失敗の歴史に学ぶ (中公新書)
この本は、現役教師が書いた新感覚の世界史教科書で、YouTubeでの授業動画が話題となり、50万部を突破しています。一般的な教科書とは異なり、年号を使わずに世界史を一つのストーリーとして解説し、読者が自然に知識を身につけられるよう工夫されています。高校生から社会人まで幅広い層に向けた内容で、歴史を数珠つなぎに学ぶ新しいアプローチを提案しています。著者は福岡県立高校の教諭で、YouTubeでの授業動画が多くの支持を得て「神授業」として評判です。
本書は、日本の歴史を網羅し、教科書には載っていない意外なエピソードも紹介する楽しい日本史の決定版です。旧石器時代から平成までの各時代を分かりやすく解説し、現代人が人生をより良く生きるためのヒントを提供しています。著者は教育評論家の後藤武士氏で、全国で講演活動を行っています。
この書籍は、人類の1000万年の歴史を網羅した内容で、先史時代から現代までの各時代を章ごとに解説しています。著者は歴史学者のジェレミー・ブラックで、彼はイギリスのエクセター大学の教授です。また、藤崎衛と下田明子も関与しており、藤崎は西洋中世史の専門家、下田は翻訳者として活動しています。
時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。 時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。 オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。 時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。 オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。
この図説は、ただの資料集ではありません。ページをめくるたびに、時代が鮮やかに蘇る感覚を味わえます。「時代の流れと地域のつながり」をここまで直感的に理解できる資料集は他にないのではないでしょうか。特に、特集ページは圧巻で、例えば「シルクロードの交易路」や「冷戦下の国際関係」の図解は感動的なほど分かりやすい。細部まで描き込まれた地図や年表は、まるで壮大な歴史ドラマを観ているかのような没入感を与えてくれます。歴史を「学ぶ」だけでなく「体感する」資料集です!
『詳説世界史』に基づき、10年ぶりに全面改訂された世界通史のロングセラー。内容は先史時代から現代までを網羅し、オリエント、地中海、アジア、ヨーロッパの発展や帝国主義、世界大戦、冷戦などを詳述。著者は東京大学名誉教授の木村靖二、岸本美緒、お茶の水女子大学教授と小松久男。
後藤武士の『読むだけですっきりわかる世界史』は、2010年から2012年にかけて出版されたシリーズの内容を一冊にまとめたもので、古代から第二次世界大戦までの歴史を解説しています。人類の誕生から歴史的な重要人物や出来事を網羅し、因果関係を明確にすることで、理解を深めることを目的としています。著者は教育評論家としても知られ、幅広いメディアで活動しています。
令和から見た日本近現代史 立憲革命としての明治維新 日清戦争と東アジア 日露戦争と近代国際社会 第一次世界大戦と日中対立の原点 近代日中関係の変容期 政党内閣と満洲事変 戦間期の軍縮会議と危機の外交 「南進」と対米開戦 米国の日本占領政策とその転換 東京裁判における法と政治 日本植民地支配と歴史認識問題 戦後日中関係 ポスト平成に向けた歴史観の問題
この書籍は、日本の歴史を図解でわかりやすく解説しており、さまざまな事件やエピソードを通じて楽しむことができます。内容は、縄文時代から弥生時代の日本文化の起源、律令国家の成立、大和政権、武士の時代、戦国時代を経て江戸幕府の成立、そして明治維新から太平洋戦争に至るまでの近代化の過程を扱っています。著者の河合敦は、難解な日本史を易しく解説することを目指しています。
『いっきに学び直す日本史入門 近代・現代 実用編』は、佐藤優氏が推薦する日本史の教科書で、読みやすく最新の情報を提供しています。主な特色は、1人の著者による通史の明確な流れ、古い学説を改訂した最新情報、そして日本史を世界史の文脈で理解する視点です。この本はビジネスパーソンが日本史の基礎知識を効率的に学ぶための最適な一冊とされ、巻頭には佐藤氏の解説、巻末には特別対談が収録されています。
この本は、世界史を楽しく学ぶための入門書で、特に教科書が面白くない、覚えることが多すぎる、歴史の流れがつかめないと感じる人に最適です。フルカラーのマンガ形式で有名な歴史人物を紹介し、国ごとに古代から現代までの歴史を整理して学べます。大手予備校の講師によるわかりやすい解説も特徴で、初学者や大学入試の基礎固めにも役立ちます。内容はフランス、朝鮮半島、ロシア、インド、アメリカ、中国など、13の国の歴史が網羅されています。
この書籍は、農業革命と国家形成に関する新たな視点を提供し、定住と穀物栽培が人類や動植物に与えた影響を探求しています。著者は、古代国家が形成される過程で非エリート層がどのような負担を強いられたのか、また農業国家の強制手法やその脆弱性について考察しています。最新の考古学や人類学の成果を基に、従来の歴史観を覆す壮大な仮説が展開されています。著者はイェール大学の教授であり、農民の抵抗に関する研究を行っています。
この書籍は、ホモ・サピエンスが他の人類種に対して繁栄した理由を探求し、国家や貨幣、企業といった虚構が文明の発展をもたらしたことを論じています。内容は三部構成で、認知革命、農業革命、人類の統一について詳述されています。著者はイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリで、彼の研究や講義も広く知られています。
全ての人にオススメしたい書籍。我々ホモ・サピエンスはなぜここまで繁栄することができたのかを著名人類学者が語る。全世界で大ヒットしているだけあって非常に面白い。ボリューミーだが、目からウロコの内容ばかりでどんどん読み進められる。
この書籍は、美術史を洞窟壁画から現代美術までの視点で物語のように描き出しており、絶えず変化しながらも繋がっている美術の流れを紹介しています。目次には、先史時代や古代文明、ギリシャ・ローマ時代、ビザンティン、イスラム、中国など多様な文化の美術が含まれています。著者エルンスト・H・ゴンブリッチは20世紀の著名な美術史家であり、彼の作品は明瞭で説得力があり、美術への深い愛情が表れています。
「歴史漫画サバイバル」シリーズの増補改訂版で、現代の小学生カノン、リュウ、ジュンが戦国時代にタイムワープし、織田信長や武田信玄などの大名と出会いながら歴史を学ぶ冒険を描いています。彼らは元の世界に戻るために戦乱の中で様々なピンチに立ち向かいます。小学校低学年向けの内容です。著者は歴史研究家の河合敦とマンガ家のトリルです。
この書籍は、フランスの歴史をわかりやすく解説しており、ガリア時代からフランス革命、ナポレオン戦争、ベル・エポック、パリ解放までの変革を取り上げています。また、コラム「そのころ、日本では?」を通じてグローバルな視点も提供します。著者は福井憲彦で、フランスを中心とした西洋近現代史の専門家です。
この書籍は、ナチス侵攻から太平洋戦争までの主要な戦闘とその経過を詳細に解説したアトラスです。時間軸と地図を連動させ、戦場や戦況の変化を視覚的に理解できるように構成されています。地図100点、総図版278点を収録し、真珠湾攻撃や沖縄戦など、日本の戦いも詳述。著者は歴史家のピーター・スノウとリチャード・オウヴァリーで、両者は歴史に関する豊富な著作を持つ専門家です。
本書は、宮崎市定による唐と宋の間の時代変革を論じた通史で、平易な文章と明確な論旨が特徴です。上巻では歴史の定義や時代区分を紹介し、古代から近世までの歴史的特徴を概観し、夏殷周から唐五代に至る内容を扱っています。全2冊から成ります。
この書籍は、日本の歴史を形成した著名な人物たちの「すごい」面と「やばい」面を紹介し、歴史の流れを理解しやすくしています。聖徳太子や織田信長など、様々な時代の人物のユニークなエピソードを通じて、日本史への興味を引き出します。著者は歴史学者や漫画家で構成されており、楽しみながら学べる内容になっています。
本書は、イギリスの政治家ウィンストン・チャーチルによる第二次世界大戦に関する記録であり、彼の強力な指導力と歴史観に基づいています。内容は1919年から1940年5月10日までの出来事を描写しており、特にヒトラーの台頭や国際情勢の変化に焦点を当てています。著者のチャーチルはノーベル文学賞を受賞した歴史家でもあり、彼の視点からの戦争の理解を深めることができます。
この書籍は、日本が太平洋戦争に突入した理由を探るもので、為政者の戦争への論理や国民の支持の背景を解明します。著者の加藤陽子は、日清戦争以降の「戦争の論理」を分析し、軍備拡張や朝鮮半島の重要性、満州事変、日中・太平洋戦争への拡大など、歴史的な要因を詳述しています。近代日本の戦争に関する理解を深める画期的な研究です。
「A Short Guide to Writing About Art」(第7版)の日本語版は、美術に関する文章を書くための必携書で、学生や美術ブロガーなど幅広い読者に向けて、美術を言葉で表現するテクニックを解説しています。内容は、作品の見方や具体的な文章技術に至るまで多岐にわたり、レポートや論文、展覧会レビューなどの執筆方法を詳しく説明しています。著者は美術史に詳しいバーネットと竹内順一で、各章には美術を書くための具体的な指針が示されています。
シリーズ累計48万部を超える経済学の入門書が10年ぶりに改訂され、経済の基礎をイラストや用語解説を交えてわかりやすく説明しています。内容は「お金とは何か」から始まり、需要と供給、ケインズ経済学、行動経済学など多岐にわたります。特に、円安や物価高の不安が増す現代において、経済学を学ぶことの重要性が強調されています。著者はジャーナリストの池上彰氏で、初めて経済学を学ぶ人や再学習を希望する人に最適な一冊です。
この書籍は、人類の始まりから現代までの歴史を85項目に分け、図解でわかりやすく解説しています。主要なテーマは「始まり」、「拡大」、「侵略」、「混迷」で、各章では重要な出来事や人物が紹介されており、パラパラとめくるだけで時代の雰囲気を理解できます。受験やビジネスの教養にも役立つ内容です。著者は歴史や古典文学に詳しい福田智弘、イラストは塩浦信太郎が手がけています。
中世フランス王権の歴史的展開 騎士道精神と宮廷風恋愛 中世フランスの社会と文化 ゴシック美術 フランス・ルネサンスの光芒 祝祭と恩赦 絶対王政と宮廷社会 宮廷社会と女性 啓蒙とロココの世紀 文学と修辞学の伝統 フランス革命期の文化、フランス革命という文化 美術展と美術館 革命の遺産と国民文化 宗教と社会 花の都パリ ベル・エポックの輝き 食文化 モード ブルターニュ 戦争と平和、前衛と古典の間で 余暇の過ごし方 フランスの映画 フランスの音楽文化 大衆化、メディア化と変容する文化国家 家族と女性 メディアとジャーナリズム 揺れ動くフランスのアイデンティティ
この書籍は、日本の歴史を神話から現代までの各時代に分けて解説しており、著者の渡部昇一が日本人特有の視点で歴史を捉えています。内容は、古代の神話、武士政権の成立、中世の動乱、近世の戦国時代から江戸幕府の興亡、近代の西洋列強との対峙、そして戦後の復興に至るまで、多様な時代の日本の姿を探求しています。著者は上智大学の名誉教授であり、国内外の大学で学びの経験があります。
世界史の各時代を成り立たせている根本的な要素や性質(=歴史の本質)を徹底的に読み解き、「世界史を再発見」する一冊。 世界史の各時代を成り立たせている根本的な要素や性質(=歴史の本質)を徹底的に読み解き、「世界史を再発見」する一冊。 世界史の各時代を成り立たせている根本的な要素や性質(=歴史の本質)を徹底的に読み解き、「世界史を再発見」する一冊。 個々の歴史事象は単独で起きているわけではありません。歴史にはそれぞれの時代を方向づけている原動力となるものがあります。本書では、まず通史で世界史を俯瞰したあと、各時代の本質的な特色をあぶり出しながら、世界史の全体像をつかみつつ、歴史の「なぜ」を明らかにしていきます。さらに歴史の細部を丹念に読み解いていくことによって、より具体的に時代に通底する本質に触れることができ、歴史の理解が深まります。 本書を読み進めるほど、耳にしたことのある断片的な世界史の知識が高次元でつながり、さらなる知的興奮を覚えることができるでしょう。 第Ⅰ部 世界史を俯瞰するための通史 第1章 古代 第2章 中世 第3章 近世 第4章 近代 第Ⅱ部 時代区分から読み解く歴史の本質 第1章 古代とは? 1 そもそも時代区分とは?―「特徴」=「システム」 2 都市国家と領域国家 3 「世界帝国」―古代の集大成 第2章 中世とは? 1 ヨーロッパにしかない時代、中世 2 2度の民族大移動が中世を作った 3 「ヨーロッパ世界」の誕生―キリスト教の時代が完成 4 第二次民族大移動―「外部勢力」と地方分権の時代 第3章 近世とは? 1 どっちつかずの時代?? 2 大航海時代―商業の時代! 3 近代世界システム―「世界の一体化」が始まる! 第4章 近代とは? 1 産業革命―大量生産の時代が到来 2 ナショナリズム―前近代に「国民」はいなかった!! 終章 世界史の全体像―古代、中世、近世、近代を整理する 第Ⅲ部 世界史を再発見する歴史の視点―より深い理解へ導く見方 第1章 交通網がつないだ帝国―すべての帝国は道を通す! 1 帝国が必ず手掛けるものとは?? 2 ローマ街道―街道から広がるローマ支配 3 ユダヤ教の成立―一神教という画期的宗教! 4 キリスト教―布教が世界を席巻する! 第2章 中世と馬―1241年、東西の騎馬が対峙したとき 1 「騎士」とは何か? 2 騎士の戦術―馬具が決定づけた「衝突撃」 3 騎馬遊牧民と馬―交易と戦闘のエキスパートたち 4 1241年、モヒの戦い―ヨーロッパと騎馬遊牧民、決戦の舞台 第3章 辺境から始まった近現代 1 近代はスイスより始まる? 2 資本主義の拡大―カルヴァンと予定説 3 もうひとつの近代―社会主義の根源
本書は、ミケランジェロやダ・ヴィンチなどの名画を366作品紹介し、1日5分で美術の基礎知識を学べる内容です。1週間で7つのテーマ(美術史、主題、ジャンル、画家の逸話、技法、謎・フェイク、周辺)を通じて西洋美術の見方を深めることができます。著者は美術評論家の瀧澤秀保氏で、長年にわたり美術教育に携わってきました。
幕末期、欧米に対し日本の自立はどのように守られたか なぜ明治の国家は天皇を必要としたか 日清・日露戦争は日本の何を変えたのか 大正デモクラシーとはどんなデモクラシーだったのか 一九三〇年代の戦争は何をめぐる闘争だったのか なぜ開戦を回避できなかったのか 占領改革は日本を変えたのか なぜ日本は高度成長ができたのか 歴史はどこへ行くのか なぜ近現代日本の通史を学ぶのか
本書は、第二次世界大戦におけるドイツ軍(空軍、海軍、陸軍、武装親衛隊)と政府の失敗を分析し、なぜ史上最強と謳われたドイツ軍が滅亡したのかを探る戦争学の新しい視点を提供する。著者は、過去の戦争からの教訓を無視した小失敗や、戦闘車両・空軍・海軍の技術的問題を考察し、ドイツ軍の優れた点も紹介している。著者の三野正洋は日本大学の講師で、現代史の執筆にも取り組んでいる。
本書『室内画の世界』は、美しい部屋の情景を描いた366点の「室内画」を紹介し、フェルメールやマティスなどの巨匠から知られざる名作まで幅広く取り上げています。著者の海野弘氏が各作品のテーマや画家について楽しく解説し、絵画の見方や知識を深める内容です。1日1作を楽しむ形式で、画家たちの自邸に招かれたような体験が提供されます。
本書は、地政学の観点から戦争や紛争の原因を探求し、地理的要因が国家に与える影響を考察しています。中国やロシアの動向、アメリカの地理的優位性の変化などを通じて、国際情勢の複雑さを明らかにします。20枚の地図を用いて、地球上の危機と平和を分析し、地形、歴史、宗教、人種、文化がどのように絡み合っているかを示しています。著者は国際情勢の取材経験が豊富なジャーナリスト、ティム・マーシャルです。
『忘れてしまった高校の世界史を復習する本』のコミック版が登場。古代から現代までを全8章の漫画と図解で学べる内容で、歴史の出来事がつながるストーリーが展開される。著者は祝田秀全で、漫画は絶牙が担当。
この本は、スウェーデン発の子ども向けに書かれた人類史の入門書で、楽しいイラストを交えながら「ホモ・サピエンス」がどのように世界を形成してきたかを探ります。人類の進化や農業の始まり、文化の交流、科学の発展、経済の仕組みについて解説し、SDGsの重要性も理解できる内容です。小学校高学年以上向けで、漢字にはルビがついており、朝読にも適しています。著者は子ども向けの科学書を多く手掛ける作家とイラストレーターです。
『ねこねこ日本史』は、歴史上の重要人物をかわいい猫のイラストと共に解説し、日本史を楽しく学べる内容です。弥生時代から江戸時代までの人物が紹介されています。著者はそにしけんじと福田智弘です。
この書籍は、日本人が第一次世界大戦の重要性を理解していないことを指摘し、戦争の背景や影響を広範な視点から解説する入門書です。著者は、覇権国と新興国の対立や技術革新、グローバリゼーションの進展など、WW1と現代の共通点を示しつつ、戦争技術や国民国家意識、経済的側面などを詳細に探ります。目次には、戦争の発端から日本の参戦、経済影響、戦後の残留物までが含まれています。著者は作家であり、経済の専門家でもあります。
本書は、日本と世界の歴史を変えた重要な事件や出来事を漫画形式で紹介しています。目次には、文明の起源から始まり、古代国家、武家政治、近代日本、二度の世界大戦、戦後の状況までが含まれています。著者はムロタニツネ象で、1953年にデビューした歴史漫画家です。
本書は、戦後日本経済の歴史を67のトピックスを通じて解説する入門書です。財閥解体や石油危機、消費税導入などの重要な出来事を追い、復興から成長、停滞までの軌跡を示しています。著者は日本経済新聞の記者で、現代経済の流れを理解するためのエピソードを中心に構成されています。また、「失われた20年」に関する補論も含まれており、初心者にも分かりやすい内容となっています。
本書は、幕末から現代までの約150年間の日本の近現代史をマンガと解説でわかりやすくまとめたものです。明治維新以降の急速な近代化、戦争、復興、そして現代の社会問題や文化の多様化を10のキーワード(経済、政治、外交など)を通じて振り返ります。著者の河合敦は、複雑な歴史を整理し、読者が理解しやすいよう工夫しています。
この書籍は、第二次世界大戦の全貌を270点以上の写真と共に紹介しています。内容は、ドイツと日本の侵攻、主要な戦闘の流れ、連合軍の反撃、終戦後の世界情勢について詳述されています。著者は池田清で、彼自身が戦争経験を持つ元海軍軍人であり、戦後は大学教授として活躍しました。
パートナーたちは画家の生涯と作品にどのような影響を及ぼしたか。そこには様々な葛藤やドラマがあった。印象派を中心とした15人。 画家たちのパートナーに焦点を当てながら、彼らが画家の生涯と作品にどのようにかかわり、影響を及ぼしたかを探ってゆく。そこには実にさまざまな葛藤やドラマがある。印象派を中心とするフランスの著名画家ら15人を取り上げる。 はじめに 1 ヴィジェ=ルブラン──王妃マリー・アントワネットに愛された美貌の女流画家 2 カウフマン──名声と失意の女流〝歴史画家〟 3 グルーズ──悪妻に悩まされ続けた風俗画家 4 ダヴィド──激動の時代に君臨した巨匠 5 アングル──保守・伝統主義を貫いた〝良き夫〟 6 マ ネ──フランス近代絵画の先駆けとなったパリジャン 7 モ ネ──生活の苦しさ、創作の苦しさを支えたふたりの妻 8 ルノワール──多くの女性を愛し描いた「バラ色の人生」の画家 9 モリゾ──男社会での制約に悩みながらも、〝最も純粋な印象派〟を貫いた紅一点 10 ピサロとシスレー ピサロ──長年貧困に苦しんだ、印象派の「農民画家」 シスレー──終始不遇な人生だった〝晴の日〟の画家 11 モローとシャヴァンヌ モロー──ひとり〝象牙の塔〟に生きた世紀末の隠者 シャヴァンヌ──名家出身の貴婦人との遅すぎる結婚 12 セザンヌ──絵画において人もリンゴも同価値と見做した〝不器用な天才〟 13 ゴーガン──都会を捨て、未開の〝楽園〟に創造の源泉をもとめて おわりに 主要参照文献
「赤毛のエイリークのサガ」と「グリンランド人のサガ」についての情報が記載されている。著者は山元正憲で、1947年に宮崎県生まれの前大学教授。ブリティッシュ・コロンビア・アイスランド・クラブの会員であり、以前は日本中世英語英文学会にも所属していた。
『詳説世界史改定版』は、教科書に完全準拠した内容で、1,800点の写真、250点の地図・図版、140点以上の史料を収録しています。第3版では各テーマに問いを追加し、学習目的を明確化。大学入学共通テストに対応するため、関連する問いも増加しています。目次は先史時代から現代に至るまでの世界史を包括的にカバーしています。
本書は、「天使と悪魔」「天国と地獄」をテーマにした絵画を集め、魅惑的なビジュアルと共にその背景にある伝説や文学を紹介しています。内容は「最後の審判」の特集を含む三章構成で、天国と地獄、天使と悪魔の系譜を探求。美術作品を通じてキリスト教の神秘的な世界を楽しむことができる一冊です。元は2015年に刊行された書籍の再編集版です。
この文章は、南北朝時代における異類異形の者たちや後醍醐天皇の特異な王権について探求する内容を紹介しています。著者は、社会や人間の潜在的な力を引き出しながら、異形の意味とその力を考察しています。目次では、異形の風景や力、後醍醐の王権に関するテーマが取り上げられています。
歴史家の加来耕三氏は、25人の歴史的英雄の失敗を独自の視点で分析し、それらの失敗から現代に通じる教訓を引き出しています。具体的には、明智光秀や黒田官兵衛、徳川家康などの事例を通じて、リーダーシップや判断力の欠如、部下との関係、時代の変化への適応などの重要な要素を探求しています。本書は、失敗から学ぶことで「成功」「逆転」「復活」の法則を見出すことを目的としています。
この参考書は、中学歴史を楽しく学ぶためのもので、ボカロ曲とPV映像が組み合わさっています。収録曲には「千本桜」や「脳漿炸裂ガール」の歴史バージョンを含む10曲があり、歌詞や映像に重要な歴史の用語や流れが散りばめられています。オリジナル曲も多数収録されており、視覚と聴覚を使って学ぶことができます。
この書籍は、フランス革命から始まる近代史の重要な出来事を描いており、ナポレオンの生涯や、ロシア、イタリア、ドイツの近代化、アメリカの歴史、中国の屈辱の歴史、二つの世界大戦の経緯とその後の世界情勢を追っています。各章では、18世紀から21世紀までの歴史的な変革や運動がまとめられています。著者は歴史学者の綿引弘、漫画家の小杉あきら、ほしのちあきです。
本書は、日本史を世界史とつなげて学ぶ重要性を説いています。著者は、日本人の起源や歴史的な出来事を通じて、日本がどのように国際的な文脈で存在しているのかを探ります。内容は、日本人のルーツ、古代の国家形成、戦国時代の国際関係、そして近代の鎖国政策まで多岐にわたり、グローバルな視点から日本の歴史を再評価することを目的としています。著者は人気の世界史講師であり、視覚的な授業スタイルが評価されています。
この本は、人類5000年の歴史を7時間で読み通すことができる新しい教科書です。著者の出口治明氏が、日本史、西洋史、文化史、経済史を一つにつなげて学べるように構成しており、流れをつかむことで教養を深めることができます。中高生から社会人まで、歴史の全体像を理解したい人に最適な入門書で、各章では紀元前から現代までの重要な歴史的出来事を網羅しています。
この教科書は、「世界史のリテラシー」を身につけるためのもので、グローバル時代におけるリベラルアーツの重要性を強調しています。日本の若手知識人が集まり、西洋中心史観から脱却し、全世界的な視点で歴史を再考する内容になっています。高校の新科目「歴史総合」にも対応しており、ビジネスパーソンや高校生など幅広い層に新しい教養を提供します。内容は、近代の歴史学、空間的想像力、社会科学の基本概念を歴史的に考察する三部構成となっています。著者は立命館大学の教授、山下範久です。
本書は、絵画をより深く理解し楽しむための指南書です。著者は、絵の「意味」と「形」の二本柱からアプローチし、特に造形面に焦点を当てています。読者は、名画の主役やバランス、色の使い方、構図などを学びながら、絵を観察する力を養うことができます。理系の人や理論を好む人にも適しており、絵をパズルのように読み解く楽しさを提供します。最終的に、名画が名画たる理由を理解し、個々の感想と客観的な分析を結びつけることを目指します。
東京大学の講義をベースにした『まなざしのレッスン 1西洋伝統絵画』の続篇.印象派以降,伝統的な絵画の枠組みが崩れていくなか,画家たちは何をめざしたのか.難解な近現代絵画を解きほぐし,まったく新しい視点から実践的に読み解く.美術館に行くのが楽しくなる決定版テキスト第2弾. 第1章 西洋近現代絵画をいかに見るか 第1部 主題とテーマ 第2章 物語表現の変容 第3章 現実の表象I 近代都市の諸相 第4章 現実の表象II 人間と自然の新たな表現 第5章 幻視の世界 第2部 造形と技法 第6章 空間と平面 第7章 色彩と筆触 第8章 抽象と超越性 第9章 引用と遊戯性 第3部 受容と枠組み 第10章 制度と運動 第11章 異文化の受容,逸脱の系譜 第12章 絵画という枠組み 掲載図版一覧 画家名索引
本書は、広義の「東洋史」をテーマに、アフロ・ユーラシア地域の歴史的論点を158項目にわたり解説したものです。各項目は背景、論点、探究のポイントに分かれており、語句説明やクロスリファレンスも豊富で、歴史研究の魅力を伝える内容となっています。著者は東京大学の吉澤誠一郎教授で、学生や研究者にとって必携の一冊です。
本書は、西洋の歴史に関する様々な「論点」を集め、真実を求める主張がどのように対立しているかを探求するテキストです。各項目は「史実」「論点」「歴史学的に考察するポイント」の3パートから成り、豊富な語句説明やクロスリファレンスにより、世界史の知識がなくても理解しやすい内容となっています。著者は歴史学の専門家であり、古代から現代に至る西洋史の主要な論点を取り上げています。
このエッセイ集では、オスマン改造以前の19世紀パリの魅力を探求し、ボードレールやプルーストが生きた時代の街の音や匂いを鮮やかに再現しています。内容は、パリの歴史や文化、香りや光の変遷をテーマにした章で構成されており、濃密な「パリ時間」を体験できる知的な旅を提供します。
「KAGEROU PROJECT」とのコラボによる学習参考書が登場。マンガとキャラクターの会話を通じて、古代文明から現代までの中学歴史の重要45テーマを効率的に学べる内容。3ステップで概要をつかみ、時代を理解し、問題演習を行う構成で、予習・復習やテスト対策に役立つ。監修は「スタディサプリ」の伊藤賀一先生。特典として歴史年表とミニポスターも付属。
この書籍は、歴史学の重要性や社会的役割について探求する内容です。著者は、歴史がどのように個人や社会に役立つのかを問い、歴史教科書の限界や相対主義・構造主義の批判に対して、歴史学が提供する「知の技法」の価値を示します。具体的には、歴史小説と歴史書の違いや従軍慰安婦論争を例に挙げ、歴史学の実用性や教育の意義を考察します。著者は社会経済史を専門とする東北大学の助教授です。
この文章は、百年戦争の期間中にフランスの運命を変えた少女ジャンヌ・ダルクについての内容を紹介しています。彼女は普通の農家の娘から「救国の英雄」となり、後に火刑にされる運命を辿ります。著者は、ジャンヌがオルレアンを解放した経緯や、彼女のカリスマ性、同時代への影響、後世における政治や宗教、文学、芸術への影響を探ります。これは、歴史的事件とその問いを通じて過去と現在を結びつける新しいシリーズの第1回配本です。
本書は、日本史の疑問を解明するために江戸時代から鎌倉時代に遡り、明治維新とフランス革命の違いや武士階級の没落、江戸時代の長期安定の理由、信長の戦国統一の真相、室町・鎌倉幕府の平家政権としての側面を探る内容です。
著者の網野善彦は、日本中世の歴史を再評価し、農業中心社会のイメージや商工業者、芸能民の賤視について考察しています。文明史的大転換期における貨幣経済、階級差別、権力、信仰、女性の地位、多様な民族社会の実態を明らかにし、均質な日本社会像に疑問を呈しています。書籍は続編と共に文庫化され、歴史の多様な側面を平易に語ります。
交戦国の外交戦略と経済情勢、技術革新の実態のみならず銃後の世論の変遷も詳説した、イギリスの代表的研究者による定評ある入門書。 交戦国の外交戦略と経済情勢、技術革新の実態のみならず銃後の世論・国民感情の変遷も詳説した、イギリスの代表的研究者による定評ある入門書。 地球上のあらゆる海で戦われ、すべての大陸の国家が参戦した未曾有の世界戦争は、一部の都市生活者の熱狂と、大多数の人びとの黙認のもとで始まった。イギリスの代表的研究者が平易な言葉で「人びとが戦争をする理由」に迫った定評ある入門書。各国の外交戦略と経済情勢、技術革新の実態のみならず銃後の世論・国民感情の変遷も詳説し、欧州の一地域紛争が世界を戦火に巻きこんでいく過程を描く。 第1章 一九一四年のヨーロッパ 第2章 戦争勃発 第3章 一九一四年──緒戦 第4章 一九一五年──戦争継続 第5章 一九一六年──消耗戦 第6章 アメリカ参戦 第7章 一九一七年──危機の年 第8章 一九一八年──決着の年 第9章 講和 訳註 訳者あとがき 地図 付録 I ウィルソン大統領の平和原則14カ条 付録 II 戦争の被害 読書案内 索引
本書は東京藝術大学の講義に基づく西洋美術の入門書で、著者が選んだ個々の作品を通じてそのメッセージをわかりやすく解説します。ビジュアルを多用し、読者が楽しみながら鑑賞眼を鍛えることを目的としています。全15回の講義形式で構成され、作品同士の関連性を示しながら、美術鑑賞の実践的なアプローチを提案。著者は東京藝大の准教授で、美術史の専門家です。
この書籍は、15世紀から18世紀にかけての世界史の重要な出来事を描いた冒険物語です。大航海時代、ルネサンス、イギリスの産業革命、絶対主義国家の興亡、中国の漢民族国家の成立、オスマン帝国の成長、アメリカ建国の歴史など、各章でさまざまな歴史的テーマが紹介されています。著者は歴史学者の綿引弘、漫画家の小杉あきら、ほしのちあきの3人で構成されています。
『イラストでサクッと理解! 流れが見えてくる日本史図鑑』の第2弾で、豊富なイラストを通じて世界史の流れを理解できる内容です。横長のワイド判で時間軸が見やすく、大人の復習や中高生の学習に適しています。各章は中国・東アジア、ヨーロッパ、中東・イスラーム、その他の地域、テーマ別に分かれています。
この文章は、四大文明の誕生から帝国の形成、宗教や思想の発展、民族や文化の違いに関する歴史的な考察をまとめた内容です。具体的には、文明の発展が乾燥地帯に起因する理由、水の影響、宗教や思想が環境に左右されること、帝国の成立と衰退、周縁地域の歴史が世界史の理解を深めることについて述べています。また、著者の角田陽一郎の経歴やメディアビジネスにおける活動も紹介されています。
『経営戦略全史』シリーズの新装マンガ版が発売され、最新の経営トピックを加筆した合本版です。マンガ形式で経営戦略の進化を学べ、各章の後には解説が付いています。内容は、歴史的な経営戦略論と現代のイノベーション論に焦点を当て、経営学の復習やビジネスに対する指南書として役立ちます。著者は経営戦略コンサルタントから教育者に転身した三谷宏治氏で、約500ページにわたるストーリー形式で経営戦略の流れを描いています。
古代から現代にいたるまで、現在のフランスを構成する地域の歴史を平易な文章で叙述。政治史を軸に、社会、経済、宗教、文化などの様々なテーマを絡めながら、各時代を多彩な執筆陣が立体的に描き出し、読者を新たなフランスの発見へといざなう。 はじめに 第Ⅰ部 古代・中世 1 ローマ帝国下のガリア――カエサルの遺産、そして「フランス」のプレリュードへ 2 「フランキア」から「フランス」へ――「フランク人」小史 3 ガリア聖歌――「フランス音楽」の古層 4 封建社会の王――前期カペー朝 5 フランス中世の教会と修道院――11〜12世紀の信仰と平安 6 フランスのロマネスク美術――大いなる実験の時代 7 「長い13世紀」とフランス王国――王権の伸長と王領地の拡大 [コラム1]12〜13世紀フランスの女性権力者 8 ゴシック建築とフランス――歴史のなかで変化する「ゴシック」 9 中世のパリ――都市代表組織の形成を中心に 10 カタリ派のコスモロジー――中世南フランスの信仰と異端迫害 11 托鉢修道会の誕生と拡大――都市社会のキリスト教信仰 12 神学vs.哲学――世界の永遠性をめぐる13世紀パリ大学での論争 13 13世紀における都市の勃興と文学――アラスの場合 14 中世フランスの民主主義――都市と村落の自治 [コラム2]サン・テミリオンのワインとジュラード 15 百年戦争の開始――相次ぐ敗北と三部会の反乱 16 百年戦争の終結とその後のフランス――諸侯と公妃に導かれるフランス [コラム3]ジャンヌ・ダルクとそのイメージ 第Ⅱ部 近世 17 フランスの宗教改革――福音主義運動の展開から改革派教会の創立へ 18 宗教戦争の終結とアンリ4世――内乱を経て王国再建へ [コラム4]フランスのルネサンス文化 19 ルイ13世とリシュリュー――国家の利益で結ばれた王と宰相 20 フロンドとマザラン――戦時体制への不満と党派間の争い 21 ルイ14世の親政――「偉大なる世紀」の光と影 22 絶対王政の統治構造――社団、儀礼、公共圏 23 近世のパリ――王権による首都統治体制の形成 24 近世フランスのキリスト教(17~18世紀)――カトリックとカルヴァン派の信仰生活 25 「近代家族」の誕生――夫婦と親子をつなぐ情愛の絆 26 啓蒙思想――「敢えて賢くあれ」 [コラム5]ジャン=ジャック・ルソー 27 ルーヴル美術館の誕生――アンシアン・レジームから革命へ 第Ⅲ部 近代 28 フランス革命の展開――中道派からみた革命 29 革命祭典――7月14日の国民祭典 30 フランス革命期における人権と外国人――普遍的理念とその限界 31 フランス革命と戦争――戦争の世界化と多義化 32 ナポレオンの統治――統領政府と第一帝政 [コラム6]名望家体制 33 復古王政と七月王政――フランス型自由主義の摸索 34 二月革命と第二共和政――「国民」の政治参加 35 ナポレオン3世と第二帝政――19世紀の転換期 36 首都パリの大改造――近代都市モデルの誕生 37 第三共和政の成立と展開――「三度目の正直」の波乱と苦闘 [コラム7]社会福祉政策の形成 38 植民地帝国の形成――産官学連携の国家事業 39 万国博覧会と大衆消費文化――19世紀の首都パリの形成 40 フランスのユダヤ人――「近代国民国家」フランスとの複雑な関係性 第Ⅳ部 現代 41 第一次世界大戦とフランス――崩されゆく国民的神話 42 両大戦間期のフランス――体制崩壊の危機を乗り越え、社会の分裂を招いた20年 43 第二次世界大戦と占領されたフランス――国民革命か共和的合法性か 44 ドゴールの時代――「二つのフランス」をつなぐ移行期 45 植民地の独立――帝国崩壊の要因と影響 46 五月事件からミッテラン政権へ――市場化改革の源流? 47 ライシテと学校教育――フランス流の市民の育て方 48 現代パリの都市空間――膨張と変貌 [コラム8]ル・コルビュジエ 49 フランスの移民――19世紀から今日まで 50 フランス、EU、グローバリゼーション――フランスはどこへ向かうのか フランスの歴史を知るための参考文献 フランス史略年表
この書籍は、2000万人の犠牲を伴った第一次世界大戦を中心に、戦争の影響で変わる世界の様子を詳細に描いています。写真やイラスト、地図を用いて戦況の変化や新兵器の登場を解説し、政治的背景や戦術の変化も詳述しています。目次は戦争の前兆から開戦、戦況の拡大、アメリカの参戦、戦後の新世界秩序までをカバーしています。著者は軍事史の専門家で、広範な著作を持つ研究者たちです。
人名や年号は減らし、「像を結ぶ」「因果関係や背景がわかる」世界史を読み解く。入試の副読本にも使える画期的な教科書。 人名や年号は極力減らす、「像を結ぶ」「因果関係や背景がわかる」説明を目指す、要所に学習者への問いかけを挟むなど様々な工夫をして、歴史に親しむ習慣を養う。市民向けや入試の副読本にも使える画期的な教科書。 カリキュラムの矛盾や入試問題に災いされて、高校生の歴史認識は後退している。本書はそのような現状を跳ね返し、歴史を学ぶ意義や面白さを知ってもらうことをモットーに、全国の高校教員と協力して作られた。人名や年号は極力減らす、「像を結ぶ」「因果関係や背景がわかる」説明を目指す、要所に学習者への問いかけを挟むなど様々な工夫をして、歴史に親しむ習慣を養う。市民向けや入試の副読本にも使える画期的な教科書。 序章 なぜ世界史を学ぶのか 1.21世紀の世界で歴史を学ぶ意味 2.世界史の入り口で 第1章 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 1.文明の誕生と国家の出現 2.遠距離の移動と交流 3.諸地域世界の成立と古代帝国の栄華 4.古代帝国の解体と紀元後3〜5世紀のユーラシア動乱 第2章 地域世界の再編 1.中央ユーラシアの発展と東アジアの再編 2.「唐宋変革」と「中央ユーラシア型国家」の時代 3.ユーラシア西方の変動と新しい地域世界の成立 4.ユーラシア南方の変容 第3章 海陸の交流とモンゴル帝国 1.海陸のネットワークの連鎖 2.モンゴル帝国とアフロ・ユーラシアの「グローバル化」 3.14世紀の危機と大崩壊 4.モンゴルの遺産・記憶とその後のユーラシア 第4章 近世世界のはじまり 1.明を中心とする国際秩序 2.西アジア・南アジアの近世帝国 3.ルネサンスと西ヨーロッパ「近代」の胎動 第5章 大航海時代 1.ヨーロッパ人の世界進出と「近代世界システム」の形成 2.銀と火器による東アジアの激動 3.17世紀の全般的危機 第6章 アジア伝統社会の成熟 1.東アジア諸国の「鎖国」 2.18世紀東アジア諸国の成熟の日中の大分岐 3.東南アジア・インド洋世界の変容 第7章 ヨーロッパの奇跡 1.イギリスとフランスの覇権争奪 2.イギリスの工業化 3.環太平洋革命の展開 第8章 近代化の広がり 1.「パクス・ブリタニカ」の成立 2.欧米の国民国家建設と工業化 3.近代化と大衆社会の萌芽 第9章 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 1.イスラーム世界の苦悩 2.南アジアの植民地化 3.東南アジアの植民地時代 4.東アジアの衝撃と模索 5.「アジア間貿易」とアジアの工業化 第10章 帝国主義とアジアのナショナリズム 1.帝国主義と第一次世界大戦 2.アジアのナショナリズム 第11章 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 1.「戦間期」の繁栄と世界恐慌 2.日中「15年」戦争 3.第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 第12章 冷戦と民族独立の時代 1.戦後の国際秩序と「冷戦」「熱戦」 2.脱植民地化と新興国の国民国家建設 3.「平和共存」と高度経済成長 4.ベトナム戦争とアメリカの覇権の動揺 5.中ソ対立と社会主義の行き詰まり 第13章 現代世界の光と影 1.新自由主義と冷戦の終結 2.開発と民主化 3.イスラームの復興と挑戦 4.グローバル化と反グローバル化 終章 どのように世界史を学ぶか 1.歴史学とはどんな学問か、どのように発展してきたか 2.世界史をさらに学びたい人のために あとがき 図版典拠一覧 索引
「現代史」に関するよくある質問
Q. 「現代史」の本を選ぶポイントは?
A. 「現代史」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「現代史」本は?
A. 当サイトのランキングでは『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで168冊の中から厳選しています。
Q. 「現代史」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「現代史」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。








































![『帝国書院 新詳 世界史B [世界史B312] 高校教科書』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51nOJkoTe7L._SL500_.jpg)








![『池上彰のやさしい経済学[令和新版] 1 しくみがわかる』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/512+OidTliL._SL500_.jpg)























![『池上彰のやさしい経済学[令和新版] 2 ニュースがわかる』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/514ImNpPysL._SL500_.jpg)































































![『[完訳版]第二次世界大戦 1――湧き起こる戦雲』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/415-NYNVx9L._SL500_.jpg)

![『詳説世界史B 改訂版 [世B310] 文部科学省検定済教科書 【81山川/世B310】』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51pHmv0qPjL._SL500_.jpg)