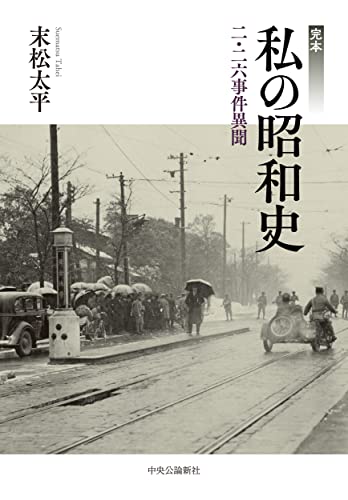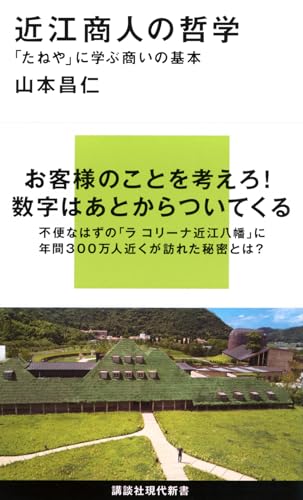【2025年】「昭和史」のおすすめ 本 93選!人気ランキング
- 昭和史 1926-1945 (平凡社ライブラリー)
- 幕末史 (新潮文庫)
- 世界史のなかの昭和史 (平凡社ライブラリー) (平凡社ライブラリー 905)
- 日本史はこんなに面白い (文春文庫 は 8-18)
- 昭和史戦後篇 (平凡社ライブラリー)
- 完本-昭和史のおんな(下) (中公文庫 さ 27-5)
- 写真で読む昭和史占領下の日本 日経プレミアシリーズ (日経プレミアシリーズ 102)
- 完本-私の昭和史-二・二六事件異聞 (単行本)
- 日本のいちばん長い日 決定版 (文春文庫 は 8-15)
- 昭和史がわかるブックガイド (文春新書 1262)
本書は、嘉永6年(1853年)からの25年間にわたる日本の歴史の激動を描いています。ペリー艦隊の来航から始まり、幕末の混乱、坂本龍馬の死、江戸城の開城、戊辰戦争、新政府の樹立と西南戦争まで、多くの歴史的人物と出来事が著者の独自の視点で語られています。著者は半藤一利で、彼は歴史作家としての業績を持っています。
聖徳太子は文武両道の「行動する思想家」だった 蝦夷のリーダー「アテルイ」はなぜ日本史から抹殺されたか 『平家物語』は、戦いのむなしさを伝えてかくも美しい 「神を目指した男」織田信長は空前絶後の革命家だった 権力を極めた人の辞世ほど「この世は虚しい」という 徳川家康だって女の前ではだらしなくゴロ寝していたのです 「古池や」の句は時代に対する俳諧興行師・芭蕉の戦略だった 妖怪が近くへやって来るのは、あなたが「貧乏で寂しいとき」です ヒトラーは二〇世紀のベルリンに巨大な阿房宮を建てようとした 開戦前夜、米国の暗号解読力は実はこんなにも「お粗末」だった 戦争中も祈り続けた昭和天皇、彼はいったい誰のことを祈ったのか あの「終戦の詔勅」をぼくは土下座して聞きました 戦後憲法はこうして生まれた。白洲次郎が見た占領下の日本 チャンバラ映画の魅力は「禁欲の美学」にあり 橋とカッパと人情と-墨田川高校同窓生の東京下町談義 特別版 戦争と艶笑の昭和史
私の昭和史 赤化将校事件 青森連隊の呼応計画 刑場の写真 夏草の蒸すころ 夏草の蒸すころ. 続 素描・竹橋事件 有馬頼義の『二・二六暗殺の目撃者』について 映画「脱出」について 利用とあこがれ/人生の本 末松太平著『私の昭和史』について
このノンフィクションは、1945年8月6日の広島への原爆投下とソ連軍の満州侵略を背景に、日本政府がポツダム宣言に対して決断を下せない状況を描写しています。著者は、8月15日を中心に展開される24時間の出来事を、詳細な取材と証言に基づいて再現し、当時の軍や政府の内部の葛藤と緊張感を伝えています。著者は半藤一利で、作家としての経歴を持ち、複数の文学賞を受賞しています。
昭和3年(1928)植民地下の釜山に生まれ育ち、戦後「肉体的望郷」に突き動かされ、日本と朝鮮半島、近代と現代、記憶と記録のはざまを彷徨いながら、詩を書き、小説で語り、新羅凧を作り海峡に揚げ続けた詩人・鈴木召平… 「二つの民族の中で、私はひょっこり生まれた昆虫でしかなかった。」 昭和3年(1928)、植民地下の南朝鮮・釜山に生まれ育ち、昭和初期の日本、戦争、民族、家族の崩壊、ふるさとの消失を、小さな体全体で受け止め過ごした少年時代。以来、「肉体的望郷」に突き動かされ、日本と朝鮮半島、近代と現代、記憶と記録のはざまをさまよいながら、詩で繋ぎ、小説で語り、新羅凧を作り海峡に揚げ続けた詩人・鈴木召平の遺稿作品集。 (四つの小詩集からなる「最終詩集」と自伝的小説『墓山の凧』他を収録した「小説集」) 〈詩篇(四つの小詩集からなる「最終詩集」)〉 Ⅰ 昭和史幻燈/Ⅱ 草梁洞大成座/Ⅲ 終戦譜/Ⅳ 輪廻半月 〈野史篇〉 Ⅴ 凧の科学/Ⅵ ハイシャンケンキチの沈黙/Ⅶ 焼土史「宮崎宣久」の場合 〈小説篇〉 Ⅷ 赤土と風―外地断章/Ⅸ 北埠頭―ハカタメモランダム/Ⅹ 墓山の凧―肉体的望郷 鈴木召平追悼文集/鈴木召平年譜
この書籍は、参謀本部作戦課と関東軍作戦課のエリート集団が自己を見失った結果、満蒙国境での悲劇が引き起こされる様子を描いています。著者は、司馬遼太郎氏が未完のテーマを引き継ぎ、モスクワのスターリンやベルリンのヒトラー、中国の動向を交えながら、混迷の時代に警鐘を鳴らします。目次には、各月ごとの章があり、著者は東京大学卒業後、文芸春秋での編集長などを経て作家として活動しています。
なぜ昭和の日本は戦争へと向かったのか。複雑きわまる戦前期を正確に理解すべく、俗説を排して信頼できる史料に依拠した研究成果。 なぜ昭和の日本は戦争へと向かったのか。 複雑きわまる戦前期を正確に理解すべく、俗説を排して信頼できる史料に依拠。 第一線の歴史家たちによる最新の研究成果。 1 ワシントン条約体制と幣原外交 渡邉公太 2 普通選挙法成立と大衆デモクラシーの開始 小山俊樹 3 北伐から張作霖爆殺事件へ 家近亮子 4 ロンドン海軍軍縮条約と宮中・政党・海軍 畑野勇 5 満州事変から国際連盟脱退へ 等松春夫 6 天皇機関説事件 柴田紳一 7 二・二六事件と昭和超国家主義運動 筒井清忠 8 盧溝橋事件──塘沽停戦協定からトラウトマン工作失敗まで 岩谷將 9 日中戦争の泥沼化と東亜新秩序声明 戸部良一 10 ノモンハン事件・日ソ中立条約 花田智之 11 日独伊三国同盟への道 武田知己 12 近衛新体制と革新官僚 牧野邦昭 13 日米交渉から開戦へ 森山優 14 「聖断」と「終戦」の政治過程 鈴木多聞 15 日本占領──アメリカの対日政策の国際的背景 井口治夫
この書籍は、昭和史の教訓を通じて現代の日本社会の問題を考察する対談集です。著者たちは、戦争とメディアの関係、ナショナリズムの高まり、そしてジャーナリズムの役割について議論し、歴史が繰り返す可能性を探ります。反骨のジャーナリストたちの仕事も紹介され、現代への警鐘が鳴らされています。
ふたつの戦場ミッドウェーと満洲 指揮官たちは戦後をどう生きたか なぜ日本人は山本五十六を忘れないのか 天皇と決断 栗林忠道と硫黄島 撤退と組織 東京の戦争 戦争と艶笑の昭和史 無責任論 幕末から昭和へ熱狂の時代に 清張さんと昭和史 戦後六十年が問いかけるもの
暴走の本質 軍備拡張競争の実態:建艦競争を中心に 近代日本における軍事力編成 近代日本の戦争を支えたソフト・システム・ハード 第二次世界大戦における日本の敗因 兵士たちの日中戦争 日本軍の航空特攻作戦の特徴 沖縄戦の軍事史的位置
ヒロシマの空 『きけわだつみのこえ』より レイテ戦記 私のひめゆり戦記 麦と兵隊 今夜、死ぬ 叫び声 指揮官たちの特攻 神聖喜劇 母と子でみる東京大空襲 断腸亭日乗 生ましめんかな 敗戦日記 はだしのゲンはピカドンを忘れない 私の中国捕虜体験 黒い雨 夏の花 沖縄よどこへ行く 回天特攻学徒隊員の記録 火垂るの墓 八月六日 暗い波濤 崖 七三一部隊で殺された人の遺族 夢がたり 戦争はおしまいになった 難民になる
欧洲大戦と日本のゆらぎ 三つの「戦争」 第二次世界大戦 南進と大東亜「解放」 朝鮮駐屯日本軍の実像 帝国在郷軍人会と政治 日本陸軍の中国共産党観 日本軍人の蔣介石観 戦前日本の危機管理 支那事変初期における近衛内閣の対応 日本人の日中戦争観 日中和平工作の挫折 汪兆銘のハノイ脱出をめぐって 桐工作をめぐって 対中和平工作 一九四二~四五年
「昭和史」に関するよくある質問
Q. 「昭和史」の本を選ぶポイントは?
A. 「昭和史」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「昭和史」本は?
A. 当サイトのランキングでは『昭和史 1926-1945 (平凡社ライブラリー)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで93冊の中から厳選しています。
Q. 「昭和史」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「昭和史」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。