【2025年】「ffs理論」のおすすめ 本 51選!人気ランキング
- 宇宙兄弟とFFS理論が教えてくれる あなたの知らないあなたの強み【自己診断ID付き】
- マッキンゼー 勝ち続ける組織の10の法則
- マーケティングとクリエイティブをもう一度やり直す 大人のドリル
- PowerPoint資料作成 プロフェッショナルの大原則
- ドラゴン桜とFFS理論が教えてくれる あなたが伸びる学び型【WEB診断付き】
- 資本主義の先を予言した 史上最高の経済学者 シュンペーター
- 社内プレゼンの資料作成術
- 一生使える 見やすい資料のデザイン入門
- 世界で一番やさしい 資料作りの教科書
- 渋沢栄一と明治の起業家たちに学ぶ 危機突破力
本書は、人気マンガ『宇宙兄弟』を通じて自分の強みを理解し、他人の個性を把握する方法を解説しています。著者は「FFS理論」を用いて、登場人物の心理や行動を分析し、自己理解、他者理解、組織理解の観点から具体的な事例を挙げています。読者は、自分に似たキャラクターを知ることで、強みを活かし、効果的なチーム作りを学ぶことができます。
本書は、マッキンゼーが20年間のケーススタディとハーバード・ビジネス・レビューの記事を基に、組織を効果的に率いるための10の法則を提唱しています。デジタル化やグローバリゼーションに対応するためのマネジメント手法を解説し、意思決定の質やスピードを向上させる方法、競争力のある組織文化の構築、優れた人材の育成と定着について具体的な実践法を紹介しています。リーダーやマネジャーにとって必携の一冊です。
この本は、人気コミック『ドラゴン桜』とFFS理論を組み合わせて、個々の特性に合った効率的な学び方を提案しています。勉強ができないと感じる理由は、適切な「勉強の型」を身につけていないからかもしれません。FFS理論に基づき、人間の性格を「保全性」と「拡散性」に分類し、それぞれの特性に応じた学習法を紹介します。読者は自己分析を通じて、自分に合った勉強法を見つけ、ストレスなく成果を上げることができるようになります。
この文章は、経済学者シュンペーターの「イノベーション」理論について紹介しています。シュンペーターは、単なるアイディアよりも既存の要素を組み合わせて新たな価値を生み出すことが重要だと説いており、スティーブ・ジョブズのiPhoneの成功がその例として挙げられています。シュンペーターの理論は、現代の経営者にとっても有用であり、変革は内から起こるべきであると強調しています。著者はシュンペーターの思想を学ぶことの重要性を訴えています。
鈴川葵の成長を描く第2弾。入社4年目の彼女はプレゼンに苦しみながら、社内の会議を改革し、資料作りを学びます。コンサルタントの父から教わった「資料作りの7つのStep」と「コミュニケーションの3つの作法」を実践し、効果的なプレゼンテーションの技術を身に付けていきます。本書では、コミュニケーションの原理を資料作りを通じて解説し、主人公の成長を通じて読者も学べる内容となっています。
本書は、渋沢栄一や三菱、三井、住友の起業家たちが逆境を乗り越えた事例を通じて、どん底でもチャンスがあることを伝えています。歴史は繰り返され、経営の原則は変わらないため、過去の成功者から学ぶ意義があります。著者は、胆力、危機管理力、先見力を持つ11人の経営者のエピソードを通じて、現代のビジネスに役立つ知恵を提供しています。読者は彼らの失敗や苦難から危機突破力を学び、ビジネスのヒントを得ることができるでしょう。
この書籍は、「アンラーン」という概念を通じて、過去の学びや思い込みを手放し、新たな成長を促す技術を紹介しています。アンラーンは、学びの効率を高めるために必要なプロセスであり、特に変化に対応するために重要です。具体的には、固定化した思考を解きほぐし、日々の小さなアンラーンを習慣化する方法が提案されています。また、アンラーンを阻む壁を理解し、それを乗り越えるためのヒントも提供されています。最終的には、アンラーンを人生やキャリアの武器として活用することが強調されています。
著者の末永雄大が、20~30代の転職希望者に向けて、転職成功のためのノウハウを解説した書籍です。内容は「準備編」と「本番編」に分かれ、自己分析や求人サイトの活用法、面接のポイントなどを詳しく説明しています。転職活動の戦略や職務経歴書の書き方、内定後の対応についても触れています。著者は転職エージェントとしての経験を基に、実践的なアドバイスを提供しています。
この文章は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の事例と価値交換の仕組みについて述べています。具体的な企業例として、Netflix、Walmart、Sephora、Macy's、Freshippo、Nike、Tesla、Uber、Starbucksが挙げられ、それぞれの業界でのDXの影響や方向性が紹介されています。また、業界別にDXの事例を分析するセクションもあります。著者は金澤一央で、DX戦略の専門家として多くのプロジェクトを手掛けてきた経歴を持っています。
本書は、自己の「強み」を見つけ、活かすための戦略やアイデアを提供するベストセラーの最新版です。著者は、自己理解の重要性や才能を「武器」として活用する方法を解説し、34の資質に基づく行動アイデアを提示しています。また、クリフトン・ストレングスというウェブテストを通じて、自分の強みを見える化する方法も紹介されています。全世界で3000万人以上が利用しているこのツールを活用し、自分自身や周囲の人々の才能を理解し、成長を促すことが目指されています。
自分の強み・弱みを知れるので一度やってみると面白いと思う。
最近は色々な診断が流行っていますが、こちらも自分の強みを知る良いきっかけになりました。ストレングス・ファインダーの診断結果が具体的で、今後の仕事や生活に活かせそうです。自分を見つめ直したい人におすすめしたい本です。
この書籍は、Webマーケティングの基本を理解できる内容で、人気のWebコンテンツにオリジナルの解説を加えています。目次には、SEO、Webデザイン、ライティング、SWOT分析、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディア運用など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者はWebライダーの松尾茂起と、イラストレーターの上野高史です。
Webマーケティングといえばこの書籍。ストーリ形式でWebマーケティングについて学べるのでサクサク読めてそれでいてWebマーケティングのエッセンスがギュッと詰まっている。それもそのはず超有名マーケターのWebライダー松尾氏が著者。Webマーケティングを学びはじめた初学者はまず手にとって欲しい書籍。ちなみにWebマーケティングの中でもかなりSEO・オウンドメディア運営にフォーカスしているので広告などについて学びたい人には向かない。
池上彰のベストセラーを漫画化した本で、コミュニケーションスキルを向上させる内容。目次には「伝える力」「相手の立場での伝え方」「聞く力」「褒める・叱る力」「文章力向上法」が含まれている。著者はジャーナリストの池上彰、漫画原作者の星井博文、漫画家のanco。
伊沢拓司が自身の「勉強法」を解説する書籍で、高校時代は成績が低迷していたが、東大受験を成功させた経験を基にした方法を紹介しています。勉強の効率を最大化するための「勉強の作法」を提唱し、受験生やビジネスマンに役立つ内容となっています。手描きの図解を用いて分かりやすく説明し、各教科の勉強法や暗記術も公開しています。全8章で構成され、受験の意義や成績の読み方、教科ごとの特徴などを掘り下げています。
この本では、メモが人生においてどれほど重要であるかが語られています。著者は、メモを通じて世界や自分を理解し、アイデアや夢を育む力を強調しています。メモは日常を変え、思考を深め、人生を豊かにする手段として位置づけられています。著者の前田裕二は、メモの魔力を活用することで人生や世界を変えることができると提唱しています。
メモの力で気づきを得る。メモを通じてアイデアや自己発見を深める本です。実践的なメモ術が紹介されていて、自分の考えを整理し、新たな視点を得られました。日常で役立つヒントが詰まっているので、一度試してみる価値ありです。
前田裕二氏の前作に感銘を受けたのでこちらも読んでみたが、個人的には期待外れ(期待値が高すぎたのかも)。前田氏と同じようにメモを取ることがハマる人もいればハマらない人もいると思う。個人的には紙でメモを取るよりも日常ではスマホのメモ機能やNotionにメモしておいて、ざっとアイデアをまとめたり整理したい時に時間をかけて紙に書く方が好きなタイプ。ただ人前でスマホを触ると相手に不快感を与えてしまう可能性があるので紙でメモを取るという姿勢は相手に好印象を与えるという意味で効果ありかもしれない。また、具体的な事象を抽象化して自分の環境に転化していくという思考プロセスは非常に勉強になった。
この本は「デザイン=楽しい」をテーマに、デザイナーの思考プロセスを豊富なビジュアルで解説します。内容は、編集とデザインの関係、デザイナーの必須ツール、デザインの基本要素(文字、言葉、色、写真、グラフ)などを扱っています。著者は株式会社コンセントのアートディレクター・デザイナーの筒井美希氏です。
デザイン全く分からない自分でもわかりやすく、デザインについて知るきっかけになりました!
デザインの基本的な考え方を視覚的にわかりやすく解説する一冊です。専門的な知識がなくても楽しめる内容で、初心者にも理解しやすく、具体的なデザイン例を豊富に掲載しています。デザインの意図や効果を実際の作品で確認できるため、デザインの背景にある理論を自然に学ぶことができます。視覚的に訴える構成が魅力で、デザイナー以外の読者にもおすすめです。
著者の鈴木光が、効率的な学びのメソッドを紹介する初著書『夢を叶えるための勉強法』。東京大学入試や司法試験予備試験を突破した経験を基に、定期テストや資格試験に役立つ勉強の基本を網羅。目次には、勉強目標の設定、問題解決の考え方、知識の定着、環境整備、結果の振り返り、科目別攻略法などが含まれ、特別コラムも収録されている。全ページにフルカラー口絵が付いている。
本書は、自己分析を通じて自分を知ることで、仕事やプライベートでの不安や悩みを解消し、充実した人生を送る方法を紹介しています。著者は、自分の強みや価値観を理解することで、適切な居場所や人間関係を見つけられると述べています。具体的なワークを通じて、自己分析をスムーズに行えるようになり、自信を持って前向きに生きる手助けをします。著者自身の経験から、強みを活かすことの重要性を強調しています。
本書は、勉強が嫌いな人に向けて、楽しく気軽に学ぶことの大切さを伝える入門書です。東大クイズ王・伊沢拓司が中心のメディア「QuizKnock」が、勉強をポジティブに捉え、自分のために学ぶことの楽しさを提案します。さまざまなワークシートやクイズを通じて、読者が「好き」を深め、学びを楽しむ方法を学ぶことができる内容です。勉強は他人に強制されるものではなく、自分の興味を追求する手段であることを強調しています。
この書籍は、「やりたいこと」を探すだけでは適職に出会えないと説き、他者に役立つ資質を見つけて活かす方法を解説しています。著者は、強みが社会的価値を生むためには「人の役に立つ」ことが重要だと強調し、ウェブテスト「コントリビファイ」を通じて自分の強みを科学的に特定する方法を提供しています。内容は「向いてる仕事」の定義や、人の役に立つ12の資質について詳述されています。
本書は、メンタリストDaiGoが自身の成功体験を基に、効率的な勉強法を初公開する内容です。彼は慶應義塾大学で人工知能を研究し、メンタリズムを日本に広めた後、ビジネスや学術の分野で活躍。累計300万部のベストセラーを持つ著者として、入学試験や資格試験に役立つ勉強法を提案します。内容は、やってはいけない勉強法や、効果的な学習テクニック、地頭を良くするためのトレーニングなど、多岐にわたります。
この本は、魚住りえによる「話し方改善」スキルの指南書で、特に「1日1分朗読」のメソッドに焦点を当てています。電話、プレゼン、会議など、さまざまな場面で役立つ話し方や声の出し方を学べる内容です。朗読を通じて得られる15の効果が紹介され、初心者でも実践できるテクニックや具体的な例文も提供されています。朗読を楽しむことで、コミュニケーション能力やストレス解消にもつながるとされています。
この書籍は、2000人以上の人生を逆転させてきた著者が、働く人々の願いを叶えるための「説得力」の重要性を説いています。著者は、ビジネスで成功するためには「魂からの説得力」が必要であり、単なる話し方や伝え方ではなく、自身の生き方が人を動かすと主張しています。内容は、「軸の定め方」「過去のさらけ出し」「行動による表現」「逆境の乗り越え方」を通じて、説得力を高める方法を探求しています。著者は自身の経験を基に、中小企業の経営コンサルタントとしての道を歩んでいます。
この書籍は、ビジネスや日常会話での効果的な説明力を向上させる方法を解説しています。著者は、説明力を高めるための練習法や具体的なテクニックを紹介し、知的な説明がどのように相手に影響を与えるかを探ります。目次では、説明力の基本、組み立て方、日常生活での実践方法、心を動かす応用技術が取り上げられています。著者は齋藤孝で、教育学やコミュニケーション論の専門家です。
本書は、独学の達人である読書猿が執筆した「勉強法の百科事典」で、ギリシア哲学から最新の論文までの知識を55の技法にまとめています。読書法や挫折克服法、時間の作り方など、独学を成功させるための具体的なアドバイスが提供されており、「自分を変えたい」と願うすべての人に向けた内容です。著者は、ブログを通じて知識を共有し続けています。
山口周さんの本はどれも外さない。その中でもこの本はいかにして独学を極めて知的戦闘能力を高めるかを学べる本。独学をする上でジャンルから選ぶと自分独自の洞察や示唆が生まれないので、そうすべきでない。むしろ自分で課題・イシューを立ててそれを解決する本をジャンル横断で読むべき、それこそ独学であるというのに感銘を受けた。どのように本から知識を吸収し自分の血肉として昇華するかが分かりやすく学べる
この書籍は、どんな場面でも恥ずかしくない語彙力と表現力を身につけるためのノートを提供します。内容は、普段の会話、お願い、言いづらいことの言い換え、気持ちの伝え方、メールや口癖の改善、会議での表現、訪問や宴会での言葉、季節の言葉など、多岐にわたります。著者は齋藤孝で、教育学やコミュニケーション論の専門家であり、多くの著書を持つベストセラー作家です。
『ドラゴン桜』の桜木先生が提案する、7日間で頭を良くする勉強法を紹介。各日のテーマは以下の通り:1日目「語彙力」、2日目「情報処理力」、3日目「質問力」、4日目「つなげる力」、5日目「分解力」、6日目「要約力」、7日目「問題作成力」。
本書は、スピーチや面接などで頻繁に使われる無意味な言葉「えーっと」「あー」などを「えーあー症候群」と定義し、その改善方法を科学的に解説します。著者は、これらの言葉を減らすことで説得力が増し、相手に伝わりやすくなると主張しています。内容は、フィラーの原因や心の状態、思考の整理、声の使い方、実践トレーニングなど多岐にわたり、短期間で改善できる方法を提供しています。著者はスピーチトレーナーとして多様な経験を持ち、実践的な指導を行っています。
本書は、若手エリートの間で人気の「FIRE」(経済的自立と早期退職を目指すライフスタイル)について、第一人者のクリスティー・シェンとブライス・リャンがその全貌を解説しています。30代で経済的自立を達成するための技術や戦略を網羅し、早期リタイアのメリットやデメリット、実践的なアドバイスを提供しています。著者は、FIREムーブメントに関する情報を発信するサイト「MILLENNIAL REVOLUTION」を運営しています。
本書は、トヨタ自動車の成功の要因としての「社内コミュニケーション術」に焦点を当てています。著者はトヨタでの経験を基に、無駄を省く会議術や本質思考、教育方法、人間関係の構築、配慮の重要性などを分析し、トヨタが大企業病に侵されずに成長し続ける理由を探ります。日本のビジネスパーソンにとって必読の内容です。
著者の平井孝志は、図を使って考えることが思考を深める理由を解説し、誰でも実践できるメソッドを体系化した書籍を提供しています。内容は、図を用いる基礎的な考え方から、具体的な図の型(ピラミッド、田の字、矢バネ、ループ)を使った実践方法までを含み、図で考えることで仕事や人生がより良くなることを示しています。著者は、MBAやPh.D.を持ち、外資系コンサルタントや大学教授としての豊富な経験を有しています。
本書は、非暴力コミュニケーション(NVC)の手法を通じて、対話を促進し暴力や対立を排除する方法を紹介しています。評価や決めつけを避け、自分の感情や必要を理解し、それを相手に伝えることで、より豊かな人間関係を築くことができます。NVCは、観察、感情の認識、必要の明確化、具体的な要求の4つの要素に基づいており、世界中で多くの人に読まれています。また、ビジネスシーンでも注目され、紛争解決の方法が新たに追加されています。著者はマーシャル・ローゼンバーグ氏で、NVCの提唱者です。
本書は、感動的で心を動かすプレゼンテーションの秘密を探るもので、著者であるナンシー・デュアルテが実践的な手法を紹介しています。内容は、聴衆の理解やストーリーの構築、記憶に残る伝え方など多岐にわたり、プレゼンの質を向上させるための具体的なアプローチが詰まっています。デュアルテはプレゼン制作の専門家であり、彼女の経験を基にしたノウハウが提供されています。
「ffs理論」に関するよくある質問
Q. 「ffs理論」の本を選ぶポイントは?
A. 「ffs理論」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「ffs理論」本は?
A. 当サイトのランキングでは『宇宙兄弟とFFS理論が教えてくれる あなたの知らないあなたの強み【自己診断ID付き】』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで51冊の中から厳選しています。
Q. 「ffs理論」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「ffs理論」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

























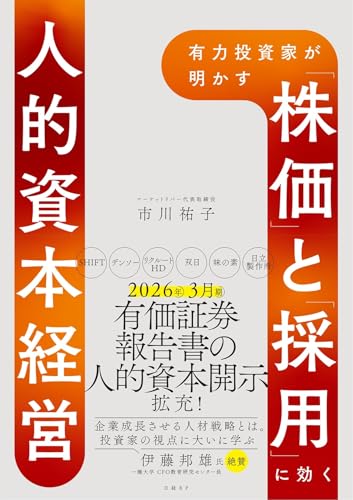
![『デザイン入門教室[特別講義] 確かな力を身に付けられる ~学び、考え、作る授業~ (Design&IDEA)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41YXUWBgsAL._SL500_.jpg)




































