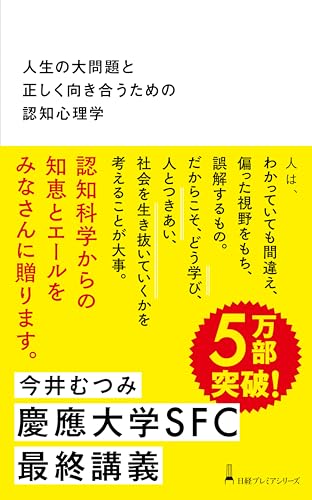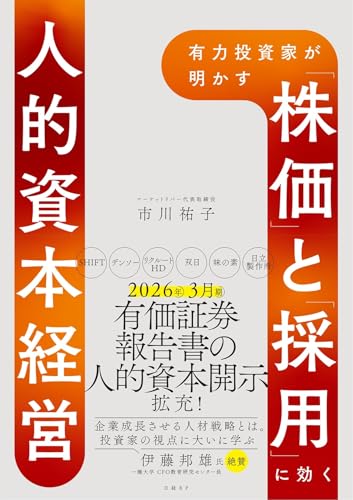【2025年】「思い込み」のおすすめ 本 168選!人気ランキング
- FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
- 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え
- 思い込みにとらわれない生き方 (一般書)
- サーチ・インサイド・ユアセルフ――仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法
- あなたの世界をガラリと変える 認知バイアスの教科書
- データ分析に必須の知識・考え方 認知バイアス入門 分析の全工程に発生するバイアス その背景・対処法まで完全網羅
- 「脳のクセ」に気づけば、見かたが変わる 認知バイアス大全
- 幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えII
- 外資系コンサルタントの企画力: 「考えるスイッチ」であなたの思い込みを覆す
- 人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学 (日経プレミアシリーズ)
本書『ファクトフルネス』は、データに基づいた世界の見方を提案し、誤った思い込みから解放されることの重要性を説いています。著者ハンス・ロスリングは、教育、貧困、環境、エネルギー、人口問題などのテーマを通じて、正しい世界の理解を促進します。2020年には多くのビジネス書ランキングで1位を獲得し、100万部以上の売上を記録。ビル・ゲイツやオバマ元大統領も絶賛し、特に教育機関での普及が進んでいます。クイズ形式で誤解を解消し、ファクトフルネスを実践する方法も紹介されています。
自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。
本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。
10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。
『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。
本書は、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)が人間関係に与える影響を探求し、それを克服する方法を提案する内容です。著者は、思い込みを認識し、相手を正しく理解することが多様性社会において重要であると強調しています。具体的には、家庭や職場での役割分担、女性の社会進出などに関連する偏見を取り上げ、思い込みにとらわれない生き方を促します。著者は昭和女子大学の学長であり、これまでに460万部以上の著作を持つ実績があります。
本書は、Googleの独自研修プログラム「サーチ・インサイド・ユアセルフ(SIY)」を通じて、楽しく創造的に働くためのマインドフルネスの実践方法を紹介しています。著者のチャディー・メンは、自己認識力や創造性を高める技法をユーモアを交えてわかりやすく説明し、ビジネスパーソンや入門者にとっての実践バイブルとしています。SIYは他の企業や大学でも採用されており、情動的知能を育むことが強調されています。
本書では、脳科学の観点から「認知バイアス」を解説し、日常生活における認識のズレや誤解のメカニズムを探ります。認知バイアスは人間関係や仕事、お金、健康に影響を与えますが、うまく活用することで幸せや成果を得ることも可能です。著者は新進気鋭の脳科学者で、読者が自分や他人を理解し、見える世界を変える手助けをします。
この書籍は、データ分析における認知バイアスや機械学習のバイアスについての理解を深めるためのガイドです。記憶や認識、判断に由来するバイアスの軽減策や、科学的因果関係の認定基準についても解説されています。各章では、バイアスの種類や対処法、ケーススタディを通じて、分析者が直面する課題とその解決策を学ぶことができます。
本書は、認知バイアスについて解説し、偏見や先入観が人間関係や組織、消費者行動、思想に与える影響を探ります。著者は、バイアスを理解し対処することで、より良い人間関係やビジネスを築く方法を提案しています。内容は、認知バイアスの種類とその対処法に分かれており、現代社会での教養として重要なテーマです。著者は名古屋大学の教授で、心理学の専門家です。
この本は、保険営業に転職した中年男性・修一が直面する困難な状況を描いています。彼は顧客の大量解約により金銭的・精神的に追い詰められ、家族の問題も抱えています。そんな時、運を「貯める」ことの重要性に気づく不思議なタクシーとの出会いがあります。著者は、努力が報われないことはないと伝え、運の使い方についての新たな視点を提供します。読者からは感動の声が寄せられ、自己成長や人生の意味を考えるきっかけとなっています。
時間に対する新たな視点が生まれる。人生の限られた時間をどう使うかについて考えさせられる一冊でした。時間を有効に使うだけでなく、無駄に見える時間も大切にする視点が新鮮で、日々の選択を見直すきっかけになりました。
限りある人生をいかに充実したものにするかについて学べる良書。仕事に追われていて時間がないビジネスパーソンに是非読んで欲しい。
悪意の有無に関係なく存在する偏見、バイアス。それがいかにして脳に刻まれ、他者に伝染し、ステレオタイプを形作っているかを知ることなしに人種差別を乗り越えることなどできない。米国の学校・企業・警察署の改革に努める心理学者が解く無意識の現実とは。 はじめに Ⅰ 私たちの目に映るもの 第1章 互いの見え方――認知とバイアス 認知の科学 人種のイメージング ひったくり犯の青年たち 第2章 何が育むのか――カテゴリー化とバイアス バイアスのメカニズム 「恐怖を感じる」 バイアスの伝達 Ⅱ 自らをどう見出すか 第3章 悪人とは?――警察とバイアス1 ティファニーと夕食を 科学のレンズ 第一幕 目に見える男 第二幕 実際よりも大きく 第三幕 人種の働き 第四幕 丸腰でも危険 第五幕 撃つか撃たないか 別れの時 第4章 黒人男性――警察とバイアス2 警察の反応 手続き的正義 不完全な盾 公園にいた無邪気な少年少女 第5章 自由な人の考え方――刑事司法とバイアス まだ自由とは言えない 事件が残した傷痕 まだまだ自由とは言えない 投獄された者 死に値する者 第6章 恐ろしい怪物――科学とバイアス 恐ろしい怪物の科学 非人間化の新科学 Ⅲ 抜け出すための道はあるか 第7章 ホームの快適さ――コミュニティとバイアス 分離された空間 汚染された人々 空間を吸収する 移住するということ 新たな場所でバイアスと闘う 第8章 厳しい教訓――教育とバイアス 共に歩く 迫りくる格差 人種問題を避けるということ バーニスの出世と帰還 第9章 シャーロッツビルの出来事――大学とバイアス 姿を示すということ 事件の余波 第10章 最後に得るもの、失うもの――ビジネスとバイアス トレーニングの効果 研修の先にあるもの 終わりに 謝辞 解説[高史明] 参考文献
中高生のほとんどは,心理学とはどういうものかを知らないが,いろんなイメージはもっている。高校の教室で行った大学教授の授業から,現代の心理学の姿を描く。「総合学習で学ぶ心のしくみとはたらき」と題した付録冊子付き。 日本では心理学が学校の教科になっていない。そのために,多くの中高生は心理学がどういうものかを知らずに,さまざまなイメージをえがいているのが現状だ。本書では,高校1年生のクラスで行なった大学教授の授業という形式で,現代の心理学の全体像とその姿をえがいていく。心理学の本当のおもしろさにふれられます。 1章 心理学で人の心が読める? 操れる? 1 心理学ってすごい? こわい? 2 人の心を読むことはできる? ウソ発見器はウソを見破れるか 心理カウンセラーの仕事 心理学の法則は統計的なもの 3 人の心を変えることはできる? 悪徳商法とカルト教団の手口 人間の心理的傾向がうまく利用されている 人が説得されやすいとき 4 質問の時間 2章 心理学ってうさんくさい? 1 心理学は占いのようなもの? 2 知能検査というもの ビネーの知能検査 知能検査のその後 知能検査の思い出 知能検査は信頼できるか――代表性と再現性 知能検査は役に立つか――診断力と予測力 3 性格検査というもの 類型論と特性論 質問紙による性格検査の作り方 投影法と作業検査法による性格検査 性格検査の有効性 4 質問の時間 3章 心理学は常識的なことばかり? 1 心のことなんて,もう知ってる? 2 心理学は何を研究するの? 意識と内観 心理実験――錯視を例に 心に代わって「行動」を研究する 無意識の存在と防衛機制 3 心理学の理論と方法って? 意識だけでは心のしくみはわからない 心理学では理論とデータが大切 学習意欲の出なくなったM君をどう理解するか 4 質問の時間 4章 心理学を学びたい人に 1 心理学にはどんな分野があるの? 2 心理学を学ぶには(1)――本を読む 3 心理学を学ぶには(2)――大学に行く 4 心理学を生かせる仕事は?
本書は、マッキンゼーが20年間のケーススタディとハーバード・ビジネス・レビューの記事を基に、組織を効果的に率いるための10の法則を提唱しています。デジタル化やグローバリゼーションに対応するためのマネジメント手法を解説し、意思決定の質やスピードを向上させる方法、競争力のある組織文化の構築、優れた人材の育成と定着について具体的な実践法を紹介しています。リーダーやマネジャーにとって必携の一冊です。
健常者の文脈に落とし込まれがちな障害者の芸術活動について、舞台に立つ障害者への取材を通して、多様な価値観のあり方を議論する。 不自由な身体でなぜ彼/彼女たちはと人前で表現活動をするのか。障害者のアートは無条件に賞賛されるべきものなのか。障害者の「表現する権利」に正面から取り組んだ注目作。 「健常者」と「障害者」、「排除」と「包摂」、「芸術」と「芸術でないもの」......不自由な身体を人前にさらしながら、彼/彼女らはさまざまな境界を越えてゆく。障害者による劇団やアート表現の現場を取材し、障害者の「生きる権利」と「表現する権利」を考えることで、今日の障害/障害者観に変革を迫る一冊。 はじめに 第1部 研究の背景と立場 第1章 研究の背景 1 障害者の表現活動の何が問題か? 2 先行研究・事例の概観 (1)「障害」と「文化」をめぐるいくつかのトピック (2) 日本における障害者の表現活動、その歴史的な展開 3 「福祉」「芸術」「療法」の融解 近年の新展開 (1) 福祉施設での「表現」の現在 かがやきキラキラ仕事館、たけし文化センター (2) 創造的なセラピスト 音楽療法を事例にとって (3) 野村誠 現代音楽と「老人ホーム」 (4) 小 括 第2章 障害者の芸術表現活動が抱える課題と問題提起 1 「障害」の立ち位置 障害学における当事者議論をもとに (1) 障害学とはどのような学問であったか (2) 障害の「他者化」にどのように立ち向かうか 平等派/差異派の議論をもとに 2 障害と芸術 精神科医から、芸術家から、福祉施設から (1) アウトサイダー・アート、アール・ブリュットの系譜 (2) 何が「アウトサイダー」か? (3) 福祉施設からの芸術表現 日本における「アウトサイダー・アート」「アール・ブリュット」小史 (4) 90年代以降の展開 3 アウトサイダー・アートと障害の他者化 (1) 障害者「自立支援」としての表現 (2) 日本での受容と原義との距離 (3) 人々がアウトサイダー・アートに希求するもの (4) 表現を通じた障害の「他者化」 4 関係性への視点 (1) アウトサイダー・アート市場への挑戦 (2) こぼれ落ちるものと「齟齬」 (3) 行為としての表現 アルス・ノヴァでの1日 (4) 欠落する「関係性」の視点の価値化に向けて 第2部 事例研究 第3章 「差異」と「共同」 マイノリマジョリテ・トラベル 1 公演《ななつの大罪》 2 エイブル・アート・ムーブメントとマイノリマジョリテ・トラベル (1) エイブル・アートとは (2) エイブル・アートの展開と批評 (3) マイノリマジョリテ・トラベルのコンセプトと活動の変遷 3 見世物小屋の「毒」 マイノリマジョリテ・トラベルとは何だったのか? (1) マイノリマジョリテ・トラベルの活動の意義 批評をもとに振り返る (2) 見世物小屋の「毒」 4 マイノリマジョリテ・トラベルは誰のもの? (1) マイノリマジョリテ・トラベルの共同制作物としての一面 (2) 障害者アートの範疇を超える「共同性」 5 マイノリマジョリテ・トラベルの意義 (1) マイノリマジョリテ・トラベルの意義とエイブル・アートの展開 (2) 活動の継続の困難さと、参加者たちの新たな活動の萌芽 第4章 「関わり」から生まれる表現 森田かずよ 1 義足と「歩く」こと 《アルクアシタ》 (1)《アルクアシタ》 (2) 自らの「リアル」を追求する 2 表現者としての萌芽 母親にとっての「障害」の受容 (1)「どうか娘が死にますように」から「あなたと私は別々の人間です」へ (2)「障害があるから余計に研ぎ澄まされる」 (3)「私、ダンス教室はじめるわ!」 3 伝え、向き合い、突き付ける 劇団「夢歩行虚構団」での7年間 (1) 障害ではなくいかに「伝わる」か (2) 自らと向き合う関係性 (3) 観客への「障害」の提示 (4) 夢歩行虚構団を支えるスタンスと変化 4 循環プロジェクト (1) 公演《≒2》と、プロジェクト開始の経緯 (2) イコールになりきれないイコール 循環プロジェクトの理念 (3) 向き合い、枷をはめ、しんどさをも抱きこむ 実際に起こった関係性 (4) 常に新しい気持ちで向き合う 森田が得たもの 5 小 括 第3部 分析と考察 第5章 「障害」「健常」再考 思考実験を通じて 1 異形の身体としての「障害」 2 2つの主体の転覆 ジャック・デリダの「歓待」の思想 (1)「歓待」の思想、その背景 (2)「条件付き歓待」「絶対的な歓待」 (3) 芸術を媒体とした「歓待」としての「襲撃」 (4) 一瞬の「絶対的歓待」を求めて 第6章 障害者の芸術表現活動が持つ多元的な価値 1 作品制作プロセスの中での関わり 「共同性」とその限界 (1)「共同性」とその限界 (2)「共犯性」、その概念モデル形成に向けて 2 「共犯」の孕む課題 アートプロジェクトの議論を援用して (1) 非専門家が介入する表現の場 (2) 共同の「ファシズム」「暴力性」 (3)「抑圧的寛容」としてのアートプロジェクト 3 「共犯性」から見える多元的な価値 (1) 3つの主体と、3つの芸術的価値 (2) 障害者との芸術表現活動の方途 (3)「共犯性」の概念モデル形成に向けて 4 本研究の今後の展望 補 章 アール・ブリュットの先へ おわりに 索 引
「手放しの法則」に基づく「セドナメソッド」は、感情を解放することで人生を変える方法を提案しています。著名人も実践しており、基本編では感情解放の手順や目標達成の方法、応用編では恐れや人間関係の改善、健康促進について説明されています。著者はセドナ・トレーニング協会を設立したヘイル・ドゥオスキン氏と、そのメソッドを日本に広めた安藤理氏、乾真由美氏です。
面接試験、人事査定など「評価」は上の立場から一方的に判定するというイメージがある。最初から基準が定められ、マニュアルに従っていればよいという印象すらある。 しかし公的な文化事業で補助金や助成金が投じられる委託事業、とくに文化事業では最初に目標を設定すること自体が困難だったり、長期の目的は変わらなくても短期的な目標が途中で変更されるということが少なくない。これらの場合手順に沿うだけでは十分な評価はできず、事業の企画運営と評価を切り離さず、相互に調整しながら弾力的に柔軟に進めていく必要がある。 本書は主に社会包摂につながる文化事業をテーマに、事業目的にかなう評価基準の導入から、具体的な評価の基礎と実践を多数の図解と実践事例の紹介により解説。アートを学ぶ学生、ホール・劇場運営者、自治体の文化事業担当者に最適、最強のガイドとなるだろう。 はじめに この本の構成 第1部 導入編 文化事業×社会包摂 1-1 社会包摂につながる芸術活動 芸術に対する二つの見方/文化政策の歴史/文化政策の役割/文化と社会包摂/社会包摂の翻訳/社会包摂につながる芸術活動/価値創造を通じた課題解決 1-2 活動から生まれること 創造/発表/鑑賞/交流/人材育成 1-3 取り組みの紹介 ・せんだいメディアテーク:「3がつ11にちをわすれないためにセンター」 ・アーツ前橋:表現の森「石坂亥士・山賀ざくろ×清水の会えいめい」 ・あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター):「光の音:影の音 耳だけで聞くものなのか」 ・可児市文化創造センターala:alaまち元気プロジェクト「スマイリングワークショップ」 ・京都国立近代美術館:「感覚をひらく 新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業」 ・NPO法人こえとことばとこころの部屋(ココルーム):「釜ヶ崎芸術大学」 ・豊中市:「世界のしょうない音楽」 ・NPO法人まる:「Lifemap」 ・那覇市若狭公民館:「パーラー公民館」 1-4 行政と現場のコミュニケーション 政策・事業立案/事業公募/事業実施/政策・事業評価 第2部 基礎編 社会に向き合う文化事業の評価 2-1 社会包摂を意識した文化事業の評価とは 何のための評価か/評価は測定ではない/目的と目標の違い/プロセス評価/アウトカム評価/事業報告/アドボカシー 2-2 評価をはじめる前に 誰が評価するのか?/何を評価するのか?/どのように評価するのか?/いつ評価するのか? 2-3 現場から学ぶ評価の知恵 1.事業関係者の意識の変化 落合千華 琉球フィルハーモニックオーケストラ:ゆいまーるミュージックプロジェクト「美らサウンズコンサート」 2.協働相手との関係づくり 岡部太郎 一般社団法人たんぽぽの家、近畿労働金庫:「ひと・アート・まち」プロジェクト 3.団体内部の人材育成 三浦宏樹 NPO法人BEPPU PROJECT:混浴温泉世界実行委員会事業 4.評価の活用とアドボカシー 吉本光宏 北九州芸術劇場(公益財団法人北九州市芸術振興財団):北九州芸術劇場の事業評価調査 5.心理学との連携による指標づくり 日下菜穂子 東京文化会館(公益財団法人東京都歴史文化財団):即興的音楽ワークショップ「音の砂場」 6.医学との連携による指標づくり 藤井昌彦 仙台富沢病院:演劇情動療法 2-4 評価をとおしたコミュニケーション 文化事業の評価と政策の関係性/評価の4つの場面におけるコミュニケーション 評価設計/指標検討/データ収集/結果の活用 第3部 シンポジウム編 現場の評価と行政の評価 現場の評価と行政の評価 1 文化事業における評価の現状と課題(大澤寅雄) 2 インタビュー調査から見えてきたこと(村谷つかさ) 3 評価への向き合い方に関する提案(中村美亜) 4 ディスカッション(片山正夫、源由理子、朝倉由希、大澤寅雄、中村美亜、村谷つかさ) 行政の評価とは?/参加型評価とは?/どうやって合意形成するか?/誰が評価指標を作るか?/価値観の違う人にどう伝えるか?/どうすれば行政は変わるのか? 第4部 実践編 価値を引き出す評価 4-1 文化事業ならではの評価 新たに生まれた価値を評価する/芸術活動の公共的価値を見定めよう/活動の価値が見える評価指標をつくろう!/対話の場面を意識して評価方法を選択しよう! 4-2 のぞいてみよう!評価のプロセス ももち文化センターのストーリー(福岡県) 4-3 4つのケーススタディ ・取手アートプロジェクトと應典院ピアレビュー評価 羽原康恵、五十殿彩子/熊倉純子、槇原彩 ・アーツコミッション・ヨコハマの伴走型事業改善評価 杉崎栄介 ・東京文化会館の独自の指標づくり 杉山幸代 ・可児市文化創造センターalaのSROI評価 落合千華、衛紀生 4-4「対話」からはじめる評価の一歩 「対話」の場を作る/誰と、どのような「対話」をするか/「対話」のポイントと工夫 ワークシートの活用法 おわりに
『「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる「繊細さん」の本』がマンガ化され、50万部のベストセラーとなりました。この本は、周囲の人の気分に敏感で、光や音に過敏な「繊細さん(HSP)」の27歳OLのストーリーを通じて、仕事や人間関係の悩みに対するアドバイスを提供します。元々はピッコマで連載された作品の書籍版です。
この書籍は、一流のプロフェッショナル365人からの知恵を集めた仕事のバイブルであり、仕事力と人間力を高める内容です。各月ごとに異なるテーマで、著名人の考えや座右の銘が紹介されています。著者は藤尾秀昭で、月刊誌『致知』の編集長を務めています。
この文章は、経済学者シュンペーターの「イノベーション」理論について紹介しています。シュンペーターは、単なるアイディアよりも既存の要素を組み合わせて新たな価値を生み出すことが重要だと説いており、スティーブ・ジョブズのiPhoneの成功がその例として挙げられています。シュンペーターの理論は、現代の経営者にとっても有用であり、変革は内から起こるべきであると強調しています。著者はシュンペーターの思想を学ぶことの重要性を訴えています。
本書は、20世紀の文豪フランツ・カフカの自虐的でネガティブな言葉を集めた名言集です。彼の日記や手紙からの引用を通じて、絶望感や弱音が満載ですが、思わず笑ったり勇気をもらったりする内容になっています。カフカの言葉は、彼自身の苦悩を反映しつつ、読者に元気を与える力を持っています。著者はカフカの翻訳や評論を行う頭木弘樹です。
日本軍がなぜ戦争に負けてしまったのかを分析し、それを元に日本の組織における問題点を浮き彫りにしている書籍。責任の所在の曖昧さと、臨機応変に対応できない官僚主義が蔓延した日本組織は危機的状況において力を発揮できない。少々歴史の話は冗長だが一読する価値のある書籍。
この書籍は選択理論を基に、自分らしさを発揮しつつ、強くしなやかな人間関係を築く方法を紹介しています。日々の小さな選択が人生に希望をもたらすことを示唆しており、ビジネス、教育、家庭、恋愛など多岐にわたる分野での応用が期待されています。著者は心理カウンセラーの渡辺奈都子氏で、リアリティセラピーを用いたカウンセリングや研修を行っています。
本書は、渋沢栄一や三菱、三井、住友の起業家たちが逆境を乗り越えた事例を通じて、どん底でもチャンスがあることを伝えています。歴史は繰り返され、経営の原則は変わらないため、過去の成功者から学ぶ意義があります。著者は、胆力、危機管理力、先見力を持つ11人の経営者のエピソードを通じて、現代のビジネスに役立つ知恵を提供しています。読者は彼らの失敗や苦難から危機突破力を学び、ビジネスのヒントを得ることができるでしょう。
この文章は、心理を読み解くための様々な視点を提供する書籍の目次を紹介しています。内容は、気持ちやタイプ、口癖や話題、行動や態度、外見、ビジネスシーン、恋愛における心理に関するものです。著者は心理学を専攻し、目白大学の教授である渋谷昌三です。
本書は、雑談に苦手意識を持つ人々に向けて、効果的な雑談力を身につけるための具体的なコツを紹介しています。雑談は友人との会話やビジネスの正式な会話とは異なる「第3の会話」であり、多くの人が失敗する原因を解説。著者は、コミュニケーションの達人が教える7つのルールや場面別のアドバイスを通じて、雑談をスムーズに行う方法を提供しています。具体的なNG例とOK例を示しながら、明日から使える実践的なテクニックを学べる内容です。
本書は、前作に続くベストセラーの第2弾で、心のクセを理解することでカルトや詐欺から身を守る方法を探ります。行動経済学、統計学、情報学の視点から60の認知バイアスを解説し、用語や事例、対処法を豊富なイラストと共に紹介しています。著者は高橋昌一郎で、論理学と科学哲学を専門とする教授です。
本書は、「無意識のバイアス」という概念を通じて、差別の問題に取り組む内容です。著者のジェシカ・ノーデルは、バイアスの理解から思考の書き換え、インクルーシブな環境の構築までを提案し、無意識のバイアスを克服する方法を探求します。著者は科学ライターであり、バイアスと差別に関する問題を長年扱ってきた実績があります。本書は多くの組織で活用され、注目を集めています。
本書は、生きづらさを感じる人々に向けて、考え方のクセやその根本的な理由を探る内容です。イライラしやすい、他人の目が気になる、自分を責めるといった特徴を持つ人々が、心の負担を軽減し、自分を取り戻す手助けをします。各章では完璧主義や他人への気遣い、自己の考え方の問題、不安や恐怖の根源について解説し、心のバランスを改善する方法も紹介しています。著者は心理カウンセラーのきい氏と精神科医のゆうきゆう氏で、実体験に基づくアドバイスが展開されています。
この書籍は、日本人が「ストレスフリーな生き方」を実現するための方法を紹介しています。著者は精神科医の樺沢紫苑で、3年間の研究を基に、ストレスや不安への対処法を科学的に解説しています。内容は人間関係、プライベート、仕事、健康、メンタルの5つのテーマに分かれ、実践的なノウハウや考え方を提供。ストレスを溜め込まず、夜にリセットすることの重要性が強調されています。著者は「几帳面でまじめな人ほどストレスを抱えやすい」とし、考え方を少し変えるだけで多くの悩みを軽減できると述べています。
ストレス要因の解決策がたっぷり詰まった1冊。日常的な悩みをカテゴリごとに分け、一つ一つ解決策が書かれているので読みやすい。過去の実験結果をもとに書かれているから説得力があるし、簡単に実践できるものが多いので良い!最近気持ちが晴れないなと思っている人におすすめ。私もこの本に助けられた人のうちの1人!
本書は、人気マンガ『宇宙兄弟』を通じて自分の強みを理解し、他人の個性を把握する方法を解説しています。著者は「FFS理論」を用いて、登場人物の心理や行動を分析し、自己理解、他者理解、組織理解の観点から具体的な事例を挙げています。読者は、自分に似たキャラクターを知ることで、強みを活かし、効果的なチーム作りを学ぶことができます。
箱を祀る霊能者と箱詰めにされた少女たちを巡る事件が、美少女転落事件とバラバラ殺人を結びつける。探偵・榎木津、文士・関口、刑事・木場が事件に関与し、京極堂の元へ向かう。果たして憑物は落とせるのか?日本推理作家協会賞受賞のミステリー作品、妖怪シリーズ第2弾。
この文章は、著者ひろゆきが影響力を持つために必要なテクニックを明かす内容を紹介しています。彼は「バイアス」や「同調圧力」、「承認欲求」などの概念を通じて、人々の思考や行動の仕組みを解説しています。ひろゆきは、インターネット掲示板「2ちゃんねる」の創設者であり、影響力のある人物として知られています。
本書は、心理カウンセラー・根本裕幸氏が「罪悪感」という感情の仕組みとその対処法を探る内容です。罪悪感は自分の幸せを妨げる要因であり、多くの人が自覚せずに抱えています。著者は、罪悪感を理解し、自分を許すことで生きやすくなる方法を提案。読者からは感動的な反響が寄せられ、自分を癒す手助けとなる一冊とされています。
この書籍は、「アンラーン」という概念を通じて、過去の学びや思い込みを手放し、新たな成長を促す技術を紹介しています。アンラーンは、学びの効率を高めるために必要なプロセスであり、特に変化に対応するために重要です。具体的には、固定化した思考を解きほぐし、日々の小さなアンラーンを習慣化する方法が提案されています。また、アンラーンを阻む壁を理解し、それを乗り越えるためのヒントも提供されています。最終的には、アンラーンを人生やキャリアの武器として活用することが強調されています。
未知の物質によって太陽に異常が生じ、地球が氷河期に突入する中、男が宇宙に飛び立ち人類を救うミッションに挑む。『火星の人』のウィアーが描く、地球滅亡の危機をテーマにした極限のエンターテインメント。
この書籍は、敏感すぎて自己肯定感に悩む人々に向けて、著者が7日間のステップで問題解決の方法を提供します。内容は、自己意識の向上、過去の振り返り、家族関係の再評価、自己肯定感の強化、人間関係の構築、敏感さを強みに変えること、そして自分の目標を実現することに焦点を当てています。著者は心理カウンセラーの根本裕幸氏で、豊富な経験を持つ専門家です。
百合は他人の目を気にして生きていたが、単純なミスで会社を辞め、離島のホテルに旅立つ。そこで出会った無神経なバーテン坂崎とドイツ人マティアスとともに、ホテルの図書室で写真を探すうちに、百合は自分の心が徐々に解放されていくのを感じる。著者は西加奈子。
いわゆる成功哲学的なよくある書籍ではなくて、宵越しの銭は持たず人生を最高に生き抜く価値観を植え付けてくれる書籍。人を選ぶ書籍ではあると思うが、自分自身の理想の生き方に思いっきりあてはまる内容で何度も読み返したい書籍。現代人にはこの生き方が合うと思っているので何かに縛られて辛そうにしていたり、思考停止でお金を稼いで日々四苦八苦したりしている人達に読んで欲しい。
『思考のトラップ』の著者デイヴィッド・マクレイニーの新作は、認知バイアスの罠を解明し、人間の思考パターンの誤りを明らかにする内容です。人は必ずしも賢くなく、一般的な意見や感情に基づく行動には多くの誤解があることを示しています。具体的な思考改善方法も提案されており、読者に新たな視点を提供します。目次には様々なバイアスや誤謬が列挙されています。
読みながら行動や考えを改められ、少しずつ自身に変化を感じられる素晴らしい書籍です!
誰もが知る名著なので一度は目を通しておくべきだが、内容は冗長で個人的にはあまりはまらなかった。重要度×緊急度のマトリクスの話が一番重要で、そこだけ理解しておけばいい気がする。緊急度は低いが重要度が高いタスクになるべく長期的な視点で取り組めるようになるべき。
学生の頃読んで衝撃を受けた書籍。退屈な日々で何か自分を変えたいと思っている若者には是非読んで本書の課題をぜひ実行して欲しい。読むだけでモチベーションを上げて終わってしまってはだめ。
老舗洋菓子チェーンのエリアマネジャーに抜擢された28歳の前島由香里は、思うようにいかず悩んでいる。そんな彼女の前にアドラー心理学の幽霊が現れ、成長を促すアドバイスを提供する。同期や部下との交流を通じて、由香里は自己理解を深め、様々な人間関係を学びながら成長していく。著者はアドラー心理学を基にしたカウンセリングを行う岩井俊憲。
本書は「アンコンシャス・バイアス」(無意識の偏見)について解説し、特にリーダーがこのバイアスに気づき、対処することの重要性を強調しています。リーダーが無意識の思い込みでメンバーの能力を決めつけることで、成長機会が失われ、組織の業績が低下することが示されています。多様性が求められる現代において、リーダーは自らのバイアスを認識し、チームがバイアスに振り回されないようにすることが、組織の未来を変える鍵であると述べています。著者は、リーダーシップ研修を通じて多くのリーダーを育成してきた専門家です。
図書館で拾い読みしたのですが、アンコンシャス・バイアスの意味は、これで合ってますか?最初はアンコンシャス(無意識)といっていながら、いつも間にか、無意識ではなく、普通の偏見の意味にすり替わっているように思います。無意識に持っているバイアスとは、本来著者の指しているようなものではないはずです。
古くから読みつがれる名著です。ただ正直冗長な部分も多いので、全部読みきる意味はあまりないかと思います。この本はナポレオンヒルという人が多くの成功者にインタビューする中で見えてきた成功者に共通する行動様式をまとめたものです。古い本ですが、今でも使える普遍的な内容になっています。正直書籍のタイトルにこの本が言いたいことのエッセンスは詰まっているのですが、目標を決めてそれを強烈に意識することが大事です。そして目標を決めるだけではなくそれを実際にどう実現するかのプロセスを考えて日々のアクションに落とし込んで愚直に実行し続けることが大事なのです。この本では取り上げられていませんが、目標の粒度としては自分がどうなっていたいか?どういう状態でいたいか?という観点で決めるのが望ましいです。例えば、お金をいくら稼げるようになりたい、資産をいくら持っていたいというのも目標になりえますが、お金はあくまで手段です。それよりもそれを達成した先に自分がどういう生活をしていたいか?どうなっていたいか?と考えることが大事。お金を目標にするのもいいですがあまり幸せな未来は待っていないでしょう。それよりも、自分になりたい姿を強烈に想像し、そこにめがけて日々行動することで必ずそれを実現することができるはず。イーロン・マスクのように多くの資産そして世界を救う大きなビジョンを持ちながら、毎日周りからの批判を浴びながら死ぬほど働く人生がいいのか?ある程度の資産を持ち、ある程度稼ぎ、時間と場所にとらわれず自由に働く人生がいいのか?なりたい姿をイメージしましょう!そしてこの本では、浪費と投資と消費の話も取り上げられています。浪費とは無駄なことにお金や時間を使うこと、投資は未来に消費は現在にお金や時間を使うこと。お金だけじゃなくて時間の概念も念頭においておくことが大事です。浪費は極力避け、目標達成するための投資もしくは今を楽しむための消費にお金や時間を使うことが大事。浪費と消費の違いは難しいですが、目的達成のモチベーションを上げるために週末に友達と遊ぶのは消費と考えてよいと思います。暇だからとりあえずパチンコに行ったり、1人でダラダラYoutubeを見るのは浪費です。浪費をしている限り、あなたはいつまで経っても目標を達成することはできません。また、この本ではとりあえず行動に移すことも大事と言っています。なりたい姿が決まったら、それを実際に体現している人に話を聞きに行くなどすぐに行動に移せることはどんどん行動に移しましょう!
「バビロンいちの大金持ち」を漫画化したこの本は、100年読み継がれるお金の知識をわかりやすく紹介しています。お金儲けのテクニックではなく、資産を増やし充実した人生を送る方法を教えます。現代人に向けた普遍的な知恵が描かれ、子どもから大人まで幅広い読者に支持されています。漫画形式により、楽しくスムーズに読み進められ、感動的なストーリーが展開されます。
漫画で分かりやすく読めるお金にまつわる話。現代にも通用するお金に関する根本的な考え方が学べる。将来のお金に不安がある人は、まずこの書籍から読んでみると良いと思う。
ウィスコンシン大学マディソン校の科学・工学分野女性リーダーシップ研究所(WISELI)が、ジェンダーに関する偏見を中心とした「無意識のバイアス」を克服するべく、スタッフ採用ワークショップのため開発したテキストの翻訳書。 ご挨拶 WISELIから日本の仲間たちへのご挨拶 このワークショップについて 背景 ワークショップデザインの要素 ワークショップの成果 ワークショップの前提条件 トレーナーのスキル 参加者の募集 ジェンダーとリーダーシップについての潜在連合テスト(IAT) ワークショップの準備と運営 女性の退職状況を示す組織のデータ ワークショップの構成要素 受講前の基準値を測る潜在連合テスト(IAT) イントロダクション モジュール1:習慣としての潜在的バイアス モジュール2:職場における潜在的バイアスの特定 モジュール3:潜在的バイアスの影響を減らす戦略 行動へのコミットメントに向けた活動 スライドと発表者用講演ノート イントロダクション モジュール1:習慣としての潜在的バイアス 無意図的なバイアスの根源を理解する モジュール2:職場における潜在的バイアスの特定 モジュール3:潜在的バイアスによる影響を減らす戦略 よくある質問と難しい議論の例 参考文献一覧 付録A:参加者用資料 付録B:プレゼンター用資料 訳者あとがき
この書籍は、無意識のバイアスについて探求し、偏見や思い込みがどのように生まれるかを解説しています。著者は、バイアスが人間の防御反応であり、意識されにくいことを示しながら、実例とデータを用いて理解を深めることを目的としています。内容は、バイアスのパターンやその影響について詳しく説明されており、読者がフラットな視点を持つための手助けを提供します。著者は、無意識のバイアス研究の権威であり、組織変革の専門家です。
この本は、心のクセやノイズを理解し、それを解消する方法を提供する内容です。著者は8000人の悩みを解決してきたカウンセラーで、自己納得感を高めることの重要性を説いています。読者は、自分の心のノイズを14タイプに分類し、日常生活でのノイズに気づく方法や、1分でできるエクササイズを通じて心を軽くする技術を学べます。メンタルノイズを手放すことで、より幸せな生活が送れるようになることを目指しています。
本書『リーダーのための【最新】認知バイアスの科学』は、リーダーが知っておくべき認知バイアスについて解説しています。バイアスは意思決定に影響を及ぼし、組織全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、リーダーはその理解が必要です。具体的には、30種類のバイアスや実際の不祥事を通じて、意思決定の罠とその対策を提案しています。著者の藤田政博は心理学の専門家で、意思決定の科学をビジネスに応用する方法を探求しています。
この書籍は、ストーリーを通じて心理テクニックを学ぶことができる内容です。目次には、日常生活や友人、対人関係、仕事、ビジネス、恋愛、自分を変える方法など、様々な心理学の応用が紹介されています。著者は精神科医のゆうきゆうで、心理学に関する多くの活動を行っています。
自分の強み・弱みを知れるので一度やってみると面白いと思う。
最近は色々な診断が流行っていますが、こちらも自分の強みを知る良いきっかけになりました。ストレングス・ファインダーの診断結果が具体的で、今後の仕事や生活に活かせそうです。自分を見つめ直したい人におすすめしたい本です。
伊良部総合病院の神経科を舞台に、様々な悩みを抱える患者たちが訪れる中、担当医・伊良部一郎の独特な性格が描かれる。彼は一風変わった精神科医であり、病める者を癒す名医なのか、トンデモ医なのか。直木賞受賞作家・奥田英朗による人気シリーズの第2弾。
この書籍は、怒りを効果的にコントロールする技術を解説しています。著者は日本アンガーマネジメント協会の安藤俊介で、怒りに関する誤解やその原因、感情の伝え方、怒りのコントロール方法などをイラストを交えて説明しています。現代社会におけるパワハラやモラハラの問題を背景に、怒りをスマートに扱うことの重要性が強調されています。
この書籍では、「サイコパス脳」と心理学を駆使して交渉や人間関係を成功に導く方法を紹介しています。著者は、3つの基本原則と27の心理テクニックを通じて、相手を操る技術や自分の感情を制御する方法を解説。具体的には、プレゼンや営業術、人間関係の構築、メンタル習慣の改善に焦点を当てています。著者は心理戦略コンサルタントであり、MENSAの会員でもあります。
本書は、著者がジェンダー・ハラスメントの実態を分析し、その防止策を提案する内容です。性役割に基づくハラスメントが職場で広く発生している一方で、加害者や被害者がその認識を持たない場合が多いことを指摘しています。具体的な事例や研修内容を通じて、偏見に気づき対策を講じることができるように構成されています。また、著者は「アンコンシャス・バイアス」に着目し、差別解消に向けた研修プログラムを開発しています。ジェンダー平等に取り組む企業にとって必読の一冊です。
本書は「認知バイアス」の理解を深めるために、心理学の実験や研究を基に解説しています。単にバイアスを排除するのではなく、思い込みを突き止め、脱却し、活用する方法についても詳しく紹介しています。全5章で構成され、認知バイアスの本質や思考プロセス、実践的なアプローチが網羅されています。著者は鈴木敏昭氏で、自己意識心理学を専門としています。
大親分ヤハウェの大活躍と大虐殺、対する人類の苦悩と希望はどのように表現されてきたのか。やくざ風物語と作品鑑賞で読みとく。 西洋美術の大テーマ、旧約聖書。大親分ヤハウェの大活躍と大虐殺、対する人類の苦悩と希望はどのように表現されてきたのか。やくざ風物語と作品鑑賞で読みとく。 西洋美術の大テーマ、旧約聖書。大親分ヤハウェの大活躍と大虐殺、対する人類の苦悩と希望はどのように表現されてきたのか。やくざ風物語と作品鑑賞で読みとく。
この本は、平本あきおのコーチングメソッドを山崎拓巳が解説したもので、メジャーリーガーやオリンピック選手などの能力を120%引き出す技術を紹介しています。重要な3要素として「同じ目線」「見える化」「臨場感」を挙げ、感情と身体の動きが行動に繋がることを強調しています。具体的なセッションの事例を通じて、読者がコーチングの技術を体感できる内容となっています。
この本は、育児のハウツーではなく、子どもにイライラするお母さんの心を和らげる「魔法の言葉」を紹介しています。イライラの原因は子どもの行動ではなく、お母さん自身の「自己否定」にあるとし、状況別にイライラを和らげる方法を提案。著者は子育てママ専門のカウンセラーで、自己肯定感を高める言葉が多く含まれています。マンガも収録されており、母親と子どもが共に幸せになる心の仕組みを学ぶ内容です。
この書籍は、日常生活で誰もが経験する認知バイアスを6つのテーマ(記憶、推定、選択、信念、因果、真偽)に分けて、イラストを用いて解説しています。著者たちは心理学の専門家であり、それぞれ異なる分野において教育や研究を行っています。
囚われの心で 勇者の帰還 晩鐘 白い花 光の雨 遺影画家 天国にいちばん近い村 さかのぼる民 饒舌な傭兵 英雄 「殻」の中の住人 さらば、相棒 グレオ爺さんの話 七十五年目の蝉時雨 母、帰る 殺戮将軍の悲劇 挽歌の島 嘘つきの少女 コトばあさんのパン 命の順位 天のつぶて 忘れないでね 弱き者からの手紙 待ち人、来りて はずれくじ 道しるべ 老兵士の遺言 語り部サミィ ハンナの旅立ち 壁の向こうに 永遠の孤独
この本は、世界最高峰の経営コンサルティング会社で教えられている問題解決の考え方を、中高生向けに身近なストーリーとイラストを交えて解説しています。問題を小さく分けて考えることで解決策が見えてくることを学び、自ら考え行動する力を育む内容です。目次では、問題解決能力の習得、原因の見極め、目標設定と達成方法についての章が設けられています。著者は、経済を専攻した後にマッキンゼーでの経験を持つ渡辺健介氏です。
この本は、心の苦しみを軽減するための43の処方箋を提供しています。「足りない」と感じる心を手放すことで、より楽に生きる方法を探ります。内容は、自分の欠点を見つめ直し、自信を持ち、他人からの影響を防ぎ、不安を解消し、本来の自分を取り戻すための具体的なアドバイスが含まれています。
親分イエスと十二人の舎弟をめぐる新約聖書の物語を、西洋美術はどのように描いてきたのか。やくざ風物語と作品鑑賞で読みとく。 カリスマ親分イエスと十二人の舎弟をめぐる悲喜劇、そして神の王国。新約聖書の物語を西洋美術はどのように描いてきたのか。やくざ風物語と作品鑑賞で読みとく。 カリスマ親分イエスと十二人の舎弟をめぐる悲喜劇、そして神の王国。新約聖書の物語を西洋美術はどのように描いてきたのか。やくざ風物語と作品鑑賞で読みとく。
この本は、セールスやマーケティングにおける顧客心理の重要性を30の法則で解説しています。著者は、テレビ通販での成功経験を基に、心理的トリガーを用いて営業成績を向上させる方法を示しています。具体的なエピソードを通じて、複雑な心理を理解しやすく伝え、読者が実践できる内容となっています。メンタリストDaiGo氏や世界一のセールスマン、ジョー・ジラード氏も推薦しており、実践的な知識を得るために読む価値がある一冊です。
この本は、行動力やコミュニケーション能力を高め、ネガティブな感情をコントロールし、迅速な決断を促す方法を紹介しています。1日15分の書く習慣を通じて、思考の制約を外し、人生を加速させる技術を学べます。目次では、思考の現実化、目標設定、行動継続の秘訣、自認力の重要性、効果的な学び方について解説されています。著者は自立型人材育成コンサルタントの横川裕之氏です。
本書は、コロンビア大学の社会心理学者ハイディ・グラントが、助けを求めることの難しさとその心理的背景を解説する実践的なガイドです。頼み事をする際の気まずさや誤解を探り、効果的な頼み方のテクニックを紹介します。内容は三部構成で、頼み事が難しい理由、良い頼み方と悪い頼み方、そして人を動かす力について述べています。
この書籍は、韓国で25万部を超えるベストセラーとなった人生エッセイで、読者に自分らしい生き方を見つける勇気を与える内容です。著者は、努力や成功の現実、自己認識の重要性、一人の時間の必要性、挑戦する権利について考察しています。疲れた日常から抜け出し、心の癒しを求める人々に向けたメッセージが詰まった一冊で、韓国の著名人にも支持されています。
著者もりえみは、恋愛や人間関係、お金などの悩みは実は同じ根本的な「傷」に起因していると述べています。彼女は、過去の誤解に気づくことで、どんな悩みも解消できると主張しています。本書では、悩みのメカニズムや、占いを通じて多くの人々の問題を解決してきた経験を共有しています。目次には、悩みの本質やお金に関する重要な話が含まれています。
この書籍は、企画、プレゼン、セールス、恋愛に役立つ45の心理術を紹介しています。著者の神岡真司は、相手の好感度を操作したり、行動を自在に操るテクニックを解説し、職場や恋愛における心理戦術を展開しています。心理学理論に基づいたコミュニケーションスキル向上の方法を学ぶことで、誰でも心理テクニックを使えるようになります。
この書籍は「認知バイアス」を活用し、相手の態度を変えたり、興味を引いたり、心を動かす方法を紹介しています。実生活に役立つスキルを学ぶことで、好感度や評価をアップさせ、交渉を有利に進めることができます。内容は魅力的に見せる方法から、男女の認知バイアス、攻めと守りの戦略まで多岐にわたります。著者はビジネス心理研究家の神岡真司です。
この文章は、ピーター・F・ドラッカーの著作の目次と著者情報を紹介しています。目次では、成果を上げるための能力や時間管理、貢献の方法、人の強みの活用、重要なことへの集中、意思決定の重要性などがテーマとして挙げられています。著者のドラッカーは、20世紀から21世紀にかけての著名な経営思想家で、マネジメントの主要な概念を発展させた人物です。また、上田惇生はドラッカーの友人であり、彼の作品を翻訳した経歴を持つ学者です。
『YES! 60 secrets from the science of persuasion』は、科学的な説得技術に関するベストセラーの最新版で、承諾を得る秘訣が50から60に増加しました。具体的な技法が豊富に紹介され、ビジネスや日常生活で即実践できる内容となっています。新たに加わった実例や改善された訳文により、さらに読みやすくなっています。著者たちは影響力の専門家で、説得に関する科学的根拠に基づいた秘訣を提供し、交渉やプレゼンテーション、マーケティングに役立つ情報が満載です。
『7つの習慣』の超入門書は、成功と幸せを手に入れる方法をストーリーと授業形式で学べる内容です。主要な習慣として、主体的であること、終わりを思い描くこと、最優先事項を優先すること、Win-Winを考えることなどが紹介されています。
この書籍は、占い師や霊能者が用いる「コールドリーディング」のテクニックをビジネスに活用する方法を解説しています。内容は、相手のタイプを理解すること、初対面での効果的なコミュニケーション技術、トラブルをチャンスに変える考え方、そして自己成長を促すプログラムについて触れています。著者はセラピストの石井裕之で、企業向けの講演やセミナーを通じてコミュニケーション技術の向上を支援しています。
この本は、ホスピス医が3500人以上の患者を看取った経験を基に、人生を振り返り、後悔のない生き方を考えるきっかけを提供するものです。著者は「もしあと1年で人生が終わるとしたら?」という問いを提示し、読者に自分の価値観や大切なものを見つめ直すよう促します。内容は、人間関係や仕事、人生の楽しみ方に焦点を当て、より良い生き方を追求するための17の提案が含まれています。
この書籍では、成功する営業に必要なスキルとして、トークに頼らず観察力や判断力を活用し、行動力を持ってチャレンジを増やし、説得力を高め、忍耐力で現状を変える方法が提案されています。著者はメンタリストDaiGoで、企業コンサルタントや作家としても活動しています。
デール・カーネギーの『人を動かす』は、1936年の初版以来、約40年ぶりに大改訂された公式本で、人間関係における「30原則」を実例を交えて解説しています。内容は、「人を動かす三原則」、「人に好かれる六原則」、「人を説得する十二原則」、「人を変える九原則」、および「幸福な家庭をつくる七原則」に分かれており、深い人間洞察とヒューマニズムに基づいています。この書は自己啓発書の原点とされ、心を動かす行動や自己変革を促す感動的な内容です。