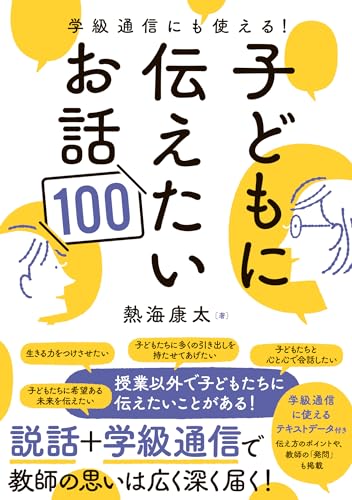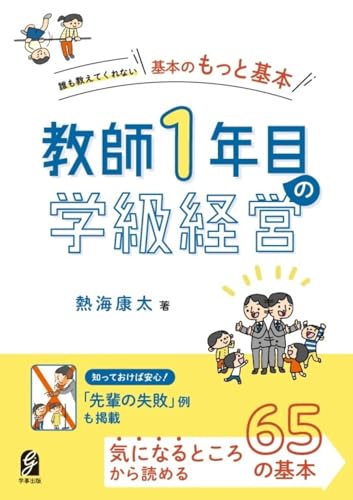【2025年】「学級経営」のおすすめ 本 152選!人気ランキング
- 新版 子供を動かす法則 (学芸みらい教育新書 2)
- イラストで見る 全活動・全行事の学級経営のすべて 小学校1年
- 信頼感で子どもとつながる学級づくり 協働を引き出す教師のリーダーシップ 小学校編 (学級を最高のチームにする極意)
- 学級経営の心得―担任の不安が自信に変わる 150のメソッド
- 先生が知っておきたい 「仕事」のデザイン 教師1年目から1年間の見通しがもてる思考法
- クラス会議で子どもが変わる: アドラー心理学でポジティブ学級づくり
- クラス全員が熱心に取り組む! 漢字指導法 ―学習活動アイデア&指導技術―
- 指導力のある学級担任がやっているたったひとつのこと 真の指導力とリーダーシップを求めるあなたに (学級経営力向上シリーズ)
- どの子も輝く教室のつくり方
- Neo classroom 学級づくりの新時代
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづけるスーパー名著!新卒の教師でもすぐに子供を動かせるようになる「法則」。 第1章 子供を動かす原理原則編(子供を動かす法則(群れとして動かす場合)-一つの法則と五つの補則 子供を動かす原則(組織として動かす場合)-三つの原則と九つの技能 新卒教師の教室は、なぜ混乱するか 「いじめ」の構造を、まず破壊せよ! 「プロの目」は、修業によって培われる 存在感が実感できてこそ子供は動く) 第2章 子供を動かす実践編(厳しく「教える」だけが動かす方法ではない 朝会に全校児童を集合させる 応援団の子供たちを動かす 指導方法を工夫して子供を動かす やるべきことを一人一人に示せ-卒業式よびかけの練習)
『板書シリーズ』の学級経営版が登場し、1年生の担任向けに一年間の行事や活動を解説した内容です。子どもたちが安心して学校生活を楽しめるよう、心構えや実践例を提供しています。特に4月の重要性を強調し、学級経営の計画的な進行をサポートする内容が盛り込まれています。初めての担任や不安を抱える先生に最適な一冊です。
この本は、著者の宮澤悠維が10年間の教師経験を基に学級経営のエッセンスをまとめたもので、150の基本的な心得を紹介しています。学級経営に悩む教師たちに向けて、心構え、原則、技法の三つの視点から実践的なアドバイスを提供し、何度でも読み返すことで学び直せる内容となっています。著者は、学級満足度を高めるためのノウハウを広めることを目指しています。
本書は、教師1年目から効果的に働くための仕事術を紹介しています。学級づくりや日々の働き方を考えるための思考法や、仕事に追われないための3つのステップ(ビジョンの明確化、多様なアイデアの提示、実行の継続)を提案。内容は、仕事のデザイン、学級の1日・1年の計画、時間を生み出すタスクデザインなど多岐にわたります。著者は15年間の公立小学校教諭を経て、オルタナティブスクールで活動する青山雄太氏です。
本書は、子どもが主体的に漢字を学ぶための新しい指導システムを提案しています。受け身の学習から脱却し、自立した学習者として成長できるようにすることが目的です。内容は、漢字指導の方法や効果的な学習活動のアイデアを紹介し、全員が漢字を定着させるためのシステムを解説しています。著者は教育者であり、数々の教育賞を受賞しています。
この書籍は、教師が教室でのリーダーシップを発揮し、子どもたちを効果的に導くための指導力の原理をまとめています。内容は、指導力のある教師の基本的な原則、信頼を得るためのスキル、成功するクラスの特徴、そして指導力を高めるために必要な資質について詳述しています。著者は、上越教育大学の教授であり、アドラー心理学を取り入れた学級経営の専門家です。
本書は、日本型教育の終焉と新たな「令和型学級づくり」について論じています。主要なキーワードは「秩序」「遊び」「自己選択」であり、教師は学級の「変数」としての役割を果たすべきと提案しています。著者は、教育現場の変化に対応するための学級経営の方法を解説し、教師力の向上を目指します。困難な教育環境における信頼関係の構築や、柔軟な学級運営の重要性も強調されています。教育現場の変化に不安を感じている人に向けた内容です。
先生や子どもたちがファシリテーターになると授業がとても楽しくなる。クラスが成長する「信頼ベース」の授業の進め方を紹介。 教師も子どももファシリテーターとなるクラスではお互いの信頼に支えられ授業をつくっていく。第1~第5までのステップに分け、小学校国語をはじめ、社会、理科、算数など著者のほか各地の授業事例を紹介しながら提案する。 先生や子どもたちがファシリテーターになると、教室に豊かな言語活動が育まれ、授業がとても楽しくなります。 子どもやクラスが成長する「信頼ベース」の授業の進め方を小学校国語、算数の授業事例などを用いて紹介します。 カラー口絵「信頼ベースの授業の進め方」 はじめに 取り扱い説明書 信頼ベースの授業 5つのステップ表 信頼ベースのクラスとは ●岩瀬直樹の授業 ①教科書に「拍手が起こる」国語 ②手を伸ばせば「物語」のある教室 ③学びの中核は対話 ④言語活動が加速するホワイトボード・ミーティング ⑤子どもたちがつくり始める学びのメインストリーム ⑥遊ぶように学び、学ぶように遊ぶ 基本的な準備物 ●信頼ベースの授業コンセプト ①信頼ベースの授業 5つのステップ 1.教室に豊かな言語活動の環境を育みます 2.信頼ベースの授業──3つの成長チャレンジと5つのステップ 3.子どもたちと先生は3つの成長にチャレンジします 4.6つの技術で学びの環境をつくります 5.特に会社活動で、子どもたちの表情が変わります ②プログラムデザイン「授業を進める6つのポイント」 1.一斉授業とファシリテーション型授業 2.学びのフレームと学びのサイクル 3.単元と授業のプログラムデザイン 4.ホワイトボード・ミーティングで「プログラムデザイン会議」 5.授業を進める6つのポイント ①学びのゴールと価値のインストラクションを共有 ②全体の流れ(見通し)と進め方、評価基準の共有 ③活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) ④観察とカンファランス、レクチャーの繰り返し ACT1 観察とカンファランスを練習しよう! ⑤学びの成果共有と価値のフィードバック ⑥振り返り ③授業でついやってしまう、よくある失敗 ACT2 シートントンキャンペーン ACT3 ハイタッチバリエーション ④信頼ベース × ○○の提案 信頼ベース × 協同学習……阿部隆幸さん ●言葉や態度を翻訳する「子ども理解」の技術を磨く ①「子ども理解」の技術を磨こう 1.心の体力が冷えると強く、激しくなる問題行動 2.不安な気持ちを翻訳して、安定的に受け止めます 3.愛情確認行動の対象は、特別の契約を結んだ相手です 4.承認欲求行動はクラスなど不特定多数が対象になります 5.状況が厳しいときほど、価値のフィードバックが大事です ②学級崩壊前後の取り組み方 1.学級崩壊前後の提案 2.担任がメンタルダウンしたときの介入方法の例 ③自分も友達も、授業で成長するクラス 1.何気ない毎日に、物語や成長が積み重なります 2.満たされた公平性と対等性の上に成り立つ多様性 3.学びの多様性が子どもたちの個性を引き出します 4.一緒に練習をしていきましょう! ACT4 教職員のためのファシリテーター度 10のチェックシート ACT5 ファシリテーターのかかわりスキル10か条 ●信頼ベースの授業 第1ステップ ①振り返りジャーナル ②絵本の対話型読み聞かせ ③会社活動 ④教室リフォームプロジェクト ⑤ミニホワイトボード ACT6 ○×クイズ ACT7 教室のあちこちで、ミニホワイトボードで対話 ミニホワイトボードの実践……石川晋さん ⑥プロジェクト・アドベンチャー プロジェクト・アドベンチャーの実践……甲斐崎博史さん ⑦クラス目標決定 ●信頼ベースの授業 第2ステップ ①オープン・クエスチョンの練習 ②ペアで聴きながらホワイトボードに書く 1.教室に多様な「承認し合う関係」を育みます 2.最初はミニホワイトボードからスタートして進化しよう! 3.ペアで聴きながら書く効果はスゴイ! 4.大事な約束「言いたくないことは、言わなくていい」 5.「聴きながら書く」に慣れてきたら、授業に活用します ③意見発表にチャレンジ「『今の自分』を話します」(小学4年国語/東京書籍) 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 2.全体の流れ(見通し)と進め方、評価基準の共有 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い)──振り返りまでの様子 ④わたしの構成要素 ⑤好きなおかしベスト5 ●信頼ベースの授業 第3ステップ ホワイトボード・ミーティング活用例 ①「学級新聞を作ろう」(小学4年国語/教育出版) 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 2.全体の流れ(見通し)と進め方、評価基準の共有 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) 4.観察とカンファランス、レクチャーの繰り返し 5.学びの成果共有と価値のフィードバック 6.振り返り ●信頼ベースの授業 第4ステップ~第5ステップ 1.「学びのサイクル」でいろんな教科が豊かになります 2.学びのフォーメーションと3つの成長チャレンジが連動します 3.カンファランスとレクチャーの充実が学び合いを促進します ①社会「江戸の文化と新しい学問」(小学6年/東京書籍) ②理科の進め方 ③算数の進め方 1.算数は積み重ねの教科です 2.チャレンジの環境設定をします 3.「構成的」から「非構成的」な学びのフォーメーションへ ④算数「小数のかけ算とわり算を考えよう」より(小学4年/東京書籍) ⑤算数「三角形のなかまを調べよう」(小学3年/東京書籍) 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 子どもたちとつくる価値のインストラクション……加藤健さん 2.めざそう!三角形マスター「三角形のなかまを調べよう」 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) ⑥算数「図形の角を調べよう」(図形の角)(小学5年/東京書籍)授業案の一例 1.学びのゴールと価値のインストラクションを共有 2.単元の見通しと評価基準 3.活動とドキドキワクワクのチャレンジ(学び合い) 4.観察とカンファランス、レクチャーの繰り返し 5.学びの成果共有と価値のフィードバック 6.振り返り ⑦子どもたちが「自分の学び」をデザインする自主学習ノート 自主学習ノートの進め方……伊垣尚人さん ⑧第5ステップのクラスの様子 主な参考文献 おわりに
日本のすべての教師に勇気と自信を与えつづける永遠の名著!技術があれば授業がうまくなり、子供たちは学校が好きになる。 第1章 授業の原則(趣意説明の原則 一時一事の原則 ほか) 第2章 教師の技量(子供に好かれる教師 子供が教わりたい教師 ほか) 第3章 授業の腕を上げる法則(根拠をもって実態をつかめ 教師の技量を向上させる常識的方法 ほか) 第4章 新しい教育文化の創造(「授業分析・授業解説」の力を付ける 教師の共通問題への挑戦 ほか)
この書籍は、教師が子どもたちに温かいメッセージを伝えることで学級の士気を高め、クラスを育てるための「トーク」の重要性を説いています。内容は、学級を育てるためのポイントや具体的なトーク例を60種類紹介しており、教師が言葉を通じて子どもと向き合う方法を提案しています。著者は岩手県の小学校で勤務する古舘良純氏で、道徳教育に関する実績があります。
この書籍は、中学校の学級経営において生徒が多様なリーダーシップを発揮し、自治的な集団を形成する方法を解説しています。リーダーシップの6つのタイプや、育成のポイント、NG事例を通じて、生徒同士の協力を促進する支援方法を紹介しています。著者は、教育における実績が豊富な川端裕介氏です。
この書籍は、5分でできる遊びを通じてクラスの雰囲気を改善し、子どもたちのつながりを深める方法を紹介しています。新学期のアイスブレイクや授業中の集中力を高める遊び、教科に関連した楽しいアクティビティが豊富に掲載されています。どの学年でも適用可能で、ペアやグループ、全体で楽しめる内容です。著者は教育現場での経験を持つ教師たちです。
「けテぶれ」学習法を用いた授業の導入と進め方を解説した本です。この方法では、子どもが自分で学びを計画・実行し、自らの成長を促します。内容は、授業の導入方法や子どもへの対応法、具体的な実践例などが含まれています。著者は兵庫県の公立小学校教員の葛原祥太で、過去の著作も成功を収めています。
この書籍は、仕事の本質や「いい仕事」が生まれる過程、そしてそれを「自分の仕事」にするために必要な要素について探求しています。著者は八木保や柳宗理、パタゴニア社など、様々な成功事例を訪ねて記録を残し、多様化する働き方に対する指針を提供しています。また、文庫化にあたり10年後のインタビューも追加されています。著者は西村佳哲で、建築設計を経てデザインレーベル「リビングワールド」を代表しています。
この書籍は、看護、教育、福祉などの対人関係専門職における実践、学び、研究の位置づけを解説しています。著者は省察的実践や成人学習理論に基づき、実践に役立つ事例やコラムを豊富に掲載。実践に悩む人や教育・研修担当者、大学院進学希望者におすすめの一冊です。
本書は、学校教育におけるICT(情報通信技術)の活用について、教師や生徒がそれを教具や文具として利用できる新たな段階に入ったことを背景に、授業づくりや臨床心理学、諸外国の事例など多角的な視点からその可能性と課題を探ります。著者は京都大学の教授で、教育のICT化を進めるための知見を提供し、読者にとっての有益な情報源となることを目指しています。
この書籍は、教師が子どもとの「ちょうどいい距離感」を築くための対話の技術を紹介しています。子どもの成長において教師の言葉が持つ影響を重視し、子どものニーズや保護者の期待を理解し、効果的にコミュニケーションを図る方法を提案しています。内容は、子どもの「欲しい」を感じ取る方法、ニーズを創出する技術、対話力の基本、教師自身の心構え、状況に応じた即興力について構成されています。著者は教育現場での経験を活かし、国内外での教育支援活動にも取り組んでいます。
この書籍は、正解のない時代に必要な「生きる力」を育むための子供向け哲学書です。内容は「自分」「社会」「学校」「人」「学び」の5章に分かれ、自己成長や社会の構築、人間関係、学びの重要性について考察しています。著者の工藤勇一は教育改革を推進してきた校長で、先の見えない時代をしなやかに生き抜くための知恵を提供しています。
本書は、文部科学省の国立教育政策研究所が発行した「キャリア・パスポート」の活用事例を10のリーフレットとしてまとめ、キャリア教育に関する調査報告書の抜粋も含まれています。キャリア教育の理解を深め、組織的な推進を促すことを目的としています。内容は、キャリア・パスポートの定義や教育現場での活用方法、自身の理解を深める手法など、多岐にわたります。また、著者はキャリア・パスポートを通じて児童生徒が自分の可能性を認識することの重要性を強調しています。
この書籍は、日本の教育の未来について全ての関係者が考えるべきだと提起しています。内容は、過酷な勤務実態やブラック校則、働き方改革など、教育現場の問題を取り上げています。著者の西村祐二は、教師としての経験を基に、教育の改善に向けた活動を行っており、労働問題や校則についての発信もしています。
この書籍は、公教育の目的を市民としての対話力を育むことに置き、学校文化の変革を提言しています。具体的には、自由の概念や共生社会の実例を通じて、異なる他者と共に生きる力を育む学校の必要性を論じています。各章では、教育の自由、管理から信任への文化のシフト、そして公教育の構造転換について議論されています。著者には、教育学の専門家や国際的な経験を持つ研究者が含まれています。
この書籍は、従来の一斉教育から個々の子どもに合わせた教育への転換を提案しています。著者は、東京都杉並区での取り組みを通じて、教育の目的を「自立」と「共生」と定義し、すべての人に学びの機会を提供する重要性を強調しています。具体的には、多様性を尊重した学びや協働を促進する人材育成、応答性のある教育施設、支援と共治を重視した行財政の必要性を論じています。全教育関係者に向けた新しい教育の指針を示す内容です。
西川純先生の新しい学級経営本では、中学校・高校における理想的な学級経営と、生徒の幸せを実現するための教師の役割について探求しています。内容は、「学び合い」の理論、学級崩壊への対処法、成功する学級の目標設定、そして未来社会での幸せな生き方についての考察が含まれています。教師は協力的な環境を作り、生徒が共に学び成長できるクラスを目指すべきだと強調しています。
この文章は、アフターコロナおよびウィズコロナの時代における生徒指導と生活指導の変革について述べています。著者は、生徒指導の「足並みバイアス」から脱却し、よりスリムで合理的なアプローチを提案しています。内容は6つの章から成り、力による制圧や形式的な指導を見直し、理想的な生徒指導の実現を目指す内容です。著者の渡辺道治は教育現場での豊富な経験を持つ教員で、国際教育支援にも積極的に関わっています。
本書では、子どもたちに伝えたいメッセージを含む100の物語を紹介しています。目的は、生きる力や希望、豊かな経験を提供し、心の交流を促進することです。各物語にはテキストデータが付属し、教師がアレンジして活用できるようになっています。内容は、発問や注意事項を含む6つのパートで構成されており、学級通信にも役立つ情報が提供されています。教師の思いを効果的に伝えるためのガイドとなっています。
この書籍は、中学校国語科における「主体的に学習に取り組む態度」の指導と評価に関するポイントを詳しく解説しています。領域や学年別に単元指導計画や評価事例が収録されており、ワークシートやノートの記述例などの実物資料も提供されています。著者は兵庫教育大学の教授、吉川芳則氏です。
新学習指導要領の実施に伴い、中学校向けの「板書」シリーズが新たに刊行されました。各教科の専門家が監修・編集し、授業づくりのポイントをわかりやすくまとめています。
この書籍は、子どもたちの学びを支えるために教師が持つべき技術について考察しています。内容は、「支え方」、「決める」、「聴く」、「拾う」、「見取る」、「つなぐ」、「伝える」、「任せる」などの技術に焦点を当てています。著者は若松俊介で、教育現場での実践を通じて「子どもが生きる」ことをテーマに研究を行っています。
一人一台端末時代にネット・リテラシーを確実に身につける授業づくりの豊富なプランを低学年、中学年、高学年ごとに提案する。 一人一台端末時代にネット・リテラシーを確実に身につける授業づくりの豊富なプランを低学年、中学年、高学年ごとに提案する。 一人一台端末が推進される今、問われているのはデジタル・テクノロジーを積極的に活用する知識とスキルをもつ人間(デジタル・シティズンシップ)の育成である。アメリカ、北欧など情報教育先進国の取り組みを多数、紹介。 子供たち一人一人が情報発信を日常的に行うようになった現在、個人情報、学校や家でPCを使う時のルール、ネット上のコミュニケーション、チャットやSNSへの投稿の仕方、ネットいじめ、ニュースを正確に読み解く力、等々、メディア/ネット・リテラシーを確実に身につける授業づくりの豊富なプランを低学年、中学年、高学年ごとに提案する。 コピーして授業でそのまま使えるシート付き。 第1章 1人1台端末時代に必要なデジタル・シティズンシップの教育授業とは? 第2章 道徳教科書で創る、デジタル・シティズンシップの授業プラン 第3章 動画を正確に読み取る能力を身につけ、フェイクにだまされない子を育てる 第4章 動画読解で切り拓く、メディア・リテラシーの授業プラン 第5章 ネットモラル検索やデジタル・インテリジェンスを取り入れた授業づくり
この文章は、教育の目的を子どもたちのためにあると強調し、教育委員会の仕事がその理念に基づくべきであると述べています。著名な教育者や教授たちが、教育の変革や未来の価値について考える重要性を指摘し、具体的な取り組みとして、公立学校の改善策や学びの選択肢の拡充、専門学校の改革、図書館のリニューアルなどが紹介されています。これらの施策は、子どもたちの意欲向上や不登校の減少を目指しています。
この書籍は、若手教員が活躍できる学校を作るためのリーダーシップや環境づくりについて述べています。指示や命令ではなく、問いかけやヒントを通じて若手を尊重し、対等な関係を築くことが重要です。また、教職員全員が活躍できる「働きやすい学校」を目指し、モチベーション管理やケアリングの重要性を強調しています。著者の住田昌治は、学校の組織マネジメントや教育環境の改善に取り組んできた経験を持つ教育者です。
吉野源三郎の名作「君たちはどう生きるか」が初のマンガ化され、80年経った今も多くの人々に支持されています。物語は、主人公コペル君と叔父さんが人間としての生き方を探求する姿を描き、いじめや貧困、格差などのテーマに真摯に向き合っています。このマンガ版は、原作のメッセージを保ちながら、読者に人生を見つめ直すきっかけを提供する一冊です。
この本は、生成AI、特にChatGPTが教師の仕事や教育に与える影響を解説しています。具体的な活用法として、授業案の作成、アウトプットの準備、文書の校正など、多様な事例を紹介。基本的な使い方から応用編まで、誰でも実践できる内容が盛り込まれています。著者は京都府の公立小学校教諭で、教育の生産性改革を推進しています。
教師が子ども達を信頼して力を引き出し、共に最高のクラスをつくるための入門書。学級経営に効果的なファシリテーション力の技を紹介 教師が子ども達を信頼し力を引き出すためにはファシリテーション力が必要。どんな学級をめざし、どうかかわり、学び合うのか。最高のクラスをつくる効果的具体的な技を紹介する。学級経営に悩む教師に必読の入門シリーズ1冊目 教師が子ども達を信頼し力を引き出すためにはファシリテーション力が必要。どんな学級をめざし、どうかかわり、学び合うのか。最高のクラスをつくる効果的具体的な技を紹介する。学級経営に悩む教師に必読の入門シリーズ1冊目 はじめに─幸せな子ども時代のために 「信頼ベースのクラス」のある1日 1.子どもの力を信じて引き出す先生=ファシリテーター ①「心の体力」を温めるエンパワメントなクラス ②冷えた心は、まず温める ③子どもたちの学び合う関係性を育み、温める ④権利と権利の対立を乗り越える力とチームワーク ⑤人権尊重スキルとしてのファシリテーション ⑥一斉授業の特徴 ⑦聴き合う関係を育むファシリテ-ション ⑧両輪が支える学び ⑨子ども時代に幸せな「体験的な学び」を積み重ねる ⑩ゴールに向けたスモールステップを刻む 2.ファシリテーターのかかわり10か条 第1条 クラスはチーム「1年後には、こうなりたい」。―ゴールを子どもたちと共有します 第2条 クラスや学びのオーナー(当事者)は子どもたち―先生もその一員です 第3条 主語はボクたち、私たち。―「やらせる」「させる」ではなく「一緒にやろう」 第4条 心の体力を温める。学び合うプロセスを育む―信頼ベースのクラスづくり 第5条 温める言葉:冷やす言葉=4:1―コミュニケーションのバランスを心がけます 第6条 好意的な関心の態度が基本スタンスです―それも「相手にとって」が、肝心です 第7条 体験的な学びを大切にする。―スモールステップでゴールをめざします 第8条 承認と共感に支えられた自己選択、自己決定。―質問の技で子どもに寄り添います 第9条 失敗もする。感情にも流される―それを大切な糧にします 第10条 ひとりでがんばりすぎない。―仕事を楽しむ!学び続けます 3.ファシリテーションの技を磨く 技1.インストラクション(説明) 技2.クエスチョン(質問) 技3.アセスメント(評価) 技4.フォーメーション(隊形) 技5.グラフィック&ソニフィケーション(可視化力&可聴化) 公開! イワセンの教室掲示!・・・4年生の巻 4.最初の1週間を丁寧につくろう ①シンプルに「幸せになりたい」気持ちがモチベーション ②丁寧にプロセスをつくる ③温かい学びを積み重ねる ④見通しを立てて取り組む ⑤やりやすいところから始める 公開! イワセンの教室リフォーム 5.1週間後の「クラス目標」のつくり方 ①授業や学級活動もゴールに向かうアクティビティ ②クラス目標を育てることでチームが育つ ③クラスの様子をアセスメントする時間 ④子どもたちの言葉でつくる ⑤子どもたちが自立した学び手に ⑥学級崩壊を経験した子どもたちのために 主な参考文献 おわりに
この書籍は、基本的な操作から応用まで、教育現場でのCanvaの活用法を3つのステップで解説しています。第1章では教師向けの使い方、第2章では子どもたちが使うためのステップ、第3章では授業での活用方法について具体的な事例が紹介されています。著者は青森県の公立小学校教諭で、プログラミング教育に関する専門家です。
クラスが信頼関係で結ばれるためのツールとして「学級通信」はかなり役立つ。その実例を実際配られた学級通信をもとに詳しく解説。 クラスが信頼関係で結ばれるためのツールとして「学級通信」はかなり役立つ。その実例を実際配られた学級通信をもとに詳しく解説。 ①教師として生徒から信頼され、②生徒同士が信頼し助け合い、③クラスが知的な集団になるという目標のためのツールとして「学級通信」は大変役に立つ。その実例を実際配られた学級通信をもとに詳しく解説。 4月―混沌緊張期に学級を組織する鉄則 5月―小集団成立期も「増やしたいことは褒める」が原則 6月―問題行動続発の6月には説教ではなく語りを増やそう 7月―夏休み明けを見据えた一学期の締めくくり方 …etc
話題の「まんがで知る教師の学び」に続く新シリーズスタート! 教育書の枠を超え、未来に向かって生きる全ての日本人が少なからず抱く問題意識をあらためて掘り起こし、投げかけます。 いまこの国で行われつつある「教育改革」が目指すものとは何か? 受験と部活動に明け暮れる中学校と時代に取り残される地域社会。 働き方も生き方も新たな局面を迎えたいま、学校と社会全体が向かうべき方向とは――。 教師(元小学校教頭)である著者が実感を込めて描くリアル・ストーリーです。 1分で読める! 水先案内的コラム「未来の社会を考えるビジネス書」では課題解決のための参考図書を紹介。 第1章 部活動と教育課程――教育課程とは何か 第2章 学習指導要領――社会に開かれた教育課程 第3章 新しい時代に求められる資質・能力――学習の基盤となる資質・能力 第4章 社会の変化――学び続ける力 第5章 学ぶ意義の明確化――なぜ学び、どういった力が身に付くのか 第6章 学習者の視点――教える側から学習する側へ 第7章 学習評価の充実――相互評価と自己評価 第8章 問題発見・解決能力――持続可能な社会づくりの担い手を育む
本書は、不安定で協働が苦手な教室に「つながり」を取り戻すための具体策を示した一冊です。子どもたちの内面を分析し、具体的なアクションやアクティビティをイラストでわかりやすく紹介しています。目次には、対等・安全な教室の基盤作りや、他者意識の醸成、関わりの量の増加など、様々な戦略が含まれています。著者の佐橋慶彦は、名古屋市の公立小学校で教育に従事し、学級経営や子ども目線のアプローチを研究しています。
学級づくりの最強アイテム「学級通信」で、教師と固い絆で結ばれた生徒同士が集団として動く実例などを、実際に配られたもので解説。 学級づくりの最強アイテム「学級通信」で生徒へ情熱を伝えるトークや、教師と固い絆で結ばれた生徒同士が集団として動く実例など、実際に配られた学級通信のテキストで解説。 学級づくりの最強アイテム「学級通信」で生徒へ情熱を伝えるトークや、教師と固い絆で結ばれた生徒同士が集団として動く実例など、実際に配られた学級通信のテキストで解説。 11月―この社会を生き抜くために習慣化しよう 12月―リップサービス無しの三者面談 1月―何でもない朝にゴミを拾いながら登校する中学生 2月―中学生時代の長谷川を越える行動を 3月―再会を誓って
この書籍は、算数授業のさまざまな要素を網羅しており、効果的な授業を行うための方法や工夫について解説しています。内容は、授業の準備や進行方法、子どもの思考を引き出すための課題提示、話し合いや発表の工夫、ノート指導や板書の重要性、教科書の扱い方、テストの意義、能動的な学習態度の育成など多岐にわたります。著者は新潟県出身の教育者で、算数教育において豊富な経験を持つ専門家です。
「宮沢賢治」の名作10話を収録した童話集で、小学生から大人まで楽しめる内容。代表作「注文の多い料理店」「セロひきのゴーシュ」「よだかの星」などが含まれ、賢治の美しい世界を詩情豊かに描いている。巻末には解説と写真付きの「宮沢賢治」文学の世界が掲載されており、漢字にはふりがなが付いている。大判ソフトカバーで、何度でも読み返せる一冊。
教育上特別な支援を必要とする児童のため学級づくりのポイントを紹介。保護者との協力の仕方、子どもが落ち着く教室の作り方など。 教育上特別な支援を必要とする児童のため学級づくりのポイントを紹介。保護者との協力の仕方、子どもが落ち着く教室の作り方、正しい行動を定着させる教師のスキル、優れた教材・教具など。 教育上特別な支援を必要とする児童のため学級づくりのポイントを紹介。保護者との協力の仕方、子どもが落ち着く教室の作り方、正しい行動を定着させる教師のスキル、優れた教材・教具など。 第1章 特別支援学級にこそ必要な向山型指導 第2章 正しい行動を定着させる教師のスキル 第3章 教室の力が生み出す支援学級のドラマ 第4章 保護者への情報提供者としての教師の役割 第5章 優れた教師の行為は優れた技術が支える 第6章 子どもが落ち着くプロの教室 第7章 子どもを伸ばす優れた教材・教具 第8章 この目で見た!参観者が分析する小野学級 第9章 学校の中の当たり前や常識を疑ってみる
ホリエモンの本は基本的にとりあえず行動しろよ!恐れるなよ!ということを言っているがこの本もご多分に漏れずそんな内容。ホリエモンの刑務所に居た時の話も語られ一旦全てを失った状態から這い上がってきたホリエモンの凄さに感銘を受けた。読めばモチベーションが上がるが行動しないと意味無し。
自分の強み・弱みを知れるので一度やってみると面白いと思う。
最近は色々な診断が流行っていますが、こちらも自分の強みを知る良いきっかけになりました。ストレングス・ファインダーの診断結果が具体的で、今後の仕事や生活に活かせそうです。自分を見つめ直したい人におすすめしたい本です。
この書籍は、算数授業を変えるための14の「しかけ」を紹介し、それぞれに5つの事例を提供しています。授業を通じて子どもたちの学びを深める方法を探る内容で、具体的な事例を通じて実践的なアイデアを提供します。著者は北海道教育大学附属札幌小学校の教諭、瀧ヶ平悠史氏です。
この書籍は、新任やキャリアの浅い教師向けに学級経営の基本を65項目紹介しています。特に、忙しい4月に役立つ内容で、各テーマは2ページで簡潔にまとめられています。先輩教師の失敗例も交え、実践的なヒントを提供。教師が抱える不安を解消し、学級経営のスキルを向上させるための強力なサポートとなる一冊です。
美しい自然のなか、両親を亡くした5歳の少年は祖父母の愛情に包まれてインディアンのライフ・スタイルと精神性を学んでゆく。優しさと痛みとユーモアにあふれたこの物語は、きわめて素朴な語り口ながら、魂の最深部からの共感を呼び覚ましてくれる。 『リトル・トリー』を分かち合う喜び 1 ぼくの名はリトル・トリー 2 母なる大地(モ・ノ・ラー)とチェロキーのおきて 3 壁に揺れる影 4 赤狐スリック 5 理解と愛 6 祖父母の昔話 7 サツマイモ・パイ 8 ぼくの秘密の場所 9 危険な商売 10 クリスチャンにだまされる 11 はだしの女の子 12 ガラガラ蛇 13 夢と土くれ 14 山頂の一夜 15 ウィロー・ジョージ 16 教会の人々 17 黄色いコート 18 山を降りる 19 天狼星(ドッグ・スター) 20 家へ帰る 21 遠い旅路の歌 リトル・トリー讃歌 宮内勝典 フォレスト・カーターと『リトル・トリー』 訳者あとがき
本書は、世阿弥の「風姿花伝」に基づき、教師の授業実践と学びのあり方を探求します。著者の佐藤学氏は、授業技術を指南するのではなく、教師の「学びの思想」と「身体技法」を伝えることを目指しています。内容は、教師としての成長や創造的な授業技法、実践例を通じた教師の役割についての考察が含まれています。佐藤氏は教育界で高く評価されている専門家です。
この書籍は、子どもとの信頼関係を築く方法や、学習支援、トラブル解決のアプローチを紹介しており、子どもに寄り添った関わり方を増やすことができる内容です。著者の佐橋慶彦は名古屋市立公立小学校で11年間教職に従事し、教育実践に関する研究と実践を行っています。
学級、学校が大変な時は子どもの状態が見えなくなりがち。 荒れパターンをを知り、学級崩壊に陥らないための応援処方… 学級、学校が大変な時は子どもの状態が見えなくなりがち。 荒れパターンをを知り、学級崩壊に陥らないための応援処方箋! 学級、学校が大変な時は子どもの状態が見えなくなりがち。 荒れパターンをを知り、学級崩壊に陥らないための応援処方箋! 1. 荒れの原因と学年特有の荒れパターンを探り、対策を立てる 2. 初任、5年目前後の荒れ、荒れパターンと防御策 3. 荒れを防ぐ授業、対応、システム、心構えを知ろう 4. 荒れに速攻有効アイテム&小技 5. フォローする立場からみる 〜荒れに対する支援でやるべきこと、やってはいけないこと〜
現代人は時間に追われ、本来の生き方を忘れてしまっている。時間を奪う「時間泥棒」に立ち向かう少女モモが、「時間の国」で時間の真の意味を探る異色のファンタジー作品。小学5・6年生以上向け。
脳科学・神経科学の進展や動機づけ研究の発展,さらに文化的多様性やICT等といった切り口から、人の「学び」の謎に迫る。 教育界に大きなインパクトを与えた『How People Learn(邦題:授業を変える)』から20年。この間に明らかになってきた研究知見に基づき再構成された待望の最新版。脳科学・神経科学の進展や動機づけ研究の発展,さらに文化的多様性やICT等といった多様な切り口から,人の「学び」の謎に迫る。 [原書]National Academies Of Sciences, Engineering, And Medicine (2018). How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures, National Academies Press. 学びはダイナミックないとなみであり、越境する科学である。 人はどこでどのように何を学ぶのか。本書は、全米科学アカデミー、医学アカデミー、工学アカデミーの総力を挙げ、脳科学と教育テクノロジーの最新の知識を盛り込んで編集された。前著『授業を変える――認知心理学のさらなる挑戦』と併読すれば、学習科学の全貌の最先端を知ることができるだろう。 ―――佐藤 学(東京大学名誉教授) 全米科学・工学・医学アカデミーについて 全米科学・工学・医学アカデミーの成果および活動について How People Learn II:The Science and Practice of Learning委員会 委員名簿 行動・認知・知覚科学委員会 委員名簿 科学教育委員会 委員名簿 謝 辞 ▶要 旨 Chapter1 導 入 ▶委員会への任務 (1)『HPLI』の貢献 (2)任務の解釈 (3)任務に取り組むためのエビデンスの収集 ▶エビデンスの取り扱い ▶本報告書のガイド Chapter2 文脈と文化 ▶学習の文化的性質 (1)文化を定義する (2)学習と発達における文化の役割 (3)社会的活動としての学習 ▶文化,生物学的特徴,そして文脈のダイナミックな相互作用 (1)社会的および情動的な影響 (2)物理的な影響 ①栄養/②睡眠/③運動/④環境中の有害物質 ▶結 論 Chapter3 学習のタイプと発達していく脳 ▶学習のタイプ (1)3つの学習シナリオ (2)学習の基本的なタイプ ①習慣の形成と条件づけ/②観察学習/③暗黙的なパターン学習/ ④知覚・運動学習/⑤事実の学習/⑥推論による学習 (3)学習タイプの統合 ▶学習と脳 (1)出生前期と生涯にわたる脳の発達と成熟 (2)学習に対応した脳の適応 ①神経組織の共有と再利用/②新しい要件への“チューニング”/ ③適応のための時間枠の変化 (3)生涯を通じ学習に関連して脳内が変化することのエビデンス ▶結 論 Chapter4 学習を支えるプロセス ▶学習の組織化 (1)実行機能 (2)学習の自己調整 ▶記 憶 (1)記憶の再構築 (2)ワーキングメモリと長期記憶 ①ワーキングメモリ/②長期記憶 (3)学習時のエピソードの記憶 ▶結 論 Chapter5 知識と推論 ▶知識ベースの構築 ▶知識と熟達化 (1)熟達化の利点 (2)知識の自然な副作用としてのバイアス ▶知識の統合と推論 (1)推 論 (2)知識と推論の年齢による変化 (3)推論に対する文化の影響 ▶学習を支援するための方略 (1)知識を保持するための方略 ①検索練習/②分散練習/③交互練習と多様性練習 (2)理解と統合のための方略 ①要約と作図/②説明の展開 ▶結 論 Chapter6 学習への動機づけ ▶理論的視座 ▶学習者の信念と価値観 (1)自己効力感 (2)価値観 (3)興 味 (4)内発的動機づけ (5)外的報酬 (6)選択の効果 ▶目標の重要性 (1)目標の種類 (2)教師が学習者の目標に与える影響 (3)学習目標とその他の目標 (4)将来のアイデンティティと長期的な粘り強さ ▶動機づけに対する社会文化的影響 (1)学習者の自己観における文化間差 (2)社会的アイデンティティと動機づけプロセス (3)ステレオタイプ脅威 ▶動機づけを向上させるための介入 ▶結 論 Chapter7 学校での学習への示唆 ▶学校での文化と学習 (1)学校と教室の文脈 ①学習環境/②バイアスの負の影響 (2)“欠陥” から “よさ” モデルへの移行 ▶学問領域固有の学習 (1)数 学 (2)科 学 (3)歴 史 ▶学習者を参加させ,力を与える (1)自己調整学習 (2)学習者を参加させる教授アプローチ ①問題基盤型・プロジェクト型学習/②協働学習 ▶学習評価 (1)学習者にフィードバックを与える (2)学習者がいかに学ぶかについてのエビデンスを評価につなげる ①ラーニング・プログレッションに基づく評価/ ②エビデンス中心のデザインによる評価のアプローチ ▶結 論 Chapter8 デジタルテクノロジー ▶学習目標に合わせたテクノロジーの利用 (1)学習テクノロジーのアフォーダンス (2)反復による学習 (3)モデルを使った深い学習 (4)協働・協同学習 (5)テクノロジーに支援された自己調整学習 ▶能動的な学習を促進するテクノロジー (1)ゲームを通して学習する (2)ストーリーや人気キャラクターを活用する (3)学習者をプロデューサー,クリエイターとして力づける (4)ものづくり(創作) (5)身体性認知 (6)対話型エージェント ▶授業設計のためのテクノロジー (1)フォーマルな学習とインフォーマルな学習を結びつける (2)指導の組織化 (3)ライティングの指導 ▶学習の機会と課題 (1)デジタルダッシュボード (2)遠隔学習 (3)個人用モバイルデバイス (4)テクノロジーの問題点 (5)ユニバーサルデザイン (6)高齢者の学習用テクノロジー (7)デジタル・デバイド(情報格差) (8)導入のための体系的アプローチ ▶結 論 Chapter9 生涯にわたる学習 241 ▶加齢に伴う変化 (1)推論と知識 (2)学習への動機づけ (3)学習活動と環境 (4)認知能力 ▶学習障害 (1)学習障害の原因 (2)読字障害 (3)算数障害 (4)成人における学習障害 (5)成人の読み書き能力 (6)介入方法 ▶高校卒業後の教育経験 ▶人材育成 (1)職場での学習を判断する根拠 (2)研修の転移 (3)職場における自律的な学習 (4)職場での自己調整学習 (5)積極的なエンゲージメントの重要性 ▶生涯学習の促進 ▶結 論 Chapter10 研究課題 ▶学習のダイナミックな性質 ▶研究課題 文 献 付録1 『How People Learn』についての研究とその使用の歴史 付録2 学習に関する研究の母集団 付録3 委員・スタッフ略歴 監訳者あとがき 索 引
「道徳読み」=教科書の読み物教材を徹底活用した、どの教科書でも使える授業法。 準備物はありません。教科書と鉛筆、そして考える頭だけ。 「道徳読み」は次の5つのパートで構成されます。 1、普通に読む 2、道徳読み(道徳さがし・道徳みつけ)をする →子どもたちは、主体的に、真剣に、教材と向き合います。 3、みつけた道徳を発表する →子どもたちは、対話を通じて自分が気づかなかった道徳を獲得。 4、登場人物に通知表を付ける →子どもたちは、自分とは異なる考え方を学びます。 5、自分を省みる →子どもたちは、自分自身への深い学びを体験します。 この授業法を学べば、誰でも、主体的・対話的で深い学びのある道徳授業ができるようになります。 本書では「道徳読み」の基本から実践までを1冊に収録しました。実践パートでは、おなじみの教材を使った授業が、学習指導案から実際の授業のながれまで全学年分掲載されています。 Ⅰ 「道徳読み」の基本 1 道徳の基本的な考え方 ①道徳脳で教材を読む/②心は自分から/③第二の天性を豊かにする/④他人には優しく。自分には? 2 「道徳読み」の方法 ①普通に読む(通読)/②道徳さがし・道徳みつけ/③発表をする/④通知表を付ける/⑤省みる(自分の心に落とす) 3 評価(子どもに対する評価) ①「特別な教科 道徳」の評価/②「道徳読み」での評価 4 「道徳読み」の効果 ①子どもへの効果/②広がる目/③教師の教材分析力がつく Ⅱ 「道徳読み」の実際 1 学年別・授業実践 第一学年 「はしのうえのおおかみ」 第二学年 「七つぼし」 第三学年 「ヒキガエルとロバ」 第四学年 「ブラッドレーのせい求書」 第五学年 「手品師」 第六学年 「ブランコ乗りとピエロ」 2 「道徳読み」をより豊かにするために 発展例① 「道徳ってどんな勉強?」 発展例② 「読み物教材以外で『道徳読み』」 Ⅲ「道徳読み」に困ったらQ&A コラム●「道徳読み」と学級づくり ① 子どもを観る視点にする/② 5分間の小さな「道徳読み」/③「法治」と「徳治」
本書『学級担任の一日』は、著者・宮澤悠維先生が小学校の学級担任としての一日をストーリー形式で描き、学級経営の具体的なメソッドを紹介しています。穏やかな授業の進行法や子どもとの距離の取り方、特別教室への遅刻防止システム、話し合いのプロセスなど、教師が知りたかった実践的な知識が詰まっています。すでに担任をしている教師にも、これから担任を目指す人にも役立つ内容で、読みやすさを重視し、集中すれば100分以内で読了可能です。学級経営の技術を理解し、子どもたちの成長を促すためのヒントが得られる一冊です。
「学級経営」に関するよくある質問
Q. 「学級経営」の本を選ぶポイントは?
A. 「学級経営」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「学級経営」本は?
A. 当サイトのランキングでは『新版 子供を動かす法則 (学芸みらい教育新書 2)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで152冊の中から厳選しています。
Q. 「学級経営」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「学級経営」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。