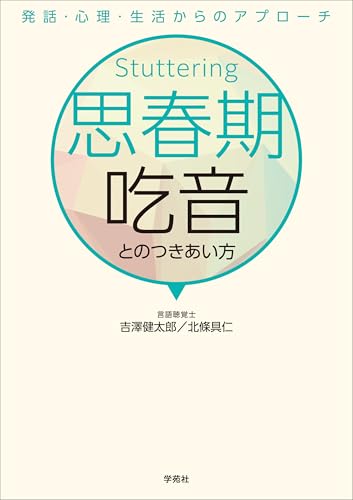【2025年】「吃音」のおすすめ 本 36選!人気ランキング
- 吃音: 伝えられないもどかしさ
- こどもの吃音症状を悪化させないためにできること ―具体的な支援の実践例と解説
- 吃音の世界 (光文社新書)
- 吃音のことがよくわかる本 (健康ライブラリー イラスト版)
- 決定版-HONZが選んだノンフィクション (単行本)
- どもる体 (シリーズ ケアをひらく)
- 自分で試す吃音の発声・発音練習帳
- 保護者の声に寄り添い、学ぶ 吃音のある子どもと家族の支援:暮らしから社会へつなげるために
- もう迷わない! ことばの教室の吃音指導:今すぐ使えるワークシート付き
- 子どもの吃音 ママ応援BOOK
発吃の後2割は吃音をもったまま成長するという現実を前提に吃音は「治す」から「悪化させない」「吃音をもったまま自由に話す」へ 発吃からその後2割は吃音をもったまま成長するという現実を前提に「吃音を治す」から「吃音を悪化させない」「吃音をもったまま自由にコミュニケーションをとる」といった転換に向けての専門家や教育現場の先生方、保護者の… 発吃からその後2割は吃音をもったまま成長するという現実を前提に「吃音を治す」から「吃音を悪化させない」「吃音をもったまま自由にコミュニケーションをとる」といった転換に向けて奮闘する専門家や教育現場の先生方、保護者の実際の支援の例と詳しい解説の書。 解説編は吃音をどうとらえるか、吃音のある子に保護者ができること、保護者と専門家による支援と協働の在り方について述べる。実践編では就学前、小学生、中学生、成人、それぞれの世代で、本人、保護者、担任の先生、言語聴覚士たちの支援の実際の手記を通して、「吃音症状の悪化とはどういう状態を指すのか」「なぜ悪化させてはいけないのか」に分かり易く答えている。 資料編は実際の吃音理解授業などで使われるスライドなどの資料を紹介していて、自由にアレンジして教育現場でも実際に使うことができる。 はじめに 解説編 堅田利明 Ⅰ吃音をどのようにとらえて、これから何をしていくとよいのでしょうか Ⅱ吃音のある子どもに保護者ができること Ⅲ吃音のある子どもと保護者への専門家による支援と協働 実践編 Ⅰ専門家ができる支援・実践について その子にとって自然な話し方を守り、育てる/餅田亜希子 吃音症状の悪化を防ぐためにー親子と紡ぐ吃音の理解・啓発の輪/西尾幸代 言聴覚士の立場から/田宮久史 Ⅱ就学前の子どもとその応援者 吃音発症/齋藤加奈子 吃音になっても、たくさんしゃべれるようになった/齋藤怜奈 知るとは つなぐとは/土屋直美 Ⅲ小学生の子どもとその応援者 伝え続けてきて/堀内美加 マネされちゃうと、気をつけちゃうし、もっと話せなくなる/堀内彩友 正しい理解から始める学校づくり/堀内絹予 子どもの成長と共に深まっていった吃音への理解/松下真生・新 新さんと出会って学んだこと/倉澤航 Ⅳ中学生の子どもとその応援者 「盛大につっかえた」と笑って言える環境が得られるまで/前川令 吃音と僕/前川橙士 吃音を正しく理解することで、お互いを思いやることができる/舘林裕二 中学校入学準備として私たちが行ったこと/小澤栄子 今のままの僕でいい、と思えるまで/小山田万紀 僕の吃音ライフ/小山田凛太郎 吃音、人との出会いで私が変わったこと/矢崎貴臣 Ⅴ成人の人の経験を通して 吃音で悩んだ経験からお伝えしたいこと/髙山祐二郎 Ⅵ吃音の理解・啓発授業の実践 自我が確立していく時期の、本児の自己理解、自己開示を支える教育相談/馬田美紀 連発を出さないように工夫した結果、吃音は悪化する/髙山祐二郎 Ⅶ理解・啓発の重要性と様々な試み 寛解後も続ける啓発活動の意義/平林実香 じっくりとお話を傾聴し、吃音の支援ができる専門家を育てる/金子多恵子 ラジオを通して、ふと誰かの耳に届いた吃音の言葉が……/餅田亜希子 資料編 おわりに
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
少年きよしは、言いたいことが言えずに孤独を感じていた。友だちが欲しいと思いながらも、夢の中の世界にしかその存在を見出せない。ある聖夜、ふしぎな「きよしこ」と出会い、彼は「大切なことは伝わる」と教えられる。この物語は、言葉を伝えられなかったすべての人に捧げられた感動的な少年小説である。著者の重松清は、現代の家族をテーマに多くの作品を発表している。
中学の入学式の日、自己紹介ができずに逃げ出した悠太の葛藤と成長を描いた物語。心をつかむ部活勧誘のチラシがきっかけで、彼は新たな出会いを経験し前進していく。著者は椎野直弥で、北海道出身の作家。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
吃音のある少年・新一は、ある日、転校生から「ボボボ、ボク、とか言うな。そのしゃべり方やめろよ」といわれます。それをきっかけにクラスの雰囲気が変わっていき、新一はしんどい思いを感じてきます。クラスのみんなに自分の気持ちを知ってもらいたい‐。新一は、お母さんや「ことばの教室」の先生の協力を受けながら、どうやったらクラスのみんなに吃音を理解してもらえるかを考えます。子どもにも読みやすいように書かれた本ですが、お母さんの気持ちや先生の視点なども考えられるような内容で、子どもにも大人にも読んで欲しい一冊です。 一 けやき 二 転校生 三 ひげ先生 四 ことばの教室 五 どもる友だち 六 お母さんにインタビュー 七 学習会 八 久しぶりのことばの教室 九 作戦会議 十 お母さんの手紙 十一 夢
著者伊藤亜紗は、視覚が人間の情報取得において重要な役割を果たす一方で、視覚を失った場合の身体や世界の捉え方について探求しています。視覚障害者の空間認識や感覚の使い方、コミュニケーション方法、ユーモアを生き抜く戦略として分析し、「見る」ことそのものを再考する内容です。目次では、空間、感覚、運動、言葉、ユーモアに関する章が設けられています。
2007年『キラキラ どもる子どものものがたり』の続編! 「吃音」に悩む思春期の子どもやその周りのあらゆる人に 2007年に出た『キラキラ どもる子どものものがたり』の続編! 「どもる」ということがどういうことか、身近にあっても正しく理解できていない「吃音」 「吃音で悩んでいる子どもやその家… 2007年に出た『キラキラ どもる子どものものがたり』の続編! 「どもる」ということがどういうことか、身近にあっても正しく理解できていない「吃音」 「吃音で悩んでいる子どもやその家族等の助けになるような本を作りたい」という著者の想いから生まれた一つの物語。 中学生になった「吃音」のある主人公、新一少年は多感な時期を日々どう生き、成長していくのか。 「吃音」で悩んでいる思春期の子どもやその周りのあらゆる人待望の「キラキラ」少年版。 別 れ 中学校に入学 才能と吃音(きつおん) 親の役割(やくわり) 吃音は個性か? 吃音の啓発(けいはつ) 喧嘩(けんか) 高校受験・面接 ひげ先生との再会(さいかい) あとがき
結婚直後、夫婦で5年間の旅に出た『遊牧夫婦』。初の新婚生活、先生との日中大議論、寝ゲリ、……遊牧夫婦の痛快ノンフィクション! 年収30万の三十路ライター、人生に迷う。結婚直後、夫婦で5年間の旅に出た『遊牧夫婦』。初の新婚生活、先生との日中大議論、寝ゲリ、吃音コンプレックス……現地で学び・生活する遊牧夫婦の痛快ノンフィクション! 年収30万の三十路ライター、人生に迷う。 結婚直後、夫婦で5年間の旅に出た『遊牧夫婦』。 本書では、旅の二年目中国に滞在した2年半の「暮らし」をお届け。 中国だから見えてくる、日本人のあり方や旅先での生活とは?働き方とは? 初の新婚生活、先生との日中大議論、寝ゲリ、吃音コンプレックス…… 現地で学び・生活する遊牧夫婦の痛快ノンフィクション!
村内先生は中学の非常勤国語講師で、言葉がつっかえるが、授業以上に重要な仕事を抱えている。いじめや家庭の問題に苦しむ生徒たちに寄り添い、彼らの心の痛みを理解し、希望を与える物語。著者の重松清は、現代の家族をテーマに多くの話題作を発表している。
「吃音」に関するよくある質問
Q. 「吃音」の本を選ぶポイントは?
A. 「吃音」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「吃音」本は?
A. 当サイトのランキングでは『吃音: 伝えられないもどかしさ』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで36冊の中から厳選しています。
Q. 「吃音」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「吃音」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。