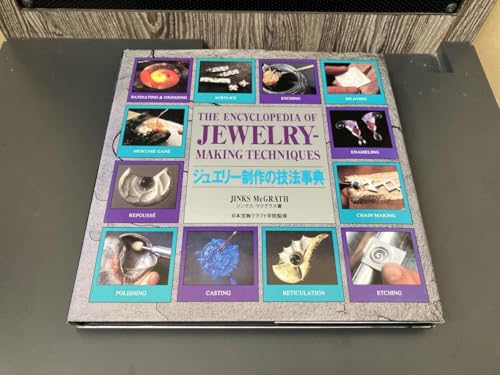【2025年】「モデリング」のおすすめ 本 144選!人気ランキング
- 無料ではじめるBlender CG アニメーションテクニック ~3DCGの構造と動かし方がしっかりわかる 【Blender 2.8対応版】
- 今日からはじめる Blender 3入門講座
- 入門Blender -ゼロから始める3D制作- 3.X対応
- Maya実践ハードサーフェスモデリング:プロップと背景から学ぶワークフロー (CG Pro Insights)
- 入門Blender2.9 ~ゼロから始める3D制作~
- 作って学ぶ! Blender入門
- Autodesk Mayaキャラクターモデリング造形力矯正バイブル -へたくそスパイラルからの脱出! ! -
- Blender リアルタイムCGキャラクター制作入門
- Blender 3DCG モデリング・マスター
- (解説動画付)ミニチュア作りで楽しくはじめる 10日でBlender 4入門
本書は、3DCGアニメ制作の基礎テクニックを学ぶためのガイドで、キャラクターの動かし方をゲームのステージをクリアする形式で楽しみながら習得できます。キーフレームやボーン、エフェクトの扱い、モデリングやレンダリングのテクニックが紹介されており、ショートムービーやアニメーションスタンプの制作を通じて、最新技術を活用したアニメーション作りを楽しむことができます。著者はCGデザイナーの大澤龍一です。
「Blender」は無料で使える高機能な3DCGソフトで、プロダクションでも利用されています。本書は、初心者向けにBlenderのインストールから基本操作、モデリング、テクスチャ、アニメーションまでを解説した入門書です。目次には3DCGの基礎知識、メッシュモデリング、スカルプトモデリング、レンダリングなどが含まれています。著者はクリエーターの伊丹シゲユキで、デザインや3D制作の専門家です。
この書籍は、Blender 2.8を使って3D制作を始める初心者向けの入門書です。インストールから基本操作、メッシュモデリング、カーブ・スカルプトモデリング、マテリアルやテクスチャの設定、アニメーション、アーマチュア、カメラとライト、レンダリングまでを網羅的に解説しています。著者はイラストレーターで、コンピュータ制作に関する豊富な経験を持っています。
Blenderは無料の3DCG作成アプリで、本書では30の制作例を通じて初心者がその機能を学べるように構成されています。各章では基本操作や質感の作成、応用機能の活用方法を解説し、著者の動画解説も提供されているため、実際の操作を確認しながら進めることができます。予約は2024年1月12日まで受け付けています。
初心者モデラー必携の「キャラクターモデリング造形力矯正バイブル」が第2版として登場しました。2013年の初版から改稿され、Autodesk Mayaの最新バージョンに対応しています。本書は、美しいキャラクター制作を目指すための詳細な手順と実例を提供し、初心者が直面するつまづきポイントを克服する手助けをします。内容は、モデリング機能やツールの使い方、キャラクターモデリングのレッスン、制作過程の実例など多岐にわたります。著者は田島キヨミで、CG制作の教育にも携わっています。
本書は、Blenderを使用してゲームやVRChat向けの3DCGキャラクターを制作する方法を解説しています。モデリングからマテリアル、テクスチャ、フェイシャル作成、さらにUnityとVRChatへのセットアップまでをカバーしており、初心者でも理解しやすい内容になっています。各章では、キャラクターデザインや素体の作成、衣装のモデリング、動作テストなどの具体的な手順が詳述されています。
本書は、初心者向けのBlender入門書で、かわいい3D作品を簡単に作れる内容です。人気YouTuber・M design氏が、Blenderの基本操作や効率的なモデリング方法を解説し、10日間でミニチュアルームを作る過程でスキルを身につけられます。各日ごとに異なる作品を作成しながら、操作方法やショートカットキーも学べます。特典として操作解説動画も提供され、初心者でも安心して取り組める構成になっています。
この書籍は、オープンソースの3DCGソフト「Blender 2.76」を用いてキャラクター制作に挑戦する内容です。著者は、アニメーション映画でのキャラクターデザインを手がけた齋藤将嗣で、友というBlenderのパワーユーザーがその美少女キャラクターを立体化します。目次では、キャラクターデザインからモデリング、セットアップ、ライティング、マテリアル設定、アニメーションまでの手順が詳述されています。著者はBlender歴10年の経験を持ち、さまざまなモデル制作に携わっています。
本書は、無料の3DCGソフト「Blender」を使った絵作りの解説書です。初心者から中級者までが対象で、章ごとに特定のポイントに焦点を当て、便利な機能やテクニックを紹介します。内容は、基本的なモデリングから質感やライティング、カメラ設定まで多岐にわたり、実際の作品制作に役立つヒントも提供しています。最新バージョン2.77に対応しています。著者はCGデザイナーの大澤龍一です。
この書籍は、数理モデルを用いて現象を理解するための基本的な統計モデルの考え方を、章ごとに異なる例題を通じて解説しています。前半では一般化線形モデル(GLM)の基礎を紹介し、後半では階層ベイズモデル化の手法をRとWinBUGSを用いて具体的に説明します。著者は久保拓弥氏で、生態学のデータ解析に関する統計学的方法を研究しています。
線形回帰分析を学んでそこから一般化線形回帰モデル、ベイズと拡張していく上で非常にオススメな本。初学者には少々難解な部分もあるが、統計学を学ぶ上で必ずどこかで読んで欲しい書籍。学生の時に読んだが、これを読むことでこれまで学んできた内容が整理され頭がクリアになった記憶がある。統計学を語るなら絶対読んで欲しい非常におすすめの書籍。
本書は、Blenderを使った3DCG制作に関する解説書で、映像演出に役立つ71のテクニックを紹介しています。プロのクリエイターが、ストーリーボードの作成から映像制作の具体的な手法まで、初心者にもわかりやすく解説。特に15秒CM制作を通じて、リギングやアニメーション、流体シミュレーションなどの技術を学ぶことができます。また、購入者には著者による解説動画が特典として提供され、実践的なテクニックを学ぶことができます。全体は2つのパートに分かれ、基礎から応用まで幅広くカバーしています。
この書籍は、無料の3DCGソフト「Blender」を用いた実写合成に焦点を当てた3DCG制作のノウハウを解説しています。クリエイターたちのインタビューや基本操作、ワークフロー、役立つ知識を含む構成で、初心者にも適した内容です。映像制作専門誌「VIDEO SALON」の特集を基に加筆・修正されており、実写とBlenderの融合を目指す人々に向けた指南書です。著者は映像作家のTaka Tachibanaを中心に、多様なクリエイターが参加しています。
この書籍は、オブジェクト指向開発の設計を強化するための手法を解説した教科書です。分析麻痺を防ぐための思考プロセスを、理論、実践、練習の3ステップで学び、ユースケースから保守性の高いコードを生成する方法を提供します。目次には要求定義、分析、設計、コーディング、テストの各プロセスが含まれており、著者たちはオブジェクト指向開発における豊富な経験を持っています。
本書は、UMLモデリングの基本を「広く・正しく・新しく」学べる内容で、イラストを用いたわかりやすい解説が特徴です。初学者でも安心して学べる構成で、各章の最後にはまとめと練習問題があり、理解度を確認できます。最新のUML2.5に対応し、実践的な開発事例も紹介されています。著者は、オージス総研の専門家たちで、様々な分野での経験を持っています。
本書は、現代社会におけるベイズ統計学の重要性を強調し、特に文科系大学での教育が不足している現状を指摘しています。ベイズ統計学は日常生活に深く根付いており、社会科学の教育においてその理解を深めることが急務とされています。内容は、ベイズの定理や確率分布、ベイズ推定などの基礎から応用までを扱っており、文科系・理科系問わず入門者を対象としています。著者は早稲田大学の教授、豊田秀樹氏です。
この書籍は、ベイズ統計の基本とその応用方法を、統計の基礎知識がない人にもわかりやすく解説しています。柔軟な事前確率を用いることで、あいまいな人間の経験則を取り入れ、実用的な情報を導き出すことができると説明されています。目次には、ベイズの定理や応用、MCMC法、階層ベイズ法などが含まれています。著者は涌井良幸で、数学教育と統計学の研究に取り組んでいます。
本書は、事業分析やデータ設計のためのモデル作成技術「TM(Theory of Models)」の入門書です。TMは厳密な文法に基づきテーブルを細分化し、ITエンジニア間の共通理解を促進し、変化に対応できるデータベース構築を可能にします。内容は、モデル作成に必要な理論や知識の解説、TMによるモデル作成の流れ、具体的な技術や文法の説明、練習問題を含み、事業構造の正確な分析とモデル化を学ぶことができます。著者は情報システムコンサルタントの佐藤正美氏です。
『メタバースに没入する準備はできているか?』は、無料で高性能な3Dアバターを作成し、VTuberやバーチャル空間での活動を楽しむためのガイドブックです。統合3DCGアプリ『Blender』を使用し、モデリングからテクスチャ設定、リギングまでの手順を解説。VRM形式に対応し、サンプルファイルも豊富に掲載されています。著者はフリーランスのデザイナーで、3DCGを活用したデザインに取り組んでいます。
本書は、近年注目されている統計モデリングについて解説しており、特にフリーソフトのStanを用いた実践的なアプローチを提供しています。Stanは高い記述力を持ち、階層モデルや状態空間モデルを簡単に記述できるため、データ解析に非常に有効です。著者は、ベイズ統計の理解を深めるための実践的な内容を重視し、StanとRを通じて統計モデリングの考え方を学ぶことができるとしています。目次には導入編、入門編、発展編があり、幅広いテーマを扱っています。著者は統計モデリングやデータサイエンスの専門家です。
かわいいアニメ絵風キャラクターをBlenderでモデリングする! Blenderの基本操作から、可愛いアニメ風の3Dキャラクターを作るためのコツまでを伝授!前後編の2巻で送る実践的解説書の前編「モデリングの巻」です。本書では、「基本編」で簡単なネコのキャラクターでBlenderの基本的な操作やモデリングに慣れるところからはじめて、「実践編」で女の子のキャラクターのモデリングまでを解説。3Dキャラクターモデラーの夏森轄氏が、自身のモデリングのノウハウをステップ・バイ・ステップで丁寧にお伝えします。本書で使用するモデル素材は、本書サポートサイトからダウンロードできます。【CONTENTS】第1部 基本編CHAPTER 1 Blender の基礎を学ぼう 1.Blenderのインストールと環境設定 2.Blenderのファイル操作と閉じる方法 3.Blenderの画面の説明 4.基本的な操作 5.移動・回転・拡縮 6.モードの切り替えと画面のカスタマイズ CHAPTER 2 簡単なネコのキャラクターを作ろう 1.モデリングをしてみよう 2.下絵を配置しよう 3.モデリングをしよう 第2 部 実践編CHAPTER 3 キャラクターの頭部を作成してみよう! 1.手順の説明とモデリングの流れ 2.モデリングの準備 3.頭部をモデリング 4.舌と歯のモデリング 5.顔の仕上げ 6.髪の毛をモデリングCHAPTER 4 キャラクターの身体を作成してみよう! 1.人体をモデリングする際の基本的な知識 2.上半身を作る 3.下半身をモデリング、身体全体の調整 4.腕と手をモデリング 5.脚・足をモデリング 6.全体の調整 CHAPTER 5 キャラクターの服を作成してみよう! 1.ワイシャツをモデリング 2.スカートをモデリング 3.パーカーをモデリング 4.靴、小物をモデリング 5.仕上げとラインアート また、本書から続く後編「トゥーンレンダリングの巻」(来春頃発売予定)では、前編「モデリングの巻」で作成したモデルを使用して、UV展開、表情の作り方、動かすための設定、アニメーションまで、トゥーンレンダリングでかわいく仕上げる手順をしっかり解説します。 ●第1部 基本編 CHAPTER 1 Blender の基礎を学ぼう 1.Blenderのインストールと環境設定 1-1.使用環境 1-2.Blenderのダウンロード手順 1-3.Blenderのインストール手順 1-4.Blenderの環境設定 2.Blenderのファイル操作と閉じる方法 2-1.ファイルの保存 2-2.保存に関するアラート画面 2-3.ファイルを開く 3.Blenderの画面の説明 3-1.各部の名称 3-2.3Dビューポートの解説 3-3.アウトライナーの解説 3-4.プロパティの解説 3-5.トップバーの解説 4.基本的な操作 4-1.視点の基本的な操作 4-2.テンキーで視点を操作 4-3.ナビゲートによる視点変更 4-4.選択について 5.移動・回転・拡縮 5-1.基本的な操作 5-2.オブジェクトの削除、追加、複製など 6.モードの切り替えと画面のカスタマイズ 6-1.モードの切り替えについて 6-2.エリアの境界を移動 6-3.エリアを分割 6-4.エリアの角から分割、統合する方法 6-5.エディタータイプについて 6-6.エリアを元に戻す方法 6-7.Chapter1のまとめ CHAPTER 2 簡単なネコのキャラクターを作ろう 1.モデリングをしてみよう 1-1.モデリングするネコのキャラクター 2.下絵を配置しよう 2-1.下絵の解説 2-2.下絵を配置する前の準備 2-3.3Dカーソルとは何か 2-4.正面と横の下絵を配置 2-5.下絵の固定と保存 3.モデリングをしよう 3-1.モデリングに慣れるためのコツ 3-2.ネコの顔をモデリング 3-3.モディファイアーを使ってみよう 3-4.ワイヤーフレームと透過 3-5.大きさを調整しよう 3-6.プロポーショナル編集で動かそう 3-7.ネコ耳をモデリングしよう 3-8.目をモデリングしよう 3-9.口をモデリングしよう 3-10.Chapter2まとめ ●第2 部 実践編 CHAPTER 3 キャラクターの頭部を作成してみよう! 1.手順の説明とモデリングの流れ 1-1.モデリングするキャラクター 1-2.下絵について 1-3.作業の手順 2.モデリングの準備 2-1.下絵を配置 2-2.下絵の配置とサイズの変更 2-3.下絵のロックと名前の変更 3.頭部をモデリング 3-1.可愛いと感じやすい顔について 3-2.平面からモデリング 3-3.目の周りをモデリング 3-4.口周りをモデリング 3-5.目と口の中をモデリング 3-6.後頭部をモデリング 3-7.首周りをモデリング 3-8.顔の微修正 3-9.耳をモデリング 3-10.斜め顔をモデリングするコツ、サブディビジョンサーフェスの追加 3-11.まつ毛・眉毛・二重をモデリング 3-12.目をモデリング 4.舌と歯のモデリング 4-1.舌のモデリング 4-2.歯のモデリング 5.顔の仕上げ 5-1.スムーズを適用 5-2.シャープを適用 6.髪の毛をモデリング 6-1.髪の毛は大きく4つの領域に分けられる 6-2.前髪をモデリング 6-3.横髪をモデリング 6-4.後ろ髪をモデリング 6-5.髪の毛仕上げ CHAPTER 4 キャラクターの身体を作成してみよう! 1.人体をモデリングする際の基本的な知識 1-1.人体をモデリングする際に意識すると良いポイント 2.上半身を作る 2-1.円、UV球を配置 2-2.上半身をモデリング 3.下半身をモデリング、身体全体の調整 3-1.お腹から下半身までをモデリング 3-2.全体の調整 4.腕と手をモデリング 4-1.腕のモデリング 4-2.手をモデリング 5.脚・足をモデリング 5-1.脚のモデリング 5-2.足のモデリング 6.全体の調整 6-1.首の位置調整 6-2.腰回りの修正 6-3.ループカットを適用 6-4.お腹のラインを修正 CHAPTER 5 キャラクターの服を作成してみよう! 1.ワイシャツをモデリング 1-1.ワイシャツ本体のモデリング 1-2.襟をモデリング 1-3.袖部分のモデリング 2.スカートをモデリング 2-1.スカート本体のモデリング 3.パーカーをモデリング 3-1.パーカー本体をモデリング 3-2.フード部分をモデリング 3-3.腕部分のモデリング 3-4.下半身側をモデリング 3-5.前立て部分をモデリング 4.靴、小物をモデリング 4-1.靴をモデリング 4-2.小物をモデリング 5.仕上げとラインアート 5-1.Bodyとfaceを統合 5-2.ラインアートの設定
本書は、Blenderを使ってかわいいキャラクターを作成し、動かす方法を詳細に解説しています。モデリング、UVマッピング、アーマチュア作成、表情設定、レンダリングなどのプロセスを学ぶことができ、最終章ではUnityとの連携やVRM形式への変換方法も紹介しています。各章では、基本情報から小物のモデリング、体の構造、テクスチャ作成、表情付け、レンダリングまで幅広くカバーし、サポートサイトからのモデル素材や動画教材も利用可能です。Blender 2.8系に基づいています。
この入門書は、初心者が人気の3DCGソフトBlenderを使ってキャラクター制作を学ぶための教材です。3ステップで進む構成で、最初はフリー素材を使ってBlenderの操作に慣れ、次にアクセサリーを作り、最終的にはVRChat用のキャラクターモデルを制作します。実践を通じて基礎を学び、自信を持って制作意欲を高める内容です。著者は3DCGクリエイターのしぐにゃもで、関連データも提供されます。
『Blenderでアニメ絵キャラクターを作ろう!』シリーズの後編「トゥーンレンダリングの巻」では、アニメ風キャラクターの制作プロセスを詳細に解説しています。内容は、リギング、スキニング、UV展開、マテリアル設定、表情作成、アニメーション制作、レンダリングまでをステップ・バイ・ステップで説明。前編ではモデリングについて解説しており、モデリングから学びたい方はそちらも参照することを推奨しています。著者はフリーランスの3Dキャラクターモデラー、夏森轄です。
この書籍は、心理統計学の理論と方法を心理学研究に特有の問題に焦点を当てて実践的に解説しています。目次には、心理学研究と統計の基礎から、回帰分析、推定や検定、実験デザイン、因子分析まで幅広いテーマが含まれています。著者は東京大学の教授で、心理統計学や心理測定学を専門としています。
この本は、ゲームを作りながらプログラミングを楽しく学べる「ふりがなプログラミングシリーズ」の一冊です。Unityの使い方やプログラミングの基本を、ブロックくずしや迷路、FPSゲームを通じて学べます。すべてのプログラムにはふりがなが振られており、漢文訓読の手法を用いた読み下し文も提供されています。対象は小学5年生以上で、初心者や過去に挫折した人にも適しています。内容はUnityの基本からゲーム制作までのステップが含まれています。
この書籍は、Blenderを使って3DCGを学ぶためのガイドであり、初心者や挫折した人向けに基本操作からキャラクターモデリング、ライティング、レンダリングまでを楽しく学べる内容です。目次にはモデリングの基本や家具・部屋のモデリング、キャラクターの作成と動かし方、マテリアル設定などが含まれています。著者は3DCGアーティストの富元秀俊とCG技術の普及に努める大澤龍一で、VRやWebベースの3DCGにも取り組んでいます。
この書籍は、住宅設計やイラスト制作に役立つ寸法に関する情報を提供する必読書です。完売した特集が合本となり、人体寸法、部屋別寸法、住宅寸法などを詳細に解説しています。具体的には、移動時や作業時の人体寸法、部屋ごとの寸法、構造や設備に関する寸法が網羅されており、快適な住宅設計に必要な情報が集約されています。クリエイターや設計者にとって、実用的な寸法資料の決定版です。
この書籍は、Autodesk Mayaの基本機能を解説した入門書です。著者は教育経験豊かな伊藤克洋氏で、仕事に必要な基礎を身につけるための内容が盛り込まれています。目次には、NURBSモデリング、Polygonモデリング、カメラやライトの操作、シェーダとレンダリングが含まれています。
文科と理科両方の学生のために,統計的なものの考え方の基礎をやさしく解説するとともに,統計学の体系的な知識を与えるように,編集・執筆された.豊富な実際例を用いつつ,図表を多くとり入れ,視覚的にもわかりやすく親しみながら学べるよう配慮した. 第1章 統計学の基礎(中井検裕,縄田和満,松原 望) 第2章 1次元のデータ(中井検裕) 第3章 2次元のデータ(中井研裕,松原 望) 第4章 確率(縄田和満,松原 望) 第5章 確率変数(松原 望) 第6章 確率分布(松原 望) 第7章 多次元の確率分布(松原 望) 第8章 大数の法則と中心極限定理(中井検裕) 第9章 標本分布(縄田和満) 第10章 正規分布からの標本(縄田和満) 第11章 推定(縄田和満) 第12章 仮説検定(縄田和満,松原 望) 第13章 回帰分析(縄田和満) 統計数値表 練習問題の解答
本書は、ビジネスで広く活用されるベイズ統計学の入門書で、数学的知識がなくても理解できるように優しく解説されています。迷惑メールの判別や未来予測に役立つ統計学の基本を、四則計算だけで学べる内容です。著者は帝京大学の教授で、数理経済学を専門としています。全てのビジネスパーソンや統計学に興味がある人におすすめの一冊です。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
現代社会においては,さまざまなデータを正しく扱うことが全てに優先する.本書は,われわれの生活や社会と直接・間接にかかわりをもつ分野で用いられている統計的方法の基礎から応用までを,具体例に即して分かりやすく解説する. 第1章 統計学とデータ(高橋伸夫) 第2章 データの分析(竹村彰通) 第3章 標本調査法(竹村彰通) 第4章 統計調査と経済統計(廣松 毅) 第5章 地域統計(中井検裕) 第6章 経済分析における回帰分析(縄田和満・松原 望) 第7章 経済時系列データの分析(国友直人) 第8章 社会調査(盛山和夫) 第9章 社会移動データの分析手法(盛山和夫) 第10章 要因探究の方法(盛山和夫) 第11章 心理測定データの解析(渡部 洋) 第12章 テスト理論(渡部 洋) 第13章 心理・教育データのための統計的方法(渡部 洋)
本書は、Blenderを使用した3Dキャラクターアニメーションの制作方法を解説しています。基本操作から魅力的なポーズの作成、自然な動きのテクニック、カメラワークのポイントまで幅広く学べます。著者・夏森轄氏のキャラクターモデルを用いて実践的に学習できる内容で、モデル素材はサポートサイトからダウンロード可能です。構成は、基本操作、ポーズ作成、アニメーション基礎、キャラクターアニメーション制作、カメラワークの学習に分かれています。
『達人に学ぶSQL徹底指南書』の第2版は、SQLを扱うエンジニア必携の書で、10年ぶりの改訂を経て、最新のSQL機能や実践的なコーディング事例を多数紹介しています。ウィンドウ関数やCASE式、外部結合などの重要なトピックを詳しく解説し、標準SQLに基づいて多様なデータベースに対応しています。また、リレーショナルデータベースの歴史や原理についても触れています。SQLを深く理解したいエンジニアやプログラマにおすすめの一冊です。
『王様戦隊キングオージャー』のCG背景を中心にしたバーチャルプロダクションガイド。作品の独自設定と高品質な映像が話題となり、CGビジュアルや制作技術を詳しく紹介。監督やプロデューサーを含む25名以上のスタッフへのインタビューも収録され、制作の熱意が伝わる内容。ビジュアル資料や制作体制図、スケジュールも含まれている。
本書は、Mayaをマスターするための教科書で、株式会社イマジカデジタルスケープのプロによる監修・執筆です。Maya2018に基づき、基礎編と作例編に分かれており、質の高い作例や演習データを通じてCG制作のプロセスを詳しく解説しています。基礎編ではMayaの基本からモデリング、アニメーション、リギングまでを学び、作例編ではローポリ・ハイポリキャラクタや背景制作を扱います。作成したシーンデータはWebからダウンロード可能です。
本書は、3Dアニメツール「MikuMikuDance」(MMD)向けの3DCGキャラクターの作り方を解説しています。無料の3Dソフト「Blender」を使用し、インストールからモデル完成までの手順を詳しく説明。モデリング、マテリアル設定、ボーンやウェイトの調整、服や表情の制作、MMDモデル化など、全8章で構成されています。MMDを自分で作りたい人に最適な一冊です。著者はMMDモデラーのマシシPです。
自然科学・工学・医学等への応用をめざしつつ,さまざまな統計学的考え方を紹介し,その基礎をわかりやすく解説する.シリーズIと同様に,豊富に実際例を用いつつ,図表を多くとり入れて,視覚的にもわかりやすく統計学を親しみながら学べるよう編集した. 第1章 確率の基礎(矢島美寛) 第2章 線形モデルと最小二乗法(廣津千尋) 第3章 実験データの分析(藤野和建) 第4章 最尤法(廣津千尋) 第5章 適合度検定(廣津千尋) 第6章 検定と標本の大きさ(竹村彰通) 第7章 分布の仮定(竹内 啓,藤野和建) 第8章 質的データの統計的分析(縄田和満) 第9章 ベイズ決定(松原 望) 第10章 確率過程の基礎(矢島美寛) 第11章 乱数の性質(伏見正則)
『絵で見てわかるSQL Serverの内部構造』が11年ぶりに改訂され、SQL Serverの物理構造や内部動作を豊富な図解で解説した一冊です。最新のデータベース環境に基づき、列ストアやインメモリ型オブジェクト、クラウドプラットフォームの解説も追加されています。これにより、SQL Serverの特性を活かし、データベースの開発や運用の効率化、トラブルシューティングに役立つ内容となっています。著者の実務経験に基づく実践的なTipsやノウハウも含まれています。
マーチン・ファウラーのベストセラー『UMLモデリング入門』の第3版は、UML 2.0に対応し新しいダイアグラムを追加した最新版です。オブジェクト指向ソフトウェア開発者に必携の書で、全編にわたってリファインが施されています。目次には、UMLの概要や各種ダイアグラム(クラス図、シーケンス図、ユースケースなど)に関する詳細が含まれています。ファウラーはオブジェクト指向技術の専門家であり、エンタープライズ系ソフトウェア開発における実績があります。
本書は、AI・データ分析プロジェクトの成功には技術知識だけでなく「ビジネス力」が重要であることを強調しています。データサイエンティストのキャリアや業界の概要から始まり、プロジェクトの立ち上げ、実行、評価、収益化までのノウハウを網羅。具体的には、課題設定、案件獲得、データ分析手法の検討、レポーティングなどのプロセスを解説し、実務に役立つ情報を提供しています。著者は業界の専門家で、実践的な知識を基にした内容となっています。
この本は、ゲームにおける背景制作における制作フローを解説した本です。国内外のゲームタイトルに携わったことのある著者が執筆しており、大規模な制作環境において、より効率化された制作の考え方や他のアーティストやエンジニアとの関わり方を解説しています。 1章:制作パイプライン 2章:モデリング・テクスチャリング 3章:地形と植生 4章:レイアウト 5章:プロシージャル 6章:周辺チームとのコラボレーション 7章:グラフィックス最適化
世界的規模で効率的に製品の開発・製作を行う際に欠かすことのできないシステムズモデリング言語SysMLの解説書。 世界的規模で効率的に製品の開発・製作を行う際に欠かすことのできないシステムズモデリング言語SysMLの解説書。言語の使い方やノウハウについて、豊富な実例をもとに分かりやすく解説。SysMLを開発したコアメンバーが執筆した書籍の翻訳本。UMLをさらに発展させたSysMLの修得ができる。 第Ⅰ部 序論 第1章 システムズエンジニアリングの概要 1.1 システムズエンジニアリングが必要な理由 1.2 システムズエンジニアリングプロセス 1.3 システムズエンジニアリングプロセスの典型的な応用 1.4 複数の専門分野からなるシステムズエンジニアリングチーム 1.5 標準規格を通じたシステムズエンジニアリング実施の体系化 1.6 まとめ 1.7 演習問題 第2章 モデルベースシステムズエンジニアリング 2.1 文書ベースアプローチとモデルベースアプローチの比較 2.2 モデリング原理 2.3 まとめ 2.4 演習問題 第3章 SysML言語概要 3.1 SysMLの目的と重要な特徴 3.2 SysMLダイアグラム 3.3 MBSEをサポートするSysMLの利用 3.4 自動車設計にSysMLを用いた簡単な例 3.5 まとめ 3.6 演習問題 第Ⅱ部 SysML言語の解説 第4章 SysML言語アーキテクチャ 4.1 OMG SysMLの言語仕様 4.2 SysML言語のアーキテクチャ 4.3 SysMLダイアグラム 4.4 ケーススタディ「監視システム」 4.5 第Ⅱ部の構成 4.6 演習問題 第5章 パッケージによるモデルの編成 5.1 概要 5.2 パッケージ図 5.3 パッケージ図を用いたパッケージの定義 5.4 パッケージ階層の編成 5.5 パッケージ図へのパッケージ化可能要素の表示 5.6 名前空間としてのパッケージ 5.7 モデル要素のパッケージへのインポート 5.8 パッケージ要素間の依存の表示 5.9 ビューとビューポイントの規定 5.10 まとめ 5.11 演習問題 第6章 ブロックによる構造のモデル化 6.1 概要 6.2 ブロック定義図によるブロックのモデル化 6.3 プロパティによるブロックの構造と性質のモデル化 6.4 ポートとフローを用いたインタフェースのモデル化 6.5 ブロックの振る舞いとモデル化 6.6 汎化を用いた分類階層のモデル化 6.7 まとめ 6.8 演習問題 第7章 パラメトリックを用いた制約のモデル化 7.1 概要 7.2 システム制約の表現 7.3 再利用を可能とするための制約ブロックの制約のカプセル化 7.4 合成を用いた複雑な制約ブロックの作成 7.5 パラメトリック図による制約ブロックのパラメータ拘束 7.6 ブロックの値プロパティの制約 7.7 ブロック構成値の取得 7.8 時間に基づく分析のための時間依存プロパティ制約 7.9 制約ブロックを用いたアイテムフローの制約 7.10 分析コンテキストの表現 7.11 候補の評価とトレードオフ検討のモデル化 7.12 まとめ 7.13 演習問題 第8章 アクティビティを用いたフローベースの振る舞いのモデリング 8.1 概要 8.2 アクティビティ図 8.3 アクション-アクティビティの基礎 8.4 アクティビティのモデリングの基礎 8.5 オブジェクトフローによるアクション間のアイテムフローの記述 8.6 制御フローを用いたアクションの実行順序の記述 8.7 シグナルや他のイベントの処理 8.8 アクティビティの高度なモデリング 8.9 アクティビティとブロックおよび振る舞いなどとの関係付け 8.10 ブロック定義図によるアクティビティ階層のモデリング 8.11 拡張機能フローブロック図 8.12 アクティビティの実行 8.13 まとめ 8.14 演習問題 第9章 相互作用を用いたメッセージベースの振る舞いのモデル化 9.1 概要 9.2 シーケンス図 9.3 相互作用としてのコンテキスト 9.4 生存線による相互作用参加者の表現 9.5 生存線間のメッセージ交換 9.6 シーケンス図における時間の表示 9.7 結合フラグメントを用いた複雑なシナリオの表現 9.8 相互作用参照を用いた複雑な相互作用の構築 9.9 内部の振る舞い表現のための生存線の分解 9.10 まとめ 9.11 演習問題 第10章 状態機械によるイベントベースの振る舞いのモデル化 10.1 概要 10.2 状態機械図 10.3 状態機械における状態の規定 10.4 状態間の遷移 10.5 状態機械とオペレーション呼び出し 10.6 状態階層 10.7 離散的状態と連続的状態の対比 10.8 まとめ 10.9 演習問題 第11章 ユースケースを用いた機能化のモデル化 11.1 概要 11.2 ユースケース図 11.3 アクターを用いたシステムのユーザー表現 11.4 ユースケースを用いたシステム機能の記述 11.5 振る舞いを用いたユースケースの精密化 11.6 まとめ 11.7 演習問題 第12章 テキストベースの要求のモデリングと,それらの設計との関係 12.1 概要 12.2 要求図 12.3 モデル上でのテキスト形式による表現 12.4 要求関係の種類 12.5 SysMLダイアグラムにおける横断関係の表現 12.6 要求関係の根拠の表現 12.7 表形式による要求と要求関係の表現 12.8 パッケージによる要求階層のモデリング 12.9 要求包含階層のモデル化 12.10 要求導出のモデリング 12.11 要求が充足されることの表明 12.12 要求が充足されることの検証 12.13 詳細化関係による要求の曖昧性の軽減 12.14 汎用目的のトレース関係の使用 12.15 まとめ 12.16 演習問題 第13章 割り当てを用いた横断関係のモデル化 13.1 概要 13.2 割り当て関係 13.3 割り当ての表記法 13.4 割り当ての種類 13.5 再利用の計画:割り当てによる定義と用法の規定 13.6 機能割り当てによる振る舞いの構造への割り当て 13.7 機能フロー割り当てを用いた機能フローと構造フローの結合 13.8 独立した構造階層間の割り当てのモデル化 13.9 割り当て構造フローのモデル化 13.10 ユーザーモデルの割り当ての評価 13.11 割り当ての次の段階 13.12 まとめ 13.13 演習問題 第14章 特定のドメインに対するSysMLのカスタマイズ 14.1 概要 14.2 再利用可能な構成要素を提供するモデルライブラリの定義 14.3 既存のSysMLの概念を拡張するためのステレオタイプ 14.4 プロファイルによるSysMLの拡張 14.5 ステレオタイプを用いるためのユーザーモデルへのプロファイルの適用 14.6 モデル構築時におけるステレオタイプの適用 14.7 まとめ 14.8 演習問題 第Ⅲ部 モデリング例 第15章 機能分析を用いた蒸留器のモデリング例 15.1 問題の記述 15.2 MBSEアプローチの定義 15.3 モデルの編成 15.4 要求の確立 15.5 振る舞いのモデル化 15.6 構造のモデル化 15.7 性能解析 15.8 初期設計の変更 15.9 まとめ 15.10 演習問題 第16章 OOSEMによる住宅セキュリティシステムのモデリング 16.1 OOSEMの概要 16.2 住宅セキュリティシステムの概要とプロジェクトの設定 16.3 OOSEMによるシステムの仕様決定と設計 16.4 まとめ 16.5 演習問題 第Ⅳ部 モデルベースシステムズエンジニアリングへの移行 第17章 システム開発環境へのSysMLの統合 17.1 システム開発環境におけるシステムモデルの役割について 17.2 システムズモデリングツールと他のツールの統合 17.3 統合システム開発環境におけるデータ交換のメカニズム 17.4 システムズモデリングツールの選択 17.5 まとめ 17.6 演習問題 第18章 組織へのSysMLの導入 18.1 改善プロセス 18.2 まとめ 18.3 演習問題 付録A SysMLリファレンスガイド A.1 概要 A.2 表記の規約 A.3 パッケージ図 A.4 ブロック定義図 A.5 内部ブロック図 A.6 パラメトリック図 A.7 アクティビティ図 A.8 シーケンス図 A.9 状態機械図 A.10 ユースケース図 A.11 要求図 A.12 割り当て A.13 ステレオタイプ 参考文献 索引
本書は、時系列データの分析方法を基礎から解説しています。探索的手法として移動平均、確率的手法として状態空間モデルを取り上げ、数式の意味やコードへの落とし込み方を丁寧に説明しています。初めて時系列分析を試みる人や、既に関わっている人にも興味深い内容となっており、応用的な話題もカバーしています。著者は牧山幸史、監修は石田基広です。
本書は、データサイエンスの基本概念から実際のビジネス活用事例までを豊富な図やイラストを用いて解説し、初心者でも理解しやすい内容になっています。データサイエンスの重要性が増す中、数学的な専門用語を避けながら、機械学習や先端テクノロジーとの関連も紹介。ビジネスパーソンや学生にとって、データサイエンスを学ぶための入門書として最適です。
本書は「はじめてのIT技術講座」シリーズのUML入門書で、主要なダイアグラムの理解と簡単なモデル作成を目指しています。章末には確認問題があり、UMTP認定試験L1レベルの対策にも適しています。UMLツール(Astah)のサンプルもダウンロード可能です。著者は河合昭男で、UML関連の教育や普及活動に従事しています。
本書は、Pixologic社の3DモデリングソフトZBrushに関する解説とチュートリアルを提供するガイドです。ZBrushは、粘土彫刻に似た直感的なアプローチで、多くのアーティストに利用されています。内容は、基本的な操作からプロジェクト例(女性戦士やエイリアンのスカルプト、歩行メカの制作)まで幅広く、KeyShotでのレンダリングや3Dプリントの技術も紹介しています。これは『Beginner's Guide to ZBrush』の日本語版です。
本書「セキュア・バイ・デザイン」は、プログラミングの質を向上させることでセキュリティを強化する方法を探求しています。著者はドメイン駆動設計(DDD)からの影響を受け、セキュリティを設計の中心に据えた「ドメイン駆動セキュリティ」を提唱しています。対象読者は基本的なプログラミング技術を持つソフトウェア開発者で、具体的な言語やフレームワークに依存しない内容です。内容は導入編、基礎編、応用編に分かれ、セキュリティの重要性、設計原則、レガシー・コードへの適用などをカバーしています。
データ分析コンペKaggleに挑戦するならこれをまず読んでおけば大丈夫!Kaggleに参加しないにしてもデータ分析の本質やテクニックがギュッと詰まっているので実務に活かせる。高度な内容も登場するが分かりやすく解説してくれるので初心者でも読みやすい。それでいてベテランの人も多くの学びがある書籍。著者はKaggleの最上位グランドマスターの方々であり説得力がある。過去のコンペの事例も取り上げてくれるのでそんなアプローチあったのかぁと学びが深い。文句なしの星5つ!
CLIP STUDIO PAINT用の3Dデッサン人形を活用したポーズ資料集が登場。523種類のポーズ素材が収録されており、360度のアングル変更や体型・性別の調整が可能。ポーズはダウンロードでき、操作方法も詳しく解説されている。プロのイラストレーターによる活用例も掲載されており、初心者から上級者まで役立つ内容となっている。
『エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計』は、2003年の出版以来、大型ソフトウェア開発における不透明感を解消するための指針として影響を与えてきた。11年が経過し、技術者の経験値が向上する中で、理論だけでなく実践的な方法論が求められている。本書は、ドメイン駆動設計(DDD)の基本概念から実践的な手法までを包括的に解説し、現代のニーズに応じた内容を提供している。目次には、ドメインやサブドメイン、アーキテクチャ、エンティティ、サービスなどの重要なトピックが含まれている。
データサイエンスを学ぶ上でこちらに一通り目を通しておくとベースが出来上がると思うのでオススメ。幅広く学べるがそこまで深く突っ込まないので気に入った領域は他の書籍で補完した方がよいかも!
この本は、光と色の理解を深め、デジタル彩色の技術を向上させるためのガイドです。読者が「色を塗ると同じになってしまう」や「迫力が出ない」という悩みを解消するために、光の性質や色の変化、陰影の表現方法を詳しく解説しています。内容は、光と色の基礎、ライティング、材質、色の調整、彩色技法、キャラクターや背景の彩色メイキングに分かれており、魅力的なイラストを描くための知識やコツが詰まっています。
本書は、Pythonのデータ処理ライブラリ「pandas」の実践的な使用法を約100のレシピ形式で紹介するもので、データ分析や科学計算に役立つ内容が含まれています。各レシピは手順や解説が整然とまとめられており、データ構造の基本から可視化技術まで幅広くカバーしています。著者はデータサイエンティストのTheo Petrouで、教育やデータ分析に関する豊富な経験を持っています。読者はデータサイエンスに興味のあるすべての人を対象としています。
この書籍は、UML(統一モデリング言語)の基礎からオブジェクト指向の概念、図形の描画方法、実務での活用方法までを初学者向けに詳しく解説しています。各章の最後には理解度チェックも用意されています。内容は、UMLの基礎知識とその適用に分かれており、著者は長瀬嘉秀と橋本大輔で、共にテクノロジックアートに関連する専門家です。
平均値から個性へ 階層モデルで「個性」をとらえる 個人差・地域差をとりこむ統計科学 全体モデルから局所モデルへ 生きた言葉をモデル化する ポスト近代科学としての統計科学 階層ベイズ講義
本書は、UML 2.xに対応したリニューアル版で、ダイアグラムの使い方やノウハウを詳しく解説しています。ユースケース図やクラス図、コンポーネント図など、幅広い図を実用的に扱い、ダイアグラム間の整合性やオブジェクト指向によるソフトウェア開発の基本も紹介しています。著者は井上樹氏で、現在は株式会社豆蔵でモデリング技術やソフトウェアエンジニアリングに関するコンサルティングを行っています。
本書は、ユニークなSQLプログラミングテクニックを75のパズルを通じて解説しています。題材は日常業務に関連し、実践的なSQL文が提供されます。集合論に基づいたテクニックが紹介され、DBエンジニアやアプリケーション開発者にとって有用な内容です。著者のジョー・セルコは、SQLに関する著名な専門家であり、実務に役立つ洞察を提供しています。
本書は、アーティストのために光と色彩の理論を解説した「A Guide for the Realist Painter」シリーズの第2巻で、現代イラストレーターのジェームス・ガーニーが自身の経験を基に書いています。光と色彩の基本について、具体例や豊富なイラストを用いてわかりやすく解説し、アート、映画、ゲームなど多様な分野のアーティストに役立つ内容です。光の性質や色の歴史、配色方法などが詳述されており、理論的な視点と実践的なテクニックが融合しています。
2023年で35周年を迎える今石進氏初の作品集。イラストレーション、メカニックデザインを中心にこれまで手掛けてきたアニメの版権イラストや原画など仕事の数々を紹介したファン待望の1冊。 ●表紙:今石進 描き下ろし ●カラーイラストレーション SDガンダムフォース絵巻武者烈伝 武化舞可編/BB戦士(LEGEND)/BB戦士(ノーマル)/BB戦士三国伝/SDガンダムワールド 三国創傑伝/SDガンダム モビルディスク/カオスギア/バトルスピリッツ ●デザインワークス 仮面天使ロゼッタ/完全勝利ダイテイオー/激闘!クラッシュギアTURBO/クラッシュギアNitro/ケロロ軍曹/星界の戦旗Ⅲ/バトルスピリッツ 少年突破バシン/バトルスピリッツ 少年激覇ダン/バトルスピリッツ ブレイヴ/バトルスピリッツ 覇王(ヒーローズ)/バトルスピリッツ ソードアイズ/最強銀河 究極(アルティメット)ゼロ~バトルスピリッツ~/バトルスピリッツ烈火魂<バーニングソウル>/バトルスピリッツ ダブルドライブ/バトルスピリッツ サーガブレイヴ/バトルスピリッツ 赫盟のガレット/バトルスピリッツミラージュ/WGPバクシード/未発表作品
本書では、VRoid Studioを使って3Dキャラクターモデルを作成する方法を解説しています。著者は200体以上の制作実績を持つVtuberで、キャラクターデザインの特徴を活かしたモデルの作り方や、自分の絵柄を3Dに再現するテクニックを紹介。内容はモデリングの基本から顔、体、服、髪型、アクセサリーの作成、カスタマイズ、アバターの活用方法まで多岐にわたります。イラストレーターBEBEによるサンプルモデルも付属。VRoid Studioは無料で、誰でも使いやすいインターフェースが魅力です。
本書は、UMLを用いてユーザーの要求をモデルに落とし込む手順とポイントを解説しています。モデル作成の難しさを踏まえ、より良いモデルを作成するための方法を伝授します。内容はモデリングの考え方、具体的なモデル作成手法、ユーザー要求のモデル化の演習を含み、著者はオブジェクト指向技術の専門家です。
ゲームクリエイター中村育美による廃墟・廃景の写真集『Project UrbEx』の日本語版。2004年以降に撮影された廃墟の写真を厳選し、解説や漫画が添えられている。荒廃した劇場や教会、人形島など多様な場所が紹介され、クリエイターや廃墟好きにとって必見の内容。著者は探索の際の安全と法令遵守を強調し、読者に冒険へのインスピレーションを提供することを目的としている。
この書籍は、時系列データの分析方法について基礎から詳しく解説しています。目次は、時系列分析の考え方、Box-Jenkins法、その他のトピック、状態空間モデル、カルマンフィルタ、ベイズ推論など多岐にわたります。著者は兵庫県出身の馬場真哉で、北海道大学水産科学院を修了しています。
この文章は、Unityを使ったゲーム制作の手順を解説する内容です。各章は以下のテーマに分かれています: 1. **Unityの準備** - インストールと基本機能の紹介。 2. **Unityの使い方** - エディターの構成と基本操作。 3. **基本的なゲーム作成** - プロジェクト作成、オブジェクトの配置、重力設定など。 4. **2Dゲーム制作** - スプライトの切り分けやプレイヤー操作の実装。 5. **ゲームのUI制作** - UIシステムの紹介とタイトル画面の作成。 6. **3Dゲーム制作** - キャラクターやステージの作成、カメラ操作、音楽追加など。 7. **スマートフォン向け改良** - スマートフォンプロジェクトの作成と操作対応。 全体を通じて、Unityを用いたゲーム開発の基礎から応用までを学ぶことができます。
製作する多種多様なモチーフの作品が、日本国内のみならず海外においても高く評価される原型師・造形作家のひとり、藤本圭紀。自身初となる作品集が満を持して登場します。氏が命を吹き込んだフィギュアたちが様々な表情で語りかけてくる本書は、フィギュア愛好家や原型師、ペインターはもちろん、今まで造形に興味がなかった方までも魅了してしまうこと間違いなし。収録作品は本書のために新規製作のフィギュアを3体をはじめ、なんと全部で23作品と大ボリューム。大判の美麗な写真からその魅力的な造形や塗装、作品の世界観をたっぷりと堪能できます。
この書籍は、地域密着型アウトドアショップがデジタルマーケティングを活用して業績を向上させるストーリーを通じて、デジタルマーケティングの基礎を学ぶ内容です。デジタル化を成功させるためには、知識を持った人材や情報を自ら取りに行く姿勢、トップの意欲が重要であると述べています。目次には、デジタルマーケティングの基本、集客手法、データ分析、ECサイト構築、SNS活用などが含まれています。著者はデジタル領域の専門家であり、データサイエンスの普及を目指して活動しています。
デジタルマーケティングとデータ分析について漫画で分かりやすく学べる。基本的な内容が網羅的に学べるのでデジタルマーケティング職についたばかりのビジネスパーソンや個人事業や中小企業でこれからデジタルに力を入れようとしている経営者にオススメ!
この書籍は、MySQLやPostgreSQLといったリレーショナルデータベースシステムにおけるアンチパターン(間違った使い方)を示し、正しいデータベースの設計・運用方法を解説しています。内容は「RDBアンチパターン」という人気連載を基にしており、データベースの設計や運用に関する具体的な問題点や改善策が紹介されています。著者は曽根壮大氏で、業務システムやWebサービスの開発・運用に豊富な経験を持っています。