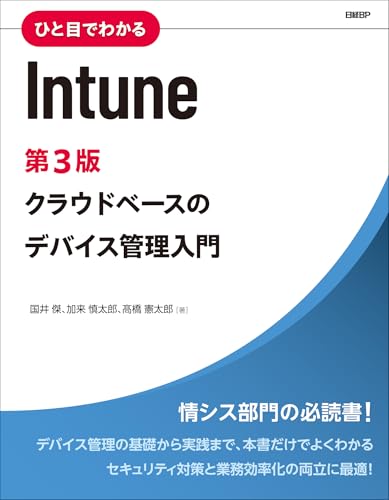【2025年】「異常検知」のおすすめ 本 86選!人気ランキング
- 入門機械学習による異常検知: Rによる実践ガイド
- 異常検知と変化検知 (機械学習プロフェッショナルシリーズ)
- Pythonではじめる異常検知入門 ―基礎から実践まで― (エンジニア入門シリーズ117)
- 時系列解析: 自己回帰型モデル・状態空間モデル・異常検知 (Advanced Python 1)
- 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)
- 時系列分析と状態空間モデルの基礎: RとStanで学ぶ理論と実装
- パターン認識と機械学習 上
- 漫画でわかる デジタルマーケティング×データ分析
- Rで学ぶVAR実証分析: 時系列分析の基礎から予測まで
- Pythonによる異常検知
この文章は、異常検知に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、異常検知の基本から正規分布や非正規データ、性能評価、次元削減、入力・出力データ、時系列データに関する異常検知までの各トピックが列挙されています。著者の井手剛は、機械工学と物理学の学位を持ち、IBMでの研究経験があります。
この書籍は、データ解析に関わる人々のために、異常検知や変化検知の理論と手法を体系的に解説したものです。著者は企業に所属しており、実用的なアルゴリズムや活用法を幅広く紹介しています。特に、大規模データから珍しいパターンや変化の兆しを迅速に捉える必要がある人にとって必読の内容です。シリーズ全体では、機械学習技術の基礎から最先端の研究までをカバーしており、研究や技術応用を目指す学生や研究者に向けたものです。
本書は「時系列解析」の手法を解説し、過去のデータから未来を予測するだけでなく、事象の理解にも役立つことを強調しています。マーケティングやIoTの実際の応用に焦点を当て、Pythonのサンプルコードを用いて基礎理論を説明。ARモデルやカルマンフィルタ、異常検知などの手法を段階的に学べるように構成されています。各手法の必要性や克服方法を提示し、読者が自学で応用範囲を広げられるよう工夫されています。
この書籍は、時系列分析の基礎から応用までを詳しく解説しています。内容は、時系列分析の基礎概念、ARMA過程、予測手法、VARモデル、単位根過程、見せかけの回帰と共和分、GARCHモデル、状態変化を伴うモデルに分かれています。著者の沖本竜義は、経済学と統計学の専門家であり、実データへの応用に必要な知識を提供しています。
この書籍は、時系列データの分析方法について基礎から詳しく解説しています。目次は、時系列分析の考え方、Box-Jenkins法、その他のトピック、状態空間モデル、カルマンフィルタ、ベイズ推論など多岐にわたります。著者は兵庫県出身の馬場真哉で、北海道大学水産科学院を修了しています。
この書籍は、地域密着型アウトドアショップがデジタルマーケティングを活用して業績を向上させるストーリーを通じて、デジタルマーケティングの基礎を学ぶ内容です。デジタル化を成功させるためには、知識を持った人材や情報を自ら取りに行く姿勢、トップの意欲が重要であると述べています。目次には、デジタルマーケティングの基本、集客手法、データ分析、ECサイト構築、SNS活用などが含まれています。著者はデジタル領域の専門家であり、データサイエンスの普及を目指して活動しています。
デジタルマーケティングとデータ分析について漫画で分かりやすく学べる。基本的な内容が網羅的に学べるのでデジタルマーケティング職についたばかりのビジネスパーソンや個人事業や中小企業でこれからデジタルに力を入れようとしている経営者にオススメ!
本書は、Rを用いたベクトル自己回帰(VAR)分析に特化した実用書で、理論やモデル構築、分析ツールに関する疑問に答えます。豊富なコード例を通じて、VAR分析を始める人々に役立つ情報を提供し、時系列分析の基礎や推定方法、検定手法などを解説しています。著者は村尾博氏で、経済学の専門家です。
本書は、AI・データ分析プロジェクトの成功には技術知識だけでなく「ビジネス力」が重要であることを強調しています。データサイエンティストのキャリアや業界の概要から始まり、プロジェクトの立ち上げ、実行、評価、収益化までのノウハウを網羅。具体的には、課題設定、案件獲得、データ分析手法の検討、レポーティングなどのプロセスを解説し、実務に役立つ情報を提供しています。著者は業界の専門家で、実践的な知識を基にした内容となっています。
この書籍は、数学の知識がなくても理解できる機械学習の入門書で、Pythonの機械学習ライブラリ「scikit-learn」を用いた実践的な解説が特徴です。著者はscikit-learnの開発に関わる専門家で、実践から理論へと学ぶスタイルを採用しています。特に「特徴量エンジニアリング」や「モデルの評価と改善」に焦点を当てており、従来の解説書にはない内容を提供しています。目次には教師あり学習、教師なし学習、データ処理などが含まれています。著者は機械学習の専門家で、産業界や学術界での経験があります。
本書は工作機械についての入門書で、日本のものづくりを支える「マザーマシン」としての役割を解説しています。工作機械の仕組み、種類、加工方法、最新の技術動向などを幅広く紹介しており、全7章で構成されています。著者は工学の専門家たちで、各自が豊富な経験を持っています。
機械学習の手法やテクニックにフォーカスした書籍ではなくて、機械学習を仕事に取り入れるためにはどうすればよいのか?どういうところに注意しなくてはいけないのかがまとめられた書籍。実務で機械学習を利用している人利用する可能性のある人は絶対に読むべき書籍。そもそも本当に機械学習を使う必要があるのかということをしっかり考える、機械学習ありきのプロジェクトは必ず失敗する。
本書は、機械学習の有名なアルゴリズムをPythonを用いてゼロから実装することを目的としています。実用的なフレームワークを使用するのではなく、機械学習の仕組みを深く理解することで応用力や問題解決力を高めることを目指しています。内容は、Pythonの基本、機械学習に必要な数学、数値計算、そして具体的な機械学習アルゴリズムに関する解説を含んでおり、初心者や実務に携わるエンジニアに適しています。著者はシルバーエッグ・テクノロジーのチーフサイエンティストで、機械学習アルゴリズムの設計・実装に精通しています。
この書籍は、NC旋盤の基本的な機能や構造、使用技術について解説しています。NC旋盤は主に丸物の量産部品加工に特化しており、マシニングセンタとは異なり量産加工の現場で重要な役割を果たします。内容は、NC旋盤の概要、構造、NC制御の基礎知識、段取り、加工のポイントなどを分かりやすく説明しています。著者は、芝浦工業大学の准教授で、機械加工に関する豊富な知識と経験を持っています。
本書は、機械学習アルゴリズムをオールカラーの図を用いてわかりやすく解説した入門書です。17種類のアルゴリズムを紹介し、各アルゴリズムの仕組みや使用方法、注意点を詳述しています。Pythonを用いたコードも掲載されており、実際に試しながら学ぶことができます。機械学習を学ぶ初心者や業務で利用している方にも役立つ内容となっています。
この書籍は、レーザ加工に必要な基礎知識や段取り、実作業のポイントを体系的に解説した実務向けの入門書です。内容は、レーザ加工機の構造や仕組み、段取りの基礎知識、実際の加工作業における注意点などが含まれており、加工品質やコスト算出方法についても触れています。著者は三菱電機の技師で、学術的な背景も持っています。
本書は、製造現場で必要な作業工具や取付具について、種類や原理、正しい使い方、便利な使い方のポイントを写真やイラストを用いて解説する実務向けの入門書です。内容は締緩工具、把握・切断工具、取付具・固定具、手仕上げ作業用工具の4章に分かれており、著者は芝浦工業大学の准教授で、ものづくりの専門家です。
この書籍は、ガウス過程に関する日本初の入門書であり、ベイズ的回帰モデルの柔軟性を解説しています。内容は線形回帰から始まり、ガウス過程の原理や教師なし学習、実応用に関する最新の話題も取り上げています。各章では、ガウス過程の基本概念、計算法、適用例などが詳しく説明されています。著者は統計や情報科学の専門家です。
本書は、モノづくり現場における「製造品質」「製造原価」「生産期間」を向上させるための治具設計に関する入門書です。治具は作業を楽にし、結果として品質向上、作業効率化、コスト削減を実現します。著者は生産技術コンサルタントの西村仁氏で、治具の導入目的や設計のコツなどを解説しています。
本書は、データマイニングにおける異常検知に特化した日本初の書籍であり、セキュリティやマーケティングなど多様な分野での応用が期待されている。著者は企業での経験を基に、数理工学的な視点から実践的な手法を解説。特に「情報論的学習理論」を用いた統一的アプローチと、具体的な事例(侵入検知や異常医療行為検出など)を通じて異常検知の方法論を示している。目次には異常検知の基本から具体的手法までが含まれている。著者は東京大学の教授で、機械学習やデータマイニングの専門家である。
この書籍は、エンドミル加工に関する基本知識や切削条件、実践的応用法を体系的に整理しています。著者は30年の経験を持つ工具メーカーの専門家で、独自の切削データやトラブル対策を提供。目次にはエンドミルの選定、材質、切削特性、トラブル予防など多岐にわたる内容が含まれ、加工実務を包括的に学ぶことができます。
本書は点過程の時系列解析に関する入門書で、データが特定のイベントの発生時刻の集合として扱われる点過程の理論と実データ解析を体系的に解説しています。地震や神経細胞の活動、金融取引などの現象を分析するために点過程が広く使われており、その応用範囲が拡大しています。著者は確率・統計の基礎を持つ読者を想定し、必要な理論や計算をできるだけ分かりやすく説明しています。目次にはポアソン過程やHawkes過程、統計推定法などが含まれています。著者は時系列解析や統計地震学の専門家です。
本書は、機械学習の解釈性とその重要性に焦点を当て、特にブラックボックスモデルの理解を助ける手法を紹介しています。著者は、解釈性を高めるための4つの手法(PFI、PD、ICE、SHAP)を説明し、実務での適用方法や注意点を解説します。具体的には、線形回帰モデルを通じて解釈性を理解し、機械学習モデルの振る舞いを説明できるようになることを目指します。また、実データ分析を通じて手法を実装することが可能です。著者は、機械学習プロジェクトに従事する経験を持つ専門家です。
本書は、計量経済分析の手法とRソフトウェアを用いた実行方法を解説した教科書で、経済学や経営学を学ぶ学生や研究者に向けています。内容は回帰分析、時系列分析(定常、非定常、GARCHモデルなど)、パネルデータ分析を中心に、各手法に必要な仮定やRのコードを詳述しています。著者は福地純一郎と伊藤有希で、いずれも経済学の専門家です。
『ゼロから作るDeep Learning』の続編である本書は、自然言語処理や時系列データ処理に焦点を当て、ディープラーニングの技術を実装レベルで学ぶことができます。具体的には、word2vec、RNN、LSTM、GRU、seq2seq、Attentionなどの最新技術を取り上げ、分かりやすく解説しています。著者は、人工知能の研究開発に従事する斎藤康毅氏です。
ゼロから分かるディープラーニングシリーズはどれも非常に分かりやすい。こちらの自然言語処理編は前作を読みディープラーニングの基本を理解してより高度なアーキテクチャを学びたいと思った時にオススメ。レベルは少々上がっているがそれでも分かりやすく学べる。RNNやLSTMなどが学べる
この書籍は、機械学習とディープラーニングの基本を図解形式で解説しており、エンジニア1年生や関連企業への就職・転職を目指す人に最適です。内容は、人工知能の基礎、機械学習とディープラーニングのプロセス、アルゴリズム、システム開発環境に関する知識を包括的に学べる構成になっています。著者は、実践的な機械学習システムの実装をサポートする専門家です。
この書籍は、計量経済学の実証分析をわかりやすく解説しており、最小二乗法や最尤法、各種回帰モデルなどの分析手法を具体例とともに紹介しています。内容は、計量経済学の基本理解から始まり、非線形モデルや因果関係の特定、パネルデータ分析まで幅広くカバーしています。著者は慶應義塾大学の山本勲教授で、応用ミクロ経済学や労働経済学が専門です。
この本は、初心者向けに「ボルツマン機械学習」を中心に機械学習を解説し、最終的には深層学習の実装まで導く内容です。イラストを用いてわかりやすく説明し、機械学習の専門用語や概念を解きほぐしています。章立ては、基礎から応用にかけて構成されており、著者は東北大学の准教授である大関真之氏です。
この書籍は、人工知能(AI)の全体像を理解し、5年後の活用イメージを掴むための内容です。3部構成で、第一部ではAIの基礎知識、第二部では機械学習のアルゴリズム、第三部ではビジネスにおけるAIの活用法を学びます。著者の梅田弘之は、システムインテグレータの代表であり、AIを活用した新しいプロダクトやサービスの開発に取り組んでいます。
本書は、データサイエンスにおけるコンペティション、特にKaggleに焦点を当て、実践的なデータ分析手法やテクニックを紹介しています。分析コンペに参加することで得られるスキルは、実務でも役立つため、特徴量の作成やモデルの評価、チューニングなどの具体的な内容が含まれています。著者たちは、データサイエンスの専門家であり、実績を持つKaggleの競技者です。この本は、コンペに挑戦したい人や実務でのモデル精度向上を目指す人にとって有益な情報源となるでしょう。
データ分析コンペKaggleに挑戦するならこれをまず読んでおけば大丈夫!Kaggleに参加しないにしてもデータ分析の本質やテクニックがギュッと詰まっているので実務に活かせる。高度な内容も登場するが分かりやすく解説してくれるので初心者でも読みやすい。それでいてベテランの人も多くの学びがある書籍。著者はKaggleの最上位グランドマスターの方々であり説得力がある。過去のコンペの事例も取り上げてくれるのでそんなアプローチあったのかぁと学びが深い。文句なしの星5つ!
この書籍は、強度設計に必要な材料力学の基礎や計算方法、実務での事例を丁寧に解説しており、機械設計の初心者から実務者まで役立つ内容を提供しています。目次には、強度設計の基本、材料力学、強度計算の方法、材料の基準強度、実務事例などが含まれています。著者の田口宏之は、豊富な設計経験を持ち、中小企業やスタートアップの支援も行っています。
AIのベースの一つである機械学習とは、コンピュータに大量のデータや経験を与えることによって、事象のパターン・ルールを発見し、予測などまでをも実現する技術である。機械学習の基礎から筆者らの最先端の研究までを初めての人にもわかりやすく解説する一冊。 はじめに 1 機械学習とは何か――人工知能(AI)の基礎知識 1.1 人間の学習能力をコンピュータで再現する「機械学習」 1.2 AI研究、これまでとこれから 1.3 人工知能の/による/のための研究 2 人工知能と社会 2.1 研究者とともに、学生とともに、エンジニアとともに 2.2 さまざまな分野におけるAI技術の応用 2.3 AIと社会の関係 3 機械学習の基礎 3.1 AIの学習モデルと学習法 3.2 3種類の機械学習 3.3 教師付き学習とは 3.4 教師なし学習とは 3.5 強化学習とは 3.6 機械学習の原理:「学習する」とは 3.7 なぜ教師付き学習で予測が当たるのか? 3.8 直線で分離できない問題への対応 4 高度化する教師付き学習 4.1 誤りを含む教師情報への対応 4.2 弱い教師情報の活用 4.3 限られた情報からロバストに:信頼できる機械学習に向けて 4.4 理研AIPに見る汎用基盤研究の現在地 5 今後の展望 5.1 モデルと学習法と、ある種の制約 5.2 機械学習の新技術:生成AI 5.3 AIと人間の未来
この文章は、鉄に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、元素の基礎知識から始まり、鉄の性質、熱処理、鍛造と鋳造、鉄鋼材料の種類、切削加工の基本、元素との関わりについての章が含まれています。著者は横山明宜で、1971年に関西学院大学を卒業後、サンドビック株式会社で様々な役職を歴任しています。
本書は、ファインチューニングの基本から実践までを具体的なPythonコードを通じて解説しています。画像識別や自然言語処理、生成AIモデル、強化学習におけるファインチューニングの手法を「レシピ」として整理し、実務での活用を目指すエンジニアや学生に向けた内容です。各章では基礎知識や手順を詳しく説明し、読者が自身の課題に合わせて実践できるようにしています。ファインチューニングを始めたい方や実践のコツを学びたい方におすすめの書籍です。
本書は、設計者が材料選択と加工方法を理解するための入門書で、材料加工学を中心に解説しています。機械材料の分類、特性、加工法、熱処理、接合技術について詳しく説明し、実践的なポイントを提供します。著者は材料力学の専門家で、実用的な知識を学ぶのに役立つ内容となっています。
本書は、数学が苦手な方でも機械学習を楽しく学べる入門書です。プログラマのアヤノと友達のミオの会話を通じて、機械学習の基本や実践方法を説明します。内容は、機械学習の重要性、回帰や分類の手法、モデルの評価、Pythonでの実装まで幅広くカバーし、数式も分かりやすく解説しています。特に、数式が苦手な方に配慮した内容になっています。著者はLINE Fukuokaのデータエンジニアで、実務経験を基にした知識を提供しています。
本書は、医療、金融、経済、天気予報など幅広い分野で利用される時系列データを通じてデータ解析手法を学ぶ内容です。データのクリーニングやプロット方法などの基本をカバーし、統計的手法と機械学習を適用した事例を紹介します。RとPythonを用いたプログラムが含まれ、データセットやコードはGitHubから入手可能です。著者はデータ解析の専門家で、各分野での応用についても触れています。
本書は、切削加工技術の進化を体系的にまとめた初の全書で、工法選択から工具・工作機械の選定、加工条件、CAD/CAM活用、計測、超精密加工などを解説しています。切削加工の特性を理解し、適切な加工法を選ぶことで生産性向上を図ることが重要です。著者は工学博士の森脇俊道氏で、切削加工に関する幅広い知識を提供しています。
この入門書は、ベイズ主義機械学習の基本原理を「モデルの構築→推論の導出」という手順で分かりやすく解説しています。内容は、機械学習とベイズ学習、基本的な確率分布、ベイズ推論による学習と予測、混合モデルと近似推論、応用モデルの構築と推論の5章から構成されています。著者は須山敦志と杉山将で、機械学習を身近に理解できるよう丁寧に記述されています。
本書は、深層学習に関する改訂版のベストセラーで、トランスフォーマーやグラフニューラルネットワーク、生成モデルなどの手法を詳しく解説しています。著者は、理論的な証明がなくても納得できる説明を重視し、実用性を考慮した内容を提供。全12章で、基本構造から各種学習方法、データが少ない場合の対策まで幅広く網羅しています。著者は東北大学の教授であり、実務家との共同研究の経験も反映されています。
本書は、音声認識システムにおける音源分離技術を解説したもので、特に中級者以上を対象としています。音源分離は、複数の音が混ざった中から特定の音を抽出する技術であり、基礎からPythonを用いた実装まで詳しく説明しています。目次には音声処理の基礎や数学的知識、古典的および現代的な音源分離方法、残響除去法などが含まれています。著者の戸上真人は音声処理の専門家で、AI研究に従事しています。
この本は、Pythonを使用した機械学習における216の問題とその解決策を提供します。データの基本的な取り扱いから、特徴量抽出、次元削減、様々なモデル(線形回帰、決定木、ランダムフォレスト、SVM、ニューラルネットワークなど)まで広範囲にカバーしています。改訂版では最新のフレームワークに対応し、PyTorchを用いたニューラルネットワークの情報が増加しています。実践的な問題解決に役立つ内容です。
本書は、機械学習や深層学習の予備知識がない読者を対象に、理論を明快に解説する入門書です。内容は、機械学習と深層学習の基本、ニューラルネットの仕組み、勾配降下法、誤差逆伝播法、自己符号化器、畳み込みニューラルネット、再帰型ニューラルネット、ボルツマンマシン、深層強化学習など多岐にわたります。著者は、理論的な基礎を重視し、学びやすい形式で解説しています。
本書は、2018年に発行された機械学習に関する書籍の全面改訂版で、不確実性の高い機械学習プロジェクトを「仕事で使う」という視点から整理しています。新たに「ML Ops」や「機械学習モデルの検証」などの章が追加され、読者が直面する問題解決に役立つ内容となっています。著者は機械学習分野の専門家で、実践的な知識を提供しています。
機械学習の手法やテクニックにフォーカスした書籍ではなくて、機械学習を仕事に取り入れるためにはどうすればよいのか?どういうところに注意しなくてはいけないのかがまとめられた書籍。実務で機械学習を利用している人利用する可能性のある人は絶対に読むべき書籍。そもそも本当に機械学習を使う必要があるのかということをしっかり考える、機械学習ありきのプロジェクトは必ず失敗する。
本書は、機械学習の基本をわかりやすく解説する入門書です。AIの様々な手法やアルゴリズムを整理し、Excelを用いて具体的に体験できる内容となっています。著者は涌井良幸と涌井貞美で、機械学習に興味がある人に最適な一冊です。目次には基本理論から回帰分析、ニューラルネットワーク、Q学習などが含まれています。
本書は、スモールデータの解析手法に焦点を当て、一般企業でのデータ解析に役立つノウハウを提供します。スモールデータは、データ量が少ない、または偏っているため、ビッグデータの手法をそのまま適用することが難しいです。本書では、スモールデータの定義から始まり、次元削減、回帰分析、クラスタリング、不均衡データ解析、異常検出などの手法を解説し、最後にスモールデータ解析のポイントをまとめています。
本書は、難解な数式やプログラミングなしで機械学習の基本概念と手法を解説する入門書です。著者の田口善弘氏は、中学数学の知識だけで理解できるように、機械学習の進歩やその本質をわかりやすく説明しています。内容には、k近傍法やニューラルネットワーク、深層学習などの手法が含まれており、学生やビジネスパーソンにとって必読の一冊です。
この書籍は、膨大な観測データから普遍的な法則を抽出する手法を解説する入門書です。高校数学から始まり、PythonやTensorFlowの実装、最新の論文に至るまで幅広くカバーしています。目次にはデータサイエンス、行列、確率論、機械学習、ニューラルネットワーク、最適化技法などが含まれ、実践的な内容が展開されています。著者は物理学の専門家で、研究者としての経験を活かして解説しています。
本書は、機械学習の基本から先進的な手法までを網羅したロングセラーのPyTorch版で、理論や数式も解説しています。前半ではscikit-learnを用いた基本的な手法やデータ前処理、後半ではPyTorchを使ったディープラーニング手法(CNN、RNN、Transformerなど)を詳述。新たにTransformerアーキテクチャやグラフニューラルネットワークに関する章も追加され、実践的な知見が得られる内容となっています。著者は機械学習の専門家で、実装を通じて理解を深めることを目的としています。
本書は、量子機械学習の基礎を学ぶための教科書であり、量子力学と機械学習の両方の初心者に向けて書かれています。数学的要素や用語を明確にし、量子コンピュータや量子機械学習への理解を深める構成になっています。著者たちは、両分野の重要な知識をコンパクトにまとめており、研究者や学生にとって有益なリソースとされています。量子コンピュータの登場により、量子力学の学び方が再考されるべき時期にあり、本書はその橋渡しをすることを目指しています。
この書籍は、ベイズ統計と機械学習の基礎理論を詳しく解説しており、統計学や確率の基礎、ベイズ推定、二項分布、共役事前分布、EMアルゴリズム、変分ベイズ、マルコフ連鎖モンテカルロ法、変分オートエンコーダなどのトピックを網羅しています。著者は筑波大学の准教授で、機械学習に関する専門知識を持っています。
本書は、機械学習におけるグラフの重要性を基礎から解説し、グラフニューラルネットワークの理論と応用を深く掘り下げたテキストです。内容は、グラフの定義やニューラルネットワークの基礎、グラフニューラルネットワークの定式化、様々なタスクへの応用、高速化手法、スペクトルグラフ理論、過平滑化現象の対策、表現能力など多岐にわたります。著者は佐藤竜馬氏で、研究者としての専門知識を活かし、理論に基づいた実践的な内容を提供しています。
この本は、ITエンジニア向けに機械学習の理論を基礎から学ぶためのものです。改訂新版として全面カラー化され、Pythonのコーディング環境もGoogle Colaboratoryに更新されています。機械学習の重要な理論がカバーされており、入門書としての定番となっています。内容はデータサイエンスの役割や機械学習アルゴリズムの分類から、最小二乗法、最尤推定法、パーセプトロン、ロジスティック回帰、k平均法、EMアルゴリズム、ベイズ推定まで多岐にわたります。著者は、中井悦司氏で、データ活用技術の普及に努めています。
この書籍は、顕微鏡画像やトランスクリプトームなどの生命科学データを用いて機械学習を学ぶ実践的なガイドです。ダウンロード可能なコードをブラウザで実行できるため、実験室の研究者でも手軽に始められます。内容は、機械学習の基礎からデータ前処理、トランスクリプトームデータの分類、画像解析、腫瘍予測、シングルセル解析、AI創薬など、多岐にわたる実践編を含み、さらなる学習のためのリソースも提供されています。
本書は転移学習に関する包括的なガイドで、基本概念から応用技術までを詳細に解説しています。内容は、転移学習の導入、ドメイン適応、事前学習済みモデル、知識蒸留、マルチタスク学習、メタ学習、継続学習など多岐にわたり、深層学習の進展に伴う実用的な方法論を提供しています。著者は情報科学の専門家で、学術的な背景を持つ研究者です。
ビジネスでの機械学習システムの設計や運用の解説書。エンド・ツー・エンドの機械学習システムを設計・構築する基本を明らかにする。 機械学習システム設計(デザイン)を業務での実践的な観点で解説!ビジネスとしての機械学習システムの設計や運用についての解説書。本書では、機械学習の最前線で活躍する著者の豊富な経験と知識に基づき、エンド・ツー・エンドの機械学習システムを設計・構築するための基本原則を明らかにします。訓練データの処理方法、特徴の使い方、モデルを再訓練する頻度、監視すべき項目……このような設計上の決定がシステム全体の目的達成にどのように寄与するのかを、実際のケーススタディを通じて理解します。機械学習プロジェクトを成功に導く上で必要な信頼性、拡張性、保守性、およびビジネス要件の変化への適応性を備えた機械学習システムを設計する包括的なアプローチを本書で学ぶことができます。
本書は、Human-in-the-Loop機械学習を活用して高品質な学習データを効率的に作成し、機械学習モデルの品質向上とコスト削減を図る方法を解説しています。特に、能動学習を用いたアノテーションプロセスの改善に重点を置き、実践的なテクニックやアノテーション管理手法を提供しています。データサイエンティストや機械学習エンジニアにとって、効果的なAIシステム開発に寄与する内容となっています。
本書は、反実仮想機械学習(CFML)に関する初の教科書で、実際には起こらなかった状況を分析する技術を機械学習に統合し、意思決定の最適化を可能にする方法を体系的に解説しています。特にオフ方策評価に焦点を当て、観測データに基づく推定技術や実践的な応用例を提供します。理論と実装をバランスよく扱い、学術研究や実務に役立つ内容となっています。著者は東京工業大学卒業後、コーネル大学で研究を続けており、関連する国際会議での発表実績も豊富です。
本書は、機械学習を用いた分子構造の生成と最適化に関する技術を、初学者向けに基礎理論から実装まで体系的に解説しています。プログラミング(Python)を通じて理解を深められるように、分子生成モデルや最適化手法について詳しく説明し、実践的な知識を提供します。内容は、分子データの表現、教師あり学習、系列モデル、変分オートエンコーダ、強化学習など多岐にわたり、分子構造を扱う研究者にも役立つ情報が含まれています。著者は日本アイ・ビー・エムの研究者で、博士号を持つ専門家です。
本書は、化学・化学工学分野でPythonを用いた機械学習の入門書であり、実験データの解析を通じて材料開発やプロセス管理を効率化する方法を解説しています。読者はPythonのインストールから基本理論、実践的なサンプルプログラムまでを学ぶことができ、改訂版では少数データに適した手法やウェブサービス「Datachemical LAB」の説明も追加されています。内容は、Pythonの基礎、データ解析・機械学習の基本、実践方法に分かれています。著者は明治大学の准教授、金子弘昌氏です。
本書は、因果推論と因果探索に関する包括的なガイドで、データサイエンティストや機械学習エンジニア向けに書かれています。内容は、因果関係の基本概念やグラフ表現、因果推論プロセスの4ステップ(モデル定義、推定、因果効果の推定、検証)を解説し、DoWhyやEconMLなどのPythonライブラリを用いた実践的な手法を紹介しています。また、因果探索の高度な技法やディープラーニングの応用についても触れています。著者は独立系の機械学習研究者で、企業向けのトレーニングも行っています。
本書は、機械学習やデータサイエンスの現場で役立つNumPyのデータ処理手法を解説した待望の第2版です。NumPyの基本から始まり、配列処理や数学関数を活用した実践的なデータ処理方法を紹介し、最終章では機械学習におけるデータ処理手法を解説します。Python 3.11およびNumPy 1.25に対応し、対象読者は機械学習エンジニアやデータサイエンティストです。著者はデータサイエンス関連のサービスを提供する企業の代表と東京大学の学生です。
本書は、量子機械学習の可能性と応用について解説しており、暗号解読や創薬、大規模気候予測などのデータ解析問題における効果を探ります。量子コンピュータの基本原理から最新の研究までを包括的に扱い、Pythonを用いた実践的な応用方法も学べます。著者の研究や文献を基に、量子コンピューティングと機械学習の融合についての知識を深めることができます。
本書は、機械学習のビジネスへの実装と運用に関する「MLOps」の実践ガイドです。第1部ではMLOpsの全体像や、それを実現するための技術、プロセス、文化について解説し、基礎知識を提供します。第2部では、実際の企業からの事例を通じて、MLOpsの具体的な実践方法を紹介しています。著者は機械学習の専門家であり、実用化に向けた知見が詰まった一冊です。
本書は、Scratchを使った小学校高学年向けの機械学習入門書です。画像認識や音声認識などのプログラムを作成しながら、機械学習の基本を楽しく学べます。難しいプログラミング言語や数学の知識は不要で、実際の応用を考える力を養うことができます。プログラミングに興味を持ち始めた子どもたちに適した内容です。目次には、さまざまなプログラム作成の章が含まれています。著者は、プログラミング教育に関わる専門家たちです。
「異常検知」に関するよくある質問
Q. 「異常検知」の本を選ぶポイントは?
A. 「異常検知」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「異常検知」本は?
A. 当サイトのランキングでは『入門機械学習による異常検知: Rによる実践ガイド』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで86冊の中から厳選しています。
Q. 「異常検知」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「異常検知」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。














![『AI・データ分析プロジェクトのすべて[ビジネス力×技術力=価値創出]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51xMXmkz4BL._SL500_.jpg)




















































![『Python機械学習プログラミング[PyTorch&scikit-learn編] (impress top gear)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51FUrutIo7L._SL500_.jpg)




![『[改訂新版]ITエンジニアのための機械学習理論入門』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41lZELJTlwS._SL500_.jpg)







![『(コードDL可能)Pythonライブラリによる因果推論・因果探索[概念と実践] 因果機械学習の鍵を解く (impress top gear)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51GvWpfSciL._SL500_.jpg)