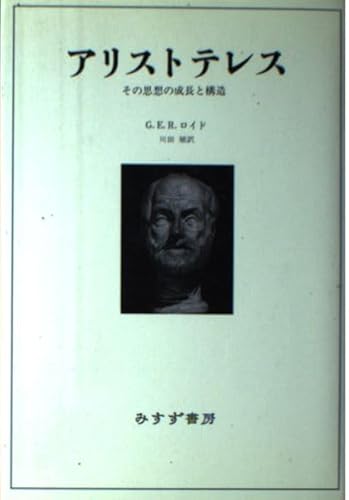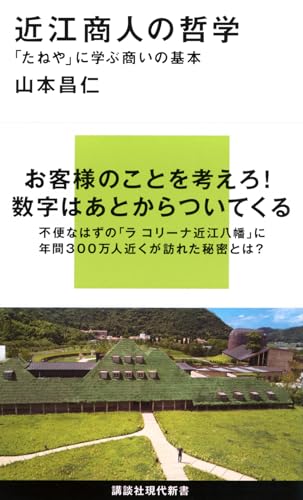【2025年】「古代ギリシア」のおすすめ 本 93選!人気ランキング
- 古代ギリシアの歴史 ポリスの興隆と衰退 (学術文庫)
- 古代ギリシャのリアル
- ラルース ギリシア・ローマ神話大事典
- 古代アテネ旅行ガイド (ちくま学芸文庫)
- 古代ギリシアがんちく図鑑
- ゆる古代ギリシア哲学入門-クセつよ逸話で学ぶ31人 (中公新書ラクレ 847)
- 天動説の絵本 てんがうごいていたころのはなし (安野光雅の絵本)
- アンティキテラ古代ギリシアのコンピュータ
- 海賊の世界史 - 古代ギリシアから大航海時代、現代ソマリアまで (中公新書 2442)
- ギリシア・ロ-マ文化誌百科: ヴィジュアル版 (上) (世界史パノラマ・シリーズ)
この書籍は、古代ギリシャにおける血液の「緑色」表現や「海」という言葉が存在しなかった理由、最高神ゼウスの「浮気性」など、学校や書籍では触れられないギリシャ神話と古代ギリシャ人の文化を探求しています。目次には、古代ギリシャの復元、ギリシャ神話の詳細、古代ギリシャ人のメンタリティに関する章が含まれています。著者は古代ギリシャとギリシャ神話の研究家、藤村シシンです。
この書籍は、ギリシア神話とローマ神話を網羅した約2500項目の事典で、神々や英雄たちの世界を豊富な図版と文芸作品の引用を通じて生き生きと描写しています。目次には、アテナイやエトルリア人、教育、宗教、祝祭、奴隷制度など多岐にわたるテーマが含まれています。
この書籍は、古代ギリシャを旅行する際のガイドブックで、名所や食文化、哲学者ソクラテスとの出会いなどの現地情報を豊富に紹介しています。特に紀元前5世紀半ばのアテネの日常生活や娯楽、著名人について詳しく描かれ、カラー図版も多数掲載されています。著者は古代ローマ史の専門家で、読者はアテネの魅力を深く理解できる内容となっています。
この本は、アポロンやポセイドンなどのオリンポスの神々や古代ギリシャの歴史、ペルシア戦争、オリンピックの起源について、イラストとエッセイを交えて紹介しています。また、ギリシャの遺跡旅行記も収録されており、古代ギリシャの全貌を理解できる内容となっています。著者は芝崎みゆきで、前作『古代エジプトうんちく図鑑』の成功を受けた待望の新作です。
この本は、日本初の哲学YouTuberによる古代ギリシア哲学の入門書で、アリストテレスやソクラテス、プラトンなど31人の哲学者の逸話を通じてその思想を紹介しています。各章では、哲学の起源、博識の意味、真理の探求、高貴な生き方、ソフィストの影響、哲学の本質、そして生き方についての哲学が探求されます。読者は面白い逸話を通じて、哲学の深い理解を得ることができます。
この書籍は、プラトン哲学の基盤にあるソクラテスの思想を深く掘り下げ、原点からの読み解きを通じて、自己再生や生の選択、反省の重要性を探求する案内書です。目次には、哲学的テーマやコスモロジーに関する考察が含まれ、現代の状況における闘いにも触れています。
「ギリシア・ローマ神話」は、西欧の文化芸術を理解するために重要な知識であり、ブルフィンチの著作は世代を問わず神話への入門書として最適です。目次には、ローマの神々や様々な神話の物語が含まれています。
ガリレオ・ガリレイの生涯を描いた本で、彼が地動説を信じ続け、権力に屈しなかった姿勢を美しい絵と共に紹介しています。理性と勇気を持った偉大な科学者の物語です。
「ギリシア神話」は、世界中の思想や芸術に影響を与えた重要な文化遺産であり、本書ではその神々や物語をわかりやすく解説しています。目次には、ゼウスやオリュンポスの神々、英雄たち、トロヤ戦争などのテーマが含まれています。著者の吉田敦彦は神話学者で、比較神話学や西洋古典学を専門としています。
哲学はどのように始まったのか? ギリシア哲学史の枠組みを根底から見直し、新たな視点で哲学者たちの思索を一望する記念碑的通史。 古代ギリシアで哲学はどのように始まったのか。近年の研究成果を踏まえギリシア哲学史の枠組みを見直し、哲学者たちの思索を新たな視座から一望する記念碑的通史 全てはここから始まる―― 古代ギリシアで哲学はどのように始まったのか。 人間と社会と自然を根源から問い、わたしたちの生き方・考え方を形作った知の原点。 近年の研究成果を踏まえギリシア哲学史の枠組みを見直し、哲学者たちの思索を新たな視座から一望する記念碑的通史! はじめに 第Ⅰ部 ギリシア哲学史序論 序章1 ギリシア哲学とは何か 1 ギリシア哲学史の哲学的意義/2 ギリシア哲学史の規定/3 ギリシア哲学史の四期区分 序章2 ギリシア哲学資料論 1 古代ギリシア哲学資料の概要/2 中世写本の伝承とテクスト校訂/3 パピュロス断片、金石文/4 断片集の編集 第Ⅱ部 初期ギリシア哲学 A ギリシア哲学の他者 1 エジプト/2 メソポタミア/3 叙事詩の伝統 B 総論 初期ギリシア哲学の枠組み C イオニアでの探究 序 探究(ヒストリアー)の成立 第1章 タレス ――最初の哲学者 1 人物と著作/2 知者/3 自然の探究/4 受容 第2章 アナクシマンドロス ――始源の探究 1 人物と著作/2 無限という始源/3 宇宙論/4 受容 第3章 アナクシメネス ――空気の変容 1 人物と著作/2 空気という始源/3 受容 第4章 クセノファネス ――神を語る詩人哲学者 1 人物と著作/2 酒詩と自然探究/3 神への視点/4 人間の認識/5 受容 第5章 ヘラクレイトス ――謎かけるロゴス 1 人物と著作/2 知への挑発/3 一なる万物/4 人間の生き方/5 受容 D イタリアでの探究 序 イタリアへの伝播 第6章 ピュタゴラス ――魂の教導者 1 人物と資料/2 生の教導/3 哲学の創始/4 受容 第7章 パルメニデス ――「ある」の衝撃 1 人物と著作/2 詩の序歌/3 真理の道/4 思い込みの道/5 受容 第8章 エレアのゼノン ――パラドクスの創出 1 人物と著作/2 逆説/3 受容 第9章 エンペドクレス ――浄化の宇宙詩 1 人物/2 著作/3 浄め/4 自然について/5 詩による真理の体験/6 受容 第10章 フィロラオス ――無限と限定の調和 1 人物と著作/2 ピュタゴラス派哲学の理論化/3 受容 第11章 アルキュタス ――数学者にして政治家 1 人物と著作/2 数学と哲学/3 受容 E イオニアでの自然哲学 序 イオニアの伝統 第12章 メリッソス ――一元論の展開 1 人物と著作/2 「ある」の一元論/3 受容 第13章 アナクサゴラス ――万物の秩序と知性 1 人物と著作/2 万物の混合/3 知性による宇宙生成/4 天体から生物まで/5 受容 第14章 レウキッポスとデモクリトス ――原子論の成立> 1 人物と著作/2 原子論/3 認識論/4 倫理的箴言/5 受容 第15章 アポロニアのディオゲネス ――自然一元論の復活 1 人物と著作/2 空気の一元論/3 受容 第Ⅲ部 古典期ギリシア哲学 A 総論 古典期ギリシア哲学の枠組み B ソフィスト思潮とソクラテス 序 ソフィストをめぐる知的活況 第16章 プロタゴラス ――最初のソフィスト 1 人物と著作/2 徳の教育/3 人間尺度説と神不可知論/4 受容 第17章 ゴルギアス ――言論の力 1 人物と著作/2 言論の技術/3 無の論証/4 受容 第18章 アンティフォン ――弁論の挑発 1 人物と著作/2 弁論術の教育/3 ノモスとフュシス/4 受容 第19章 ソクラテス ――対話による生の吟味 1 人物/2 資料/3 対話と不知/4 徳と知/5 受容 第20章 プロディコス ――言葉の正しさ 1 人物と著作/2 言葉の探究/3 神々について/4 受容 第21章 ヒッピアス ――記憶の博捜 1 人物と著作/2 オリンピック競技会と博識/3 受容 C ソクラテス文学とプラトン 序 ソクラテス文学とソクラテス派 第22章 アンティステネス ――ソフィストとソクラテスのハイブリッド 1 人物と著作/2 弁論術と哲学/3 倫理説/4 言語論/5 受容 第23章 アリスティッポス ――快楽主義の創始者 1 人物と著作/2 快楽の現実主義/3 受容 第24章 プラトン ――対話篇と学園の哲学 1 人物/2 著作/3 解釈の枠組み/4 魂とイデア/5 ディアレクティケー/6 受容 第25章 クセノフォン ――有為な人間の教育 1 人物と著作/2 立派な生と教育/3 受容 第26章 イソクラテス ――弁論と哲学の一致 1 人物と著作/2 弁論術の教育/3 スタイルの実験/4 受容 D アカデメイアとアリストテレス 序 アテナイの哲学学校 第27章 スペウシッポス ――イデアなき多元と分割 1 人物と著作/2 イデア論否定と数学/3 類似性の分類論/4 受容 第28章 クセノクラテス ――イデアと数の一致 1 人物と著作/2 宇宙論的存在論/3 受容 第29章 ヘラクレイデス ――バロックの学問と文学 1 人物と著作/2 文学と対話篇/3 哲学議論の応酬/4 受容 第30章 アリストテレス ――あらゆる学問知識の探究 1 人物/2 著作/3 学問と方法/4 言葉から実在へ/5 自然から形而上学へ/6 人間の幸福/7 受容 第31章 テオフラストス ――自然と人間の観察者 1 人物/2 著作/3 自然学と植物論/4 形而上学/5 性格論/6 受容 第32章 シノペのディオゲネス ――犬と呼ばれた哲学者 1 人物と資料/2 逸話による哲学/3 価値の転倒/4 受容 注 あとがき 参考文献 ギリシア哲学史関連年表 人名索引 事項索引
この書籍は、西欧文化の源流である神話や伝説を平易に紹介し、現代に息づくその精神を伝えています。ヘラクレスやアポローンなどの神々の物語や人間味あふれるエピソードが豊富に含まれており、壮大な物語が人類の遺産として描かれています。著者トマス・ブルフィンチは、古典文学の重要性を広めた人物です。
本書は、星や星座を季節ごとに紹介し、初心者が星空を楽しむためのガイドです。星座の形や見つけ方を手描きのイラストを用いてわかりやすく解説しており、読者は実際の星空を眺めながら星座を覚えていくことができます。星の明るさや色、動きについても触れ、双眼鏡や望遠鏡がなくても星を見つける楽しさを提供します。著者は漫画家の森雅之です。
この書籍は、古代ギリシャの三大哲学者であるソクラテス、プラトン、アリストテレスの思想をわかりやすく解説した入門書です。著者は哲学の専門家で、彼らの哲学的議論や重要な著作を整理し、エピソードを交えて説明しています。読者は複雑な思考を理解しやすくなり、ギリシャ哲学の基本を身につけることができます。
今日から古代ギリシアで生きていくためのあらゆるノウハウをこの一冊に。日々の生活作法はもちろん、当時ならではの身分や教養、そして緊急事態の対応まで幅広くわかりやすくユーモアを交えて「歩き方」を案内。
この書籍は、西欧文化の源流となる神話や伝説を平易な言葉で紹介し、トロイア戦争やオデュッセウスの冒険などの壮大な物語を詳細に描いています。充実した索引や読書案内も付いており、東洋や北欧の神話も網羅した決定版です。著者トマス・ブルフィンチは、古典文学や精神文化の重要性を広めた人物です。
この書籍は、ヘレニズム時代から古代後期にかけての科学的探求におけるギリシア的発想の特徴や方法、成果を解説しています。目次には、ヘレニズム時代の科学、アリストテレス以後のリュケイオン、エピクロス派とストア派、数学、天文学、生物学と医術、応用機械学、プトレマイオス、ガレノス、古代科学の衰退に関する章が含まれています。
この本は、ギリシャ神話を神々や英雄、怪物を通じて紹介し、それぞれのキャラクターの特徴や逸話、興味深いトリビアを提供します。内容はオリュンポスの12神やティタン神族、愛された者たち、叙事詩、獣や怪物、不幸な者たちのエピソードなど多岐にわたり、ギリシャ神話の魅力を楽しみながら学ぶことができます。著者は歴史学の専門家で、比較神話学の教授が執筆しています。
ヨーロッパ史に「近世」は存在するか。主権国家と複合国家の相克という視点から、中世でも近代でもないその独自性に迫る画期的試み。 ヨーロッパ史において近世とはいかなる時代か。宗教、経済、帝国、戦争という四つの特質に注目し、主権国家と複合国家の相克という観点からその全貌を描き出す。 ヨーロッパ史において「近世」とはいかなる時代か。宗教改革からフランス革命にかけてのこの時期は、ときに「近代」の準備段階とみなされ、ときに「長い中世」の一部とされてきた。だが近年、複合国家論などが提唱されるなかで、中世とも近代とも異なる独自の時代として近世を位置づける動きが広がっている。では、その独自性とは何か。近世を多様な地域が複雑に絡み合う歴史的空間と捉え、人やモノのグローバルな移動に注目することで、これまで教科書などでは十分に語られてこなかったその複雑なうねりをダイナミックに描き出す。 【目次】 はしがき――「中世」でも「近代」でもない時代 序章 ヨーロッパ近世の二つの顔――主権国家と複合国家 ヤヌスの二つの顔/教科書の中のヨーロッパ近世史/現代ヨーロッパの光景から/「地域」から考える/「複合国家」とは何か/本書の論点と構成 第一部 ヨーロッパ近世の構成要素 第1章 宗教と複合国家 「宗教改革」とは何か/ルターと「プロテスタント」の誕生/ツヴィングリとブツァー/カルヴァンの宗教改革/宗教改革と主権国家/宗教改革と神聖ローマ帝国の分裂 第2章 経済と地域社会 地域の経済活動/ヨーロッパ近世の重商主義/地域から見た価格革命と物価騰貴/サースクの局地的経済論/一七、一八世紀イングランドの毛織物工業 第3章 帝国と複合国家 大航海時代/ポルトガルとスペインの植民地貿易/大航海時代と主権国家/帝国建設と複合国家/君主による帝国建設/会社組織による植民地建設 第4章 戦争と講和条約 近世の戦争と主権国家/近世初期のイタリア戦争/パーカーの軍事革命論/三〇年戦争/ウェストファリア条約/「ウェストファリアの神話」/主権国家論の問題点 第二部 ヨーロッパ大陸の複合君主政国家 第5章 神聖ローマ帝国と地域――複合国家としての帝国 近世初頭の複合国家/「怪物のような国家」/近世の神聖ローマ帝国/神聖ローマ帝国の「まとまり」と合意形成/ウェストファリア条約以降の帝国存続/オーストリアとプロイセン 第6章 スペインの国家と地域――カスティーリャとアラゴン カルロス一世とフェリペ二世/スペイン複合君主国/スペインの統合政策の問題点/フランスとの比較/スペインの財政的負担/アラゴン連合王国の抵抗理念/一七世紀スペインの衰退 第7章 フランスの国家と地域――パリと周辺地域 フランス近世の歩み/フランス絶対王政の確立/フランスの統合政策の問題点/フランス絶対王政の評価/二つの顔を持つフランス近世 第8章 オーストリアとプロイセン――神聖ローマ帝国内の主導権争い 神聖ローマ帝国の国制/神聖ローマ帝国をめぐる主導権争い/マリア・テレジア期の集権化と分権化/プロイセン近世史の評価/複合国家プロイセン/神聖ローマ帝国の中のプロイセン 第三部 オランダとイギリスの複合国家 第9章 オランダの国家と地域――ネーデルラントの南部と北部 ネーデルラント独立戦争/オランダの繁栄/一七世紀オランダは「中世」か「近代」か/複合国家オランダの「紐帯」/宗教と経済活動という「紐帯」 第10章 一六世紀イギリスの複合国家と地域――イングランドとウェールズ ブリテン諸島を結んだ「紐帯」/一六世紀イングランドの集権化と宗教改革/エリザベス女王の時代/ネーデルラントの亡命者と技術移転/スコットランドとアイルランドの動き/イングランドとウェールズの合同/ウェールズの社会と文化/ウェールズ政策とアイルランド政策 第11章 ピューリタン革命と複合国家の危機――スコットランドとアイルランド 一七世紀の危機/ジェイムズ一世とブリテン統合/チャールズ一世の国教会強制とピューリタン/ピューリタンの「避難所」オランダ/スコットランドとアイルランドの反発/スコットランド暴動から長期議会へ/スコットランド契約派の改革/アイルランド反乱の衝撃/内戦の勃発と議会軍の勝利/セクトと平等派 第12章 ピューリタン革命から名誉革命へ――イギリス複合国家の確立 国王なき時代へ/共和政の実験/アイルランドとスコットランドの征服/複合国家の形成/ヒュー・ピーターの提言/指名議会とプロテクター政権/「近世」的な革命が「近世」を変えた/王政復古から名誉革命へ/再度のアイルランド征服/イングランドとスコットランドの合同 第四部 複合国家の変質と存続 第13章 宗教的亡命者と複合国家の思想 近世における変化の兆し/宗教的迫害と移民/スペインの宗教迫害とユダヤ人/フランスの宗教迫害とユグノー/亡命者を受け入れたイングランド/イングランドのカトリック差別/「獲得によるコモンウェルス」を説くホッブズ/複合国家の思想家ハリントン 第14章 商業・貿易とイギリス産業革命 商業や貿易という「紐帯」/バーボンの『交易論』/イングランドの商業革命/フランスの経済発展/「イングランド帝国」から「ブリテン帝国」へ/産業革命と奴隷貿易/長期にわたる産業革命 第15章 英仏抗争とアメリカ独立戦争 「紐帯」を強化する戦争/戦時の「紐帯」としての国王/商人や一般人にとっての戦争/「財政軍事国家」の登場/フランスの財政破綻を招いた英仏戦争 第16章 啓蒙思想とフランス革命 啓蒙思想とフランス革命の関係/啓蒙思想の宗教的寛容論/啓蒙思想の奴隷制批判/東欧・ロシアでの啓蒙思想普及/アメリカとフランスを結ぶ大西洋革命/国民国家の形成と地方主義 終章 比較と展望のヨーロッパ近世史 本書のまとめ/近世の二つの政治組織モデル/日本近世との比較/現代への展望 あとがき――「歴史総合」から除外されたヨーロッパ近世史 参考文献
この作品は、種子島の美しい発射場から日本のロケットが打ち上がるまでの過程を、子ども目線で描いています。メインキャラクターのかみなりくんと小おにちゃんが、ロケットの打ち上げの流れを体験しながら案内し、特にパノラマページでの打ち上げシーンが迫力満点です。各ページには英訳と隠し絵もあり、ロケットに関するトリビアも紹介されています。著者は実際に打ち上げを体験し、その感動を絵に込めています。
『ソクラテスの弁明』『オイディプス王』『国家』など古代ギリシア哲学・文学の名作が提起する、人間存在をめぐる根源的問題を縦横に論じる講義。 ソクラテスは言う――「いちばん大切なのは、単に生きることではなく、よく生きることだ」。では「よく生きる」とはどのようなことか。「単に生きること」だけでも容易ではない状況を、人はいかに生きるべきなのか。本書はそうした根源的な問いについて、『ソクラテスの弁明』『オイディプス王』『国家』をはじめとする古代ギリシアの哲学、文学の名作を手引きに、深く掘り下げて考える。2400年のはるかな時を超えて現代の我々に生きるヒントを示してくれる古代の叡智の数々を、ギリシア哲学研究の碩学が縦横に論じ、わかりやすく読み解いて伝える連続講義。 はじめに 第1講 ソクラテスと「無知の自覚」 第2講 オイディプスと自己の深淵――自分を知ることの悲劇 第3講 個人と社会I――『アンティゴネー』における人の法と神々の掟 第4講 個人と社会II――プロメテウスとゼウスの贈り物 第5講 法と人間I――アンティフォンの挑戦と目撃者の不在 第6講 法と人間II――ソクラテスは、なぜ脱獄しなかったか 第7講 力と正義I――古代ギリシア人と現実政治(リアルポリティックス) 第8講 力と正義II――ソフォクレス『フィロクテテス』と大政治のなかの個人 第9講 徳と悪徳I――プラトン『ラケス』と勇気への問い 第10講 徳と悪徳II――アリストテレスの勇気論 第11講 徳と悪徳III――アリスティッポスの人生指南 第12講 理性と情念I――メデイアとまちがいだらけの夫選び 第13講 理性と情念II――プラトン『国家』における魂の三角関係 第14講 美とエロースの探求――プラトン『饗宴』を読む 第15講 芸術と真理――プラトン『国家』におけるミーメーシス(模倣)論 第16講 真と嘘I――ゴルギアスと、人を言いくるめる方法 第17講 真と嘘II――プラトンの弁論術批判 第18講 ソクラテスと若者たちI――アリストファネス『雲』と美風の崩壊 第19講 ソクラテスと若者たちII――エレンコス(論駁)の成人指定 第20講 国のかたち、人のかたち――民主主義と独裁 第21講 敷居の外で――伝デモステネス『ネアイラ弾劾』をめぐって 第22講 理想国の女性たち――「哲人女王」への道 第23講 哲学者と自殺――ソクラテスからストア派まで 第24講 ソクラテスと老い――クセノフォン『ソクラテスの弁明』をめぐって 第25講 運命の転変と苦悩――クロイソスの場合 第26講 運命と自由――自己を選ぶ 古代ギリシアの哲人 関連年表 古代ギリシア 関連地図 あとがき 学芸文庫版あとがき 人名索引
本書は、ギリシア神話の影響を解説し、台風やシャンゼリゼー大通りの名の由縁など、日常生活に根付く神話の重要性を示しています。オリュンポスの神々や古代の伝説を体系的にまとめたもので、著者は西洋古典学者の呉茂一。彼は東京大学で教え、日伊文化交流にも貢献しました。
この書籍は、古代ギリシャの哲学の起源や哲学者たちの思想、彼らの言葉による証明、神や死、幸福に関する考え、国家との関係などを探求しています。著者は学習院大学の教授と非常勤講師で、哲学に関する専門知識を持っています。各章では、哲学の基本概念や歴史的背景が解説されています。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
初期自然学から,問う人ソクラテスを描いて新しい知の探求の道を開いたプラトン,諸学の礎を築いたアリストテレスへ.人間の「知」のあらゆる萌芽を秘めつつ,哲学そのものの成立の機微をうかがう待望の通史.
本書は、宇宙の形状や構造についての人類の探求の歴史を、イラストを通じて学ぶ絵本です。内容は古代ギリシアの宇宙観からビッグバン理論、現代の科学的観測、未来の宇宙についての考察まで多岐にわたります。親子で楽しめる内容になっています。著者は宇宙観を研究する絵本作家のギヨーム・デュプラで、翻訳は渡辺滋人が担当しています。
この本は、月や火星の探査について、豊富な写真とイラストを用いて解説する入門書です。2019年はアポロ11号の月面着陸から50年となり、各国が宇宙探査に注力しています。中国は月の裏側探査に成功し、火星探査ではロシアや米スペースXが有人探査を計画しています。内容は月・火星の基本情報、宇宙探査の歴史、最新ミッションについてわかりやすく紹介しており、小学生から大人まで楽しめる内容です。
この書籍は、アポロドーロスによるギリシア神話の原典を紹介しており、古代の著述に基づいた神話伝説を体系的にまとめています。内容は三巻に分かれており、神々や英雄の系譜、トロイア物語などが詳述されています。従来の感傷的な解釈とは異なり、古代ギリシアの純粋な物語を提供し、西欧文化への影響を理解するための重要な資料です。
本書は、古代ギリシア哲学の巨人アリストテレスの知の探求を再発見する試みである。彼は形式論理学の基礎を築き、近代自然科学の発展に寄与した。内容は、知への欲求や論理学の誕生、自然と原因、生命の意味、善の追求など多岐にわたり、アリストテレスの思考法が現代にどう影響しているかを探る。著者は大阪府立大学の教授、山口義久。
ハイデガーの「存在の思索」に寄り添いつつ、人類にとって原初の思索・哲学を「みずみずしい姿」で復活させ、従来のギリシア哲学観に変更を求めるとともに、そこから西洋哲学一般、近代科学、人間の思考のあり方そのものに疑問を呈する、過激にして痛烈な現代文明批判の書(上下巻)。 まえがき 本書(上巻)に登場する主な哲学者 生没年早見表 紀元前5世紀ごろのギリシアと周辺諸国地図 第1講 ギリシア哲学俯瞰 言語について 本講義の記述方針 第2講 ミレトスの哲学者(Ⅰ) タレス 哲学者、タレス。 タレスの哲学 コラム:逸話 第3講 ミレトスの哲学者(Ⅱ) アナクシマンドロス アナクシマンドロス哲学の原理 ヒューマニズムを徹底的に超える哲学 アナクシマンドロス、自然の境内に住まう。 第4講 ミレトスの哲学者(Ⅲ) アナクシメネス 哲学者、アナクシメネス。 アナクシメネスの自然哲学 コラム:太古的概念「ピュシス」 第5講 ピュタゴラス 哲学者、ピュタゴラス。 ピュタゴラスとテラトポイイア 第6講 アルキュタス ギリシア世界に確信を持つ哲学者、アルキュタス。 アルキュタスの哲学 コラム一:ピュタゴラス教団 コラム二:ピュタゴラス派の数形而上学 第7講 ヘラクレイトス ロゴスvs主観性 ヘラクレイトスの自然哲学 コラム一:世界大火 コラム二:ヘラクレイトスの出自と著作 第8講 エレア派(Ⅰ) 故郷喪失の哲学者クセノパネス クセノパネスの神観 クセノパネスの哲学 コラム:漂白の哲学者クセノパネス 第9講 エレア派(Ⅱ) パルメニデス(其の一) 天才も存在の構造を脱しえず、パルメニデス。 古代のパルメニデス評価 第10講 エレア派(Ⅲ) パルメニデス(其の二) 近代のパルメニデス解釈史、ないしは誤解史 再び歴史的存在としてのパルメニデスに コラム:哲学者パルメニデス 第11講 エレア派(Ⅳ) ゼノンとメリッソス (1)ゼノン 哲学者、ゼノン。 ゼノンの哲学 (2)メリッソス 第12講 エンペドクレス 哲学者エンペドクレス エンペドクレスの自然哲学 コラム:アクラガスの哲学者エンペドクレス 第13講 アナクサゴラス 伝統の哲学者、アナクサゴラス。 アナクサゴラスの自然哲学 コラム:クラゾメナイの哲学者アナクサゴラス 第14講 デモクリトス 哲学者、デモクリトス。 原子論哲学概観 第15講 ハイデガーと原初の哲学者たち――アナクシマンドロス、ヘラクレイトス、パルメニデス―― 初期ギリシアに対するハイデガーの基本スタンス アナクシマンドロス ヘラクレイトス パルメニデス 回顧と展望 人名索引
本書は、神秘と数式が交錯する天文学の歴史を、美しい200枚の絵画や画像を通じて探求する内容です。人類が手の届かない世界をどのように想像し、描写してきたかを、天動説から地動説、月の地図、太陽系の探求などを通じて紹介しています。目次には、プトレマイオスからコペルニクス、月や星、太陽系の中心としての太陽、宇宙の果てに向かう探求が含まれています。
哲学と哲学史をめぐって パルメニデス エンペドクレスとアナクサゴラス 古代ギリシアの数学 ソクラテスそしてプラトン アリストテレス ニーチェとギリシア ハイデガーと前ソクラテス期の哲学者たち 「哲学史」の作り方
この文章は、ヘーシオドスが仕事や農耕の重要性を神々の教えとして説き、人間が神ゼウスの正義を信じて労働に励むべきだと物語る内容を紹介しています。古代ギリシアの教訓叙事詩からは、詩人の苦しみが伝わります。また、『ホメーロスとヘーシオドスの歌競べ』が付載されています。
この書籍は、古代ローマ帝国の崩壊から宗教改革までの中世の歴史を新たな視点で描いています。内容は二部構成で、第一部ではローマ帝国や蛮族、ビザンツ帝国、アラブ帝国を扱い、第二部ではフランク人や修道士、騎士、十字軍戦士に焦点を当てています。著者は歴史家ダン・ジョーンズで、彼は多くのベストセラーを執筆し、テレビ番組の制作にも関わっています。翻訳はダコスタ吉村花子が担当しています。
西洋文化・伝統の根幹をなす営み、ここに始まる-西洋哲学の全体像を描き出す日本初のシリーズ、第10弾。 総論 始まりとしてのギリシア 1 最初の哲学者たち 2 エレア学派と多元論者たち 3 ソフィスト思潮 4 ソクラテス 5 小ソクラテス学派 6 プラトン 7 アリストテレス 8 テオプラストスと初期ペリパトス学派
このガイドブックは、アポロ1号から17号までの月探査の歴史を豊富な図版や一次史料を用いて解説し、宇宙開発の進展を振り返る内容です。読者は専用アプリを通じて動画や音声、3Dモデルを体験でき、月を目指した宇宙飛行士たちの苦闘とその功績が描かれています。著者は宇宙開発に詳しいロッド・パイル氏で、インタラクティブな要素も特徴です。
本書は、ギリシャ神話の入門書で、映画やゲーム、アニメなど現代の作品に影響を与えた神話の魅力を紹介しています。コメディタッチのマンガでオリンポスの12神や物語の概要をわかりやすく解説し、武器や怪物の辞典も収録。アカデミックな内容も含まれ、神々の人間味あふれるエピソードを楽しむことができます。著者は西洋史や神話に詳しい佐藤俊之と、イラストレーターの山里將樹です。
実体と属性 実体と付帯性 実体と本質 生成と質料 定義と質料 存在と形相 結合体の一性 普遍と形相 定義と形相 第一義的なデュナミス 能力と可能性 質料と可能態 エネルゲイアとエンテレケイア 現実態としての魂 本質・形相・現実態
この書籍では、古代の神々が暴れまわる様子を描き、彼らの真実の姿を身近に感じることができる内容となっています。著者は人気ブロガーで、目次には天地創造や神々の戦争、人類の誕生などが含まれています。著者の荒川祐二は、掃除活動を通じて作家としての道を歩み、ひぐらしカンナは漫画家であり、陰陽五行の宿命鑑定士としても活動しています。
本書は、中世哲学がトリビアルな問題と見なされる理由を「普遍論争」に焦点を当てて探求します。「普遍は存在するのか?」という問いを通じて、中世哲学の豊かな可能性を明らかにし、哲学入門としても適した内容です。目次には、普遍論争の歴史、記号と事物の関係、代表理論についての議論、二十世紀における中世哲学の位置づけが含まれています。著者は山内志朗で、中世哲学を専門とし、幅広いテーマで研究・執筆を行っています。
◆哲学の究極の問いに挑む 世界にはいったい何が存在するのか。この哲学を代表する問いを扱う存在論は、いまや躍進を遂げています。古代・中世にあっては思弁と自然言葉を頼りに進められていた存在論ですが、現代では論理学を武器とすることで、高度に抽象的な概念を明晰に扱うことに成功し、工学などの分野にも影響を与えるような熱気のある学問へと新生しているのです。学生と教員との対話を織り交ぜ、存在論初心者から哲学愛好家まで、存在論の最先端へと招待する待望の本格教科書の登場です。著者は九州大学文学部准教授。 現代存在論講義 I 目次 序 文 本書の成立とスタイル 本書の主題 本書を世に問う理由─なぜ『現在論在論講義』なのか 著者の立場─暗黙の前提 第一講義 イントロダクション─存在論とは何か 1 何が存在するのか 1.1 「何が存在するのか」から「どのような種類のものが存在するのか」へ 1.2 性質と関係 1.3 物とプロセス 1.4 部分と集まり 1.5 種という普遍者 1.6 可能的対象および虚構的対象 2 存在論の諸区分 2.1 領域的存在論と形式的存在論 2.2 応用存在論と哲学的存在論 Box 1 表象的人工物としての存在論─存在論の可能な定義 2.3 形式的存在論と形式化された存在論 2.4 存在論の道具としての論理学 Box 2 同値、分析あるいは存在論的説明について 2.5 存在論とメタ存在論 まとめ 第二講義 方法論あるいはメタ存在論について 1 存在論的コミットメントとその周辺 1.1 世界についての語りと思考 1.2 存在論的コミットメントの基準 Box 3 すべてのものが存在する?!─存在の一義性について 1.3 パラフレーズ Box 4 “No entity without identity”─クワイン的メタ存在論の否定的テーゼ 2 理論的美徳─「適切な存在論」の基準について 2.1 単純性 2.2 説明力 2.3 直観および他の諸理論との整合性 3 非クワイン的なメタ存在論 3.1 虚構主義 3.2 マイノング主義 3.3 新カルナップ主義 Box 5 カルナップと存在論 まとめ 第三講義 カテゴリーの体系─形式的因子と形式的関係 1 カテゴリーと形式的因子 1.1 カテゴリーの個別化─形式的因子 1.2 存在論的スクエア 2 形式的関係 2.1 4カテゴリー存在論における形式的関係 2.2 存在論的セクステットと形式的関係 Table 1 主要な形式的関係のまとめ まとめ 第四講義 性質に関する実在論 1 ものが性質をもつということ 1.1 何が問われているのか 1.2 存在論的説明あるいは分析について 1.3 実在論による説明 2 実在論の擁護 2.1 分類の基礎 2.2 日常的な言語使用 2.3 自然法則と性質 3 ミニマルな実在論 3.1 述語と性質 3.2 否定的性質 3.3 選言的性質 3.4 連言的性質と構造的性質 3.5 付録:高階の普遍者について Box 6 アームストロングへの疑問 まとめ 第五講義 唯名論への応答 1 クラス唯名論 1.1 クラスによる説明 1.2 例化されていない性質および共外延的性質の問題 1.3 クラスの同一性基準と性質 1.4 すべてのクラスは性質に対応するのか 2 類似性唯名論 2.1 類似性の哲学 2.2 類似性唯名論への反論 3 述語唯名論 3.1 正統派の唯名論 3.2 述語唯名論への反論 4 トロープ唯名論 4.1 実在論の代替理論としてのトロープ理論 4.2 トロープの主要な特性とそれにもとづく「構築」 4.3 トロープ唯名論のテーゼとそれへの反論 Box 7 トロープへのコミットメントを動機づける理由 4.4 実在論との共存 まとめ 結語にかえて─存在の問いはトリヴァルに解決されるのか? 読書案内 あとがき 索引 装幀─荒川伸生
◆存在論の豊饒な沃野への招待 論理学を武器として“存在”の謎を解明する、現代存在論の本格入門書、待望の第2弾です。学生と教員との対話のかたちで存在論の基礎を明晰に論じて好評を博した1巻に続き、2巻は4つの主題を論じる各論編。目の前にある机のような「中間サイズの物質的対象」、生物・物質・人工物の「種」、現実世界と事物のあり方が異なる「可能世界」、そして小説のキャラクターといった「虚構的対象」について、現代哲学はどのように把握するのでしょうか。より身近な対象へと問いを広げた本書は、さらに読者の哲学的探究心を揺する1冊です。著者は九州大学文学部准教授。 現代存在論講義 Ⅱ 目次 序 文 I巻のおさらい II巻の内容について 第一講義 中間サイズの物質的対象 1 物質的構成の問題 1.1 二つの相反する直観 1.2 粘土の塊と像 1.3 ニヒリズムあるいは消去主義について 1.4 像と粘土の塊との非同一性を擁護する 1.5 構成関係の定義 2 通時的同一性の問題─変化と同一性 2.1 同一性とライプニッツの法則 2.2 四次元主義 Box 1 四次元主義と物質的構成の問題 2.3 三次元主義 2.4 通時的同一性の条件あるいは存続条件について まとめ 第二講義 種に関する実在論 1 種に関する実在論 1.1 種についての直観 1.2 普遍者としての種 Box 2 種の個体説について 1.3 性質と種(その一)─偶然的述定と本質的述定 1.4 性質と種(その二)─述語の共有 1.5 性質と種(その三)─タイプ的対象としての種 Box 3 種の例化を表現する“is”は冗長ではない 2 種と同一性 2.1 数え上げ可能性 2.2 種と同一性基準 3 種と法則的一般化 3.1 法則的言明 3.2 種と規範性 Box 4 HPC説と「自然種の一般理論」 4 付録─種的論理について まとめ 第三講義 可能世界と虚構主義 1 様相概念と可能世界 1.1 様相概念─可能性と必然性 1.2 可能世界─様相文が真であるとはいかなることか 1.3 付録─可能世界意味論の基本的アイディア 2 様相の形而上学 2.1 可能世界への量化と現実主義的実在論 2.2 ルイス型実在論 3 虚構主義 3.1 反実在論としての様相虚構主義 3.2 フィクションにおける「真理」とのアナロジー 3.3 背景とメタ理論的考察 3.4 虚構主義への反論1 3.5 虚構主義への反論2 まとめ 第四講義 虚構的対象 1 基本的構図 1.1 実在論か非実在論か 1.2 虚構と真理 1.3 記述の理論 2 現代の実在論的理論 2.1 マイノング主義(その1)─〈ある〉と〈存在する〉との区分 2.2 マイノング主義(その2)─述定の区分および不完全性 Box 5 非コミットメント型マイノング主義 2.3 理論的対象説 Box 6 虚構的対象についての虚構主義 2.4 人工物説 まとめ 結語にかえて──イージー・アプローチと実践的制約 読書案内 あとがき 索引 装幀─荒川伸生
形而上学とは何か アリストテレス的形而上学を擁護する 存在と量化について考え直す 同一性・量化・数 存在論的カテゴリー 種は存在論的に基礎的か 四つのカテゴリーのうちふたつは余分か 四つのカテゴリー 新アリストテレス主義と実体 発生ポテンシャル 生命の起源と生命の定義 本質・必然性・説明 現実性なくして潜在性なし 新アリストテレス主義的実体存在論のひとつの形
著者ヨゼフ・ピーパーは、20世紀の著名なキリスト教哲学者であり、トマス・アクィナスの解釈を基にヨーロッパの伝統的な徳論を描いた名著を翻訳した。作品では、思慮、正義、勇気、節制という四つの枢要徳が、キリスト教の信仰、希望、愛とともに人々の行動規範を支える重要性が説かれている。特に思慮は他の徳の基盤であり、真実に基づく行動を促すものである。著者は、徳を人間存在全体と関連づける必要性を強調し、徳が切り離されると道徳主義に陥る危険性を警告している。
この書籍は、徳倫理学の入門書であり、善き生を求める古代から現代に至る倫理学の発展を解説しています。功利主義や義務論とは異なり、個々の行為ではなく人生全体を考察する視点を提供し、古代ギリシアや中世、西洋の哲学、中国の儒教、近現代の思想家を網羅しています。また、環境、医療、ビジネス、政治などの応用倫理についても触れています。著者は、各分野で活躍する研究者たちです。
本書は、徳倫理学を中心に、行為者の性格に焦点を当てた倫理的議論を展開する。アリストテレス以来の徳の概念を再評価し、フィリッパ・フットやロザリンド・ハーストハウスなどの主要論者の論文が収録されている。内容は、ニーチェの価値再評価から始まり、現代倫理理論、功利主義との関係、徳と正しさの相互作用など、多岐にわたるテーマを扱っている。著者は加藤尚武と児玉聡で、倫理学の専門家である。
「古代ギリシア」に関するよくある質問
Q. 「古代ギリシア」の本を選ぶポイントは?
A. 「古代ギリシア」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「古代ギリシア」本は?
A. 当サイトのランキングでは『古代ギリシアの歴史 ポリスの興隆と衰退 (学術文庫)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで93冊の中から厳選しています。
Q. 「古代ギリシア」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「古代ギリシア」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。