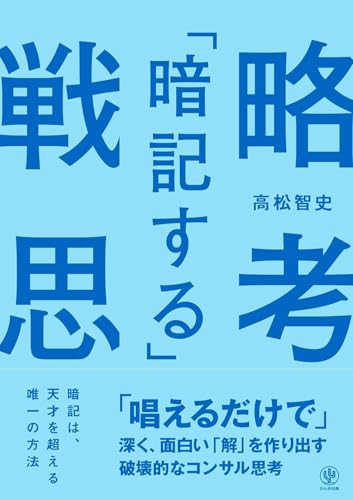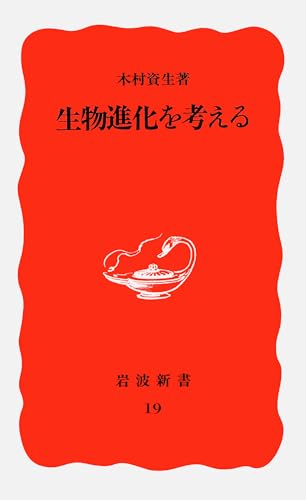【2025年】「進化」のおすすめ 本 116選!人気ランキング
- 進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる
- 生物の進化大図鑑【コンパクト版】
- 決定版-HONZが選んだノンフィクション (単行本)
- ネアンデルタール人は私たちと交配した
- カラー図解 進化の教科書 第1巻 進化の歴史 (ブルーバックス 1990)
- 進化論はいかに進化したか (新潮選書)
- 生物の進化大事典
- コンサルが「マネージャー時代」に学ぶコト 知るだけでビジネスモンスターになれる79のスキル/思考と矜持
- 分子進化と分子系統学
- 進化のはなし―地球の生命はどこからきたか (児童図書館・絵本の部屋)
身近な生き物やなじみ深い生き物はどのように進化してきたのか。生き物の家系図である「系統樹」と最新研究を踏まえながら紐解く。 身近な生き物やなじみ深い生き物はどのように進化してきたのか。生き物の家系図である「系統樹」と最新研究を踏まえながら紐解く。 身近な生きもの、なじみ深い生きものを取り上げ、それらがどのように進化してきたか、最新研究を踏まえながら紐解いていきます。 第1章は「イヌ――もっとも身近な伴侶動物の起源」「ネコ――イエネコ進化史」「ウマ・ロバ――文明に大きな影響を与えた家畜の起源」「スズメ――鳥類最大グループの多様性」といった【身近な動物たちの起源】のお話。第2章【植物とそれに依存する生き物たち】と第3章【大繁栄する昆虫たち】では、植物や菌類、昆虫の進化や起源を紹介します。そして、第4章【進化する進化生物学】では、進化生物学に関する興味深いさまざまな話題を語ります。 著者は、日本科学読物賞や日本進化学会賞・木村資生記念学術賞などの受賞歴がある、進化生物学者の長谷川政美先生。近著に『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)や『ウイルスとは何か』(中公新書)などがあります。 生き物の家系図である「系統樹」をはじめ、図や写真をふんだんに掲載。進化にまつわる信頼できる最新情報満載の一冊です。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
本書は、2022年ノーベル医学・生理学賞を受賞したスヴァンテ・ペーボ博士の回想録で、彼の数十年にわたる古代DNA研究の軌跡を描いています。ペーボは、ネアンデルタール人のDNAを復元し、その遺伝子が現生人類の中に数%残っていることを明らかにしました。苦難の中で新技術「次世代シーケンサー」を駆使し、約4万年前のネアンデルタール人のゲノム解読に成功。この発見は、現生人類がアフリカを出た後にネアンデルタール人と交配した証拠となり、彼らとの接触の実態を解明する道を開きました。科学の面白さをユーモアを交えて伝える内容です。
この書籍は、ダーウィンの進化論の正誤を整理し、進化論の歴史を解明するものです。『種の起源』が出版されてから160年が経過し、ダーウィンの理論には今でも有効な部分と誤りがあるため、多くの人が進化論を誤解しています。著者の更科功は古生物学の専門家で、進化の過程やダーウィンの考え方について詳しく解説しています。目次では、ダーウィンの正当性や進化の誤解、生物の進化の具体例が取り上げられています。
この本は、コンサルタントのマネージャーとして成功するための79の技術を紹介しています。マネージャーはクライアントや自分自身のために「お金」を生むことが重要で、3年にわたる成長過程を通じて、インテレクチャルリーダーシップやクライアントへの売り込み、部下への愛情をテーマにしています。著者は高松智史で、NTTデータやBCGでの経験を基に、思考の進化を促す内容を提供しています。
生命は困難に直面しながら絶滅と進化を繰り返し、しぶとく生き続けてきた。本書はその奇跡の物語。生命38億年の歴史を超圧縮! ジャレド・ダイアモンド(「銃・病原菌・鉄」著者)超絶賛! 本書は、生命38億年の歴史がわずか1冊に超圧縮されたサイエンス書。 地球が誕生してから、何十億年もの間、この星はあまりにも過酷な場所だった。激しく波立つ海、絶え間ない火山の噴火、大気の絶えない変化。生命はあらゆる困難に直面しながら、絶滅と進化を繰り返した。 ホモ・サピエンスの拡散に至るまで、生命は臆することなく、しぶとく生き続けてきた。生命が常に存在し、今日も存在し続けている。本書は、その奇跡の物語を描き出す。 巨大な超大陸の漂流、衝突、合体。海を住処とする「群生」するバクテリア、三畳紀の恐竜。既に絶滅したまるで異星人のような姿をした生命たち。著者は、地球上の生命の歴史を、物語のように魅力的に語る。と言っても、これは絵空事ではない。最新の科学的根拠に基づいて、地球という惑星を舞台として繰り広げられる、生命38億年の旅だ。 本書は、サイエンス雑誌「ネイチャー」の生物学シニアエディターであり、元カリフォルニア大学指導教授でもある著者が、知見の広さを活かしつつ、研究の最前線から情報を元に、地球に生命が誕生してから現在までの物語、そしてサピエンスの「未来と終末」をたどる極上の書! 1章:炎と氷の歌 2章:生物、大集合 3章:背骨のはじまり 4章:渚に打ち上げられて 5章:羊膜類あらわる 6章:トライアシック(三畳紀)・パーク 7章:進撃の恐竜 8章:素晴らしき哉、哺乳類 9章:猿の惑星 10章:世界を股にかける 11章:先史時代の終わり 12章:未来の歴史 参考文献 注釈 謝辞 訳者あとがき
本書は、著者が出会った奇妙な症状を持つ患者たちを通じて、脳の不思議な働きや仕組みについて考察する内容です。切断された手足を感じるスポーツ選手や、自分の体の一部を他人だと主張する患者などの実例を挙げ、脳の機能や意識、自己の本質に迫ります。著者は、左脳と右脳の異なる役割についての仮説や、意識に関する「ハードプロブレム」など、現代の神経科学の最前線をわかりやすく解説しています。名著が文庫化され、脳の世界の魅力を伝えています。
本書は,動物に関するフィールド生物学の基礎を学ぶための入門書である.フィールド生物学とは,生物学の中でも,進化学,系統分類学,生態学,行動学,自然保護などの野外のフィールドワークを基盤とした研究体系を指している.これまで日本では,フィールド生物学に関して専門家向けの本が多く,平易に解説した基礎的な本が少なかった.本書は読者として,大学の教養教育を学ぶ学生はもとより,高大接続教育を学ぶ高校生や大学補習教育の学生,専門教育の基礎を学ぶ学生,フィールド生物学に興味を持つ一般読者や高校生,を想定している.本書は,豊富な研究事例を専門的な観点から解りやすく解説しており,動物系のフィールド生物学に関し,概要を知り,基礎的な知識が得られるように編集してある.加えて,日本のフィールド生物学の歴史や現状に関し,簡単な解説も掲載している.【主要目次】序章 進化生態学を解説するにあたっての前書き第I部 生物の進化学第1章 生物の進化とは第2章 細胞分裂,染色体,メンデル遺伝第3章 連鎖,エピスタシス作用,性の決定と伴性遺伝第4章 量的遺伝と計量遺伝学,遺伝分散第5章 遺伝子の本体DNA,遺伝子の翻訳とタンパク質合成第6章 変異と突然変異第7章 集団遺伝第8章 種とは何か第9章 自然選択説 遺伝子プール理論による進化の再定義第10章 自然選択の実例・進化の総合説第11章 種分化理論第II部 進化から見た動物生態学第12章 生態学とはどのような学問分野だろうか第13章 個体群における個体数の増加,種内競争,大卵少産・小卵多産,rK-選択第14章 動物の生理生態第15章 種間競争,競争排除則,ニッチ分化,空間利用第16章 捕食-被捕食,メタ個体群,個体群のサイクル変動第17章 種間関係:寄生,共生,共種分化第18章 種間相互作用,栄養段階と食物連鎖,生物群集の種多様性第19章 生物地理学第20章 生態系の構造,物質循環,エネルギー流第III部 行動生態学第21章 動物行動学の歴史,行動心理学の形成第22章 動物行動学の発展第23章 血縁選択説と行動生態学の登場,真性社会性動物,子殺し行動第24章 最適戦略理論,ゲーム理論とESS第25章 性選択理論と配偶者選択行動第26章 父権の確保と精子競争第27章 性の進化,性に関する諸問題第28章 性比に関する諸問題,性比進化の仮説第29章 動物の配偶形態第IV部 環境と保全の生物学第30章 地球環境問題;地球環境問題各論第31章 生物多様性問題;森林破壊・生態系の破壊と生物多様第32章 外来種問題第33章 生物保全問題の別視点;流域思考と都市の生態系保全など終章 日本の進化学や生態学周辺の話 序章 進化生態学を解説するにあたっての前書き 第I部 生物の進化学 第1章 生物の進化とは 1.1 生物の進化の説明 1.2 進化現象の概略 1.3 進化は観察できる 1.4 現代の遺伝学と進化学の簡潔なまとめ 第2章 細胞分裂,染色体,メンデル遺伝 2.1 細胞分裂と染色体 2.2 メンデルによる遺伝の法則の発見 第3章 連鎖,エピスタシス作用,性の決定と伴性遺伝 3.1 連鎖と組換え 3.2 いろいろな遺伝とエピスタシス作用 3.3 伴性遺伝 第4章 量的遺伝と計量遺伝学,遺伝分散 4.1 量的遺伝と計量遺伝学 4.2 量的遺伝をもたらすものとしての遺伝子分散 第5章 遺伝子の本体DNA,遺伝子の翻訳とタンパク質合成 5.1 遺伝物質としてのDNA 5.2 DNA構造の解明と複製方法 5.3 DNA遺伝情報の発現のメカニズム 第6章 変異と突然変異 6.1 変異と突然変異 6.2 染色体突然変異 6.3 DNA情報の突然変異 第7章 集団遺伝 7.1 集団遺伝学 7.2 ハーディー・ワインベルグの法則 第8章 種とは何か 8.1 変異とは何か 8.2 生物における種の定義 8.3 生殖隔離 8.4 生物の分類学 第9章 自然選択説 遺伝子プール理論による進化の再定義 9.1 生物の進化と自然選択 9.2 遺伝的浮動,中立説,分子進化 第10章 自然選択の実例・進化の総合説 10.1 自然選択 10.2 自然選択の研究例 10.3 社会進化論 第11章 種分化理論 11.1 種分化の様式 11.2 異所的種分化 11.3 側所的種分化 11.4 同所的種分化 11.5 種分化が成立するまでに要する時間 11.6 その他の種分化モデル 第II部 進化から見た動物生態学 第12章 生態学とはどのような学問分野だろうか 12.1 階層構造で構成された観察単位 第13章 個体群における個体数の増加,種内競争,大卵少産・小卵多産,rK-選択 13.1 個体群動態 13.2 生活史の進化;繁殖方法の戦略 13.3 生活史形質の適応的表現可塑性 第14章 動物の生理生態 14.1 動物の資源としての食物 14.2 動物の時間制御:休眠,生物時計 第15章 種間競争,競争排除則,ニッチ分化,空間利用 15.1 資源としての食物・空間・時間 15.2 ニッチ分割と形質置換 第16章 捕食-被捕食,メタ個体群,個体群のサイクル変動 16.1 異なった栄養段階の動物の種間関係 16.2 個体数の変動とその要因,非周期的な爆発的増加 第17章 種間関係:寄生,共生,共種分化 17.1 動物の種間相互作用としての寄生と共生 17.2 生物間相互作用としての共生 17.3 送粉共生と共種分化,擬態 第18章 種間相互作用,栄養段階と食物連鎖,生物群集の種多様性 18.1 生物群集と種間相互作用 18.2 生物群集の生物多様性 第19章 生物地理学 19.1 古典的な生物地理学 19.2 島の生物群集をモデルとした現代の生物地理学 第20章 生態系の構造,物質循環,エネルギー流 20.1 生態系の基本構造 20.2 エネルギー流と物質循環 第III部 行動生態学 第21章 動物行動学の歴史,行動心理学の形成 21.1 日本における行動学分野の流行の推移 21.2 動物行動学の歴史 第22章 動物行動学の発展 22.1 ドイツにおける行動心理学の発達 22.2 闘争行動と闘争の儀式化の発見,宥和行動とあいさつ行動 22.3 行動心理学の発展的解消 第23章 血縁選択説と行動生態学の登場,真性社会性動物,子殺し行動 23.1 行動生態学の成立と血縁選択説 23.2 子殺し行動の発見と血縁選択説による再評価 第24章 最適戦略理論,ゲーム理論とESS 24.1 最適行動戦略理論 24.2 相互扶助行動とゲーム理論 24.3 代替戦略と生活史多型 第25章 性選択理論と配偶者選択行動 25.1 性選択理論の登場 25.2 配偶者選択行動 25.3 配偶者選択行動の進化に関する仮説 第26章 父権の確保と精子競争 26.1 父権の確保 26.2 交尾ガード 26.3 精子競争 第27章 性の進化,性に関する諸問題 27.1 何故有性生殖が進化したのだろうか? 27.2 何故性は2種類(メスとオス)型が圧倒的に多いのだろうか? 27.3 性の決定様式 第28章 性比に関する諸問題,性比進化の仮説 28.1 何故メスとオスの性比は1:1であることが多いのだろうか 28.2 フィシャー性比とは異なる理由で性比が0.5からずれる事例 第29章 動物の配偶形態 29.1 動物の配偶形態とは 29.2 動物の一夫一妻の説明 29.3 動物のその他の婚姻形態 第IV部 環境と保全の生物学 第30章 地球環境問題;地球環境問題各論 30.1 IGBPと地球環境問題 30.2 生態系サービスとSDGs 30.3 人新世 第31章 生物多様性問題;森林破壊・生態系の破壊と生物多様 31.1 生物多様性の3要素 31.2 気候変動と森林破壊の影響 31.3 絶滅危惧にある動物種 第32章 外来種問題 32.1 外来種問題の現状:外来種問題の5要素 32.2 外来種問題の対策と外来種の管理 第33章 生物保全問題の別視点;流域思考と都市の生態系保全など 33.1 別な視点からの外来種問題 33.2 極相林の思考と,日本土着思考としての里山運動 33.3 流域思考と都市生態系 終章 日本の進化学や生態学周辺の話
本書は、人類の進化と歴史を地図や図解を用いて解説したものです。600万〜700万年前にチンパンジーとの共通祖先から進化した人類は、多くの種が絶滅する中でホモ・サピエンスだけが生き残りました。アフリカからの拡散、様々な人類の形態、文化の発展、言語や遺伝子の多様性について詳述し、化石データや復元像を交えて人類の歴史を辿ります。著者は進化論の専門家で、古人類学的な視点から人類の足跡を探求しています。
本書は、ダーウィンの進化論に対して最初に異を唱えたファーブルの批判が、現代のネオダーウィニズムによってまだ論破されていないことを指摘し、進化論の問題点や最新の研究(ゲノム編集など)を解説しています。著者の池田清彦は、生物学者であり、構造主義生物学を提唱しています。目次には、進化論の歴史や人類の進化についての章も含まれています。
この本は、コンサルティングに必要な思考や技術が「才能」ではなく、実践的なスキルであることを強調しています。104のビジネススキルを紹介し、業界や職種に関わらず全てのビジネスパーソンに役立つ内容です。目次では、1年目から4年目までの成長過程を通じて、コンサルタントとしての心得やマネジメント技術の違いを示しています。
本書は、生物学者・五箇公一による生物学の入門書で、コロナ時代を生き抜くための知識を提供します。内容は、性の仕組みや人間社会への生物学の影響、遺伝、優生学の危険性、生物多様性、未来の生物学など多岐にわたります。著者は、メディアでの活動を通じて生物学の重要性を広めており、読者がより強く優しくなる手助けを目指しています。
プレートひしめく列島上に住む日本人にとって、最も必要なのに最も軽んじられている学問―ー「地学」の知られざる面白さを教えます! 東日本大震災を境に、日本列島は「大地変動の時代」に入ってしまった! 複数のプレートがひしめく恐るべき地理的条件にあるこの国で生き延びるには、「地学」の知識が不可欠だ。しかし、高校での履修率は低く、多くの人の地学リテラシーは中学レベルで止まったままである。ご存じ「地学の伝道師」が、地学の「おもしろいところ」「ためになるところ」だけを一冊に詰め込んだ、すべての日本人に捧げるサバイバルのための地学入門。 はじめに 第1章 地球は丸かった──人類がそのことに気づくまで コラム(1)鎌田先生はなぜ地学の研究者を志したのですか? 第2章 地球の歴史を編む──地層と化石という「古文書」 コラム(2)地学を研究していて最も驚いたことは? 第3章 過去は未来を語るか──斉一説と激変説 コラム(3)日本の地学研究や地学教育は世界で盛んなほうですか? 第4章 そして革命は起こった──動いていた大陸 コラム(4)日本の地学研究者はどのような業績をあげていますか? 第5章 マグマのサイエンス──地球は軟らかい コラム(5)最近の地学で最も目ざましい研究成果は何ですか? 第6章 もうひとつの革命──対流していたマントル コラム(6)地学研究において鎌田先生が最もこだわっているものは? 第7章 大量絶滅のメカニズム──地球が生物に襲いかかるとき コラム(7)大学で地学を学ぶにはどんな学部(学科)に進めばよいですか? 第8章 日本列島の地学──西日本大震災は必ず来る コラム(8)地学で学んだことを生かせる仕事にはどんなものがありますか? 第9章 巨大噴火のリスク──脅威は地震だけではない あとがき
この書籍は、ダーウィンの進化論が独自に生まれたものではなく、古代ギリシャから現代に至るまでの「進化」概念の歴史を探る内容です。著者は、アリストテレスや荘子、ダ・ヴィンチ、ウォレスなどの思想を通じて進化論の系譜を描き、ダーウィン以前、ダーウィンの時代、ダーウィン以後の進化論の発展を解説しています。著者は科学ジャーナリストのジョン・グリビンとメアリー・グリビンで、翻訳は水谷淳が担当しています。
本書は、研究者のためのコミュニケーション指南書であり、理系人間の特性や自己管理、交渉術、チームリーダーシップ、上司との関係構築、同僚との協力、学術生活の困難、学術から企業への移行、科学技術の未来に焦点を当てています。
ノーベル賞受賞の動物行動学者ローレンツが、ハイイロガンの雌のヒナとの出会いを通じて、動物の生態をユーモアと共感を持って描いた名作。ヒナが著者を母親と認めてついてくる様子が印象的に描かれている。第2版へのまえがきも初めて収録されている。
本書は進化論の入門書で、著者は進化生物学者の長谷川英祐。進化論の歴史や概念をわかりやすく解説し、生物の多様性と適応についての知的冒険を提供します。内容にはダーウィンの研究や遺伝子の理解、進化論の未来などが含まれ、特に専門家でない読者に向けて書かれています。進化の魅力を知りたい方に最適な一冊です。
この書籍は、脊椎動物200体の骨格を写真で紹介し、進化の記憶を探求する内容です。目次は体の構造や種の誕生、進化の過程などを含んでいます。著者は自然科学や海洋生物学の専門家であり、写真家やアートディレクターも参加しています。
この本は、「暗記する」戦略思考を学ぶための実用的なガイドです。戦略思考とは、解答や意見を生成するための考え方であり、著者は特定のフレーズを覚えることでこの技術を身につけることができると提唱しています。内容は、実際のビジネスや人生のシナリオを通じて思考を切り替える方法や、戦略思考のマップを提示し、考える力を強化するための具体的な手法を紹介しています。著者は、NTTデータやBCGでの経験を基に、面白くインパクトのある思考を追求しています。
地球に関わるあらゆる事象を丸ごと科学する学問は、未来を生きるための大切な知恵を教えてくれる。 宇宙や生命はどうやって生まれたのか。地球のエネルギー資源はどう作られているのか。気候変動や災害の原因は何か。ミクロからマクロまで、地球に関わるあらゆる事象を丸ごと科学する学問=地球科学は、未来を生きるための大切な知恵を教えてくれる。大人の学び直しにも最適な知的刺激に満ちた一冊。 第 1 章 地球・生命 1 「大ボラふき」で始まった宇宙 2 ブラックホール研究にノーベル物理学賞 3 ブラックホールの撮影成功 4 太陽系の誕生 5 地球型惑星と木星型惑星 6 冥王星は惑星ではない?! 7 月は地球の一億年後輩 8 もし月がなかったら 9 マグマオーシャンの誕生 10 原始大気の誕生 11 原始海洋の誕生 12 核・マントル・地殻の分化 13 生命が生きられる条件 14 巨大な「磁石」の地球 15 太陽風から生命を守る地磁気の「バリア」 16 動く大陸&割れる大地 17 大西洋の中央に巨大な山脈発見 18 海嶺が〝上陸〞したアイスランド 19 プルーム・テクトニクス理論の誕生 20 二億〜三億年後の「超大陸」 補講1 地球科学を学ぶ視座 第 2 章 環境・気象 21 熱輸送を支配する表層海流と偏西・貿易風 22 気候の安定に寄与する深層海流 23 台風発生のメカニズム 24 エルニーニョ現象とラニーニャ現象 25 貿易風の変化が農業とインフラに甚大被害 26 豪雨をもたらす積乱雲の連続 27 線状降水帯の災害を減らす六カ条 28 突然襲ってくる竜巻の被害 29 気流が吹き降ろす「ダウンバースト現象」 30 「炭素循環」が決める二酸化炭素濃度 31 変わる地球大気中の二酸化炭素濃度 32 固体地球の炭素循環とマントル対流 33 海水と大気の間で大循環する炭素 34 太陽との距離が平均気温に影響 35 太陽黒点の変化と地球の平均気温 36 異常気象と寒冷化を引き起こす大噴火 37 一九世紀のカルデラ噴火が引き起こした寒冷化 38 人類を絶滅寸前にした巨大噴火 39 二酸化炭素による地球温暖化への寄与度 補講2 人新世の地球科学 第 3 章 資源・エネルギー 40 海の原始生物が作った鉄鉱石 41 火山国・日本に埋もれる金鉱脈 42 特殊な噴火口が運んだダイヤモンド 43 産業の「ビタミン」レアメタルは地球上に偏在 44 レアアースをめぐる海洋探査 45 材料資源の宝庫コバルトリッチクラスト 46 脱炭素化で需要急増のリチウム 47 「枯渇しない」石油のナゾ 48 採取技術が進化する天然ガス 49 「シェール革命」のインパクト 50 可採年数「一三四年」の石炭 51 資源小国・日本で自給可能な石灰石 52 太古の豊かな海からの「贈り物」 53 「火山の恵み」の地熱資源 補講3 地球科学を築き上げた名著=ライエルの『地質学原理』 第 4 章 地震・津波・噴火 54 「大地変動」の時代に入った日本 55 首都直下地震のリスク 56 千年ぶりに直下型地震が頻発 57 二〇三〇年代に南海トラフ巨大地震 58 東日本大震災とケタ違いの被害 59 「プレ西日本大震災」 60 プレート沈み込みで地震多発 61 首都圏にひしめく三枚のプレート 62 平安時代との類似性 63 噴火予知のメカニズム 64 富士山噴火の降灰被害 65 一七年ぶり改定のハザードマップ 66 噴火前の「低周波地震」が前兆 67 北西―南東に広がる「側火口」 68 豊肥火山地域の活動再開 69 活発化する鹿児島・桜島 70 「一〇〇年に一度」大噴火で軽石漂着 71 地球の巨大な「裂け目」で噴火 72 トンガ海底火山の大噴火 補講4 地球科学を築き上げた名著――ウェゲナー『大陸と海洋の起源』 おわりに――地球科学に含まれる「実学」と「教養」 人名・事項索引
本書は、ヒトの心の働きを生物進化の観点から理解することを目的とし、進化論の基本概念や進化心理学の知見を紹介しています。生物学の知識がない読者を対象に、進化がヒトの社会行動や心の働きにどのように関わるかを解説し、進化心理学の重要なテーマについても触れています。目次には、進化の定義、ヒトの進化、利他行動、性、配偶者選択、子育て、認知、感情、協力、文化などが含まれています。著者は東京大学の准教授で、専門は社会心理学と進化心理学です。
え、そうだったの⁉「進化論の今」を知る最適の一冊!これが「ほんとうの進化論」です!実証と反証を繰り返してきた進化論の歴史、遺伝子工学が炙り出した「ネオダーウィニズム」の矛盾、「構造主義進化論」という新たなアプローチまで語り尽くす、知的テンターテインメント!「ネオダーウィニズム」とは、「ある生物の遺伝子に突然変異が起こり、環境により適応的な変異個体が自然選択によって集団内に広がり、その繰り返しで生物は環境に適応するように進化する」という理論です。19世紀の半ばにダーウィンが提唱した「進化論」に修正を加え、メンデルの「遺伝学説」やそのほかのアイデアを合わせたこの理論を、多くの人はいまだに信奉し続けていますが、この理論で進化のすべては絶対に説明できません。メディアでおなじみの生物学者、池田清彦が、進化論の歴史をたどりながら、ネオダーウィニズムの矛盾を突き、最新の知見にもとづいた「もっと本質的な進化論=リアル進化論」をわかりやすく解説します。サイエンスに興味があるビジネスパーソンから学生まで、進化論の入門としても、学び直しとしてもピッタリの一冊。知的好奇心をくすぐり、誰かに話したくなる要素が満載です!●「進化」という概念を初めて論じたラマルク●ダーウィンの「進化論」に影響を与えたマルサスの「人口論●「用不用説」と「自然選択説」の違いとは?●「ネオダーウィニズム」という折衷説●分子レベルの変異に自然選択はかからない●「遺伝子を取り巻く環境の変化」で形質は大きく変わる●生物の劇的な多様化は地球環境激変の時期に起きている●大進化はアクシデントで起こる……etc.
本書は、YouTubeで人気の新進気鋭の研究者たちが、進化生物学の魅力をマンガとクイズを通じてわかりやすく伝える一冊です。キリンの首の長さや生物の多様性、性の進化など、様々な疑問に答えながら、大学レベルの知識を楽しく学べます。美しい生物の写真も掲載されており、読むことで生物への愛着が深まる内容です。全体を通して、進化の歴史や生物の関係性を探ることで、世界の見え方が変わるかもしれません。
本書は、答えのない課題に対処するための思考技術を解説しています。著者は元戦略コンサルタントで、3000人以上に「考え方」を教えてきました。内容は、「答えのないゲーム」の戦い方、示唆の抽出、健全な議論のための思考技術、問題解決プロセスの体得、そして異なる思考スタイルの比較を含みます。この本を通じて、読者は考えることの楽しさを見出し、後悔のない選択ができるようになることを目指しています。
この書籍は、SDGsの理念の源流である生態学について、基礎から地球環境問題までを豊富な図や写真を用いて解説しており、SDGsの本質を理解する手助けをします。著者のジュリア・シュローダーは、動物生態学の博士号を持ち、進化生物学の研究と教育に従事しています。
本書は、岩や泥、水底で生活する動植物「ベントス」をテーマに、動物生態学の基礎を解説しています。豊富なオールカラーの写真や図解、用語解説、コラム、マンガを通じて、楽しく学べる内容となっています。目次には、環境、進化、多様性、生活史、種間関係、個体群動態、生物群集、生態系の物質・エネルギーの流れ、保全と利用など、幅広いトピックが含まれています。
フェルミ推定は、未知の数値を常識や知識に基づいて論理的に計算する戦略的思考を指し、単なる因数分解やコンサルティングツールではない。著者の高松智史は、この手法を用いてビジネスパーソンとしての能力を高める方法を解説しており、具体的な解法や実践的なトレーニング方法についても触れている。
なぜ進化という考え方がそれほど魅惑的なのか,脳から認知・発達,社会・文化,組織・経営に至るまで,どれほど幅広く有効に応用できるか——「進化」に憑りつかれ,誤解と闘いながら険しい道を切り拓いてきた心理学者たちから,これから進化心理学を志す読者への熱いメッセージ. Ⅰ そもそもなぜ進化なのか——進化心理学の基本問題 1 進化心理学という科学革命に参加して(デヴィッド・M・バス) 2 進化は心の仮説生成器(マーティン・デイリー&マーゴ・ウィルソン) 3 進化心理学の来し方と行く末(ロビン・I・ダンバー) 4 心という塗り絵にひそむ動機と合理性(ダグラス・ケンリック) 5 心を生む1100グラム——脳という物質 ヴィクター・S・ジョンストン) 6 反発あってこその進化心理学(ロバート・クルツバーン) II 心と社会を進化から考える 1 ヒトは社会の中で進化した(ユージーン・バーンスタイン) 2 家族関係の進化心理学——出生順と立場争い(フランク・J・サロウェイ) 3 配偶者選びは商品選びと似ている?(ノーマン・P・リー[李天正]) 4 自己欺瞞、見栄、そして父子関係(チャン・レイ[張雷]) 5 あなたの家族は誰?——血縁関係がわかるわけ(デボラ・リーバーマン) 6 集団間の偏見は自然の摂理(カルロス・ナヴァレット) III 認知と発達を進化から考える 1 120万人と人口の0.1%——書き方で数の印象が変わるのはなぜ?(ゲイリー・ブレイズ) 2 交換と安全——人はどこまで論理的か?(ローレンス・フィディック) 3 ヒトは何を覚えてきたのか——記憶の進化心理学(スタンレー・クライン) 4 ヒトの成長を進化からとらえる(ブルース・J・エリス) 5 思春期の到来と自己欺瞞(ミシェル・K・サービー) IV 意思決定と組織運営を進化から考える 1 ヒューリスティクス——不確実な世界を生き抜く意思決定の方法(ゲルト・ギーゲレンツァー) 2 進化心理学へのシンプルな道(ピーター・トッド) 3 究極の選択を迫られたとき(王暁田) 4 男と女が無理する理由(サラ・E・ヒル) 5 医者の不養生——産業組織心理学者がルールを守らないわけ(ステファン・M・コラレリ) 6 仕事と性差(キングスレー・R・ブラウン) 7 ビジネスとマネジメントに進化心理学を導入する(ナイジェル・ニコルソン) V 文化と知性を進化から考える 1 文化抜きにはヒトの進化は語れない(ピーター・J・リチャーソン) 2 制度という環境の中でヒトは生きる(山岸俊男) 3 ヒトを特別なチンパンジーたらしめるもの(長谷川寿一) 4 話すことと書くこと(デヴィッド・C・ギアリー) 5 脳が自らを研究するとき——氏と育ちの二分法を超えて(クラーク・バレット) VI 未来の進化心理学者たちへ 1 苦労の末学んだ12の教訓(ダニエル・M・T・フェスラー) 2 生態学者が進化心理学者になるまで——新しい分野への挑戦(ボビー・S・ロウ) 3 消費するヒト(ガッド・サード) 4 レポートが論文になるまで——進化心理学は科学たりうるか?(ティモシー・カテラー) 5 進化に興味をもつ人たちへの4つのアドバイス(ジェフリー・ミラー) 監訳者あとがき ○北京大学出版会から2011年に出版された“Thus Spake Evolutionary Psychologists”(『進化心理学家如是説』)を翻訳.
この書籍は、生命の本質について分子生物学がどのように答えているかを探求し、歴史的な科学者たちの思考を紹介しながら、現代の生命観を明らかにします。著者の福岡伸一は、分子生物学の成果を平易に解説し、読者の視点を変える内容を提供しています。多くの著名人から高く評価され、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞しています。
「空気」は理論的に説明できる! 終戦の御聖断は3回あった! 開戦の理由は誰もが知っていた! 対日石油全面禁輸の意外な真相? 「空気」は理論的に説明できる! 終戦の御聖断は3回あった! 開戦の理由は誰もが知っていた! 対日石油全面禁輸の意外な真相とは? ベンダサンの名義で語った本音! 「空気」は理論的に説明できる! 終戦の御聖断は3回あった! 開戦の理由は誰もが知っていた! 対日石油全面禁輸の意外な真相とは? ベンダサンの名義で語った本音! 旧日本軍の一下級将校だった山本七平氏が、その生死をさまよう過酷な体験をベースにし、日本人のために全身全霊で書き上げた『「空気」の研究』。しかし、40年以上たっても、彼の労作が現実にほとんど影響を与えていないことは、極めて不思議なことであると同時に悲しいことです。本書は、このことについての私自身のための備忘録です。(「まえがき」より) まえがき 序章 「空気の研究」の研究 赤の他人に無関心な日本人 人骨投棄作業でダウンした日本人 池田信夫氏の『「空気」の構造』 池田信夫ブログからの刺激 大東亜戦争の七不思議 「空気」の研究は「日本教」の研究でもある 「いいかげんさ」こそが日本の底力 【ミニ知識】山本七平氏と『「空気」の研究』について 第一部 大東亜戦争「意志決定」のサイエンス 第一部のはじめに 第一章 開戦のサイエンス 漠然とした疑問 開戦の経緯 昭和天皇独白録 アメリカによる〝突然〟の対日石油禁輸 対日石油禁輸の真相 バトル・オブ・ブリテンの予想外の影響 独ソ戦を絶対に必要としたドイツ 日本軍は「ダメな会社」だったのか 【まとめ】 【コラム】国民的人気があった東條英機 第二章 ゲーム理論のサイエンス 行動経済学理論で考える プロスペクト理論によるシミュレーション ゲーム理論で考える 囚人のジレンマによるシミュレーション 【まとめ】 【コラム】空気を読まないがゆえに成功した新幹線 第三章 情報戦のサイエンス 情報戦が苦手な日本 昭和16年夏の敗戦 バイウォーター『太平洋大戦争』 1941年12月8日付朝日新聞夕刊の社説 短期決戦はあり得ない 後付けだった「大東亜共栄圏」 有能な報道官だった宋美齢 【まとめ】 【コラム】大東亜戦争の開戦は真珠湾攻撃ではない 第四章 御聖断のサイエンス 1945年の「御聖断」は3回あった 6月終戦説と6月の「御聖断」 原爆投下とポツダム宣言 御聖断のインテリジェンス 一死以テ大罪ヲ謝シ奉ル 「鬼畜米英」が「マッカーサー万歳」になった理由 戦時体制は継続しているのか 【まとめ】 【ミニ知識】地方政治における「御聖断」 【コラム】オレンジ計画とレインボー・プラン 第五章 開戦を回避する方法はあったのか 開戦を回避する方法はあったのか 3つの選択肢 御聖断で開戦回避は可能なのか 日比谷焼打事件と二・二六事件 戦艦大和が特攻出撃した理由 ゲーム理論で謎は解明できるのか 【まとめ】 【ミニ解説】開戦は「英霊に相すまぬ」からか 【コラム】源氏物語と戦艦大和の共通点 第二部 古代史のオマージュとしての近代日本 第二部のはじめに 第六章 日本教とは何か 日本教の4つの「教義」 話し合い絶対主義のサイエンス 稟議書に見る話し合い絶対主義 五箇条の御誓文 一揆の規約 怨霊鎮魂のサイエンス 英霊に相すまぬ 「戦死者に申し訳ない」という呪縛 賭け事が嫌いな日本人 肝試し大会に対する日米の対照的な反応 日本一の大魔王・崇徳天皇 言霊のサイエンス 『日本教について』での言霊への言及 穢れ忌避のサイエンス 日本人は「無宗教」なのか 「天皇の人間宣言」と日本型組織 靖国神社が必要な理由 【まとめ】 【コラム】現代における「英霊に相すまぬ」 第七章 日本教のサイエンス 日本型組織の構造 アニミズムの世界 五箇条の御誓文と帝国憲法と教育勅語 アメリカの独立宣言との比較 日本教と疑似血縁集団 日本教と穢れ忌避 自転する組織 アメリカの追悼式との比較 日本型組織 存続の条件 なぜ日本国憲法は改正してはいけないのか 進化心理学で考える日本教 ネットオークション実験で考える 【まとめ】 【コラム】日本人は本当に平和的な民族なのか あとがき 主な参考文献
この書籍は、人類が地球の覇者となった理由を「先見性」に焦点を当てて探求するポピュラー・サイエンス作品です。著者は、先史時代の遺跡や動物の知性を比較し、心のタイムトラベルという能力が人類の進化を促進したと論じています。進化人類学や心理学などの学問を駆使し、未来を予測し行動することが人類の発展にどのように寄与したかを詳細に描写しています。
さまざまな生命を育む地球は,どのようにして生まれ,現在のような豊かな環境を作り出したのだろうか? 地球と同じような「生命の惑星」は他にも存在するのだろうか? 本書は,ビッグバンによる宇宙の創生から,太陽系の誕生,地球の進化,人類文明の台頭に至るまでの137億年の地球の歩みを辿る壮大な物語である.また,この物語を明らかにするために科学者たちがいかに考えて理論を組み立てたか,またその理論はどれほど信頼できるのかを,予備知識のない読者にも理解できるよう丁寧に解説する.ダークエネルギーやスノーボールアース仮説,太陽系外惑星など,近年急激に理解が進んだ話題まで網羅されており,現代宇宙科学の入門書としても最適な一冊. *推 薦* 本書は包括的で魅力的な環境科学の旅である.世界を代表する科学者チャールズ・ラングミューアーとウォリー・ブロッカーが本書を通じて教えてくれることは,生存可能な唯一既知の惑星に住む私たちの,軌跡と未来を考えるための重要な手掛かりとなるだろう. ペンシルバニア州立大学教授 リチャード・アレイ これは壮大な書物である.伝説的に著名な初版本の見事できわめて価値のある改訂版である.この新版は,初版のちりを払ったようなものではない.まったく新しい章がいくつも加えられ,新しい発見の数々がわかりやすく紹介されている.本書はまさに今必要とされるものであり,私はこの改訂版を心から歓迎する. シカゴ大学教授 レイモンド・ピエールハンバート NASAは現在私たちのとなりの惑星である火星の生存可能性を調査している.洞察に満ちかつ親しみやすい本書は,まさに今この時に,私たちの地球の生存可能性を理解することがいかに重要かを思い出させてくれる.本書は総合的かつ最新であるとともに,新しい発想,不完全な理解,および論争が,科学知識をいかに進歩させるかをあきらかにする. マサチューセッツ工科大学教授 ロジャー・エヴァレット・サモンズ 著者まえがき 訳者まえがき 第1章 序論 自然システムとしての地球と生命 はじめに 「システム」 「自然システム」の特徴 まとめ 参考図書 第2章 背景 ビッグバンと銀河の形成 はじめに ビッグバン ビッグバン仮説に対するさらなる証拠 膨張する宇宙とダークエネルギー ビッグバン直後の時期 まとめ 参考図書 第3章 原材料 恒星の元素合成 はじめに 太陽の化学組成 水素,ヘリウム,銀河,恒星 ビッグバンの間の元素合成 恒星内元素合成 中性子捕獲による元素合成 恒星の元素合成仮説を支持する証拠 まとめ 参考図書 第4章 予備加工 有機分子と無機分子の合成 はじめに 分子 物質の状態 分子の二大グループ:無機分子と有機分子 分子合成の環境 まとめ 第5章 重量構造物 太陽系星雲から惑星と衛星をつくる はじめに 惑星の重要な統計 隕石からの証拠 太陽系形成のシナリオ 地球型惑星の化学組成を理解する まとめ 参考図書 第6章 スケジュール 放射性核種によるタイムスケールの定量 はじめに 放射性崩壊を用いる年代測定 元素の年齢 消滅放射性核種を用いた太古の短寿命過程の解明 まとめ 参考図書 第7章 内装工事 コア,マントル,地殻,海洋,大気の分離 はじめに 地球の構造 地球の層の化学組成 地球の層の起源 まとめ 第8章 近くの天体と争う 衛星,小惑星,隕石,衝突 はじめに 太陽系の天体の多様性 月の起源 衝突を用いて惑星表面の年代を決定する 月の内部構造の形成 太陽系における衝突の歴史 地球への影響 将来の衝突 まとめ 参考図書 第9章 環境を快適にする 流水,温度制御,日よけ はじめに 惑星の揮発性物質の収支 40億年前の水の証拠 表面の揮発性物質の制御 表面温度 地球の長期のサーモスタット 日よけ まとめ 参考図書 第10章 循環を確立する プレートテクトニクス はじめに 静的な地球という観点 大陸移動説 海洋底からの新しいデータ 古地磁気からの証拠 地震活動度の全球分布 プレートテクトニクス理論 プレートテクトニクス革命 時間を通した運動 まとめ 参考図書 第11章 内部の循環 マントル対流とその表面との関係 はじめに 地球内部の動き マントル対流 プレートの形状はマントルの対流セルに対応しているか? マントルの能動的上昇流:プルームの頭と尾 拡大中心における海洋地殻の生成 まとめ 参考図書 第12章 層と層を結びつける 固体の地球,液体の海,気体の大気 はじめに 全球的システムとしての海嶺 海嶺と生存可能性 収束境界における地球化学過程 プレート再循環の最終結果 まとめ 参考図書 第13章 表面に入植する 惑星過程としての生命の起源 はじめに 生命と宇宙 生命の単一性 最初の生命 生命の起源 生命に至る道程 生命の起源に関する一般的考察 まとめ 参考図書 第14章 競争を生き抜く 生物多様性の創造における進化と絶滅の役割 はじめに 岩石記録からあきらかにされた生命と地球の歴史 化石と現在の生命を結びつける:進化論 DNA 革命 進化の半面としての絶滅 まとめ 参考図書 第15章 表面にエネルギーを与える 生命と惑星の共進化による惑星燃料電池の形成 はじめに 電流としての生命 還元的な初期地球 最初の3 つのエネルギー革命 惑星の燃料電池 まとめ 第16章 エクステリアの改装 惑星表面の酸化の記録 はじめに 地球と酸素 炭素:酸素生産の記録 炭素:岩石記録からの証拠 鉄と硫黄:酸素消費の記録 鉄:岩石記録の証拠 硫黄:岩石記録の証拠 顕生代の高い酸素濃度の証拠 20 億年前から6 億年前の酸素 酸素の全球収支 まとめ 参考図書 第17章 惑星の進化 破局的事変の重要性と定向進化の問題 はじめに 顕生代の惑星進化 プレートテクトニクスと進化 惑星進化の原理とは? 定向進化の可能性に関する考察 まとめ 参考図書 第18章 気候に対処する 自然の気候変動の原因と結果 はじめに 中期間の気候変動:氷河期 軌道周期 急激な気候変動 人類の衝撃 まとめ 参考図書 第19章 ホモ・サピエンスの興隆 地球の資源を利用した惑星支配 はじめに 人類時代の夜明け 人類のエネルギー革命 地球の宝箱 資源の分類 リサイクルできない有限の資源 まとめ 第20章 舵を取る人類 惑星の文脈における人類文明 はじめに 地球に対する人類の衝撃 将来の予測 可能な解決策 より広範な問題 人類代? まとめ 参考図書 第21章 私たちはひとりぼっちか? 宇宙の生存可能性についての疑問 はじめに 惑星探査 銀河系の生存可能な惑星の数:確率論アプローチ 惑星の文脈における人類文明:宇宙の進化と生命 まとめ 参考図書 用語集 索 引
本書は、フェルミ推定を通じて問題解決の技術を習得する方法を解説しています。フェルミ推定を磨くことで、数字に強くなり、ロジカルな思考や戦略的思考を自然に身につけることができます。内容は、具体的な市場規模の推定事例やビジネスでの応用、さらには新たな問題解決の思考法についても触れています。著者は高松智史で、一橋大学卒業後、NTTデータやBCGでの経験を持ち、「考えるエンジン講座」を提供しています。
この書籍では、人間の進化と幸せの関係について探求しています。著者のウィリアム・フォン・ヒッペルは、炎上やフェイクニュース、格差社会などのヒトの行動が、古代からの生存戦略に根ざしていると論じています。内容は、ヒトの進化の過程や社会的な側面、そして進化がどのように人間に幸せをもたらしたかを解説しています。著者は心理学の教授で、オーストラリアに在住しています。
何をすべきか自分で判断して行動する「行為主体性」はいかに進化したのか? 認知心理学の巨人トマセロが斬新な新理論を提唱する。 何をすべきか自分で判断し、能動的に行動する――それが行為主体性だ。別々に扱われてきた動物と人間の心理学研究の成果を統合し、人間の行為主体性が進化した道筋を示す新理論を提唱する、認知心理学の巨人トマセロの新理論。 認知心理学の巨人トマセロが提唱する、画期的な新理論!何をするべきかを自分で意思決定し、能動的に行動する能力、それが「行為主体性」だ。生物はどのようにして、ただ刺激に反応して動くだけの存在から、人間のような複雑な行動ができるまでに進化したのか? 太古の爬虫類、哺乳類、大型類人猿、初期人類の四つの行為主体を取り上げ、意思決定の心理構造がどのように複雑化していったのかを読み解いていく。進化心理学、進化生物学、行動生態学、認知科学など、これまで別々に取り上げられることの多かった人間と動物の研究をまとめ上げ、包括的な行為主体のモデルを提唱し、その進化の道筋を解明する画期的な新理論。◆賞賛の言葉◆「説得力があってわかりやすい、すでに古典というべき書。科学を前進させ、人間の本性を学ぶ次世代の学徒に読み継がれることだろう」――ブライアン・ヘア(デューク大学進化人類学教授、『ヒトは〈家畜化〉して進化した』著者)「心理学の第一原理は心理や行動ではなく、行為主体性であるべきだという斬新な洞察に満ちている」――デイヴィッド・バクハースト(カナダ・クイーンズ大学卓越教授) ◆目次◆ 第1章 はじめに 動物心理に対する進化生物学的アプローチ/人間の心理に対する進化的なアプローチ/本書の目標 第2章 行為主体のフィードバック制御モデル 行為主体の機械モデル/生態系が課す問題のタイプ/絶滅種のモデルとしての現存種 第3章 目標指向的行為主体――太古の脊椎動物 生きた(非行為主体的)アクター/目標指向的行為主体/生態的ニッチと経験的ニッチ/行為主体の基盤 第4章 意図的行為主体――太古の哺乳類 情動、認知、学習/実行層/行動実行に関する意思決定/実行(認知)制御/道具的学習/自己の目標指向的な行動や注意の経験 第5章 合理的行為主体――太古の類人猿 社会生態的な難題/因果性の理解/意図的な行動の理解/合理的な意思決定と認知制御/反省層とその経験的ニッチ/だが大型類人猿はほんとうに合理的なのか? 第6章 社会規範的行為主体――太古の人類 初期人類の協働における共同的行為主体性/共同目標を設定する/役割の連携/協力し合いながら協働を自己調節する/協力的合理性とその経験的ニッチ/文化集団における現生人類の集合的行為主体性/集合的な目標の形成/社会的役割の連携/社会規範を介しての集合的な自己調節/規範的合理性とその経験的ニッチ/人間の行為主体性の複雑さ 第7章 行動組織としての行為主体 補足説明A 補足説明B
本書は、樹木の根が森林生態系を支え、減災機能や物質循環に果たす役割について解説する唯一の教科書です。樹木の根は、太い根で支え合い、細い根で養水分を吸収することで、環境に適応しながら生育します。内容は、根の構造や機能、環境変動への反応、減災機能、そして生態系サービスに関する知見を網羅しており、持続可能な森林への貢献を強調しています。著者は森林科学や生態学の専門家です。
この本は、著者がBCGでの経験を通じて得た「行動を変える」技術「スウィッチ」を紹介しています。著者は、戦略やコンサルティングのセンスがなかったものの、「チャーム」を活かして先輩たちから多くのことを学びました。目次には、愛や想像力、チャーム、論点の重要性、示唆の見抜き方などが含まれており、行動や人生を今すぐ変える方法が提案されています。著者は一橋大学卒業後、NTTデータとBCGでの経験を活かし、考えるエンジン講座を設立しました。
本書は、人間のセクシャリティが動物と比べて奇妙であることを探求し、性のあり方が社会の在り方に与える影響を考察しています。著者は、動物の性行動と人間の性行動を対比しながら、人間の性生活の進化や性の楽しさの理由を解明します。目次には、男女の利害対立や授乳の役割など多様なテーマが含まれています。著者は進化生物学者のジャレド・ダイアモンドと動物行動学者の長谷川寿一です。
臨機応変に維持される鳥の群れの仕組みを,社会生物学の知見から鳥類学者が柔らかい語り口でひもとくよみもの。全国群れマップ・野鳥調査ガイド付き! 臨機応変に維持される鳥の群れの仕組みを,社会生物学の知見から鳥類学者が柔らかい語り口でひもとくよみもの。【科学のとびら10 鳥はなぜ集まる?(1990年刊)】の改訂版。全国群れマップ・野鳥調査ガイド付き! 1. いろいろな群れ 2. ねぐらはエサの情報センター? 3. 鳥は寝る前に集まる 4. みんなで食べるとどうなるか 5. 弱い鳥でもみんなで防衛 6. 目の数を増やすか,うすめるか 7. 一羽と群れとどっちがいい? 8. 群れは利己性の産物? 9. 警戒声は誰のため? 10. 小鳥は昼間に仇討ち ―モビングの行動学 11. 群れの中にも不平等 12. 鳥たちの寄合所帯 13. みんなで通ればこわくない 14. 寄らば混群のかげ 15. 群れの中でもだましあい 16. 行動生態学から群れを考える
仲直りの機能とメカニズムを,進化生物学のモデル研究,動物行動学の研究,心理学の研究を駆使し,進化心理学の視点から読み解く。 いざこざを解決する「仲直り」はヒト以外の様々な動物にも見られる。赦しと謝罪の2つの側面をもつ仲直りの機能とメカニズムを進化生物学のモデル研究,動物行動学の研究,心理学の研究を駆使し,進化心理学の視点から読み解… ケンカや誤解から生じるいざこざを解決する「仲直り」は,ヒト以外のさまざまな動物にも見られる興味深い現象です。赦しと謝罪の2つの側面をもつ仲直りの機能とメカニズムを,進化生物学のモデル研究,動物行動学の研究,心理学の研究を駆使し,進化心理学の視点から読み解きます。 第1章 動物たちの仲直り 第2章 行動の進化の理 第3章 赦すことの理 第4章 和解シグナルの進化 第5章 謝罪の理 第6章 仲直りの至近要因 第7章 仲直りする力
本書は、経済学の魅力を多角的に探求し、歴史的な出来事や理論を通じて経済の力がどのように世界を動かしてきたかを解説します。古代から現代までの経済発展や重要な人物を振り返りながら、読者が経済学をより深く理解できるように導く一冊です。著名な経済学者たちからも高く評価されており、経済に興味がある人にとって必読の書とされています。
本書は歴史学、考古学、経済学、経済史、などの専門家が、それぞれのテーマでの比較史、自然実験で分析した論文を集めたものである。 本書は歴史学、考古学、経済学、経済史、地理学、政治学など幅広い専門家たちがそれぞれのテーマでの比較史、自然実験で分析した論文を集めたものである。比較も2つから81の島々や時代は過去から現在まで幅広く扱っている。 2019年ノーベル経済学賞を著者のお一人(第6章執筆)アビジット・バナジー氏が受賞しました! 自然科学の実験室の実験(ラボ実験)のように、歴史学や経済学は実験を行うことができない。様々な要因が存在してそれをコントロールすることが不可能であるからだ。しかし、近年、計量・統計分析が洗練され、ラボ実験やフィールド実験が盛んに行われるようになってきた。さらにまったくコントロールされない現実の対象を分析するための自然実験も行われるようになってきた。 本書は、歴史学、考古学、経済学、経済史、地理学、政治学など幅広い専門家たちが、それぞれのテーマでの比較史、自然実験で分析した論文を集めたものである。比較も2つの対象から81の島々の対象や233の地域を対象にしたものまで、地域は太平洋の島々からアメリカ、中米、ヨーロッパ、インドまで、また時代は過去から現在まで幅広く扱っている。 プロローグ ジャレド・ダイアモンド+ジェイムズ・A・ロビンソン 第1章 ポリネシアの島々を文化実験する パトリック・V・カーチ 第2章 アメリカ西部はなぜ移民が増えたのか ――19世紀植民地の成長の三段階 ジェイムズ・ベリッチ 第3章 銀行制度はいかにして成立したか ――アメリカ・ブラジル・メキシコからのエビデンス スティーブン・ヘイバー 第4章 ひとつの島はなぜ豊かな国と貧しい国にわかれたか ――島の中と島と島の間の比較 ジャレド・ダイアモンド 第5章 奴隷貿易はアフリカにどのような影響を与えたか ネイサン・ナン 第6章 イギリスのインド統治はなにを残したか ――制度を比較分析する アビジット・バナジー+ラクシュミ・アイヤー 第7章 フランス革命の拡大と自然実験 ――アンシャンレジームから資本主義へ ダロン・アセモグル+ダビデ・カントーニ+ サイモン・ジョンソン+ジェイムズ・A・ロビンソン あとがき 人類史における比較研究法 ジャレド・ダイアモンド+ジェイムズ・A・ロビンソン 原注
本書は、動物のコミュニケーションや言語の起源について高校生と考察する内容です。第1章では進化生物学を通じてコミュニケーションの本質を探り、第2章では言葉の起源について「歌」が重要であることを論じます。第3章では感情の伝達について考察し、第4章では思考や意識の形成における他者とのつながりを探ります。著者は東京大学の岡ノ谷一夫教授で、生物心理学や動物行動学が専門です。
この文章は、生態学に関する内容の目次を示しており、遺伝子や地球環境から生物の多様性、進化、適応戦略、行動、相互作用、生物群集、エコシステムの構造と機能、さらには保全と環境問題に至るまでの幅広いテーマを扱っています。
この書籍は「食べる」「考える」「結婚する」といった日常的な行動を、行動の機能と進化の観点から解説する中項目事典です。人間行動進化学の視点を通じて、様々な行動についての理解を深める内容で、コラムや用語解説も含まれています。著者は生物科学や心理学の専門家で、各々が大学教授として活躍しています。
この書籍は進化心理学について、他の諸分野との関連や最新の研究成果を解説しています。内容は、進化心理学の定義、神経・生理、感情、認知、性、発達、パーソナリティ、社会、言語、文化、道徳、宗教、教育、犯罪にわたる幅広いテーマを網羅しています。著者は小田亮と大坪庸介で、それぞれ生物科学と心理学の専門家です。
本書は、河川が人類の文明に与えた影響を探求する文明論であり、河川の存在が定住パターンや戦争、国境、貿易にどのように関わってきたかを多彩なエピソードを通じて描いています。著者は、河川がどのように人類の生活様式を形成してきたかを明らかにし、その「見えない力」を浮き彫りにしています。
この書籍は、エピジェネティクスという新しい生命科学の概念を探求し、従来のゲノム中心の生命観を変える内容です。エピジェネティクスは遺伝や突然変異とは異なり、ゲノムに上書きされた情報がさまざまな生命現象や病気に影響を与えることを解説しています。著者の仲野徹は、この分野の専門家であり、エピジェネティクスの分子基盤、植物や動物における応用、病気との関連について詳述し、生命の神秘を楽しく伝えています。
細胞間の振動からAIの作曲まで、音楽はどのように生まれ、人類の進化と文明に何をもたらしたのか。世界をリードする音楽学者が描き出す壮大な人類史。「音楽のための『銃・病原菌・鋼鉄』だ」 ダニエル・レヴィティン評
この書籍は、農業革命と国家形成に関する新たな視点を提供し、定住と穀物栽培が人類や動植物に与えた影響を探求しています。著者は、古代国家が形成される過程で非エリート層がどのような負担を強いられたのか、また農業国家の強制手法やその脆弱性について考察しています。最新の考古学や人類学の成果を基に、従来の歴史観を覆す壮大な仮説が展開されています。著者はイェール大学の教授であり、農民の抵抗に関する研究を行っています。
この本は、生物が独自の知覚と行動で形成する「環世界」の多様性を探求し、動物の感覚から知覚、行動への影響を考察します。ユクスキュルの理論に基づき、行動は環世界に依存していることを示し、生き物の世界像を理解する旅に誘います。目次には、環境、知覚時間、探索像など多様なテーマが含まれています。
本書では、飼い猫が描かれた猫の絵に反応する様子から、動物の知覚と現実認識について考察されている。著者は、動物が知覚する世界がそれぞれの現実であり、客観的な環境は存在しないと主張。これを「イリュージョン」と名づけ、動物行動学の視点から人間の認識論に迫る内容となっている。著者は日高敏隆で、動物学の権威として知られる。
本書は、量子力学の創始者が生命の本質を探求した名著であり、遺伝の仕組みや染色体の行動を物理学と化学の観点から説明しています。著者は、負のエントロピー論などのテーマを通じて、生命現象の背後にある物理法則の意義を考察し、決定論と自由意思についても触れています。目次は古典物理学者のアプローチから始まり、遺伝、突然変異、量子力学の発見、そして生命の物理法則への支配に関する章で構成されています。
この書籍は、ダーウィンの進化論の発展と分子生物学が進化の理解に与えた影響を探求しています。内容は、生物の多様性、進化の歴史、遺伝学に基づく進化機構、突然変異、自然淘汰、集団遺伝学、分子進化、そして中立説に至るまで多岐にわたります。また、進化の道筋を辿りながら人類の未来についても考察しています。著者は、進化の概念をわかりやすく解説し、進化遺伝学的視点を提示しています。
この文章は、生物の多様性と進化に関する内容を紹介する書籍の構成を示しています。内容は以下の通りです: 1. **生物の多様性と適応** - 種の多様性や行動のデザインを探る。 2. **生命の長い鎖** - 進化、DNA、遺伝子の役割を解説。 3. **自然淘汰と適応** - 適応のメカニズムや自然淘汰の働きを説明。 4. **変異の性質と淘汰の種類** - 変異の源や淘汰の種類を詳述。 5. **新しい種の誕生** - 種の定義や新種の出現を考察。 6. **進化的軍拡競争と共進化** - 生物間の相互作用と競争を説明。 7. **最適化の理論** - 生物の行動戦略を探る。 8. **頻度依存による自然淘汰** - ゲーム理論を用いた進化の戦略を分析。 9. **雄と雌の違い** - 有性生殖の意義と性差の進化を考察。 10. **進化の考えがたどった道** - 進化の歴史と理論の発展を振り返る。 全体を通じて、生物の進化や適応のメカニズム、種の多様性についての理解を深める内容となっています。
脳神経科医オリヴァー・サックスが、奇妙な症状を抱える患者たちの物語を描いた医学エッセイ集。24篇から成り、喪失、過剰、移行、純真といったテーマで、患者たちが障害を抱えながらも人間らしく生きる姿を愛情を込めて表現している。文庫化されたこの作品は、感動と驚きに満ちている。著者は医学と文学の両方で評価されている。
この書籍では、昆虫が人間の行動や社会の多くの側面を先取りしていることを探求しています。狩猟採集や農業、戦争、繁殖行動など、さまざまなテーマを通じて、昆虫の多様性や彼らの社会生活について解説。著者は、昆虫研究の第一人者であり、彼らの驚くべき生態や人間との関わりを紹介しています。
本書は、動物のサイズがその行動や寿命、時間の感覚に与える影響を探求し、サイズに基づく動物のデザインの理解を深める新しい生物学入門書です。心臓の鼓動やエネルギー消費はサイズに関係なく共通であることを示し、動物の特性を通じて人類の未来に役立つ洞察を提供します。目次には、サイズと進化、エネルギー消費、行動圏など多様なテーマが含まれています。
脳科学者のジル・ボルト・テイラーは、37歳で脳卒中に襲われ、脳の機能が著しく損傷しました。8年間のリハビリを経て復活し、脳に関する新たな発見や気づきを得た彼女の経験を描いた感動的なメモワールです。著者はハーバード大学で脳神経科学を研究し、精神疾患の啓発活動にも取り組んでいます。
この書籍は、人体を構成する多様な細胞について解説しており、数百種類の細胞がそれぞれ異なる役割を持つことを示しています。著者たちは、細胞を「パスタづくりの巨匠」や「スポーツ万能」などの比喩を用いて表現し、最新技術でその多様性を捉えています。著者は藤田恒夫と牛木辰男で、共に新潟大学での教授職を経て名誉教授となっています。
全ての人にオススメしたい書籍。我々ホモ・サピエンスはなぜここまで繁栄することができたのかを著名人類学者が語る。全世界で大ヒットしているだけあって非常に面白い。ボリューミーだが、目からウロコの内容ばかりでどんどん読み進められる。
この書籍では、セックス、ドラッグ、アルコール、食事、ギャンブルなどの「快感」とその「依存」のメカニズムを、実験やエピソードを通じて解明しています。著者デイヴィッド・J・リンデンは神経科学者で、脳の快感に関する最新の科学的知見を紹介し、なぜ私たちが特定の行動にハマるのかを探求しています。目次には、快感の神経機構や依存症に関する章が含まれています。
この作品は、人類の約20万年の歴史を通じて心の進化を探るドキュメンタリーを基にした科学ノンフィクションです。著者は、心理学や遺伝子学、経済学、脳科学などの知見を用いて、心の変遷を解明します。各章では、協力や道具の使用、農業革命、貨幣の誕生など、人類の進化における重要なテーマが扱われています。第10回パピルス賞を受賞した作品です。
利根川進氏が1987年にノーベル生理学・医学賞を受賞した背景や彼の研究について、立花隆氏が20時間にわたってインタビューを行った内容を紹介。分子生物学の進展や利根川氏の論文の重要性を探りながら、最先端の生命科学の世界を解説している。目次には、彼の経歴や科学に対する考え方が含まれている。
本書では、ヒトとサルの遺伝子がほぼ同じであるにもかかわらず、外見や特性が異なる理由を探ります。ヒトゲノムのわずか2%が遺伝子部分で、残りの98%は「非コードDNA」と呼ばれ、かつては無駄なものと考えられていました。しかし、最近の研究でこの非コードDNAが生命の進化や老化、寿命に重要な役割を果たしていることが明らかになりました。著者はこの「暗黒領域」の機能を解説し、サルとヒトの違いを生み出すメカニズムを豊富なエピソードと共に紹介します。
この書籍は、微生物や寄生生物が人間の脳や神経に与える影響について探求しています。寄生生物は感情や行動を操り、気分や体臭、人格、認知能力を変えるだけでなく、空腹感や体重もコントロールします。また、ネコやイヌから感染する寄生生物が交通事故や学習能力の低下に関与することも示されています。さらに、これらの生物は道徳や文化、社会的な違いにも影響を与えることが明らかになっています。著者は神経寄生生物学の専門家に取材し、これらの複雑なメカニズムを解明しています。
この文章は、R・カーソンが化学薬品の乱用による自然破壊と人体への影響を告発した著作について紹介しています。彼女の警告は、初版から数十年経った今でも衝撃的であり、人類はこの問題の解決策を見出していないと述べています。また、作品は20世紀のベストセラーであり、新装版が待望されていることも触れています。目次には、自然や環境に関する多様なテーマが含まれています。
「進化」に関するよくある質問
Q. 「進化」の本を選ぶポイントは?
A. 「進化」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「進化」本は?
A. 当サイトのランキングでは『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで116冊の中から厳選しています。
Q. 「進化」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「進化」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。