【2025年】「財務会計」のおすすめ 本 174選!人気ランキング
- 会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方
- 【新版】財務3表一体理解法 (朝日新書)
- 会計学入門〈第5版〉 (日経文庫)
- 【新版】財務3表図解分析法 (朝日新書)
- スタンダードテキスト財務会計論I 基本論点編〈第17版〉
- 財務諸表の見方<第14版> (日経文庫)
- 財務会計講義〈第26版〉
- イチからわかる!「会計」の基本と実践
- 管理会計〔第七版〕
- ざっくり分かるファイナンス 経営センスを磨くための財務
この書籍は、シリーズ累計80万部を突破した会計学習の定番教科書の再改訂版で、初学者向けに基礎を重視した内容になっています。財務3表を取引ごとに作成する「会計ドリル」を中心に、会計の基本から読み解き方までをやさしく解説し、全ビジネスパーソンにとって必読の一冊です。著者は國貞克則で、豊富な実務経験と教育背景を持っています。
この書籍は、財務3表の分析法を図解化し、同業同規模の企業を比較することで経営の全貌を明らかにする内容です。特に、キャッシュフロー分析を通じて経営戦略を解明し、会計の専門知識がない人でも理解できるように再編成されています。最新の決算データを用いて、グローバルIT企業の財務特徴も解説しています。著者は経営の専門家で、セミナーやeラーニング講座も担当しています。
このテキストは、財務会計の基本概念や個別財務諸表について詳述した、詳細な財務会計の教科書です。特に会計基準の解説だけでなく、その背後にある考え方を明確にし、論点整理が分かりやすくなっています。設例や仕訳を用いて理解を深める工夫がされており、最新の四半期開示制度にも対応しています。公認会計士や税理士試験の対策に適した基本書です。著者陣は各大学の教授で、会計分野での豊富な経験を持っています。
本書は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を基礎から最新の改正まで解説したロングセラーの最新版です。初心者からベテランまで幅広く支持されており、最新の会計基準や実例を交えた内容が特徴です。読者は銀行員や経理担当者、学生など多岐にわたり、財務諸表を理解するための実用的な情報を提供しています。目次には、各種財務諸表の解説や見方、企業価値の理解に関する章が含まれています。
このテキストは、財務会計の全体像を解説した定番の教科書であり、学部学生やビジネスパーソンに広く支持されています。公認会計士や税理士試験の基本書としても適しており、最新の企業会計動向や制度改正を反映した30年以上の歴史を持つ最新版です。目次には、財務会計の機能から財務諸表の作成まで、幅広いトピックが含まれています。
この書籍は、ポスト会計時代に必要な基本知識を提供しています。内容は、会計とファイナンスの違い、ファイナンスの基本、時間価値、お金の評価、投資判断基準、借入と返済方法について構成されています。著者の石野雄一は、財務戦略コンサルタントとしての経験を持ち、企業戦略と資本市場に焦点を当てたコンサルティングを行っています。
本書は、会計の仕組みを人間ドラマと結びつけて紹介する「会計エンタテインメント」です。著名人のエピソードを通じて、簿記や財務会計、管理会計について楽しく学べる内容になっています。数字や専門用語は使わず、波乱万丈な物語を展開しながら、会計の歴史や重要な革命を解説しています。著者は会計士であり、講師としての経験を活かして、読者に好奇心を持って会計を理解してもらうことを目指しています。
本書は、コーポレートファイナンスの基礎を分かりやすく解説した入門書であり、企業価値向上のための重要な知識を提供します。新版では新たなテーマを加え、理解が難しい項目について丁寧に説明しています。目次には、リスク・リターン、キャッシュフローの現在価値、企業の投資決定、資金調達、利益還元などが含まれています。著者は京都大学の教授、砂川伸幸です。
この書籍は、財務会計に関する詳細なテキストで、金融商品やデリバティブ、リース、減損、研究開発費、退職給付など幅広いトピックを扱っています。会計基準の解説だけでなく、その基礎的な考え方にも重点を置き、論点整理や具体的な事例を通じて理解を深める内容です。第17版では最新のリース会計基準などの改正にも対応しており、公認会計士や税理士試験の対策に最適な基本書となっています。著者陣は会計学の専門家で構成されています。
このテキストは、財務会計に関する詳細な教材で、基本論点編では基礎概念や個別財務諸表の主要項目を解説しています。会計基準の考え方を明確にし、設例や仕訳を用いて理解を助ける内容です。第18版では、四半期開示制度の見直しや制度改正に対応し、全体の内容も見直されています。著者は会計学の専門家で、各自が多くの学術的役職を歴任しています。
本書は、ビジネスパーソンに必要な財務会計の基本知識を英語と日本語で解説し、架空のストーリーを通じて事業活動が財務三表にどのように反映されるかを示します。財務諸表の読み方や財務分析手法、会計の限界についても触れ、グローバルに活躍するためのスキルを養う内容となっています。著者は昭和女子大学の教授で、企業財務や経営管理の豊富な経験を持っています。
本書は、会計の基礎から重要論点までを網羅的に解説した入門書です。著者は人気講師で、会計ルールや論点の「考え方」をわかりやすく説明し、初学者でも理解しやすい内容になっています。図解や設例を多用し、設例から論点を説明する逆のアプローチを採用しているため、学習が進めやすいです。公認会計士や税理士試験、簿記検定試験を目指す人や、企業の経理部門に配属されたばかりの人に適しています。
この書籍は、財務3表の基本から解説し、決算書の読み方や会計の全体像を分かりやすく学べる入門書です。図解を用いて財務3表のつながりを直感的に理解でき、経営分析や会計の実務での活用方法も紹介しています。著者は『財務3表一体理解法』の著者で、会計教育やコンサルティングに携わっています。
この書籍は、企業分析において財務情報だけではなく、非財務情報も重要であることを強調しています。決算書や有価証券報告書、統合報告書など多様な情報を活用することで、企業のビジネスモデルをより深く理解できると述べています。目次には、収益構造やビジネスモデルの比較、キャッシュフローの分析、企業評価、ESGの視点、IPO分析など多岐にわたるテーマが含まれています。著者は、財務コンサルタントとしての経験を持つ村上茂久氏です。
本書は、大学生や社会人向けのコーポレートファイナンスとバリュエーションのテキストで、企業価値向上や持続可能な成長に関する現代ビジネスの重要な概念を学ぶことができます。主な特徴は、事業戦略との関連を重視、ESGの要素を取り入れ、エクセルを用いた実践的な学習を提供している点です。内容はコーポレートファイナンスの基礎から企業価値評価まで幅広く、著者は京都大学やシスメックスの専門家です。
本書は、クイズと会話を通じて実在企業のビジネス戦略を理解するための会計入門書の続編です。財務3表の基礎から始まり、時系列分析や競合比較分析、事例分析を通じて、企業の決算書を読み解く方法を学べます。著者は公認会計士で、Twitterで10万人のフォロワーを持ち、財務諸表の理解を広める活動をしています。豊富な図解とキャラクターの会話を通じて、読者は実践的な分析視点を身につけることができます。
この文章は、メアリー・バフェットとデビッド・クラークによる書籍の目次と著者情報を紹介しています。内容は、財務諸表の読み方やバフェット流の投資法、企業評価の方法について述べられており、特に永続的競争優位性を持つ企業に焦点を当てています。著者はそれぞれ作家、ポートフォリオ・マネジャー、翻訳者としての経歴を持っています。
この本は、会計の基本を理解するためのストーリーを提供しています。主人公あかねがアクセサリー販売の会社を設立し、実際のビジネス経験を通じて会計の仕組みを学ぶ過程を描いています。お小遣い帳や家計簿を理解できる人なら、会計も理解できるというアプローチで、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の関連性を解説しています。著者は経営コンサルタントの國貞克則氏で、実務に基づいた知識を提供しています。
本書は「財務3表」の視点から「管理会計」を解説し、原価計算や損益分岐点、キャッシュフロー・マネジメントなどのテーマを扱っています。経営目線での投資評価や事業再生の分析を実践的に紹介し、専門家でない読者にも理解しやすく説明しています。著者は國貞克則で、経営学の知識を基にした新しい管理会計のアプローチを提案しています。
この書籍は、財務会計に関する詳細なテキストであり、金融商品、リース、研究開発、退職給付、税効果、企業結合などの会計基準を詳述しています。基礎的な考え方に重点を置き、論点整理が明確で、実例や仕訳を通じて理解を助ける内容です。第18版では新しいリース会計基準などの改正も反映されています。著者は会計学の専門家であり、それぞれが多くの学会や試験委員を歴任しています。
本書は、コーポレート・ファイナンスを活用して企業の経営戦略を評価し、企業価値を向上させる方法を解説しています。資金調達やM&A、配当政策などのテーマに焦点を当て、経営判断に役立つ事例を紹介。著者の中野誠は、一橋大学の教授であり、経営における財務戦略の理解と応用を促進することを目的としています。
本書は、企業の価値評価、リスク管理、資本支出予算のベストプラクティス、資金調達の決定、利益還元政策に関する包括的な議論を提供しています。著者は、ファイナンスの専門家であり、エージェンシー問題や行動ファイナンスについても触れています。内容は、企業の目標や投資判断、ポートフォリオ理論、資本コスト、証券発行の方法など多岐にわたります。
本書は、中小企業の経営者が財務や現預金の重要性を理解し、会社を持続的に成長させるための「お金のルール」を解説しています。内容は、将来のビジョンや財務戦略、資金繰りの仕組み、数字の読み方、財務の内製化についての章で構成されており、経営者が会社を潰さないための具体的なアドバイスを提供しています。著者は税理士の湯原重之氏です。
この書籍は、人気ビジネススクール教授による「会計」と「経営戦略」の統合的な学習法を紹介しています。会計力と戦略思考力を同時に養うことを目指し、トヨタやニトリの決算書を通じて実践的に学ぶ内容です。内容は、損益計算書や貸借対照表の読み解き方、業界競争環境の理解、バリューチェーンやマーケティング戦略の分析など、多岐にわたります。最終的には、会計指標の活用やIFRS決算書の分析方法についても触れています。
この文章は、管理会計に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、管理会計の基礎から経営戦略に至るまでの内容を含み、具体的には財務諸表分析、業績管理、経営意思決定、戦略的会計などが取り上げられています。著者は一橋大学の教授陣であり、各自が商学博士を取得し、多くの学会賞を受賞している専門家たちです。
本書は、財務諸表監査の具体的な実施方法を解説し、監査報告書の記載例を含む大幅改訂版です。公認会計士試験合格者や経理担当者、監査実務に携わる専門家に向けて、監査実務の詳細を学ぶための必携書となっています。内容にはリスク・アプローチや監査手続き、会計上の見積もり、不正リスクなどが含まれています。著者は公認会計士であり、監査業務やコンサルティングに豊富な経験を持つ専門家です。
USCPA試験が2024年1月に新制度に移行することに伴い、受験者が知っておくべき情報を提供する資格・キャリアガイドです。試験の難易度、適性、キャリアパスなどを解説し、USCPA資格の活かし方や他の会計資格との比較も行っています。著者はUSCPA資格を持ち、豊富な実務経験を持つ専門家です。
本書は、2023年2月1日までに公表された会計基準や法令を収録した第13版で、法人税等会計基準や包括利益会計基準の改正に対応しています。公表機関名や改正日を記載し、企業会計基準の最終改正日や適用日も一覧で提供。公認会計士試験や税理士試験の受験学習、経理実務に役立つ内容となっています。目次には会計基準、会計法、金融商品取引法、関連法規が含まれています。
この文章は、M&A(合併・買収)に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、M&Aの基本概念や目的、企業価値の決定要因、実際の事例、狙われる企業の特徴、実施方法、敵対的買収の防止策、今後の動向についての章で構成されています。著者の宮崎哲也は、ビジネスフォーラム研究所の設立者であり、九州情報大学の教授としてM&Aや関連分野での研究・講演活動を行っています。
本書は、経理部に配属された若手社会人や学生向けの経理入門書です。経理の仕事の本質や必要なスキル、キャリアの可能性を理解し、やりがいを感じられる内容となっています。ストーリー形式で進行し、主人公の「会計太郎」が公認会計士YouTuberの「くろい」に相談する形で、マンガや図解を交えながらわかりやすく解説しています。著者は豊富な実務経験を持つ公認会計士の白井敬祐氏で、経理の楽しさを伝えることを目指しています。
本書は、決算書を視覚的に理解し、ビジネスパーソンに必要な会計の基礎を身につけるための指南書です。図解を用いることで難しい計算式を覚えずに本質を把握でき、段階的な学習ステップにより理解度を高めます。また、「取引フロー図」を通じて経済活動を可視化し、キャッシュフロー経営やビジネスモデルの理解を深めます。著者は多様な会計業務の経験を持つ公認会計士で、実践的な知識を提供しています。
ハンディ六法のトップセラー〝ポケ六”の最新版。民法(家族法),刑事訴訟規則,公益信託に関する法律等重要改正に対応。 *法学の講義から日常実務まで必要な基本法令をもれなく収録 *最新の改正条に傍線付加 *重要法令は大文字・理解を深める参照条文・便利な事項索引付き *メールサービス「ポケ六通信」への登録で,刊行後の改正情報を配信 *丈夫で開きやすいしなやかな造本 *『有斐閣六法の使い方・読み方』をウェブに公開,さらにご希望の方に小冊子を贈呈 《令和7年版の特色》 ◇官報の発行に関する法律,公益信託に関する法律を新採録 ◇民法(家族法),刑事訴訟規則,公益信託に関する法律等重要改正に対応 ◇参照条文・事項索引等充実した編集内容 〈新収録法令〉 官報の発行に関する法律,公益信託に関する法律(旧:公益信託ニ関スル法律) 〈主な改正〉民法,刑事訴訟規則,公益信託に関する法律,育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律,大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法),金融商品取引法,金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧:金融サービスの提供に関する法律)等
この本は、会計を経理だけでなく、組織の利益を最大化するための「会計感覚」として捉える重要性を説いています。著者は元国税調査官の経営コンサルタントで、管理会計や財務会計、税務会計をストーリー形式でわかりやすく解説しています。目次には、売上の誤解、管理会計の基本、決算書のポイント、キャッシュフローの重要性、PDCAサイクルの活用法などが含まれ、幅広い読者に向けた会計リテラシー向上を目指しています。
この本は、中小企業のM&A(合併・買収)を成功させるための秘訣を漫画形式で解説しています。後継者不在や相続問題などの悩みを解決し、オーナー社長が知りたいM&Aの重要ポイントを網羅しています。著者はM&Aの専門家であり、豊富な実績を持つ大山敬義氏です。目次には、事業承継の難しさやM&Aの準備、トラブル対応などが含まれています。
本書は、会計の基本概念を視覚的に理解するための「会計の地図」を用いた入門書です。100以上の図解を通じて、売上や利益、資産、負債などの会計用語の意味や関係性を示し、読者が自分の仕事と社会とのつながりを理解できるようにします。著者たちは、ビジュアルコミュニケーションを活用して、複雑な会計の仕組みをシンプルに説明し、ビジネスの面白さを伝えています。
この本は、小さな会社の経理担当者向けに、経理業務の実務や迷いやすい点を「1日」「1ヶ月」「1年」の単位で解説しています。内容は、経理の基本テクニックや業務の流れ、現金管理、売上・仕入管理、月次決算、年次決算の重要性などを網羅しており、実践的な知識を提供します。
著者の天野敦之は、公認会計士試験に一発合格し、会計の基本をイラストや図を用いてわかりやすく解説した書籍を執筆しました。内容は決算書の仕組みや各種財務諸表の読み方、収益性や安全性の分析、決算書と株価の関係などを網羅しています。著者は経営コンサルタントとしても活動しています。
この書籍は、1000人の社長から学んだ決算書の効果的な活用法を解説しています。内容は、会社のお金の流れや売上とキャッシュフローの関係、費用管理、バランスシートの重要性、借金のメリット・デメリット、税金の影響、成長と資金の蓄積について触れています。著者の児玉尚彦は税理士で、経理業務の改善やキャッシュフロー経営に関する豊富な経験を持ち、中小企業へのサポートを行っています。
この書籍は、消費税アップに負けず、逆風をチャンスに変える方法を紹介しています。著者の税理士・岩松正記が、2000人以上の経営者と向き合った経験を基に、税金に関する「ソン・トク」を解説。目次には、会社設立や経費、申告方法、副業サラリーマン、税理士との関係など、多岐にわたるテーマが含まれています。
企業が営む主要な活動に焦点を当て,財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,最新情報を盛り込んだ好評テキストの最新版。 企業が営む主要な活動に焦点を当て,財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。データを最新にして,新しい動向を踏まえた内容を盛り込んで,理解がいっそう深まるように工夫。 第1章 会計の種類と役割 第2章 財務会計のシステムと基本原則 第3章 企業の設立と資金調達 第4章 仕入・生産活動 第5章 販売活動 第6章 設備投資と研究開発 第7章 資金の管理と運用 第8章 国際活動 第9章 税金と配当 第10章 財務諸表の作成と公開 第11章 企業集団の財務報告 第12章 財務諸表による経営分析
本書は管理会計の重要性を説き、ビジネス判断における数字の活用方法を解説しています。管理会計は経理や財務だけでなく、全てのビジネスパーソンに必要な視点を提供し、意思決定のリスクを減少させます。内容は、短期的な意思決定、原価管理、長期的な戦略的意思決定に分かれており、具体的な分析手法や管理方法を網羅しています。著者は経営コンサルタントとしての経験を持つ専門家で、実践的な知識を提供しています。
英語のテキストではわからない「ビジネスでの使い方」を解説。英文会計の用語辞典ではできない「効率的な学習」が可能。厳選した重要単語を、現場でのニュアンスや関連用語との組合せ方まで掘り下げて解説した「会計×英語」入門の決定版! 1 紛らわしい言葉を整理しよう(Sales vs Revenue vs Profit Profit vs Income vs Margin vs Earnings vs Return ほか) 2 数字にまつわる表現を整理しよう(長い数値の読み方 小数点の読み方 ほか) 3 企業活動の重要な表現を押さえよう(グループ会社を正確に呼ぼう 主要なステークホルダーを英語で言おう ほか) 4 決算書類に関する知識を確認しよう(財務3表のいろいろな呼び方に慣れておこう キャッシュフロー計算書の構造を押さえよう ほか)
実務を熟知した「経理部長」が新人向けにやさしく解説。入社からの時期ごとに、徐々に内容をステップアップ。入社からの時期別に、「経理部長の期待」を掲載。 1章 経理の仕事の基本を知ろう 2章 新人経理担当者が最初に任される仕事とは 3章 仕事に慣れてきたら、次はこれにチャレンジしよう! 4章 1年目にここまでは確実にマスターしよう! 5章 1年目からこんな勉強もはじめよう! 6章 経理担当者としてのさらなるステップアップ
この書籍は、論文試験の重要な出題領域を整理し、思考力や判断力を試すための30題の問題と過去問研究を含む内容です。第6版では2018年の監査基準改訂にも対応しており、「監査上の主要な検討事項(KAM)」についても触れています。著者は公認会計士としての豊富な経験を持つ専門家たちで、監査や税務、コンサルティングの分野で活躍しています。
本書は、ANAやトヨタなどの企業の決算書を使って、財務諸表を理解するための基本ルールを解説しています。著者は経営コンサルタントの小宮一慶氏で、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の読み方を初心者向けに説明します。数字が苦手な人でも、基礎から応用までのステップで財務諸表を理解できるようになることを目指しています。読者は、企業の特徴や経営方針を読み取る力を養い、ビジネスや人生に役立てることが期待されます。
この書籍は、JT(日本たばこ産業)のM&A戦略に焦点を当て、特に22,500億円を投じた英国のたばこメーカー、ギャラハーの買収を成功させたCFOの経験を語っています。内容は、JTの海外事業やM&Aの選択理由、経営ガバナンスについての考察を含む第1部と、CFOとしての役割やリーダーシップについての第2部に分かれています。著者は新貝康司で、JTの副社長として重要な役割を果たしてきました。
この辞典は、海外事業に関連する会計・税務用語を収録した実務向けの英和・和英辞典で、9,860語の英和、6,930語の和英を含み、実務で役立つ解説や重要なフレーズも提供しています。付録には財務諸表のひな型やIFRS基準書の用語、国際税務の分野別用語が含まれています。著者は公認会計士・税理士の佐和周氏で、企業の海外進出を支援する専門家です。
本書は、起業を目指す人々の疑問や不安を解消するために、年間200件の起業相談を行うコンサルタントが執筆した実践的なガイドです。会社勤めをしながら起業準備を進め、成功のための必要な知識(ビジネスプラン、資金繰り、集客など)を紹介しています。起業の心構えやリスク管理についても触れ、具体的なアドバイスを提供しています。著者は起業支援の専門家であり、起業家のための包括的なサポートを行っています。
財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。 企業が営む主要な活動に焦点を当て,財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。データを最新にして,新しい内容とし,理解がいっそう深まるように工夫した。 第1章 会計の種類と役割 第2章 財務会計のシステムと基本原則 第3章 企業の設立と資金調達 第4章 仕入・生産活動 第5章 販売活動 第6章 設備投資と研究開発 第7章 資金の管理と運用 第8章 国際活動 第9章 税金と配当 第10章 財務諸表の作成と公開 第11章 企業集団の財務報告 第12章 財務諸表による経営分析
本書は、企業価値評価の理論と実践をケーススタディを通じてわかりやすく解説したビジネスリテラシー必読の書です。目次は企業価値評価の考え方や基礎、クロスボーダー評価、実践、検証に分かれています。著者は経営学の専門家であり、実務経験も豊富です。
本書は、簿記の知識がない人でも英文会計を学べるように工夫されており、イラストや図解を多用してわかりやすく解説しています。学習内容をすぐに例題で確認できる形式で、BATiCの試験テキストとしても適しています。内容は国際財務報告基準(IFRS)や複式簿記、試算表など多岐にわたり、著者は経営学の准教授で多くの資格を持つ専門家です。
この本は、決算書を単なる数字の羅列ではなく、企業や業界の成長ストーリーとして読み解く方法を紹介しています。著者は、数字が読めないと感じる人々に向けて、実践的な決算分析の技術を提供し、ビジネスの理解を深めることを目的としています。内容は、ECビジネスやFinTech、広告、携帯キャリアなど、さまざまな業界の決算分析事例を通じて、企業の戦略や未来を予測する力を養うものです。読者は、決算を読む習慣を身につけることで、ビジネススキルを向上させることができるとされています。
本書は、公認会計士であり外資系会計コンサルタントの著者が、「数字アレルギー」を解消するために考案した簿記入門書です。イラストや図解を多用し、簿記の基礎から決算書作成までを効率的に学べる内容となっています。特に「仕訳」の理解を重視しており、ビジネスチャンスを広げるためのスキルを身につけることができます。初めて簿記を学ぶ人や、資格取得を目指す人に最適な一冊です。
この本は、中小企業におけるM&A(合併・買収)の重要性を解説し、買い手と売り手の双方が知っておくべきポイントをQ&A形式でわかりやすく説明しています。著者は東海地区のM&Aアドバイザーで、基本知識や実例を交えながら、失敗しないM&Aの進め方を紹介しています。目次には、M&Aの注意点、会社を売る際のポイント、買う際の注意点、支援者の役割についての章があります。著者は名南M&A株式会社の代表で、豊富な実績を持つ専門家です。
この書籍は、AIやIoTなどの技術革新が進む中で、会計学の未来を探求する入門テキストです。伝統的な会計学から離れ、ゲーム理論や実験経済学の視点を取り入れて、新しい時代の会計人に必要な教養を提示します。目次は、人間の社会性と会計、新しい教養への準備、会計の原初形態、会計利益と人間心理、制度のデザイン、未来の会計について構成されています。著者は、同志社大学の教授であり、公認会計士でもある田口聡志氏です。
この書籍は、企業価値評価について最新の理論と実務をわかりやすく解説しています。マーケット、インカム、コストの視点から理解を深める内容で、各章では評価方法や留意点、無形資産の評価についても触れています。
この書籍は、会計士が企業の決算書を分析し、表面には現れない企業の「裏の顔」を明らかにする内容です。具体的には、ソニーの赤字決算と法人税、父娘対立の大塚家具、日本型と米国型経営の違い、日産のコストダウンの重要性、キーエンスの高利益率、スカイマークの倒産原因、そして東芝の不適切会計を取り上げています。各章では、企業の実態や経営の課題が数字を通じて解説されています。著者は公認会計士の前川修満氏です。
本書は、MBA必修科目の会計を10時間で学べる実践的な入門書です。財務会計と管理会計の基本知識を、トヨタやJALなどの企業実例を交えながら解説しています。左ページに解説、右ページに図解を配置し、視覚的に理解しやすい構成です。早稲田大学ビジネススクールの授業内容を凝縮し、会計の基礎を身につけたい人に最適です。会計の知識を活用することでビジネスパーソンとしての成長が期待できます。
本書は、買い手企業の担当者がM&Aを進める際の重要ポイントを時系列で解説しています。第2版では、会社法や税制改正などの最新の法律・会計・税務の変更を反映し、実務に基づいたストラクチャリング部分を中心に加筆・修正されています。内容はプレM&A、実行、ポストM&Aの各フェーズに分かれており、具体的な手順や戦略が詳述されています。著者はM&Aや経営戦略の専門家で、豊富な実務経験を持っています。
本書は、ビジネスパーソンが経営に関連する数字を理解し、意思決定に活用するためのガイドです。経理や財務の専門家に頼るだけでなく、企画や営業などの現場の担当者が数字を「ざっくり」理解することが重要であると強調しています。内容は、財務会計、ファイナンス、管理会計の22テーマを取り上げ、ストーリーや具体例を用いてわかりやすく説明しています。各テーマには重要ポイントの強調や復習用のまとめもあり、実践力を養うことができます。著者は早稲田大学の教授で、公認会計士の西山茂氏です。
出題可能性の高い問題を厳選収載! ポイントを絞った解説で完全理解!合格に必要なすべてを集約した、短答式対策の決定版! 監査上の主要な検討事項(KAM)を導入する 平成30年改訂監査基準に対応! 出題可能性の高い問題を厳選収載! ポイントを絞った解説で完全理解! 合格に必要なすべてを集約した、短答式試験対策の決定版! 合格実績抜群のTACが示す、ベーシックレベル問題のみを厳選収録! 入門レベルの学習を終えた方が、合格に向けて一段階ステップアップするための問題集です! ■□■ 基礎的な問題を落とさないために!■□■ 公認会計士試験合格の最も重要なポイントは 「誰もが得点できる基礎的な出題を落とさない」ということです。 本書は入門レベルの学習を終えた方が、合格に向けてしっかり基礎レベルを マスターし、一段階ステップアップすることを目的として編まれた問題集です。 各分野の重要性・出題可能性を吟味し、良問を厳選収録しています。 ■□■ 本書はこんな方に最適です! ■□■ (1)短答式試験対策を本格的に始めた方 (2)苦手論点を克服したい方 (3)着実に得点を重ねたい試験直前期の方 ※本書の内容は、平成31年4月1日現在有効な法令等を前提としています。 【第11版からの改正点】 50問中4問を新規問題に差替え。 その他、選択肢の修正多数。
偏差値35から、大学在学中に公認会計士試験に合格、 世界一の会計事務所に入社後起業に成功、年収1億超を稼ぐ著者の会計本。 会計を学ばずに副業・起業するのは「自殺行為」である! 偏差値35から、大学在学中に公認会計士試験に合格、 世界一の規模の会計事務所・デロイト・トウシュ・トーマツに入社するも 起業に成功・独立して年収1億超を稼ぐ著者に初めての「会計本」! 複雑で敬遠されがちな「会計知識」を とにかくカンタンにわかりやすく、 実例を挙げながら解説します。 著者のように、副業からの起業を考えている方には まさに実践的な必読の一冊! ************************* 第1章 僕が起業をした理由 ~今なぜ副業・起業が必要なのか? 起業することで上がるスキルがある! 今、おすすめの副業は? 会社員を辞める前に、ぜひしておきたいこと なぜ「起業」には、会計思考が必要なのか 第2章 公認会計士だから教えられる会計の基礎知識 BSとPLを知るとお金の流れがわかる 減価償却という考え方はなぜ必要なのか? PL=損益計算書の“5つの利益”を知ろう 売掛のタイミングについて 第3章 起業家だから教えられる会計のリアル 副業と起業は何が違う? 起業をすればさらに経費の幅が広がる 全損の保険は本当に節税になる? スーツや中古車の購入は節税になるか 人は雇わない方がいい、その理由とは 第4章 ネットビジネスを必ず成功に導く会計思考 ビジネスの成功ポイントは変動費化に 「利益を上げたら投資」がBSの安定に 今、ネットビジネスを始めるなら「物販」 クラウドファンディングという方法はありか? 第5章 ビジネス拡大に不可欠な会計思考 利益が出たら、投資はすべき? 投資は長く続けないと意味がない 個人の投資に不動産以外はおすすめしない理由 つぶれない次世代の「さおだけ屋」はあるのか 第6章 対談1 森貞仁 インターネット起業は、貯金ゼロでも、始められる 会計は、実践をしながら学んでいった 法人にしてよかったのは、税金の知識が身についたこと 起業を考えている人は、3カ月間、死ぬほど頑張れ! 第6章 対談2 河村裕一 3年間を起業準備にあて、資金500万円で起業 車は2年で買い替えることで税金対策に 起業をするには、人脈が重要。人脈によって助かったことも 起業をするなら副業からでOK。ただ寝る間を惜しんで本気で!
財務諸表の作成過程を平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたロングセラー・テキストの最新版。 企業が営む主要な活動に焦点を当て,財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。データを最新にして,新しい動向を踏まえた内容を盛り込んで,理解がいっそう深まるように工夫。 第1章 会計の種類と役割 第2章 財務会計のシステムと基本原則 第3章 企業の設立と資金調達 第4章 仕入・生産活動 第5章 販売活動 第6章 設備投資と研究開発 第7章 資金の管理と運用 第8章 国際活動 第9章 税金と配当 第10章 財務諸表の作成と公開 第11章 企業集団の財務報告 第12章 財務諸表による経営分析
この書籍は、法人・個人事業者向けに、仕訳の処理方法や注意点を詳しく解説しており、日常的に使用する勘定科目についても網羅しています。著者の北川真貴は税理士で、難病を克服した後に会計業務に従事し、さまざまな業種の顧問先を持っています。
この書籍は、管理会計コンサルティングを通じてチーム力を最大化し、企業を活性化するための実践的な手法を提供します。「見える化」から「行動化」までのプロセスを解説し、全国の実践例やコラムを通じて経営者や専門家に向けた具体的なアプローチを紹介しています。内容は、管理会計の実務、事例紹介、現場データ様式集の3部構成で、実践的なノウハウが網羅されています。著者は藤本康男と篠田朝也で、それぞれ経理や経済学の専門家です。
本書は、監査制度や監査基準を体系的に解説した詳しいテキストで、公認会計士試験対策にも適しています。新しい監査環境に対応した人材育成を目指し、監査の基礎概念から金融商品取引法監査、内部統制監査などを図表を用いてわかりやすく説明しています。第7版では最新の制度改正を反映し、内容がさらに充実しています。著者は著名な大学教授で、公認会計士試験委員でもあります。
本書は、日本における「会社買収」に対する違和感を考察し、企業に値段を付けることの本質を解説します。資本主義の仕組みを基に、企業価値算定の基本や賢い投資家になるための知識を提供。また、日本と米国の敵対的M&Aの違いにも触れ、企業評価の重要性を論じています。著者はM&Aの専門家であり、実務に基づいた視点で内容を展開しています。
「財務会計」に関するよくある質問
Q. 「財務会計」の本を選ぶポイントは?
A. 「財務会計」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「財務会計」本は?
A. 当サイトのランキングでは『会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで174冊の中から厳選しています。
Q. 「財務会計」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「財務会計」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。


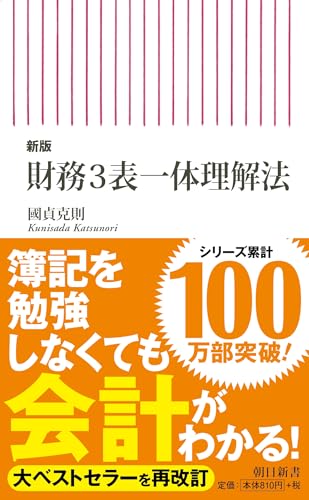


















![『会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方 [実践編]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51-lB7t22AL._SL500_.jpg)


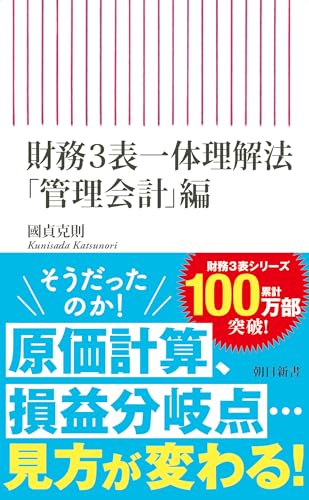




![『【新版】財務3表一体理解法 [発展編] (朝日新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/5148obMOJcL._SL500_.jpg)
















』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41St16XCeNL._SL500_.jpg)





















![『公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ~くわかる本 [第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51cEEmwKAhL._SL500_.jpg)

















































![『80分でマスター! [ガチ速]簿記入門』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51WxRSO38CL._SL500_.jpg)



















 (よくわかる社労士シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51IY8NJYliL._SL500_.jpg)



















![『新財務会計学[第6版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41-wTKhvFTL._SL500_.jpg)



























