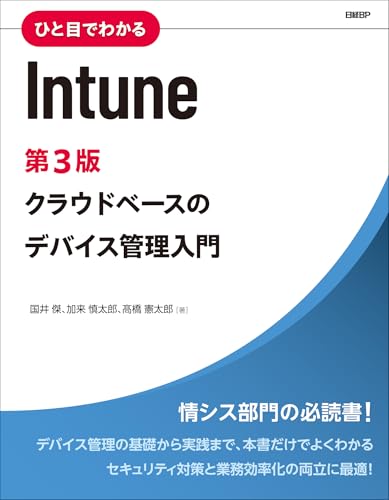【2025年】「Googleスライド」のおすすめ 本 144選!人気ランキング
- 一生使える 見やすい資料のデザイン入門
- 社内プレゼンの資料作成術
- Google流資料作成術
- 社外プレゼンの資料作成術【完全版】
- なるほどデザイン〈目で見て楽しむ新しいデザインの本。〉
- PowerPoint資料作成 プロフェッショナルの大原則
- Googleサービス 完全ガイドブック
- 社外プレゼンの資料作成術
- 今すぐ使えるかんたん Google Workspace 完全ガイドブック 困った解決&便利技
- 世界で一番やさしい 資料作りの教科書
この書籍は、Google社員が実践する「ストーリーテリング」の手法を紹介し、複雑なデータをシンプルにわかりやすく伝える資料作成術を解説しています。ポイントとして「本当に使えるグラフは12種類」「余計な要素を取りのぞく」「ストーリーは三幕で構成する」などが挙げられ、データを活用して効果的にストーリーを語ることの重要性が強調されています。著者はGoogleでビジュアライゼーションの講座を担当していたコール・ヌッスバウマーで、企業や団体向けにビジュアルコミュニケーションの研修を行っています。
本書は、効果的なプレゼン資料の作成術を解説した完全版で、営業やコンペでの成功を目指す内容です。感情に訴えるプレゼンが重要で、視覚的に理解しやすいスライドやストーリーが成約率を向上させます。著者は、数々の企業でプレゼン研修やコンサルティングを行ってきた実績を持つ前田鎌利氏で、具体的なテクニックやデザインのポイントを豊富なビジュアルで紹介しています。
この本は「デザイン=楽しい」をテーマに、デザイナーの思考プロセスを豊富なビジュアルで解説します。内容は、編集とデザインの関係、デザイナーの必須ツール、デザインの基本要素(文字、言葉、色、写真、グラフ)などを扱っています。著者は株式会社コンセントのアートディレクター・デザイナーの筒井美希氏です。
デザイン全く分からない自分でもわかりやすく、デザインについて知るきっかけになりました!
デザインの基本的な考え方を視覚的にわかりやすく解説する一冊です。専門的な知識がなくても楽しめる内容で、初心者にも理解しやすく、具体的なデザイン例を豊富に掲載しています。デザインの意図や効果を実際の作品で確認できるため、デザインの背景にある理論を自然に学ぶことができます。視覚的に訴える構成が魅力で、デザイナー以外の読者にもおすすめです。
この書籍は、Googleの各種サービス(検索、Gmail、Googleマップ、カレンダー、YouTube、Googleフォトなど)の使い方を紹介しており、無料で利用できる便利な機能を解説しています。パソコンだけでなく、スマホやタブレットでも利用可能で、特にGmailの新デザインにも対応しています。目次には、基本知識や各サービスの活用法が詳しく説明されています。
本書は、リモートワークの普及に伴い、Google Workspaceの活用方法をまとめた指南書です。初心者や利用者が直面しやすい問題や管理に必要な知識を幅広く紹介しており、673の技を通じて、GmailやGoogle Meet、Google Driveなどの各ツールの活用法を解説しています。著者はそれぞれ異なるバックグラウンドを持ち、デジタル分野での豊富な経験を活かしています。
鈴川葵の成長を描く第2弾。入社4年目の彼女はプレゼンに苦しみながら、社内の会議を改革し、資料作りを学びます。コンサルタントの父から教わった「資料作りの7つのStep」と「コミュニケーションの3つの作法」を実践し、効果的なプレゼンテーションの技術を身に付けていきます。本書では、コミュニケーションの原理を資料作りを通じて解説し、主人公の成長を通じて読者も学べる内容となっています。
この書籍は、ビジネスプレゼンテーションの技術を向上させるためのビジュアル解説書です。パワーポイントを使った資料作成のデザインや、プレゼンの目的に基づく考え方を学ぶことができます。具体的なテクニックやレイアウトの方法、効果的なグラフの使い方などが紹介されており、初心者でも実践的なスキルを身につけられる内容です。著者は、研究発表のデザインを普及するためのウェブサイトも運営しています。
本書は、826名の意思決定者へのヒアリングと5万1544枚のパワーポイント資料のAI分析を基に、「相手を動かす資料作成の勝ちパターン」を紹介します。資料作成のゴールは「思いどおりに相手を動かす」ことで、具体的なルールやテクニックを提供。内容は、資料作成のコツ、画像やグラフの活用法、成功のための心がけ、時短術など多岐にわたります。著者は元マイクロソフトのPowerPoint事業責任者の越川慎司です。
この書籍は、効果的なプレゼン資料作成のノウハウを提供するもので、シンプルかつ論理的なスライド作成を重視しています。具体的には、キーメッセージを13字以内に収め、スライドは5~9枚に抑えることが推奨されています。著者の前田鎌利は、ソフトバンクでの豊富な経験を基に、誰もが納得するプレゼンテーションの技術を解説し、実践的なアドバイスを提供しています。
この書籍は、ヒット商品がどのように生まれるかを探求し、有名企業17社の実際のプレゼン資料を通じてそのプロセスを紹介しています。各企業が直面した課題や成功事例を通じて、商品開発やマーケティングの重要な要素を明らかにしています。著者はビジネス書作家の戸田覚氏で、具体的な事例を通じて商品開発の戦略や工夫を伝えています。
この書籍は、1000人以上の社長や企業幹部に影響を与えた「伝説の家庭教師」の話し方のメソッドを初めて公開しています。内容は「雑談」「プレゼン」「説得」「説明」「ほめ方」「叱り方」と多岐にわたり、リモート時代にも対応した実践的なノウハウが満載です。全50のルールを通じて、話し方を改善し、仕事や人間関係を円滑にする方法が紹介されています。著者はエグゼクティブ・スピーチコーチの岡本純子氏で、豊富な経験を基にした具体的なテクニックが特徴です。
Googleのビジネスツール「Google Workspace」の解説書です。GmailやDriveなどのアプリの使い方から、管理者向け機能やセキュリティまで網羅的に解説。企業の導入事例なども紹介しています。 本書は、Googleが提供するビジネスツール「Google Workspace」の解説書です。GmailやDriveなどのGoogleアプリの使い方解説だけでなく、管理者向け機能やセキュリティまで網羅的に解説。企業の導入事例なども紹介していますので、テレワークや仕事の効率化、生産性向上にあたっての導入・運用のマニュアルとしても有用です。
本書は、GoogleスプレッドシートのマクロやGoogle Apps Scriptの基本から始まり、データ集計やスタイル付け、グラフやピボットテーブルの挿入方法を解説します。さらに、GUIとの連携、Googleフォームを使ったデータ入力、GmailやGoogleカレンダーとの連携、Webデータの取得方法なども学べます。最後に、スプレッドシートをWebページに埋め込む方法も紹介。プログラム学習にはWebブラウザのみで、新たなインストールは不要です。業務効率化を目指す方やプログラミングに興味がある方におすすめの一冊です。
本書『一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 完全版』は、見やすい資料作成のための最強の入門書で、デザイン初心者でも簡単に改善できる知識とコツを提供します。具体的には、見やすさの重要性や基本的なデザイン技術、作業効率を上げる方法、さまざまな資料に応じた表現テクニックを解説しています。著者の森重湧太は、教育工学や認知科学を活かし、実践的なノウハウをまとめた経験を持つ専門家です。
本書は、自作のスライドやチラシ、企画書などのデザインが効果的でない理由が、センスの欠如ではなく基本ルールの不理解にあることを指摘しています。デザインの基本ルールを学ぶことで、WordやPowerPointを使って魅力的で伝わりやすい資料を作成できるようになります。特にユニバーサルデザインに配慮した方法も紹介されており、幅広い読者に向けておすすめされています。内容は書体、文章、図表、レイアウト、配色など多岐にわたり、実践的なアドバイスが提供されています。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
本書は、リモートワークにおいてGoogleスプレッドシートを効果的に活用するためのノウハウを提供しています。Excelからの移行を考える人や、スプレッドシートを十分に使いこなせていない人に向けて、インプット・アウトプットの効率化やデータの可視化、チームでの共有方法などを具体的に解説しています。著者はYouTubeチャンネル「Youseful」と連携しており、実務に役立つ内容が豊富です。
本書は、入社2年目の鈴川葵が職場の非効率な会議に疑問を抱き、コンサルタントの父の助けを借りて会議改革に挑む物語です。葵は「魔法の一言」やファシリテーション技術を学び、会議を改善し、部署全体を巻き込んで成果を上げていきます。会議の効率化方法を通じて、読者は実践的な知識を得ることができます。
本書は、素人デザイナー向けに、よくあるデザインの失敗例とその改善方法を解説しています。著者はプロのデザイナーで、初心者でも理解しやすい内容で、チラシやポスター、プレゼン資料などのデザインを向上させるノウハウを提供します。各章では原稿、レイアウト、フォント、カラー、写真・イラストに関する具体的なアドバイスがあり、ビフォーアフターの例も紹介されています。デザインを自分で作る必要がある人におすすめの一冊です。
新型コロナウイルスの影響により、テレワークなど、働き方の方向転換が迫られている企業が多くなっています。そんな状況の中、無料で使えるビデオ会議ツール(Web会議ツール)として「Google Meet」に注目が集まっています。本書ではGoogle Meetをはじめて使う人に向けて、基本的な使い方だけでなく、画面共有やホワイトボードなど、便利に使いこなすためのテクニックをわかりやすく解説していきます。なお、iPhoneやAndroidスマートフォンの操作についても解説しています。 第1章 Google Meetのキホン 01 Google Meetとは 02 Google Meetを利用するには 03 無料版と有料版の違いを確認する 04 必要な機材を確認する 05 利用できるスマホやタブレットを確認する 06 利用できるWebブラウザーを確認する 07 Google Chromeをインストールする 08 Googleアカウントを作成する 09 ログインする 第2章 会議に参加する 10 会議に参加するには 11 URLをクリックして会議に参加する 12 Gmailから会議に参加する 13 Google カレンダーから会議に参加する 14 Google Meetから会議に参加する 15 基本画面を確認する 16 マイクをオン/オフにする 17 カメラをオン/オフにする 18 チャットでやり取りする 19 会議から退出する 第3章 会議を開催する 20 会議を開催するには 21 Google Meet から会議を開催する 22 Gmail から会議を開催する 23 Google カレンダーから会議を開催する 24 Outlookから会議を開催する 25 参加者を追加する 26 参加者を承認する 27 参加者のマイクをミュートする 28 参加者を退出させる 29 会議を終了する 第4章 使いやすく設定する 30 画面の表示方法を変更する 31 マイクやスピーカーの音質を変更する 32 スマートフォンから音声を出力する 33 画質を変更する 34 通知設定を変更する 35 アカウントを切り替える 第5章 便利な機能を利用する 36 ファイルを共有する 37 画面を共有する 38 プレゼンテーションを行う 39 ホワイトボードを利用する 40 ビデオを録画する 41 録画したビデオを出力する 42 背景を変更する 第6章 さらに使いこなす 43 Google Chromeの拡張機能をインストールする 44 絵文字でリアクションする 45 出欠の確認をする 46 便利な多機能を利用する 47 ミュートを解除する 第7章 スマートフォンやタブレットで利用する 48 Android版、iPhone版について 49 アプリをインストールする 50 ログインする 51 URLをタップして会議に参加する 52 Gmailから会議に参加する 53 Google カレンダーから会議に参加する 54 [Google Meet]アプリから会議に参加する 55 基本画面を確認する 56 マイクとスピーカーをオン/オフにする 57 カメラをオン/オフにする 58 画面を共有する 59 共有ファイルを確認する 60 チャットでやり取りする 61 会議から退出する 第8章 疑問・困った解決Q&A 62 会議を円滑に進めるには? 63 ハウリングを防ぐには? 64 外部アプリと連携するには? 65 プランを変更するには?
この書籍は、コンテンツマーケティングの専門家であるジョー・ピュリッジによって、顧客のニーズに応えるコンテンツの作成、配布、管理について詳しく解説しています。内容は、コンテンツマーケティングの定義や歴史、戦略の策定、プロセス管理、ストーリーのプロモーション、効果測定など多岐にわたります。著者はコンテンツマーケティング・インスティテュートの創設者であり、業界の第一人者です。
本書『最高のプレゼン』は、堀江貴文がプレゼンテーションの極意を解説した実用書です。プレゼンは「ライブ」であり、相手との「1対1の会話」のように行うことが重要と説きます。具体的なメソッドとして、「Me、We、Now」などの共感を呼ぶ技術や、スライド作成のポイントを紹介。プレゼンを通じて思いを伝える力を身につけることで、ビジネスや日常生活を向上させることができると強調しています。全体を通して、プレゼンの目的や準備、実践方法について具体的なアドバイスが提供されています。
『Googleスプレッドシートは燃え尽きたExcel職人の魂で動いているんだ』は、異世界転生とGoogleスプレッドシートを融合させたITライトノベルです。著者はExcel職人が転生してGoogleスプレッドシートの世界で冒険するストーリーを描き、豪華なイラストと技術解説コラムも収録されています。読者はスプレッドシートの独自関数や実践的な使い方を学ぶことができ、ライトノベルファンにも楽しめる内容です。各章ではVLOOKUPやIMAGE、SPLITなどの関数について詳しく解説されています。
本書は、グラフを通じてデータの誤解を招く手法を解説した一般読者向けのガイドです。著者はインフォグラフィックスのエキスパートで、175種類のグラフを用いて気候変動、選挙、健康問題などのテーマを扱っています。SNSやマスメディアでの情報の真偽を見極める重要性が増す中、誤解を避けるためのグラフ・リテラシーを学ぶことができます。カジュアルな文体で読みやすく、情報リテラシーの向上を目指しています。
本書は、デザインの知識や経験がない人向けに、クイズ形式で資料やスライドのデザインテクニックを学ぶことができるガイドです。楽しみながら「Good & Bad」なデザインを理解し、PowerPointを使った実践的なスキルを身につけます。具体的には、デザインの基本やルールを学び、NGな資料を改善するポイントを把握することができます。多くのデザイン例を通じて、資料作成のヒントを得ることも可能です。
本書は、コンテンツマーケティングの実践的なノウハウを提供する講座です。内容は、基本概念や始め方、コンテンツの作成方法、拡散手法、チューニング、成功事例など多岐にわたります。これにより、コンテンツの設計力を高め、現場での実践力を身につけることができます。
この書籍は、学校DX(デジタルトランスフォーメーション)を理解するための基本編と活用編の2部構成で、Google for Educationを活用した具体的な進め方やメリットを解説しています。基本編では学校DXの実現方法やステップを紹介し、活用編では管理者や教師の働き方改革、新しいチームのつながり方などを提案しています。また、付録にはGoogle for Educationの活用アイデアも含まれています。キャラクターによるやさしい解説が特徴です。
この本は、ノンデザイナーのビジネスパーソン向けに、プレゼン資料のデザイン技法を紹介しています。プレゼンでの悩み(聴衆の反応が悪い、内容が伝わらないなど)は、デザインによって解決可能であると述べています。具体的なデザイン原則(整列、視線の流れ、余白、対比など)を学ぶことで、誰でも効果的なプレゼン資料を作成できるようになることを目指しています。著者は、プレゼン資料向けのデザインノウハウを提供するサイトを運営しています。
池上彰のベストセラーを漫画化した本で、コミュニケーションスキルを向上させる内容。目次には「伝える力」「相手の立場での伝え方」「聞く力」「褒める・叱る力」「文章力向上法」が含まれている。著者はジャーナリストの池上彰、漫画原作者の星井博文、漫画家のanco。
この書籍は、Googleスプレッドシートを仕事で効果的に活用するためのガイドです。ピボットテーブルや便利な関数を使って資料作成を効率化し、データ分析を簡単に行える方法を学べます。目次には、スプレッドシートの概要、関数の使い方、ピボットテーブルの活用法、データの視覚化などが含まれています。著者はプログラミングに関する豊富な経験を持つ薬師寺国安です。
この書籍は、効果的なスライド作成やグラフ・チャートの描き方を解説しており、シンプルなスライドにするためのテクニックを紹介しています。内容は、スライドの基本構成、視覚化のためのグラフ・チャート作成方法、シンプルさを追求するためのヒント、そして練習問題を含んでいます。著者は、コンサルティング業界での経験を活かし、わかりやすいスライド作成を教えてきた専門家です。
本書では、日本人が苦手とする「打ち解ける」「間を埋める」「盛り上げる」雑談の重要性と、世界の一流ビジネスマンがどのように活用しているかを探ります。日本では雑談が主に世間話とされがちですが、著者はビジネスの場での戦略的な「対話」としての雑談の価値を強調。グーグルでの経験を基に、雑談を通じて関係を築き、成果を上げる方法や、避けるべきNGポイントについても詳述しています。雑談を武器として活用することで、ビジネスのパフォーマンス向上に繋がるとしています。
伝える力は現代、誰もが身につけるべき必須のスキル。これ一冊で、あなたは聴衆を夢中にさせられる! アイデア満載の必読書。 伝える力は現代、誰もが身につけるべき必須のスキル。これ一冊で、あなたは聴衆を夢中にさせられる! アイデア満載の必読書。
この書籍は、GIGAスクール構想に基づき、1人1台端末の活用方法を101のアイデアで紹介しています。授業でのアプリ活用を「導入」「情報収集」「整理・分析」「意見交流・共有」「まとめ」「振り返り」「評価」の7つの場面に分類し、具体的なアプリの使用例を提供しています。また、学校生活や校務におけるアプリ活用のアイデアも掲載されています。著者は教育現場で活躍する専門家たちで構成されています。
この本は、デザインにおける「余白」の重要性を解説し、カフェ、ビジネス、和もの、化粧品、季節もの、ラグジュアリーなど多様なデザインのレイアウト例を紹介しています。デザインの基礎を学ぶための実用的なガイドです。
余白がもたらすデザインの効果を深く掘り下げた一冊です。余白の取り方一つでデザインの印象が大きく変わることを、多彩な事例を通して解説しています。視覚的なバランスや、情報の整理の仕方に焦点を当てており、シンプルで洗練されたデザインを目指す人にとって必携のガイドブックです。余白の重要性を理解することで、よりプロフェッショナルなデザインが可能になります。
本書は、戦略コンサルタントが「相手の頭の中を整理しながら伝える技術」を解説しています。説明が苦手な人は、話す内容や順番を意識せずに話すため、相手が混乱します。本書では、「何をどの順番で話すか」を意識することで、プレゼンテーションやコミュニケーションの結果や印象が大きく改善されることを示しています。具体的な章では、説明力を高める方法や思考整理のコツが紹介されています。著者は田中耕比古氏で、幅広い業界でコンサルティングを行っています。
この書籍は、プレゼン資料やポスター作成に役立つデザインテクニックを紹介しています。内容は、自己分析から始まり、パワーポイントを使った基本・応用の描き方、グラフや表の作成、効果的な配色、フォントと文字組、レイアウトの基本と応用まで多岐にわたります。著者は田中佐代子で、デザインの専門家としての経験を生かし、資料作成を楽しくするための基本をまとめています。
この書籍は、Webマーケティングの基本を理解できる内容で、人気のWebコンテンツにオリジナルの解説を加えています。目次には、SEO、Webデザイン、ライティング、SWOT分析、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディア運用など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者はWebライダーの松尾茂起と、イラストレーターの上野高史です。
Webマーケティングといえばこの書籍。ストーリ形式でWebマーケティングについて学べるのでサクサク読めてそれでいてWebマーケティングのエッセンスがギュッと詰まっている。それもそのはず超有名マーケターのWebライダー松尾氏が著者。Webマーケティングを学びはじめた初学者はまず手にとって欲しい書籍。ちなみにWebマーケティングの中でもかなりSEO・オウンドメディア運営にフォーカスしているので広告などについて学びたい人には向かない。
バーバラ・ミントが著した本は、コミュニケーション力を向上させるための文章の書き方を紹介しています。内容は、書く技術、考える技術、問題解決の技術、表現の技術の4部構成で、特にピラミッド構造を活用した文書作成法に焦点を当てています。また、構造がない状況での問題解決や重要ポイントのまとめも含まれています。
本書は、コンテンツマーケティングを通じて潜在ユーザーをWebサイトに呼び込む方法を解説しています。内容は、コンテンツ制作やSEOの基本、オウンドメディアのライティング術、SEOを意識したWebサイト制作、リスティング広告の活用法など多岐にわたります。著者たちは、限られた予算や人手でも実践可能なノウハウを提供し、読者が自社のビジネスやユーザー理解を深め、効果的なコンテンツを作成できるようサポートします。
この書籍は、「話せるのに書けない」と感じる人々のための文章技術を教える授業です。著者は、15年間のライティング経験を基に、話し言葉を文章に変換する方法や、文章のリズム、構成、読者を意識した書き方などを解説します。学校では学べない“書く技術”を身につけるための実践的な内容が含まれています。
この書籍は、英語でのプレゼンテーションを自信を持って行うための実践的なポイントを体系的に学べる内容です。準備から発表、質疑応答、懇親会でのコミュニケーションまでをカバーし、重要フレーズ集も収録しています。著者の島村東世子は、英語教育の専門家であり、多くの企業や大学でプレゼンテーション教育を行っています。
本書は、オウンドメディアの成功に必要な事前調査やコンテンツ制作、運用、改善方法を解説しています。失敗例と成功事例を交え、初心者にもわかりやすく具体的な手順を示します。目次にはオウンドメディアの基本、失敗と成功の事例、制作や運用の手法が含まれています。著者は、ディーエムソリューションズの専門家で、実績豊富なマーケティングのプロです。
この書籍は、最新のSEO(検索エンジン最適化)を学ぶための定番の入門書で、5年ぶりにリニューアルされています。SEOの本質は「訪問者の目的に応えるサイト作り」であり、キーワード選定やサイト構造の整備が重要です。経験豊富な講師陣が具体的なノウハウをわかりやすく解説。特に、Googleの新しい評価基準「E-E-A-T」に基づくコンテンツマーケティングや、最新ツールの活用方法も紹介されています。初心者から企業のWeb担当者まで幅広い読者におすすめの内容です。
この本は、文章力を向上させるための40の重要スキルを紹介しています。特に、シンプルな文章を書くことや、伝わる文章には「型」があることが強調されています。1位から7位のルールを実践することで文章力が向上し、20位まで習得すれば「文章がうまい人」になり、40位まで達成すれば「プロ級の書く力」が得られます。ビジネス文書やSNS、ブログなど幅広い場面で役立つ内容です。著者は、編集やライティングの経験豊富な専門家たちです。
著者の上阪徹は、書くスピードを向上させることで仕事の効率を高める方法を紹介しています。彼自身、遅筆から超速筆家に変わる過程で得た10倍速のメソッドを公開し、誰でも「伝わる文章」を簡単に書けるようになることを目指しています。内容は、素材の集め方や文章の構成、整え方など、具体的な技術に焦点を当てており、メールから本まで様々な文書を効率よく書くための実践的なガイドとなっています。
本書は、ビジネスパーソンが効果的な資料を迅速に作成するための技術を解説しています。著者は、NTTグループや日本IBMでの経験を基に、提案資料に必要な「6要素」を「A4一枚」にまとめる方法を紹介。資料作成に不慣れな人でも理解しやすいように、情報収集や資料の見せ方についても触れています。ビジネススキルを向上させるための実践的なガイドです。
この書籍は、Webサイトで成果を上げるための文章の書き方をストーリー形式で学ぶ実用入門書であり、特にSEOに強いライティングに焦点を当てています。目次には、SEOライティングの基本や独自の強み(USP)の活用、リライトや推敲の重要性、オウンドメディアの活用法などが含まれています。著者はWebマーケティングの専門家であり、音楽活動も行っています。また、イラストレーターも参加しており、視覚的な要素も重視されています。
沈黙のWebマーケティングに続いて2作目となる本書。1作目を読んでハマった方はぜひこちらの2作目も読んでみて欲しい。ストーリ形式で分かりやすくSEOライティングについて学べる
本書はGoogleアナリティクス4(GA4)に関する解説書で、ユニバーサルアナリティクス(UA)からの移行や新規導入者向けに、基礎知識、導入・設定方法、指標やディメンションの解説、レポートのカスタマイズ、データ分析のテクニックを提供します。また、Looker StudioやBigQueryとの連携方法も紹介しており、WebサイトのコンバージョンやLTV向上に役立つ実践的なノウハウが満載です。著者はWeb解析の専門家で、豊富な実績を持っています。
本書は、社会人や学生向けに豊富な文例とノウハウを提供し、効果的な文章を書くための指導を行っています。目次には、短く、自然で正しい表現、明確な意図、分かりやすさ、簡潔さ、共感を呼ぶ書き方、表記やレイアウトの重要性についての章が含まれています。著者の阿部紘久は、東京大学卒業後、さまざまな企業での経験を経て、昭和女子大学で文章指導を行っています。
本書は、伝統的なデザイン原則や視覚的教訓を活用し、明確なコミュニケーションを実現する方法を解説しています。著者ガー・レイノルズの第2作目で、タイポグラフィや色彩、ストーリーテリング、データの簡素化などの要素を取り上げています。また、プレゼンテーションを向上させるためのデザイン原則や実践的なスライドサンプルも紹介されています。著者はプレゼンテーションデザインの第一人者であり、関西外大の准教授としても活動しています。
この書籍は、文章が書けない理由と、書くための実践的なメソッドを紹介しています。著者はニュースメディアで新人教育を担当しており、書ける人が自然に行っている基本を誰でも学べるように伝授します。企画書や報告書、ブログなどに役立つ内容で、特に言いたいことが伝えられない、書き始めが分からない、書き終えられない人におすすめです。ポイントとしては、事前に計画を立てることや構成の工夫、読み返しの重要性などが挙げられています。
本書は、1万人以上の転職支援を行ってきたキャリアコンサルタントが、転職面接のノウハウを提供します。説得力のある志望動機やアピールポイントの伝え方、難しい質問への対処法など、実践的な内容が豊富に含まれています。特に「転職に不利」とされる経験をポジティブにアピールする方法に焦点を当て、面接官に好印象を与えるための準備や心構えを解説しています。著者はキャリアコンサルタントとしての豊富な経験を持ち、実践的なアドバイスを通じて自信を持って面接に臨めるようサポートしています。
本書は、ビジネスにおける資料作成(ドキュメンテーション)のテクニックを紹介しています。内容は、プロフェッショナルな資料に求められる要素や、目的・ターゲット・メッセージの明確化、資料の構成、情報の質と量の最適化、ビジュアルテクニック、クオリティ向上のヒントなど多岐にわたります。著者は清水久三子で、日本IBMでリーダーとして活躍しています。
大学生がプレゼンをより効果的に行う技術を、「聴衆」「資料」「話し手」という3つの視点から、初心者にも分かりやすく解説。 ビジネスシーンではなく、大学現場でのプレゼンテーションについての入門書。大学生がプレゼンをより効果的に行う技術を、「聴衆」「資料」「話し手」という3つの視点から、初心者にも分かりやすく解説。 ▼プレゼンに初挑戦!! でもどうやって!? アカデミック・プレゼンテーションに必要なスキルを3段階にわけて解説。 基礎・準備・実践の3点からプレゼンに臨む学生をサポートする。 この本は大学生になって、初めてプレゼンテーションに臨む方、また入学前にプレゼンテーションの予習をしたい方のためのものです。 大学生が直面する「アカデミック・プレゼンテーション」はこれまでの高校生活で行ってきた発表とも、また社会人が行うプレゼンテーションとも異なり、独特のスキル、そして準備が求められます。本書はそうしたスキルや準備はもちろん、アカデミック・プレゼンテーションに臨む際に必要なノウハウが全て詰まった一冊となっています。 はじめに 第1部 基礎編 プレゼンテーションについて考えてみよう! 第1章 ところでプレゼンテーションって何さ? 1. 「問い」を立てることから始まる 2. 「問い」の哲学! 第2章 テーマや問いってどうやって立てるの? 1. テーマや問いの絞り方 2. 困った! どうしても「問い」が思い浮かばない 3. 困った時のメソッド――拡散と収束 第3章 助けて! どうやって調べればいいの? 1. 文献調査はなぜ必要なの? 2. 本をどうやって探せばよいの? 3. 雑誌論文はどうやって見つければよいの? 4. 本や雑誌を入手するにはどうしたらよいの? 5. どんな本を読めばよいのだろう 第4章 考えたことをまとめろと言われても…… 1. AはBである 2. A、B、C……なので、Dである 3. AがBなのは、Cが前提でないと成り立たない 4. AがBなのは、CがDであるのと似ているからだ 5. 仮説演繹法 第5章 アウトプットって、どうすりゃいいの? 1. 誰がプレゼンテーションを聴いているか、分かってる? 2. アウトラインの構成 3. 発表原稿の作成 4. 絶対にやってはいけないこと! 剽窃とデータ改竄 5. 読み上げ原稿か、暗記か 第2部 準備編 スライドを作ってみよう! 第6章 よいスライドってどんなのか教えて! 1. スライド作成の準備に取りかかる前に 第7章 理解してもらえるスライドとは 1. スライドのアジェンダ(骨子)と発表内容の計画 2. アジェンダの重要性 3. プレゼンテーションの計画を立てる 4. どのような資料が求められているのか 第8章 さあ、スライドってどうやって作ればいいの? 1. なぜスライドを使うのか? 2. スライドは諸刃の剣――求められる「適度な」情報量 第3部 実践編 さあ、プレゼンテーションに挑戦! 第9章 ついに、本番! 1. リハーサルは必須! 2. 配布資料の印刷 3. F君の失敗 4. どんな服装? やっぱりスーツ? 5. 会場に行く時間は? 6. 会場に着いたら、とにかくうろうろ 7. よいプレゼンテーションをするには 8. パフォーマンスは必要か 第10章 聴衆からですが、質問があります! 1. 質疑応答って何? 2. 質問の壁 3. 質問の3つのパターン 4. 語の意味を問う 5. 「本当にそうなのだろうか」と問う 6. 「本当にそれだけなのだろうか」と問う 第11章 わかりました、質問にお答えしましょう 1. 「語の意味を問う」に答える 2. 「本当にそうなのだろうか」に答える 3. 「本当にそれだけなのだろうか」に答える 4. 水掛け論って何? 5. 適切な反論とは? 第12章 プレゼンテーション後は早く帰りたいけど…… 1. 自分のプレゼンテーション後に何をすればよいか? 2. プレゼンテーションの美学 附録 プレゼンテーション実践例 参考文献一覧
この書籍は、面接における質問の裏にある本音を理解することで、効果的な答え方を身につけるためのガイドです。著者は6万人以上の就職支援を行ったプロで、面接準備や質問への正しい回答方法、ライバルとの差別化のための直前対策を提供しています。具体的な質問例とその意図を解説し、内定獲得のための戦略を紹介しています。著者はキャリアコンサルタントで、採用側の視点からのアドバイスが評価されています。
この教材は中上級から超級の日本語学習者を対象に、フォーマルな場面での発音練習を目的としています。内容は基礎編とフレージング練習に分かれ、聞きやすく分かりやすい発音を身につけるための具体的な練習が含まれています。著者は早稲田大学や東京外国語大学の非常勤講師です。
ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。
プレゼンは苦手だけど成功したい、会議の司会も緊張するけどやるしかない。そんなプレゼンと会議のプレッシャーが解消できる1冊。 プレゼンは苦手だけど成功したい、会議の司会も緊張するけどやるしかない。そんなプレゼンと会議のプレッシャーが解消できる1冊。
この書籍は、プロが使う資料作成のスキルやテクニックを紹介しています。内容は、スケルトン作成、ドラフト作成(文・図)、フィックス作成の各章に分かれ、具体的な方法や参考情報が提供されています。著者は外資系コンサルタントで、システム運用改善やファシリテーションに精通しています。
この書籍は、会社やチームで共有するための「資料作成の基本ルール」をまとめたもので、各ステップが1分で実行できる簡潔な内容です。エクセルの使い方、魅力的なグラフの作成法、効果的なプレゼン資料の構成などが紹介されており、外資系のスキルを手軽に習得できます。著者は熊野整氏で、豊富な実務経験を持ち、個人向けエクセルセミナーも人気です。
本書は、資料作成に関する基本を解説したビジネス書で、特に初心者向けに「基礎のキソ」を重視しています。著者は、伝わる資料作りのために必要なテクニックや考え方を紹介し、テンプレートに頼らずに自分で資料を作成する方法を伝授します。目次には、資料作成の基本や説得力を高める方法、実際の作成手順が含まれています。著者は知的生産研究家の永田豊志氏です。
著者の森秀明は、効率的な資料作成とコミュニケーションの手法を紹介する書籍を執筆しました。内容は、資料作成のガイドライン、ビジュアルと論理の関係、相手を説得するロジック、そしてコミュニケーションの重要性などに焦点を当てています。著者は多くのコンサルタントを育てた経験を活かし、実践的なアプローチを提供しています。
本書は「自分らしいプレゼン」の重要性を説き、聴衆の心を動かすための考え方やテクニックを紹介しています。プレゼンはビジネスにおいて不可欠であり、上手なプレゼンを真似るだけでは成功しません。自然体で自分の想いを伝えることが大切で、共感を生むプレゼンが求められます。内容は「自分らしさの発見」「聴き手の理解」「プレゼンの構成」「デザインの重要性」など多岐にわたり、実践的なワークや資料テンプレートも提供されています。著者は経験豊富なプレゼンデザイナーで、ビジネスパーソンが自分の想いを発信する手助けをしています。
本書は、様々な資料の添削を行ってきたコンサルタントが、「残念な資料」の原因とその改善方法を詳述したものです。資料には目的が曖昧、結論が不明確、根拠が不足しているなどの問題があると指摘し、これを解決するための4つのステップ(結論の明確化、目的の明示、具体化、根拠の再構築)を提案しています。具体的な改善例や資料作成のフォーマットも紹介されており、ロジカルな資料作成を目指す内容となっています。
この書籍は、プロの英語プレゼンテーション講師が論理的に話を進める手法や説得力のある資料作成法を紹介しています。目次には、構成や資料作成、イントロダクション、本題の伝え方、まとめ、質疑応答、ジェスチャー、オンラインプレゼンテーション、スライド例などが含まれています。著者の江藤友佳は、英語教育とビジネスプレゼンテーションの専門家で、企業研修や教材制作を行っています。
この書籍は、資料作成における基本的なスキルやテクニックを解説しており、特に見落としがちなポイントに焦点を当てています。内容は、資料作成の流れ、安定感のあるルールの設計、分かりやすい資料作成、視覚的に魅力的な資料作成に分かれています。著者は外資系コンサルタントの吉澤準特で、幅広いコンサルティング経験を持つ専門家です。
『あなたのプレゼン 誰も聞いてませんよ!』の続編で、著者がプレゼンテーションのスライド作成技術を原則から具体的な修正方法まで解説しています。多くの実例を通じて好みのスライド型を学べるほか、ポスター作成に関する内容も含まれています。
『スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン』の著者カーマイン・ガロが、シェリル・サンドバーグやビル・ゲイツなどのTEDトークを分析し、成功するプレゼンテーションのテクニックを紹介しています。内容は感情に訴える技術、目新しさの演出、記憶に残る話し方の3部構成で、具体的な方法論が示されています。著者はコミュニケーションコーチで、多くの企業で講演経験があります。翻訳は土方奈美が担当。
この書籍は、パワーポイントでの資料作成時の悩みや不安を解消するための外資系コンサルタントのテクニックを紹介しています。具体的なビフォーアフターの例を通じて、効果的なPRポイントの見つけ方や不都合なデータの扱い方を提案しています。
本書では、ビジネス資料を効果的に作成するための「デザイン」と「編集力」の重要性を解説しています。見栄えだけではなく、整理された内容が必要で、メリハリのある資料が相手に伝わると強調しています。具体的な悩みを解決するために、Before/Afterの作例を用いて、改善点を赤ペン添削スタイルで示し、レイアウトや配色、編集の考え方を紹介しています。資料作成の参考になる内容です。
本書は、スピーチや面接などで頻繁に使われる無意味な言葉「えーっと」「あー」などを「えーあー症候群」と定義し、その改善方法を科学的に解説します。著者は、これらの言葉を減らすことで説得力が増し、相手に伝わりやすくなると主張しています。内容は、フィラーの原因や心の状態、思考の整理、声の使い方、実践トレーニングなど多岐にわたり、短期間で改善できる方法を提供しています。著者はスピーチトレーナーとして多様な経験を持ち、実践的な指導を行っています。
この書籍は、ビジネスパーソン向けにプレゼン資料作成の基本をビジュアルで解説しており、初心者でも即実践できる内容になっています。資料の説得力を高める構成やスライド作成、効果的なグラフの使い方、見やすい資料への改善方法、パワーポイントの便利技などが紹介されています。著者は岸啓介で、ビジネスデザインに精通した専門家です。
本書は、効果的な「伝え方」の原理原則を解説しています。著者の松永光弘は、長文メールや情報過多による伝達の失敗を避けるため、シンプルなコミュニケーションの方法を提案。多くのクリエイターとの経験を基に、伝え方の重要な要素や魅力を引き出す方法をまとめています。内容は、伝え方の原則、魅力の語り方、メッセージの見つけ方、最適化の手法など、具体的な章立てで構成されています。松永氏は編集家として多くの著名クリエイターを支援し、幅広い分野でのコミュニケーションに貢献しています。
『スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい』の続編では、資料作成における基本的なノウハウを解説し、他人に迷惑をかけないためのWordとExcelのテクニックを紹介しています。著者は2000人以上の受講生を指導したベテランで、資料作成の新常識や効率的な文書管理、データ入力の工夫を提案。サンプルファイルを使って実践的に学ぶことができ、社会人として必要なパソコンスキルを身につける内容です。
この書籍は、「よい表現」を「最高の表現」に引き上げるための視点とスキルを提供し、100以上のエクササイズを収録しています。ビフォー・アフターを通じて改善点を指摘し、認知メカニズムを詳しく解説しています。目次には、コンテキスト理解、伝わりやすい表現選び、不要要素の除去、注意を引く方法、デザイン思考、ストーリー伝達などが含まれています。著者は、ビジュアルコミュニケーションの専門家であり、企業や団体向けに研修を行っています。
この書籍は、トヨタ式の「A3用紙1枚」にまとめる資料作成術を紹介しています。内容は、問題解決のためのA3報告書の作成方法、真因分析や解決策の導出、企画提案書の作成、革新的なアイデアを生むアナロジー思考に関する技術が含まれています。著者の稲垣公夫は、トヨタ生産方式を研究し、経営企画の経験を持つ専門家です。
この書籍は、ビル・ゲイツに絶賛されたプレゼンテーション技術を紹介しています。著者は、日本マイクロソフトの澤円で、全世界で12万人のトップに選ばれた実績があります。内容は、人を動かすための「6つの法則」を基に、プレゼン・発表・報告・セールスなどさまざまな場面での効果的な伝え方を解説しています。目次には、プレゼンの大原則やビジョン作り、構成や話し方のテクニックが含まれています。
本書は、プレゼンテーションの成功率を高めるためのノウハウを3つのステップ(内容づくり、資料のデザイン、伝え方の練習)で解説した入門書です。著者は多くの法人研修やセミナーを行っており、ITやデザインの知識がなくても理解できるよう配慮されています。改訂版ではオンラインプレゼンのポイントも追加されています。プレゼンに苦手意識がある人や、自己流を卒業したい人に特におすすめです。豊富な図解と具体的な説明で、基本から学ぶことができます。
「Googleスライド」に関するよくある質問
Q. 「Googleスライド」の本を選ぶポイントは?
A. 「Googleスライド」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「Googleスライド」本は?
A. 当サイトのランキングでは『一生使える 見やすい資料のデザイン入門』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで144冊の中から厳選しています。
Q. 「Googleスライド」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「Googleスライド」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。





















![『Google Workspace完全マニュアル[第3版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51k1c-PyCUL._SL500_.jpg)





![『デザイン入門教室[特別講義] 確かな力を身に付けられる ~学び、考え、作る授業~ (Design&IDEA)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41YXUWBgsAL._SL500_.jpg)