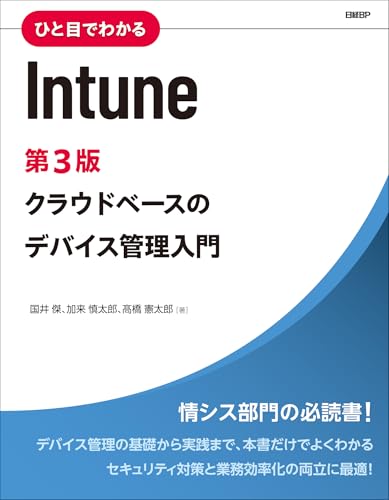【2025年】「セキュリティエンジニア」のおすすめ 本 99選!人気ランキング
- 図解即戦力 情報セキュリティの技術と対策がこれ1冊でしっかりわかる教科書
- 詳解 インシデントレスポンス ―現代のサイバー攻撃に対処するデジタルフォレンジックの基礎から実践まで
- 【イラスト図解満載】情報セキュリティの基礎知識
- 暗号技術入門 第3版
- 図解入門 よくわかる 最新 情報セキュリティの技術と対策 (How-nual図解入門Visual Guide Book)
- サーバ/インフラエンジニアの基本がこれ1冊でしっかり身につく本
- 絵で見てわかるITインフラの仕組み 新装版
- 動かして学ぶセキュリティ入門講座 (Informatics&IDEA)
- ゼロからはじめるLinuxサーバー構築・運用ガイド 動かしながら学ぶWebサーバーの作り方
- 体系的に学ぶ 安全なWebアプリケーションの作り方 脆弱性が生まれる原理と対策の実践
この書籍は、情報セキュリティに関する基本知識をキーワード形式で解説しており、特に「情報セキュリティマネジメント試験」の午前重点分野に焦点を当てています。内容は、セキュリティの概念、サイバー攻撃の手法、基礎技術、管理方法、対策知識、実装に関する知識など多岐にわたります。イラストを用いてわかりやすく説明されており、情報セキュリティマネジメント試験受験者におすすめです。著者はサイバーセキュリティの専門家で、実務経験を持つプロフェッショナルです。
本書は、インシデント対応に必要な専門知識を持つ実務家が執筆したもので、ログ分析やフォレンジック、マルウェア解析などの技術を紹介しています。現代の脅威に対応するための最新技術や実践的なアプローチを解説し、IT専門家や学生、セキュリティエンジニアに役立つ内容となっています。目次は準備、対応、精緻化の三部構成で、具体的な手法や改善策が含まれています。
『新版暗号技術入門』の改訂版は、2008年の刊行以来セキュリティ関連で人気を保ち続けている書籍です。暗号技術の基本を図解と易しい文章で解説し、対称暗号や公開鍵暗号、デジタル署名などを取り上げています。第3版では、現代の暗号技術に関する最新情報や、SHA-3、SSL/TLSへの攻撃、ビットコインとの関係などが加筆されています。全ての人にとって必読の内容で、暗号の歴史から応用技術まで幅広くカバーしています。
この書籍は、情報セキュリティの重要性と対策について解説しています。サイバー犯罪やウイルスからの防御を目的とし、コンピューターやスマートフォンが必須の現代社会において、ウイルス対策ソフトやゼロトラスト・セキュリティなど、幅広い対策を紹介しています。内容は、情報セキュリティの基礎、サイバー攻撃の理解、技術的対応策、具体的なセキュリティ対策、関連制度について構成されています。著者はサイエンスライターの若狭直道です。
本書は、サーバやインフラの運用・管理に必要な技術や知識を基礎から解説した教科書です。ネットワークやサーバの基本知識に加え、クラウド関連の知識やエンジニアとしての考え方、学習法、スキルアップ、業務知識、職業倫理も取り上げています。これからサーバ/インフラエンジニアを目指す人に適した内容となっています。目次には、エンジニアとしての生き方、ネットワーク、インターネット、サーバ、仮想化、ミドルウェア、Webサービス運用、セキュリティ、クラウド、法律・ライセンスの基礎知識が含まれています。著者は馬場俊彰氏で、豊富な実務経験を持つエンジニアです。
『絵で見てわかるITインフラの仕組み』の新装版は、ITインフラの基盤技術を理解しやすく解説しています。著者の経験を基に、アーキテクチャ、ネットワーク、サーバーなどをマクロからミクロの視点で説明し、共通する原理を本質的に理解できるように工夫されています。図が豊富で、実務経験が浅い方でもイメージしやすく、インフラ担当者やアプリ開発者、DB管理者におすすめです。
本書は、企業や個人のセキュリティ対策に役立つ知識を図解で提供する「使える教科書」です。基本的な考え方から具体的な技術、運用方法までを網羅しており、管理者や開発者にとっても有益です。目次には、ネットワーク攻撃やウイルス、暗号技術、法律など多岐にわたるテーマが含まれています。読者は興味のある項目を選んで学ぶことができ、実習項目もあり、自宅で体験することが可能です。セキュリティ対策を強化したい人に特におすすめです。
本書は、経営者やマネジメント層が知っておくべきサイバーセキュリティの基本知識を解説した入門書です。サイバー攻撃が企業にとって重大なリスクとなる中、経営層の関心が薄い現状を指摘し、責任を果たすための役割や戦略、組織づくり、システム管理、インシデント対応について具体的に説明します。豊富な図版を用い、実践的な内容が盛り込まれており、業種や規模を問わず多くの経営者に推奨されています。著者はNECのサイバーセキュリティ専門家です。
本書は「サイバーセキュリティ」をテーマに、専門家以外でも理解できる内容を提供します。前半では情報資産の保全やリスク、対策について解説し、後半では技術的な詳細に踏み込みます。ITパスポート合格者や基本情報技術者を目指す人向けに、専門用語を丁寧に説明しながら、サイバー攻撃の手口やセキュリティの基本、関連技術について学べる内容です。著者は情報セキュリティの専門家で、実践的な知識を身につけることができます。
この書籍は、ハッカーの視点から攻撃手法を分析し、防御方法の本質を理解するためのセキュリティガイドの改訂版です。目次にはプログラミング、脆弱性攻撃、ネットワーク、シェルコード、攻撃と防御の共進化、暗号学などが含まれています。著者はセキュリティの専門家であり、ハッキングやプログラミングに関する豊富な経験を持っています。
本書は、インターネット技術における情報セキュリティの基礎を体系的に解説した入門書で、特にネットワークセキュリティ技術の最新情報を提供しています。内容は暗号技術、認証技術、セキュリティプロトコル、ホストおよびネットワークセキュリティ、Webセキュリティに及び、10年ぶりに大幅な改訂が行われています。著者は情報セキュリティ技術の専門家で、サイバーセキュリティの人材育成にも取り組んでいます。
本書は、Web系エンジニアになるための包括的なガイドです。IT業界の基盤が確立され、プログラミング教育が普及する中、特に需要が高まっているWeb系エンジニアの職業について、必要な知識やキャリアステップを解説しています。内容は、Web系企業の定義や職種、使用する技術、働き方、フリーランスへの道、キャリア形成の戦略など多岐にわたります。初学者や駆け出しエンジニアがWeb業界の全体像を理解し、必要なスキルを把握できる一冊です。著者は豊富な経験を持つエンジニアで、実体験に基づいた情報を提供しています。
本書は、Dockerを使ってコンテナ技術を学び、仮想サーバーを簡単に構築する方法を解説した初心者向けのガイドです。Webクリエイターやエンジニアが本番環境での検証を行うために必要な知識を提供し、Linux、Webサーバー、データベース、WordPressの設定ファイルも掲載しています。手順はステップ・バイ・ステップで説明されており、仮想化技術に不安を感じる人でも取り組みやすい内容となっています。
この書籍は、情報セキュリティマネジメント(SG)試験に向けたテキストと問題集で、科目A・Bを徹底的に対策します。改訂版では最新の動向を反映し、基礎から確実な知識を身につけるためのアジャイル式学習法を採用。AIによる出題傾向分析や、科目Bに関する事例問題も収録されており、合格力を高めるためのサンプル問題や過去問題解説も提供されています。さらに、電子版PDFや単語帳などの特典もあり、試験直前の要点チェックが可能です。著者は、情報セキュリティ分野での豊富な経験を持つ専門家です。
本書は、サイバーセキュリティエンジニアを目指す学生や、関連部署に異動した社会人向けの教科書です。サイバーセキュリティの重要性が増す中、様々な職種があるため、基礎知識と専門知識を学ぶことが求められます。前半では基本的な知識を、後半では具体的な職種に必要な知識を解説しています。内容は、情報セキュリティの基礎、セキュリティエンジニアの仕事内容、マネジメント、セキュア開発、脆弱性対応、オペレーション、インシデント管理など多岐にわたります。セキュリティエンジニアを目指す人にとっての入門書として推奨されています。
コレ一冊読めばWeb技術の基本が分かる!新しいテクノロジーが登場しても基本となるWebの技術は非常に大事だし活きる!IT系の仕事に付く人はまずこの書籍を読んで基本を固めるべし!
本書は、現代の分散システム設計におけるデータの扱いに焦点を当て、リレーショナルデータベースやNoSQL、ストリーム処理などのテクノロジーの特性を詳述しています。データ指向アプリケーションの設計に必要な基本概念を解説し、レプリケーションやトランザクション、バッチ処理などの分散データの管理手法についても触れています。ソフトウェアエンジニアやアーキテクトにとって必携の一冊です。
本書は、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める中で直面する情報セキュリティの問題に焦点を当てています。特に、CISO(最高情報セキュリティ責任者)の役割を通じて、情報セキュリティの課題解決方法を最新情報に基づいて提案しています。目次には、情報セキュリティの基礎知識、指標化、監査、DXとの関係、インシデント対応、CISOの責務などが含まれています。著者は高橋正和氏で、豊富な経験を持つセキュリティの専門家です。
本書は、業務レベルでのLinuxサーバ運用に必要な基本知識をまとめた教科書で、コマンドの実行例を多数掲載しています。学習者は実際にコマンドを実行しながら、Linuxの基礎を学ぶことができます。目次には、Linuxの導入からネットワーク管理、セキュリティ対策まで幅広いテーマが含まれています。著者は、LinuxやUNIXの専門家であり、長年の経験を持っています。
本書は、Wiresharkの機能とパケット解析技術を詳しく解説した改訂第3版で、TSharkに関する新たな情報が追加されています。実際のパケット情報を用いて問題解析を行い、キャプチャファイルはWebからダウンロード可能で、初心者でも理解を深められる内容です。また、日本語版ではWin10PcapやUSBPcapの解説も含まれています。著者はコンピュータセキュリティの専門家や技術者で構成されています。
この書籍は、TCP/IPの基礎を3分で理解できる内容で、ネットワークの基本知識、信号の伝送、IPアドレッシング、ルーティング、コネクションとポート番号について解説しています。著者の網野衛二は、コンピューター専門学校の講師であり、ネットワークに関する講座や連載を行っています。
この書籍は、ITインフラの基礎知識を包括的に解説しており、サーバー、OS、ネットワーク、ストレージ、仮想化、クラウド、データセンター、セキュリティ、運用などの最新情報が含まれています。新入社員やインフラエンジニアを目指す人に推奨される入門書です。著者は富士通やLINEでの豊富な経験を持つ佐野裕氏です。
この書籍は、WebブラウザがURLを入力してからWebページが表示されるまでのプロセスを探る内容で、ネットワーク技術に関する基礎解説が大幅に加筆された改訂版です。目次にはブラウザ内部のメッセージ作成、TCP/IPプロトコル、LAN機器(ハブ、スイッチ、ルーター)、アクセス回線とプロバイダ、サーバー側のLAN、Webサーバーへの到達と応答データの戻りなどが含まれています。著者はネットワーク業界での経験を持つ戸根勤氏です。
デジタル・フォレンジックに携わる情報処理技術者や警察・検察、金融関係者、弁護士向けにまとめられた実践に役立つ教科書。 デジタル・フォレンジックがどのような技術なのか、といった基礎的事項から、法律や法廷対話といった実践的・応用的事項までを記載し、包括的に学べるようにまとめた。 デジタル・フォレンジックとは、事件や事故発生時に、捜査や裁判の証拠などに用いられる電磁的記録データを解析する技術やその手法をいう。本書はデジタル・フォレンジックに携わる情報処理技術者や警察・検察、金融関係者、弁護士向けにまとめられた実践に役立つ教科書。どのような技術なのか、といった基礎的事項から、実際に用いる簡単なツールの使い方やOSおよびファイルシステムの解説、さらには法律や法廷対話といった実践的・応用的事項までを記載し、包括的に学べるようにまとめた。 まえがき 第1章 デジタル・フォレンジック入門 1.1 デジタル・フォレンジックとは何か 1.2 デジタル・フォレンジックが重要になってきた背景 1.3 デジタル・フォレンジックの主要な手順 1.3.1 手順の分類法 1.3.2 デジタル・フォレンジックの手順の一例 1.4 デジタル・フォレンジックの分類軸 1.5 デジタル・フォレンジックにおいて必要となる技術の概要 1.5.1 手順に対応する技術 1.5.2 ファイル復元技術の概要 1.6 デジタル・フォレンジックの作業を実施する上で注意すべき事項 1.6.1 プライバシーとの関連 1.6.2 早急な対応との関連 1.7 類似の用語との関係 1.8 デジタル・フォレンジックの法的側面の概要 1.8.1 民事訴訟法における証拠としての有効性 1.8.2 刑事訴訟法における証拠としての有効性 1.9 本書の構成 参考文献 第2章 ハードディスクの構造とファイルシステム 2.1 コンピュータの構造と補助記憶装置 2.2 補助記憶装置 2.2.1 ハードディスク 2.2.2 フラッシュメモリ 2.2.3 光学ディスク 2.2.4 磁気テープ 2.3 ハードディスクドライブ内のデータの消去技術と復元技術 2.3.1 ファイルシステムとファイルの削除 2.3.2 ファイルやデータの復元技術 第3章 デジタル・フォレンジックのためのOS入門 3.1 コンピュータ内のソフトウェア 3.2 オペレーティングシステムとその起動 3.3 ファイルシステムの基本的機能 3.4 プロセス管理とメモリ管理 3.5 データ表現 3.6 ログとダンプ 第4章 フォレンジック作業の実際―データの収集 4.1 エビデンスの取り扱い 4.2 ハードウェアによるデータ収集 4.3 ソフトウェアブートによるデータ収集 4.4 ソフトウェアによるデータ収集 4.5 ファイルデータのみの収集 4.6 モバイル端末のデータ収集 4.7 メモリなどの揮発性情報のデータ収集 4.8 外部記録媒体のデータ収集 4.9 セキュリティ設定がある場合の対処法 4.10 Evidence InformationとChain of Custody 4.11 収集用ソフトウェアの使用方法 参考文献 第5章 フォレンジック作業の実際―データの復元 5.1 データの削除 5.2 データの復元 5.2.1 メタデータからの復元 5.2.2 カービングによる復元 5.2.3 上書きされたデータの復元 5.3 データの隠蔽 5.4 データ復元のツール 第6章 フォレンジック作業の実際―データの分析 6.1 データ分析の基本 6.1.1 Windowsレジストリ 6.1.2 Windowsシステムファイル 6.1.3 時刻 6.1.4 ハッシュ分析 6.1.5 プログラム実行履歴 6.1.6 デバイス接続履歴 6.2 タイムライン分析 6.3 ユーザファイルの解析 6.3.1 文字コード 6.3.2 キーワード検索 6.3.3 類似ファイルの検索 6.3.4 Predictive Coding(プレディクティブコーディング) 6.3.5 ファイルヘッダー 6.3.6 メタデータ 6.3.7 画像ファイルの調査 6.3.8 Eメールの調査 6.3.9 インターネットアクセス履歴の調査 6.4 データ解析ソフトウェア(Autopsy)の使用方法 6.4.1 Autopsyの概要と特徴 6.4.2 Autopsyの起動とデータ読み込み手順 第7章 スマートフォンなどのフォレンジック 7.1 モバイル・フォレンジックの必要性と課題 7.1.1 なぜモバイル・フォレンジックが必要か 7.1.2 モバイル・フォレンジックの課題 7.1.3 モバイル端末に関連するデータの格納先 7.2 モバイル端末のデータ収集 7.2.1 モバイル端末収集時の注意点 7.2.2 ロジカルデータ収集 7.2.3 物理データ収集 7.3 iOS端末におけるフォレンジック 7.3.1 iOS端末におけるロジカルデータ収集方法 7.3.2 ジェイルブレイク 7.3.3 iOS端末におけるアプリのデータ構造 7.3.4 PLIST解析 7.4 Android端末におけるフォレンジック 7.4.1 Android端末におけるロジカルデータ収集方法 7.4.2 ルーティング 7.4.3 Android端末におけるSDカード調査の重要性 7.4.4 Android端末におけるアプリのデータ構造 7.5 SQLite解析 第8章 ネットワーク・フォレンジック 8.1 ネットワーク・フォレンジックの必要性 8.2 ネットワークログの管理 8.2.1 ネットワークログの収集ポイント 8.2.2 ログの取得・管理の在り方 8.2.3 ネットワークログの分析 8.3 トラフィック監視 8.3.1 イベントに基づくアラートの監視 8.3.2 パケットキャプチャ 8.3.3 トラフィック統計監視 8.4 標的型攻撃とフォレンジック 8.4.1 標的型攻撃と対策の概要 8.4.2 SIEM 参考文献 第9章 フォレンジックの応用 9.1 デジタル・フォレンジックを適用するインシデント 9.1.1 PCなどの情報処理機器に対する不正の例 9.1.2 PCなどの情報処理機器を利用した不正の例 9.1.3 デバイス別の分析対象ファイル 9.2 民間におけるデジタル・フォレンジック調査事例 9.2.1 PCに対する不正:不正アクセスによる情報漏洩調査事例 9.2.2 PCを利用した不正:不正会計調査事例 9.2.3 民間におけるフォレンジック報告書の例 9.3 省庁の犯則事件調査における事例 9.4 訴訟に対応するためのeディスカバリにおける事例 9.4.1 情報ガバナンス 9.4.2 データの特定 9.4.3 データの保全 9.4.4 データの収集 9.4.5 データの処理 9.4.6 データの分析 9.4.7 データのレビュー 9.4.8 提出データの作成 参考文献 第10章 法リテラシーと法廷対応 10.1 法的観点からのデジタル・フォレンジックの重要性 10.2 裁判メカニズム 10.2.1 結論(判決の主文) 10.2.2 権利・義務の発生 10.2.3 主文の強制的な実現 10.2.4 裁判を審理する3つのステージ 10.3 ケース・スタディー営業秘密の不正取得(情報漏洩)を例に 10.4 請求原因 10.4.1 大前提(法律要件) 10.4.2 小前提(エレメント) 10.4.3 請求原因の証明による効果 10.4.4 判決の主文に示される付随事項 10.5 抗弁・再抗弁・再々抗弁 10.5.1 抗弁 10.5.2 再抗弁 10.5.3 再々抗弁 10.6 証明責任の分配の整理 10.7 直接事実・間接事実・補助事実 10.7.1 直接事実(エレメント) 10.7.2 間接事実 10.7.3 補助事実 10.8 証拠調べ方法 10.8.1 人証(証人・当事者) 10.8.2 書証 10.8.3 検証 10.8.4 鑑定 10.8.5 クラウド業者からの民事訴訟法上の証拠収集 10.8.6 犯罪被害者保護法による刑事公判記録の閲覧謄写 10.8.7 プライバシーや営業秘密に対する民事訴訟法の配慮 10.9 民事訴訟法の証拠保全 10.9.1 民事訴訟法の証拠保全の手続趣旨 10.9.2 証拠保全を使った人証(証人・当事者)・書証・検証・鑑定 10.9.3 人工知能 10.10 証人尋問の実際 10.11 証人尋問の解説 10.11.1 準備書面 10.11.2 準備書面の「陳述」 10.11.3 書証(甲号証・乙号証) 10.11.4 原本提出の原則 10.11.5 文書成立の真正 10.11.6 人定質問 10.11.7 宣誓 10.11.8 尋問の順序 10.11.9 訴訟記録の閲覧謄写複製制限(民事訴訟法92条) 10.11.10 証人尋問冒頭の質問事項 10.11.11 書類に基づく陳述の制限 10.11.12 尋問に対する異議 10.11.13 証拠保全の強制力 参考文献 第11章 デジタル・フォレンジックの歴史と今後の展開 11.1 デジタル・フォレンジックの簡単な歴史 11.2 今後の動向の概要 11.3 PCの記憶媒体としてのSSDの普及とフォレンジック 11.4 eディスカバリやネットワーク・フォレンジックにおけるAIの利用 11.4.1 eディスカバリにおけるAIの利用 11.4.2 サイバーインテリジェンスへのAIの応用 11.4.3 ネットワーク・フォレンジック対策のインテリジェント化 11.5 おわりに 11.6 さらに知りたい人のために 参考文献 ミニテスト ミニテスト解答 索引 COLUMN スラック領域 インターネットフォレンジック 情報漏洩の発見的コントロール 内部不正者の実際
本書『マスタリングTCP/IP 入門編 第6版』は、TCP/IPに関する解説書の最新版で、時代に即したトピックを追加し内容を刷新しています。豊富な図版や脚注を用いて、TCP/IPの基本をわかりやすく解説しており、ネットワークやインターネットプロトコルの理解を深めるための入門書として最適です。著者は複数の専門家で構成されています。
本書は、新人エンジニアやクラウドに取り組むエンジニア向けに、Amazon Web Services、Google Cloud Platform、Microsoft Azureなどの主要クラウドサービスの全体像や、実際の企業事例を通じてクラウドの構築と運用のノウハウを学ぶためのガイドです。特集では、クラウドの現状と未来、主要プラットフォームの詳細、そして実践的な事例を紹介し、クラウドを効果的に活用するための知識を提供します。
本書は、急速に普及するWeb APIのセキュリティ対策に焦点を当てています。API呼び出しが全Webトラフィックの80%以上を占める中、サイバー攻撃も増加しており、脆弱性のテストが重要です。攻撃者の視点からAPIの機能を理解し、情報漏洩のリスクを防ぐ方法を学びます。内容は、WebアプリケーションやAPIの基礎知識、検証用ラボの構築、さまざまな攻撃手法の解説に分かれ、REST APIとGraphQL APIのセキュリティテストに特に重点を置いています。情報セキュリティやWebアプリケーション開発に関心があるエンジニアにとって有益です。
このテキストは、情報セキュリティ管理士認定試験合格を目指すための必携書で、わかりやすい解説と豊富な演習問題を提供しています。内容は情報セキュリティの基本、脅威と対策、コンピュータの知識、そして総合演習問題で構成されています。著者は、25,000名以上を指導した経験を持つ情報処理技術者試験対策の講師です。
本書は、クラウドサービス「Amazon Web Services(AWS)」を利用してネットワークやサーバーの構築を学ぶためのガイドです。初心者やアプリ開発者に最適で、実機に触れることなくインフラ技術を習得できます。改訂4版では、AWSの最新UI、Amazon Linux 2023への対応、TLS/SSLやHTTP/2への配慮が追加されています。内容はシステム構築からネットワーク、サーバー、Webサーバーのインストール、通信の仕組みまで幅広くカバーしています。著者は技術者としての豊富な経験を持つ専門家たちです。
この書籍は、企業のサイバーセキュリティ対策に関する基本事項や、平時と有事の対応を詳述しています。特に、ランサムウェアインシデントへの具体的な対応事例を通じて、国内外の法令に基づく実務上の留意点を解説しています。著者はサイバーセキュリティの専門家で、組織の危機管理や業務復帰、損害賠償責任についても触れています。
本書は2020年2月に改訂されたCCNA試験(試験番号200-301)に対応したテキストと問題集で、IT専門スクールの講師が執筆しています。基礎力を効率的に身につけることができ、理解度を確認するための問題や模擬試験が収録されています。独学での学習をサポートし、初めてCCNA試験に挑戦する人に最適です。合格に必要なポイントを網羅し、1冊で合格を目指せる内容となっています。
本書は、サイバー攻撃やサイバーセキュリティに関する法的論点を、個人や企業、取引先、ITベンダー、従業員などの当事者別に整理し、裁判例を参考にした損害補填の考え方を検討しています。また、サイバーインシデントに対する平時と有事の対応を体系的にまとめており、具体的なインシデントに対する対応マニュアルも提供しています。
本書は、LPICのレベル1試験がVersion4.0から5.0にアップデートされたことに対応した学習書です。内容はLPI-incの認定テキストに基づき、101試験と102試験に対応しています。章ごとに練習問題や模擬試験を収録し、Linux実習環境も提供されています。LPIC試験の対策やLinux学習に役立つ一冊です。
本書は、GoogleのセキュリティとSREの専門家が、セキュアでスケーラブル、かつ信頼性の高いシステムを設計するためのベストプラクティスを紹介します。システムの設計、実装、保守に関する考え方や実践法に加え、組織文化の重要性についても説明しています。内容は、セキュリティと信頼性の関係、設計のトレードオフ、ディザスタプランニングなど、多岐にわたります。
本書は、情報セキュリティ技術者向けにPython 3に対応して改訂された必携書で、サイバー攻撃手法を解説しています。基本的な通信プログラムからProxy、Rawデータ、Webアプリケーションへの攻撃、トロイの木馬の動作、フォレンジック手法、OSINTまでをカバーし、攻撃者の手法と防御方法を学べます。また、日本語版には「Slackボットを通じた命令の送受信」や「OpenDirのダンプツール」などの付録も収録されています。著者はサイバーセキュリティの専門家やプロのプログラマーで構成されています。
内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が、企業向けにサイバーセキュリティ対策に関する法令をQ&A形式で解説したハンドブックを発行しました。内容は、平時の対策やインシデント発生時の法的課題に関するもので、サイバーセキュリティの基本法や情報開示、個人データの取り扱いなど多岐にわたります。
本書は、CSIRT(コンピュータセキュリティインシデント対応チーム)の構築と運用に必要な知識を網羅しており、サイバー攻撃から組織を守るためのインシデント対応の基本やセキュリティモニタリング、プランニング方法などを解説しています。著者はシスコシステムズのセキュリティ専門家で、実践的な知見を基にした内容が特徴です。CSIRTの導入を検討している企業の実務者にとって必読の一冊です。
本書は、サイバー攻撃の常態化に対し、国際法がどのように対応するかを解説したものです。著者は日本政府代表として国連のサイバーセキュリティ会議に参加した外交官であり、各国の立場や国際的な議論の現状、課題について分かりやすく説明しています。巻末には、日本政府の立場や関連資料が収録されており、初学者や専門家にとっても有益な内容となっています。
本書は、AI時代におけるサイバーセキュリティの重要性とリスクについて解説するもので、企業や個人が自らの資産や信用を守るための対策を紹介しています。サイバー攻撃の手法や情報漏洩のリスクに対する防止策を第一人者に質問しながら掘り下げ、最新の知識を得ることができます。内容は、サイバーセキュリティの基礎から先進事例まで幅広くカバーしており、ビジネスにおけるセキュリティの重要性も強調されています。
本書は、OSINT(オープンソースインテリジェンス)を含む脅威インテリジェンスの基礎知識と実践手法を解説しています。インターネット上の情報を活用して自社のセキュリティ状態を把握し、攻撃に備える「攻めのセキュリティ」を実現するための内容です。章立ては、OSINTの基礎、必携ツールの使い方、情報の可視化、グローバルな活用事例となっています。
本書は、情報セキュリティのエンジニアや研究者向けに機械学習の基礎を解説した入門書です。フィッシングサイトやマルウェア検出、侵入検知システムにおける機械学習の適用方法を実装レベルで学ぶことができ、検出回避の手法も紹介されています。Python 3に対応したサンプルコードを用い、Google Colaboratoryで実践的に学習できます。著者は情報セキュリティの専門家であり、各章では具体的な技術や問題解決の手法が詳述されています。
ロシア・ウクライナ戦争と領域横断の戦い ハイブリッド戦争の概念 先端技術の進化と領域統合の戦い サイバー活動・電磁波・宇宙に関する技術的展開の国際人道法への影響 民間企業活動と新領域における安全保障問題 サイバー領域の安全保障と法的課題 サイバー攻撃対処をめぐる諸課題 サイバー領域の安全保障政策の方向性 国内法制度とサイバー分野 国際法上合法なサイバー作戦の範囲 宇宙領域のアセット防護 宇宙領域の安全保障の法的課題 電磁波領域の安全保障利用と法的課題 無人兵器の発展と法的課題 無人兵器の運用と法的課題 無人兵器の国際法規制 新領域の安全保障体制のあり方と法的課題〈提言〉
サイバー攻撃の90%はうっかりミスによるもので、職員が正しい知識を持つことが重要です。本書は、ITやデジタルツールに不慣れな人々に向けて、サイバー空間の防御基礎を解説しています。目次には、セキュリティ対策や攻撃手法、SNSの脅威、セキュリティ運用などが含まれています。
本書は、エシカルハッキングの事例を通じて、アプリケーションの脆弱性を発見し報告する方法を解説しています。TwitterやFacebook、Googleなどの実例を挙げ、攻撃者がどのようにしてユーザーを騙し、情報を盗むか、また様々なウェブセキュリティの脆弱性について詳述しています。バグハンターやセキュアなアプリケーションを開発したいエンジニアにとって必携の一冊です。著者は経験豊富なバグバウンティハンターで、現在はアプリケーションセキュリティエンジニアとして活躍しています。
本書は、現代のWebブラウザにおけるセキュリティ機構を解説し、開発者が理解すべき脅威や対策を整理しています。攻撃者とブラウザ開発者の歴史的なせめぎ合いを背景に、Webセキュリティの基本概念や主要な機構(Origin、CORS、Cookie、HTTPSなど)について詳述しています。また、さまざまな攻撃手法の進化も取り上げ、Webセキュリティの理解を深める内容となっています。
ポートスキャンで攻撃手法を理解しセキュリティ思考を深める!脆弱性診断やペネトレーションテストで使われる技術にポートスキャンがあります。本書では、ポートスキャンを用いて攻撃者がネットワークを経由してどのように攻撃してくるのかを具体的な手法を交えて学び、攻撃手法を知ることでセキュリティレベルの向上を目指します。Scapyを用いたポートスキャナの自作、ポートスキャンの仕組みとネットワークプログラミングの基本、脆弱性診断やペネトレーションテストで不可欠なツールなどについて解説します。
「セキュリティエンジニア」に関するよくある質問
Q. 「セキュリティエンジニア」の本を選ぶポイントは?
A. 「セキュリティエンジニア」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「セキュリティエンジニア」本は?
A. 当サイトのランキングでは『図解即戦力 情報セキュリティの技術と対策がこれ1冊でしっかりわかる教科書』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで99冊の中から厳選しています。
Q. 「セキュリティエンジニア」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「セキュリティエンジニア」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。












































![『[改訂新版] 3分間ネットワーク基礎講座』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51oegv0Zi4L._SL500_.jpg)

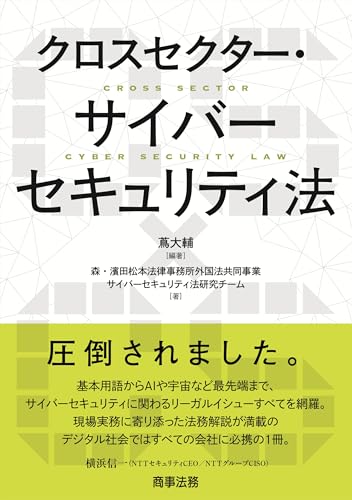



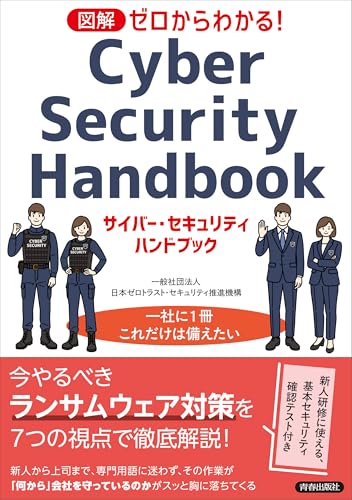








![『クラウドエンジニア養成読本[クラウドを武器にするための知識&実例満載! ] (Software Design plusシリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/61fVpJ0Dd0L._SL500_.jpg)







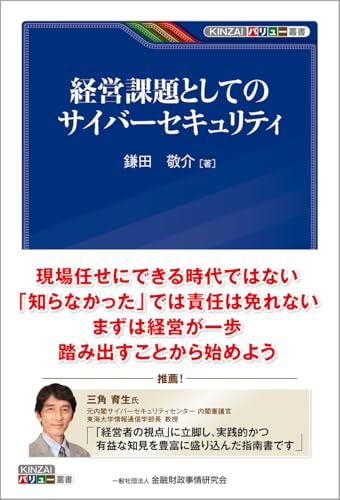


![『シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集[対応試験]200-301』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ePkoEBL5L._SL500_.jpg)