【2026年】「福祉」のおすすめ 本 112選!人気ランキング
- ケースワークの原則[新訳改訂版]:援助関係を形成する技法
- 参加したくなる会議のつくり方 公務員のためのファシリテーション入門
- イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術
- わかる!受かる!介護福祉士国家試験合格テキスト2021
- 福祉住環境コーディネーター検定試験3級公式テキスト
- 希望のつくり方 (岩波新書)
- 社会福祉士国家試験のためのレビューブック 2025
- 高齢者福祉 (最新・はじめて学ぶ社会福祉)
- 介護で使える言葉がけ シーン別実例250
- 福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト
この本は、ケースワークにおける援助関係を説明、定義、分析することを目的としています。目次は二部構成で、第一部では援助関係の本質や形成の原則について述べ、第二部では具体的な原則(個別化、感情表現、情緒的関与、受容など)を詳しく解説しています。著者は、ソーシャルワークや福祉学の専門家たちです。
この本は、会議における意見の出し方や結論のまとめ方を改善するためのファシリテーション技術を紹介しています。基礎から技術、実践、成長に至るまで、効果的な会議の準備や対話の進行方法を解説し、オンライン会議でも活用できる内容となっています。著者は多様なセクターでの経験を持つ加留部貴行氏で、ファシリテーションの専門家として活躍しています。
介護の専門家・三好春樹先生が、高齢者の自立を促すための介護技術を解説した初心者向けの本です。体に負担をかけない介助法や、よくある勘違いを指摘し、豊富なイラストで動作のポイントを示しています。介護する側とされる側の双方にとって快適な生活を実現するための内容で、家族や介護職、医療関係者におすすめです。
本書は、希望を自ら見つける重要性を説いています。著者は、希望とは何か、なぜ失われたのか、そしてそれをどのように取り戻すかを探求し、様々な事例や物語を通じて、希望を育むためのヒントを提供します。希望は与えられるものではなく、個人やコミュニティが共に創り出すものであるとのメッセージが込められています。各章では、希望の定義、失われた理由、希望の物語、取り戻すための方法が詳述されています。最終的には、希望を作り出すための具体的なアプローチが提案されています。
本書は、介護現場での効果的な「言葉がけ」の基本をシーン別に紹介し、実践的な対応テクニックを提供しています。内容は、起床・就寝、歩行・車イス、食事、入浴、更衣・整容、排泄、レクリエーション、送迎・外出、認知症など様々な状況に分かれています。著者は介護福祉士であり、コミュニケーションや認知症ケアに関する研修講師としても活動しています。
この文章は、ソーシャル・ケース・ワークに関する目次を示しており、ソーシャル・ケース・ワークの定義、相互依存、個人差、意図的な行為の基礎、家庭や学校、職場、病院、裁判所との関係、ソーシャル・ワークの形態と相互関係、そしてケース・ワークと民主主義についての内容が含まれています。
この書籍では、体を動かすレク、頭を使うレク、音楽を使うレク、ものづくりレクの4つのカテゴリーから100種類のレクリエーション活動を紹介しています。内容は、レクリエーションの意義や目的、具体的な活動例として風船バレーや脳トレゲーム、音楽クイズ、手芸などが含まれています。著者の加藤翼は介護福祉士で、認知症予防に関連したレクリエーションに力を入れています。
本書は、日本が「移民国家」としての現実を認識する必要性を論じています。過去30年間で在日外国人が約3倍に増加し、外国人労働者の受け入れも拡大しています。著者は、日本の移民事情を多角的に分析し、特に「遅れてきた移民国家」としての日本の実像や、外国人労働者の権利、技能実習生の問題などを探求しています。最終的には、移民を否認する国としての日本の未来を考察しています。
この書籍は、トラウマを抱える女性たちが専門家の援助を受けた後、どのように「普通の生活」を取り戻し、生き延びてきたかを探る内容です。目次には、孤独感や自傷行為、身体との向き合い方、具体的な生き延びる方法などが含まれています。著者は、薬物・アルコール依存の女性支援を行うダルク女性ハウスの代表と、被害体験を持つ女性の福祉支援を行うNPO法人リカバリーの代表で、それぞれの経験を基にした実践的な知見が提供されています。
本書は、精神保健福祉の現場でのアセスメントに関する実践ガイドで、特に新人やベテランのソーシャルワーカー向けに27の実践スキルを紹介しています。内容は、アセスメントの失敗ポイント、プロセスモデル、必要な姿勢や価値、研修プログラムの考え方など多岐にわたります。著者は、精神保健福祉士としての豊富な経験を持つ大学教授たちです。
本書は、認知症の患者数が増加する中で、認知症の人とのコミュニケーション方法を解説しています。著者の豊富な経験を基に、認知症の人の不可解な行動の背後にある心理をマンガ形式で紹介し、理解を深めることで介護の負担を軽減し、愛情を持って接する方法を提案しています。内容は、認知症の人が見ている世界や具体的な事例を通じて、心の中を理解するためのヒントを提供しています。
この書籍は、スマートフォンが私たちの身体や社会に与える影響について考察しています。目次では、日常性の理解、フィールドワークの重要性、「あたりまえ」を疑う視点、日常生活の批判的調査方法論などが取り上げられています。著者は好井裕明で、社会学の専門家としての経歴を持ち、差別や映画の社会学に関心を寄せています。
この書籍は、ソーシャルワークの理論やアプローチを事例やイラストを用いてわかりやすく解説しています。著名な研究者の理論を基に、人々の問題を深く考察し、新しい解決策を探ります。目次は、10の主要な理論・アプローチとその組み合わせに関する内容を含んでおり、具体的な事例も紹介されています。著者は川村隆彦で、社会福祉学の専門家です。
本書は、認知症の人とのコミュニケーションを改善するための具体的な「言いかえ」フレーズを紹介しています。著者は認知症研究の第一人者で、認知症の人の心を理解し、伝わりやすい言葉を使うことで、家族のストレスを軽減できることを提案しています。具体的な事例を挙げ、感情を考慮した優しい声かけが重要であることを強調。また、認知症の基礎知識や家族の悩みに対するQ&Aも掲載されており、実用的なガイドとして活用できます。
この書籍は、グローバル化が進む中で地域のアイデンティティを守り、人々が幸福に暮らせる町のあり方を探求しています。具体的には、スローシティやショッピングモールの排除、地域資源の活用など、さまざまな町の取り組みを紹介し、それぞれの町が直面する課題と解決策を示しています。著者はノンフィクション作家の島村菜津で、イタリア各地の事例を通じて、地域社会の重要性を考察しています。
福祉は、ごく一部の困っている人のためのものではない。私やあなたを追い詰める自己責任論を超えて、ケアし合える社会を目指そう! 支援が必要な人は「困った人」じゃない。元気な人も誰かの助けが必要になることもある。私やあなたを追い詰める自己責任論を超えてケアし合える社会を目指そう! 支援が必要な人は「困った人」じゃない。元気な人も誰かの助けが必要になることもある。私やあなたを追い詰める自己責任論を超えてケアし合える社会を目指そう! 福祉は、ごく一部の困っている人のためのものではありません。病気や障害、貧困などで悪循環状況に陥って幸福ではない状態の人が、どうやったら好循環に向かい、幸福を目指せるか。元気な人も、しんどくて誰かの助けが必要になることもあります。自分自身の弱さや無力さを認め、他者に頼ることによって自立の道が開きます。その際の助け合いの仕組みを考え、伴走するのが福祉です。他者とともにケアし合う関係性を生み出すことこそ、日本社会に求められていることだと考えます。 第一章 あなたの一段は他人の十段? 第二章 なぜ人は追い込まれていくの? 第三章 家族が支えるのが当たり前? 第四章 ともにケアし合う社会とは?
この書籍は、相談面接技術に関する内容を扱っており、主に以下の三つの章で構成されています。第一章では、面接の環境や時間の使い方について説明し、第二章では面接技術の具体的な方法を紹介しています。第三章では、逐語的に相談面接技術を学ぶことに焦点を当て、実際の面接の進め方や援助関係の構築について述べています。著者は岩間伸之で、大阪市立大学の准教授であり、社会福祉学の専門家です。
この文章は、援助職者に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、援助職者の基本的な視点や援助関係、アセスメント、相談面接のプロセス、高齢者への援助、燃えつき防止策、介護の現実、ケアマネジメントについての章が並んでいます。著者の渡部律子は、社会福祉学や心理学の専門家で、日米での臨床経験と教育歴を持っています。
この本は、外国人労働者、移民、難民の違いをわかりやすく解説し、彼らとの接し方について考察しています。現在、戦争や貧困から逃れるために多くの人が移動しており、日本でも外国人労働者の受け入れが進んでいます。著者は、これらの問題を中学生から大人まで理解できるように説明し、今後の社会での共生の重要性を強調しています。目次には、外国人労働者や難民の定義、日本の受け入れ政策、世界の事例、そして外国人との関係構築に関する章が含まれています。
福祉や教育の分野をもむしばむ能力主義や競争社会から脱却し、路上の出会いから生まれた「支援者/要支援者」に分けない非援助的アプローチで、人々が“仲間”として関わり合う共同体自治の実践を描きます。 学校や病院、施設で「要支援者」とされた人びとと共に、年齢や属性を超えて居場所と役割を取り戻すための方法(共同体自治)を提示。 「第1回未来をつくる こどもまんなかアワード」最高賞の内閣総理大臣表彰を受賞した実践をはじめ、社会教育・生涯学習の豊富な事例も収録しています。 第1章 能力主義にむしばまれる児童福祉 第2章 私自身、かつて能力主義に陥った 第3章 出会いと交流から生まれる多様性 第4章 能力主義をどう乗り越えるか
著者の大塚紗瑛は、母の祖父母の介護を見て介護職に興味を持ち、老人ホームで働くことに。周囲の冷たい視線や身体的な苦労がある中でも、この仕事を好きだと感じています。本書は、介護職の日常を描いたコミック&エッセイで、SNSで多くの反響を呼びました。
本書は、成人、家族、子ども、カップルの初回面接の進め方や、成育歴の聴き取り、自傷や他害のリスクアセスメント、虐待のアセスメント、心理検査の活用法、アセスメント結果の記述方法などを詳しく解説しています。限られた時間内での効果的なアセスメントを支援するため、精神状態検査(MSE)の使用法も紹介。臨床場面を想定した具体的な指摘があり、初学者から経験者まで幅広く役立つ内容です。各章では、初回面接の実施方法やアセスメントの視点が整理されています。
「介護うつ」「高齢者の虐待」「共倒れ」といった暗いワードが当たり前に飛び交う介護の世界。その実情はほとんど世に知られていない。高齢者の増加や人手不足などに伴い、介護現場における諸問題は年々深刻化しているが、人口の約3割が高齢者となった今、こうした問題は決して他人事で済まされない。人々は介護の現実に目を向ける必要がある。 介護現場の最前線である介護施設は、必ずしも綺麗な世界ではない。介護士たちはさまざまな葛藤を抱えながら、日々厳しい現実に直面している。凶暴な利用者に指を噛みちぎられた職員、薬の過剰な投与により認知症を悪化させられた利用者、看護師による医療機器の操作の実験台にされる利用者……これらの凄惨な出来事はすべて、著者が介護士として目の当たりにしたものである。 さまざまな施設を渡り歩いた現役介護士が、介護の世界の過酷な現実を告白する。
福祉を通じて社会を描く。地域ごとの通時的な「経糸」,地域を超えた共時的な「緯糸」,多彩な「コラム」が編み出す,福祉の織物。 適切な生存・生活の追求すなわち福祉を,政治・経済にも比肩する歴史の基底と捉え,先史から現代まで全地球的に通観。「人が集団として生きること」に問い迫る。地域ごとの通時的な「経糸」,地域を超えた共時的な「緯糸」,多彩な「コラム」が編み出す,福祉の織物。 序 福祉を通じて人間社会を描く =編者 第1部 先史~古代――共同体の存続模索 経糸1-1章 先史時代 =山田康弘 緯糸1(人類学の成果)〔1〕贈与論,その先へ =中村沙絵 コラム1-① シュメール社会と福祉 =辻田明子 経糸1-2章 ギリシア・ローマ =増永理考 経糸1-3章 中国 =横山裕 経糸1-4章 日本 =有富純也 コラム1-② 古墳と福祉 =下垣仁志 第2部 古代末期~中世――宗教を通じた生活・生存再編 経糸2-1章 西ヨーロッパ =河原温 経糸2-2章 ビザンツ帝国 =大月康弘 経糸2-3章 中東(イスラーム世界) =三浦徹 緯糸2(世界宗教)〔1〕ユダヤ教 =田中利光 緯糸2(世界宗教)〔2〕キリスト教 =土井健司 緯糸2(世界宗教)〔3〕イスラーム =八木久美子 経糸2-4章 中国①(宋代) =須江隆 経糸2-5章 中国②(元代/モンゴル帝国) =秦玲子 経糸2-6章 日本――作善としての福祉:12世紀後半から14世紀前半 =西田友広 緯糸2(世界宗教)〔4〕儒教 =水口拓寿 緯糸2(世界宗教)〔5〕仏教 =船山徹 第3部 中世末~近世――公的施策の萌芽 経糸3-1章 西ヨーロッパ =佐々木博光 コラム3-① 迫害被害者支援 =西川杉子 経糸3-2章 ポーランド・リトアニア共和国 =小山哲 緯糸3(近世帝国)〔1〕ポルトガル =疇谷憲洋 緯糸3(近世帝国)〔2〕スペイン =横山和加子 緯糸3(近世帝国)〔3〕オランダ =安平弦司 経糸3-3章 オスマン帝国 =林佳世子 緯糸3(近世帝国)〔4〕ムガル帝国 =真下裕之 緯糸3(近世帝国)〔5〕清朝 =村上正和 経糸3-4章 朝鮮王朝 =長森美信 経糸3-5章 日本 =齊藤紘子 経糸3-6章 中国 =夫馬進 第4部 近代――「西洋近代」的規範の影響 経糸4-1章 イギリス =金澤周作 コラム4-① 都市と自然 =水野祥子 緯糸4-i(帝国主義・植民地主義)〔1〕イギリス =大澤広晃 経糸4-2章 アメリカ合衆国 =鰐淵秀一 経糸4-3章 フランス =前田更子 緯糸4-i(帝国主義・植民地主義)〔2〕フランス =岡田友和 経糸4-4章 ドイツ =中野智世 経糸4-5章 中国 =穐山新 緯糸4-ii(トランスナショナル・ネットワーク)〔1〕移民(華僑) =志賀市子 緯糸4-ii(トランスナショナル・ネットワーク)〔2〕労働者インターナショナル =福元健之 緯糸4-ii(トランスナショナル・ネットワーク)〔3〕宗教の「インターナショナル」 =金澤周作 経糸4-6章 日本 =松沢裕作 コラム4-② 植民地朝鮮の仏教と社会事業 =川瀬貴也 コラム4-③ アイヌへの救済や「福祉」 =麓慎一 コラム4-④ 大災害・大飢饉への支援 =金澤周作 第5部 現代――イデオロギーとグローバリゼーション 経糸5-1章 アメリカ合衆国 =中野耕太郎 経糸5-2章 スウェーデン =石原俊時 経糸5-3章 ドイツ =北村陽子 コラム5-① 福祉レジーム =掛貝祐太 コラム5-② 障害者福祉 =北村陽子 緯糸5(国際NGOと国際機関)〔1〕セーブ・ザ・チルドレン =金澤周作 経糸5-4章 ソヴィエト連邦 =池田嘉郎 経糸5-5章 アフリカ =松田素二 コラム5-③ 生活協同組合とフェアトレード:消費者がつくる福祉のかたち =浮網佳苗 経糸5-6章 イスラーム世界 =子島進 経糸5-7章 インド =茶谷智之 緯糸5(国際NGOと国際機関)〔2〕国際機構 =舘葉月 緯糸5(国際NGOと国際機関)〔3〕国際赤十字・赤新月運動 =舘葉月 緯糸5(国際NGOと国際機関)〔4〕国境なき医師団 =舘葉月 経糸5-8章 中国 =アンドレ・ラリベルテ/小堀慎悟訳 経糸5-9章 日本 =岩永理恵 コラム5-④ 動物福祉 =伊東剛史 コラム5-⑤ 福祉と医療:近現代イギリスの医療のエトス =高林陽展
本書は、地域を基盤としたソーシャルワークの理論と実践について、著者の岩間伸之氏が解説しています。「行政」「専門機関」「地域住民」が協力して住民主体のソーシャルワークを展開するための指南書であり、地域の総合相談拠点の取り組みを紹介しています。目次には、本人主体のソーシャルワーク理論、地域を基盤としたソーシャルワークの全体像、総合相談の実践、ソーシャルワークにおける価値についての章が含まれています。著者は社会福祉の専門家であり、理論書として今後の社会福祉の方向性を示しています。
この書籍は、自己欺瞞の「箱」からの脱出方法を探る内容で、三部構成になっています。第1部では「箱」に入ることの問題を考察し、第2部では人がどのようにして「箱」に入るのかを探ります。第3部では「箱」から出るための方法や、人との接し方を提案しています。著者は金森重樹で、ビジネスプロデューサーとして活動し、資産形成をサポートする事業を運営しています。
この書籍は、日本における子どもの貧困問題を多角的に分析し、貧困の定義や現状、政策の効果を検証します。貧困世帯で育つことの影響、特に母子世帯の経済状況や育成環境、学歴社会との関連性についても考察されています。著者は、貧困の連鎖を断ち切るために必要な「子ども対策」を提案し、具体的な政策のステップを示しています。全体を通じて、子どもの幸福を重視したアプローチが求められています。
英国の児童保護改革の成果から生まれた本書は、エビデンスをふまえた早期支援の重要性を強調する。ソーシャルワーカーの評価や判断能力・組織・人材育成のあり方等を多岐にわたって論じ、日本の児童相談所をはじめとする専門職に向けて正しい道標を提供する。 第3版への序文 謝辞 第1章 はじめに 本書の概要 第2章 複合適応システム(CAS)としての児童保護機関 複合的視点から世界を理解すること 応用システム分析の実例としての児童保護に関するムンロー・レビュー 結論 第3章 児童保護業務の専門性 専門知識についての議論 直観と分析 コグニティブ・コンティヌアム(認知連続体) 感情と論理的思考 ケース事例 直観的推論の強みと限界 直観的推論の限界 分析的推論の強みと限界 結論 第4章 複雑な社会的介入の評価 コンテクストの重要性 因果関係のメカニズムの重要性 介入は効果があるのか? 継続的な学習の重要性 複合的介入のためのリサーチメソッド ウェブサイトと参考資料 結論 第5章 社会的コンテクスト 子ども期への認識 福祉と家族政策の現在の課題 児童福祉と児童保護サービスの発展 児童福祉の重要な進展 児童虐待に対する社会の認識の高まり 結論 第6章 児童虐待の定義 定義の実例 児童虐待の社会的構築 虐待の定義の問題の影響 結論 第7章 実践における不確実性という課題 リスク要因の理解 基準率の錯誤 統計的リスクアセスメント、臨床的リスクアセスメント 予測解析の課題 結論 第8章 リスクアセスメントのプロセス リスクアセスメントの段階 第1段階:何が起きた、あるいは起きているのか? 第2段階:これから何が起きそうか? 第3段階:それはどのぐらいの可能性があるか? 第4段階:それはどれぐらい望ましくないことか? 第5段階:リスクの総合的判定―可能性と深刻度の組み合わせ 結論 第9章 意思決定 限定合理性と「満足化」 パターン認識での意思決定 直観的意思決定のバイアス 決定理論 結論 第10章 組織による有効な実務のサポート 個人のパフォーマンスに対するシステムの理解 家族への直接支援のサポート マネジメントと組織文化 フィードバック 結論 第11章 結論 分析的スキル及び直観的スキルと知識を統合する 職場環境 実務のためのツール設計 結論 監訳者あとがき 文献 著者・監訳者・訳者略歴
著者は約20年の臨床経験を持つ心理カウンセラーで、他人の言葉に振り回されやすい敏感な人々への対処法を提供します。特に、他人の言葉に真剣に悩む人や共感しすぎる人に向けて、言葉の価値を再評価し、スルースキルを身につける重要性を説いています。内容は、他人の言葉に振り回されるメカニズムや、スルースキルを通じて自分の言葉を取り戻す方法に焦点を当てています。
この文章は、地域社会における多様な課題や支援体制についての内容を示しています。具体的には、地域共生社会の実現、福祉ガバナンス、多機関の協働、地域基盤のソーシャルワーク、災害時の支援体制、福祉計画の重要性とその運用、福祉行財政システムに関する章立てが紹介されています。
この本は、福祉の仕事において本当に大切な要素について考察するもので、著者が10年以上にわたり「良い支援とは何か」を追求してきた結果をまとめています。内容は、福祉との出会い、児童福祉から障害福祉への移行、支援の在り方、領域を超えた福祉の可能性を探ることに焦点を当てています。著者は、読者と共に福祉について考えることを呼びかけています。
2021年度版の医療福祉サービスガイドブックは、利用者の生活に沿った解説を提供し、最新情報を反映して理解しやすくなっています。医療保険、生活保護、年金保険、介護保険、障害者支援法、子ども支援、自然災害対応など、全国共通の制度から地域特有のサービスまで幅広くカバー。コロナ禍でのサービスも含まれており、医療福祉関係者にとって必携の一冊です。
この文章は、ソーシャルワークに関する書籍の目次を示しており、以下の7つの章から構成されています。1章では総合的な支援の実践、2章では援助関係の形成、3章ではネットワークの形成、4章では社会資源の活用と調整、5章ではカンファレンス、6章では事例分析・検討・研究、7章では関連技法について述べられています。
本書は、経済的不況以上に深刻な「生きる意味の不況」に苦しむ現代人に向けて、苦悩の根源とその克服方法を探る内容です。著者は、空しさを感じる私たちが本当に欲しいものを見つけ、内的成長を促す社会を築くことの重要性を提言しています。目次では、苦悩の正体、数値化と効率化の影響、そして生きる意味を創造する社会について論じています。著者は文化人類学の専門家で、東京工業大学の助教授です。
この書籍はスタンフォード大学の人気講義を基にしたもので、精神的ストレスに対処する方法を科学的に解説しています。「ストレスは悪い」という思い込みを捨て、ストレスを力に変えることで人生を変えることができると提案しています。著者のケリー・マクゴニガルは健康心理学者で、ストレスを活用する実践的なガイドを提供しています。
この書籍は、日本語が明治以来の西洋文化の影響を受けて豊かな近代文学を形成してきた過程を探求し、現在のグローバル化における英語の影響に対する日本語の未来を考察しています。著者の水村美苗は、言語の重要性や日本語の進化について述べ、さまざまな文化的背景を持つ作家たちの視点を通じて、現代における言語の役割を問いかけています。内容は多岐にわたり、著者の経歴も紹介されています。
この書籍は「ヤングケアラー」、すなわち家族の介護を担う子どもたちに焦点を当て、その実態や支援の必要性を探求しています。著者は、高校生への調査を通じて、日本のヤングケアラーの状況を明らかにし、孤立や負担を抱える子どもたちの声を紹介しています。社会的背景として少子高齢化や家族主義が挙げられ、支援の重要性が強調されています。最終章では、地域や学校、福祉専門職による支援の具体策が提案されています。著者はヤングケアラー研究の第一人者であり、実践的な支援のあり方を模索しています。
この書籍は、グローバリゼーションと文化の関係、特に文化的アイデンティティの重要性を探求しています。著者は、文化が政策にどのように活用されるべきか、またその危険性と可能性について考察します。内容は五つの章に分かれ、グローバリゼーションが文化に与える影響、人間の安全保障の視点、ソフトパワーの競争、新たな担い手の登場、理論と政策の関係を論じています。全体を通じて、文化の未来についての問いが提起されています。
増田レポートが示す地方消滅の危機に対し、農山村は過疎化や高齢化に立ち向かい、実際に再生の道を模索している。本書では、研究者が地方の現状や地域づくりの歴史、政策の新展開、農山村移住の課題などを詳しく報告し、地方消滅論の意図を批判的に考察している。著者は明治大学の教授で、農政学や地域ガバナンスの専門家である小田切徳美氏。
この書籍は、自然と社会の未来について探求し、人と自然の相互関係や合意形成の重要性を論じています。著者は様々な地域の自然に関する活動を観察し、災害時や都市部での実践を通じて、自然とコミュニティの未来を描き出しています。目次には、自然の定義、地域のコモンズの仕組み、多様な価値の合意形成、実践における人と自然の関わりが含まれています。著者の宮内泰介は環境社会学の専門家で、フィールドワークを通じて自然とコミュニティに関する研究を行っています。
日常の中の素朴な疑問から性暴力被害者の自己責任論まで――「ジェンダー研究のゼミに所属している」学生たちが、そのことゆえに友人・知人から投げかけられたさまざまな「問い」に悩みつつ、それらに真っ正面から向き合った、真摯で誠実なQ&A集。 はじめに――ジェンダーってなに? 第一章 これってどうなの? 素朴な疑問 1.男女平等をめざす世の中で女子校の意義ってなに? 2.「〇〇男子/〇〇女子」って言い方したらダメ? 3.男女平等は大事だけど、身体の違いもあるし仕事の向き不向きはあるんじゃない? 4.ジェンダーを勉強したら、イクメンにならないといけないんでしょ? 5.専業主婦になりたい人もいるよね? 6.男女平等っていうけど、女性も「女らしさ」を利用しているよね? コラム1 女子力って……? 第二章 セクシュアル・マイノリティについてもっと知りたい! 7.テレビにはゲイや女装家、トランスジェンダーが出ているけれど、違いはなんなの? 8.「ホモ」、「レズ」って呼び方はダメなの? 9.子ども産めないのに、同性婚って必要あるの? 10.人を好きになったりセックスしたくなったりするのは誰でも自然なことだよね? 11.日本はLGBTに寛容な国だよね? 12.友達だと思ってたのに告られた……誰かに相談していい? コラム2 多数派の人たちの幸せは? 第三章 フェミニズムって怖いもの? 13.フェミニズムって危険な思想なんでしょ? 14.どうしてフェミニストはCMみたいな些細なことに噛みつくの? 15.どうしてフェミニストは萌えキャラを目の敵にするの? 16.どうしてフェミニストはミスコンに反対するの? 17.フェミニストはなにかと女性差別というけど、伝統や文化も重んじるべきじゃない? 18.ジェンダー研究に関心をもっている人とフェミニストとは別なんでしょ? コラム3 ジェンダー研究は女性の学問? 第四章 めざしているのは逆差別? 19.男だって大変なのに、女がすぐハラスメントと騒ぐのって逆差別では? 20.管理職の女性を30%にするって、女性だけを優遇する逆差別じゃない? 21.東大が女子学生だけに家賃補助をするのって逆差別じゃない? 22.女性専用車両って男性への差別じゃない? 23.女性はバリキャリか専業主婦か選べるのに、男性は働くしか選択肢がないのっておかしくない? 24.恋愛のハードルって男の方が高い。女ってだけでモテるんだから女はずるくない? コラム4 なんでジェンダーのゼミにいるのに化粧してるの? 第五章性暴力についてもっと考えたい! 25.性欲って本能でしょ、そのせいで男性が女性を襲うのも仕方ないよね? 26.性暴力って被害にあう側にも落ち度があるんじゃない? 27.性暴力の被害者って女性だけだよね? 28.性行為しておいて後から「あれはレイプだった」っておかしくない? 29.性暴力ってある日突然見知らぬ人からレイプされることだよね? コラム5 ジェンダーを勉強するとつらくなる? 読書案内 おわりに
この書籍は、戦後60年にわたって語られてきた太平洋戦争の全体像を明確に捉える試みです。旧日本軍の構造や開戦の背景、戦争の継続理由、敗戦のプロセスを探求し、単純な善悪の二元論を排除して歴史的文脈に位置づけます。著者はノンフィクション作家の保阪正康で、昭和史の実証的研究を行っています。
障害者を考えることは健常者を考えることであり、同時に自分自身を考えること、なぜ人と人は支え合うかを「障害」を軸に解き明かす。 障害者を考えることは健常者を考えることであり、同時に自分自身を考えること、なぜ人と人は支え合うかを「障害」を軸に解き明かす。 『こんな夜更けにバナナかよ』から15年、渡辺一史最新刊! ほんとうに障害者はいなくなった方がいいですか? 今日、インターネット上に渦巻く次のような「問い」にあなたならどう答えますか? 「障害者って、生きてる価値はあるんでしょうか?」 「なんで税金を重くしてまで、障害者や老人を助けなくてはいけないのですか?」 「自然界は弱肉強食なのに、なぜ人間社会では弱者を救おうとするのですか?」 気鋭のノンフィクションライターが、豊富な取材経験をもとにキレイゴトではない「答え」を真摯に探究! あらためて障害や福祉の意味を問い直す。 障害者について考えることは、健常者について考えることであり、同時に、自分自身について考えることでもある。2016年に相模原市で起きた障害者殺傷事件などを通して、人と社会、人と人のあり方を根底から見つめ直す。
この書籍は、医療ソーシャルワーカー(MSW)の離職要因を分析し、ストレスケアの実践的な方法を紹介しています。各働く環境や業務の特性を考慮し、共感を得やすい事例やQ&Aを通じて、具体的な解決策を提供します。内容は、ストレスマネジメントや職場環境の改善提案を含み、10年後もMSWとして働き続けるためのアドバイスも含まれています。著者は、医療や福祉の分野で豊富な経験を持つ専門家たちです。
本書では、日本社会における困窮と孤立の問題を背景に、共生の場を創出し支え合う制度の必要性を論じています。著者は「共生保障」という新しい生活保障のビジョンを提示し、雇用の拡大や多様な居住形態の実現に向けた具体的な制度提案を行っています。内容は、制度の課題、共生保障の概念、地域での実践、社会保障改革の展望、共生の価値と政治についての考察を含んでいます。著者は政治学と福祉政策の専門家です。
この書籍は、現代社会における人々のつながりや対立を乗り越える方法を探るもので、著者は「実験社会科学」を用いてメタモラルの可能性を文理横断的に考察しています。内容は、ヒトの適応や社会性、利他性、共感、正義とモラルについての章で構成されています。著者は東京大学の教授で、心理学の専門家です。
この書籍は、尖閣諸島や竹島、北朝鮮の核開発などの軍事的緊張の中で、戦争と平和の条件を探求する国際政治学の入門書です。著者は、信頼できない外国政府に対抗するために軍隊が必要とされる逆説的な状況を考察し、戦争の条件を深く考えることで平和の条件を見出す方法を模索しています。内容は、戦争の必要性、国際関係、民主主義、ナショナリズムなど多岐にわたります。著者は東京大学の教授で、国際政治と東南アジア政治が専門です。
この本は、認知症の専門医である長谷川和夫が自身の認知症体験を通じて、認知症の実態や予防策、医療の役割を伝える内容です。長谷川は「長谷川式スケール」の開発者であり、認知症の歴史や社会における理解の必要性についても触れています。著者は、認知症に関する知識を広め、日本人に伝えたいメッセージを込めた「認知症の生き字引」としてこの書をまとめました。
この書籍は、人間同士の「さわる」や「ふれる」行為が生む交流の深さを探求しています。介助、教育、性愛など多様な場面で、コミュニケーションは単なる情報伝達を超え、相互的な信頼や共鳴を生み出します。著者は、触覚が新たな関係を創造する可能性を示し、倫理や信頼、コミュニケーションの役割について論じています。全6章から構成され、触覚の重要性や人間関係の豊かさを考察しています。著者は東京工業大学の准教授で、美学と現代アートが専門です。
本書は、現代の精神医療の変化を反映した第2版で、特に「統合失調症」への病名変更などの重要な修正が加えられています。ケアの基本もさらに向上され、看護師だけでなく全ての医療者にとって有用な内容となっています。
在日韓国・朝鮮人、日系ボリビア人、ベトナムやクルドの難民、フィリピンの移民など、日本には数多くの「外国につながる子どもたち」が暮らしています。その子どもたちがどのように日本に住み、どのような問題と直面しているのか、まんがを通して考えます。 第1話 ディエゴの物語〜海をこえてきた転校生 ◆この本を読むみなさんへ 第2話 ユヘの物語〜私が日本で生まれた理由 第3話 ナミの物語〜おばあちゃんと中国 第4話 リカルドの物語〜沖縄とボリビアのあいだで 第5話 フォンの物語〜ベトナムからの小さな船 第6話 ネブローズの物語〜ふるさとには帰れない 第7話 武来杏の物語〜やっと一緒に暮らせる 第8話 カルロスの物語〜ぼくたちの日本語教室 第9話 ビアンカの物語〜学校に行きたい 第10話 ジョシーの物語〜日本にいさせて 第11話 ソフィーラの物語〜お母さんと話しができない! 第12話 アンドレの物語〜高校進学の壁 第13話 タオの体験〜外人といわないで 第14話 栄子の物語〜震災で起こったこと 第15話 アリの物語〜増えてるの? 外国人犯罪 第16話 スンジャの物語〜ひとさし指の自由 第17話 アレックスの物語〜ぼくたちの進路は? 第18話 美里の物語〜私のほんとうの名前 第19話 リリアンの体験〜私の生き方 第20話 だいき&こうたの物語〜ジュワニと友だちになれてよかった ◆この本のテーマと内容 あとがき
この書籍は、身体障害認定に関する基準や要領、疑義解釈を障害種別ごとに整理し、診断書の記載例や解説を豊富に収録しています。医師や自治体関係者に向けて、平成30年7月からの視覚障害基準の見直しにも対応した内容となっています。目次には法令や通知、各障害に関する認定事務が含まれています。
この書籍は、日本の人口が2040年代に1億人を下回り、高齢者が4割を占める「超高齢国」となる予測を背景に、少子化の進行原因を探ります。著者は、バブル崩壊後の雇用状況が就職氷河期世代の未婚化を招き、若者の生活を犠牲にした結果、少子化が進んだと指摘します。少子化対策の失敗の歴史と、若者への就労支援や貧困対策が重要であると主張し、常見陽平氏との対談も収録されています。著者は、育児支援や保育政策を研究してきた前田正子教授です。
「福祉」に関するよくある質問
Q. 「福祉」の本を選ぶポイントは?
A. 「福祉」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「福祉」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ケースワークの原則[新訳改訂版]:援助関係を形成する技法』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで112冊の中から厳選しています。
Q. 「福祉」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「福祉」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『ケースワークの原則[新訳改訂版]:援助関係を形成する技法』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41bu30JJazL._SL500_.jpg)








































![『援助を深める事例研究の方法[第2版]:対人援助のためのケースカンファレンス (MINERVA福祉ライブラリー32)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/512P9712WTL._SL500_.jpg)

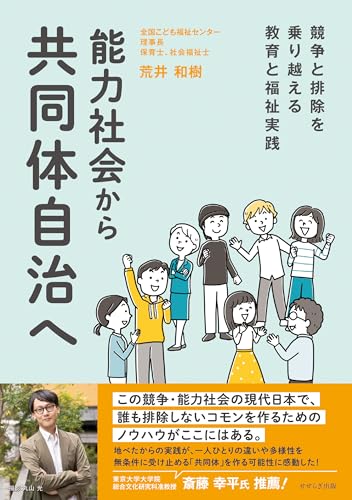









![『ソーシャルワーク演習ワークブック[第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41lGU0bHTSL._SL500_.jpg)




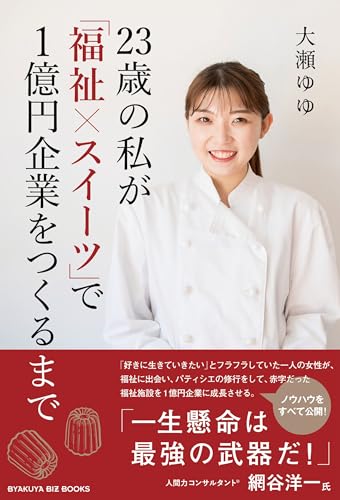
















![『ソーシャルワークの理論と方法[社会専門] (最新社会福祉士養成講座)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41HCKHUXAFL._SL500_.jpg)




























![『福祉の哲学 [改訂版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51A-PXUrH5L._SL500_.jpg)


















