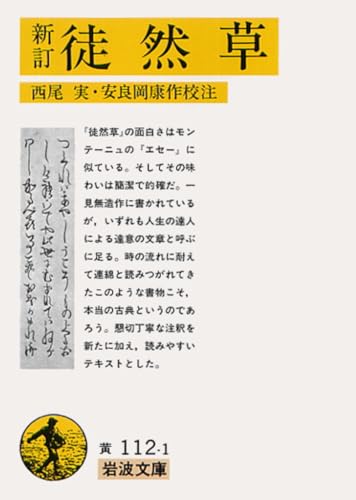【2025年】「徒然草」のおすすめ 本 45選!人気ランキング
- 新版 徒然草 現代語訳付き (角川ソフィア文庫)
- すらすら読める徒然草 (講談社文庫 な 90-2)
- こころ彩る徒然草 ~兼好さんと、お茶をいっぷく
- しっかりと古典を読むための 徒然草全釈 拡大復刻版
- 徒然草 ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 (角川文庫ソフィア 99 ビギナーズ・クラシックス)
- けろけろけろっぴの『徒然草』 毎日を素敵に変える考え方 (朝日文庫)
- 徒然草 (新潮CD)
- 吉田兼好とは誰だったのか 徒然草の謎 (幻冬舎新書)
- まんがで読む 徒然草・おくのほそ道
- 絵本 徒然草 上
『徒然草』は、日本人に親しまれる随筆で、243段の話題が無常観や尚古的思想を背景に連想的に並ぶ。人生、恋愛、政道、自然観などについて触れ、中世の現実を見据えた視点も持つ。最近の歴史学の研究成果を反映し、本文や注釈、現代語訳が刷新された決定版として提供されている。著者は鎌倉時代の兼好法師で、和歌の名手として知られる。
中野孝次が選び抜いた『徒然草』の原文を基にした“わが徒然草”を紹介する本。原文には総ルビと現代語訳、解説が付いており、南北朝時代を生きた兼好の言葉が現代に生きる意味を持つことを伝える。内容は世俗の話や生死、趣味、美など多岐にわたり、著者の生き方や思いが反映されている。
『徒然草』の意訳と美しい写真、イラストを通じて、現代に通じる66のメッセージを楽しむ本です。兼好法師と共にお茶を飲みながら、心に響く言葉を読み進めることで、新たな発見や生き方のヒントが得られます。各話は印象的なフレーズのみを抜粋しており、音読することも推奨されています。全体を通じて、より明るく楽しい生き方を提案しています。著者は木村耕一。
『徒然草』は、日本の中世の知識人・吉田兼好が自然や世相を観察し、無常観や求道精神を反映させた随筆集です。古文と現代語訳が併載され、朗読にも適しており、役立つ図版やコラムも豊富に含まれています。内容には、自己発見や政治倫理、友情、読書の重要性など、多岐にわたるテーマが扱われています。
出会いの時 サフラン 桐の花とカステラ 星を拾う 秋の七草に添えて 棋聖・名人を語る ウッチャリ拾い 走ラヌ名馬 私の家 触覚について 柳の説 奥常念岳の絶巓に立つ記 浜の月夜/清光館哀史 遍路 玉島円通寺 春深く 飯待つ間 予が四十歳 枇杷の花 永遠の感覚 十年 随筆問答 野崎村のお光さんへ 夢殿の救世観音 文学とは何ぞや 「が」「そして」「しかし」 変な音 雑念 大阪言葉小片 世間 事実と伝説 末期の眼 無常という事 いろいろの死 翠陰居士 結婚 浅草紙 雨粒 雪を作る話 具象以前 鏡のなかの世界/かがみ再論
『方丈記』は、鴨長明が大火や飢饉、大地震などの天災や人災を通じて人間の苦悩や世の無常を描いた名文です。長明は俗界を離れて方丈の庵での生活を楽しむが、真の安らぎは得られず、自己の生き方を省察します。本書は、この古典を現代人に響く作品として新たに校訂された原文と現代語訳、評言で構成されています。著者の鴨長明は、様々な災害を体験し、出家後に人生を深く考察しました。
「自分のために作る料理」が、 様々な悩みを解きほぐす。 その日々を追いかけた、 実践・料理ドキュメンタリー。 【磯野真穂さん(文化人類学者)推薦!】 食べることは生きること。なのに、自分のための料理は億劫。それはなぜ?料理を愛する著者が贈る、これまでにない料理本。 * * * 著者のもとに寄せられた「自分のために料理が作れない」人々の声。「誰かのためにだったら料理をつくれるけど、自分のためとなると面倒で、適当になってしまう」。そんな「自分のために料理ができない」と感じている世帯も年齢もばらばらな6名の参加者を、著者が3ヵ月間「自炊コーチ」! その後、精神科医の星野概念さんと共に、気持ちの変化や発見などについてインタビューすることで、「何が起こっているのか」が明らかになる――。「自分で料理して食べる」ことの実践法と、その「効用」を伝える、自炊をしながら健やかに暮らしたい人を応援する一冊。 * * * 【目次より】 料理は大変だと思っているあなたに Stage1 料理の問題たち 1 料理についてこんがらがってしまっていること 2 自分のために料理するのって難しい? Stage2 実践!自分のために料理を作る Stage3 自分のために料理を作る七つのヒント 絶対に自炊して欲しい、なんて言えない おまけ・本書で紹介したレシピ しょうが焼き ワンパンで作れる「トマトツナパスタ」 レンチンで作れる「シーフードカレー」 好きな野菜で作れる豚汁 カブの葉とじゃこの炒め物 カブとしらすのサラダ まえがき 料理は大変だと思っているあなたに Stage1 料理の問題たち 1 料理についてこんがらがってしまっていること 「理想の家庭料理像」に押しつぶされそうになっていませんか? 食事は決めることが多すぎる 献立を立てるのは大仕事 気楽に料理がしたいと思いながらもできないのはなぜ? 誰も褒めてくれない問題/料理の面白さ、楽しさがいまいちわからない 家事をする元気がない 自分の料理に自信が持てない。おいしそうと思えない 料理上手のSNSがたまにしんどく感じられるのはなぜ? 料理と自尊心との密接な関わり 2 自分のために料理するのって難しい? 何のために料理するのか目的を絞ろう 自分を大事にするための料理 自炊は自分の帰る場所を作ること 世界でたった一人のオーダーメイドな料理人の誕生 Stage2 実践!自分のために料理を作る 01 土門さん第1回【30代・女性・執筆業】 料理とは何か/調理の基本/調味の基本/レシピを見ないでしょうが焼きを作る/新しいしょうが焼きにチャレンジする/まとめ 02 藤井さん第1回【30代・男性・会社員】 自炊のモチベーションの上げ方/トマトパスタを作っていく/料理は途中でやめたっていい/夕食はイベント化されすぎている?/包丁、まな板は使わずカレーを作る/食べることをもっと楽しもう 03 横山さん(仮名)第1回【30代・女性・会社員】 料理は体力のあるうちにやる/隙間時間の一手間が料理のハードルを下げる/食習慣を作る心を見つめてみる/料理は自分らしくなるレッスン/「世の中は壮大な役割分担」/疲れていると、料理はできない/豚汁の下ごしらえをする/豚汁の合間にカブサラダ作り/カブサラダが完成/味噌が溶き残ってもご愛嬌/ヘルシーな食事が自分で作れた * 対話の時間を味わいたい――星野概念 * 01 土門さん第2回【30代・女性・執筆業】 おいしさの九割は安心感でできている/食べることに対して積極的になりました/きついダイエットをしていた一〇代、二〇代/料理は音楽と似ている/レシピの余白を読み解く/まとめ 02 藤井さん第2回【30代・男性・会社員】 目玉焼きで気分が上がるという気づき/料理で知りたいのはレシピだけじゃない/「小料理屋形式」のメリット/山口式スーパー改革案?/「自分のために料理ができない」とは/コンビニおにぎりは一点だけど袋麵は〇・五点/無限に語れる料理のあれこれ/自分を喜ばせて「大丈夫」を担保する 03 横山さん第2回【30代・女性・会社員】 一ヵ月でここまで変わった/気分の浮き沈みが激しいんです/気分の安定のために味わい始めました/料理は「今、ここ」に集中させてくれる/西洋医学ではわからない食のリアル/料理は無心になれる/長続きする幸せ 04 伊藤さん第2回【30代・女性・会社員】 料理は筋トレなんだな/仕事はできても料理ができない私/作る人が一番えらい/母の食卓の愛おしさとコンプレックスと/置いてきた宿題の解き方/評価されない、自分が満たされる世界/自分の身体にしたがい、知恵をつける/自分の「子ども」を解放しよう 05 小山田さん第2回【20代・女性】 料理のプロなのに、料理ができない/優しさがプライベートを浸食してくるとき/自分を喜ばせられた幸せ/人間関係のトラウマが「合わせる私」を作っている/優しくておいしくて幸せ、でも食べたらなくなってしまう/続ける中でわかることがある/過程を「味わう」/「味わい」の喜びは背中で示す/今やっていることを感じる/「味わいアンテナ」を伸ばそう/試行錯誤こそが「味わい」 06 川崎さん第2回【50代・女性・販売員】 お弁当を買う日もあります/「料理のテトリス」/一人だとついおやつを食べてしまう/一人になった寂しさと自由さ/原発事故の爪痕とコロナ禍の家族の変化/火を使わない夏の料理が知りたい/川崎さんのお料理、食べてみたいな Stage3 自分のために料理を作る7つのヒント 1 六名の参加者に三ヵ月間レッスンをしてみて 調理の「なぜ」がわかると、他の料理にも応用できる 億劫なことはやらなくていい 日々の食べているものをもっと肯定しよう 自炊について話す機会の必要性 2 自分のために料理を作る七つのヒント ヒント①:自分が食べたいものを作る ヒント②:結果ではなく、プロセスに集中する ヒント③:作った料理を細かく評価せず、やりすぎくらい自分を褒める ヒント④:下手な自分を愛でる ヒント⑤:他人と比べない ヒント⑥:心の中の小さな自分に作ってあげる ヒント⑦:環境を変える あとがき 絶対に自炊して欲しい、なんて言えない おまけ 本書で紹介したレシピ しょうが焼き ワンパンで作れる「トマトツナパスタ」 レンチンで作れる「シーフードカレー」 好きな野菜で作れる豚汁 カブの葉とじゃこの炒め物 カブとしらすのサラダ
「人間関係」「ほどよい仕事」「日本の美意識」「孤独のススメ」徒然草は、現代に寄り添う古典だ。 本書は、兼好法師を主人公としたマンガと、解説で、徒然草を読み解き、古典として読み継がれてきた生き方のヒントを毎日の生活に生かすための本です。【今、なぜ徒然草か?】・研究者が徒然草に注目!「隠遁者だといわれた兼好像は捏造だった!」⇒実は兼好は社交性があり、自由な感性をもつ「バランス感のあるご意見番」だった。・「ゆらぎを認め、謙虚に自分らしくあろうとする姿勢」が「何事にも白黒はっきりつけなければ気が済まない」現代人の清涼剤に!⇒「お酒は人付き合いでも健康でも災いの元」と言ったり、 「月の夜にのんびりと語りながら酒を飲んで語るのは最高」と言ったり 兼好はその場に合わせつつ、自分に向き合って語ります。・「人間関係」「ほどよい仕事」「日本の美意識」「孤独のススメ」など毎日の生活が豊かになるヒントが満載!【本文より】兼好は歌人ですから恋や季節、人生への述懐も語ります。好奇心旺盛のぞき見精神で見聞きしたものを書き記します。孤独をよしとする兼好の「おひとりさま」論は現代人にこそ通じるものがありそうです。誰に読ませたいと気負ってはいない。書かねばならないなんて追い立てられてもいない。思い浮かんだことを書きたくなって心にまかせて書いてゆく。七〇〇年前に書かれたそんな古典からあなたの心にもふっと引っかかる一文が見つかるかもしれません。 第1章 散歩の名人 ●あえて「用のないところ」をつくるよさ ●この木がなかったらよかったのに ●ライバル頓阿との歌合戦 ●酒席が映す私たちの本性 第2章 話し上手・聞き上手 ●知らない人の胸にひびく言葉 ●兼好の取材力、描写力 ●高僧発「中世のダジャレ」 ●名君を育てた「おかみさん力」 第3章 孤独のススメ ●よき友だち付き合いを考える ●すべてのことから離れる境地 ●すべてのことを「頼み」にしない ●傷つかない生き方 第4章 個性派法師に学ぶ ●もし「死」がなかったら? ●人はどうしてほしがるのか ●深い知識も使いよう ●猫またというものありて 第5章 プロフェッショナル ●専門家のワザこそ尊きものなり ●一刹那に生じる怠け心 ●貶されても稽古に励む ●フラットでやわらかいモノの見方 第6章 恋を語る ●恋心を理解しない男というものは ●しのぶ女性の心づかいに触れる ●兼好が描く、男女の語らい ●男を試す女たち 第7章 みやび“日本の美意識” ●四季がめぐり、迎える新たな朝 ●目で見ることにとらわれる ●不揃いのよさ、未完成という構え ●近代文人の徒然草対決 第8章 生と死 ●とどまることのない時の中で ●亡くなった人はいずれ忘れ去られていく ●死は背後から迫っているのだ ●人生をさし貫くメッセージ
本書は、後悔しない人生を送るための「お金の使い方」を提案するベストセラーで、17万部を突破。経済学者や起業家からも高評価を得ており、人生を豊かにするための経験への投資を重視しています。著者は、貯金の目的や生き方について再考を促し、具体的なルールを示しています。主な内容には、経験にお金を使うこと、子供には早めに資産を与えること、人生の終わりを意識することなどが含まれています。著者は、経済的な豊かさだけでなく、充実した人生を送ることを強調しています。
いわゆる成功哲学的なよくある書籍ではなくて、宵越しの銭は持たず人生を最高に生き抜く価値観を植え付けてくれる書籍。人を選ぶ書籍ではあると思うが、自分自身の理想の生き方に思いっきりあてはまる内容で何度も読み返したい書籍。現代人にはこの生き方が合うと思っているので何かに縛られて辛そうにしていたり、思考停止でお金を稼いで日々四苦八苦したりしている人達に読んで欲しい。
勉強の仕方、友達の作り方など、生きる上での大切なことが書かれた『徒然草』。子どもにこそ伝えたいエッセンスを抜き出し解説する。 勉強の仕方、友達の作り方など、生きる上での大切なことが書かれた『徒然草』。子どもにこそ伝えたいエッセンスを抜き出し解説する。
ベストセラー『潤うからだ』から6年。森田敦子、待望の新刊!女性の「性」にまつわる意識を変えたベストセラー『潤うからだ』の著者、森田敦子さんが、満を持して世に放つ!「世界を変える女性100人」に選ばれた著者が贈る、今、女性が絶対に読んでおきたい、何歳からでもできる「性の学び直し」。CONTENTS1章 性教育のはじまり 自尊心を育てる ~幼少期、思春期小さい子どもに性を否定しない/男の子の性教育は「3歳・小3・13歳」/初潮を迎える子どもには/腟まわりの正しい洗い方 など2章 フェイクのない性 感じるからだ ~青年期快感をさえぎるのはからだの「冷え」/言いにくいことを伝える勇気/楽器で奏でる音楽のようなセックスを/乳がんチェックのためにも乳房に触れる など3章 ゆらぐからだとこころ 「次の性」の始まり ~更年期「セックスレスは当たり前」の日本/セックスは必要なもの?/セルフプレジャーと健康/性交痛の原因となる腟萎縮や腟乾燥 など4章 健康寿命をのばす こころの解放のとき ~老年期予防可能な子宮脱/おむつの話/介護と腟まわりの関係/健康に生きて、健康に死ぬということ など今、女性にとってもっとも大切なのは、複雑な自分のからだや「性」のことについて知り、自分自身を慈しむこと。小さい子どもをもつお母さんには、性教育のことから。妊娠・出産・子育て時期には、健全な感じるからだをつくる。更年期世代には、辛い時期を乗り越えるために。そして、理想の老年期に向けて――。「あなたのからだの物語」を紡いでいきましょう。また、本書の装画と本文イラストは、数多くのプロダクトや広告、装画で活躍されている人気イラストレーターの北澤平祐氏が担当しています。
「ホットガール」はセルフラブがつくる セラピーは心の必需品 「リアル&楽しい」食に夢中 エブエブ旋風の奇跡 さよなら「インフルエンサー」消費 つながりが広げる読書 ブランド価値より「今」の価値 「仕事≠人生」的な働き方 Z世代の革命のかたち アーティストと同じ目線で音楽に参加する 「セルフケア・セルフラブ」と"対話"
“わたし”なき“わたしたち”は空虚であり、“わたしたち”につながらない“わたし”は孤独である。製品やサービスを、チームや組織を、そして地域や社会を、ウェルビーイングにするには、どうすれば?3つのデザイン領域「ゆらぎ・ゆだね・ゆとり」から紐解く、ウェルビーイングのつくりかた。ウェルビーイング研究の第一人者、渡邊淳司/ドミニク・チェンの両氏が案内する、協働に向けた実践の手引き。 第1章 ウェルビーイングの捉え方とその実践に向けた共通基盤 Q1:なぜウェルビーイングなのか? 社会構造と価値観の変化 本書でのウェルビーイングの捉え方 Q2:ウェルビーイングはどう測るのか? “わたし”と“ひとびと”、そして“わたしたち” 主観的ウェルビーイング 大規模測定の事例 Q3:ウェルビーイングに何が大事なのか? “わたし”のウェルビーイングの心理的要因 “わたし”のウェルビーイングの環境要因 “ひとびと”のウェルビーイングの環境要因 Q4:なぜ“わたしたち”なのか? “わたし”でもなく“ひとびと”でもない “わたしたち”の社会的意義 “わたしたち”の日常での実践 Q5:“わたしたち”をどう実現するのか? “わたしたち”のアウトカムとドライバー “わたしたち”の〈対象領域〉の広がり “わたしたち”の〈関係者〉の広がり:間主観 “わたしたち”の〈関係者〉の広がり:一人称かつ三人称 ウェルビーイングに資するサービス/プロダクトの設計に向けて 第2章 “わたしたち”のウェルビーイングをつくりあうデザインガイド ウェルビーイングをデザインするための視点 わたしたちのウェルビーイングのためのハッカソン 相互行為(インタラクション)の視点 ウェルビーイングが生まれる相互行為 “わたしたち”を支える3つのデザイン要素:ゆらぎ、ゆだね、ゆとり 適切な変化を見定める:「ゆらぎ」 他律と自律の望ましいバランス:「ゆだね」 目的ではなく経験そのものの価値:「ゆとり」 “わたしたち”の持続性 「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」から“わたしたち”を考えるデザインケーススタディ ゆらぎのデザインケーススタディ ゆだねのデザインケーススタディ ゆとりのデザインケーススタディ “わたしたち”が持続するデザインケーススタディ 「“わたしたち”のウェルビーイング」のデザインに向けて 第3章 “わたしたち”のウェルビーイングへ向けたアイデアサンプル集 測る・つくる(渡邊淳司) 1:副詞・副産物としてのウェルビーイング 2:数値にする限界と可能性 3:ポジティブなインパクトを解像度高く設計する 4:対話のための場づくり 暮らす・生きる(ドミニク・チェン) 1:「子育て」から「子育ち」へ 2:ぬか床から見える世界 3:遊びがつくる逸脱と自律 4:移動が拡張する自己 感じる・つながる(渡邊淳司) 1:触覚でつながる 2:共感でつながる 3:スポーツでつながる 4:「特別の教科 道徳」とウェルビーイング 伝える・知る(ドミニク・チェン) 1:コミュニケーションにおける実験 2:ウェブ体験を再発明する 3:アルゴリズムとジャーナリズム 4:生成系AI(ChatGPTなど)とのウェルな付き合い方 著者対談:ゆ理論の射程──あとがきにかえて
「徒然草」に関するよくある質問
Q. 「徒然草」の本を選ぶポイントは?
A. 「徒然草」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「徒然草」本は?
A. 当サイトのランキングでは『新版 徒然草 現代語訳付き (角川ソフィア文庫)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで45冊の中から厳選しています。
Q. 「徒然草」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「徒然草」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。