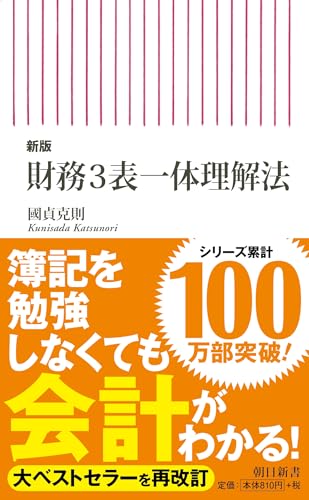【2025年】「企業会計原則」のおすすめ 本 105選!人気ランキング
- 会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方
- ビジネス・アカウンティング〈第4版〉
- 新・現代会計入門 第6版
- 財務諸表監査の実務〈第4版〉
- 【増補改訂】 財務3表一体理解法 (朝日新書)
- この1冊ですべてわかる 財務会計の基本
- 現代税務会計論〈第7版〉
- 管理会計のエッセンス(原著第7版)
- カンタン図解で圧倒的によくわかる! 【決定版】決算書を読む技術
- 開業から1年目までの個人事業・フリーランスの始め方と手続・
このテキストは、企業会計に関する最新の理論や制度を学べる画期的な教材です。内容は、企業の会計行動や現実の影響を多面的に理解することに重点を置いており、理論や歴史、実務事例を網羅しています。各章は異なるテーマに分かれており、必要に応じて特定の部分を選んで学ぶことが可能です。著者は一橋大学の伊藤邦雄教授で、最新の会計制度や実務に基づいた内容が特徴です。
本書は、財務諸表監査の具体的な実施方法を解説し、監査報告書の記載例を含む大幅改訂版です。公認会計士試験合格者や経理担当者、監査実務に携わる専門家に向けて、監査実務の詳細を学ぶための必携書となっています。内容にはリスク・アプローチや監査手続き、会計上の見積もり、不正リスクなどが含まれています。著者は公認会計士であり、監査業務やコンサルティングに豊富な経験を持つ専門家です。
本書は、会計の基礎から重要論点までを網羅的に解説した入門書です。著者は人気講師で、会計ルールや論点の「考え方」をわかりやすく説明し、初学者でも理解しやすい内容になっています。図解や設例を多用し、設例から論点を説明する逆のアプローチを採用しているため、学習が進めやすいです。公認会計士や税理士試験、簿記検定試験を目指す人や、企業の経理部門に配属されたばかりの人に適しています。
このテキストは、税務会計の全体像を新たな体系で描き出し、主に初学者向けに基礎的な概念や考え方を解説しています。また、令和6(2024)年度税制改正にも対応しています。内容は、税務会計の総論、国内税制の整備、国際課税の進展など多岐にわたります。著者は成道秀雄と坂本雅士で、それぞれの大学で教授としての経歴を持ち、税務会計研究において重要な役割を果たしています。
本書は、決算書を視覚的に理解し、ビジネスパーソンに必要な会計の基礎を身につけるための指南書です。図解を用いることで難しい計算式を覚えずに本質を把握でき、段階的な学習ステップにより理解度を高めます。また、「取引フロー図」を通じて経済活動を可視化し、キャッシュフロー経営やビジネスモデルの理解を深めます。著者は多様な会計業務の経験を持つ公認会計士で、実践的な知識を提供しています。
この本は、会計を経理だけでなく、組織の利益を最大化するための「会計感覚」として捉える重要性を説いています。著者は元国税調査官の経営コンサルタントで、管理会計や財務会計、税務会計をストーリー形式でわかりやすく解説しています。目次には、売上の誤解、管理会計の基本、決算書のポイント、キャッシュフローの重要性、PDCAサイクルの活用法などが含まれ、幅広い読者に向けた会計リテラシー向上を目指しています。
本書は第3版で、ものづくりやサービス業における原価計算の理論と実践を体系的に解説しています。日本企業の経営システムの基盤である原価計算の重要性を強調し、公認会計士試験の学習にも役立つ内容です。目次は序論、原価計算制度、経営管理のための原価計算と分析の3部構成で、著者は一橋大学の教授たちです。
本書は、税務会計の基礎概念を明確に解説した入門テキストで、大学生や初めて税務を担当する社会人に適しています。15の講で構成され、租税制度、税務行政、税理士制度、国際課税なども取り上げています。著者は早稲田大学商学部卒のタカクリュウタ氏です。
この書籍は、消費税アップに負けず、逆風をチャンスに変える方法を紹介しています。著者の税理士・岩松正記が、2000人以上の経営者と向き合った経験を基に、税金に関する「ソン・トク」を解説。目次には、会社設立や経費、申告方法、副業サラリーマン、税理士との関係など、多岐にわたるテーマが含まれています。
このテキストは、会計と法人税法の基本を学ぶための入門書であり、2021年度の改正に対応しています。内容は、租税の目的や体系、課税所得の計算、減価償却、役員給与など多岐にわたる税務会計の重要項目をやさしく解説しています。著者は谷川喜美江で、千葉商科大学の教授です。
この書籍は、シリーズ累計80万部を突破した会計学習の定番教科書の再改訂版で、初学者向けに基礎を重視した内容になっています。財務3表を取引ごとに作成する「会計ドリル」を中心に、会計の基本から読み解き方までをやさしく解説し、全ビジネスパーソンにとって必読の一冊です。著者は國貞克則で、豊富な実務経験と教育背景を持っています。
企業が営む主要な活動に焦点を当て,財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,最新情報を盛り込んだ好評テキストの最新版。 企業が営む主要な活動に焦点を当て,財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。データを最新にして,新しい動向を踏まえた内容を盛り込んで,理解がいっそう深まるように工夫。 第1章 会計の種類と役割 第2章 財務会計のシステムと基本原則 第3章 企業の設立と資金調達 第4章 仕入・生産活動 第5章 販売活動 第6章 設備投資と研究開発 第7章 資金の管理と運用 第8章 国際活動 第9章 税金と配当 第10章 財務諸表の作成と公開 第11章 企業集団の財務報告 第12章 財務諸表による経営分析
本書は、起業を目指す人々の疑問や不安を解消するために、年間200件の起業相談を行うコンサルタントが執筆した実践的なガイドです。会社勤めをしながら起業準備を進め、成功のための必要な知識(ビジネスプラン、資金繰り、集客など)を紹介しています。起業の心構えやリスク管理についても触れ、具体的なアドバイスを提供しています。著者は起業支援の専門家であり、起業家のための包括的なサポートを行っています。
財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。 企業が営む主要な活動に焦点を当て,財務諸表の作成プロセスを平明に解説し,変貌する財務会計の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。データを最新にして,新しい内容とし,理解がいっそう深まるように工夫した。 第1章 会計の種類と役割 第2章 財務会計のシステムと基本原則 第3章 企業の設立と資金調達 第4章 仕入・生産活動 第5章 販売活動 第6章 設備投資と研究開発 第7章 資金の管理と運用 第8章 国際活動 第9章 税金と配当 第10章 財務諸表の作成と公開 第11章 企業集団の財務報告 第12章 財務諸表による経営分析
このテキストは、財務会計の基本概念や個別財務諸表について詳述した、詳細な財務会計の教科書です。特に会計基準の解説だけでなく、その背後にある考え方を明確にし、論点整理が分かりやすくなっています。設例や仕訳を用いて理解を深める工夫がされており、最新の四半期開示制度にも対応しています。公認会計士や税理士試験の対策に適した基本書です。著者陣は各大学の教授で、会計分野での豊富な経験を持っています。
この文章は、税務会計に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、税務会計の基礎や法人税、課税所得の計算、消費税制、国際課税など、税務会計に関する多様なテーマが含まれています。著者は税務会計の専門家であり、各自が大学教授や税理士としての経歴を持っています。
この本は、決算書を単なる数字の羅列ではなく、企業や業界の成長ストーリーとして読み解く方法を紹介しています。著者は、数字が読めないと感じる人々に向けて、実践的な決算分析の技術を提供し、ビジネスの理解を深めることを目的としています。内容は、ECビジネスやFinTech、広告、携帯キャリアなど、さまざまな業界の決算分析事例を通じて、企業の戦略や未来を予測する力を養うものです。読者は、決算を読む習慣を身につけることで、ビジネススキルを向上させることができるとされています。
この文章は、管理会計に関する研究のトレンドや方法論、特定のテーマに焦点を当てた内容を示しています。目次には、日本と欧米の研究動向、学際的なアプローチ、予算管理、業績評価、環境管理会計などが含まれています。また、著者情報として、加登豊、松尾貴巳、梶原武久の経歴が紹介されています。
この文章は、メアリー・バフェットとデビッド・クラークによる書籍の目次と著者情報を紹介しています。内容は、財務諸表の読み方やバフェット流の投資法、企業評価の方法について述べられており、特に永続的競争優位性を持つ企業に焦点を当てています。著者はそれぞれ作家、ポートフォリオ・マネジャー、翻訳者としての経歴を持っています。
この書籍は、AIやIoTなどの技術革新が進む中で、会計学の未来を探求する入門テキストです。伝統的な会計学から離れ、ゲーム理論や実験経済学の視点を取り入れて、新しい時代の会計人に必要な教養を提示します。目次は、人間の社会性と会計、新しい教養への準備、会計の原初形態、会計利益と人間心理、制度のデザイン、未来の会計について構成されています。著者は、同志社大学の教授であり、公認会計士でもある田口聡志氏です。
この書籍は、「新地方公会計制度の統一的な基準」に基づき、平成27年1月の総務省通知を反映した内容です。目次は、会計の基本概念や公会計の流れ、会計報告の方法、議会との関係、そして新地方公会計制度の目的や課題について解説しています。公会計の問題点や財務書類の重要性も取り上げられています。
この書籍は、法人・個人事業者向けに、仕訳の処理方法や注意点を詳しく解説しており、日常的に使用する勘定科目についても網羅しています。著者の北川真貴は税理士で、難病を克服した後に会計業務に従事し、さまざまな業種の顧問先を持っています。
本書は、MBA必修科目の会計を10時間で学べる実践的な入門書です。財務会計と管理会計の基本知識を、トヨタやJALなどの企業実例を交えながら解説しています。左ページに解説、右ページに図解を配置し、視覚的に理解しやすい構成です。早稲田大学ビジネススクールの授業内容を凝縮し、会計の基礎を身につけたい人に最適です。会計の知識を活用することでビジネスパーソンとしての成長が期待できます。
この書籍は、受験生から実務家までのために、会計税務に関する必要な知識をコンパクトに解説しています。内容は会社法、金融商品取引法、各種会計基準、法人税、所得税などの最新改正を反映しており、日常業務に役立つ法令や通達を網羅しています。目次には、開示制度、資産・負債・純資産項目、財務諸表、税法などが含まれています。
本書は、日本における「会社買収」に対する違和感を考察し、企業に値段を付けることの本質を解説します。資本主義の仕組みを基に、企業価値算定の基本や賢い投資家になるための知識を提供。また、日本と米国の敵対的M&Aの違いにも触れ、企業評価の重要性を論じています。著者はM&Aの専門家であり、実務に基づいた視点で内容を展開しています。
本書は、経営と会計の関係を理解するための入門書であり、ビジネスモデルの理解を深めるための「会計の常識」をまとめています。著者は西山茂教授で、内容はROEの向上やレバレッジの使い方、リスク管理、成長持続など、ビジネスの基本的な考え方を解説しています。具体的なビジネスシナリオに基づいた質問に答えることで、実践的な会計思考を養うことができます。
この文章は、法人税法と消費税法に関する内容をまとめた目次です。第1編では法人税の基礎概念や益金・損金の計算、税額計算について説明され、第2編では消費税法の概要、納税義務者、課税対象、課税期間、税率、税額控除などが扱われています。
日商簿記検定に完全準拠したテキストで、統一試験とネット試験に対応した模擬問題が3回分収録されています。著者は商学の専門家で、簿記の基本から財務諸表まで幅広い内容を網羅しています。
この書籍は、人気ビジネススクール教授による「会計」と「経営戦略」の統合的な学習法を紹介しています。会計力と戦略思考力を同時に養うことを目指し、トヨタやニトリの決算書を通じて実践的に学ぶ内容です。内容は、損益計算書や貸借対照表の読み解き方、業界競争環境の理解、バリューチェーンやマーケティング戦略の分析など、多岐にわたります。最終的には、会計指標の活用やIFRS決算書の分析方法についても触れています。
本書は、企業の価値がどのように決まるかを解明し、投資の基本原理をシンプルに理解することを目的としています。著者は、ファイナンスやM&Aの実務を現場感覚で捉え、企業価値や株価算定、M&Aの実務について具体的な事例を交えて解説します。著者の森生明は、M&Aアドバイザーとしての豊富な経験を持ち、現在は法律事務所の経営顧問などを務めています。
本書は、税務会計論の基本的な論題と方法論を再検討し、課税所得の計算に関する知見を提供する。第1章から第3章では税務会計の基礎を探求し、第4章から第6章では寄附金、公正処理基準、損失について論じる。第7章から第9章では租税法律主義や公平性を会計学の視点から検討し、基本原理への内在化を考察。最後に第10章では、日本、アメリカ、ドイツの所得計算構造を明らかにする。著者は税理士であり、経済学の博士号を持つ末永英男氏。
本書は、会計の基本的な仕組みや考え方を明確に解説し、最新の会計制度についても検証した大学テキストです。会計学の進化を静態論から動態論、収益費用アプローチから資産負債アプローチへの移行を通じて説明し、その意義を対立概念の比較によって浮き彫りにします。特に第5版では、新基準に基づくFASB概念書第8号の改訂や、国際基準と米国基準のリースに関する共通点についても言及しています。著者は藤井秀樹氏で、会計学の専門家です。
本書は、経営・財務・経理・IRに関わる人々に向けて、重要な経営指標とその選び方を解説しています。著者は、48の指標と31のケーススタディを通じて、企業価値の最大化や持続的成長のための具体的な目標設定を提案。特に、売上高営業利益率やROEなどの指標が強調され、経営者の創意工夫が重要であることが示されています。著者は実務経験豊富なプロフェッショナルで、企業経営における示唆を提供することを目的としています。
本書は、会計の学習方法を根本から変えることを目的としています。著者坂本冬彦氏は、会計の急所を「3つの絵」でシンプルに説明し、実戦に役立つ会計戦略を伝授します。100枚のユニークなイラストを通じて、借方・貸方や財務諸表の理解を深め、新人ビジネスマンや経理担当者に役立つ内容となっています。
本書は、固定資産の取得から減価償却、資本的支出、除却・譲渡までの税務・会計処理を詳細に解説しています。第7版では、自然災害への対応として新たに「災害があったときの処理」を設け、特別償却と圧縮記帳について新たな事例を加えました。また、設備投資減税についても改訂されています。令和3年4月1日現在の法令に基づき加筆・修正された内容となっています。著者は公認会計士・税理士の太田達也氏です。
本書は、企業価値向上のための税務計画が企業にどのように反映され、投資者や課税当局がどのように対応するかを探求し、税制が企業の資源配分や所得分配に与える影響を明らかにする。内容は、目的と構成、分析枠組み、課税所得計算と財務報告の関係、税負担削減行動、経営意思決定への税制の影響、課税管轄間の利益移転、税務法令遵守の研究と制度設計、研究の現状と将来の展望に分かれている。
本書の目的・方法と構成 中小会社の会計とその保証をめぐる会社法上の諸問題 会社法監査の義務付け範囲とIAASBの「複雑性の低い事業体の監査」プロジェクト 中小企業会計の制度的特徴 書面添付制度の利用状況と普及への課題 中小企業決算開示の信頼性等に関する質問票調査 税務会計論等からの考察 内部監査の視点からみた税理士の期中関与による決算書の信頼性向上効果 財務諸表の信頼性確保における専門家業務の位置づけ DXによる透明性・信頼性への貢献可能性 書面添付制度の実務的課題と活用の方策 諸外国における監査以外の中小企業の会計情報の信頼性確保策 総括と今後の課題
本書は、ユニクロやアスクルの成長を支えたコンサルタントが、企業の成長を促すための会計思考の重要性と具体的な数字の活用方法を解説しています。内容は、会計思考経営の必要性、迅速な月次決算と予算管理、利益を生む損益構造の構築、経営指標の活用法、成功企業のケーススタディなど、多岐にわたります。著者は公認会計士であり、実績豊富なコンサルタントです。
膨大な米国会計基準を主要論点ごとに解説。企業結合-JVの形成等2023年9月30日までの基準をフォロー。 膨大な米国会計基準を主要な論点ごとに体系的に解説。第13版では企業結合-ジョイント・ベンチャーの形成等2023年9月30日までの基準改訂をフォロー。IFRSとの比較も明示。
この書籍は、ビジネス・スクールで学ぶ会計スキルを9つのストーリーを通じて簡潔に解説しています。財務諸表の大きなボックスに注目し、会計用語を無視しても理解できる内容で、損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書の読み方を学ぶことができます。著者は慶應義塾大学の准教授で、税務会計を専門としています。
この本は、フリーランスや個人事業者向けに、旅費や家賃、衣服費などの経費をどのように税金控除として落とせるかを具体的に説明しています。著者は税理士で、領収書やレシートの扱い、経費処理の基礎知識、経費として認められるかの判断基準について詳しく解説しています。フリーランスの疑問に答え、税金をできるだけ抑えるための実践的なアドバイスを提供しています。
判例研究の分析視点と評価方法 エス・ブイ・シー事件 所有権移転外ファイナンスリース事件 プリペイドカード事件 興銀事件 中部電力事件 オリックス銀行事件 弁護士報酬の着手金の収入計上時期 弁護士会役員交際費事件 法人所得課税と減価償却. 1 法人所得課税と減価償却. 2 税務会計研究の再検討
この書籍は、中小企業経営者が余計な納税を避けるための合法的な対策を解説しています。内容は、税務調査の実態、重加算税の回避方法、経理ミスや不正への対処、人件費の設定の盲点、節税のグレーゾーンについて触れています。また、著者の見田村元宣は税理士としての豊富な経験を持ち、マーケティングや事業承継に関するコンサルティングも行っています。
本書は、財務会計の基本をコンパクトに解説し、財務諸表を「読む力」を養うことを重視しています。各章の冒頭にはクイズがあり、考えながら学ぶことで推理力や分析力を高める工夫がされています。必要な専門知識を身につけることで、ビジネスシーンで役立つ財務諸表の理解が深まります。著者は小栗崇資氏で、会計に関する多数の著書があります。
企業会計基準委員会(ASBJ)は、令和2年3月31日に「収益認識に関する会計基準」の改正を公表しました。この改正により、注記事項の定めが中心となり、最終版が確定しました。改正基準は令和3年4月1日以降の会計年度から適用されます。本書では、改正基準の注記事項の扱いや、会計・法人税・消費税に関する具体例を交えた解説が行われています。目次には、収益認識の基本内容や適用ステップ、業種別論点、開示などが含まれています。
本書は、株式会社の解散から清算結了に関する税務・会計問題を具体的なケースに基づいて解説しています。第4版では、2011年以降の改正を反映し、最新の申告書記載例を提供。また、新たに完全支配関係にある内国法人間の寄附や欠損金の引継ぎに関するケースを追加し、グループ通算制度の影響についても触れています。目次は解説編、設例編、個別テーマに分かれており、様々な状況に対応した内容となっています。
この書籍は、財務会計に関する詳細なテキストで、金融商品やデリバティブ、リース、減損、研究開発費、退職給付など幅広いトピックを扱っています。会計基準の解説だけでなく、その基礎的な考え方にも重点を置き、論点整理や具体的な事例を通じて理解を深める内容です。第17版では最新のリース会計基準などの改正にも対応しており、公認会計士や税理士試験の対策に最適な基本書となっています。著者陣は会計学の専門家で構成されています。
本書は、連結財務諸表の作成手順や実務上の論点を詳しく解説した決定版であり、第3版ではグループ通算制度や法人税等の会計基準の改正、中間財務諸表に関する基準を扱っています。内容は、基礎から具体的な手続き、資本連結、持分法、外貨換算、税効果会計、注記に至るまで網羅されており、実例を交えてわかりやすく説明されています。
この書籍は、ソフトウェア取引の流れや会計・税務処理を図解でわかりやすく解説しており、新収益認識基準の影響や変更点も扱っています。特徴として「図解」「専門用語少なめ」「キャラクター」があり、楽しく読める内容です。目次には、ソフトウェアの特異性や収益認識、会計処理、減価償却などのテーマが含まれています。
本書は1940年に米国で刊行され、世界中で翻訳されてきた読書技術に関する書籍です。良書とは何か、読書の本質を探求し、初級から高度な読書技術まで具体的な方法を解説しています。読者を積極的な読書へ導き、自身を高めるための手引書となっています。目次は読書の意味、分析読書、文学の読み方、そして読書の最終目標について構成されています。
政治現象を印象論ではなく,実証的に分析するには,どのような作法に従うべきか。身近な社会現象,政治現象を題材に解説する。 実際に起こる政治現象を,印象論ではなく客観的にとらえ,なぜその現象が生じたのかを経験的・実証的に分析するには,どのような作法に従えばよいか。政治学だけでなく,広く社会科学を学ぶ読者を対象に,身近で一般的な社会現象や政治現象を題材に解説する。 序 章 説明という試み 第1章 説明の枠組み─原因を明らかにするとはどういうことか 第2章 科学の条件としての反証可能性─「何でも説明できる」ってダメですか? 第3章 観察,説明,理論─固有名詞を捨てる意味 第4章 推論としての記述 第5章 共変関係を探る─違いを知るとはどういうことか 第6章 原因の時間的先行─因果関係の向きを問う 第7章 他の変数の統制─それは本当の原因ですか? 第8章 分析の単位,選択のバイアス,観察のユニバース 第9章 比較事例研究の可能性 第10章 単一事例研究の用い方 終 章 政治学と方法論 ちょっと長い,少し個人的な,あとがき
長年にわたり自治体行政に携わった著者が、自治体財務会計の仕組みを丁寧に解説。基礎知識を習得しつつ実践的な力も鍛えられる。 長年にわたり自治体行政の実務に携わってきた著者が,法律や条例の根拠条文に立ち返り,その行間に込められた趣旨・目的を読み解きながら,自治体財務会計の仕組みを丁寧に解説する。基礎知識を習得しつつ,財務会計の民主主義的思考力を磨く。 序 章 自治体財務会計を読み解くための視点 第1章 自治体財務会計の全体を俯瞰する 第2章 予 算 第3章 収 入 第4章 支 出 第5章 会計年度末における予算の繰越しの計算 第6章 決 算 第7章 決算統計 第8章 健全化判断比率の公表等 第9章 財務書類四表の作成 第10章 国民主権原理が自治体財務会計の民主的統制を支える
本書は、質的データを効果的に分析し、質の高い論文やレポートにまとめるためのガイドブックです。薄い記述を克服し、分厚い記述に変えるためのコツやヒントが豊富に紹介されています。内容は、質的データ分析の基本原理と実際の手法に分かれており、資料整理、コーディング、分析、概念モデル作成、報告書作成のプロセスが詳述されています。著者は一橋大学の教授で、文化社会学と定性的調査方法論を専門としています。
この書籍は、質的研究におけるQDAソフトウェアの活用法を解説しています。文字データを整理し、意味を掘り起こして論文にまとめる技法を紹介。目次には、質的データの定義、分析の基本原理、プロジェクトファイルの作成、コーディング、比較分析、分析メモの作成などが含まれています。著者は佐藤郁哉で、文化社会学と質的調査方法論を専門としています。
『質的研究入門』は、質的研究の最新動向を反映した全面改訂版で、旧版からの改良に加え新たに11章を追加しています。人文・社会科学、医学、看護学、エスノグラフィー、ジャーナリズム、マーケティングなど幅広い分野の読者に向けた内容で、質的研究の方法論やデザイン、データ収集、分析手法などを体系的に解説しています。著者は質的研究の専門家であり、実践的な視点から質的研究の基礎を提供しています。
この書籍は多変量解析に関連する基本的な統計手法を紹介しており、クラスター分析、主成分分析、重回帰分析、パス解析、因子分析、数量化分析などが含まれています。また、各手法の数値例に基づくソフトウェア操作の概要も提供されています。著者は大阪大学の教授で、心理学を専攻した足立浩平氏です。
本書は、回帰分析の正しい使い方をRを用いて解説したもので、特に因果分析に焦点を当てています。第2版ではRコードの記法を更新し、実データを用いた演習を強化。基礎編では回帰分析や統計の基礎を学び、実践編では様々な分析手法を紹介。数値シミュレーションを通じて直感的な理解を促し、プログラミングマニュアルとしても利用可能です。著者は早稲田大学の准教授たちです。
この書籍は、心理統計学の理論と方法を心理学研究に特有の問題に焦点を当てて実践的に解説しています。目次には、心理学研究と統計の基礎から、回帰分析、推定や検定、実験デザイン、因子分析まで幅広いテーマが含まれています。著者は東京大学の教授で、心理統計学や心理測定学を専門としています。
用語の意味を問う基礎的な問題から,研究を視野に入れた応用的な問題まで幅広い問題を設定した演習書。新しいトピックも紹介。 多くの問題を実際に解くことで,心理統計の考え方について,より深く理解することを目指したワークブック(演習書)。用語の意味を問う基礎的な問題から,研究を視野に入れた応用的な問題まで幅広い問題を設定。心理統計に関する新しいトピックも紹介する。 第1章 心理学研究と統計 第2章 分布の記述的指標とその性質 第3章 相関関係の把握と回帰分析 第4章 確率モデルと標本分布 第5章 推定と検定の考え方 第6章 平均値差と連関に関する推測 第7章 線形モデルの基礎 第8章 偏相関と重回帰分析 第9章 実験デザインと分散分析 第10章 因子分析と共分散構造分析 付 録
近年の心理学や関連領域において広く用いられるようになってきている統計的方法を,前編の内容と関連づけながら解説。 前編『心理統計学の基礎』でねらいとした「統合的理解」を,新しい内容によって広げ,それを通して理解をさらに深められる待望の続編! 近年の心理学や関連領域における統計的方法の活用の現況と心理統計学を学ぶ学生のニーズをふまえ,重要な内容を精選して解説。 第1章 本書の構成と学習の進め方 第2章 分布間の関係と非心分布への拡張─検定力と信頼区間のために 第3章 効果量⑴─2変数データの分析において 第4章 効果量⑵─多変数データの分析において 第5章 対比分析 第6章 マルチレベル分析 第7章 メタ分析 第8章 ベイズ推測
本書は、統計学の基礎から応用までを扱った内容で、基礎編ではR言語を用いた記述統計や統計的仮説検定について解説し、応用編ではベクトルや行列、データフレーム、外れ値の影響などを取り上げています。著者は、教育心理学を専門とする学者たちで、各自が教育機関での実績を持っています。