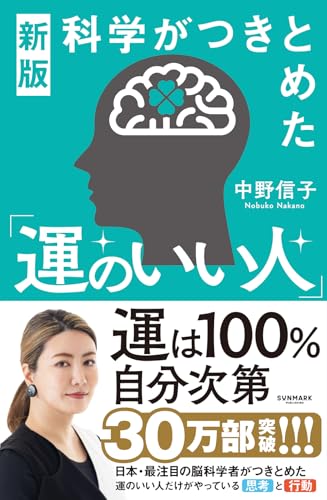【2025年】「中野信子」のおすすめ 本 80選!人気ランキング
- 新版 科学がつきとめた「運のいい人」
- サイコパス (文春新書)
- シャーデンフロイデ 他人を引きずり下ろす快感 (幻冬舎新書)
- エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術
- 中野信子のこどもアート脳科学 「わからない」を楽しむ高IQ脳のそだて方 (中野信子のこども脳科学)
- 世界の「頭のいい人」がやっていることを1冊にまとめてみた
- 人は、なぜ他人を許せないのか?
- 脳科学からみた「祈り」
- メカ屋のための脳科学入門-脳をリバースエンジニアリングする-
- ヒトは「いじめ」をやめられない (小学館新書)
本書は、運の良さは生まれつきではなく、考え方や行動パターンによって変わることを示し、「運のいい人」になるための習慣を紹介しています。著者である脳科学者・中野信子は、運の良さを高めるための思考法や行動を解説し、具体的な方法を提案しています。内容は、自己中心的な思考、ポジティブな自己イメージ、他者との共生、個人の幸せに基づく目標設定、そして祈りの重要性に分かれています。
この書籍は、サイコパスの脳の特性とその社会的影響について探求しています。サイコパスは外見は魅力的でありながら、他者への共感が欠如し、冷酷な行動を取ることが多いとされています。脳科学の進歩により、サイコパスの脳の構造や機能が明らかになり、彼らが必ずしも犯罪者ではなく、ビジネスや政治の分野で成功する傾向があることも示されています。本書では、サイコパスの心理的特徴、脳の働き、進化的な視点からの考察が展開され、一般の人々がサイコパスを理解する手助けをします。著者は脳科学者の中野信子です。
この書籍は、職場や家庭、友人関係などでの困難なコミュニケーションに対処するための知的戦略を提案しています。著者は、直接的な本音を言うことが必ずしも良いわけではなく、関係性を壊さずに自分の気持ちを伝える方法を学ぶ重要性を強調しています。特に「エレガントな毒」を使ったコミュニケーション技術を紹介し、相手を傷つけずに自分の意見を表現する方法を探ります。京都の文化やコミュニケーションの知恵も取り入れ、実践的なレッスンを通じて、より良い人間関係を築くことを目指します。著者は脳科学者の中野信子氏です。
脳科学者・中野信子が「アート」を通じて「高IQ脳」を育て、「わからない」を楽しむ方法を伝える本です。内容は、アートの力や美の感覚、想像力の重要性、人間の生存とアートの関係、他者への思いやり、子どものアート脳に関するQ&Aなどを掘り下げています。著者は脳神経医学博士で、現在は大学で教えながらメディアでも活動しています。
本書は、脳科学者の中野信子が「世界で通用する頭のいい人」が実践している31の方法を紹介しています。これらの方法は、空気を読まないことや適度なストレスを与えること、嫌いな仕事を他人に振ることなど、脳科学的に理にかなったテクニックです。内容は、頭のいい人の特徴や心がけ、スケジュールの立て方、自己分析、自己改良の方法について具体的に解説されており、誰でも実践できるコツが満載です。
この書籍は、脳科学をエンジニアリングの視点から探求する内容で、以下の5つの編から構成されています。第1編では脳の構造と機能を紹介し、第2編では神経細胞の特性と情報処理メカニズムを解説。第3編では運動の制御機構について、第4編では知覚の形成と脳の学習メカニズムを探ります。最後に第5編では脳と芸術の関係を考察し、好みや芸術の法則性について論じています。著者は東京大学の高橋宏知で、神経工学と聴覚生理学の専門家です。
本書は、脳科学者の中野信子が「努力は報われる」という信念の真偽を探り、努力の本質とその影響を解説します。著者は、無駄な努力を避けるために、自分の本当にやりたいことを見極める重要性を強調し、社会の常識に対する疑問を提起します。努力信仰がもたらす弊害や、ブラック企業や少子化問題についても考察し、努力をしないで生きる方法や、夢を実現するための戦略を示します。読者に自分の才能を見つけ、より効率的に生きるためのヒントを提供する内容です。
この書籍は、脳の構造や機能について豊富なカラー図版を用いてわかりやすく解説しています。脳の進化、神経細胞やグリア細胞の役割、記憶の形成と蓄積、意識や思考のメカニズムなど、脳に関する多様な謎を最新の研究を交えて紹介しています。医学生や医療関係者だけでなく、脳に興味があるすべての人にとって必読の一冊です。著者は、脳の高次機能や進化に関する研究を行っている京都大学名誉教授の三上章允です。
この文章は、脳の構造や機能、記憶、学習、意識、倫理に関する内容を扱った書籍の目次を紹介しています。手法編では脳の観察方法、記憶・学習編では海馬の役割、意識編では情動や無意識の意思決定、倫理編では社会的価値について触れています。また、著者の高橋宏知は神経工学と聴覚生理学の専門家で、東京大学で講師を務めています。
本書は脳の基本的な構造や機能をイラストと図解でわかりやすく解説した入門書です。脳の役割、感情や記憶、体との連携、五感のメカニズム、体の調整機能、老化に伴う病気について触れています。監修者の加藤俊徳氏は、脳を理解することが人生を知ることにつながると述べ、脳の成長と変化が個人の経験に影響を与えることを強調しています。読者に脳への関心を深めてもらうことを目的としています。
この本は、脳の不思議や可能性について探求する内容で、右脳と左脳の役割、脳の細胞の重要性、自己認識のメカニズムなどを解説しています。目次では、脳の歴史や脳科学と心理学の関係、夢のメカニズムなど多様なテーマが取り上げられています。著者は毛内拡で、脳科学の専門家として研究を行っています。
人類は、なぜ「さみしい」という感情を持つのか?あなたの知らないあなたの心を脳科学の視点で解き明かす! さみしさは心の弱さではない。生き延びるための本能-。人類は、なぜ「さみしい」という感情を持つのか?あなたの知らないあなたの心を脳科学が解き明かす!「ひとりでいるのがつらい」「誰といても満たされない」集団をつくり、社会生活を営むわたしたち人類のなかで、さみしい・孤独だと一度たりとも感じたことがない人は、おそらくいないのではないでしょうか。集団をつくる生物は、孤立すればより危険が増すため、さみしさを感じる機能をデフォルトで備えているはずだからです。さみしさは人類が生き延びるための本能であり、心の弱さではありません。それなのになぜ、私たちは、「さみしいのは、よくないことだ」「ひとりぼっちは、みじめだ」などと考えてしまうのでしょうか。そこには、さみしさという感情を捉える際に起こりがちな、さまざまな思い込みや刷り込み、偏見が隠れています。本書では、脳科学的、生物学的な視点から、なぜ、さみしいという感情が生じるのかという問いに焦点をあてていきます。また、なぜ、さみしいという感情をネガティブなものと捉えてしまうのか、その科学的要因、社会的要因からも考察していきます。すべての感情には、意味があるはずです。であれば、さみしいという感情が生じたときにも、無理に抑え付けたり、なかったことにしたりするのではなく、「そこにはどんな意味があるのか」を考え、理解していくほうが、この感情をスムーズに扱えるのではないでしょうか。さみしさの扱い方に慣れ、その生じる仕組みを理解することで、さみしさを必要以上におそれることなく、振り回されることもなく、上手に付き合いながら、長い人生をより豊かに、穏やかな気持ちで過ごしていくことができるようになるはずです。 ○第1章 なぜ、人はさみしくなるのか …さみしさは「人間が生き延びるため」の仕組み …さみしさの本質を知る意味 など ○第2章 わたしたちがさみしさを不快に感じる理由 …「さみしいのは、よくないことだ」という思い込みが苦しみを強める …なぜ「ソロ活」は流行し、「ぼっち」は忌み嫌われるのか など ○第3章 脳や心の発達とさみしさの関係 …わたしたちの脳や心は石器時代から変わっていない …思春期に孤独感が強くなる理由 など ○第4章 さみしさがもたらす危険性 …心の弱みに付け込む悪意ある人たち …「激しい怒り」に内在する強いさみしさ など ○第5章 さみしさとうまく付き合っていくために …趣味でつながる新しい共同体の在り方 …さみしいときに持つべき思考の〝置き換え″ など
判断や意思決定過程と理論における歴史的基礎,認知的一貫性と非一貫性,神経経済学と神経生物学など6つの分野に焦点を当て詳説。 判断や意思決定過程とその理論探求は,経済的な影響のみならず,人の幸福と関連する重要課題として学際的な広がりを見せている。本書ではその歴史的基礎,認知的一貫性と非一貫性,ヒューリスティクスとバイアス,神経経済学と神経生物学,発達段階における差異と個人差,意思決定の改善の6つの分野に焦点を当て詳説する。 【主な目次】 序章 ●第I部 歴史的基盤 第1章 熟達者による意思決定:5人のキーとなる心理学者の影響 ●第II部 認知的一貫性と非一貫性 第2章 認知的一貫性:認知的・動機づけ的観点 第3章 感情予想に関する矛盾をはらんだ乖離についてのファジートレース理論による説明 ●第III部 ヒューリスティクスとバイアス 第4章 ファジートレース理論における直観,干渉,抑制,そして個人差の問題 第5章 意思決定前にみられる情報の歪曲 第6章 精密性効果:精密な数値表現が日常的判断にどのような影響を及ぼすか ●第IV部 神経経済学と神経生物学 第7章 フレーミング効果の行動的・神経科学的分析による意思決定過程の検討 第8章 “熱い”認知と二重システム:導入・批判・展望 第9章 慈善的寄付の基盤となる神経経済学と二重過程モデル ●第V部 発達と個人差 第10章 発達におけるリスク志向性:決定方略,感情,制御の変化 第11章 意思決定能力の生涯発達 ●第VI部 よりよい決定のために 第12章 リスクのある意思決定の予測因子:フィッシング攻撃の実例に基づく,判断と意思決定の向上 第13章 シミュレーション結果の経験による判断と意思決定の改善 序章 第Ⅰ部 歴史的基盤 第1章 熟達者による意思決定:5人のキーとなる心理学者の影響 1節 James McKeen Cattell 2節 Wilhelm Wundt 3節 Edward Titchener 4節 Edwin G. Boring 5節 一般化された普通の成人の心 6節 計量心理分析を用いた伝統的な意思決定研究 7節 線形モデルを用いた伝統的な意思決定研究 8節 情報の利用に関する仮説 9節 ヒューリスティクスとバイアスによる伝統的な意思決定研究 10節 Wilhelm Wundt とWard Edwards 第Ⅱ部 認知的一貫性と非一貫性 第2章 認知的一貫性:認知的・動機づけ的観点 1節 認知的一貫性に関する諸理論 1.認知的一貫性の潮流/2.自己理論の潮流/3.意味管理の潮流/4.個人差の潮流 2節 統合的枠組み 1.既存の枠組み/2.枠組みを拡張する 3節 実験結果 4節 結論 第3章 感情予想に関する矛盾をはらんだ乖離についてのファジートレース理論による説明 1節 ファジートレース理論 2節 主旨と発達,熟達化 3節 リスクの知覚とリスクテイキング 4節 少数の特性から高い正確性を得る 5節 ファジートレース理論と感情の記憶 6節 幸福度と主観的ウェルビーイングのアセスメント 7節 主旨に基づいた感情価の判断 8節 逐語的詳細に基づいた正確な判断 9節 主旨情報に基づく全般的予測 10節 結論 第Ⅲ部 ヒューリスティクスとバイアス 第4章 ファジートレース理論における直観,干渉,抑制,そして個人差の問題 1節 判断,意思決定における干渉 1.干渉の処理 2節 主旨に基づいた意思決定 3節 個人差と抑制 4節 衝動性と直観:異なる概念 5節 認知的能力の高さがよい判断・意思決定につながらない場合 6節 結論 第5章 意思決定前にみられる情報の歪曲 1節 経験的証拠 2節 情報の歪曲は測定方法によるアーティファクトなのか 3節 情報の歪曲は取り除くことができるのか 4節 情報の歪曲を示さない人は存在するのだろうか 5節 情報の歪曲は何によって引き起こされるのか 6節 インプリケーション 1.初頭効果による解釈 7節 情報の歪曲の合理性とベイズ推定 8節 ヘッドスタートの影響 9節 出現した選好に対する関与 10節 判断と意思決定の研究パラダイム 11節 エピローグ 1.情報の歪曲に関する研究の歴史/2.実験パラダイム間の対立 第6章 精密性効果:精密な数値表現が日常的判断にどのような影響を及ぼすか 1節 不一致帰属仮説 2節 計算容易性効果 1.不一致帰属の役割/2.素朴理論の役割 3節 精密性効果 1.不一致帰属の役割/2.素朴理論の役割 4節 精密性と信用可能性 1.文脈的手がかりの役割 5節 精密性と希少性 1.文脈的手がかりの役割 6節 精密性と信頼区間 7節 残された課題 1.神経科学の役割 8節 結論 第Ⅳ部 神経経済学と神経生物学 第7章 フレーミング効果の行動的・神経科学的分析による意思決定過程の検討 1節 序論 1.課題 2節 フレーミングタスク 3節 個人差について 4節 二重過程理論 5節 情動過程とフレーミング効果 6節 フレーミング効果とそれ以外の効果における脳代謝レベルでの効果 7節 意思決定の新しい理論を検証するための新しい方法 8節 特殊な集団におけるフレーミング効果 9節 生涯にわたる意思決定 10節 高齢の意思決定者におけるフレーミングと課題に関連した違い 11節 まとめ,結論と将来の研究 第8章 “熱い”認知と二重システム:導入・批判・展望 1節 温度隠喩 2節 “熱”から自律神経反応と誘因顕著性へ 3節 二重過程と二重システムモデル 4節 展望:さらに優れた疑問の問いかけ 5節 R3:熟考の再処理と強化モデル 第9章 慈善的寄付の基盤となる神経経済学と二重過程モデル 1節 二重過程の枠組み 2節 慈善的寄付における,情動と認知の役割について 3節 命の評価における行動的な偏見 4節 心理物理的な無感覚 5節 規模の感受性の鈍麻 6節 同定可能性 7節 疑似無効力とプロポーション優越性 8節 慈善的寄付の神経経済学的視点 9節 まとめ 第Ⅴ部 発達と個人差 第10章 発達におけるリスク志向性:決定方略,感情,制御の変化 1節 決定方略 1.統合的な方略とヒューリスティック/2.統合的な決定方略とヒューリスティックの発達プロセス/3.意思決定の神経科学 2節 感情と制御:二重過程モデルによる説明 1.文脈/2.個人差/3.感情と制御:よい意思決定を学習する 3節 結論 第11章 意思決定能力の生涯発達 1節 意思決定能力の定義 1.規範的理論:人はどのように意思決定を行うべきか?/2.記述的研究:人はどのようなときに規範的な基準に反する意思決定を行うのか? 2節 意思決定能力の生涯発達 1.青年期と成人期の意思決定能力に関する比較/2.高齢者と若い成人の意思決定能力についての比較 3節 意思決定能力の総合的な尺度の開発とその妥当性の検討 1.個人差を反映した妥当性のある意思決定能力の尺度の必要性/2.個人差を反映した意思決定能力の尺度の開発と妥当性の検討/3.意思決定能力の要因と結果を考察する枠組み 4節 今後の展望 第Ⅵ部 よりよい決定のために 第12章 リスクのある意思決定の予測因子:フィッシング攻撃の実例に基づく,判断と意思決定の向上 1節 実証的に支持される知見 2節 考察 第13章 シミュレーション結果の経験による判断と意思決定の改善 1節 人の認知処理の長所と短所 2節 判断課題の構造 3節 人と課題とのマッチング:その含意 4節 シミュレーションの経験の検討:研究プログラムの概要 1.確率判断課題/2.投資/3.競争的行動 5節 考察 文献 人名索引 事項索引 監訳者あとがき
この書籍は、YouTubeの人気動画「科学的根拠に基づく最高の勉強法」を基に、効率的な勉強法を科学的に解説しています。著者は医者としての経験を通じて、従来の学習法(再読、ノート写し、ハイライトなど)が効果的でないことを指摘し、アウトプットの重要性を強調しています。具体的な勉強法として、アクティブリコールや分散学習、記憶術などを紹介し、心身や環境を整える方法についても触れています。著者は、誰でも実践できる効果的な学習法を提供することを目指しています。
脳科学者のジル・ボルト・テイラーは、37歳で脳卒中に襲われ、脳の機能が著しく損傷しました。8年間のリハビリを経て復活し、脳に関する新たな発見や気づきを得た彼女の経験を描いた感動的なメモワールです。著者はハーバード大学で脳神経科学を研究し、精神疾患の啓発活動にも取り組んでいます。
この書籍は、最新の脳科学を基に人間の心と行動を科学的に検証し、行動の背後にある理由を解明します。脳の機能や記憶力向上、メンタルの鍛え方、恋愛やダイエットの方法、認知機能の維持、天才と普通の人の脳の違いなど、実生活に役立つ情報が豊富に含まれています。全5章で脳と心の関係、感覚の不思議、意外な研究結果、恐怖に関する研究、倫理的問題の処理などを紹介し、脳科学への興味を引き立てる内容となっています。著者は玉川大学脳科学研究所の教授、坂上雅道氏です。
この書籍は、第37回講談社科学出版賞を受賞した作品で、脳の機能に関する新たな視点を提供しています。従来の常識ではニューロンが脳の働きを担っているとされていましたが、著者は「すきま」と呼ばれる脳内の細胞外スペースに注目し、そこに流れる脳脊髄液やグリア細胞が心や知性の源である可能性を示唆しています。内容は、脳の掃除機能や認知症との関係、情報伝達の新しいメカニズム、知性の進化など多岐にわたります。著者は脳科学の新しいアプローチを提唱し、脳を健康に保つ方法についても考察しています。
「金スマ」や「NHKおはよう日本」で話題のCDブック「野田あすか」は、発達障害や解離性障害を抱えるピアニストの体験を描いています。著者の野田あすかは、いじめや退学、自傷行為を経て、20歳で広汎性発達障害と診断されました。彼女の思いや悩みを文章とCDで表現し、障害を理解する手助けとなる内容です。脳科学者の中野信子氏も本書を高く評価しています。
本書は、脳科学者の中野信子が、脳を効果的に働かせる方法を解説し、仕事や恋愛、人間関係を向上させるための具体的なテクニックを紹介しています。脳は単純な反応パターンを持っており、それをうまく活用することで集中力、記憶力、判断力、モテ力、アイデア力、努力、運、愛情力を高められるとしています。
この書籍は、楽観主義と悲観主義の脳の活動パターンの違いを探求し、人格形成のメカニズムを心理学、分子遺伝学、神経科学の視点から解明します。著名な楽観主義者たちを例に、彼らが逆境を克服する際の思考方法を考察しています。著者は心理学者・神経科学者のエレーヌ・フォックスで、オックスフォード大学で感情神経科学センターを率いています。
この書籍は、脳科学と身体運動学の観点から音楽の演奏における脳と身体の関係を探求しています。目次には、超絶技巧の実現、音の動きへの変換、音楽家の聴覚、楽譜の理解と記憶、ピアニストの障害と省エネ技術、運動技能、感動的な演奏についての章が含まれています。著者は音楽演奏科学者の古屋晋一で、医学博士の学位を持ち、国内外で講演活動を行っています。
この書籍は、うつ病や自閉スペクトラム症、ADHD、PTSD、統合失調症、双極性障害などの精神疾患のメカニズムと治療法について、最新の研究成果を基に解説しています。精神疾患は脳の変化から生じることが多く、遺伝や環境要因が影響を与えます。各章では、シナプスやゲノム、脳回路、慢性ストレス、動く遺伝因子、治療法などが詳しく探求され、精神疾患を「治る病」にするための道筋が示されています。著者たちは、脳科学や新たな治療アプローチを通じて、精神疾患の理解を深め、支援方法を模索しています。
この書籍は、最新の実証研究に基づき、効率的な学習法について解説しています。一般的に信じられている学習方法が実は非効率であることを示し、記憶と学習の科学的知見を提供します。特に、テストの重要性、練習の組み合わせ、学習の難しさの受け入れ、能力の伸ばし方、学びの定着方法などについて詳述しています。ビジネスパーソンや教育者、学生に向けたアドバイスも含まれており、実践的な学びを促進する内容です。著者は心理学者で、学習と記憶の専門家たちです。
この書籍は「引き寄せの法則」が科学的に実在することを探求し、脳科学、エピジェネティクス、量子物理学などの研究を通じて、思考が物質に与える影響を実証しています。各章では、脳の働き、エネルギーの物質化、感情の環境への影響、DNAの制御、思考の共鳴、シンクロニシティのメカニズム、そして思考を超える意識について解説し、実践的なエクササイズも提供しています。著者はエネルギー心理学を研究する専門家たちです。
この書籍は、脳の働きについての最新研究を紹介し、記憶や感情、認知のメカニズムを探求しています。具体的には、グリア細胞やニューロン、空間記憶、感情の神経回路など、脳内のさまざまな「つながり」を解明する9つの章から構成されています。脳の機能や病気の治療法、親子の絆に関する研究も含まれており、心を生み出す脳の理解を深める内容となっています。
脳科学者・中野信子の初めての児童書は、子どもたちが「イヤな気持ち」にどう向き合い、エネルギーに変えるかを脳科学の視点から解説しています。人間関係や将来への不安、承認欲求などの悩みを抱える思春期の子どもたちに、自分の力で感情を処理する方法をアドバイスします。内容は、脳の機能や「イヤな気持ち」を成長の糧とする重要性についてのメッセージを含んでいます。
本書は、池谷裕二による脳講義シリーズの完結編であり、累計43万部を超えるベストセラー作品です。著者は、脳の存在理由や人間の生きる目的について探求し、脳科学が導く思いもよらない結論を提示します。3日間の講義を通じて、夢と現実、人工知能の影響、脳の役割など多様なテーマを扱い、生命の本質的な喜びを感じる重要性を訴えています。
本書は、現代人が抱える慢性的なストレスとエネルギー不足に対処するための最新の科学的健康法「バイオハック」を紹介しています。著者はスタンフォード大学の医学博士で、脳と身体を最適化する方法や、運動、食事、メンタルケアに関する実践的なアドバイスを提供し、幸福度を高めるための手法を豊富に掲載しています。具体的には、ミトコンドリアの活用、効率的な運動法、食事管理、ストレス解消法などが含まれ、誰でもすぐに実践できる内容となっています。最終的には、頭脳の明晰さと身体的健康を維持し、長寿を実現することを目指しています。
本書は、ハーバード大学医学部の准教授である小児精神科医・脳神経科学者が著した、感情をより良いものに変える思考法「リアプレイザル(Reappraisal)」についての解説書です。リアプレイザルは、認知行動療法の一部であり、不安や恐怖などのネガティブな感情をコントロールする方法です。著者は、脳の仕組みや感情のメカニズムを科学的に解明し、自己肯定感を高める方法や、メンタルヘルスを保つための知識を提供しています。内容は、感情の理解、再評価の手法、レジリエンスの育成、メンタルヘルスの重要性、社会的な偏見への対処法など多岐にわたります。
本書は、脳を理解し使いこなすことで、自己成長や幸せを得る方法を紹介しています。最新の脳科学に基づき、従来の誤解(例:右脳・左脳の概念)を払拭し、脳の構造や機能を理解することでポジティブな思考や生活習慣の改善を促します。著者の増田勝利は、脳科学や心理学を応用し、成功に導くメソッドや幸せを呼び寄せる方法を提供。また、ビジネス効率を高めるための戦術も解説しています。全体を通じて、脳との正しい付き合い方を学ぶことができる一冊です。
自分探し」は、これでおしまい! 「やりたいことがわからない人」に贈る科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」。 「私は、何がしたいんだろう?」「自分の人生、このままでいいのだろうか?」一度でも、こんなことを考えたことはありませんか?人と比べて、「何者でもない自分」に絶望したとき先が見えなくて、「将来が不安」なとき就職、転職、結婚、第2の人生……「人生の岐路」に立たされたとき今の仕事に「やりがい」を感じられないときなかなか結果が出なくて「焦っている」ときそんなとき、向いている仕事、自分の強み、進むべき道を考えて、自分で、自分がわからなくなる――。こうした「自分探し」は、今日でもうおしまい!本書は、200以上の論文と7つのワークで、科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」を解説します。ワーク1 「ライフワークの原石」を見つけようワーク2 「ライフワークの原石」を採点してみようワーク3 7つの質問で「自分の個性」を可視化するワーク4 自分の才能がわかる「診断シート」ワーク5 自分に「向いている仕事」を探すワーク6 「3つのバランス」を確認しようワーク7 「メメント・モリ」で人生の優先順位を明らかにこの1冊で、これまでのモヤモヤがパっと晴れる「やりたいこと探し」の決定版。
本書は、悪い習慣を直すための簡単な解決策を提供するのではなく、習慣の形成メカニズムを科学的に解明し、習慣を変えるための実証的な方法を紹介する。第I部では、脳神経科学や心理学に基づき習慣の性質を説明し、第II部では行動変容の科学に基づく具体的な手法を提案する。著者はオープンサイエンス運動をリードする認知神経科学者であり、習慣に関する最新の研究を通じて、習慣の実像を探求している。
この本は、ドーパミンが私たちの欲求、創造性、成功に与える影響を探求しています。ドーパミンは「快楽物質」ではなく、「欲求ドーパミン」と「制御ドーパミン」の2つの回路を通じて期待や達成感を生み出します。著者は、恋愛、依存症、創造性、政治、社会の進歩など、多様なテーマを通じてドーパミンの役割を解説し、未来志向のドーパミンと現在志向のバランスが脳の潜在能力を引き出す鍵であると述べています。著者はダニエル・Z・リーバーマンとマイケル・E・ロングです。
このビジュアル図鑑は、脳の構造や機能、最新の研究成果をわかりやすく解説しており、入門書や参考書に最適です。内容は脳の成り立ち、機能、感覚、コミュニケーション、記憶、意識、未来の脳、関連疾患について構成されています。著者は九州大学の専門家たちです。
本書は、脳からコンピュータに意識を移すという革新的な研究を紹介し、意識の生成やアップロードの可能性について探求しています。著者は、意識の解明と不老不死の実現を目指し、脳と機械をつなぐ新型インターフェースや人工神経回路網の利用を提案しています。内容は、意識の本質やアップロード後の存在についての問いを含み、科学者としての人生をかけた研究成果がまとめられています。
心が弱っているのは「脳」の調子が悪いだけかも? ――心のはたらきを捉えなおして、悩みにとらわれすぎない自分になろう。 心が弱っているのは「脳」の調子が悪いだけかも? ――あいまいで実体のなさそうな「心」を脳科学から捉えなおして、悩みにとらわれすぎない自分になろう。 心が弱っているのは「脳」の調子が悪いだけかも? ――あいまいで実体のなさそうな「心」を脳科学から捉えなおして、悩みにとらわれすぎない自分になろう。
この文章は、脳科学の研究に基づき、子どもの脳や心の発達と日常生活の関連性を明らかにした内容を紹介しています。具体的には、読み聞かせや読書が子どもの言語発達に与える影響、家庭での学習習慣が脳の発達に良い影響を及ぼすこと、メディアやインターネットの利用が言語能力に悪影響を及ぼすことなどが挙げられています。また、親子関係や生活習慣が子どもの脳の発達に重要であることも強調されています。全体として、子どもたちの周囲の大人に知ってほしい情報がまとめられています。
本書は、直観を活用した最高の意思決定を科学的に解説しています。著者は脳の専門医で、直観を引き出すためには「集中」ではなく「意識の分散」が重要であると述べています。また、直観のメカニズムや実践的思考法を紹介し、AI時代における脳の使い方についても触れています。内容は6章から構成されており、直観力を高めるための方法が具体的に解説されています。
この書籍は、860億個のニューロンが脳内でどのように繋がり、コミュニケーションを行っているかを探求しています。ニューロンの繋がりは、ケガや病気、成長過程の異常によって変化し、これが自閉スペクトラム症やうつ病、統合失調症などの精神疾患に繋がる可能性があります。著者は神経科学の専門家であり、脳の混乱が思考や感情、行動に与える影響を研究し、治療法の可能性を模索しています。内容は脳障害や精神疾患に関する章で構成されており、脳と心の関係を明らかにすることを目指しています。
この本は、1万人以上の脳を診断した医師が「老害」の原因と対策を解明する内容です。「老害」とは、他人の意見を無視したり、新しいものを否定する行動を指します。著者は脳科学の視点から、老害の進行を防ぐためのテクニックや、老害の兆候をチェックするテストを提供しています。主な章では、老害が社会に与える影響、認知症との関連、老害脳の兆候、予防法、自己防衛のテクニックが紹介されています。
腸と脳の相互作用を示す「脳腸相関」が注目されており、腸内環境の乱れが不眠、うつ、発達障害、肥満、高血圧、糖尿病、感染症の重症化など全身の不調に関与していることが明らかになっています。本書では、腸が脳や体に与える影響を分子・細胞レベルで解説し、腸内環境を整える重要性を強調しています。著者は東京大学の坪井貴司教授で、最新の研究成果を基に腸の役割を探ります。
この本は、スタンフォード大学の脳神経外科医が「引き寄せの法則」とその科学的根拠を解説し、富と幸運を引き寄せるための6つの具体的なステップを提供しています。内容は、集中力の回復、真の願望の明確化、ネガティブな自己イメージの排除、無意識への意図の埋め込み、目的の追求、期待を手放すことに焦点を当てています。著者は、自己実現を促進するための脳の働きとその活用法を紹介し、科学と個人の経験を結びつけています。
本書は、脳の重要性とその構造を生徒と先生の対話形式でわかりやすく解説する入門書です。脳は1000億個の神経細胞から成り、情報をやり取りする巨大なネットワークを形成しています。内容は、脳の基本的な構造や機能、感情の生成、脳の病気についても触れています。理科が苦手な人でも楽しめる内容で、著者は東京大学の教授であり、細胞生理学や神経生理学が専門です。
本書は、脳科学者が「運がいい」とは何かを解明し、運を良くするための脳の習慣法を紹介しています。具体的には、脳を活性化するために新しい道を選ぶことや、迷った際には新しい選択肢を選ぶこと、スマホの通知をOFFにして脳疲労を軽減する方法などが提案されています。内容は行動習慣と回復習慣に分かれており、脳の使い方やストレス管理、睡眠の重要性についても触れています。著者は脳神経科学者の毛内拡氏です。
本書は、生成AIが人間の脳の使い方にどのような影響を与えるかを探求しています。著者は、AIが人間の能力を補完し、特にクリエイティビティにおいて人間が持つ独自の価値を強調しています。AIの特性やプロンプト作成のコツ、AIの意識の有無についても論じられ、生成AIが抱える問題や未来の可能性についても考察されています。最終的に、AIの存在が人間の価値を否定するものではなく、むしろ人間らしい行動に特化することを促進すると述べています。
本書では、「心」が実際には存在しないという視点から、心の定義やその起源、性格や感情との関係について探求しています。著者は、生物学的に見た場合、心は脳の働きの結果であり、単なる解釈に過ぎないと主張しています。心の正体を科学的に解明することで、感情に振り回されることや不合理な判断に悩む読者にとっての理解が深まることを目指しています。
本書は脳の科学に関する基礎知識や最新の研究成果を紹介しています。脳の構造や機能、記憶のメカニズム、うつ病やアルツハイマー病などの心の病、発達障害の特性について詳しく解説しています。また、天才の脳の特性や創造性、記憶力の驚異的な能力についても触れています。脳研究の最前線や最新技術を活用したアプローチも紹介され、脳の理解を深めるための内容が盛り込まれています。
「中野信子」に関するよくある質問
Q. 「中野信子」の本を選ぶポイントは?
A. 「中野信子」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「中野信子」本は?
A. 当サイトのランキングでは『新版 科学がつきとめた「運のいい人」』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで80冊の中から厳選しています。
Q. 「中野信子」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「中野信子」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。