【2025年】「計量経済学」のおすすめ 本 127選!人気ランキング
- ミクロ経済学の力
- 計量経済学 (New Liberal Arts Selection)
- 計量経済学の第一歩 -- 実証分析のススメ (有斐閣ストゥディア)
- 統計学入門 (基礎統計学Ⅰ)
- Rによる計量経済学 第2版
- この世で一番おもしろい統計学――誰も「データ」でダマされなくなるかもしれない16講+α
- 経済学・入門 第3版 (有斐閣アルマ)
- 計量経済学のための数学
- 実証分析のための計量経済学
- 予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)
『経済セミナー』の人気連載が単行本化され、ミクロ経済学の本質を深く理解できる内容となっています。著者は東京大学の神取道宏教授で、価格理論やゲーム理論など、経済学の基礎から新しい流れまでを解説しています。全ての人に経済の理解を促すことを目的としたこの書籍は、読み応えのあるレクチャー形式で展開されています。
確率・統計の基礎から因果関係を識別するための応用手法,マクロ経済データの時系列分析の解説まで扱う。演習問題も充実。 確率・統計の基礎から因果関係を識別するための応用手法,マクロ経済データの時系列分析の解説まで扱う。また分析手法の理論的説明だけでなく,その手法を用いた実証例を紹介して理解を深めることができる。演習問題やデータ提供などのウェブサポートも充実。 第1章 計量経済学の目的と特徴 第Ⅰ部 基礎編:実証分析のための基礎知識 第2章 データの整理と確率変数の基礎 第3章 統計理論の基礎 第4章 線形単回帰モデルの推定と検定 第5章 重回帰モデルの推定と検定 第Ⅱ部 ミクロ編:ミクロデータの分析手法 第6章 パネルデータ分析 第7章 操作変数法 第8章 制限従属変数モデル 第9章 政策評価モデル 第Ⅲ部 マクロ編:時系列データの分析手法 第10章 系列相関と時系列モデル 第11章 トレンドと構造変化 第12章 VAR モデル 付録 A 線形代数と漸近理論の基礎 B 回帰分析の漸近理論 C 実証研究の手引き D 文献・学習ガイド
重回帰分析から操作変数法などの応用手法まで,できるだけ直観的な説明を重視して紹介し,ウェブに例題/演習問題のデータも用意。 初心者でも読み進めることができるように,確率・統計の基本から丁寧に解説し,まずは回帰分析を徹底的にマスターします。また,操作変数法,パネル・データ分析などのの応用手法も,できるだけ直観的な説明を重視し紹介しています。 第1章 なぜ計量経済学が必要なのか 第1部 確率と統計のおさらい 第2章 データの扱い方─数字に隠された意味を読み取る 第3章 計量経済学のための確率論─不確かなことについて語る 第4章 統計学による推論─観察されたデータの背後にあるメカニズムを探る 第2部 計量経済学の基本 第5章 単回帰分析─2つの事柄の関係をシンプルなモデルに当てはめる 第6章 重回帰分析の基本─外的条件を制御して本質に迫る 第7章 重回帰分析の応用─本質に迫るためのいくつかのコツ 第3部 政策評価のための発展的方法 第8章 操作変数法─政策変数を間接的に動かして本質に迫る 第9章 パネル・データ分析─繰り返し観察することでわかること 第10章 マッチング法─似た人を探して比較する 第11章 回帰不連続デザイン─「事件」の前後を比較する
文科と理科両方の学生のために,統計的なものの考え方の基礎をやさしく解説するとともに,統計学の体系的な知識を与えるように,編集・執筆された.豊富な実際例を用いつつ,図表を多くとり入れ,視覚的にもわかりやすく親しみながら学べるよう配慮した. 第1章 統計学の基礎(中井検裕,縄田和満,松原 望) 第2章 1次元のデータ(中井検裕) 第3章 2次元のデータ(中井研裕,松原 望) 第4章 確率(縄田和満,松原 望) 第5章 確率変数(松原 望) 第6章 確率分布(松原 望) 第7章 多次元の確率分布(松原 望) 第8章 大数の法則と中心極限定理(中井検裕) 第9章 標本分布(縄田和満) 第10章 正規分布からの標本(縄田和満) 第11章 推定(縄田和満) 第12章 仮説検定(縄田和満,松原 望) 第13章 回帰分析(縄田和満) 統計数値表 練習問題の解答
この書籍は、経済学の基本的な視点を養うために、戦後の日本経済の成長やバブル、アベノミクスに至るまでの歴史を解説し、ミクロ・マクロ経済学の理論やNPO、環境問題などの現代的課題にも触れています。著者は慶應義塾大学の教授で、経済学の専門家としての経歴を持っています。
この書籍は、進んだ計量経済学を学ぶために必要な数学の基礎を解説しています。内容は2部構成で、第1部では集合論と線形代数(集合、ベクトル空間、行列など)を扱い、第2部では確率論と回帰分析の基礎(確率空間、期待値、大数の法則、中心極限定理など)を説明しています。著者は早稲田大学の准教授、田中久稔氏です。
この書籍は、計量経済学の実証分析をわかりやすく解説しており、最小二乗法や最尤法、各種回帰モデルなどの分析手法を具体例とともに紹介しています。内容は、計量経済学の基本理解から始まり、非線形モデルや因果関係の特定、パネルデータ分析まで幅広くカバーしています。著者は慶應義塾大学の山本勲教授で、応用ミクロ経済学や労働経済学が専門です。
この本は、行動経済学の視点から人間の不合理な行動を探求し、予測することでダイエット成功や新商品開発に役立つ可能性を示しています。著者ダン・アリエリーは行動経済学の専門家で、さまざまな実験を通じて人間の行動の背後にある心理を解明しています。文庫版は、彼のベストセラー作品であり、相対性や社会規範、価格の影響など多岐にわたるテーマを扱っています。翻訳は熊谷淳子が担当しています。
本書は、ビジネスにおけるデータ分析の重要性とそのバイアスを取り除くための手法を解説しています。特に、意思決定に影響を与えるデータの生成過程におけるバイアスの存在を指摘し、単純な比較が誤った結論を導く可能性について警鐘を鳴らします。著者は、RCT(ランダム化比較試験)を理想的な分析手法として紹介し、RCTが実施できない場合でも因果推論を用いて効果的な分析が可能であることを説明します。目次には、セレクションバイアスや回帰分析、傾向スコア、差分の差分法などの具体的な手法が含まれています。著者は経済学の専門家で、データサイエンスの分野でも活躍しています。
最新版の統計学スタンダードテキストが発行され、因果推論の基礎や「差の差の分析」を新たに追加し、仮説検定の章も大幅に拡充されています。内容はデータ整理、確率、標本調査、推定、回帰分析など多岐にわたり、読みやすい2色刷りで提供されています。著者は大阪大学の大屋幸輔教授です。
この書籍は、マーケティング調査や金融リスク、株・為替のボラティリティ、選挙の出口調査など、さまざまな分野でのデータ分析の基礎を解説しています。内容は、標準偏差や検定、区間推定などの基本的な統計手法から、観測データを用いた母集団の推定方法まで幅広くカバーしています。著者は帝京大学の助教授で、数理経済学を専門とする小島寛之氏です。
この書籍は、経済学の入門書であり、現実経済や新たな経済学の動向を分かりやすく解説しています。内容はミクロ経済学とマクロ経済学に分かれ、需要と供給、消費者行動、市場の失敗、経済政策など幅広いテーマを扱っています。著者は東京大学の教授、伊藤元重氏です。
本書は、経済学における因果推論の基礎から実践までを丁寧に解説しており、無作為化実験や回帰非連続デザイン、差の差法などの理論と最新の手法を網羅しています。著者はRの分析コードを提供し、実践的な学習をサポート。潜在結果モデルに基づいて一貫した説明がなされ、説得力のある実証分析の技術を習得できる内容となっています。著者は経済学の専門家であり、実証分析に関する豊富な経験を持っています。
『経済学で出る数学』は、経済学に必要な数学を高校数学から再学習するための書籍です。各章は例題、復習、練習問題を通じて、読者が自力で問題を解けるように構成されています。内容は、1次関数や市場メカニズム、独占・寡占市場、金利計算、微分、ベクトル、確率、積分、経済成長理論など多岐にわたります。著者は尾山大輔と安田洋祐で、丁寧な説明と練習問題の追加により、理解を深めることができます。
この文章は、最新改訂版のマクロ経済学テキストの内容を紹介しています。全7部、18章から構成され、世界金融危機後の金融規制やマクロ経済政策の変化を取り上げています。各部では、経済学の基本原理、データ、長期的な経済成長、貨幣と価格、開放経済、短期的な経済変動について解説されており、実際の経済の面白さを実感できる内容になっています。
この書籍は、計量経済学の主要手法である線形回帰、操作変数法、差分の差分について解説し、実験学派のアプローチが応用経済学に与えた影響を探ります。内容は準備編、コア、拡張の三部構成で、特に回帰分析やパネルデータの扱いに焦点を当てています。著者は労働経済学の専門家で、各自が経済学の学位を持ち、研究や教育に従事しています。
『ヤバい経済学』の著者たちによる初中級向けのミクロ経済学テキスト。豊富な実例やグラフを用いて理論をわかりやすく解説し、数学が苦手な学生でも理解できるよう配慮されている。練習問題やコラムもあり、実際のデータを活用した学びが可能。基礎概念から市場分析、消費者・生産者行動まで幅広くカバーしている。ビジネスマンや大学一年生に最適な内容。
元ギリシャ財務大臣ヤニス・バルファキスが、十代の娘の質問をきっかけに経済の仕組みを解説する本。彼は「格差」の歴史を1万年以上遡り、農業の発明から産業革命、仮想通貨、AI革命までを多様な視点で論じる。シンプルで響く言葉で経済と文明の本質を探求し、世界的に評価されている。著者は経済学教授であり、民主的ヨーロッパ運動の共同設立者でもある。
『大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる』がマンガ化され、初心者でも理解しやすい内容になっています。著者の井堀名誉教授が、経済学の基本概念をカツヤマさんにわかりやすく解説。ミクロ経済学とマクロ経済学の主要なテーマを扱い、経済学の重要性や実生活への応用についても触れています。数字に弱い人でも「経済学ってこういうことだったのか!」と理解できる一冊です。
初歩から段階を踏み解説。難しい箇所には印を付し、目的に合わせた学習ができる。新たにデータ・サイエンスとの関連の章を新設。 長年好評を博してきた,信頼の厚い定番テキスト。初歩から段階を踏んで解説。やや難しい箇所には印を付し,目的に合わせた学習ができる。練習問題も充実している。近年の動向に合わせて,新たにデータ・サイエンスとの関連を説明する章を設けた最新版。 序 章 不確かさの時代に向き合う基本統計学 第1章 平均値と分散 第2章 度数分布 第3章 回帰と相関の分析 第4章 確 率 第5章 確率変数と確率分布 第6章 主な確率分布 第7章 標本分布 第8章 推 定 第9章 検 定 第10章 回帰の推測統計理論 終 章 統計学の歴史,因果関係分析,データ・サイエンス
この本は、経済学の常識を根本的に見直す内容で、日本経済の成長停滞やデフレの原因、経済政策の誤解を解説しています。第1部では、日本経済の現状やお金、税金、財政再建のシナリオについて詳述し、第2部では経済学者の誤りやその理論の限界を指摘しています。著者は、経済学がもはや宗教のようになっていると批判し、平成の過ちを繰り返さないための理解を促しています。
現代社会においては,さまざまなデータを正しく扱うことが全てに優先する.本書は,われわれの生活や社会と直接・間接にかかわりをもつ分野で用いられている統計的方法の基礎から応用までを,具体例に即して分かりやすく解説する. 第1章 統計学とデータ(高橋伸夫) 第2章 データの分析(竹村彰通) 第3章 標本調査法(竹村彰通) 第4章 統計調査と経済統計(廣松 毅) 第5章 地域統計(中井検裕) 第6章 経済分析における回帰分析(縄田和満・松原 望) 第7章 経済時系列データの分析(国友直人) 第8章 社会調査(盛山和夫) 第9章 社会移動データの分析手法(盛山和夫) 第10章 要因探究の方法(盛山和夫) 第11章 心理測定データの解析(渡部 洋) 第12章 テスト理論(渡部 洋) 第13章 心理・教育データのための統計的方法(渡部 洋)
この書籍は、ミクロ経済学の基本を学べる内容で、身近な経済ニュースを通じて経済学の考え方を理解することができます。目次には、経済学の基本概念や市場の仕組み、労働市場、公共財、格差問題など多岐にわたるテーマが含まれており、経済についての理解を深める手助けをします。著者は経済学者のティモシー・テイラー、ジャーナリストの池上彰、翻訳家の高橋璃子です。
著者が経済学の重要性を感じ、経済学を学ぶ必要性を伝えるために本書を執筆しました。テレビや新聞で経済に関する情報が常に流れている中、真の教養を得るためには経済学の思考枠組みを理解することが重要です。著者は東京大学での20年以上の教育経験を基に、ミクロ経済学とマクロ経済学のエッセンスを20項目にまとめ、1日30分で学べる内容にしています。主要なトピックには消費者行動、企業行動、市場機能、財政・金融政策、経済成長などが含まれています。
本書は、スタンフォード大学の“最優秀講義賞”を受賞した経済学の授業を再現し、経済政策のニュースを分かりやすく解説します。マクロ経済、GDP、失業率、インフレ、財政政策、国際貿易などのテーマを扱い、誰でも経済通になれる内容です。著者は経済学者のティモシー・テイラー、ジャーナリストの池上彰、翻訳家の高橋璃子です。
経済活動と立地との関係を明らかにし,企業の集積や都市化のメカニズムを解明する,空間経済学の待望のスタンダード・テキスト。 なぜ産業は地理的に集中するのか? 企業の集積や都市はどのように形成されるのか? 現実の経済活動における重要な問いに,空間経済学はいかに答えを導き出すのか──理論の基礎から飛躍的に発展する最先端の研究までを学び,そのメカニズムを解明する。 第1章 序 論 第2章 新貿易理論 第3章 新貿易理論モデルの類型と応用・拡張 第4章 新経済地理学 第5章 新経済地理学モデルの類型と応用・拡張 第6章 空間経済学と単一中心都市モデル 第7章 空間経済学と動学的分析 第8章 空間経済学と租税競争 第9章 空間競争と中心地理論
経済評論家・山崎元が著した本は、お金の稼ぎ方や増やし方についての実践的なアドバイスを提供し、資本主義経済の仕組みを理解することで有利に働く方法を示しています。著者は、世間の流れに流されず、自分の価値を見極めることの重要性を強調し、幸せな人生を送るための戦略や哲学を展開しています。本書は、人生の幸福を追求するための希望を与える内容となっています。また、著者の手紙も収録されています。
自然科学・工学・医学等への応用をめざしつつ,さまざまな統計学的考え方を紹介し,その基礎をわかりやすく解説する.シリーズIと同様に,豊富に実際例を用いつつ,図表を多くとり入れて,視覚的にもわかりやすく統計学を親しみながら学べるよう編集した. 第1章 確率の基礎(矢島美寛) 第2章 線形モデルと最小二乗法(廣津千尋) 第3章 実験データの分析(藤野和建) 第4章 最尤法(廣津千尋) 第5章 適合度検定(廣津千尋) 第6章 検定と標本の大きさ(竹村彰通) 第7章 分布の仮定(竹内 啓,藤野和建) 第8章 質的データの統計的分析(縄田和満) 第9章 ベイズ決定(松原 望) 第10章 確率過程の基礎(矢島美寛) 第11章 乱数の性質(伏見正則)
本書は、著名な経済学者が企業の価格設定や戦略を経済学の理論を通じて解説する内容です。具体的な企業の事例を用い、価格理論、ゲーム理論、行動経済学などを活用して、ビジネスの仕組みを深く理解できるように説明しています。AIやデジタル化、サブスクリプションモデルなどの最新のビジネストピックも取り入れ、内容を刷新。経済学を基にしたビジネスの理解を深めることができる一冊です。
この書籍は、歴史を「お金の流れ」に焦点を当てて分析し、5000年の経済と権力の動きを追跡しています。著者は元国税調査官の大村大次郎で、歴史的な出来事や文明の興亡を脱税や金融破綻などの経済的要因から解説しています。各章では古代エジプトやローマ、ナポレオンの敗北、明治日本の成長など、さまざまな時代の事例を取り上げ、経済が歴史に与える影響を探ります。
本書では、一般的に信じられている通説(例:健診で健康になる、テレビが学力を下げる、偏差値の高い大学が収入を上げる)が経済学の研究によって否定される理由を解説しています。著者は「因果推論」の手法を用い、数式なしでわかりやすく説明することで、根拠のない通説にだまされない力を養うことを目指しています。各章では、様々な因果関係を証明する方法(ランダム化比較試験、自然実験、差の差分析など)を紹介しています。
この書籍は、貧困問題に関する最新の研究を紹介しており、従来の市場対政府の単純な対立を超え、ランダム化対照試行(RCT)という実証実験を通じて具体的な解決策を明らかにしています。著者はアビジット・バナジーとエスター・デュフロで、彼らは貧困削減に関する重要な洞察を提供し、経済学の新たな視点を提示しています。この本は、貧困問題に関心のある人々にとって必読の内容となっています。
今回の改訂に当たっては、旧版の説明を全体にわたってさらにわかりやすく丁寧にすることを中心的なねらいとした。また不正確な箇所の訂正、説明例題の入れかえや追加、数値の変更、練習問題の解答の誤りの訂正などを行なった。 第1章 平均値と分散 第2章 度数分布 第3章 回帰と相関の分析 第4章 確率 第5章 確率変数と確率分布 第6章 主な確率分布 第7章 標本分布 第8章 推定 第9章 検定 第10章 回帰の推測統計理論
本書は、経済学の入門テキストの改訂版で、ハーバード大学やシカゴ大学の学生にも使用される内容です。高校生にも理解できるように丁寧に解説されており、ミクロ経済学とマクロ経済学の主要なトピックを網羅しています。具体的には、経済学の原理、需要と供給、効率性、外部性、国民所得、貯蓄・投資、総需要と供給などが含まれています。この1冊で経済学の基本を学ぶことができます。
本書は、教育に関する一般的な思い込みに科学的根拠を持って反論し、教育経済学の視点から「成功する教育・子育て」についての知見を提供します。内容は、ゲームの影響やご褒美の効果、非認知能力の重要性、少人数学級の効果、良い教師の条件など多岐にわたります。著者は、個人の経験よりもデータに基づく教育の重要性を強調し、教育関係者や親にとって必読の一冊とされています。
統計学の入門書は数多くあるが、初歩的レベルにとどまり、中級レベルのテキストとのギャップは大きい。本書は読者を中級レベルの入口ぐらいまで誘おうというものである。経済・経営系の学生を対象に書かれているが、理工系学生にも理解が深まるよう、重要な事項の証明などの数学的展開も試みている。 第1章 データの記述 第2章 確率 第3章 確率変数と確率分布 第4章 離散確率変数の確率分布 第5章 連続確率変数の確率分布 第6章 多変数の確率分布 第7章 パラメータ推定法と推定量の特性 第8章 パラメータの区間推定 第9章 仮説検定 第10章 回帰分析 付章 クラメール・ラオ不等式および最尤推定量の性質
本書は、行動経済学を通じて人間の非合理的な意思決定を学び、ビジネスや生活に活かす方法を紹介する内容です。著者は東京大学の阿部誠教授で、行動経済学の基本概念をイラスト図解でわかりやすく解説し、実例を交えて応用法を提案しています。特に「ナッジ理論」やマーケティングへの活用事例が取り上げられ、ビジネスパーソンが戦略や企画を提案する際の参考になる一冊です。
この書籍は、数理モデルを用いて現象を理解するための基本的な統計モデルの考え方を、章ごとに異なる例題を通じて解説しています。前半では一般化線形モデル(GLM)の基礎を紹介し、後半では階層ベイズモデル化の手法をRとWinBUGSを用いて具体的に説明します。著者は久保拓弥氏で、生態学のデータ解析に関する統計学的方法を研究しています。
線形回帰分析を学んでそこから一般化線形回帰モデル、ベイズと拡張していく上で非常にオススメな本。初学者には少々難解な部分もあるが、統計学を学ぶ上で必ずどこかで読んで欲しい書籍。学生の時に読んだが、これを読むことでこれまで学んできた内容が整理され頭がクリアになった記憶がある。統計学を語るなら絶対読んで欲しい非常におすすめの書籍。
本書は、初学者向けの経済学入門テキスト『経済学入門(第3版)』の改訂版で、2007年に刊行された第2版から大幅に更新されています。主な変更点は、執筆陣の変更によりミクロ経済学とマクロ経済学がそれぞれ1人の著者によって担当され、内容が初歩から中級にわたるように整理されたことです。また、日本の事例を多く取り入れたコラムが刷新され、経済学の理解を深める内容になっています。目次はミクロ経済学とマクロ経済学の各章で構成され、今後の学習に向けた章も含まれています。著者は早稲田大学の教授陣です。
ミクロ経済学の第一人者による東大講義ノートをベースに編集された,最新のテキスト.伝統的な理論と新しい展開を踏まえた,中級以上向け.数学解説やコラムも充実し,現実の社会問題への応用にも役立つ内容.経済学部の学生だけでなく,ビジネスマンなどの経済学的思考の涵養にも最適な一冊. ※正誤表なども掲載している著者グループのウェブサイトはこちらです.ご参考ください. 序章:ミクロ経済学の方法と目的 第I部:経済主体の行動と価格理論 第1章 消費者行動/第2章 生産者行動/第3章 市場均衡 第II部:ゲーム理論と情報・インセンティヴ 第4章 ゲーム理論の基礎/第5章 不完全競争/第6章 不確実性と情報の非対称性/第7章 外部性と公共財 リーディング・リスト
本書は、経済を「たった1つの図」で説明し、経済の基本をシンプルに理解できるようにすることを目的としています。著者の高橋洋一氏は、ミクロ経済学やマクロ経済学、金融政策、財政政策について具体例を交えて解説し、読者が自分の頭で考えられるようになることを目指しています。特に最新の経済情報にも触れ、経済ニュースを理解する力を養う内容です。
本書は、ビッグデータを用いた因果関係分析の重要性を解説し、データ分析における人間の判断の役割を強調しています。具体的には、広告や政策の影響を評価するための手法として、ランダム化比較試験やRDデザイン、パネル・データ分析などを、数式を使わずに具体例とビジュアルで説明します。また、ビジネスや政策形成におけるデータ分析の実践方法やその限界についても触れています。著者はシカゴ大学の助教授で、経済学の専門家です。
統計的因果推論について分かりやすく学べる。この領域はちゃんと学ぼうとすると奥が深くかなり込み入った内容になってしまうが、この書籍では初めての人にも分かりやすくまとめてありオススメ。
本書は、計量経済分析の手法とRソフトウェアを用いた実行方法を解説した教科書で、経済学や経営学を学ぶ学生や研究者に向けています。内容は回帰分析、時系列分析(定常、非定常、GARCHモデルなど)、パネルデータ分析を中心に、各手法に必要な仮定やRのコードを詳述しています。著者は福地純一郎と伊藤有希で、いずれも経済学の専門家です。
この本は、「日本がもしも100人の島だったら?」という視点から、経済の基本的な仕組みをわかりやすく解説しています。金利、国債、為替、インフレなどの難解な概念を簡潔に理解できるようにし、読者が自分の意見を持てるようになることを目指しています。目次には、経済の基礎から国家の役割、景気や物価、貿易と為替、そして未来の課題まで多岐にわたるトピックが含まれています。著者は経済評論家や学者で、一般向けに最新の経済学を解説することに定評があります。
初学者が躓きやすい箇所にポイントを絞り,具体例とイラストをふんだんに盛り込んで,わかりやすく解説した好評入門書の新版。 初めて勉強する人が躓きやすい箇所にポイントを絞ったうえで,イメージしやすい具体例とイラストをふんだんに盛り込み,わかりやすく解説した好評入門書の新版。新しいコラムを多数追加し,初学者がミクロ経済学の勉強で感じるモヤモヤを徹底的に解消する! 2色刷。 第1部 ミクロ経済学の考え方 第1章 ミクロ経済学とは? 第2章 個人の選択を考える 第2部 完全競争市場 第3章 需要曲線と供給曲線 第4章 市場均衡と効率性 第5章 完全競争市場への政府介入と 死荷重の発生 第3部 市場の失敗と政府の役割 第6章 市場の失敗と政府の役割 第7章 独 占 第8章 外部性 第9章 公共財 第10章 情報の非対称性 第11章 取引費用 第4部 ゲーム理論 第12章 ゲーム理論と制度設計
本書は、近年注目されている統計モデリングについて解説しており、特にフリーソフトのStanを用いた実践的なアプローチを提供しています。Stanは高い記述力を持ち、階層モデルや状態空間モデルを簡単に記述できるため、データ解析に非常に有効です。著者は、ベイズ統計の理解を深めるための実践的な内容を重視し、StanとRを通じて統計モデリングの考え方を学ぶことができるとしています。目次には導入編、入門編、発展編があり、幅広いテーマを扱っています。著者は統計モデリングやデータサイエンスの専門家です。
イングランド銀行が提供する経済入門書で、経済に関する基本的な疑問を10の質問を通じてわかりやすく解説しています。景気や金利、インフレ・デフレ、GDPなどの用語や、経済危機や気候変動といった現代の問題を理解する手助けをします。高校生から一般のビジネスパーソンまで幅広い読者に向けた内容で、経済学の基本をシンプルに学べる一冊です。著者はイングランド銀行のエコノミストです。
この書籍は、グローバル経済の混乱を理解するための入門書であり、ヨーロッパの債務危機やウォール街のデモ、ジャスミン革命などの事例を取り上げています。内容は現代経済学の基本概念からマクロ経済学、経済成長、失業、インフレーション、グローバル危機に至るまで多岐にわたります。著者はノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・E・スティグリッツをはじめとする多くの著名な経済学者です。
本書『入門経済学』は、著者たちの『ミクロ経済学』と『マクロ経済学』から15章を選び、経済学の基本概念を学ぶために再構成されたテキストです。3部構成で、第1部は経済学の基本知識、第2部はミクロ経済学の基礎、第3部はマクロ経済学の基礎を扱います。著者は経済学のシンプルな考え方が現実の問題を理解し改善するのに役立つとし、最新のトピックを取り入れた「新しい」内容が特徴です。テキストには、経済学の原理や現実社会の問題を解決するためのコラムが含まれ、学生が経済を理解するための優先事項として位置づけられています。読後には、経済社会に対する見方が変わることが期待されています。
この書籍は、経済に不慣れな人でも理解しやすい形で最新の「お金の常識」を学べる内容です。目次には、お金の基本、稼ぎ方、将来のための蓄え方、最新の金融情報、そしてお金の流れについての章が含まれています。著者は金融教育ベンチャーのCEOであり、経済アナリストとしての豊富な経験を持つ森永康平氏です。
本書は、全米の大学で広く使用されている最新のミクロ経済学テキストで、新たに「計量」の章とメカニズム・デザインに関する議論を追加しています。目次には市場、需要、選択、均衡、外部性など多様なトピックが含まれており、実践的な要素が強化されています。著者は佐藤隆三で、経済学の著名な専門家です。
各章,理論の導入にあとには,必ず関連した実証分析を紹介するなど理論と実証のバランスを意識した労働経済学の体系的テキスト。 理論と実証のバランスを意識し,身近な題材と豊富なデータを扱いながら労働経済学を学ぶ。理論の説明では,ていねいな数式展開に図表も多く用い,実証例では因果関係の解明に重点をおいたものを取り上げた。はじめて労働経済学を学ぶ学生にも,発展的な労働経済学を学びたい学生にも読み進められる内容に。演習問題も充実。 第1章 労働経済学への招待:理論と実証をつなぐ 第2章 労働供給 第3章 労働供給モデルの応用 第4章 労働需要 第5章 労働市場の均衡 第6章 補償賃金格差 第7章 教育と労働市場 第8章 技能形成と外部・内部労働市場 第9章 労働市場における男女差 第10章 これからの日本社会と労働経済学
本書は、デフレに慣れた日本人に向けて、インフレ時代を乗り切るための経済指標の重要性を解説しています。近年の物価高騰や金利上昇などの影響で経済が不透明な中、適切な指標を理解することで資産を守り、増やす手助けとなる内容です。主な章では、重要な経済指標の解説や、米国の指標、景気を読む企業、コモディティの関係などが扱われています。著者はエミン・ユルマズで、経済の理解を深めたい人々に向けた指南書となっています。
2021年版の『試験対応 新・らくらくミクロ経済学入門』は、茂木喜久雄氏による公務員試験や資格試験対策に最適な教材です。4色オールカラーで、グラフを活用しながら直感的に理解できる内容が特徴です。試験に出やすいポイントや用語解説が充実しており、実力チェック問題も含まれています。内容は消費者行動から国際貿易まで幅広く、資格試験に向けた学習計画も提案されています。
この本は、現代の経済の基本的な概念や仕組みをわかりやすく解説しています。内容は、「デジタル通貨」「仮想通貨」「電子マネー」の違いや、アメリカの銀行破綻の理由、中国の経済体制、物価上昇の原因、景気の良し悪し、日本の新しい経済の形など、多岐にわたります。著者の池上彰が、経済の基本的な質問に答えながら、現代の経済の動きを解明していきます。
この書籍は、ミクロ経済学の理解を深めるために要点解説、例題、練習問題を組み合わせた構成になっており、初版よりボリュームが増加しています。内容は消費者行動や企業行動、競争経済の均衡など広範囲にわたり、公務員試験や大学院入試の対策に適しています。著者は一橋大学の名誉教授、武隈愼一氏です。
奥野正寛編『ミクロ経済学』の執筆陣によるワークブック.ゲーム理論などの新分野を扱った中級ミクロ問題集.各種試験対策に役立つ,演習形式での自学自習が可能.改訂版では問題数が倍増し,量的学習が一層充実.学習の進め方も丁寧に説明. 第I部 価格理論 第1章 消費者行動 第2章 生産者行動 第3章 市場均衡 第II部 ゲーム理論 第4章 ゲーム理論の基礎 第5章 不完全競争 第6章 不完全性と情報の非対称性 第7章 外部性と公共財
2022年から高校での投資教育が必須となり、経済教育への関心が高まっている。本書は、経済の基本やお金の流れ、投資の知識を初心者向けにわかりやすく解説する入門書で、著者のNobbyが「なぜ?」や「どうすればいい?」といった疑問に答える。内容は、世界情勢や日本経済、アジア経済、資源と情報の関係、投資の基礎に関する章で構成されている。
本書は、経済学の基本的な考え方をシンプルに解説し、現実のデータを基に経済社会を理解するための入門テキストです。3つの原理「最適化」「均衡」「経験主義」を中心に、身近な事例を用いて経済現象の原因と結果を直感的に理解することを目指しています。豊富な補助教材も用意されており、授業をサポートします。内容は、経済学の基礎からマクロ経済学、経済成長、景気変動、国際貿易に至るまで幅広くカバーしています。著者は著名な経済学者たちで、最新の事例を取り入れたわかりやすい教科書となっています。
この書籍は、日本経済の現状を解説するもので、ファイナンシャルプランナーと元為替ディーラーの著者が、日経平均株価の最高値更新や対外純資産の世界一を背景に、国民が経済の恩恵を感じられない理由を探ります。また、政府の借金や物価高、円安の影響についても触れ、将来に対する不安を軽減する視点を提供します。目次には、国の借金、年金制度、投資戦略など、経済に関する多様なテーマが含まれています。
この書籍は、専門知識がなくても理解できるように環境問題を解説した入門書の最新版です。最近の環境問題や政策の動向を反映し、図表やトピックスも更新されています。内容は、環境問題のメカニズム、政策の基礎理論、企業の環境対策など多岐にわたり、オンライン講義用のサポートページも充実しています。著者は環境経済学の専門家で、具体的な環境問題を取り上げながら、数式を使わずに基本的な考え方を説明しています。
この書籍は、日本初の行動経済学入門テキストであり、行動ファイナンスや幸福の経済学など多岐にわたるテーマを網羅しています。人間の非合理的な感情や行動を体系的に解明する内容で、全9章から構成されています。著者は経済学の専門家で、各章ではヒューリスティクス、リスク選好、社会的選好などの重要な概念が扱われています。
本書は、マクロ経済学の基本概念とデータの解釈を解説し、長期的な経済成長論を中心に経済動向を考察するテキストです。目次には、マクロ経済学の紹介、計測、経済成長の概要、各種モデル、労働市場、インフレーションなどが含まれています。著者はスタンフォード大学のチャールズ・I・ジョーンズ教授をはじめ、マクロ経済学の専門家たちです。
この書籍は、イノベーション都市の高卒者が旧来型製造業都市の大卒者よりも高い収入を得ている現象を探求し、新しい仕事の創出場所や「ものづくり」だけでは経済が成長しない理由を論じています。目次には、都市の浮沈、イノベーションの影響、給料の決定要因、移住の影響、地域再生の条件などが含まれています。著者はエンリコ・モレッティで、労働経済学や都市経済学の専門家です。
この書籍は、日本、アメリカ、中国、ヨーロッパの64の経済指標を解説し、個人投資家や金融関係者が経済動向を把握するための知識を提供します。著者は経済アナリストで、経済指標の読み方や投資時のポイントをわかりやすく紹介。経済ニュースを理解するための専門用語の解説も含まれており、経済学に興味がある人にも適しています。また、経済指標の公表時期をまとめたカレンダーも掲載されています。
「計量経済学」に関するよくある質問
Q. 「計量経済学」の本を選ぶポイントは?
A. 「計量経済学」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「計量経済学」本は?
A. 当サイトのランキングでは『ミクロ経済学の力』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで127冊の中から厳選しています。
Q. 「計量経済学」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「計量経済学」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。











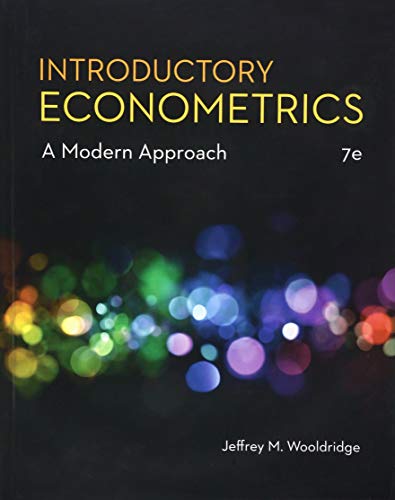






![『入門経済学[第4版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41dClUCUpEL._SL500_.jpg)

![『[改訂版]経済学で出る数学 高校数学からきちんと攻める』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51DaoUAGa5L._SL500_.jpg)


















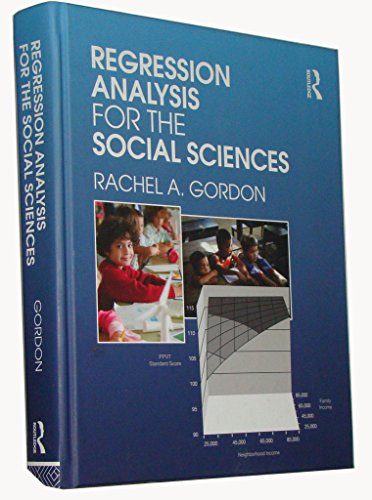
























































![『入門ミクロ経済学 [原著第9版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41diLq75Q8L._SL500_.jpg)










































