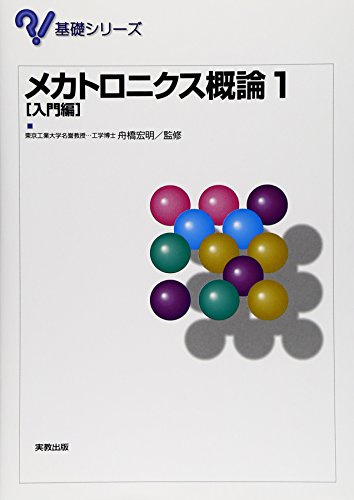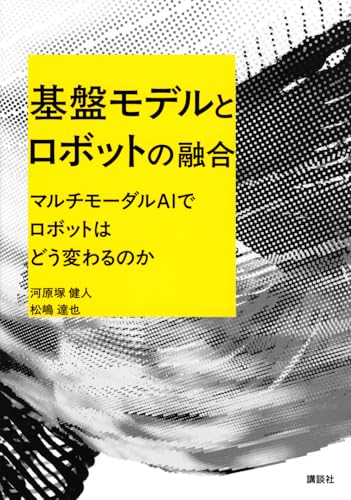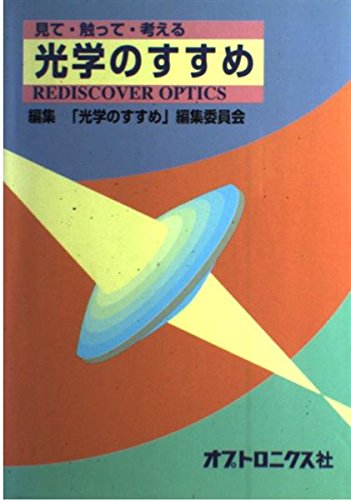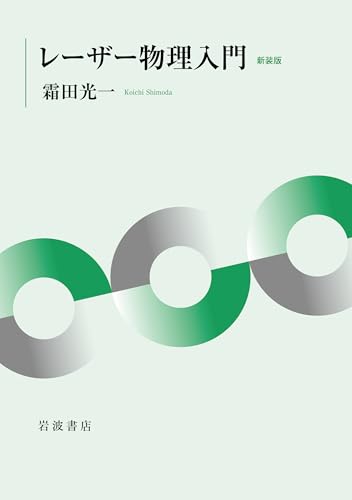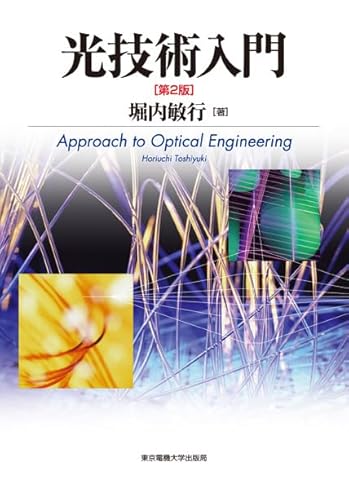【2025年】「ロボット工学」のおすすめ 本 115選!人気ランキング
- ロボット工学の基礎(第3版)
- 入門 ロボット工学
- 実践 ロボット制御: 基礎から動力学まで
- ロボットによる工場自動化教本 最適な自動化ラインの設計から立ち上げまで
- 産業用ロボット The ビギニング
- 未来を変えるロボット図鑑
- わかりやすいロボットシステム入門(改訂3版): メカニズムから制御、システムまで
- 実際の設計選書 設計者に必要なメカトロニクスの基礎知識
- イラストで学ぶ ロボット工学 (KS情報科学専門書)
- 図解 モノづくりのための やさしい機械設計
このテキストは、全国の大学や高専で使用されているロボット工学の教科書で、改訂により視認性と記述が向上しました。初心者向けに力学や代数の基本からロボットのセンサ、機構、運動学、制御までを学ぶことができ、例題や演習問題を通じて基礎を習得できます。内容はロボットの歴史から始まり、感覚、アクチュエータ、運動学、動力学、誤差解析、位置制御、力制御などを網羅しています。著者は川崎晴久で、工学博士の資格を持ち、長年にわたり教育と研究に従事してきました。
この書籍は、ロボット工学の基礎を学べる入門書で、特に2自由度ロボットアームを題材にしています。直感的でわかりやすい内容が特徴で、難しい数学は避けつつ、数式の導出過程も丁寧に説明されています。例題や演習問題を通じて理解度を確認でき、後半には数値シミュレーションの例もあり、実践的な学びを提供します。初学者や他の書籍で難しいと感じた方にも適しています。目次にはロボットの基本から運動学、静力学、制御までが含まれています。著者は大阪市立大学の高田洋吾氏です。
本書は、ロボットを効果的に制御するための知識を体系的に解説した教科書です。従来の理論中心のアプローチから脱却し、ロボティクスを独立した学問として実践的に学べる内容になっています。多自由度ロボットの制御技術を解析的・数値的に整理し、実装に必要な情報を提供します。目次は運動学、ヤコビ行列、動力学と運動制御に分かれており、著者は大阪大学の細田耕教授です。
この書籍は、初心者向けの「産業用ロボット」入門書であり、産業用ロボットの基本概念や種類、構成要素、制御装置、性能、周辺機器、法令について解説しています。著者の西田麻美は、機械設計やロボット教育に従事する専門家で、数々の受賞歴があります。
本書は、ロボットシステムに関する定番教科書の改訂版であり、近年の技術や社会の変化を反映した内容となっています。ロボットの基礎から応用技術までを包括的に解説し、メカトロニクスやセンサ、アクチュエータ、運動制御など多岐にわたるトピックを扱っています。著者はロボット技術の専門家であり、実務と学術の両方で豊富な経験を持っています。
『イラストで学ぶ人工知能概論』の第2弾『ホイールダック2号@ホーム』は、ロボット工学の基本をストーリー仕立てで学べる書籍です。マニピュレータ制御に必要な数学的・物理的な概念を解説し、章末問題で計算力を養う内容となっています。主なトピックには、基本的な制御、自由度、運動学、ロボット用アクチュエータやセンサなどが含まれています。著者は福岡工業大学の教授木野仁と立命館大学の教授谷口忠大です。
本書は機械力学の基礎知識をわかりやすく解説しており、機械の構成要素の力や運動を理解するためのモデル化や運動方程式について学べる内容です。目次には、機械要素の力学に関する様々な章が含まれており、著者は三好孝典氏で、豊橋技術科学大学の教授です。
本書は、人工知能(AI)と人間の創造性の関係を探求し、AIが持つ可能性について考察しています。著者は、AIを単なる道具としてではなく、人間の創造性を拡張するパートナーとして捉え、AIと人間の創作行為の歴史を辿ります。AIが創造性を持ち得るかどうかを問い、模倣を通じて人間の創造性を新たに理解する試みを展開。最終的には、AIと創造性の未来に光を当てます。著者はAIを用いたアートや研究を行う徳井直生氏です。
高橋麻奈の「やさしいC」は、プログラミング初心者向けのC言語教科書で、シリーズ累計100万部を突破しました。新装丁で読みやすく改訂され、豊富なイラストやサンプルプログラムを用いて基本を丁寧に解説しています。新しいC言語仕様やVisual Studio 2017への対応も含まれ、初心者がしっかりとC言語を学べる内容です。著者は東京大学卒の高橋麻奈です。
この解説本は、機械設計における業務上の課題とその解決策を明示的に紹介しています。設計者が押さえておくべき重要ポイントをまとめており、内容は設計業務の基本から安全性、品質、環境への配慮、効率的な業務遂行、知識の保護まで多岐にわたります。著者は、技術士であり、機械設計に関する教育や研修を行っている専門家です。
この書籍は、機械工学の基本を親しみやすいイラストでわかりやすく解説しており、公式や数式は最小限に抑えています。初心者や機械を学び始める人に最適で、ものづくりに関する広範な知識を提供します。目次には、機械工学の基礎から材料、力、運動、加工方法、機械のしくみ、制御、熱までが含まれています。著者は小峯龍男で、工学の専門家です。
本書は、800円弱で入手可能なPicoおよびPico Wマイコンボードについて、仕様や製作例を幅広く解説しています。内容は、開発の基礎知識からプログラマブルI/O、USB機能、リアルタイムOS、人工知能の搭載、開発事例、Windowsでの利用、MicroPythonやC++による拡張モジュールの作成、Pico Wの活用事例まで多岐にわたります。
本書は、2020年版の最新JISに基づく機械製図の基礎知識を「網羅的に」「やさしく」解説しています。視覚的に理解できるよう図面にポイントを示し、実践的な題材を用いてものづくりを意識した学びを提供します。正しい図面の描き方や間違いやすい例を示すことで、基礎をしっかり身につけることができます。著者は同志社大学の名誉教授などで、内容はISOに準拠した図面作成の要点を含んでいます。目次には、図形、寸法、幾何公差、材料記号など多岐にわたるテーマが含まれています。
本書は、2020年から義務教育に導入されるプログラミングの基礎であるアルゴリズムについての入門書です。アルゴリズムの考え方や仕組みを楽しく学べる内容で、問題解決や計算方法に関する様々な処理手順を紹介しています。目次には、アルゴリズムの基本やその応用、さらにはプログラミング環境「Scratch」を使った実践も含まれています。著者は坂巻佳壽美で、長年にわたり技術指導に従事してきました。
本書は、機械設計エンジニアが複雑な動作を実現するためのメカニズム設計のヒントを提供します。さまざまな機構を目的や動作に基づいて分類し、比較・選択を容易にする内容で、具体的な動作解析も含まれています。若手からベテラン設計者まで幅広く活用できる資料で、直線運動や回転運動など8つの章に分かれています。著者は岩本太郎氏で、機械工学の専門家です。
この書籍は、ROS 2 Humbleに対応した改訂版で、人工知能とロボット工学を実践的に学ぶことができます。主な変更点には、通信方式の改善、新しい音声認識技術の導入、ナビゲーションやマニピュレーションのプログラムの追加が含まれています。内容は、AIロボットの制作、ROS 2の基礎、音声認識、ナビゲーション、視覚認識、マニピュレーション、行動計画など多岐にわたります。著者はロボット工学の専門家で、実績も豊富です。
この文章は、人工生命やアンドロイドの進化がもたらす未来についての考察を紹介しています。著者の石黒浩と池上高志は、技術の進展が「人間」の定義をどのように変えるかを探求し、時間、知能、機械化、意識、社会性などのテーマを通じて、私たちの世界認識がどのように変わるかを議論しています。特に、人工生命やアンドロイドとの共存が近づく中で、「人間であること」の意味を再考する必要性が強調されています。
本書は、Raspberry Pi 4 Model Bを用いて家族向けのコミュニケーションロボット「SIRO」を製作する方法を紹介しています。内容は、Raspberry Piの準備からロボットのハードウェア製作、基本機能の実現、制御プログラムの構成まで多岐にわたります。幅広い知識が必要ですが、初心者でも取り組みやすい内容です。サンプルプログラムのダウンロードも可能で、DIY工作として楽しめる一冊です。著者は機械メーカーに勤めるサラリーマンで、ロボティクスを専攻しています。
本書ではリンカとローダの役割を実践を通じて説明し、コア・ダンプの解析やリンカの自作などの実験を行います。目次には、リンカ・スクリプトの利用法や簡易ローダの作成、共有ライブラリの使い方などが含まれています。著者の坂井弘亮は、ネットワーク製品の開発に従事しながら、様々な技術に関する活動を行っています。
本書は、デジタル画像処理の基礎から最新技術までを体系的に学べる入門書です。自動運転やAIの進展に対応した内容に改訂され、初版のわかりやすい解説が維持されています。目次には、画像の基礎、カラー画像、フィルタ処理、圧縮技術、AIと画像認識などが含まれ、幅広い応用分野をカバーしています。著者は岐阜大学の山田宏尚教授で、画像処理やメカトロニクスの専門家です。
光村図書の令和6年度版小学2年生国語教科書に対応した「ロボット」の調べ学習本です。低学年向けにロボットの特徴をわかりやすく説明し、QRコードやまとめシートなどの付録も充実しています。2巻では掃除、介護、音楽制作など身近なロボットを紹介しています。
この本は、IoTやAIの普及に伴い重要性が増すセンサについて、機械設計者が知っておくべき基本的なポイントをイラストや図を使ってわかりやすく解説しています。メカトロニクス関連の設計に必要なセンサの基礎知識を楽しく学べる内容で、目次にはセンサの特性や信号処理技術、データシートの読み方などが含まれています。著者はメカトロニクスやロボット教育の専門家で、豊富な経験を持つ大学教員です。
この本は、ロボットの基本知識を包括的に紹介しており、技術の構成、種類、働く場所について詳しく解説しています。内容はセンサや制御技術、産業用ロボット、医療や福祉分野での応用、日常生活を支えるサービスロボット、そしてロボットの社会への実装など多岐にわたります。全体を通じて、ロボットの基礎から未来の展望までを理解できる内容となっています。
本書はシーケンス制御プログラムの作成に関する考え方や技術を定石集としてまとめ、具体的な機構図を用いてプログラムの作り方を解説しています。内容は基礎知識から初級・中級・実用テクニック、システム構築に至るまで多岐にわたります。著者は熊谷英樹で、電気工学の専門家としての経歴を持ち、多くの教育活動にも従事しています。
本書は、2019年に刊行された「ROS2 ではじめよう 次世代ロボットプログラミング」の改訂版で、ロボット開発のミドルウェアROS 2に焦点を当てています。基本概念から応用、実践的な使用方法まで幅広く解説し、C++やPythonを用いたプログラミング方法や主要ツール、実際のロボットハードウェアを使った例も紹介しています。対象はロボット開発者やエンジニア、研究者などで、ROS 2の理解を深め、革新的なロボットアプリケーションの開発を促進することを目的としています。
自動運転車やケア・ロボット、自律型兵器などが引き起こしうる、もはや SF では済まされない倫理的問題を通し、人間の道徳を考える、知的興奮に満ちた入門書。「本書には、ロボットや AI という新しい隣人たちとつきあう上で参考となる倫理学の知恵がつまっている」 —— 伊勢田哲治。 はじめに Ⅰ ロボットから倫理を考える 第1章 機械の中の道徳 —— 道徳的であるとはそもそもどういうことかを考える 1-1 アシモフのロボット工学三原則 1-2 倫理はプログラム可能か? 1-3 道徳と感情 1-4 機械化された道徳は道徳なのか? 1-5 おわりに 第2章 葛藤するロボット —— 倫理学の主要な立場について考える 2-1 まず倫理に含めないものを除外しよう 2-2 倫理学を三つに分ける 2-3 規範倫理学の主要な二つの立場 : 帰結主義 (功利主義) と義務論 2-4 功利主義 2-5 義務論 2-6 第三の立場 : 徳倫理学 2-7 おわりに 第3章 私のせいではない、ロボットのせいだ —— 道徳的行為者性と責任について考える 3-1 「ロボットに責任を帰属する」 とは? 3-2 ロボットも責任主体になれるかも? : 両立論の考え 3-3 人は自己形成をコントロールできない : 非両立論の考え 3-4 ロボットへの帰責は可能か? 3-5 おわりに 第4章 この映画の撮影で虐待されたロボットはいません —— 道徳的被行為者性について考える 4-1 道徳的被行為者とは 4-2 道徳的被行為者としての人間 4-3 道徳的被行為者の範囲は? 4-4 ロボットを道徳的被行為者とみなす必要性はあるか? 4-5 おわりに Ⅱ ロボットの倫理を考える 第5章 AI と誠 —— ソーシャル・ロボットについて考える 5-1 ソーシャル・ロボットの普及 5-2 まやかしの関係? 5-3 ソーシャル・ロボットはユーザーを欺いていると言えるのか? 5-4 うそも方便 5-5 ソーシャル・ロボットが社会に与える影響 5-6 おわりに 第6章 壁にマイクあり障子にカメラあり —— ロボット社会のプライバシー問題について考える 6-1 ロボット利用に伴うプライバシー問題 6-2 プライバシー権とは 6-3 プライバシーの価値と情報化時代のプライバシー理論 6-4 ロボット共生社会における情報プライバシー 6-5 おわりに 第7章 良いも悪いもリモコン次第? —— 兵器としてのロボットについて考える 7-1 遠隔操作型兵器から自律型兵器へ 7-2 戦争にも倫理はある 7-3 自律型兵器をめぐる賛否両論 7-4 兵器開発競争への懸念 7-5 戦争の生態系 7-6 おわりに 第8章 はたらくロボット —— 近未来の労働のあり方について考える 8-1 創作物における 「はたらくロボット」 8-2 機械はなんでもできる 8-3 技術的失業と機械との競争 8-4 社会的な影響と対策 8-5 悪いことだけなのか? 8-6 ロボットにできるからといってロボットに任せたいとは限らない 8-7 労働者としてのロボットの責任と権利 8-8 おわりに
本書は、急速に進化するAI技術とその影響を考察し、特にロボット法の必要性を強調しています。自律的に行動するロボットが社会に及ぼすリスクや倫理的課題について、制御不可能性や不透明性を軸に議論します。EUのAI法などの国際的な動向を踏まえ、生成AIの利用、メタバース、医療・司法分野におけるAIの活用についても触れています。著者は、AIガバナンスを考える上でロボット法が重要であると提案しています。
この文章は、からくりやメカニズムに関する内容を扱った書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、さまざまなメカニズムの種類や運動変換の方法、アクチュエータとの連結、設計に関するトピックが列挙されています。著者は熊谷英樹氏で、工学の専門家であり、複数の教育機関で非常勤講師を務めています。
本書は、油圧・空気圧システムの基礎から回路図の読み方、設計方法までを解説した実務書です。若手技術者や機械系学生向けに、実例を交えながら実践的な知識を提供します。内容は油圧編と空気圧編に分かれ、それぞれ基礎、機器の構造、基本回路、設計について詳しく説明されています。教育用資料としても活用可能です。著者は油圧技術の専門家で、業界での経験を活かした内容となっています。
本書は、AIやロボット技術の進化に伴う倫理的問題を考察し、人間の道徳について探求する入門書です。著者たちは、ロボットやAIとの関係における倫理学の知恵を提供し、道徳的行為者性や責任、プライバシー、労働の未来などのテーマを扱っています。著者は名古屋大学や南山大学、金沢大学の教授陣で構成されています。
本書は、工作機械産業の重要性とその革新の歴史を、ファナックとインテルの事例を通じて探求しています。工作機械は「マザーマシン」と呼ばれ、様々な製品の製造に欠かせない存在であり、特に日本の工作機械産業は過去25年間、世界最強を維持しています。著者はこの産業の技術が国家の安全保障にも影響を与えることを強調し、歴史を学ぶことで未来の創造につなげることを目的としています。
本書は、日本のAI研究の第一人者である著者が、2020年代から2040年代にかけてのAIの社会への浸透を予測し、AIに関する誤解を解消しながら、AIを受け入れるための社会的要件を明らかにする内容です。各章では、AIの本質、期待される役割、教育への影響、産業での活用、そしてAIと共に生きる未来のシナリオについて論じています。著者は、工学博士であり、AIの協調研究に取り組んでいる専門家です。
『Mother Machine』は、工作機械メーカー・ヤマザキマザックの100年にわたる挑戦を描いた書籍です。著者の神舘和典は、同社の創業からブランドの確立、国際展開、技術革新、そして次世代人材育成に至るまでの軌跡を紹介しています。特に、英国のサッチャー首相や中国の江沢民からの評価を受けたことが強調され、世界市場でのリーダーシップを確立する過程が詳細に述べられています。
本書は若手ロボット研究者がロボットの歴史を振り返り、未来のロボット技術の進化と私たちの生活の変化について考察する内容です。ロボットに関する知識がない人でも理解しやすく、人間とロボットの役割の違いや、ロボットの働き方、遊び方、学び方についても触れています。著者は東京大学の講師で、ロボット工学の専門家です。
本書は熱処理技術の基礎を平易に解説し、鋼の変化や実例を紹介する入門ガイドです。内容は鉄材料、金属の性質、熱処理装置、手法、恒温変態、表面処理、鋼の熱処理、管理と品質に関する章で構成されています。著者は工学博士で、熱処理に関する豊富な経験を持つ坂本卓教授です。
この書籍は、ICTやIoTを活用したデジタル・トランスフォーメーション(DX)が農業ビジネスと農村社会に与える影響を探求しています。自動耕作や農地最適管理などの支援システムを中心に、第4次農業革命の展開策を提案しています。また、次世代農業ロボット「MY DONKEY」の導入や、スマート農業の普及を通じて、農業のビジネス化や農村のデジタル化を進める戦略が述べられています。著者は農業ビジネスや地域活性化の専門家であり、実践的な知見が盛り込まれています。
この書籍は、メカトロニクスに関する包括的な内容を扱っており、基礎知識から機械要素、センサ技術、アクチュエータ、制御システム、ロボット技術まで広範囲にわたる。著者は三浦宏文氏で、東京大学と工学院大学の名誉教授である。最終章ではロボット競技大会の事例研究も紹介されている。
アンドロイドとは何か 漱石アンドロイド計画 漱石アンドロイドの制作 動きはじめる漱石 漱石と出会う体験の創出. 1 漱石と出会う体験の創出. 2 再生ロボットに権利はあるのか?それは誰が行使するのか? アンドロイドによる進化 アンドロイドの発話行為、どこまでホンモノに近づけるか アンドロイドとのコミュニケーションと体験の価値 アンドロイド基本原則はどうあるべきか 人がアンドロイドとして甦る未来
これまでの産業用ロボットの歴史を振り返りながら、これまでどのようなロボットが市場で求められてきたのかについて順に触れていく。 これまでの産業用ロボットの歴史を振り返りながら、これまでどのようなロボットが市場で求められてきたのかについて順に触れていく。その中で核となる自動化の考え方、ロボット自体の要素技術についても解説する。
この文章は、パターン認識と統計的学習に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、特徴空間、線形識別法、ナイーブベイズ法、次元縮約、テンプレートマッチング、決定木、集団学習法、非線形判別関数、ニューラルネットワーク、カーネル法などのトピックが含まれています。著者は後藤正幸と小林学で、それぞれの学歴と職歴が記載されています。
この書籍は、脳科学をエンジニアリングの視点から探求する内容で、以下の5つの編から構成されています。第1編では脳の構造と機能を紹介し、第2編では神経細胞の特性と情報処理メカニズムを解説。第3編では運動の制御機構について、第4編では知覚の形成と脳の学習メカニズムを探ります。最後に第5編では脳と芸術の関係を考察し、好みや芸術の法則性について論じています。著者は東京大学の高橋宏知で、神経工学と聴覚生理学の専門家です。
この文章は、脳の構造や機能、記憶、学習、意識、倫理に関する内容を扱った書籍の目次を紹介しています。手法編では脳の観察方法、記憶・学習編では海馬の役割、意識編では情動や無意識の意思決定、倫理編では社会的価値について触れています。また、著者の高橋宏知は神経工学と聴覚生理学の専門家で、東京大学で講師を務めています。
本書は、人工知能アルゴリズムに関する教科書で、探索、ゲーム、機械学習、知識表現、セマンティックWebを解説しています。読者は最適解の発見や意思決定の自動化、知識の理解と推論技術を学びます。各章では、人工知能の歴史、探索手法、ゲーム理論、進化的計算、ニューラルネットワーク、強化学習、その他の機械学習手法、知識表現、セマンティックWeb技術について詳述し、C言語やPythonのソースコードも提供されています。著者は中京大学の教授たちで、実践的なプログラム作成を通じて理解を深めることができます。
光線の基本的な性質から、各種応用光学や機器について最新のものを記載。理解が難解な数式について、展開の補足を行った。 人間の五感の中でも、とくに情報量が多い視覚と密接な関連を持つ「光」の利用技術は、近年ますます重要性を増している。これらについて光線の基本的な性質から、各種応用光学や機器について最新のものを記載。理解が難解な数式について、展開の補足を行った。 第1章 光線の性質 1.1 光とは 1.2 幾何光学 1.3 幾何光学の基本原理 1.4 幾何光学の基本法則 1.5 正規反射と乱反射 1.6 全反射 参考文献 第2章 レンズによる結像 2.1 凸レンズと凹レンズ 2.2 光軸と焦点 2.3 主点と主平面 2.4 球面における屈折 2.5 凸レンズによる結像 2.6 凹レンズによる結像 2.7 ニュートンの結像式 2.8 レンズを2枚重ねたときの焦点距離 参考文献 第3章 ミラーによる結像 3.1 凸面鏡と凹面鏡 3.2 凹面鏡による平行光の集束 3.3 凸面鏡による平行光の発散 3.4 凹面鏡による結像 3.5 凸面鏡による結像 3.6 平面鏡による結像 3.7 球面以外の二次曲面の性質 参考文献 第4章 収差 4.1 球面による収差 4.2 色収差 参考文献 第5章 光の波動性 5.1 光の波動的な特徴 5.2 光の波動の解析 5.3 干渉 5.4 偏光 5.5 反射特性への波動性の影響 参考文献 第6章 回折 6.1 回折現象 6.2 短形スリット2によるフラウンホーファ回折 6.3 回折格子 6.4 円形開口によるフランホーファ回折 6.5 レンズによるフランフォーファ回折 6.6 スリットによるフレネル回折 6.7 ナイフエッジによるフレネル回折 6.8 光波の複素数表現 参考文献 第7章 光の粒子性 7.1 水素の輝線スペクトル 7.2 光子と光子のもつエネルギ 参考文献 第8章 光と視覚 8.1 人間の目の構造 8.2 人間の目の解像度 8.3 光の強さ 8.4 めがね 参考文献 第9章 レーザ 9.1 レーザ光の発生 9.2 レーザ光のモード 9.3 レーザ光の種類と用途 参考文献 第10章 光ファイバー 10.1 光ファイバーの構造 10.2 光の伝播可能角度 10.3 通信用光ファイバー 10.4 画像取り出し用光ファイバー 10.5 ライトガイド 参考文献 第11章 光学機器 11.1 拡大鏡(ルーペ) 11.2 顕微鏡 11.3 望遠鏡 11.4 カメラ 11.5 コピー機 11.6 レーザプリンタ 参考文献 第12章 光応用技術 12.1 液晶ディスプレイ 12.2 ホログラフィ 12.3 干渉を利用した距離測定技術 12.4 屈折率分布の可視化技術 12.5 発光ダイオード 12.6 光造形法 12.7 リソグラフィ 参考文献 索引
この書籍は、小児科医の高橋孝雄が36年間の経験を基にした子育て論を紹介しています。すべての子どもは親から受け継いだ素晴らしい才能を持ち、親はその才能を温かく見守ることが重要だと説いています。各章では、子どもの個性や能力、子育ての悩み解消法、自己肯定感を育む方法、病気を通じて学んだことなどが取り上げられています。子育てに関する悩みを解消するための具体的なアドバイスが提供されています。