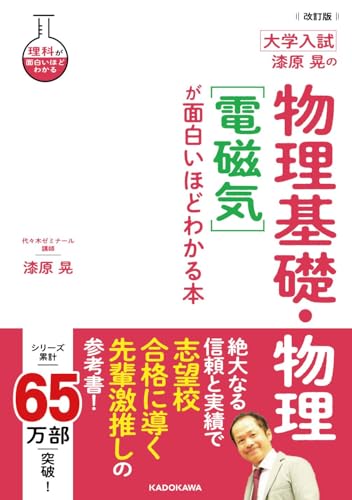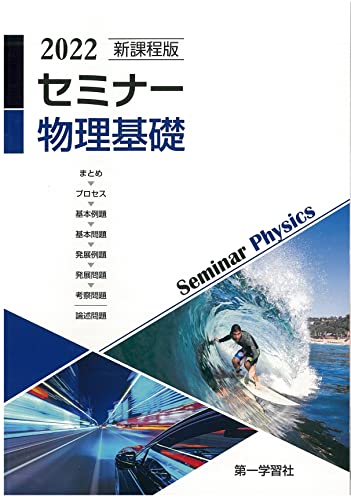【2025年】「物理」のおすすめ 本 178選!人気ランキング
- 橋元の物理基礎をはじめからていねいに (東進ブックス 大学受験 名人の授業)
- 名問の森 物理[力学・熱・波動I] (河合塾シリーズ)
- 良問の風物理頻出・標準入試問題集 (河合塾シリーズ)
- 橋元の物理をはじめからていねいに【改訂版】力学編 (東進ブックス 大学受験 名人の授業シリーズ)
- 物理のエッセンス 力学・波動 (河合塾シリーズ)
- 宇宙一わかりやすい高校物理 力学・波動
- 物理のエッセンス [力学・波動] 五訂版 (河合塾SERIES)
- 宇宙一わかりやすい高校物理 電磁気・熱・原子 改訂版
- 考える力学
- 秘伝の物理問題集[力学・熱・波動・電磁気・原子] (ひとりで学べる)
物理を得意科目にしたいあなたに! -さわやかに”分かる”から、あざやかに”解ける”へ-●物理を学習する上で最も基本となる「感覚的な理解」と、問題を解く上で大切な「考え方の流れ」が身につきます。●解法のノウハウや、公式の体系を目に見える形で満載。●イメージのつかみにくい「波動」では、特に図をふんだんに用い、波のいろいろな現象が視覚的に理解できるようにしました。 ●すべての例題と問題は、入試問題の詳しい分析に基づいて、最大の効果が得られるよう内容と構成に工夫をこらしたオリジナル問題です。
本書は2022年度以降入学の学生向けの新課程版物理参考書です。左ページにわかりやすい解説、右ページに図解があり、初学者でも学びやすい構成です。別冊の問題集や章末チェックで実力を確認でき、受験に必要な重要ポイントが網羅されています。ユルいキャラクターが描かれていますが、本格的な内容が詰まっており、楽しみながら物理を学べることを目的としています。
この書籍は、全国No.1の学校平均点を達成した教材を基にした問題集で、400ページにわたる丁寧な解説が特徴です。実力をつけるための問題を厳選し、著者によるYouTube解説動画も提供されています。生徒たちからの合格実績も多く、教育関係者にとって必携の一冊です。著者の青山均は公立中学校の教員を経て、サレジオ学院で物理を教え、学力向上に努めています。
●難問を避け、頻出・オーソドックスで、さらに応用のきく問題を154題収録●巻末に論述問題を系統的に取り扱い、物理の理解を深められる一冊●近年の入試問題も採り入れ、更なる充実を図っています
この参考書は、2007年の初版以来、わかりやすさが評価されており、新課程に対応した改訂版です。物理基礎と物理の「力学」と「熱力学」を学べ、教科書の弱点を克服した解説が特徴です。内容は「Story」「POINT」「チェック問題」「まとめ」の4つの構成で、物理現象のイメージや基本原理、解法を丁寧に解説しています。幅広い学習に対応し、国公立二次試験や私大入試対策にも役立ちます。
「難問題の系統とその解き方 物理」が新装第3版としてリニューアルされ、旧版を「力学,熱,波動 編」と「電磁気,原子 編」に分冊しました。内容はそのままにデザインを刷新し、読みやすく使いやすくなっています。受験生必携の書で、例題と93の演習問題を収録しています。各章は力学、熱、波動に分かれ、それぞれ要項、例題、演習問題が含まれています。
「難問題の系統とその解き方 物理」の新装第3版がリニューアルされ、旧版を「力学,熱,波動 編」と「電磁気,原子 編」に分冊。デザインが刷新され、読みやすく使いやすくなりました。内容はそのままに、例題と84の演習問題を通じて受験生に役立つ一冊です。各章は電磁気と原子に分かれ、要項、例題、演習問題が含まれています。
この書籍は、エネルギー、温度、熱力学、化学変化、量子論など、物理化学の基本的な概念を広範にカバーしています。主要なトピックには、気体の性質、熱力学の法則、相転移、化学平衡、化学反応速度論、原子構造、化学結合、分子間相互作用、統計熱力学などが含まれています。著者は千原秀昭、稲葉章、鈴木晴の3名で、いずれも大阪大学に関連する専門家です。
《新入試対応》 共通テストの出題形式を集中攻略! ◆特長◆ 掲載問題数: 98題(力学40題・熱11題・波動16題・電磁気23題・原子7題)+実験・考察問題7題 過去に出題された入試問題を精選し、大学受験基礎から共通テストレベルまでの実力を養うことができます(全問マークセンス方式に対応) 学習アドバイス: 幅広い知識が試される! 教科書の図や写真も要チェック! 考え方のポイントをたくさん押さえよう! 解ける問題を1つでも多く自分の味方に! ◆自分にあったレベルが選べる!◆ 1 基礎レベル 2 共通テストレベル 3 私大標準・国公立大レベル 4 私大上位・国公立大上位レベル 第1章 力学 1 等速直線運動 2 等加速度直線運動 3 落体の運動 4 力のつりあい 5 運動の法則 6 仕事と力学的エネルギー 7 慣性力 8 剛体のつりあい 9 運動量保存とはねかえり係数 10 等速円運動 11 単振動 12 万有引力による運動 第2章 熱 13 気体の状態変化 14 気体の内部エネルギー 15 熱力学第一法則 第3章 波動 16 屈折の法則 17 波の干渉 18 ドップラー効果 19 レンズ 20 光の屈折 21 ヤングの実験,回折格子 22 薄膜による光の干渉 23 くさび形空気層における光の干渉 第4章 電磁気 24 静電誘導,クーロンの法則 25 点電荷による電場・電位 26 コンデンサー 27 コンデンサーを含む回路 28 電気抵抗 29 直流回路,ブリッジ回路 30 非線形抵抗 31 電流による磁場 32 ローレンツ力 33 電磁誘導 34 交流回路 第5章 原子 35 トムソンの実験 36 光電効果 37 X線の発生 38 ボーア模型 39 放射性崩壊,半減期 40 核エネルギー 第6章 実験・考察問題
この書籍は2022年度以降に入学した学生向けの新課程版で、左ページに解説、右ページに図解があり、初学者にも理解しやすい構成です。別冊の問題集や章末のチェックで実力を試せる内容が特徴で、受験物理の重要な要素がしっかりまとめられています。著者は楽しみながら勉強できるよう工夫を凝らしており、物理の学習を楽しく進めることを目的としています。
この書籍は、力学の学習において問題練習が重要であることを強調し、初歩から高度な問題まで幅広く収録して解説しています。内容は運動の記述、質点の力学、質点系・剛体の力学、解析力学、相対論的力学の各章に分かれ、ベクトル、運動法則、剛体運動、Lagrangeの方程式、特殊相対論的力学など多岐にわたるテーマを扱っています。
物理を得意科目にしたいあなたに! -さわやかに”分かる”から、あざやかに”解ける”へ-●物理を学習する上で最も基本となる「感覚的な理解」と、問題を解く上で大切な「考え方の流れ」が身につきます。●解法のノウハウや、公式の体系を目に見える形で満載。●苦手な人が多いといわれる「熱」や「原子」では、身近なことがらを例にとって法則や学説を説明し、誰にでもわかるようにしました。●すべての例題と問題は、入試問題の詳しい分析に基づいて、最大の効果が得られるよう内容と構成に工夫をこらしたオリジナル問題です。
この参考書は、2007年の初版以来、わかりやすさで高評価を受けており、新課程に対応した改訂版です。『物理基礎』と『物理』の「波動」と「原子」分野を学べる内容で、教科書の弱点を克服し、疑問点を残さない解説が特徴です。各テーマは「Story」、「POINT」、「チェック問題」、「まとめ」の4部構成で、物理現象をイメージしやすく、基本原理を理解しやすいように工夫されています。問題も豊富で、解法を丁寧に教えることで自信を持って学習できるようになっています。
本書は、入試物理の問題を解く楽しさを提供するために、力学、熱、波動の各編から厳選した問題を収録しています。解答・解説では問題の重要度や考え方を詳述しており、理系の国公立大二次試験や私立大入試を受験する学生に最適です。
2007年に発行された参考書が新課程に対応した改訂版としてリニューアルされました。この本は、物理基礎と物理の「電気」と「磁気」分野を扱い、教科書の弱点を克服したわかりやすい解説が特徴です。内容は「Story」、「POINT」、「チェック問題」、「まとめ」の4部構成で、物理現象のイメージを伝え、基本原理を導き、解法を丁寧に教えます。日常学習から入試対策まで幅広く活用でき、効果的な学習法が提案されています。
出版社からの内容紹介では、物理に関する3つの教材が紹介されています。三訂版の「物理入門問題精講」、五訂版の「基礎問題精講」、七訂版の「標準問題精講」がそれぞれISBN番号と共に提供されています。
難関大学入試まで対応した受験生定番の受験対策問題集。今までの重要問題集のクオリティはそのままに,新課程に対応しました。入試問題から156題の良問を選び,最新の入試問題と入試傾向も反映。まずは標準的なA問題を解くことで頻出問題を学習し,B問題で応用力を養成できる。必ず解いて欲しい「必解」印を付けた問題は86題掲載。思考力・判断力・表現力を必要とする問題も「考察問題」として最終章に特集。QRコードからもヒントを参照できるようになりました。別冊解答では本冊以上のページ数で,詳しく丁寧な解説を掲載。さらに,小冊子「入試直前の最終確認」付き。
この文章は、物理学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、相対性原理や電磁波、重力場の方程式など、相対論や場の理論に関する重要なトピックが含まれています。著者は恒藤敏彦と広重徹で、どちらも京都大学理学部出身の著名な物理学者です。
運動・温度・圧力……こうした日常の諸現象を説明したのが古典力学である.今「ゆとり教育」の名目で,日常生活を科学の目で理解する営みが失われている.携帯電話ひとつとっても,もはや古典力学を越えた物理学に支えられているにもかかわらず.エネルギーの概念を軸に物理学の基礎を学び,科学のセンスを身につける,学生必携の一冊.実験をイメージし,理解を助ける動画CD-ROM付. 目 次 序 (1) ギリシャ自然哲学 (2) ニュートン前史 (3) ニュートン力学の誕生 月はなぜ落ちないか 第Ⅰ章 力、速度、加速度 (1)ベクトル (2)ベクトルのスカラー積(内積) (3)力のつり合い (4)速度、加速度 (5)円運動する粒子の速度、加速度 余談:ガリレオとベクトル 第Ⅱ章 ニュートンの運動法則 (1)運動の3法則 (2)慣性質量と重力質量 (3)重力下での物体の運動 (4)抵抗のある場合の運動 余談:ガリレオの運動論1 第Ⅲ章 種々の拘束のある運動 (1)拘束運動 (2)バネによる振動 (3)単振子の運動 余談:ガリレオの運動論2 余談:ガリレオの運動論3 第Ⅳ章 万有引力とクーロン力 (1)万有引力 (2)大きな球の質量中心 (3)クーロン力 トライアル:クーロン力の大きさ 余談:遠隔作用 デカルト vs. ニュートン 第Ⅴ章 仕事とエネルギー (1)仕事と運動エネルギー (2)保存力場 (3)位置エネルギー (4)場の勾配 余談:“エネルギー”のルーツ 第Ⅵ章 振動のエネルギー (1) 調和振動のエネルギー (2) 抵抗のある場合 (3) 振動エネルギーの伝播 余談:光の波動説と粒子説 ホイヘンス vs. ニュートン 第Ⅶ章 角運動量保存則 (1)ベクトル積 (2)角運動量 (3)楕円軌道 (4)決定論的世界観とそれからの離脱 余談:レ・メカニケ 余談:ニュートンの面積速度 第Ⅷ章 静電場 (1)電場の重ね合わせ (2)ガウスの法則 (3)静電ポテンシャル (4)金属導体の性質 余談:キャヴェンディッシュの実験 余談:アース 第Ⅸ章 場のエネルギー (1)平板コンデンサーに蓄積されるエネルギー (2)原子核のエネルギー (3)静電応力 余談:核分裂 第Ⅹ章 電流、電力エネルギー (1)オーム法則 (2)電力エネルギー 余談:電源と回路 余談:超伝導 第ⅩⅠ章 運動量保存、衝突 (1)ガリレイ変換と運動量保存則 (2)重心系 (3)衝突 余談:ホイヘンスの衝突理論 第ⅩⅡ章 気体の圧力と温度 (1)気体の圧力 (2)気体の温度 (3)速度と密度の分布 余談:熱の仕事当量 余談:第1種の永久機関 第ⅩⅢ章 熱力学法則とエントロピー (1)熱エネルギー、熱力学第一法則 (2)断熱変化と等温変化 (3)不可逆過程 (4)エントロピー エピローグ Appendix (1) 簡単な関数の微分と積分 (2) 三角関数の微分、積分 (3) 物体の斜面落下に関するガリレオの展開 (4) 振子の周期 (5) 惑星の軌道半径と公転周期
本書は、相対性理論と並ぶ現代物理学の重要な柱である量子論を初心者向けにわかりやすく解説しています。図やイラストを多用し、量子論の基本的な概念や歴史、解釈問題について触れ、最先端の物理学の世界を手軽に理解できるようにしています。
固体物理学の入門的なテキスト。量子力学、統計力学などの基礎から半導体などの応用までを丁寧に解説。異分野の方にもお薦めです。 順を追ったていねいな解説により、全体を通して学生1人でも読み進められるようなつくりを心がけました。また例題や演習問題によりさらに理解を深めることができます。固体物理学の基本概念が深くわかる1冊で、はじめての本として最適です。この本を読んだ後に『キッテル 固体物理学入門』や、さらに難易度の高い教科書へ進むと、より理解が深まるはずです。学生だけではなく、異分野の研究者にも自信を持ってお薦めします。 本書は固体物理学の入門的な教科書です。 B5版2色刷りとし、わかりやすさと同時に見やすさも追求しました。 はじめて固体物理学を学ぶ人が、その基本から学べるように 「第4章 量子力学の基礎」「第5章 統計力学の基礎」では 固体物理学の前提となる基本原理を解説しています。 また、「第12章 固体の光学的性質」の前半でも 電磁気学の基礎について解説をしています。 順を追ったていねいな解説により、全体を通して 学生1人でも読み進められるようなつくりを心がけました。 また例題や演習問題によりさらに理解を深めることができます。 固体物理学の基本概念が深くわかる1冊で、はじめての本として最適です。 この本を読んだ後に『キッテル 固体物理学入門』や、さらに難易度の高い 教科書へ進むと、より理解が深まるはずです。 学生だけではなく、異分野の研究者にも自信を持ってお薦めします。 第1章 序章―固体物理学では何を学ぶのか 第2章 結晶構造 2.1 結晶とは 2.2 格子 2.3 結晶構造の具体例 2.4 ミラー指数 第3章 逆格子 3.1 逆格子空間 3.2 逆格子ベクトル 3.3 結晶による回折 第4章 量子力学の基礎 4.1 粒子と波の二重性 4.2 演算子,固有値・固有関数 4.3 シュレーディンガー方程式 4.4 物理量の期待値 4.5 不確定性原理 4.6 無限に深い1次元の井戸型ポテンシャル 4.7 角運動量 4.8 水素原子の電子状態 4.9 多電子原子の電子状態 4.10 調和振動子 第5章 統計力学の基礎 5.1 フェルミ粒子とボース粒子 5.2 グランドカノニカル分布 5.3 フェルミ分布 5.4 ボース分布 第6章 固体における結合 6.1 結合エネルギー 6.2 共有結合 6.3 イオン結合 6.4 金属結合 6.5 ファン・デル・ワールス結合 6.6 結合の概念図 第7章 格子振動とフォノン 7.1 1種類の原子からなる1次元の格子振動 7.2 2種類の原子からなる1次元の格子振動 7.3 音響モード,光学モード 7.4 3次元の格子振動 7.5 フォノン:格子振動の量子化 第8章 固体の熱的性質 8.1 固体の比熱 8.2 固体の熱伝導 第9章 自由電子論 9.1 自由電子モデル 9.2 状態密度,電子のエネルギー分布 第10章 バンド理論 10.1 バンドについての概説 10.2 1電子シュレーディンガー方程式 10.3 ブロッホの定理 10.4 ほとんど自由な電子モデルによるバンド理論の導出 10.5 強結合近似によるバンド理論の導出 第11章 固体中の電気伝導 第12章 固体の光学的性質 第13章 固体の磁気的性質 第14章 半導体 第15章 超伝導
この書籍は、学校で苦しんでいる学生に向けて、人生を諦めずに未来を切り開く方法を提案しています。著者は、不登校や中退、ひきこもりの経験を持つ若者たちを10年以上サポートしてきた専門家で、大学受験が人生を変えるチャンスであると強調しています。具体的な勉強法や心構えを紹介し、自分に合った環境を見つける重要性を説いています。目次には、不登校の乗り越え方や社会で生きるための知識も含まれています。
この書籍は、1900年にM・プランクが「量子」という概念を考案したことから始まり、量子力学の発展と、それに伴う物理学の変革を描いたノンフィクションです。アインシュタインとボーアの論争を中心に、ハイゼンベルク、ド・ブロイ、シュレーディンガーなどの物理学者の人間ドラマも交えながら、物理学の100年の歴史を追います。著者はマンジット・クマールで、翻訳は青木薫が担当しています。
本書は、全ページ漫画形式で物理の基本を学べる画期的な学習漫画です。物理知識がゼロの人でも理解しやすく、数式や難しい解説はなく、視覚的に楽しみながら学べます。著者のネコザメタカシさんは、物理の面白さを再発見した経験をもとに、読者が物理を楽しめるように工夫しています。中学・高校の物理を学び直したい人や、物理に苦手意識を持つ人に最適な一冊です。巻末にはオリジナルの周期表が付いています。
固体物理学は、その学問自体として発展するとともに、現代のエレクトロニクスや素材産業などの工学分野の研究の基礎となっている。他方、固体物理学はトランジスターの発見をきっかけに隆盛し、また大規模集積回路に用いられるMOS反転層を舞台に量子ホール効果が観測されるなど、工学と固体物理学は相互に密接に影響を与えながら発展してきた。 著者は東京大学物性研究所で理学としての固体物理学を研究し、その後同大学工学部で工学としての固体物理学を研究・教育してきた。この経験を活かし、理学と工学の接点に立って、固体物理学の基礎教科書としてまとめたものが本書である。 姉妹書の『基礎演習シリーズ 固体物理学』(ISBN 978-4-7853-8104-2)との併用により、一層の理解の助けとなろう。 1.物質の存在形態 基礎事項 1.1 結晶 1.2 アモルファス 1.3 準結晶 1.4 典型的な結晶構造 1.5 結合力 例題/演習問題/問題解答 2.物質の構造解析 基礎事項 2.1 X線回折 2.2 結晶面の指数 2.3 ブラッグの回折条件 2.4 ラウエの回折条件 2.5 逆格子空間 2.6 第一ブリルアンゾーン 2.7 ブロッホの定理 例題/演習問題/問題解答 3.格子波-フォノン 基礎事項 3.1 格子波の分類 3.2 フォノン 3.3 格子波の関与する現象 (格子比熱,デバイ-ワラー因子,フォノンポラリトン) 例題/演習問題/問題解答 4.ブロッホ電子-エネルギーバンド 基礎事項 4.1 自由電子モデル 4.2 ブロッホ関数 4.3 ボルン-フォン・カルマンの周期的境界条件 4.4 空格子のバンド構造 4.5 OPW(直行平面波法) 4.6 金属と絶縁体 4.7 モット絶縁体 例題/演習問題/問題解答 5.金属と半導体 基礎事項 5.1 金属の電子比熱 5.2 結晶の比熱 5.3 半導体 5.4 正孔 5.5 ドナーとアクセプター 5.6 金属の電気伝導度 5.7 半導体の電気伝導度とホール係数 5.8 半導体デバイス 例題/演習問題/問題解答 6.光学的性質 基礎事項 6.1 光学定数 6.2 誘電関数 6.3 クラマース-クローニヒの関係式 6.4 振動子強度の総和則 6.5 バンド間遷移 6.6 エクシトン 6.7 プラズモン 例題/演習問題/問題解答 7.超伝導 基礎事項 7.1 超伝導4つの実験事実 7.2 二電子間引力ポテンシャル 7.3 正常金属の不安定性 7.4 エネルギーギャップの形成 7.5 同位体元素効果 7.6 マイスナー効果 7.7 第一種・第二種超伝導体 例題/演習問題/問題解答 8.磁性 基礎事項 8.1 磁性の起源 8.2 フントの規則 8.3 スピン-軌道相互作用 8.4 多重項の記述 8.5 ヴァン・ブレックの常磁性 8.6 パウリの常磁性(金属) 8.7 ランダウの反磁性(金属) 8.8 断熱消磁による冷却 8.9 磁気共鳴 8.10 強磁性 8.11 スピン間の相互作用 例題/演習問題/問題解答
効率よく,35日で進める共通テスト対策問題集。 頻出の重要30項目に取り組んだ後,「巻末演習」5項目で,改めて,共通テスト特有の問題形式の確認ができる!例題→演習問題で1項目が構成され,例題の解答・解説中にある「CHART」では,項目ごとの重要事項や問題を解く際のポイントがまとめられている。また,CHARTや見返しで扱った公式・重要事項を確認できるコンテンツをアプリ「数研Library」でも無料配信! 隙間時間を使って手軽に基本固めができる。短期間で共通テスト対策を行いたい人にオススメ。 第1章力と運動・熱 斜方投射 剛体 運動量 等速円運動 慣性力 単振動 万有引力 気体の状態変化① 気体の状態変化② 小問集合① 第2章波 波の伝わり方 音の干渉 ドップラー効果 光の性質 レンズ 光の干渉① 光の干渉② 小問集合② 第3章電気と磁気 電場と電位 コンデンサー① コンデンサー② 電気回路① 電気回路② ローレンツ力 電磁誘導 交流回路 小問集合③ 第4章原子 電子と光 原子と原子核 小問集合④ 第5章巻末演習 グラフ・図の読み取り 資料の読み取り 考察問題 読解問題①(会話文) 読解問題②(長文)
1848年、米国での事故により、現場監督P・ゲージの性格が変わった。この事例を通じて、著者アントニオ・ダマシオは、合理的な意思決定が身体状態と結びついた情動や感情の影響を受けることを示す「ソマティック・マーカー仮説」を提唱。彼は心身二元論を批判し、心、脳、身体の関係を探求する。新訳文庫版で、著者の経歴も紹介されている。
不安が自信に変わる! 正答への最短ルートがこの1冊に! 本書は、「共通テスト」で必要な基礎力と実戦力を「11」のテーマで効果的に学ぶことができます。 本書のゴールは、高校物理を体系的に学ぶことではなく、共通テスト物理で高得点を取ることです! その目的を達するために本書で取り上げたのは、以下の3つです。 ① 重要であり、他単元・分野にも関連する ② 習得してしまえば、他単元は自習が可能 ③ 受験生が苦手にしがち この3つの基準に該当する単元を、全分野で取り上げました。 たとえば、力学。本書は11の「講」で構成されていますが、第1講は力に関する講です。ここでの理解は力学全般に影響が大きく、また電磁気や熱力学にも関連が強いです。 第2講は力のモーメント。受験生が苦手にしがちな単元です。第3~5講は運動している物体に関する講です。この先の講で力学の学習を続けても、他の解法は存在しません。それはなぜか? 第5講までを学習すれば、 問題を解くためのアイテムが8割方そろうので、その後は、これら式の組み合わせですべての問題が解けてしまう からです。 万有引力で新しい話題が出てきたり、円運動では式の見た目の形が少々異なったりしますが、考え方は変わりません。つまり、最初にぶれることのない 太い幹を習得し、その後は枝葉を足していくのです。 繰り返しになりますが、本書は、高得点を獲得するために何が必要かに、とことん絞って構成されています。 ●本書の構成 【1】 「ここが大切!」 各テーマで必須の知識を確認しましょう。 山縣先生が、必要なことだけをコンパクト&わかりやすくまとめてくれました。「練習問題」「実戦問題」を解くための準備を調えることできます。 【2】 「練習問題」 「共通テスト」的な問題の切り口をおさえましょう。 「こう解く!」で、解き方、考え方の確認をしましょう。 また、文末の「解法ポイント」では、ミスなく、効率よく解くための山縣先生直伝の解法テクニックを掲載しました。 じっくり読みこんでください。 【3】 「実戦問題」 解くための力が身についているかの確認を行います。自力で解いた後には、「こう解く!」で考え方、解き方のチェックをしましょう。以上のサイクルを繰り返すことで、「共通テスト 物理」の対策はバッチリです! 第1講 力のつり合い 第2講 力のモーメント 第3講 運動方程式 第4講 仕事・エネルギー 第5講 力積・運動量 第6講 熱力学 第7講 波 動 第8講 直流回路 第9講 コンデンサー 第10講 電磁誘導 第11講 光電効果
◎オリジナル模試と過去問の演習で総仕上げ! Z会オリジナル模試(5回分)に加え、2022年度本試験・追試験、2021年度本試験(第1日程・第2日程)を掲載しています。オリジナル模試で実戦力を養成したあとは、本試験、追試験の過去問を用いて実力を確認することができます。 ◎情報収集で万全の準備を 共通テストを乗り切るには、早めに基礎を固めることが第一。とはいえできるだけ効率よく学習を進めるために、出題傾向を把握し、適切な学習計画を立てることも大切です。本書は過去問や試行調査をもとに新傾向に対応した問題を掲載しているので、共通テストへの準備に役立ちます。 ◎復習に役立つ丁寧な解答・解説 実戦的な演習のあとは、しっかり復習することが何よりも大切。本書では、解答に丁寧な解説がほどこされています。共通テストを突破するために必要な重要事項が書かれていますので、必ず確認しましょう。単なる答え合わせにとどまらず、解答にいたる道筋を理解して、確実に実力を固めることができます。
出題傾向と対策を徹底分析! 大学入学共通テストに精通したスタッフが作成するオリジナル予想問題集 出題傾向と対策を徹底分析! 大学入学共通テストに精通したスタッフが作成するオリジナル予想問題集。 大学入学共通テストの出題傾向と対策に精通した代ゼミスタッフが作成する共通テストオリジナル予想問題をはじめ、出題分析や学習アドバイスも収録。 ■予想問題5回収録(代々木ゼミナール主催の共通テスト系模擬試験などから良問を厳選) ■2022共通テスト本試験問題・解答解説も収録 ■本番に準拠したマークシート解答用紙添付
実験考察・データの読み取り 問題文から物理現象を見抜く洞察力をみがく! 実験考察・データの読み取り 問題文から物理現象を見抜く洞察力をみがく! 実験考察・データの読み取り 問題文から物理現象を見抜く洞察力をみがく!
共通テストと同じ形式・傾向のオリジナル問題5回分を収録!東進の講師陣によるどこよりも詳しい解説で傾向と対策がよくわかる!QRコードからワンポイント解説動画を見ることができる!
「化学なのに何の困果で物理まで…」と今日も学生の嘆き節。教科書は無愛想で勉強する気も雲散霧消。そんなあなたにぴったりの一冊! 試験まで時間がないあなたに最適の一冊。「化学なのに、何の困果で物理まで…」と今日も大学生の嘆き節。その上、教科書は分厚く無愛想で、勉強する気も雲散霧消。そんなあなたにぴったりの一冊 まえがき 講義01 気体の性質 講義02 熱力学第1法則 講義03 エンタルピー 講義04 化学反応とエンタルピー 講義05 エントロピーと熱力学第2法則 講義06 自由エネルギー 講義07 化学ポテンシャル 講義08 化学平衡 講義09 相平衡 講義10 多成分系の相平衡 講義11 溶液の性質 講義12 電気化学 講義13 反応速度 付録 偏微分と全微分
◎本番直前の最終チェックに! 共通テストの出題形式・設問パターンを分析したZ会オリジナル問題を収録。共通テストの準備の総仕上げとしてご利用ください。 ◎「学習診断」で平均点やライバルとの差を確認! 所定のサイトに自己採点結果を入力すると、自分の得点と、Z会想定平均点やライバルの点数との比較ができます。さらに、Z会編集部から直前対策のアドバイスメッセージが届きます。
この書籍は、生命の本質について分子生物学がどのように答えているかを探求し、歴史的な科学者たちの思考を紹介しながら、現代の生命観を明らかにします。著者の福岡伸一は、分子生物学の成果を平易に解説し、読者の視点を変える内容を提供しています。多くの著名人から高く評価され、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞しています。
入試対策最初の一歩。スタディサプリの名物講師が実力を引き上げてくれる スタディサプリで基礎から応用まで講座を担当している中野先生による, 物理に悩める受験生だけでなく,物理を学習した全員に向けて, 入試レベルの問題の解き方を身につけてもらう「取扱説明書」を執筆しました。 本書は,各節が基本事項→基本問題→実践問題の形になっています。 ・基本事項では,なるべく詳しく説明し,一通り読むだけでも身につく入試物理で必要な知識を掲載しました。 ・基本問題では,物理用語や公式の使い方を確認し,実戦問題を解く際のヒントにもなっています。 ・実践問題では,多くの入試頻出テーマをカバーできるように,実際の入試問題から厳選しました。 基礎的なものからややハイレベルな問題まで入っていますが,この1冊で入試に十分通用する実力が身につきますので, 問題をどんどん解きまくってください! 物理の問題には,いつもよく使う決まった知識・手順があります。 (1) 何を「覚える」べきなのか。 (2) 覚えた知識を「どのように使えば」よいのか (3) 更なる成長のためには「何をすれば」よいのか 本書では上の3つを意識して学習できるようにしましょう。 そして,最後に1つ,物理の学習上めちゃくちゃ大事なことをいいます! 「必ず常に紙とペンを脇に置きながら,自分で式変形したり,実際に計算して,必ず手を動かしましょう!」 いちおう学校では習ったけど、入試対策なんて何も考えていないよ……というビギナーのキミに使ってもらいたい。入試で問われる基本事項と解き方を1冊に集約。「物理基礎」と「物理」が1冊で学べるお得すぎる本。 第1章 力学 第2章 熱力学 第3章 波動 第4章 電磁気 第5章 原子
●試行調査問題と公式発表資料をもとにした詳細な分析 まず最初に,「高大接続改革」と「大学入試の変革」についての情報を読み解き,「センター入試」が「共通テスト」と変わることで,出題や評価の仕方がどのように変化するのかをつかみましょう。 ●大学入学共通テスト試行問題をそのままのレイアウトで掲載 平成30年に行われた試行調査問題を詳しく解説した上で,傾向と対策を詳説しています。実際の試行調査問題も掲載していますから,併せてしっかりと読み,「共通テスト」がどのような構成になっているのかを理解しましょう。 ●本番を想定したオリジナル問題を1回分掲載 試行調査を徹底分析した模擬問題も掲載しています。実施時間を測り,試験形式で演習してみましょう。本番の共通テストと同様に,「自己採点」まで確実にできるようにしましょう。 ●わかりやすく丁寧な全問解説 得点力を上げていくためには,誤答箇所について確実にできるようにすることが最も効果的です。自己採点の後は,特に誤答箇所について解説をよく読み,その後の学習の指針としてください。
この教科書は学部学生向けの量子力学入門書で、前期量子論を簡略化し、解析力学の基礎を省略しています。各章には例題と演習問題があり、自習を促進する工夫がされています。内容は量子論の誕生から始まり、シュレーディンガー方程式、1次元量子系、量子力学の基本性質、中心力場のシュレーディンガー方程式などを網羅しています。また、詳しい解答解説も付いています。
出題傾向と対策を徹底分析! 大学入学共通テストに精通したスタッフが作成するオリジナル予想問題集 出題傾向と対策を徹底分析! 大学入学共通テスト本試験や試行調査、過去の大学入試センター試験の出題傾向と対策に精通した代ゼミスタッフが作成する共通テスト向けオリジナル予想問題をはじめ、本試験問題をもとにした分析や学習アドバイスも収録 ■2021共通テスト本試験[第1日程]問題・解答解説も収録 ■本番に準拠したマークシート解答用紙添付 ※物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎の4科目をこの1冊に収録 ※本書以外に2科目を抜粋編集した『2022大学入学共通テスト実戦問題集化学基礎+生物基礎』、『2022大学入学共通テスト実戦問題集生物基礎+地学基礎』があります
量子力学・統計力学の初歩を前提に固体物理学の基礎事項を丁寧に解説した、学部学生〜院生向きテキスト・参考書である。最近の研究成果の中から本書のレベルにふさわしい教材として、例えばグラファイトシートやカーボンナノチューブを取り上げている点や、絶縁体・半導体を「金属化」という観点を強調して解説している点など、オーソドックスな構成の中にも新鮮な内容が盛り込まれている。また、分かりやすさという点で、特に数式を抑えることはせず、むしろ式が意味する物理的内容を十分理解できることに意を尽くしている。固体一般の性質を一通り説明したのち、半導体、磁性、超伝導までの内容を、最新の知見をふまえ、またレベルを逸脱することなく、丁寧に解説している。 原子の中の電子 原子が集まってつくる固体 格子振動 自由電子モデル 結晶中の電子の状態 エネルギー・バンドから見た金属、絶縁体の区別 金属の伝導電子-その役割と実験的証拠 伝導電子の輸送現象-電流と熱流 半導体、絶縁体とキャリヤーの制御 固体の光学的性質 固体の磁性 超伝導
本書は、電磁気学の法則と数学表現に悩む初学者のために、各法則の物理的意味と相互関係をわかりやすく解説しています。高校数学を基に計算過程を詳細に示し、数学に煩わされずに理解できるよう配慮されています。内容は大学初年級向けで、静電場から電磁波までの各章が含まれています。
この50題で入試物理[物理基礎・物理]に必要な基礎力を強化する問題集 大学入試物理[物理基礎・物理]に向けて,まずは身につけておくべき考え方と解き方を習得できる問題集です。 入試頻出テーマを最小限の問題数で効率よく理解することで、合格への道筋「ゴールデンルート」が開けます。 【掲載問題】 入試に最低限必要な基礎力を固めるための50題をセレクトしました。 最後まで挫折せずに終えられることができるように,ヒントの形で要点がつかめる工夫をしています。 【合格へのゴールデンルート:GR】 問題を解くときにポイントになることが書かれています。 解答や解き方が思い浮かばなかったら,GRにある空欄を埋めてみましょう。 物理現象や公式・原理など,忘れていた事項がきちんと定着できます。 【解答への道しるべ】 GRで提示された内容について端的にまとめています。 基礎レベルだからこそ,身につけておくべき重要事項ばかりなので,きちんと理解しておきましょう。 【解答・解説】 問題の着眼点,考え方・解き方だけでなく,受験生がつまずきやすい急所をくわしく解説しました。 「解答への道しるべ」に書かれている内容を踏まえた解答はオーソドックスなものばかりなので,基礎力がしっかり固まります。 本書は,教科書の節末問題・章末問題や傍用問題集で,どう解いたらよいかが身についていない人,他の問題集でどう解いたらよいか困っている受験生や学習した内容と問題とのギャップを感じている受験生に最適な問題集です。 また,苦手な分野やテーマを見つけ出すのにもちょうどいい問題集なので,解けなかった問題には再度チャレンジしてみてください。 初めて入試問題に取り組む受験生のための問題集。この50題で入試に最低限必要なことを学習します。問題を解くための基礎知識や着眼点を丁寧に解説しますので、考え方や解き方が自然と身につきます。 CHAPTER 1 力学 CHAPTER 2 波動 CHAPTER 3 熱 CHAPTER 4 電磁気 CHAPTER 5 原子
この書籍は、マックスウェルの悪魔をテーマに、タイムマシンや永久機関の実現を通じてエントロピーの概念を解説しています。著者は、物理学の知識を活かし、エントロピーが時間の向きを決める仕組みを面白くわかりやすく説明し、人類の未来における悪魔の役割を考察しています。電子書籍は画像形式で提供され、タブレットでの閲読が推奨されています。
一流の執筆陣が妥協を排し世に送った至高の教科書。練り上げられた問題と丁寧な解答は知的刺激に溢れ、力学の醍醐味を存分に味わうことができる。 一流の執筆陣が妥協を排し世に送った至高の教科書。練り上げられた問題と丁寧な解答は知的刺激に溢れ、力学の醍醐味を存分に味わうことができる。 === 「力学の原理に差はないのだから,教養課程の学生が専門課程に相当する部分まで進んでいけない理由はない.進めるだけ進め,少なくとも道は開いているほうがよい,行く先で解けるようになる面白い問題に展望があるほうがよい」(「はじめに」より)。本書で提供される問題は、机上で考えられたものだけではなく、実際の自然現象に即して創られたものも多く含まれる。それらは難解な問題もあるが、話題は広く、古典力学の豊かさを余すところなく示している。経験豊富な執筆陣が、一切の妥協を排して世に送った類書のない力学演習書。練り上げられた刺激的な問題と詳細な解説で、力学の高みへといざなう。 === 力学の高みへといざなう 類書のない力学演習書 === 【目次】 増補・改訂版を贈る はじめに 文庫版出版によせて 第1章 運動学 第2章 質点の力学 第3章 非線形振動 第4章 動く座標系 第5章 質点系の力学 第6章 剛体の力学 第7章 重力の起こす運動 第8章 電磁場における運動 付録 索引 増補・改訂版を贈る はじめに 文庫版出版によせて 第1章 運動学 第2章 質点の力学 第3章 非線形振動 第4章 動く座標系 第5章 質点系の力学 第6章 剛体の力学 第7章 重力の起こす運動 第8章 電磁場における運動 付録 索引
マサチューセッツ工科大学のウォルター・ルーウィン教授による物理学入門の授業が、YouTubeやiTunes Uで無料公開され、多くの人々に人気を博しています。教授はエネルギー保存の法則を実演し、物理学の美しさを伝えることに重点を置いています。授業では、虹の色の順番やビッグバンの音、宇宙の謎など、様々な物理現象について探求しています。NHKでもシリーズとして放映されています。
本書は、解析力学を素直な方法で解説し、難解な概念を明確に説明しています。内容には、ニュートン形式、配位空間、ラグランジアン、共変性、対称性、ハミルトニアンなど、多岐にわたるトピックが含まれ、特に他書では見られないCaratheodory-Jacobi-Lieの定理についても触れています。著者は井田大輔で、学習院大学の教授です。
この書籍は、次世代の物理学徒向けに量子力学を再構成したもので、15章から成り立っています。内容は、隠れた変数理論から始まり、量子状態、量子測定、量子情報物理学など幅広いテーマを扱っています。学部生から専門家まで必読の一冊です。
本書は難関大学を目指す人のための演習書です。受験指導で圧倒的な人気と信頼を得ている著者が、国公立大2次・私立大の入試問題を徹底的に分析し、難関大学の入試で合否の分かれ目になる問題を厳選して、それらを解くためにはどのように学習したらよいのかを示しながら丁寧に解説しました(解説編272ページ)。したがって、基本的な学習を終了した上で本書にチャレンジすれば、大きな効果が得られます。
この文章は、重力の不思議な性質とその宇宙における重要性について述べています。重力は生命や星の形成に不可欠で、その研究はニュートンやアインシュタインの理論を経て現在の第三の黄金期を迎えています。内容は、特殊相対論や一般相対論、ブラックホール、量子力学、超弦理論など多岐にわたり、重力の謎を解明する冒険が描かれています。著者は大栗博司で、素粒子論や超弦理論の専門家です。
本書は、ノーベル賞受賞の「特異点定理」を一般向けに解説し、一般相対性理論における特異点の必然性とその影響を探る。特異点では物理法則が破綻し、ペンローズが提唱した「宇宙検閲官仮説」によって、裸の特異点がブラックホールに覆われる可能性がある。この仮説の検証を通じて最新の宇宙理論が生まれる過程を描き、特異点に関する物理学者たちの研究の最前線を紹介する。著者は一般相対性理論や重力理論の専門家、真貝寿明教授。
上級クラスの固体物理学に現れる諸概念を、総合的・包括的に解説した教科書。固体における電子系の量子力学的な扱い方の基礎を紹介してから、近藤問題、ボゾン化、金属超伝導、電子の局在、量子相転移、トポロジカル状態、強相関電子系などの具体的な諸問題を詳しく論じる。 緒論 相互作用のない電子気体 Born‐Oppenheimer近似 第2量子化 Hartree‐Fock近似 相互作用のある電子気体 金属中の局在磁気能率 局在磁気能率の抑制:近藤問題 遮蔽とプラズマ振動 ボゾン化〔ほか〕
この書籍は、ラグランジアンと最小作用の原理から始まり、対称性、保存則、拘束のある系などの物理学の基礎概念を扱っています。また、ハミルトン形式や正準変換、ハミルトン-ヤコビ理論、微分形式を用いた記述、さらには場の理論や古典力学から量子力学への移行についても論じています。著者は京都大学の畑浩之教授です。
難関大学入試まで対応した受験生定番の受験対策問題集。 入試問題から156題の良問を選び,最新の入試問題と入試傾向を反映。まずは標準的なA問題を解くことで頻出問題を学習し,余力があればB問題で応用力を養成できる。必ず解いて欲しい「必解」印を付けた問題は85題掲載。近年話題の思考力・判断力・表現力を必要とする問題も「考察問題」として最終章で特集。別冊解答は本冊以上の168ページで,詳しく丁寧な解説を掲載。別冊解答に掲載の「ヒント!」は解説の前に読むことで問題の解き方が身につく。さらに,小冊子「入試直前の最終確認」付き。