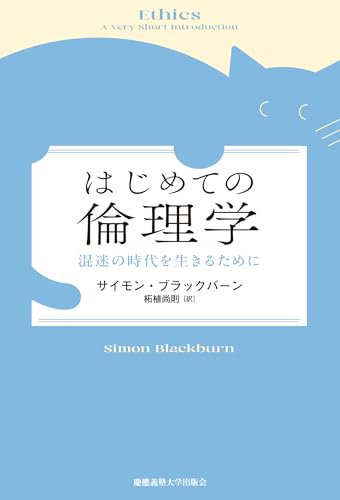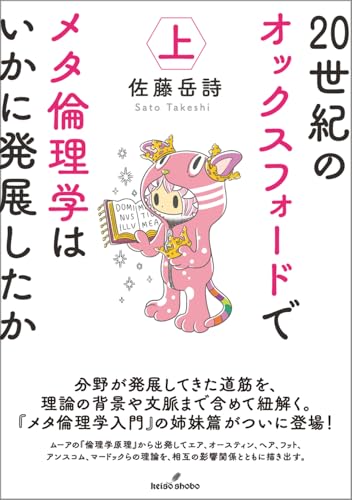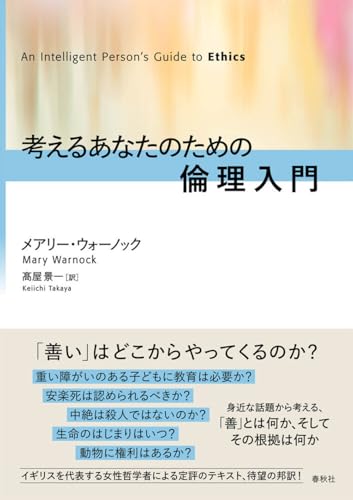【2025年】「功利主義」のおすすめ 本 120選!人気ランキング
- 功利主義入門: はじめての倫理学 (ちくま新書 967)
- これからの「正義」の話をしよう (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)
- 入門・倫理学
- ベンサム―功利主義入門
- ニコマコス倫理学(アリストテレス) 上 (岩波文庫 青 604-1)
- 実践・倫理学 (けいそうブックス)
- 倫理思考トレーニング (ちくま新書 1875)
- 倫理学入門-アリストテレスから生殖技術、AIまで (中公新書 2598)
- 動物からの倫理学入門
- マンガで学ぶ生命倫理
本書は倫理学を「倫理について批判的に考える学問」と位置づけ、特に「功利主義」に焦点を当てています。倫理学の意義や実用性を示し、社会の常識やルールを再考する技術を提供します。内容は、功利主義の基本からその批判、公共政策への応用、幸福の概念、道徳心理学との関連まで幅広く探求しています。著者は東京大学の専任講師で、倫理学と政治哲学を専門とし、現代の生命倫理についても考察しています。
『入門・医療倫理』から倫理理論に関する章を抜粋し再編集した入門テキスト。倫理学の基礎、規範倫理学、メタ倫理学、政治哲学を体系的に学べる内容で、英米系倫理学理論をわかりやすく解説。倫理学を初めて学ぶ学生に最適な一冊。著者は東京大学と京都大学の教授陣。
ジェレミー・ベンサムの本格的入門書。快楽と苦痛の原理による立法の科学を構想し共同体の幸福を目指した思想家の全貌を平易に解説。 功利主義の創始者、ジェレミー・ベンサムの本格的入門書。快楽と苦痛が基礎づける原理(功利原理)による立法の科学を構想し、共同体の幸福=「最大多数の最大幸福」を目指した思想家の全貌を平易に解説。 “苦痛と快楽が人間の心理学と倫理学の両方にとっての基礎となっているという主張や、幸福とは快楽が苦痛を上回っている状態であるという主張を現代科学が論証しているとしたら、ベンサムや彼が創りだした功利主義的伝統は、20世紀の批判者たちの多くが認めてもよいと考えていた以上に、はるかに予見的なものであったということになるでしょう。”――本書「日本語版への序文」より 現代のさまざまな分野に、実践・理論の両面で大きな影響を及ぼしているジェレミー・ベンサム(1748-1832)。本書は、彼の厖大な草稿類を整理・校訂するベンサム・プロジェクトを牽引し、新著作集の編集主幹をつとめる、「世界一ベンサムを知る」著者による本格的な入門書である。苦痛と快楽が基礎づける原理(功利性の原理)による立法の科学を構想し、共同体の幸福=「最大多数の最大幸福」を目指したこの思想家の全貌を平易に解説し、従来触れられてこなかった宗教と性、拷問に関する理論に言及するなど、最新の研究成果をもとに彼の功利主義思想を体系的に論じる。 詳細な読書案内とともに、ジョン・ロールズ『正義論』(1971)における功利主義批判以降のベンサム研究の動向を論じる訳者解説(小畑俊太郎執筆)を付した、新しい功利主義入門。 日本語版への序文 謝辞 第一章 ベンサムとは誰か 生まれ、家族、教育 法学 民主主義への移行 「世界の立法者」 ベンサムの功績と意義 第二章 どのベンサムか 誰が何を読むのか ジェレミー・ベンサム著作集 テクストを作り出す エティエンヌ・デュモン―編集者であり解釈者 キャノンを構成する 『法一般論』の再編集 新著作集の利点 第三章 功利性の原理 功利性 論理学と言語 ベンサムの心理学理論に対する批判 ベンサムの倫理学理論に対する批判 功利主義対直観主義 第四章 パノプティコン パノプティコンの考案者 パノプティコン書簡 パノプティコン補遺 救貧パノプティコン 救貧パノプティコンの放棄 監獄型パノプティ コンの放棄 第五章 政治的誤謬 誤謬とは何か 誤謬の源泉 錯誤 誤謬の事例 現代における 誤謬 結論 第六章 宗教と性 ジョン・バウリングとグロート夫妻 宇宙の設計者 人格同一性の問 題 永遠の生命と非存在 イエスの啓示宗教 イエスの真の目的 禁欲主義とイエスのセクシュアリティ ベンサムのメッセージ 第七章 拷問 拷問控訴 権力分立論 ベンサムの証拠排除論 キツネ狩猟者の誤 謬 単座制 ベンサムによる拷問の正当化 自由と安全 死後に 有効となる追記 註 読書案内 訳者解説 訳者あとがき 索引 著者・訳者紹介
この文章は、古代ギリシアにおける倫理学の名著について紹介しています。著者は「幸福」を人生の究極の目的とし、その概念を詳細に分析しています。この考えは当時の市民に向けられ、ルネサンス以降の西洋思想や人間形成に大きな影響を与えました。目次では、善の追求、政治的活動の重要性、幸福の本質、習慣づけの役割などが論じられています。幸福は快楽や名誉、富とは異なるものであり、学習や習慣づけを通じて獲得されるとされています。
意見のすれ違う人と話し合うのは不毛か。「論破」したら勝ち、でいいのか。生産的議論のためのクリティカル・ディスカッション入門。 意見のすれ違う人と話し合うのは不毛か。「論破」したら勝ち、でいいのか。「価値観の壁」を越え、生産的に議論するためのクリティカル・ディスカッション入門。 意見のすれ違いの根底には「倫理問題」がある――。 「はい論破」ではなく、協力的で生産的な議論を。 わかり合えない人と話し合うための討論の技法! 物事の善し悪しを判断するのは難しい。社会のあるべき姿や幸せの形も人それぞれ。ならば意見のすれ違う人と対話するのは不毛なのだろうか。それでも私たちは他者と共に社会をつくるため、答えの出ない問題について話し合わなければいけないことがある。そんなとき、小手先の論理で相手を説き伏せようとする前に、対立の根本に遡って「そもそも倫理とは何か」と考えてみることがとても役に立つ。「価値観の壁」を越え、生産的に議論するためのクリティカル・ディスカッション入門。 はしがき 序章 哲学思考のその先へ SS0-1 唯一無二の食事1/クリティカル・シンキングとは/協力的クリティカル・シンキング/倫理的クリティカル・シンキング/倫理的思考における文脈主義/SS0-2 唯一無二の食事2/「そもそも倫理とは何か」を考える必要がでてくるのはどういうときか/本書の構成 ブックガイド 第一章 倫理を外から眺める SS1-1 エンケラドス生命たちの自衛1/自然主義的視点/モラル・サイコロジー/暴走路面電車という思考実験/倫理的判断ははらわたの感覚で決まっている/倫理は進化のプロセスで形成された?/道徳は簡単には進化に還元できない/運命共同体が生む道徳/SS1-2 エンケラドス生命たちの自衛2 ブックガイド 第二章 複視的に世界を眺める方法――中の人にしか見えない「社会」とは? SS2-1 見えるようになったもの1/拡張現実とは/「社会的な事実」とは/なぜ一万円札には価値があるか―制度的な規則と制度的事実/やりとりの中から浮かび上がる「社会」/社会的な存在としての「自己」/一貫性論争/コラム 平野啓一郎の分人主義/拡張現実としての「社会的事実」/「社会メガネ」は気の持ちよう?/一様ではない「社会メガネ」/二重写しに世界を見る/SS2-2 見えるようになったもの2/社会の存在論 ブックガイド 第三章 倫理とは何か――自由意志と倫理はどのように「見える」ようになるか 1 道徳的主体としての自分 SS3-1 丘に穴掘る部族の覚醒1/倫理メガネをかけて世界を眺める/「自由意志メガネ」のむこうに見える道徳的主体/自由意志は存在しないのか/道徳判断と行為はどうつながるか 2 善悪の客観性はどこからくるのか SS3-2 丘に穴掘る部族の覚醒2/「べき」には一貫性が求められる/客観主義と実在論/「客観性」や「実在性」は異星人にも見えるのか/「道徳的理由」に彩られた世界/コラム 非認知主義に対するアドバンテージ(ガチな人向けの補足)/人々はどのくらい道徳を客観的に捉えているか 3 善悪はフィクションか 「倫理メガネ」と錯誤理論/メガネをかける=感受性を研ぎ澄ます/SS3-3 丘に穴掘る部族の覚醒③/倫理とは半強制参加の拡張現実だ/自分のメガネは見えない/「倫理メガネ」の多層性と多様性 ブックガイド 第四章 倫理的思考の四つのものさし――善悪をどう測るか 1 倫理的思考のものさし SS4-1 旧友の依頼1/規範倫理学の考え方/四つのものさし 2 結果のものさし 幸せについての三つの考え方/功利主義という考え方/価値があるのは「幸福」だけか/コラム 生命の価値 3 ルールのものさし ルールの類型化/義務論1――一見自明の義務/義務論2――カント主義の場合/切り札としての権利/自己決定権とインフォームド・コンセント/誰の視点かで変わる答え/副次効果という考え方は有効か 4 性格のものさし 古代ギリシアから儒教まで/性格のものさしの特徴 5 関係のものさし ケアするものとされるものの関係/専門職倫理/関係のものさしはあくまで関係がある限りで働く/コラム 自分に対する責任 6 四つのものさしを使いこなす 四つのものさしの関係/ものさしへの感受性を研ぎ澄ます/SS4-2 旧友の依頼②/正当化的用法と発見的用法/倫理判断のクリームシチューモデル/コラム 未確定領域功利主義(ガチな人向けの補足) ブックガイド 第五章 なぜ意見が食い違うのか――倫理問題の難しさ 1 意見はどこで食い違っているか SS5-1 真空愛着1/すれ違いのパターン分類 2 言葉の意味についての食い違い SS5-2 真空愛着2/「定義」のずれ/言葉のネットワークのずれ/空を飛べないものは鳥ではない?――事例ベースで学んだ概念のずれ/言葉の使い方をどうすり合わせるか 3 事実関係についての食い違い SS5-3 真空愛着3/誰が何を言ったかの食い違い/調査が必要なことがらについての食い違い/調査結果の解釈のずれ/幅のある推定値/将来予測のずれ/誰が情報提供者として信頼できるか/バイアスが対立の溝を深める 4 価値についての食い違い SS5-4 真空愛着4/強制参加の中の自由度が生む考え方の違い/コラム とがめるほどでない過ち/社会メガネの食い違い 5 問題設定についての食い違い SS5-5 真空愛着5/問題の基本的枠組みについてのずれ/検討範囲のずれ/「次元数」の違い/誰に立証責任があるか/見え方の差を生む心理的背景/どれでもよいというわけではない 6 多対多の論争における食い違い SS5-6 真空愛着6/SNSが社会を分断する?/なぜネットはいつも揉めているのか――敵対的な討論状況/なぜ討論相手の主張をまじめに受けとれないか/一般化された欠如モデル/多対多討論状況/やっつける「敵」を特定する――「陣営」のイメージの危険性/わら人形論法の温床――多対多討論状況が生む討論のすれ違い/多対多敵対的討論状況というモデル ブックガイド 第六章 互いの論証をチェックする――協力的に討論をするための技法1 1 協力的討論のながれ SS6-1 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)1/協力的に討論するための五つのステップ/協力的態度は相互作用の中で作られる/「対立の解消」の二つのパターン 2 論証図をつくる 論証図における矢印の意味/コラム MECE(ミーシー)/消極的根拠と否定的根拠/論証構造の類型/論証図についてのよくある疑問 3 暗黙の前提と結論の明示化 暗黙の結論の明示化 4 前提と推論の予備チェック 事実関係をチェックする/価値主張をチェックする/誤謬推論になっていないかチェックする/文脈にあった推論になっているか ブックガイド 第七章 論破ではなく協力――協力的に討論をするための技法2 1 対論図をつくる SS7-1 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)2/対論図の基本的な考え方/対論になっていない討論/わら人形論法と論点ずらしの誤謬/コラム 食い違いのポイントをしぼりこむ方法/どういう場合に考えを変えるか訊いてみる/SS7-2 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)3 2 対立をどう解消するか 言葉遣いのすり合わせ/事実認識のすり合わせ/心理学的仕組みに注意をはらう/価値主張のずれの解消/メガネをすり合わせる/正解は発見されるのか発明されるのか/価値の大小についての食い違い/問題設定についての食い違い/地平の融合/SS7-3 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)4 3 多対多敵対的討論状況にどう対処するか 一般化された欠如モデルを避ける/「陣営」として捉えない/ゼロサム的に問題を捉えない/第三者にどう見えるかも気にかける/コラム ネガティブ・ケイパビリティ ブックガイド 第八章 批判的でいるのはいつでもよいことか──無理せずクリティカルに生きる SS8-1 エピローグ1/ここまでのおさらい/クリティカル・シンキングはどこまで合理的か/クリティカル・シンキングは騙されにくいか/SS8-2 エピローグ2/?つきとも協力すべきか/自分を傷つけようとしている相手ならどうか/SS8-3 エピローグ3/売られた喧嘩は買うしかないのか/当事者を傷つける心配はないか――二次被害の可能性と文脈の分業/SS8-4 エピローグ4/身の危険を感じたら考える前にまず逃げよ――緊急事態とクリティカル・シンキング/無理せずクリティカルに生きる ブックガイド 注/あとがき
本書は倫理学の基本理論を紹介し、「善い」とは何か、助け合うべき理由や限界について考察します。アリストテレスやカントの理論を平易に解説し、現代の課題(医療、人工知能、戦争、環境問題など)を倫理学の視点から探求します。社会契約論や功利主義に関する図解や思想家のコラムも含まれています。著者は哲学・倫理学を専門とする品川哲彦です。
この書籍は、女子高生の体験を通じて生殖医療やがん告知、中絶、安楽死、クローン技術などの生命倫理に関する問題を考察する入門書です。各章では、具体的な事例を挙げながら、倫理的な問いかけを行い、読者に深い思索を促します。著者は倫理学や生命倫理学の専門家で、漫画家も参加しています。
京都議定書の発効、「持続可能性」「エコロジカル・フットプリント」といった概念の登場を踏まえて、好評の初版を大幅に改訂。 京都議定書の発効,温暖化に伴う気候変動の再評価,世界規模での貧富の差の拡大,「持続可能性」「エコロジカル・フットプリント」「拡大された製造者責任」といった概念の登場など,環境をめぐる理論的な状況の変化に対応して,好評の初版を大幅に改訂。 第1章 環境問題を倫理学で解決できるだろうか 第2章 人間中心主義と人間非中心主義との不毛な対立 第3章 持続可能性とは何か 第4章 文明と人間の原存在の意味への問い 第5章 環境正義の思想 第6章 動物解放論 第7章 生態系と倫理学 第8章 自然保護 第9章 環境問題に宗教はどうかかわるか 第10章 消費者の自由と責任 第11章 京都議定書と国際協力 第12章 環境と平和
本書は、ギリシアの思想とヘブライの信仰がヨーロッパ哲学の基盤であることを探求する。第1部ではギリシアの思想、特にホメロスや哲学の発展を扱い、第2部では旧約・新約聖書を通じてヘブライの信仰を考察。第3部では中世から近現代の哲学の流れを分析し、これらの源泉がどのように現代思想に影響を与えているかを明らかにする。著者は岩田靖夫で、古代ギリシア哲学を専門とする教授である。
現代の政治理論の重要な主題や概念をとりあげて,わかりやすく解説した入門書の新版。新たに「環境と政治」の章を設けた。 現代の政治理論の重要な主題や概念をとりあげて,わかりやすく解説した入門書の新版。初版刊行後の政治理論研究の進展をふまえ全体をアップデートするとともに,新たに「環境と政治」の章を設けた。より深く政治について考えたい人に最適の入門書。 第1章 政 治(川崎 修) 第2章 権 力(川崎 修) 第3章 リベラリズムの展開(金田耕一) 第4章 現代の自由論(金田耕一) 第5章 平 等(飯田文雄) 第6章 デモクラシー(杉田 敦/早川 誠) 第7章 ネーションとエスニシティ(杉田 敦/早川 誠) 第8章 フェミニズムと政治理論(井上匡子) 第9章 公共性と市民社会(谷澤正嗣/早川 誠) 第10章 環境と政治(尾内隆之) 第11章 国境をこえる政治の理論(遠藤誠治) 読書案内/引用・参考文献
「学問の意義」「功利主義」「ジェンダー論」「幸福論」の4つのカテゴリーで構成する、進化論を軸にしたこれからの倫理学。 現代哲学を「政治的正しさ」の呪縛から解放する快著 ──帯文・東浩紀 ポリティカル・コレクトネス、差別、格差、ジェンダー、動物の権利……いま私たちが直面している様々な問題について考えるとき、カギを握るのは「道徳」。進化心理学をはじめとする最新の学問の知見と、古典的な思想家たちの議論をミックスした、未来志向とアナクロニズムが併存したあたらしい道徳論。「学問の意義」「功利主義」「ジェンダー論」「幸福論」の4つのカテゴリーで構成する、進化論を軸にしたこれからの倫理学。 哲学といえば、「答えの出ない問いに悩み続けることだ」と言われることもある。だが、わたしはそうは思わない。悩み続けることなんて学問ではないし、答えを出せない思考なんて意味がない。哲学的思考とは、わたしたちを悩ませる物事についてなんらかのかたちで正解を出すことのできる考え方なのだ。(…) この本のなかでは、常識はずれな主張も、常識通りの主張も、おおむね同じような考え方から導きだされている。それは、なんらかの事実についてのできるだけ正しい知識に基づきながら、ものごとの意味や価値について論理的に思考することだ。これこそが、わたしにとっての「哲学的思考」である。(…)倫理学のおもしろさ、そして心理学をはじめとする様々な学問のおもしろさをひとりでも多くの読者に伝えることが、この本の最大の目的である。(「まえがき」より) 【目次】 ■第1部 現代における学問的知見のあり方 第1章 リベラルだからこそ「進化論」から目を逸らしてはいけない 第2章 人文学は何の役に立つのか? 第3章 なぜ動物を傷つけることは「差別」であるのか? ■第2部 功利主義 第4章 「権利」という言葉は使わないほうがいいかもしれない 第5章 「トロッコ問題」について考えなければいけない理由 第6章 マザー・テレサの「名言」と効果的な利他主義 ■第3部 ジェンダー論 第7章 フェミニズムは「男性問題」を語れるか? 第8章 「ケア」や「共感」を道徳の基盤とすることはできるのか? 第9章 ロマンティック・ラブを擁護する ■第4部 幸福論 第10章 ストア哲学の幸福論は現代にも通じるのか? 第11章 快楽だけでは幸福にたどりつけない理由 第12章 仕事は禍いの根源なのか、それとも幸福の源泉なのか? 終章 黄金律と「輪の拡大」、道徳的フリン効果と物語的想像力 【目次】 ■第1部 現代における学問的知見のあり方 第1章 リベラルだからこそ「進化論」から目を逸らしてはいけない 第2章 人文学は何の役に立つのか? 第3章 なぜ動物を傷つけることは「差別」であるのか? ■第2部 功利主義 第4章 「権利」という言葉は使わないほうがいいかもしれない 第5章 「トロッコ問題」について考えなければいけない理由 第6章 マザー・テレサの「名言」と効果的な利他主義 ■第3部 ジェンダー論 第7章 フェミニズムは「男性問題」を語れるか? 第8章 「ケア」や「共感」を道徳の基盤とすることはできるのか? 第9章 ロマンティック・ラブを擁護する ■第4部 幸福論 第10章 ストア哲学の幸福論は現代にも通じるのか? 第11章 快楽だけでは幸福にたどりつけない理由 第12章 仕事は禍いの根源なのか、それとも幸福の源泉なのか? 終章 黄金律と「輪の拡大」、道徳的フリン効果と物語的想像力
日経BPクラシックス28タイトル目は、豚とソクラテスを対比した名言で知られるジョン・スチュアート・ミル『功利主義』の新訳。以下、中山元さんによる訳者あとがき「ミル『功利主義』の果たした役割」から。本書に掲載した『功利主義』の論文は、一八六一年に『フレーザーズ・マガジン』誌に分載されて、一八六三年に著作として発表されたものである。この論文はベンサムの思想を功利主義という観点から巧みに要約したものであり、ベンサムの著作では明確に語られていなかったところまで掘り下げて検討し、部分的にはベンサムの功利主義の思想を補足して、その欠点を是正することを試みたものである。 この論文がベンサムの思想に加えた「補足」と修正は、大きく分けて三つに集約することができるだろう。まずベンサムの思想において示された快楽計算の要素を薄めて、快楽よりも幸福に重点を置いたことである。ベンサムは功利の原理について、「人間が苦痛と快という二人の主人によって支配されていること」と説明している。人間のすべての行動は、苦痛を回避し、快楽を求めるという原理によって支配されており、こうした原理によって説明できると考えていた。そしてすべての法は、この原理に適うように定める必要があり、そのためには法によって影響をうけるすべての人々の快の合計と苦痛の合計を計算して、それが差し引きでプラスになるようにすべきだと考えたのである。 第1章 概論 第2章 功利主義とは何か 第3章 功利の原理の最終的な強制力について 第4章 功利の原理はどのように証明できるか 第5章 正義と功利の関係について 付録 ベンサム論
この書籍は、センター試験・倫理の形式で西洋思想を学ぶための内容で、ソクラテスからウィトゲンシュタインまでの重要な哲学的テーマを厳選した20問を通じて解説しています。著者は哲学の基本を楽しく理解できるように工夫しており、古代から近代、そして批判的な哲学の流れを網羅しています。著者は東京大学哲学科卒のライター・編集者、斎藤哲也氏です。
・20世紀を代表する哲学者、バーナード・ウィリアムズによるカリフォルニア大学の名講義。 ・西洋哲学が見落としていた「倫理」をギリシア古典に発見し、近代道徳の呪縛から解放する〈反道徳的な倫理学〉。 ・解説=納富信留(東京大学大学院教授) 近代以降の進歩主義的な見方では、古代ギリシア人は未開の心性をもち、より洗練された道徳が人間性を陶冶してきたと捉えられてきた。 ウィリアムズはこのような道徳哲学の提示する人間が、生きられた経験から切り離された、無性格な道徳的自己であるとして批判する。それとは対照的に、具体的な性格と来歴をもつ人々を描く、ホメロスの叙事詩やアイスキュロス、ソポクレスらの悲劇作品を読み解き、そこに流れる豊かな倫理的思考を明らかにする。 道徳哲学やプラトン、アリストテレスらの哲学を批判的に参照しながら、恥と罪、必然性(運命)と義務、運命と自由意思、責任と行為者性といった概念をめぐる議論を通して、古代と現代を通じてこの現実を生きる人間の生の姿を描き出す、カリフォルニア大学の名講義。 はじめに 二〇〇八年版への序文 A. A. ロング 第一章 古代の解放 第二章 行為者性のいくつかの中心 第三章 責任を認識すること 第四章 恥と自律 第五章 いくつかの必然的なアイデンティティ 第六章 可能性・自由・力 解説 古代ギリシアから私たちが学ぶこと 納富信留 訳者あとがき 古典文献一覧 参考文献一覧 附録1/附録2 注 索引
本書は、現代倫理学の主要な問題を日常の倫理的ジレンマを通じて明らかにし、読者が倫理学の議論に親しむことを目的としています。著者は、難解な理論よりも実生活に即した問題を通じて、21世紀の倫理の枠組みを描くことを目指しています。具体的なテーマとして、嘘や殺人、エゴイズム、幸福の計算、正義の原理など、さまざまな倫理的問いが扱われています。
モラルなき現代に正義・愛・自由を問う、新しい倫理学! 社会も、経済も、政治も、科学も、倫理なしには成り立たない。 倫理がなければ、生きることすら難しい。 人生の局面で判断を間違わないために、正義と、愛と、自由の原理を押さえ、 自分なりの生き方の原則を作る! 道徳的混乱に満ちた現代で、 人生を炎上させずにエンジョイする、〈使える〉倫理学入門。 * * * * 科学はみんなが学ばなくても、科学者が研究してくれれば、それで進歩します。 でも、倫理は違います。 というのは、倫理に関する知識は放っておいてはちゃんと働かないからです。 そして、倫理がなければ、我々は生きることも難しくなる。 だから、一人ひとりが倫理について考えた方がよいのです。 倫理っていうのは、他人事じゃなくて、自分自身の人生の問題だからです。 ――「まえがき」より まえがき はじめに/最初で最後の倫理学の本/考える倫理学?/倫理学と自分たちを繫ぐ/数万人の著者がいる本/主人公は私 序章 この本の使い方 いきなりの抜き打ちテスト!/結局、この本で何ができるか/この本の読み方 パート0 倫理学とは何か 第1章 倫理とは何か 1 - 1 まずはざっくりと ざっくり言って、倫理学って?/で、倫理って?/人間だもの/人間がいて、何かして/だから善悪が生まれる/ルールというか、規範/まとめ 1 - 2 倫理が必要なわけ ふーん、それで?/ガリンペイロの世界/倫理、道徳の必要性 1 - 3 倫理、道徳が意識されないわけ なぜ道徳は意識されないか/言葉・文法と道徳・倫理学の類似/小学校の「道徳」の時間はなんだったのか/空気のような/倫理学の小道1:倫理学がますます必要に? 第2章 倫理学とは何か 2 - 1 残念! 倫理にも弱点が…… 道徳の弱点/善悪なんて人によって違う!?/倫理、道徳を整理する/仕方ないでは困る! 2 - 2 それは自由のために 「道徳は押しつけである」説/子どもは分かってくれない!/それを大人は教えてくれない/倫理学は人を自由にする/倫理学の小道2:科学と倫理学、原因と理由 2 - 3 最も役立つ知識 「倫理学は役立たない」説/役に立つのが分かりにくい/倫理学は独特の仕方で役に立つ/倫理のない医者、非道徳的な技術者/倫理学の小道3:技術と倫理の関係、ついでに職業倫理について 2 - 4 倫理学の答え 倫理学に答えは?/具体的な答えが欲しい!?/「倫理」と「倫理の原理」/そして、使うのは「私」/コラム1:倫理学と人生論 2 - 5 ちょこっと例題――運命のボタン ボタンを押して一億円/思考実験/二つのレベルを分ける/心理の原因、道徳の理由/相互性/正義の原理/道徳の基本原理と理由 インターミッション1 倫理の三つの領域 第3章 倫理の三つの領域 3 - 1 三つの関係 分かれ道/人間の関係としての倫理/個人と社会と、そして/噓とカント/友人より義務が大事!?/コラム2:カントと『ライアーゲーム』とインターネット/人間像の違い/コラム3:カントの定言命法(倫理学用語の難しさと便利さ)/三つの関係 3 - 2 三つの関係を確かめる 二つの極とその中間/ある倫理学者の一日/具体例の分析/重なり合う関係 3 - 3 マンガに応用する 三つの関係を応用する/『デスノート』の分析/『ウロボロス――警察ヲ裁クハ我ニアリ』の分析/『ワンピース』の分析 パート1 社会の倫理:正義 第4章 正義の正体 4 - 1 釣り合いとしての正義 夜神君は正義か?/意見をまとめる/罪と罰の釣り合い/天秤のイメージ 4 - 2 社会、正義、ジコチュー 一人では決められない/正義とジコチュー/みんな同等 4 - 3 生きている社会 生きて動いている社会/正義は自然には生まれない 第5章 正義を洗う 5 - 1 勝った方が正義? 「正義」にしては薄すぎる?/「勝った方が正義」?/「正義の味方」? 5 - 2 正義なんてない? 「正義は人によって違う」?/「正義なんて自分の都合」?/正義は自分たちで作るもの 5 - 3 正義の理念と方法 もう一つの「正義はない」/理念と方法、目的と手段/理念は一つ、方法はたくさん/本の読み方についての注意 第6章 正義のパターン 6 - 1 調整の正義 正義にもパターンがある/調整の正義と法/復讐と正義は違う 6 - 2 交換の正義 交換の正義と経済/調整と交換、法と経済/臓器売買はオッケーか/コラム4:回るお金を支える倫理の力 6 - 3 分配の正義 分配の正義と政治/二種の分配方法/二種の分配の使い分け 6 - 4 パターン分けの意味 一つの正義、三つのパターン/三つのパターンは決め方の違い/パターン分けの意味/序章の問一の答え 第7章 個人と社会 7 - 1 なぜ正義が大事なのか 正義はなぜ必要か/正義がないと「ズルい!」になる/正義がないと「ひどい!」のまま/正義と権利/倫理学の小道4:権利、正義、法/他人同士が傷つけ合わな/倫理学の小道5:正義は時代によって変化する?――権利拡張の歴史 7 - 2 正義を「私」に落とし込む 正義と「私」?/正義と義務/個人の自由/「自由」というと? パート2 個人の倫理:自由 第8章 二種類の自由 8 - 1 消極的自由 自由と制限/「無制限な自由」の罠/自由に制限が必要なわけ/愚行権/義務の範囲/消極的自由 8 - 2 積極的自由 積極的自由/『デスノート』から『バクマン。』へ/「自分」について/自律/自律と自立/「本当の自分」 第9章 自律と幸福 9 - 1 アリストテレス先生の幸福論 なぜ自分への制限が必要なのか/優先順位を決める/幸福/アリストテレスの幸福主義/お金と人気と快楽/幸福とは何か?/アリストテレスから離れて 9 - 2 幸福、目的、質 お金持ちか、幸せか?/質と量/目的と手段 9 - 3 幸福の正体 「質より量、目的より手段」の挙げ句に/例えば、安楽死/幸福の正体/コラム5:遊び、幸福、暇(アリストテレスとマルクス) 第10章 運命と出会い 10 - 1 運命と幸福 なぜ幸福になるのは難しいか/運命/運命と出会い 10 - 2 身近な関係と愛 幸福を成り立たせるもの/身近な関係で大事なもの?/ここは一丁「愛」ということで パート3 身近な関係の倫理:愛 第11章 愛とは何でないか 11 - 1 恋愛こそ愛である? 難しい愛/余計なイメージを取り除く/「愛=セックス」説/「恋愛中心」説/愛の伝統的な分類法 11 - 2 愛とは感情である? 「愛=感情」説/ストーカーは愛するか/不安定な愛?/愛の形 第12章 恋愛と友情 12 - 1 男女間に友情は成り立つか? アリストテレスの恋愛論?/男女間に友情は成り立つか/男女間では恋愛しかない?/男女間の友情?/友情型と恋愛型/相補性と共同性 12 - 2 愛する人は一人だけ? 愛する理由/愛する人は一人だけ?/愛と正義/オンリー・ワン 12 - 3 友達がよそよそしくなるとき 愛の強さの違い/友達がよそよそしくなるとき/愛は外からは分からない/不釣り合いなカップルの謎/愛の偏り/コラム6:嫁姑問題はなぜ難しいか(あるいはマスオさんはなぜ磯野家に同居しているか) 12 - 4 あなたがここにいてほしい 愛で大事なこと/共通のものを大事にする/「徳は孤ならず」/本当の友情?/大事なものを大事にする/あなたがここにいてほしい/序章の問二の答え 第13章 愛のパターン 13 - 1 家族をバラバラにする! 親子愛は?/親子愛は相補型/相補型にも二種類ある!/『サザエさん』はなぜ面白いか/それでも一つのまとまり 13 - 2 愛の内と外 二×二で、四種類/縦の共同性/身近な関係としての会社?/身近な関係の内と外/コラム7:ぼくのおじさん 13 - 3 会社は面白い! 会社は面白い!/会社は作られる/何を大事にする関係か/契約があるか、ないか/会社は組織される/会社が社会的に見える理由 第14章 身近な関係と個人、社会 14 - 1 身近な関係と個人 ブラック企業が生まれるわけ/身近な関係と個人/音楽とスポーツの比喩/スポーツと会社、音楽と恋愛 14 - 2 身近な関係と社会 身近な関係と個人、社会/児童虐待はなぜ防ぎにくいか?/親子と社会/上司の不正な命令に従うか?/会社と社会/身近な関係と社会/視野を広く/コラム8:内部告発は裏切りか? インターミッション2 倫理のケーススタディ 第15章 愛や正義の使い方 15 - 1 試験の採点 倫理の基本原理のまとめ/試験の採点をする1/試験の採点をする2/試験の採点をする3/直観と手続き/間違いを防ぐ/コラム9:税金の納め方 15 - 2 ジレンマの解決 道徳的ジレンマ/ハインツのジレンマ/人生の解釈学 第16章 人生の解釈学 16 - 1 マンガの解釈学 マンガの解釈学/『噓喰い』、『カイジ』などの場合/『逃げ恥』の場合/愛と契約/お金で愛は買えるか? 16 - 2 小説も読もう 小説も読もう/「半沢直樹」の原型/『火花』/自律からおじさんまで/活きた倫理学 16 - 3 ついでに映画も ついでに映画も/『ゴッドファーザー』、ドンの場合/序章の問三の答え/身内、社会、居場所/マイケルの場合/倫理学の小道6:カント対孔子/地味な物語 第17章 身近な話題に倫理学はいかが 17 - 1 ネットとかSNSとか インターネットの新しさ/SNSのSは何? 17 - 2 浮気とか不倫とか 友人と恋人の境目は?/どこからが浮気か?/浮気と不倫/三角関係は?/一夫多妻制の意味/『終末のハーレム』 パート4 攻めの倫理! 第18章 攻めの倫理、守りの倫理 今までを振り返ると/倫理、道徳の二つのイメージ/攻めの倫理と守りの倫理/必要条件と十分条件/「あれかこれか」と「あれもこれも」/やっぱり分けよう 第19章 身近な関係での攻めの倫理 19 - 1 縦の相補型(ついでにケア倫理) 身近な関係における守りと攻め/縦の相補型/ケアの倫理/ケアと正義/ケアと愛/倫理学も進歩する 19 - 2 横の相補型(ついでに医療倫理) 横の相補型/医療の社会性/医療の相補性/患者の権利とインフォームド・コンセント/問題が複雑になる理由 19 - 3 横の共同型(ついでのついでに共同体主義) 横の共同型/『3月のライオン』と『となりの怪物くん』/地域コミュニティ/倫理学の小道7:コミュニタリアニズム/実は私、町内会長です/守りであり、攻めであり 19 - 4 縦の共同型(おまけに経営倫理) 縦の共同型/会社は複雑な組織/攻めに出ると――横と縦の違い/自己目的化する組織/会社も主体である/経営倫理――コンプライアンスとCSR 第20章 社会における攻めの倫理 20 - 1 最大多数の最大幸福!? 社会における守りと攻め/社会改良のための功利主義/功利主義の弱点/倫理学の小道8:動物の権利/功利主義の弱点?/使える場合と使えない場合/倫理学の小道9:功利主義のあれこれ 20 - 2 倫理から政治へ みんなにとって何が大事かが決まる場合/人によって何が大事か違う場合?/不妊治療を健康保険で?/なぜ「政治」なんていうものが必要なのか/多数決とは何か 20 - 3 アファーマティブ・アクション! 攻めの正義?/税金の使い方/アファーマティブ・アクション/積極的正義? 20 - 4 神の正義、人の正義 完全な正義/人間だもの(悪い意味で)/宗教マンガとしての『デスノート』/神の正義、人の正義/コラム10:宗教と経済/倫理学の小道10:グローバリゼーションと正義 第21章 個人における攻めの倫理 21 - 1 自己への自由 個人における攻めと守り/攻めに出るのも難しい/困難な自由 21 - 2 不確定義務 四つの自由/法的義務と道徳的義務/完全義務と不完全義務/「親切」/なぜ親切が不完全なのか/権利を伴わない義務/倫理学の小道11:グローバル正義論 21 - 3 他者への自由 不確定義務は義務なのか?/カントの「義務」論/他者への自由/厄介な自由 21 - 4 自己からの自由 チョー義務!/自己犠牲否定論?/もう一つ自己犠牲否定論/無償の愛/自己からの自由/コラム11:道元の言葉「仏道をならふといふは……」 終章 全体のおさらい 1 倫理の基本原理とパターン 三×四で、合計一二個/段階を分ける 2 人間関係に関する注意 関係の複合/関係の多面性/関係の変化 3 広く見て柔軟にバランスを 幅広く考える/「主人公は私」再び/全体のバランス/自分でも倫理学を作る、自分の人生を作る あとがき 付録パート1 倫理学の内と外 I章 倫理学のアウトライン I - 1 倫理学の三分野 倫理学の中身/規範倫理学/応用倫理学/メタ倫理学/記述倫理学 I - 2 ざっくり倫理学の歴史 規範倫理学の三つの立場/まずはソクラテスから、倫理学の始まり/徳の倫理/義務論と功利主義/問題は? II章 倫理学のお隣さん 倫理学のお隣さん/社会・人間科学の基礎としての倫理学/法と倫理、二種の規範/法と道徳の違い/法に則って粛々と…/それぞれの強みと弱み/倫理学の小道12:倫理は文化によって違う?(相対主義の問題) 付録パート2 倫理学の方法 III章 倫理学の方法 III - 1 まとめる 倫理学者はどうやって研究しているか/やり方の基本/価値判断から規範へ/ノー・モア・ルールズ!/規範から基本原理へ/理由としての原理 III - 2 どーんと原理から考える 「まとめる」方法の難点1――手間がかかる!/「まとめる」方法の難点2――どこで止めたらいいの!?/発想の転換 付録パート3 倫理の基本原理 IV章 多すぎても少なすぎても IV - 1 基本は一つか ベンサムの場合/功利主義の弱点/ゴドウィンの場合 IV - 2 基本はたくさんか ほんのついでのアリストテレス/徳倫理学の利点/徳倫理学の弱点/多すぎても少なすぎても V章 基本原理の基盤を求めて 少数原理主義は倫理を狭く考えている/観点を定める/コラム12:道徳的柔軟性
本書は、西洋哲学の流れをプラトンからニーチェ以降の反哲学に分けて解説し、難解な哲学用語を平易に理解できるようにすることを目指しています。目次には、哲学の起源、キリスト教との関係、近代哲学の発展、反哲学の誕生、ハイデガーの影響などが含まれ、現代の思想状況も俯瞰しています。著者は哲学者の木田元で、現代西洋哲学の主要著作を日本語に翻訳したことで知られています。
哲学の入門として最適なのだろうが、これを読んでも残念ながら哲学の面白さというのは分からなかった。。。もっと入門としては山口周さんの武器になる哲学がおすすめ。もはや哲学書と言っていいのかは分からないが・・・
本書は、ベンサムの思想がフランス革命を経てイングランド国制批判として展開していく過程を同時代の知的文脈と関連づけて考察する。 本書は、ベンサムの思想が、フランス革命の衝撃を経てイングランド国制批判として展開していく過程を同時代の知的文脈と関連づけて考察する。ベンサムの「自由な国家」の具体的構想を明らかにする。 ▼フランス革命はジェレミー・ベンサムの社会認識と人間観を大きく揺るがした。ウィリアム・ブラックストンへの批判から始められた思索がたどりついた「立法の科学」と「自由な国家」構想。革命の動乱を契機に、ベンサムは、構想が前提とする合理的な人間――適切に功利計算ができる人間――の存立を阻む様々な外的要因に関心を広げてゆく。人民による世論が決定的な意味を持つ民主政治において、アナーキーに陥ることのない「自由な国家」はいかにして可能なのか。 本書は、ベンサムの思想が、フランス革命の衝撃を経てイングランド国制批判として展開していく過程を同時代の知的文脈と関連づけて考察する。イングランド国教会批判と議会改革論を経て『憲法典』に結実する、ベンサムの「自由な国家」の具体的構想が明らかにされる。 一貫した哲学を持つ功利主義者像を相対化し、ベンサムの生涯にわたる思想的格闘を追究する画期的な研究成果。 はじめに 第一章 ブラックストンのイングランド国制論 第一節 イングランド法の基礎原理 (一) 自然法と神法 (二) 所有権の起源と基礎 第二節 イングランド法の歴史と古来の国制 第三節 イングランド国制の均衡と調和 (一) 主権の基礎と諸形態 (二) 「権力均衡」 の政治学 第二章 ベンサムにおける 「立法の科学」 と 「自由な国家」 第一節 「立法の科学」 の再構築 (一) 神学と法学 (二) 解説的法学と評価的法学 (三) 「犯罪」 の諸類型と 「私的倫理」 第二節 ベンサムの主権論と 「自由な国家」 (一) 主権の神学的基盤とイングランド議会 (二) 服従の習慣―― 「政治社会」の多様性 (三) 「専制的統治」 と 「自由な国家」 第三章 フランス革命とイングランド国制 第一節 参照基準としてのイングランド国制 (一) 社会認識―― フランスとイングランド (二) 諸利益の制度的統合 (三) 「安全」 と 「平等」 ―― 幸福の判断能力 第二節 「政治的急進主義」 の成立 (一) 憲法制定国民議会と 『権力の分割』 (二) 『フランス憲法典草案』 の構造 (三) イングランド国制の 「腐敗」 問題 第三節 革命への懐疑と批判 (一) 憲法改正条項と立法府の全能性 (二) 植民地解放の正義と利益 (三) 権利宣言批判―― 『大げさなナンセンス』 第四章 イングランド国教会と世論 第一節 ベンサム宗教論の基本的視座 第二節 国民協会と三位一体教義法 第三節 イングランド国教会の 「腐敗」 問題 第四節 ベンサムの教会論 第五節 イングランド国教会の 「安楽死」 と 「宗教的自由」 第五章 統治の「経済性」と統治者の「適性能力」 第一節 イングランド国制論における経営的視座の成立 (一) バークの影響力論と 「高貴な原理」 (二) ベンサムにおける 「経済性」 の擁護 (三) 官職俸給最小化原理の展開 第二節 統治者の 「道徳的適性能力」 と議会改革 (一) 「適性能力」 の三類型 (二) 政治的急進主義の展開 (三) 統治者の 「道徳的適性能力」 と 「世論法廷」 第三節 統治者の 「知的適性能力」 と官僚制構想 (一) 「政治的誤謬」 と 「世論法廷」 (二) 統治者の「知的適性能力」 と 『クレストメイシア』 おわりに あとがき 文献一覧 索引
本書は、合理的な判断を行うための心の働きを探る内容で、行動経済学や認知心理学の実験を通じて、人がどのように判断エラーを犯すのかを解明しています。著者はノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマンで、幸福感や投資家・起業家の心理についてもわかりやすく説明しています。目次は、二つの思考システム、ヒューリスティクスとバイアス、自信過剰などのテーマで構成されています。
意味、分析と説明 人間の心理学 規範理論 公開性とベンサムの価値の理論の進展 ベンサムの平等に感応的な価値の理論 普遍的利益と特殊な利益 功利性、公的なルールとコモン・ローの司法的判断 功利性と命令 事実、フィクションと法 「フランスのナンセンス」の擁護 功利主義的国際秩序 正義の魂 ベンサム
この書籍は、大学における倫理学の重要性を強調し、世界の問題に取り組むための人材育成を目的とした入門書です。善悪や正義、幸福に関する価値を他者と共に考える能力が求められる中、倫理学の主要理論や様々な視点(功利主義、道徳感情論、社会契約論、正義論、ケアの倫理、フェミニスト倫理学など)を学ぶための章立てがされています。
この書籍は、倫理学の基本を解説した入門書で、三つの主要な部に分かれています。第1部では規範倫理学として義務論、功利主義、徳倫理学を比較し、私たちが何をすべきかを探ります。第2部はメタ倫理学で、「善」の性質や非認知主義と認知主義の対立について論じます。第3部では応用倫理学として、環境倫理、動物倫理、生命倫理などの具体的な問題に対処します。著者は中村隆文で、哲学を専攻し、大学で教鞭を執っています。
幸福,道徳,そして統治 コモン・ロー的伝統とベンサムの法理論 ジェレミー・ベンサムとH.L.A.ハートの「法理学における功利主義的伝統」 ベンサム言語論の挑戦 ベンサムにおけるキリスト教と功利主義 広まり変転する〈ベンサム〉から蘇るベンサム像へ 功利主義と配分的正義 憲法上の権利と安全 ベンサムにおける功利主義的統治の成立 功利主義はなぜ不評か ベンサムの統治功利主義の可能性 統治と監視の幸福な関係 功利主義とマイノリティー グローバリゼーションとベンサム
短歌で哲学を詠む?その破天荒な試みがもたらした絶大な効果!…本書は高校生から読める「哲学史」を目指して書き下ろされた。古代ギリシアのタレスからアリストテレスまで、また中世神学、カント、ヘーゲルからドゥルーズ=ガタリまで、一気に読ませると同時に、学説の丁寧な解説により哲学の醍醐味を十分に味わうことができる。そして本書の最大の魅力は、短歌の抒情性と簡潔性が複雑な西欧哲学の本質に見事に迫り、そのエッセンスを掴んでいること。本書に触れた読者はおそらく、まるで哲学の大海原に漕ぎ出す船に乗ったかのような知的興奮と醍醐味を堪能するにちがいない。 1 ギリシア哲学 2 イエス・キリストと教父哲学 3 中世神学 4 ルネッサンスの哲学 5 近世哲学 6 近現代哲学 7 構造主義以降
サイモン・ブラックバーンの著書は、倫理学を初めて学ぶ読者向けの超入門書であり、現代の陰謀論や政治不信に対処するための思考力を養うことを目的としています。内容は、倫理学の基本概念や脅威、倫理的な考え方を解説し、附録には人物解説や読書案内が充実しています。初版以来、「最初に読むべき一冊」として評価されており、基礎から応用までをコンパクトに学べる内容です。
法哲学の「欲張り」な教科書。わかりやすくておもしろく、最新の研究成果を盛り込みながら、日本だけでなく国際的にも通用する標準… 「わかりやすく,おもしろい教科書」--謳うのは簡単,でもそれがいちばん難しい--だからこそ,挑戦しました。「そうか!」という瞬間が本書には必ずあります。なぜならあなたと一緒に徹底的に考えるから。わからないことほど楽しい,そんな知の世界へ飛び込みましょう。 第Ⅰ部 正義論 Chapter 01 功利主義 Chapter 02 正 義 Chapter 03 自 由 Chapter 04 平 等 Chapter 05 権 利 Chapter 06 正義論の最前線 第Ⅱ部 法概念論 Chapter 07 ルールとしての法 Chapter 08 法の価値 Chapter 09 法の権威 Chapter 10 解釈としての法 Chapter 11 批判理論 Chapter 12 遵法義務 Epilogue 法哲学の基礎理論
本書は、図解を用いて哲学の歴史をわかりやすく解説した入門書です。ソクラテス以前から21世紀の思想まで幅広くカバーし、中世の普遍論争やハイデガーの『存在と時間』なども詳しく説明しています。哲学用語の理解を助けるための解説や、問題設定の背景を丁寧に説明し、視覚的な資料を多く用いることで直感的な理解を促進します。著者は専修大学の教授で、現代哲学や舞踊研究に精通しています。
日本人はいかなる思想を持って生きてきたのか――。この問いを生涯をかけて追究した日本倫理思想史家による、遺著にして最終到達点。解説 上原雅文 日本人とはいかなる思想を持って生きてきた人々なのだろうか――。その探究は「今・此処」を生きる「現存」としての日本人が、どのようにして「無窮・無辺な「時・空」」を志向し、いかなる「形而上の存在」を「夢想」して生の「究極の拠りどころ」を求めてきたのかを、過去にさかのぼって解明することに他ならない。本書は、倫理学者・哲学者として「よい「生」」とは何かを問い続けてきた佐藤正英の研究の最終到達点とも言える傑作。全面改訂版をほぼ書き終えたところで亡くなった著者の遺志を継いだ研究者による校訂を経た完全版。解説 上原雅文 序章 倫理学とは I 倫理の名辞 II よい「生」 第一章 現存/形而上の存在 第二章 〈もの〉との協和 I 外なる他である〈もの〉 II 〈もの〉神の顕現 III 〈もの〉神を祀る祭祀 第三章 天空/地上 I 天空 II イザナキ・イザナミの子生み III 大いなるアマテラス・タケハヤスサノヲの子生み IV ホノニニギ葦原中国へ V 神武天皇、ヤマトタケル 第四章 和歌・作り物語 I 和歌の発生 II 花鳥風月の成立 III 「もののあはれ」 IV 作り物語 第五章 〈たま〉の転変 I 自である内なる〈たま〉 II 「いのち」 第六章 仏の絶対知 I 釈迦仏 II 大乗仏教の移入 III 大乗仏教の土着 第七章 大乗仏教の展開 I 極楽浄土・念仏 II 釈迦仏との出遇いとしての行業 第八章 武の呪力 I 鳥・獣・虫・魚との争い II 「つはもの」・「いくさ」 III 武の様態 IV 擬制としての親族共同体 V 妻子への情愛 VI 「名」を惜しむ 第九章 武士の世 第十章 「気」「理」の展開 第十一章 村落共同体 I 家居 II 村落 III 見知らない村落・町 第十二章 文明共同体 I 外発的開化 II 身近な他者との融和 III 有用な「知」の地平 IV 己れに回帰する「知」 V 倫理学構築の試み 終章 凡常な己れの地平 注 解説(上原雅文) 佐藤正英 主な業績一覧 事項索引
カント哲学の核心は、理性が持つ欺瞞性に対する挑戦にある。彼は理性の二面性を発見し、それを批判することで哲学の新たな道を切り開いた。本書では、カントの生涯や思想を探求し、特に『純粋理性批判』を通じてその哲学の核心を明確に解説する。各章では、理性のアイデンティティや批判哲学の背景、自由と道徳法則の関係などが論じられ、カントの新たな像が描かれる。
〈人間vs.自然〉では環境問題は解決できない.「自然」「生命」「精神」などの象徴的なテーマから,「持続可能性」「外来生物」,そして「地球温暖化」など現代の地球環境問題まで,すべての二項対立図式を超えて,私たちがこれから豊かに生きていくための環境倫理の新しい地平を拓く! 序章 環境倫理の現在——二項対立図式を超えて(鬼頭秀一) 第I部 環境倫理が語れること 1 人間・自然——「自然を守る」とはなにを守ることか(森岡正博) 2 自然・人為——都市と人工物の倫理(吉永明弘) 3 生命・殺生——肉食の倫理,菜食の論理(白水士郎) 4 公害・正義——「環境」から切り捨てられたもの/者(丸山徳次) 5 責任・未来——世代間倫理の行方(蔵田伸雄) 6 精神・豊かさ——生きものと人がともに育む豊かさ(福永真弓) 第II部 環境倫理のまなざしと現場 7 「外来対在来」を問う——地域社会のなかの外来種(立澤史郎) 8 「持続可能性」を問う——「持続可能な」野生動物保護管理の政治と倫理(安田章人) 9 「文化の対立」を問う——捕鯨問題の「二項対立」を超えて(佐久間淳子) 10 「自然の再生」を問う——環境倫理と歴史認識(瀬戸口明久) 11 「地球に優しい」を問う——自然エネルギーと自然「保護」の隘路(丸山康司) Box1 野生復帰を問う−野生復帰において人はどこまで操作可能か(池田 啓) Box2 政策からこぼれ落ちるローカル知——ウチダザリガニと人間の環境問題(二宮咲子) 第III部 環境倫理から生まれる政策 12 家庭から社会へ——持続可能な社会に続く道を地球温暖化問題から考える(井上有一) 13 知識から知慧へ——土着的知識と科学的知識をつなぐレジデント型研究機関(佐藤 哲) 14 政策から政/祭へ——熟議型市民政治とローカルな共的管理の対立を乗り越えるために(富田涼都) 15 安全から危険へ——生態リスク管理と予防原則をめぐって(松田裕之) 16 制御から管理へ——包括的ウェルネスの思想(桑子敏雄) 終章 恵みも禍も——豊かに生きるための環境倫理(鬼頭秀一)
この書籍は、徳倫理学の入門書であり、善き生を求める古代から現代に至る倫理学の発展を解説しています。功利主義や義務論とは異なり、個々の行為ではなく人生全体を考察する視点を提供し、古代ギリシアや中世、西洋の哲学、中国の儒教、近現代の思想家を網羅しています。また、環境、医療、ビジネス、政治などの応用倫理についても触れています。著者は、各分野で活躍する研究者たちです。
私たちの身近な物事を通して、人間の弱さや卑しさに眼差しをむける、倫理学の超入門書。 欲望とは何か、なぜ過去の記憶に悩まされるのか、偶然性とは何か、人生に意味はあるのか、そして〈私〉とは何か。私たちの身近な物事を通して、人間の弱さや卑しさに眼差しをむける、倫理学の超入門書。 人間の弱さや卑しさに眼差しをむける小さくて深い倫理学の入門書 ▼愛とは何か、正義とは何か、欲望とは何か、なぜ過去の記憶に悩まされるのか、偶然性とは何か、人生に意味はあるのか、そして〈私〉とは何か。身近な物事を通して、人間の弱さや卑しさに眼差しをむける、倫理学の入門書。 三田哲学会は創立100年を機に、専門的な研究成果を「生きられる知」として伝え、 公共の中に行き渡らせる媒体として本叢書の発刊を企図した。 シリーズ名は、ars incognita アルス インコグニタ。 ラテン語で「未知の技法」を意味する。 単なる知識の獲得ではなく、新たな「生きる技法としての知」を作り出すという精神を表現している。 1 小さな倫理学のすすめ 2 欲望の倫理学 3 情念のない人間は倫理的なのか 4 〈私〉という苦しみ 5 世界の中心で〈私〉を叫ぶ 6 天使たちの倫理学 7 偶然性を問うこと 8 ハビトゥスを歌うこと 9 風や流れとしての〈私〉 10 過去が苦しめ続けること 11 〈私〉もまた暗闇の中にありき 12 傷つきやすさ 13 涙の中の倫理学 14 さらば、正義の味方 15 友達がいないこと 16 倫理学も真理へと強制されるのか 17 人生に目的はない 18 悪と暴力性、あるいはサディズムとは何か 19 〈私〉への救済と〈私〉からの救済 20 〈私〉とは何か 後書き
このビジュアル大図鑑は、古代から現代までの哲学者198名の生涯や思想を網羅し、視覚的に楽しめる構成となっています。古代ギリシャからポスト構造主義まで、幅広い哲学者を取り上げ、女性哲学者も多数含まれています。内容は時代ごとに整理されており、写真や図版が豊富で、哲学史を楽しく学べる一冊です。著者はケンブリッジ大学のサイモン・ブラックバーンと東京大学の熊野純彦です。
宇宙倫理学とは何か 宇宙活動はなぜ倫理学を必要とするか 宇宙倫理学とエビデンス 宇宙の道と人の道 政治哲学から見た宇宙政策 科学技術社会論から見た宇宙事故災害 宇宙時代における環境倫理学 宇宙に拡大する環境問題 惑星改造の許容可能性 宇宙ビジネスにおける社会的責任 宇宙における安全保障 宇宙資源の採掘に関する道徳的懸念 宇宙倫理とロボット倫理 人類存続は宇宙開発の根拠になるか
世界における動物福祉論の最大の画期となり、現在まで重要性を増し続ける革命的書物にしてシンガーの代表作。そのあまりに苛烈かつ論理的な倫理の要求は、われわれ全存在に向けられている。大幅な改稿を施された2009年版にもとづく決定版。 第1章 すべての動物は平等である 第2章 研究の道具 第3章 工場畜産を打倒せよ 第4章 ベジタリアンになる 第5章 人間による支配 第6章 現代のスピシーシズム
この書籍は、人と動物の関係に関するさまざまな倫理的問題を探求しています。ペットのしつけや動物の殺処分、化粧品の動物実験、肉食、動物園、外来種、医療のための動物実験、野生動物の保護と駆除、イルカ・クジラの問題など、多岐にわたるテーマを扱っています。高校生の「生き物探偵」がこれらの問題に挑むマンガ形式で、読者に考える機会を提供します。著者は哲学者で、科学哲学や倫理学を専門としています。
本書は、哲学の歴史を「魂の哲学」から「意識の哲学」、「言語の哲学」を経て「生命の哲学」へと展開するストーリーとして描いています。古代から21世紀までの人間の思考と精神の営みを探求し、ヘーゲルやシュペングラー、ローティを超えた新たな哲学史を提示します。著者は伊藤邦武で、京都大学で学び、教授を務めた経験があります。
本書は、AIやロボット技術の進化に伴う倫理的問題を考察し、人間の道徳について探求する入門書です。著者たちは、ロボットやAIとの関係における倫理学の知恵を提供し、道徳的行為者性や責任、プライバシー、労働の未来などのテーマを扱っています。著者は名古屋大学や南山大学、金沢大学の教授陣で構成されています。
この入門書は、古代から現代までの哲学の流れや近代日本の哲学、主要な哲学的テーマを網羅しています。見開き2ページで各トピックを解説しており、全体の流れを理解しつつ個別の学びが可能です。現代的なテーマとしてSTS(科学技術社会論)、子どもの哲学、クィア・LGBT、アフォーダンスなども取り上げています。著者は東京大学、阪大、慶應義塾大学の教授たちです。
この文章は、R・カーソンが化学薬品の乱用による自然破壊と人体への影響を告発した著作について紹介しています。彼女の警告は、初版から数十年経った今でも衝撃的であり、人類はこの問題の解決策を見出していないと述べています。また、作品は20世紀のベストセラーであり、新装版が待望されていることも触れています。目次には、自然や環境に関する多様なテーマが含まれています。
「共感」に基づく「徳」の倫理学。ヒュームの多元的な価値観は示唆に富み、高度で多様な技術が発達した現代において有効な議論を提起する。近年注目度がますます高まる道徳論を最新訳で読む。 「共感」に基づく「徳」の倫理学。ヒュームの多元的な価値観は示唆に富み、高度で多様な技術が発達した現代において有効な議論を提起する。近年注目度がますます高まる道徳論を最新訳で読む。 凡 例 訳者からのメッセージ 読者案内 第一部 徳と悪徳一般について 第一節 道徳的区別は理性に由来しない 第二節 道徳的区別は道徳的感覚に由来する 第二部 正義と不正義について 第一節 正義 自然的徳か、それとも人為的徳か 第二節 正義と所有の起源について 第三節 所有について決定する、諸々の規則について 第四節 同意による所有権の移譲について 第五節 約束の責務について 第六節 正義と不正義に関するいくつかの更なる省察 第七節 統治機構の起源について 第八節 〔統治機構に対する〕忠誠の源泉について 第九節 〔統治機構への〕忠誠の限度について 第十節 忠誠の対象について 第十一節 諸国間の法について 第十二節 貞操と慎ましさについて 第三部 他の徳と悪徳について 第一節 自然的徳と自然的悪徳の起源について 第二節 こころの偉大さについて 第三節 善良さと善意について 第四節 自然に備わる能力について 第五節 自然に備わる能力に関するいくつかの更なる省察 第六節 本書の結論 解説 あとがき 索引(人名・事項)
この文章は、哲学者の一覧と著者情報を提供しています。著者は柘植尚則で、倫理学を専門とし、慶應義塾大学の教授です。彼は1964年に大阪で生まれ、1993年に大阪大学大学院を退学しました。
現代倫理学の基本文献。利他性が生物学的な起源を超えて普遍的な倫理へと拡張していくプロセスを鮮やかに描きだす。 理性の力がひろげる〈利他の輪〉 倫理とはなにか? 謎を解く鍵はダーウィン進化論にある。家族や友人への思いやりは、やがて見知らぬ他人へ、さらに動物へと向かう──利他性が生物学的な起源を超えて普遍的な倫理へと拡張していくプロセスを鮮やかに描きだす現代倫理学の基本文献。日々の選択から地球規模の課題にいたるまで、よりよい世界を願うすべての人に。 二〇一一年版へのまえがき まえがき 第一章 利他性の起源 第二章 倫理の生物学的基盤 第三章 進化から倫理へ? 第四章 理性 第五章 理性と遺伝子 第六章 倫理の新しい理解 引用文献に関する注 二〇一一年版へのあとがき 訳者解説 索引
この書籍は、現代の高度な医療において、生命に関する重要な決定権が誰にあるのかを探る内容です。著者は、様々な視点から「いのち」の判断についての対話を促し、終わり、始まり、質、優先順位などのテーマを扱っています。著者は小林亜津子で、生命倫理学の専門家です。
18世紀スコットランドの哲学者ヒュームの主著『人間本性論』は、これまで認識論的な側面のみ注目されてきたが、むしろ全体的テーマは人間論にあり、その根幹には倫理学がある。ヒュームの倫理思想は功利主義にもカント的な義務論にも属さない「徳(virtue)の倫理学」であることを示しながら、その現代的な意義を明らかにする。 凡例 はじめに 一 問題の所在と本書の目標 二 ヒュームの位置、魅力と独創性 三 テクストに関する方針 四 本書の構成 第一部 認識論的な基礎 第 一 章 ヒュームの信念論 一 認識論をおさえておくべき理由 二 ヒュームの知覚論 三 「信念」の特徴 四 信念のもう一つの特徴 ——「心の作用」 五 「心の作用」が果たす役割 六 「真なる信念」と「偽なる信念」の区別 第 二 章 一般的規則と事実判断 一 「一般的規則」の一般的な特徴 二 想像力の一般的規則 三 陥る錯誤 四 知性の一般的規則 五 反省による信念の活気の減少 六 反省と「心の強さ」 七 極めて危険なディレンマ 第二部 道徳的評価と行為の動機づけ 第 三 章 ヒュームの「道徳的評価」論 一 一般的観点とその導入の背景 二 一般的観点は「道徳的観点」か? 三 「身近な人々の観点」としての一般的観点 四 道徳的評価の説明に見られる間隙 五 道徳的評価と一般的規則 (1)一般的規則 再考 (2)「習慣」と「反省」による一般的規則の区別 (3)道徳的評価の第一の体系 ——個人内部における評価の仕組み (4)道徳的評価の第二の体系 ——社交や会話を通じた評価の仕組み 六 襤褸を纏った徳 七 徳の区分と一般的観点の関与 八 「人間」を見つめるということ 第 四 章 道徳的な行為の動機づけ 一 内在主義と外在主義 ——メタ倫理学とヒューム研究 二 道徳感情の正体? ——伝統的な二つの解釈 三 義務感による行為の動機づけ 四 道徳感情と行為の動機づけ (1)「内在主義—間接情念」説 (2)「内在主義—直接情念」説 五 判断の「動機外在主義」解釈 (1)道徳感情・共感・欲求 (2)行為の動機づけと共感 ——徳倫理学的な動機づけのメカニズム 補 章 「欲求」の捉え方 ——「ヒューム主義」に関する一考察 一 欲求の命題主義的な捉え方とその問題点 (1)マイケル・スミスによるヒューム主義的信念—欲求モデル (2)「適合の向き」の難点 二 ヒューミッシュモデル ——欲求の快楽主義的な捉え方 三 ヒューミッシュモデルの検討 第三部 徳の区分 ——人為と自然 第 五 章 人為的徳論 一 ヒュームのコンヴェンション論と「利益」の問題 二 コンヴェンションの形成とその背景 三 〈自己利益〉および〈共通する利益〉とは何か? (1)〈自己利益〉と〈共通する利益〉 (2)〈共通する利益〉の内実 四 〈共通する利益〉と〈公共的な利益〉 (1)〈共通する利益〉と〈公共的な利益〉は同じものか? (2)公共的な利益〉の内実 五 本解釈の検討 (1)〈公共的な利益〉と二つの社会 (2)〈公共的な効用〉とは何であったのか? 第 六 章 自然的徳と共感 一 自然的徳の特徴 二 共感と自然的徳の及ぶ範囲の拡張 (1)二種類の共感 (2)制限された共感と拡張された共感 第四部 「社交・会話」と「時間軸」 第 七 章 道徳と「社交・会話」 一 一般的観点の採用と社交・会話 二 ヒュームにおける「文明社会論」 (1)『人間本性論』における「文明社会論」 (2)社交・会話と「文明社会論」 三 社交・会話と人間性の増幅 (1)『道徳・政治・文芸論集』における社交・会話 (2)『道徳原理の探求』における「人間性」と「他者への関心」 四 社交・会話と自然的徳の涵養 第 八 章 「道徳」と「人々の意見」、そして「時間」 一 異なる「信念」の取り扱い 二 ヒュームの道徳論における「信念」に関する問題 (1)信念と道徳的行為の動機づけ (2)人々の意見の「権威」と「不可謬性」 三 ヒュームの信念論 ふたたび (1)信念の構成要素 (2)「心の作用」に対する一般的規則と反省の影響 四 人々の意見がもつ権威 (1)信念と意見、習慣と風習 (2)家庭での教育における習慣と風習の一致 (3)人々の意見が権威をもつとはいかなることか 五 人々の意見の不可謬性 (1)「完全な不可謬性」という問題 (2)信念の真偽と一般的規則 (3)人々の意見が不可謬であるとはいかなることか (4)道徳の一般的規則と「時間軸」 終 章 社交と時間の倫理学 あとがき 参考文献 索引(人名/事項)
ソクラテスからデリダまで古典・名著の精粋を抄訳,直接に原典を読むことを通して哲学することの魅惑と苛烈さに誘なう.簡潔な概説とともに,西洋哲学史を一望することができるアンソロジー.巻末に邦訳文献を紹介,教養課程のテキストに最適. 【執筆者】山本巍,今井知正,宮本久雄,藤本隆志,門脇俊介,野矢茂樹,高橋哲哉 第一章 古代哲学 序 哲学の始めと「始め」の哲学 1 ソクラテス以前の哲学 a ミレトス学派 b ヘラクレイトス c パルメニデス d エンペドクレス e デモクリトス 2 アテナイ盛期の哲学 a ソクラテス b プラトン c アリストテレス 3 ヘレニズム期の哲学 第二章 中世哲学 序 旅人の帰郷の哲学 1 キリストと教父たち a 教父哲学の胎動 b 初期教父時代 c 盛期教父時代 d 晩期教父時代 2 学僧たち a 初期スコラ哲学 b 中期スコラ哲学 c 盛期スコラ哲学 d 晩期スコラ哲学 結び 中世哲学の遺産と今日的問い 第三章 近代哲学 序 ヒューマニズムの哲学 1 近代理性の哲学 a デカルト b スピノザとライプニッツ 2 イギリス経験論 a ロック b バークリー c ヒューム 3 ドイツ観念論 a カント b ヘーゲル 第四章 現代哲学 序 実体主義から機能主義へ 1 ニーチェ 2 プラグマティズム 3 論理的言語分析の哲学 a フレーゲ b ラッセル c 前期ウィトゲンシュタイン d 論理実証主義 4 現象学とその周辺 a フッサール b ハイデッガー c ベルクソンからフランス現象学へ 5 分析哲学 a 後期ウィトゲンシュタイン b オースティン c クワイン 6 ヨーロッパ哲学の現在 a ドイツ哲学 b フランス哲学 あとがき/邦訳文献一覧/人名索引
アリストテレスともう一つのメタ倫理学 ヒューム道徳哲学の二つの顔 カントの倫理学とカント主義のメタ倫理学 行為の理由についての論争 自然主義と非自然主義の論争について 道徳的説明についての論争 進化論的暴露論証とはどのような論証なのか 非認知主義についての論争 道徳的非実在論 義務様相表現の意味論 我々は客観主義者なのか? その他の研究動向
本書は、重要な哲学者の思想を平易に解説し、原典資料を集めた手引き書である。内容は古代から現代にかけての哲学の流れをカバーしており、著者たちは各分野の専門家である。
この書籍は、現代医療とバイオテクノロジーの進展が「より健康に、より長く生きたい」という人々の願いをどのように実現しているかを探求しています。しかし、生命科学の進歩が「いのちをつくり変える」領域に踏み込む可能性についても警鐘を鳴らし、新しい倫理観を考える必要性を提起しています。目次では、治療を超えた身体の改造、出生前診断、再生医療、死生観など、多岐にわたるテーマが扱われています。著者は島薗進で、宗教や死生学の専門家です。
西洋文化・伝統の根幹をなす営み、ここに始まる-西洋哲学の全体像を描き出す日本初のシリーズ、第10弾。 総論 始まりとしてのギリシア 1 最初の哲学者たち 2 エレア学派と多元論者たち 3 ソフィスト思潮 4 ソクラテス 5 小ソクラテス学派 6 プラトン 7 アリストテレス 8 テオプラストスと初期ペリパトス学派
本書は、21世紀初頭にオランダで合法化された安楽死について、年間6000人以上の実施が行われている現状を紹介し、自己決定意識の拡大や超高齢化社会の中で、ベルギー、スイス、カナダ、米国へと広がる流れを描く。一方、精神疾患や認知症の人々への適用に関する問題も浮上している。著者は、安楽死の実態や日本における尊厳死の問題、人類の自死に関する思想史を探求し、「死の医療化」の現状を考察する。
この作品は、アリストテレスが「自然学者」と位置づけたソクラテス以前の哲学者たちが、神や自己の内的世界、社会問題に関心を持っていたことを探求しています。タレス、ピュタゴラス、ヘラクレイトスなどの思想を詳細に分析し、彼らの言葉の真価を明らかにすることを目的としています。内容は二部構成で、第一部では哲学者たちの思想を、第二部では彼らの著作の断片を紹介しています。
ハイデガーの「存在の思索」に寄り添いつつ、人類にとって原初の思索・哲学を「みずみずしい姿」で復活させ、従来のギリシア哲学観に変更を求めるとともに、そこから西洋哲学一般、近代科学、人間の思考のあり方そのものに疑問を呈する、過激にして痛烈な現代文明批判の書(上下巻)。 まえがき 本書(上巻)に登場する主な哲学者 生没年早見表 紀元前5世紀ごろのギリシアと周辺諸国地図 第1講 ギリシア哲学俯瞰 言語について 本講義の記述方針 第2講 ミレトスの哲学者(Ⅰ) タレス 哲学者、タレス。 タレスの哲学 コラム:逸話 第3講 ミレトスの哲学者(Ⅱ) アナクシマンドロス アナクシマンドロス哲学の原理 ヒューマニズムを徹底的に超える哲学 アナクシマンドロス、自然の境内に住まう。 第4講 ミレトスの哲学者(Ⅲ) アナクシメネス 哲学者、アナクシメネス。 アナクシメネスの自然哲学 コラム:太古的概念「ピュシス」 第5講 ピュタゴラス 哲学者、ピュタゴラス。 ピュタゴラスとテラトポイイア 第6講 アルキュタス ギリシア世界に確信を持つ哲学者、アルキュタス。 アルキュタスの哲学 コラム一:ピュタゴラス教団 コラム二:ピュタゴラス派の数形而上学 第7講 ヘラクレイトス ロゴスvs主観性 ヘラクレイトスの自然哲学 コラム一:世界大火 コラム二:ヘラクレイトスの出自と著作 第8講 エレア派(Ⅰ) 故郷喪失の哲学者クセノパネス クセノパネスの神観 クセノパネスの哲学 コラム:漂白の哲学者クセノパネス 第9講 エレア派(Ⅱ) パルメニデス(其の一) 天才も存在の構造を脱しえず、パルメニデス。 古代のパルメニデス評価 第10講 エレア派(Ⅲ) パルメニデス(其の二) 近代のパルメニデス解釈史、ないしは誤解史 再び歴史的存在としてのパルメニデスに コラム:哲学者パルメニデス 第11講 エレア派(Ⅳ) ゼノンとメリッソス (1)ゼノン 哲学者、ゼノン。 ゼノンの哲学 (2)メリッソス 第12講 エンペドクレス 哲学者エンペドクレス エンペドクレスの自然哲学 コラム:アクラガスの哲学者エンペドクレス 第13講 アナクサゴラス 伝統の哲学者、アナクサゴラス。 アナクサゴラスの自然哲学 コラム:クラゾメナイの哲学者アナクサゴラス 第14講 デモクリトス 哲学者、デモクリトス。 原子論哲学概観 第15講 ハイデガーと原初の哲学者たち――アナクシマンドロス、ヘラクレイトス、パルメニデス―― 初期ギリシアに対するハイデガーの基本スタンス アナクシマンドロス ヘラクレイトス パルメニデス 回顧と展望 人名索引
哲学はどのように始まったのか? ギリシア哲学史の枠組みを根底から見直し、新たな視点で哲学者たちの思索を一望する記念碑的通史。 古代ギリシアで哲学はどのように始まったのか。近年の研究成果を踏まえギリシア哲学史の枠組みを見直し、哲学者たちの思索を新たな視座から一望する記念碑的通史 全てはここから始まる―― 古代ギリシアで哲学はどのように始まったのか。 人間と社会と自然を根源から問い、わたしたちの生き方・考え方を形作った知の原点。 近年の研究成果を踏まえギリシア哲学史の枠組みを見直し、哲学者たちの思索を新たな視座から一望する記念碑的通史! はじめに 第Ⅰ部 ギリシア哲学史序論 序章1 ギリシア哲学とは何か 1 ギリシア哲学史の哲学的意義/2 ギリシア哲学史の規定/3 ギリシア哲学史の四期区分 序章2 ギリシア哲学資料論 1 古代ギリシア哲学資料の概要/2 中世写本の伝承とテクスト校訂/3 パピュロス断片、金石文/4 断片集の編集 第Ⅱ部 初期ギリシア哲学 A ギリシア哲学の他者 1 エジプト/2 メソポタミア/3 叙事詩の伝統 B 総論 初期ギリシア哲学の枠組み C イオニアでの探究 序 探究(ヒストリアー)の成立 第1章 タレス ――最初の哲学者 1 人物と著作/2 知者/3 自然の探究/4 受容 第2章 アナクシマンドロス ――始源の探究 1 人物と著作/2 無限という始源/3 宇宙論/4 受容 第3章 アナクシメネス ――空気の変容 1 人物と著作/2 空気という始源/3 受容 第4章 クセノファネス ――神を語る詩人哲学者 1 人物と著作/2 酒詩と自然探究/3 神への視点/4 人間の認識/5 受容 第5章 ヘラクレイトス ――謎かけるロゴス 1 人物と著作/2 知への挑発/3 一なる万物/4 人間の生き方/5 受容 D イタリアでの探究 序 イタリアへの伝播 第6章 ピュタゴラス ――魂の教導者 1 人物と資料/2 生の教導/3 哲学の創始/4 受容 第7章 パルメニデス ――「ある」の衝撃 1 人物と著作/2 詩の序歌/3 真理の道/4 思い込みの道/5 受容 第8章 エレアのゼノン ――パラドクスの創出 1 人物と著作/2 逆説/3 受容 第9章 エンペドクレス ――浄化の宇宙詩 1 人物/2 著作/3 浄め/4 自然について/5 詩による真理の体験/6 受容 第10章 フィロラオス ――無限と限定の調和 1 人物と著作/2 ピュタゴラス派哲学の理論化/3 受容 第11章 アルキュタス ――数学者にして政治家 1 人物と著作/2 数学と哲学/3 受容 E イオニアでの自然哲学 序 イオニアの伝統 第12章 メリッソス ――一元論の展開 1 人物と著作/2 「ある」の一元論/3 受容 第13章 アナクサゴラス ――万物の秩序と知性 1 人物と著作/2 万物の混合/3 知性による宇宙生成/4 天体から生物まで/5 受容 第14章 レウキッポスとデモクリトス ――原子論の成立> 1 人物と著作/2 原子論/3 認識論/4 倫理的箴言/5 受容 第15章 アポロニアのディオゲネス ――自然一元論の復活 1 人物と著作/2 空気の一元論/3 受容 第Ⅲ部 古典期ギリシア哲学 A 総論 古典期ギリシア哲学の枠組み B ソフィスト思潮とソクラテス 序 ソフィストをめぐる知的活況 第16章 プロタゴラス ――最初のソフィスト 1 人物と著作/2 徳の教育/3 人間尺度説と神不可知論/4 受容 第17章 ゴルギアス ――言論の力 1 人物と著作/2 言論の技術/3 無の論証/4 受容 第18章 アンティフォン ――弁論の挑発 1 人物と著作/2 弁論術の教育/3 ノモスとフュシス/4 受容 第19章 ソクラテス ――対話による生の吟味 1 人物/2 資料/3 対話と不知/4 徳と知/5 受容 第20章 プロディコス ――言葉の正しさ 1 人物と著作/2 言葉の探究/3 神々について/4 受容 第21章 ヒッピアス ――記憶の博捜 1 人物と著作/2 オリンピック競技会と博識/3 受容 C ソクラテス文学とプラトン 序 ソクラテス文学とソクラテス派 第22章 アンティステネス ――ソフィストとソクラテスのハイブリッド 1 人物と著作/2 弁論術と哲学/3 倫理説/4 言語論/5 受容 第23章 アリスティッポス ――快楽主義の創始者 1 人物と著作/2 快楽の現実主義/3 受容 第24章 プラトン ――対話篇と学園の哲学 1 人物/2 著作/3 解釈の枠組み/4 魂とイデア/5 ディアレクティケー/6 受容 第25章 クセノフォン ――有為な人間の教育 1 人物と著作/2 立派な生と教育/3 受容 第26章 イソクラテス ――弁論と哲学の一致 1 人物と著作/2 弁論術の教育/3 スタイルの実験/4 受容 D アカデメイアとアリストテレス 序 アテナイの哲学学校 第27章 スペウシッポス ――イデアなき多元と分割 1 人物と著作/2 イデア論否定と数学/3 類似性の分類論/4 受容 第28章 クセノクラテス ――イデアと数の一致 1 人物と著作/2 宇宙論的存在論/3 受容 第29章 ヘラクレイデス ――バロックの学問と文学 1 人物と著作/2 文学と対話篇/3 哲学議論の応酬/4 受容 第30章 アリストテレス ――あらゆる学問知識の探究 1 人物/2 著作/3 学問と方法/4 言葉から実在へ/5 自然から形而上学へ/6 人間の幸福/7 受容 第31章 テオフラストス ――自然と人間の観察者 1 人物/2 著作/3 自然学と植物論/4 形而上学/5 性格論/6 受容 第32章 シノペのディオゲネス ――犬と呼ばれた哲学者 1 人物と資料/2 逸話による哲学/3 価値の転倒/4 受容 注 あとがき 参考文献 ギリシア哲学史関連年表 人名索引 事項索引
この文章は、著書の目次と著者情報を紹介しています。目次では、信仰と知の調和をテーマにした哲学者や思想の流れが列挙されており、アレクサンドリアの神学から始まり、アウグスティヌス、トマス・アクィナス、オッカムなどの重要な哲学者が含まれています。著者は慶應義塾大学教授の中川純男で、1948年に広島県で生まれ、京都大学大学院を修了しています。
戦後日本を代表する哲学者、野田又夫によるロングセラー入門書で、ルネサンスから現代までの約80人の哲学者の理論とその背景を解説し、500年の哲学史を概観しています。中世から近世への移行、啓蒙主義とロマン主義の対立、20世紀の実存哲学への発展など、哲学の流れを明らかにしています。目次は近世と現代の哲学の概観に分かれており、詳細な分析が行われています。
フランス現代思想の入門書で、19世紀から現代までの120名の重要思想家を解説しています。気鋭の執筆陣による詳細な説明や図説、歴史的背景を学べるコラムが多数掲載されており、哲学を学び始める人に適した一冊です。著者はフランス哲学や倫理学の専門家で構成されています。
古代ギリシアにおけるデモクラシーの誕生から19世紀までの政治思想の流れを平易に説明したテキスト。 古代ギリシアにおけるデモクラシーの誕生以来の政治思想の流れを平易に説明したテキスト。政治的人文主義や共和主義といった,近年活発に議論されている考え方を盛り込み,グローバル・ヒストリーの時代にふさわしい新しい政治思想史を構想する。 はじめに 政治思想史とは何か 第1章 古代ギリシアの政治思想 第2章 ローマの政治思想 第3章 中世ヨーロッパの政治思想 第4章 ルネサンスと宗教改革 第5章 17世紀イングランドの政治思想 第6章 18世紀の政治思想 第7章 米仏二つの革命 第8章 19世紀の政治思想 結 章 20世紀の政治思想
本書は、西洋哲学の全体像を描く日本初のシリーズの第4弾であり、理性の力の限界について探求しています。目次には、カントやドイツ観念論、ドイツ啓蒙主義、フィヒテ、ヘーゲル、ドイツ自然哲学、ロマン主義などの重要な哲学者と思想が含まれています。
この本は、坂本龍馬や福沢諭吉など25人の歴史的人物を通じて、幕末から明治期にかけての日本の形成について探求しています。激動の社会背景の中で、彼らがどのような日本を目指したのかを考察し、近代日本の歴史を学ぶ内容です。目次は近代への先駆者、国民の形成、アジア・世界の中の日本、体制の変革を志す人々に分かれています。
本書は、実存主義の先駆者キルケゴールの生涯と思想を探求する内容です。キルケゴールは、父との葛藤や恋愛の悲劇を経て、実存的思索に至ります。彼の主要著作には「死に至る病」や「あれかこれか」があり、個別者の真理を神との関係で追求しました。目次では、彼の生涯や思想の各側面が詳述されており、著者は工藤綏夫です。
1930年代、近代西洋の理念に危機が訪れる中、日本で独自の「無」の哲学が生まれました。この哲学は形而上学的原理を批判し、京都学派の哲学者たち(西田幾多郎、田辺元、和辻哲郎、九鬼周造、三木清)の思想をわかりやすく紹介する入門書です。著者は田中久文で、日本の近代哲学を伝統思想と関連づけて考察しています。
本書は現象学の全貌を解説し、空虚になった学問の危機を克服する思想を探求します。著者は、現象学の基本概念や直接経験の重要性、時間と空間の構造、他者との関係について論じています。また、フッサールとハイデガーの哲学的関係を通じて「自分自身で考える人」と「ともに哲学する」ことの意味を考察しています。著者は現代哲学における現象学の意義を強調しています。
本書は、フッサール現象学を単なる哲学の方法論ではなく、西欧形而上学の歴史における重要な出来事として捉え、現代思想の根本問題に新たな解答を提供することを目的としています。著者はフッサールの原テクストに独自の解釈を加え、意識、存在、人間、理性、物、世界に関する問題を探求します。内容は序章から始まり、前期現象学、発生的現象学、人間存在の問題、現代の存在論、そして最後の思想的境位について構成されています。この文庫版は、初版以来多くの知識人に影響を与えた名著です。
「功利主義」に関するよくある質問
Q. 「功利主義」の本を選ぶポイントは?
A. 「功利主義」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「功利主義」本は?
A. 当サイトのランキングでは『功利主義入門: はじめての倫理学 (ちくま新書 967)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで120冊の中から厳選しています。
Q. 「功利主義」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「功利主義」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。