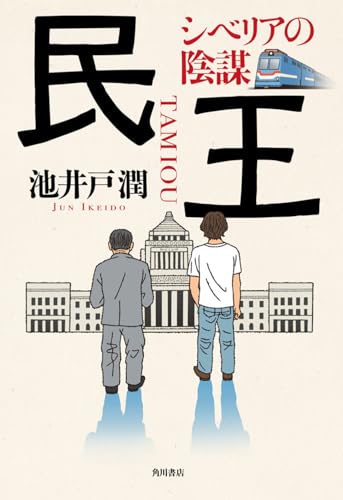【2025年】「政治」のおすすめ 本 153選!人気ランキング
- 政治学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)
- 政治学
- 今さら聞けない! 政治のキホンが2時間で全部頭に入る
- 国際政治学 (New Liberal Arts Selection)
- 政治学の第一歩〔新版〕 (有斐閣ストゥディア)
- 14歳からの政治入門
- 教養としての政治学入門 (ちくま新書)
- 国際政治 - 恐怖と希望 (中公新書 108)
- 国際紛争 -- 理論と歴史 原書第10版
- 政治学 第2版
国民(本人)が政府(代理人)を雇い自らの利益の実現を図るという観点から,政治学の理論や考え方,対象を体系的に解説。2色刷 主権者である国民(本人)が政府(代理人)を雇って自らの利益の実現(共通の目的)を図ると,本人─代理人関係に注目して政治をとらえ,その課題から政治学の理論や考え方,対象を体系的に整理・解説する。事実関係やデータの更新など補訂を施した。2色刷。 序 章 「七人の侍」の政治学 第1部 統治の正統性──政治の課題とは何か 第1章 政策の対立軸/第2章 政治と経済/第3章 自由と自由主義/第4章 福祉国家/第5章 国家と権力/第6章 市民社会と国民国家/第7章 国内社会と国際関係/第8章 国際関係における安全保障/第9章 国際関係における富の配分 第2部 統治の効率──代理人の設計 第10章 議 会/第11章 執政部/第12章 官僚制/第13章 中央地方関係/第14章 国際制度 第3部 統治のプロセス──代理人の活動 第15章 政策過程/第16章 対外政策の形成/第17章 制度と政策 第4部 統治のモニタリング──何がデモクラシーを支えるか 第18章 デモクラシー/第19章 投票行動/第20章 政治の心理/第21章 世論とメディア/第22章 選挙と政治参加/第23章 利益団体と政治/第24章 政 党 引用文献/事項索引/人名索引
政治学のエッセンスが1冊で学べる,コンパクトでリーダブルなテキスト.民主政治の起源,仕組み,概念を明快に解説する.選挙制度,議会と政党,地方自治,グローバル化など,重要なトピックをカバー.政治学の基本を知りたい学生,学び直したい社会人必読. 第1章 民主政治の起源 第2章 民主政治の変容 第3章 福祉と政治 第4章 民主政治のさまざまな仕組み 第5章 選挙 第6章 議会と政党 第7章 政策過程と官僚・利益集団 第8章 世論とマスメディア 第9章 地方自治 第10章 グローバル化 第11章 民主政治の現在 【本文・コラム執筆者】 飯尾潤,池本大輔,犬塚 元,井柳美紀,上神貴佳,内山 融,宇野重規,逢坂 巌,川崎 修,川出良枝,杉田 敦,谷口将紀,中神由美子,早川 誠,前田幸男
この本は、政治や憲法、国会などの基本的な仕組みを、小学生にもわかりやすく解説した「学び直し」の教材です。著者は中学受験の社会科の専門家で、政治に対する理解不足を感じる人々のために、複雑な政治の概念を明確にし、コンプレックスを解消することを目的としています。目次には政治の基本から選挙、裁判所、地方自治、社会保障までのテーマが含まれています。
国際政治学を専攻する3人の著者が,各人の得意分野を生かし,総花的であるよりも深く掘り下げようと心がけて書き上げた教科書。 国際政治を歴史的観点からとらえる,社会科学としての国際政治学を基本的研究手法とする,理論的枠組みをふまえつつ国際政治の諸側面について実証分析を行う,という著者3人が,各人の得意分野を生かし,総花的であるよりも深く掘り下げようと心がけた教科書。 序 章 分析枠組みとしての国際政治学 第1章 国際政治学の見取り図 第2章 国際政治の歴史的視角 第3章 対外政策の選択 第4章 国際秩序 第5章 安全保障 第6章 国際政治経済 第7章 越境的世界 引用文献 事項索引 人名索引
このテキストは、合理的選択と戦略的相互作用の視点から政治を解説した新版の書籍です。内容を見直し、データを更新して読みやすくなっており、ウェブサポートも充実しています。各章では、政治の基本概念から選挙、政党、政策過程、国際政治経済まで幅広く取り上げています。著者は、政治学や行政学の専門家であり、現在は大学教授として活躍しています。
本書は、ジャーナリストの池上彰が中学生を対象に行った特別授業を基に、政治の重要性や選挙の意義について解説します。生徒たちの鋭い質問に答える形で、政治が私たちの生活にどのように関わっているのかを説明し、選挙に行くことの重要性や国の借金の実態についても触れています。授業を通じて生徒たちは政治を身近な問題として捉え、未来に向けての意識を高めることができました。全体を通じて、政治の基本的な知識をわかりやすく伝える内容になっています。
いま政治学では何が問題なのか。政治史・政治理論・国際政治・福祉・行政学など12のテーマで初学者を導く政治学への道案内。 いま政治学では何が問題になっているのか。政治史・政治理論・国際政治・福祉・行政学・地方自治などの専門研究者が12のテーマで初学者を導く政治学への道案内。
この書籍は、戦争の危機がなぜ続くのかという問いに対し、国際政治の現実を分析する入門書です。著者は、軍縮、経済交流、国際機構などを具体的に検討し、国家利益やイデオロギーの絡み合いを踏まえた議論を展開しています。国際関係を単純化せず、現実的な視点から平和の実現を探求しています。著者は高坂正堯で、国際政治学の専門家です。
世界中の多くの大学で使われている国際政治学の定番教科書を,近年の国際紛争の引火点を扱う新章を追加して改訂。2色刷。 世界中の多くの大学で使われている国際政治学の定番教科書の最新版。東欧や中東の紛争,中国の台頭,北朝鮮の脅威など,国際紛争の引火点を理論と歴史の両面から説明する新たな章を加えた。各章の学習目標を示し関連年表を増やし,2色刷となってますます充実。 第1章 世界政治における紛争と協調には一貫した論理があるか? 第2章 紛争と協調を説明する──知の技法 第3章 ウェストファリアから第一次世界大戦まで 第4章 集団安全保障の挫折と第二次世界大戦 第5章 冷 戦 第6章 冷戦後の紛争と協調 第7章 現在の引火点 第8章 グローバリゼーションと相互依存 第9章 情報革命と脱国家的主体 第10章 未来に何を期待できるか?
政治学のエッセンスが学べる好評テキストの最新版。最新の政治状況をふまえて全面改訂。民主政治のしくみと基本的な考え方を明快に解説する。選挙制度、議会と政党、戦後の国際政治とグローバル化など、日本と世界の今がわかるテーマをカバー。学生、社会人必携の一冊。 第1章 民主政治の起源 第2章 民主政治の変容 第3章 福祉と政治 第4章 民主政治のさまざまな仕組み 第5章 選挙 第6章 議会と政党 第7章 政策過程と官僚・利益集団 第8章 世論とマスメディア 第9章 地方自治 第10章 グローバル化 第11章 民主政治の現在
初版刊行以降に起こった国際政治の動きをふまえて新版化。新たに,「科学技術とエネルギー」のunitを追加している。 「歴史」「理論」「アクター」「イシュー」という4つの章から,バランスよく国際政治学を学べると好評の入門テキストの新版。近年の国際政治の動きをふまえて,各unitをアップデートし,さらに新unit「科学技術とエネルギー」を追加。 unit0 国際政治学を学ぶ 第1章 国際政治のあゆみ unit1 主権国家の誕生/unit2 ナショナリズムと帝国主義の時代/unit3 第一次世界大戦/unit4 第二次世界大戦/unit5 冷戦 第2章 国際政治の見方 unit6 パワーと国益/unit7 対立と協調/unit8 支配と従属/unit9 規範と制度/unit10 安全保障/unit11 国際政治経済/unit12 国際政治における文化 第3章 国際政治のしくみ unit13 政治体制/unit14 対外政策決定過程/unit15 外交交渉/unit16 国連の役割/unit17 地域主義/unit18 脱国家的主体 第4章 国際政治の課題 unit19 核/unit20 新しい戦争/unit21 国連PKO,人道的介入,平和構築/unit22 人権と民主主義/unit23 グローバリゼーション/unit24 開発援助/unit25 地球環境問題/unit26 科学技術とエネルギー unit27 さらに国際政治学を学ぶために
目まぐるしく変わり、大きく動く国内外の政治・経済・社会情勢のニュースを見ない日はなく、子どもたちも理解は出来なくとも毎日、その報道を目にし耳にして過ごしているでしょう。そんな時代だからこそ、子どもにはまず「政治」というものの仕組み・考え方・関わり方を理解することが必要と考え本書が企画されました。 本書の特徴は、政治の仕組みの理解で終わらず、そこから一歩進んだ「小学生でも政治参加できる」というメッセージとその方法や事例を掲載していることです。「政治」を生活に密着した身近なものとして感じることを本書の最終的な狙いとしています。 読者である子どもたちに、「政治」を自分事として考えてもらうために、マンガを掲載しています。主人公である小学生4人が、公園の利用方法が変更されたことに不満を抱き、自分たちでできることを考え、行動する物語です。その過程で、「国民主権」「民主主義」「選挙権」などの政治の仕組みを学び、政治への参加も体験します。ストーリー仕立てのマンガで課題を提示してから解説という展開で、共感・理解がしやすい構成となっています。 諸外国では学校教育の中で「政治・社会参加」の学習がされ、若者の積極的な政治参加が見られます。長年、低投票率のままの日本において、子どもたちが「国民一人ひとりの力が政治を決める」という意識を持つことは重要であり、本書がその一助となるでしょう。
好評を得てきた政治学の入門テキストの第4版。政治学の新たな研究成果と,現実政治の変化を反映させ,新版化した。 政治学の入門書として好評を得てきたテキストの第4版。政治学の主な領域の重要な知識を網羅的・体系的に解説するという特長を維持しつつ,新たな研究成果と,日本で起こった政権交代や中東諸国の民主化,世界的な経済危機といった現実の変化を反映させ,新版化した。 序 章 政治学のアイデンティティー 第1章 政治の世界 第2章 政治体制と変動 第3章 政治,経済,福祉 第4章 政治制度と政治過程 第5章 公共政策と行政 第6章 政党と政党制 第7章 政治意識と政治文化 第8章 政治空間の再編成 第9章 近代の国際政治と現代の国際政治 第10章 グローバル・プロブレマティーク 第11章 政治学の潮流 終 章 『現代政治学』からのメッセージ
本書は、ポピュリズムの現象を多角的に分析し、その影響を探る。イギリスのEU離脱やトランプ大統領の誕生、反イスラムなどの排外主義が広がる中、ポピュリズムが民主主義に脅威を与える一方で、ラテンアメリカでは人民解放の力となり、ヨーロッパでは既成政党に改革を促す役割もあると指摘。著者は、ポピュリズムの本質を理解するために、南北アメリカや日本を含む現状を分析している。
本書は、政治に関する基本的な疑問に結論から直接答える新しい形式の入門書です。解散や総辞職の時期、アメリカの大統領選の違い、ロビー活動、小選挙区と比例代表の違い、政党交付金、パレスチナの紛争、ロシアのウクライナ侵攻など、今さら聞けない知識を簡潔に解説しています。忙しい現代人向けにハンディサイズで、スキマ時間に学べる内容となっており、政治をフラットに理解したい人に最適です。著者は公民科教育の専門家で、長年教育に携わっています。
本書は、国際政治学の古典的名著であり、ハンス・J・モーゲンソーの現実主義に基づいています。内容は三部構成で、第一部では国際政治の理論と実践、第二部では権力闘争のメカニズム、第三部では国力の本質とその要素を探求しています。モーゲンソーは、人間の本性に基づく権力と国益の概念を通じて、国際平和の実現を主張しています。
代議制民主主義は、有権者が選挙で政治家を選び、政治家が政策を決定する仕組みである。戦後、黄金期を迎えたが、経済成長の鈍化やグローバル化の影響で機能不全に陥っている。この書籍では、代議制民主主義の本質や存在意義を問い直し、歴史、課題、制度、将来の改革について考察している。著者は京都大学の教授、待鳥聡史氏である。
この本は、早稲田大学の政治入門講義を基にしており、読者を「政治的存在」にすることを目的としています。内容は、価値や人権、教育、労働、階級、結婚、生命、秩序、刑罰、象徴、政府、国民、恐怖などのテーマを扱っています。著者は大田比路で、現在は個人投資家として活動しながら早稲田大学の非常勤講師も務めています。
この書籍は、政治の基本的な仕組みや選挙、国会、内閣、憲法、裁判所、地方自治について詳しく解説しており、政治に対する理解を深めるための決定版です。著者の池上彰は、わかりやすい解説で知られるジャーナリストであり、読者が投票や政治参加を考える際の指針となる内容が盛り込まれています。
角川まんが学習シリーズの『のびーるシリーズ』に新たに社会が登場し、ジェイクとシェリーが地球外生命体ふえーる君と共に日本の政治を学びます。内容は日本国憲法や選挙、国会、内閣、裁判所、地方自治、経済、国際社会など多岐にわたり、カードバトル形式で進行します。楽しみながら政治知識を身につけられる構成で、中学受験や公民の先取り学習にも役立つ解説ページやクイズが充実しています。
本書は比較政治学の主要テーマ(国家建設、民主化、政治制度、福祉国家など)を広く扱い、基礎的概念や中心的課題、最新理論を紹介する。著者は慶應義塾大学の教授、粕谷祐子氏である。
この本は、ドラえもんを通じて政治の仕組みを学ぶ入門書であり、小・中学校の社会科教科書に基づいています。地域の政治や選挙制度、世界の政治形態や歴史など、様々なテーマをわかりやすく解説し、読者に政治を身近に感じさせることを目指しています。著者は鈴木寛で、政治や教育に関する豊富な経験を持っています。家族で楽しめる内容です。
本書は、ピューリタニズムの経済倫理が近代資本主義の発展に寄与したという歴史的逆説を探求するもので、マックス・ヴェーバーの比較宗教社会学的研究の重要な出発点を示しています。内容は、信仰と社会層分化、資本主義の精神、ルッターの天職観念に関する問題提起から始まり、禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理とその宗教的基盤に焦点を当てています。旧版を改訳し、理解しやすい解説が付されています。
本書は、日本国憲法の枠組みの中で展開された戦後日本政治を分析している。自民党と社会党のイデオロギー対立が1960年の安保改定問題でピークに達した後、自民党は経済成長に専念し、一党支配を強化した。80年代末からは「改革」が焦点となり、民主党政権を経た後、第二次安倍政権以降は再び与党と野党が防衛問題を巡って対立している。著者は憲法をめぐる対立に注目し、戦後日本政治の変遷と現在の状況を考察している。
このテキストは、政治思想を時代順に解説し、主要な思想家や重要なキーワードを紹介する内容です。特に「主権」「ナショナリズム」などの基本概念や、近年の「保守・リベラル」「ポピュリズム」「公共性」なども取り上げています。また、日本の政治思想についても触れ、現代に繋がる思想の流れを示しています。著者は成蹊大学、立命館大学、明治大学の教授陣です。
紛争や悲劇は避けることができないのか。どうして日本の政治家の大半は男性なのか。そもそも政治はなぜ必要なのか。東大1、2年生たちの好奇心に応えながら、法学部の政治学系スタッフがそれぞれの研究について熱く語った珠玉の講義。東大で政治を学び、東大から政治を考えよう。 はじめに 第1講 日本の有権者と政治家――序論にかえて(谷口将紀) 第2講 政治とは、国際政治とは――戦争と平和の問題を中心に(遠藤乾) 第3講 「冷戦の終わり方」を問い直す――ドイツ統一をめぐる国際政治史研究を題材に(板橋拓己) 第4講 「利益誘導」の条件――日仏の政治史を比較すると何が見えるか?(中山洋平) 第5講 現代アメリカの政治――「分断」の由来と大統領の挑戦(梅川健) 第6講 「中国化」の中国政治――習近平のアイデンティティ政治を読み解く(平野聡) 第7講 自由をめぐる政治思想(川出良枝) 第8講 「公共」と政治学のあいだ――日本政治思想史の視角から(苅部直) 第9講 戦前の政党内閣期が示唆すること(五百旗頭薫) 第10講 現代日本の官僚制と自治制――行政研究の焦点(金井利之) 第11講 ジェンダーと政治(前田健太郎) 第12講 憲法をめぐる政治学(境家史郎) 第13講 租税政策をめぐる福祉国家の政治――比較の中の日本(加藤淳子)
田中角栄は高等小学校卒ながら卓越した金銭感覚と人心掌握術で若くして政界で重要な役職を歴任し、最終的には総理大臣に就任した。「今太閤」「庶民宰相」と称され、国民からの支持を受けた彼の知られざる素顔を、金権政治を批判してきた著者が描く。
この本は、「日本がもしも100人の島だったら?」という視点から、経済の基本的な仕組みをわかりやすく解説しています。金利、国債、為替、インフレなどの難解な概念を簡潔に理解できるようにし、読者が自分の意見を持てるようになることを目指しています。目次には、経済の基礎から国家の役割、景気や物価、貿易と為替、そして未来の課題まで多岐にわたるトピックが含まれています。著者は経済評論家や学者で、一般向けに最新の経済学を解説することに定評があります。
数ある名言集の中でも、推奨に値する名言集だと云えます。その名言より、処世術、人との関わり方など、言葉と短い補足と画像のビジュアルで、より記憶に焼き付きやすく。いつどこで活用できるのか?わかりませんが、咄嗟の判断ができる男に魅力がないわけがなく。行動だけでなく判断力も身につく新しい参考書と思えるような書籍でした。
この書籍は、日本政治の裏側と表側を深く理解するための重要な一冊であり、特に小沢一郎氏の政治活動に焦点を当てています。著者は、小沢氏の政権交代に対する理解や、彼が直面した敗北からの立ち直りを通じて、日本政治の課題を浮き彫りにしています。内容は、小沢氏への独占インタビューを基に、民主党政権や自民党の権力構造、政治改革の必要性などを探求し、今後の日本政治に向けた道標を示しています。政治に関心のある人々にとって必読の書です。
リベラル・デモクラシーというしくみに注目し,歴史の大きな流れをたどりつつ,政治のルールや政治学の基本的知識を解説する。 「右」「左」「イデオロギー」「公共性」……。政治を語るうえでよく目にする言葉や政治学の基本的知識を,歴史・思想をふまえて丁寧に説明していきます。政治なんて縁遠いと感じている人も,まずは本書で政治のルールやしくみを学んでみよう。 はじめに 政治学にようこそ 第1部 いまの政治はどのように動いているか 第1章 仕事としての政治 第2章 選挙 第3章 政党 第4章 政体と政治過程 第5章 政治とメディア 第2部 リベラル・デモクラシーの歩み 第6章 近代日本のリベラル・デモクラシー 第7章 戦後日本のリベラル・デモクラシー 第8章 リベラル・デモクラシーのめばえ 第9章 国民国家と民主化の時代 第10章 イデオロギーと世界戦争 第3部 これからの政治 第11章 デモクラシーというやり方 第12章 公と私 第13章 国境を越える政治 第14章 ユートピアとディストピア 終章 政治学はどんな学問だろうか
政治学で用いられる多様な方法を,体系的かつ平易な言葉で説明し,それぞれの方法の特徴や相互の関係を明らかにする。 社会科学の他分野の問題関心や考え方を柔軟にとりいれ,さまざまな分析手法が用いられる政治学。そうした多様な方法を,近年の研究蓄積もふまえて,体系的かつ平易な言葉で説明する。それぞれの方法の特徴や相互の関係を明らかにし,政治学の方法の俯瞰図を示す。 第1章 政治学の方法とは 第2章 事例研究 第3章 計量分析 第4章 フォーマル・モデリング 第5章 実験の方法 第6章 政治学の方法の展開 引用・参考文献/読書ガイド/索引
学校改革の旗手と「哲学対話」を広める教育学者が教育の本質を徹底議論! 究極の目的は「民主主義」教育だった。 学校改革の旗手と「哲学対話」を広める教育学者が教育の本質を徹底議論! 究極の目的は「民主主義」教育だった。 ★ベストセラー『学校の「当たり前」をやめた。』著者 元麹町中の校長と、「哲学対話」で著名な教育哲学者が初タッグ! ★宿題廃止、全員担任制、合唱コンクール廃止… 究極の狙いは「民主主義」教育だった! ★教育関係者・必読のあらたな羅針盤 分断の時代を生きる子どもたちに必須の「対話の力」とは? ★親も注目! ビジネスパーソンの現場にも役立つ必須知識 「教育の役割とは何か?」 「学校は何のためにあるか?」 学校改革の旗手と教育の本質を問い続けてきた哲学者・教育学者が 教育の本質を徹底議論! 究極の目的は「民主主義」教育だった。 ーー「多数決で決めよう」のどこに問題があるか、わかりますか? 「誰一人置き去りにしない」を教えるはずの教室で 平然と少数派を切り捨て、 一度決めたことには従え! と「従順な子」をつくる教育がおこなわれている。 未来の社会をつくる子どもたちに本当に伝えるべきことは、 対立を乗り越え、合意形成に至るプロセスを経験させることではないか。 学校で起きるトラブルこそが絶好の学び場であるはず…… 本書は、子どもたちの「対話の力」を重視し、 学校で民主的な力をいかに育むかを提案する実践的教育書だ。 民主主義の考え方を広めていくことで 当事者意識が低い「日本社会」をアップデートする、 著者二人のつよい覚悟を持って書かれた。 いじめ、理不尽な校則、不登校、体罰、 心の教育、多数者の専制、学級王国・・・ いまの学校が抱える大問題を分析しながら 何ができるか、どこから変えていけるか、 哲学と実践を見事につなぐ画期的1冊。 現場で奮闘する教育関係者・保護者、必読! 序章 学校は何のために存在するか──いま本当に身につけてほしい力 工藤勇一 トラブルは絶好の学びの場/教育の究極の目標/「殴らなきゃ生徒はわからないよ」/民主的な学校の条件/なぜいま、教育と民主主義なのか/従順さを求める教育を終わりにする/哲学から実践への橋渡し 1章 民主主義の土台としての学校──全員が合意できる「最上位目標」を探せ 「多数決で決めよう」のどこが問題か、わかりますか?/デモクラシーの歴史/少数派を切り捨てない「対話の方法」/多数決を使っていいときの「条件」/起点としての「自由の相互承認」と「一般意志」/ 公教育の役割を再定義する/自由な社会なら何をしてもいいのか/学校って「自分の将来のため」にあるの?/ラーニングコンパス2030の衝撃/ロシアのウクライナ侵攻をどう見るか/当事者意識の低い日本/「問題は、あなたが行動を起こすかどうかだ」 2章 日本の学校の大問題──民主主義を妨げる 6つの課題 課題1 ─ 心の教育:「思いやり」で対立は解消できない/嫌いな人がいたってかまわない/子どものへの愛情なんて見えないもの 課題2 ─ いじめ問題:「いじめ撲滅」の発想がいじめを増やす/逃げ場のない学校設計への提言 課題3 ─ 教員養成 :家族システムから考える「日本人の従属性」 課題4 ─ 理不尽な校則:「ルールは守るもの」と教える学校教育 課題5 ─ 学級運営:「学級王国」大好きな教員たち/「教師の仮面」を脱げ! 課題6 ─ 教師の問題:どんな教育なら「よい」と言えるのか 3章 学校は「対話」で変わる──教育現場でいますぐできる 哲学と実践 政治教育はいらない/学校運営を子どもに託すというやり方/子どもが変われば、保護者も変わる/ 合意をめざすアプローチーー超ディベート/生徒会の定期的なスクラップ&ビルドを/スピーチ指導を徹底する理由/理想とのギャップに苦しむ教員へ/「校則づくり」は注意が必要/これからのリーダーに求められる条/校長でなくても一人の教師から変えられる/保護者が学校を変えたい、と思ったら/意識改革は3つのステップで進む/みんなが元気になる三者面談 終章 教育を哲学するという意味 苫野一徳 “本質”を問う哲学/志の連鎖/「読書対話の会」への誘い /教育学がなすべき使命
安全保障を考える際に基礎となる概念や政策を,歴史的事象を事例に理論的に考察する。バランス・オブ・パワーや戦争原因を追加。 なにゆえ国際政治学は,安全保障に多大な関心を寄せてきたのか。セキュリティ・ディレンマ,失う恐怖,抑止,核戦略,危機管理,同盟など,基礎となる概念や政策を,歴史的事象を事例に理論的に考察する。バランス・オブ・パワー論や戦争原因論を追加し全体を改訂。 第二版まえがき 初版まえがき 第1章 はじめにツキュディデスありき 第2章 アナーキーという秩序 第3章 安全保障 第4章 セキュリテイ・ディレンマ 第5章 失う恐怖の国際理論 第6章 抑止のディレンマと抑止失敗 第7章 核戦略と現代の苦悩 第8章 国際危機と危機管理 第9章 なぜ同盟は形成され,存続するのか 第10章 未来からの教訓─同盟が終わるとき 第11章 バランス・オブ・パワー《新規》 第12章 戦争はなぜ起こるのか《新規》 終 章 国際政治の悲劇を避けられるか 《新規》 第二版あとがき 初版あとがき
政治をどのように読み解くか.政治についてどのように思考するか.金融市場の肥大化,政治基盤の液状化,イデオロギーの現代的展開などを踏まえて政治はどこへ向かうのかを展望する,定評あるテキストの待望の改訂版. 序論 第一章 現代政治学の展開 第二章 理論・概念・価値判断 第一部 原論 第一章 人間 第二章 政治 第三章 権力と政治権力 第四章 政治システム・政府 第五章 正統性 第六章 リーダーとリーダーシップ 第七章 公共の利益と公民の徳 第二部 現代民主政治論 第一章 民主政治 第二章 民主政治の諸条件 第三章 民主政治の制度 第四章 投票行動と政治意識 第五章 政党 第六章 官僚制 第七章 利益集団 第八章 政治経済体制と民主政治 第九章 エスノポリティクス 第一〇章 政治思潮とイデオロギー むすび 政治判断について
この書籍は、日本の政党政治の可能性と選挙による変革について解説しています。著者は、選挙制度、政党組織、権力分立、選挙管理の各側面を取り上げ、政治に対する理解を深めるための12の重要なポイントを提示しています。著者は大阪大学の准教授であり、行政学や地方自治を専門としています。
本書は、明石市長を務めた泉房穂氏が、日本の政治を変えるために闘った経験を記録したものです。彼は、10歳で「優しい社会」を実現する決意をし、47歳で市長に就任。議会やマスコミ、利権に囲まれながらも、市民の支持を得て新たな政治闘争を宣言します。内容は、彼の市長選挙の勝利、政治家引退の真相、行政の問題点、そして「誰一人見捨てない社会」を目指す姿勢について語られています。
現代世界を理解するためには,それを形作ってきた歴史を把握することが必要不可欠である.16世紀から第二次世界大戦終結に至る国際関係史を,ヨーロッパからアメリカ大陸,アジア,アフリカ,中東まで広く視野に入れ,平易かつ丁寧に描いた決定版通史. 第I章 ヨーロッパの勢力拡張開始期の世界 第II章 大西洋圏の諸革命とウィーン体制 第III章 イギリスの経済的優越と新たな国民国家の登場 第IV章 帝国主義の時代の国際関係 第V章 帝国主義世界とヨーロッパの大国間関係 第VI章 第一次世界大戦と国際情勢の新展開 第VII章 パリ講和と戦後世界の混乱 第VIII章 相対的な安定の回復 第IX章 国際秩序の崩壊と戦争の勃発 第X章 地球規模の戦争としての第二次世界大戦 終章 国際関係史の中の第二次世界大戦 参考文献/年表
この書籍は、アメリカにおける反知性主義の背景とその影響を探るもので、特にキリスト教がこの風潮を育んできたことに焦点を当てています。著者は、反インテリの風潮、キリスト教の盛況、ビジネスマンの自己啓発、極端な道徳主義の政治などの現象を、歴史的視点から解明し、反知性主義の恐ろしい力と意外な利点を描写しています。著者は森本あんりで、国際基督教大学の教授や副学長を務めています。
主権国家体系の成立と展開に着目し歴史的な観点から国際政治の歩みを辿る。宗教改革からトランプ大統領の誕生までをこの一冊で。 現代の世界は,どのようにして成り立ってきたのか。主権国家の成立とその地理的拡大,そしてその部分的な変容に着目し,歴史的な観点から国際政治の歩みをたどる。宗教改革からトランプ大統領の誕生までの約500年間の国際政治の大きな流れをつかむ。 序 章 なぜ国際政治史を学ぶのか 第1部 主権国家体系の誕生と展開 第1章 近代主権国家体系の生成 第2章 勢力均衡とナショナリズム 第3章 帝国主義の時代 第2部 2度の世界大戦 第4章 第一次世界大戦の衝撃 第5章 第一次世界大戦後の国際秩序 第6章 国際秩序の崩壊 第3部 冷 戦 第7章 冷戦の起源と分断体制の形成 第8章 グローバル化する冷戦 第9章 冷戦体制の変容 第10章 冷戦終結への道 第4部 主権国家体系を超えて 第11章 湾岸戦争とソ連解体 第12章 EUの誕生と深化・拡大 第13章 冷戦後の地域紛争・民族紛争 第14章 新興国の台頭 第15章 21世紀の国際政治
国を追われた二匹のアマガエルが夢の楽園にたどり着くが、その国は「三戒」と「謝りソング」で守られている。しかし、凶暴なウシガエルの脅威が迫り、楽園の真実が明らかになる。この物語は現代の寓話であり、国家の意味を問いかける作品として一部では「予言書」とも呼ばれている。著者は百田尚樹で、彼は放送作家から作家として成功を収めた。
民主主義、自由主義、共和主義、そして社会主義。今日の政治を支える重要思想を一望し、政治を主体的に考える知性を磨く白熱の講義。 民主主義だけでは民主主義は機能しない。それを補完・抑制する自由主義、共和主義、社会主義などの重要思想を一望し、政治について考えることの本質に迫る。 民主主義だけでは、民主主義は成り立たない? プラトン、アリストテレスからカント、ヘーゲル、ラスキまで、 今日の政治を支える重要思想を一望する 近年、民主主義の危機が叫ばれ、その重要性を訴える議論が巻き起こっている。だが、民主主義を擁護するだけで本当に今日の「危機」は回避できるだろうか。むしろ、民主主義それ自体がポピュリズムなどの現象を招いているのではないか。本書では、政治思想が「民主政」批判から始まったことに注目しつつ、民主主義だけでなく、それを補完・抑制する原理としての自由主義や共和主義、社会主義などを取り上げ、それぞれの歴史的展開や要点を整理していく。民主主義を機能不全から救い出すために何が必要か、その核心に迫る白熱の講義。 === まえがき(空前の「民主主義」ブーム?/「選挙は大事」というけれど……/政治「思想」の重要性) 序章 人間と政治――なぜ市民が政治学を学ぶのか 1 政治責任について――「政治」というあまり気乗りのしない営み(「政界」と「政治の世界」/原罪としての政治責任/法律、道徳、政治) 2 人為と自然――運命としての政治?(人間特有の営みとしての政治/政治と運命/政治責任からの逃走/無為から生じる政治責任/政治的決断――政治と学問の対立/半神半獣としての人間) 3 政治リテラシーの涵養に向けて(政治と道徳/「悪さ加減の選択」としての政治/政治の世界の複雑性/「政治思想」とは何か/本書のアプローチ) 第1章 民主主義――それだけで十分か 1 古代民主政の誕生と衰退――デモクラシーの揺籃期(民主政以前の時代の運命観と政治観/「政治」の誕生――自然から人為へ/暴力から言葉へ/ノモスを相対化する視点/ペロポネソス戦争とピュシスの主観化/ソクラテスとソフィストの対決/ソクラテスの死) 2 古代民主政の実践と政治思想の誕生(プラトンの絶望と民主政批判/アリストテレスの哲学と国制分類論/穏健な民主政と過度な民主政) 3 近代民主主義の誕生――政治理念からエートスへ(一般意志は代表されえない/現在主義の問題/政治的実践としての近代民主主義/エートスとしての民主主義/後見人を求める民衆) 4 現代民主主義のもう一つの思想的基盤(ルソーの文明社会批判/エリートに対する軽蔑/失われた「自然」への憧憬/ニーチェの刹那主義) 5 民主主義の現在(頭数を数えるデモクラシー/転機としての第一次世界大戦/いわゆる「おまかせ民主主義」/政党の存在意義) 第2章 自由主義――なぜ生まれ、なぜ根づいたのか 1 古代世界に見られるリベラリズム的要素(ヘレニズム思想/パンとサーカス/キリスト教の登場/「神の国」と「地の国」) 2 中世におけるリベラリズムの萌芽(立憲主義の萌芽/議会主義の萌芽/資本主義を支えるエートス) 3 リベラリズムの体系化(自由主義の出発点としてのロック/ロックの所有権論/ロックの社会契約論/モンテスキューの三権分立論/イギリスにおける議院内閣制の成立/ヒュームの「黙約」論/ヒュームの文明社会論の思想史的意義/「共感」を求める人間本性/スミスの経済的自由主義) 4 社会に浸透するリベラリズム(法学者ベンサムの功利主義思想/近代社会というパノプティコン/パノプティコンと新救貧法/ヴィクトリアニズムという監獄/ウィッグの反民主主義思想/J・S・ミルの「思想の自由市場」論/スペンサーの社会進化論/「自然」の領域の変遷/進歩に対する楽観) 5 リベラリズムの現在(権力の制限という諸刃の剣/自由主義の陥穽) 第3章 リベラル・デモクラシー――歴史の終着点か 1 民主主義と自由主義の交錯(J・S・ミルの危害原理/ワイマール憲法の穴/シュミットの議会主義批判/喝采と民主主義/〈等価性の世界〉における決断主義) 2 リベラル・デモクラシーの隘路(「歴史の終わり」?/〈国制〉に対する過信/公的なものへの冷笑) 第4章 共和主義――誰もが「市民」になれるか 1 古代における共和主義の誕生(共和主義の三つの要素/プラトンの哲人王思想/アリストテレスの混合政体論/古代ローマの共和政/キケロの共和政擁護論) 2 近代における共和主義の継承(ルソーの民主政批判/自然的自由から市民的自由へ/ルソーの「一般意志」論/カントの哲学的前提/カントのパターナリズム批判/他律と自律/賢くある勇気/カントにおける共和主義と共和政) 3 民主主義と共和主義の逆転(ベンサムの民主主義/ベンサムの共和主義/過渡期としてのJ・S・ミル) 4 隠された共和主義の伝統(ヘーゲルの遺産/止揚される市民社会/ヘーゲルのロマン主義批判/混合政体としての立憲君主政/海を渡るヘーゲル/グリーンの「知的愛国者」論/ラスキの「多元的宇宙」論/ラスキの「思慮なき服従」批判) 5 共和主義と日本(忠誠と反逆/失われゆく〈武士のエートス〉/現代に生き続ける共和主義的制度/現代に生き続ける共和主義的精神/共和主義的シティズンシップ) 第5章 社会主義――過去の遺物か 1 マルクス主義と社会学――根本にある発想(「政治思想」としての社会主義/マルクスのヘーゲル批判/モノと化した人間たち/マルクスの下部構造論/マルクスの夢見た社会/社会学と社会調査の貢献/マンハイムの知識社会学) 2 自由主義と社会主義の融合(グリーンの「積極的自由」概念/ホブハウスの自由主義的社会主義/社会主義と民主主義の相補関係/ホブハウスの客観主義的権利論) 3 自由主義と社会主義の反発(ラスキのマルクス主義受容と計画社会論/ケインズのニューリベラリズム/ラスキの計画民主主義論/対抗イデオロギーとしてのネオリベラリズム/福祉国家と畜群としての大衆/小括) 終章 民主主義を活かすために――なぜいま政治思想か(政治思想と人間/人民の召使としての政治家/政治責任と希望について/リベラル・デモクラシーの超克) 読書案内/あとがき/参考文献/人名索引
泉房穂市長の著書は、障害を持つ弟への「復讐」として市長になった経緯や、明石市での革新的な政策、コロナ禍の中での自治体の役割、そして日本の政治への希望を伝えています。著者は明石市民としての視点から、社会を変える方法をまとめており、特に子どもや高齢者、障害者福祉に力を入れた施策が市の好循環を生んでいることを強調しています。
20世紀とはいかなる時代であったのか? 帝国主義、2つの大戦、冷戦、地域紛争の惨禍を経験した激動の世紀の実像を手際よく描き出し、多元主義的国際社会実現の可能性を考える。豊富な図版・資料とともに、現代の国際政治の流れを新たな叙述で描き切った信頼のテキスト。 序 章 20世紀と国際政治 1 「国際社会」 と 「国際政治」 2 20世紀はどんな時代であったか 第Ⅰ部 2つの世界大戦の時代 第1章 帝国主義の時代と第一次世界大戦 1 帝国主義の時代 2 第一次世界大戦と各国の戦争目的 第2章 第一次世界大戦後の国際体制 1 ロシア革命とウィルソンの14カ条 2 大戦の終結とヴェルサイユ講和会議 3 ヴェルサイユ=ワシントン体制 第3章 1930年代危機と第二次世界大戦の起源 1 世界恐慌と国際体制の崩壊 2 ファシズム諸国の対外侵略と宥和政策 3 第二次世界大戦への道 第4章 第二次世界大戦 1 枢軸国の攻勢と戦線の拡大 2 反ファシズム連合の形成 3 ヨーロッパ第二戦線問題 第5章 第二次世界大戦の終結と戦後秩序 1 戦後秩序の形成 2 大戦の終結と諸結果 第Ⅱ部 冷戦と地域紛争の時代 第6章 冷戦の起源とヨーロッパの分裂 1 米、ソの戦後政策と冷戦の起源 2 ヨーロッパ分断への政治過程 第7章 冷戦と超大国の支配 1 覇権システムとしての冷戦体制 2 アジアと冷戦 第8章 冷戦の諸相 1 冷戦と核兵器体系 2 デタントから冷戦終結へ 第9章 冷戦後の世界と地域紛争 1 「冷戦後」 と地域紛争 2 民族・宗教と地域紛争 —— ユーゴスラヴィア 第10章 中東紛争と湾岸戦争 1 中東紛争と大国の歴史的責任 2 湾岸戦争とその遺産 第11章 テロとの戦争 —— アフガニスタンとイラク 1 9.11事件とアフガニスタン戦争 2 イラク戦争と国際秩序 終 章 21世紀の国際社会と国際政治 1 その後の国際社会 2 21世紀の課題 付 録 : 国際連合憲章
幕末から冷戦終結に至る130年余の日本の近代国家形成を,対外問題とそれへの権力の対応を中心に分析・考察する。 近代国家は,国民の上に巨大な力を及ぼす一方で,国民の支持なしには存在できない。また,内政と国際関係が密接に結び付く。幕末から冷戦終結に至る130年余の日本の近代を,中央レベルの政治権力を対象として分析・考察する。「植民地とその後」を加筆。 第1章 幕藩体制の政治的特質 第2章 西洋の衝撃への対応 第3章 明治国家の建設 第4章 政府批判の噴出 第5章 明治憲法体制の成立 第6章 議会政治の定着 第7章 日清・日露戦争 第8章 帝国の膨張 第9章 政党政治の発展 第10章 国際協調と政党内閣 第11章 軍部の台頭 第12章 帝国の崩壊 第13章 敗戦・占領・講和 第14章 自民党政治の発展 第15章 国際秩序の変容と冷戦の終焉 補 章 植民地とその後
気鋭の若手研究者が、既存の政治学に進化論的なパラダイムシフトを迫る壮大かつ野心的な試み。 気鋭の若手研究者が、既存の政治学に進化論的なパラダイムシフトを迫る壮大かつ野心的な試み。 進化政治学(evolutionary political science)とは、1980年代の米国政治学界… 気鋭の若手研究者が、既存の政治学に進化論的なパラダイムシフトを迫る壮大かつ野心的な試み。 進化政治学(evolutionary political science)とは、1980年代の米国政治学界で生まれた概念。進化心理学を中心とする進化論的視点から政治現象を分析する手法で、欧米では最先端だが、外交史研究が主流な日本ではほぼ皆無ともいえる状況。科学哲学の科学的実在論、進化心理学、脳科学、歴史学といった諸分野の知見を総動員し、新たな進化政治学に基づいたリアリスト理論を構築する。 “戦争と平和の問題に関心を寄せる国際政治学者にとっては、個々の進化政治学的知見を国際政治研究に組み入れるだけでなく、進化政治学という革新的なアプローチ自体がいかなる意義や論争をはらんでいるのか、こうした点を科学哲学の議論を踏まえつつ方法論に自覚的な形で再考することが必要とされている”(「まえがき」より) 序 章 進化政治学に基づいた国際政治研究 第1章 進化政治学とは何か ――その理論的基盤とそれをめぐる論争 第1節 進化政治学の起源と前提 第2節 進化政治学の基盤としての進化心理学 第3節 進化政治学をめぐる論争 第2章 進化政治学の政治学への貢献 ――科学的実在論の視点からの一考察 第1節 政治心理学を例として―究極要因による至近要因の統合 第2節 リアリズムを例として―理論を科学的に裏付ける 第3章 国際政治理論はいかにして評価できるのか ――新たな方法論的枠組みの構築に向けて 第1節 決定不全性に由来する国際政治理論研究への批判 第2節 科学的実在論による決定不全性の克服 第3節 新たな方法論的枠組み―科学的実在論に基づいた実証主義の再構築 第4章 新たなリアリスト理論 ――進化政治学に基づいたリアリスト理論 第1節 セイヤーの進化的リアリズム―その意義と限界 第2節 新たなリアリスト理論―進化のリアリスト理論 第3節 進化のリアリスト理論のインプリケーション 第5章 ナショナリズムと戦争 ――ナショナリスト的神話モデル 第1節 ナショナリズムとリアリズム―指導者によるナショナリスト的神話作り 第2節 部族主義の心理メカニズム―内集団への愛と外集団への敵意 第3節 新たなリアリストモデル―ナショナリスト的神話モデル 第4節 比較事例研究―第一次世界大戦、日中戦争、ウクライナ危機 第6章 過信と対外政策の失敗 ――楽観性バイアスモデル 第1節 楽観性バイアスとは何か―肯定的幻想と不協和低減効果 第2節 新たなリアリストモデル―楽観性バイアスモデル 第3節 事例研究―日ソ中立条約締結に至る日本外交 第7章 怒りの衝動と国家の攻撃行動 ――怒りの報復モデル 第1節 怒りの修正理論とは何か―幸福の交換比率と憤りのシステム 第2節 新たなリアリストモデル―怒りの報復モデル 第3節 比較事例研究―日独伊三国軍事同盟、太平洋戦争 終 章 進化政治学に基づいた国際政治研究の展望 第1節 総括―進化政治学はいかにして戦争を説明するのか 第2節 本研究に想定される批判 第3節 本研究のインプリケーション―学際的アプローチの重要性 第4節 今後の研究課題―進化政治学は平和を説明できるか 第5節 結語―自然科学と社会科学の統合に向けて
本書は比較政治学における政治制度とその政治的・経済的帰結の関係を新制度論の視点から整理し紹介しています。目次には、制度論、選挙制度、執政制度、政党制度、議会制度、官僚制、司法制度、中央銀行制度、中央・地方関係制度が含まれています。著者は建林正彦、曽我謙悟、待鳥聡史の3名で、それぞれの専門分野における経歴や業績が紹介されています。
この書籍は、日本の政治が右傾化しているのか、あるいは「普通の国」になろうとしているのかを探る内容です。著者は、日本社会が右へと進む過程を詳細に分析し、新しい右派連合の形成とその影響を考察しています。目次では、旧右派連合の歴史や新右派への転換、自由と民主主義の危機、そしてリベラル左派の再生の可能性について論じています。著者は中野晃一氏で、比較政治学や日本政治を専門としています。
政治と経済の相互作用に着目し,理論と歴史/事例分析/展望の3部構成で現代の国際社会が抱える問題を解説するテキスト第3版。 政治と経済の相互作用に着目し,「理論と歴史」「事例分析」「展望」の3部構成で現代の国際社会が抱える問題を解説する。新版以降の国際社会と国際政治経済学の変化をふまえ,各章をヴァージョンアップするとともに,新たに「金融」「移民」の章を設けた。 第3版はしがき 序 章 「経済」の論理と「政治」の論理 第1部 国際政治経済学の理論と歴史 第1章 国際政治経済の見方 第2章 力の構造と国際経済体制 第3章 冷戦とブレトンウッズ体制 第2部 国際政治経済体制の動態 第4章 安全保障と経済 第5章 保護貿易をめぐる政治と経済 第6章 金融グローバル化の構図 第7章 科学技術と現代国際関係 第8章 移民をめぐる政治と経済 第9章 経済発展と人権,民主化 第10章 地球環境をめぐる政治経済 第3部 国際政治経済秩序の模索 第11章 グローバル・レベルの国際秩序の模索 第12章 リージョナル・レベルの国際秩序の模索 第13章 ナショナル・レベルからの国際秩序の模索 終 章 国際政治経済学の未来像 補 論 研究の手引き
ヘーゲルの最後の主著は、主観的な正しさよりも客観的な理法を重視しており、特に倫理について家族、市民社会、国家の観点から論じています。著者ヘーゲルは近代ドイツの重要な哲学者で、社会的現実における人間の理解を深め、マルクスに影響を与えました。藤野渉と赤沢正敏は、著者の情報として記載されています。
女子中学生のジュリが法律の神様ジャスと出会い、法律のないパラレルワールドに連れて行かれる物語。無法の世界での奇想天外な出来事を通じて、六法のしくみや考え方が学べる内容。著者は法律の専門家であり、大学で法学を教えている。
「御威光」の支配から文明開化へ——激動の時代に生み出された政治をめぐる思想を,まったく新しい視点でとらえなおす通史.徂徠,宣長,そして武士や女性など,いかに生きるべきかを問い,苦闘する人々の,真摯な思索の軌跡をたどる. 序 章 本書への招待 第一章 「中華」の政治思想——儒学 第二章 武士たちの悩み 第三章 「御威光」の構造——徳川政治体制 第四章 「家職国家」と「立身出世」 第五章 魅力的な危険思想——儒学の摂取と軋轢 第六章 隣国の正統——朱子学の体系 第七章 「愛」の逆説——伊藤仁斎(東涯)の思想 第八章 「日本国王」のために——新井白石の思想と政策 第九章 反「近代」の構想——荻生徂徠の思想 第十章 無頼と放伐——徂徠学の崩壊 第十一章 反都市のユートピア——安藤昌益の思想 第十二章 「御百姓」たちと強訴 第十三章 奇妙な「真心」——本居宣長の思想 第十四章 民ヲウカス——海保青陵の思想 第十五章 「日本」とは何か——構造と変化 第十六章 「性」の不思議 第十七章 「西洋」とは何か——構造と変化 第十八章 思想問題としての「開国」 第十九章 「瓦解」と「一新」 第二十章 「文明開化」 第二十一章 福沢諭吉の「誓願」 第二十二章 ルソーと理義——中江兆民の思想 あとがき
本書は、対中半導体輸出規制などの「経済の武器化」が進む中で、国際社会における「パワー」の本質を探求しています。目に見えない権力、例えば通信ネットワークの管理や通貨のコントロールが地政学的な力として重要であることを示し、米中対立の中でも米国が超大国としての地位を維持する理由を解明しています。さらに、米国の地経学的パワーを再評価し、その持続的な発揮のための国際秩序のあり方を提案しています。
著者真山仁は、ロッキード事件に関する疑問を解明するため、事件の全貌を再検討します。検察の主張の不整合や重要な証言の見落とし、隠された「児玉ルート」の真実を探り、戦後から続く日米関係の暗部を明らかにします。目次では、事件の背景や裁判の不正、角栄の葬られた理由などが取り上げられています。
本書は、ネットショッピングや買い物に関心がある人々に向けて、行動経済学の知識を活用し、無駄な買い物を避けるための実践的なガイドです。内容は、ネットでの買い物の失敗を避ける方法や、損をしやすいセールやサブスクリプションについての考察、選択肢の広げすぎに注意するポイント、大きな買い物に関する知識などが含まれています。著者は橋本之克で、行動経済学を基にしたマーケティングやブランディングの専門家です。
高畠通敏、佐々木毅、三谷太一郎という、「日本の政治学の歴史の中で、新しい時代を切り開く新しい政治観を作り上げた」政治学者の著作を丹念に読み込み、その全体像に迫る。 小野塚喜平次、吉野作造、南原繁、丸山眞男、京極純一を取り上げた『おのがデモンに聞け』の〝続編〟! まえがき 第1章 高畠通敏における「市民の政治学」 はじめに――戦後政治学の最終走者 1 歩く戦後思想史のような人 2 衝撃のデビュー作二つ 3 六〇年安保からベ平連まで――『思想の科学』の時代 4 運動と現場の政治学 5 政治改革批判 第2章 佐々木毅と政治学の運命 はじめに――佐々木政治学の画期性 1 政治学史への関心 2 現代アメリカの思想と政治 3 現代日本の思想と政治 4 政治学原論へ 第3章 三谷太一郎における歴史の消去 はじめに――三谷政治史学の特質 1 原敬の政治指導 2 思想家吉野作造 3 昭和戦前期の政治と軍事と思想 4 吉野作造と丸山眞男 終 章 誰のための政治学か――結びに代えて あとがき 主要人名索引
この書籍は、日本の戦後史における対米隷属の歴史を探るもので、著者は元外交官の孫崎享。日本の政治家たち(石橋湛山、岸信介、田中角栄、小沢一郎など)が、アメリカとの関係でどのように葬られてきたのかを分析している。著者は、対米交渉や基地問題を通じて、日本の国家のあり方を問い直し、戦後の真実を明らかにしようとしている。各章では、安保闘争の真相や対米自主派の政治家たちの運命、日米関係の不平等性について詳述されている。
『Modern Political Analysis』の第五版は、1963年の初版以来、アメリカ政治学の教科書として定番となっており、著者ダールの理論を分かりやすくまとめています。権力や影響力についての詳細な議論からポリアーキーの概念までを扱い、重要な部分も新たに訳出されています。目次には政治の定義、影響力の記述・解釈・評価、政治システムの共通性と違い、ポリアーキーの説明、政治的人間についてなどが含まれています。著者はイェール大学の名誉教授ダールと、立教大学の名誉教授高畠です。
本書は、日本の地方政府の実態と変貌を、政治制度、国との関係、地域社会・経済の観点から分析しています。地方分権改革によって、教育や介護、空き家問題などの身近な課題に取り組む地方自治体に力が与えられ、国家の2.5倍の支出と4倍の人員を持つ地方政府の構造が描かれています。著者は曽我謙悟で、行政学や現代日本政治を専門としています。
本書は、プラトンがソクラテスの処刑を契機に、正義の実現には国家の在り方をも問う必要があると考えた結果、哲人統治の思想を提示する作品です。プラトンの対話篇の中でも特に重要な位置を占めています。
この書籍は、投資とニュースの基本をわかりやすく解説し、図解を通じて理解を深める内容です。著者の崔真淑氏は、株価の決まり方や経済指標の読み方、政治の影響、金融の仕組み、ビジネスニュースと株価の関係、銘柄選定のポイントなどを扱っています。初心者でも理解しやすいように構成されており、投資に役立つ情報が詰まっています。著者は経済学者であり、メディアでの解説経験も豊富です。
本書は、日本の経済成長が停滞する中で、大都市、特に大阪の役割に焦点を当てている。大阪は橋下徹の「大阪都構想」を通じて変革を遂げ、注目を集めている。著者は、大都市が新たな成長のエンジンになり得るかを探り、大阪の歴史や橋下と大阪維新の会の支持の理由を分析している。
この書籍は、1993年に誕生した欧州連合(EU)が直面する複合的な危機について分析しています。ユーロ危機、難民流入、テロ事件、イギリスの離脱などの試練を経て、EUが崩壊するのか、その原因や影響を探ります。著者はEUの歴史的背景と現状を考察し、今後の欧州と世界の展望を示しています。著者は国際政治とヨーロッパ政治の専門家、遠藤乾です。
総理に返り咲いた著者による経済・外交安保の「政権公約」を附したベストセラーの完全版。保守の姿、この国のあり方を説く必読の書。 真の保守とは何か? 総理に返り咲いた著者による経済・外交安保の「政権公約」を附したベストセラーの完全版。保守の姿、この国のあり方を説く必読の書。
『国家』の第六巻から第十巻では、ソクラテスを通じた理想国における哲人統治の概念が展開され、哲学者が学ぶべき内容が探求されます。善のイデアや哲学的認識について、「太陽」「線分」「洞窟」の比喩を用いて説明され、最終的に正義が人間の幸福をもたらすと結論づけられています。
本書は、政治の基本概念や仕組みを分かりやすく解説した入門書です。政治の成り立ちや日常生活との関連を理解し、合意形成の重要性を学ぶことができます。著者は、政治が難解ではなく、私たちの生活に直結していることを示し、子供にも教えたくなる内容を提供しています。
マックス・ヴェーバーの講演記録で、政治の本質や政治家に求められる資質と倫理について語られています。彼は、困難な状況でも「それにもかかわらず!」と言える自信を持つ人が政治に向いていると主張しています。
「大阪維新」の政治について,有権者の維新への支持態度を実証的に分析することによって明らかにし,民主主義の可能性を探る。 「大阪維新」の政治について,有権者の維新への支持態度を実証的に分析することによって明らかにする。サーベイ実験などの手法を用いて,維新に扇動された有権者といったポピュリズム論を反証する。また有権者の批判的志向性を見出し,民主主義の可能性を探る。 序章 課題としての維新支持研究 第Ⅰ部 問いと仮説 第1章 維新をめぐる2つの謎 第2章 維新政治のパズルを解く 第Ⅱ部 維新支持と投票行動 第3章 維新支持とポピュリズム 第4章 なぜ維新は支持されるのか:維新RFSEによる検証 第5章 維新ラベルと投票選択:コンジョイント実験による検証 第Ⅲ部 特別区設置住民投票 第6章 都構想知識の分析 第7章 投票用紙は投票行動を変えるのか:投票用紙フレーミング実験による検証 第8章 特別区設置住民投票下の投票行動 終章 我々は民主主義を信頼できるのか 補論A 批判的志向性は反対を促すか:サーベイ実験による検証 補論B 都民ファーストの躍進とポピュリズム
「達成される政策目標」として「平和」をとらえ,国際紛争の時代の「平和政策」を体系的にまとめた初めてのテキスト。 「達成されるべき政策目標」として「平和」をとらえ,国際紛争の時代の「平和政策」を体系的にまとめた初めてのテキスト。国際政治の基礎理論,国際紛争の実態,平和構築の実際について第一級の執筆陣が的確に分析・考察する。国際紛争や国際関係の初学者に最適。 序 章 政策としての平和=藤原帰一 第Ⅰ部 国際紛争をどうとらえるか 第1章 国際紛争はどうとらえられてきたのか=藤原帰一/第2章 現代紛争の構造とグローバリゼーション=遠藤誠治/第3章 国際法と国際組織の役割=山田哲也/第4章 地域機構は役に立つのか=坪内 淳/第5章 紛争と国際経済組織=大芝 亮 第Ⅱ部 現代国際紛争の実態 第6章 植民地支配の遺産と開発途上国=半澤朝彦/第7章 兵器はどう規制されてきたか=佐渡紀子/第8章 核軍拡と核軍縮=水本和実/第9章 人の移動と難民保護=栗栖薫子/第10章 テロリズムとテロ対策=宮坂直史 第Ⅲ部 平和構築の実際 第11章 軍事介入=星野俊也/第12章 平和構築における政治・法制度改革=篠田英朗/第13章 紛争後選挙と選挙支援=上杉勇司/第14章 国際犯罪と刑法=〓山佳奈子/第15章 開発協力=広瀬 訓/第16章 平和構築とジェンダー=竹中千春/第17章 NGOと市民社会=大西健丞 終 章 国際紛争をこえて=山田哲也
近代と向き合い、格闘し、支えた思想家たちの思考のエッセンスを平易に解説、自由と公共をめぐる思想的遺産を縦横に論じて、現代社会をよりよく考える基盤を指し示す。政治・経済・哲学の枠を超え、近代社会の通奏低音をなす思想の姿を浮かび上がらせた、刺激に満ちた最良の道案内。 序 章 社会思想とは何か 1 社会思想の歴史とは何か 2 社会思想史の方法 3 「時代」 と 「思想」 の文脈 4 社会思想の基本問題 —— 「自由」 と 「公共」 の相関 第1章 マキアヴェリの社会思想 1 「時代」 の文脈 —— 市場経済の復活と近代国家の胎動 2 「思想」 の文脈 —— イタリア・ルネサンスの人文主義 3 マキアヴェリの 「問題」 4 『君主論』 の人間観 5 『ディスコルシ』 の共和制論 6 マキアヴェリにおける 「自由」 と 「公共」 第2章 宗教改革の社会思想 1 「時代」 の文脈 —— 近代国家の出現と市場経済の発展 2 「思想」 の文脈 —— ルネサンスから宗教改革へ 3 宗教改革思想の 「問題」 4 ルターの信仰義認論と万人司祭主義 5 カルヴァンの予定説と資本主義の精神 6 宗教改革思想における 「自由」 と 「公共」 第3章 古典的 「社会契約」 思想の展開 1 「時代」 の文脈 —— 国際商業戦争の幕開け 2 「思想」 の文脈 —— 科学革命から自然法学へ 3 社会契約思想の 「問題」 4 ホッブズの機械論的人間観と絶対主権の理論 5 ロックの理性的人間観と政治社会論 6 社会契約思想における 「自由」 と 「公共」 第4章 啓蒙思想と文明社会論の展開 1 「時代」 の文脈 —— 文明社会の発展 2 「思想」 の文脈 —— フランスとスコットランド 3 啓蒙思想の 「問題」 4 フランス啓蒙の文明社会像 —— ヴォルテールから重農主義まで 5 スコットランド啓蒙の文明社会像 —— ハチソンとヒューム 6 啓蒙思想における 「自由」 と 「公共」 第5章 ルソーの文明批判と人民主権論 1 「時代」 の文脈 —— 文明社会の危機 2 「思想」 の文脈 —— 啓蒙から文明批判へ 3 ルソーの 「問題」 4 『社会契約論』 における一般意志と人民主権 5 ルソーにおける 「自由」 と 「公共」 第6章 スミスにおける経済学の成立 1 「時代」 の文脈 —— 文明社会の危機を超えて 2 「思想」 の文脈 —— 啓蒙から社会科学へ 3 スミスの 「問題」 4 『道徳感情論』 における共感と道徳秩序 5 『国富論』 における分業・市場・富裕 6 スミスにおける 「自由」 と 「公共」 第7章 「哲学的急進主義」 の社会思想 —— 保守から改革へ 1 「時代」 の文脈 —— 二重革命のはじまり 2 「思想」 の文脈 —— バークとマルサス 3 哲学的急進主義の 「問題」 4 功利主義の思想 —— ベンサムとジェームズ・ミル 5 古典派経済学の思想 —— リカードウの 『経済学原理』 6 哲学的急進主義における 「自由」 と 「公共」 第8章 近代自由主義の批判と継承 —— 後進国における 「自由」 1 「時代」 の文脈 —— 二重革命の光と影 2 「思想」 の文脈 —— カント、フィヒテ、ロマン主義における自我の発見 3 ヘーゲルの 「問題」 4 ヘーゲルの学問論と市民社会論 5 ヘーゲルにおける 「自由」 と 「公共」 第9章 マルクスの資本主義批判 1 「時代」 の文脈 —— 資本主義の危機 2 「思想」 の文脈 —— マルクス以前の社会主義 3 マルクスの 「問題」 4 哲学批判 —— 『経済学・哲学草稿』 から 『ドイツ・イデオロギー』 へ 5 『資本論』 の資本主義批判 6 マルクスにおける 「自由」 と 「公共」 第10章 J・S・ミルにおける文明社会論の再建 1 「時代」 の文脈 —— 資本主義の変化と民主主義の進展 2 「思想」 の文脈 —— 哲学的急進主義の再検討 3 ミルの 「問題」 4 哲学と道徳の革新 5 社会主義の可能性 6 ミルにおける 「自由」 と 「公共」 第11章 西欧文明の危機とヴェーバー 1 「時代」 の文脈 —— 帝国主義と大衆社会 2 「思想」 の文脈 —— 実証主義の諸潮流 3 ヴェーバーの 「問題」 4 『職業としての学問』 と近代合理主義の起源 5 『職業としての政治』 と民主主義の運命 6 ヴェーバーにおける 「自由」 と 「公共」 第12章 「全体主義」 批判の社会思想 —— フランクフルト学派とケインズ、ハイエク 1 「時代」 の文脈 —— 世界大戦、ロシア革命、大恐慌 2 「思想」 の文脈 —— 全体主義批判の諸相 3 全体主義批判の 「問題」 4 『啓蒙の弁証法』 の資本主義文明批判 5 ケインズとハイエクにおける2つの自由主義 6 全体主義批判における 「自由」 と 「公共」 第13章 現代 「リベラリズム」 の諸潮流 1 「時代」 の文脈 —— 社会主義体制の成立と崩壊 2 「思想」 の文脈 —— 「歴史の終わり」 か 「文明の衝突」 か 3 現代リベラリズムの 「問題」 4 ハーバーマスとロールズ 5 ロールズにおける公正としての正義 6 現代リベラリズムにおける 「自由」 と 「公共」 終 章 社会思想の歴史から何を学ぶか 1 方法からの問い 2 現代における 「自由」 と 「公共」 の可能性
いかにして世界は再編されているのか? 21世紀世界を支配するに至った新自由主義の30年の政治経済的過程とその構造的メカニズムを世界的権威が初めて明らかにする 渡辺治《日本における新自由主義の展開》収載 新自由主義(ネオリベラリズム)とは―― 「市場の公平性」こそが「倫理」であり、国家・社会の機能のすべて、人間の行為のすべてを導くことができるという指針である、という教義である。1970年代以降、小さな政府・民営化・規制緩和・市場の自由化などを旗印にして、先進国から途上国までグローバルに浸透していき、思想的にも現実的にも21世紀世界を支配するものとなった。 では、新自由主義とは、どうして発生し、どのように各国政府に取り入れられ、いかに各国民の同意をも取りつけていったのか? それは誰によって、誰のために推し進められてきたのか? そして世界をいかなるものに再編しているのか? 本書は、世界を舞台にした30年にわたる政治経済史を追いながら、その構造的メカニズム、その全貌と本質を明らかにするものである。 序文 第1章 自由とはこういうこと 新自由主義への転換はなぜ起こったのか? 新自由主義理論の台頭 新自由主義化と階級権力 自由の展望 第2章 同意の形成 アメリカにおける同意形成 イギリスにおける同意形成 第3章 新自由主義国家 理論における新自由主義国家 緊張と矛盾 実践における新自由主義国家 新保守主義の台頭 第4章 地理的不均等発展 新自由主義化のムービングマップ 新自由主義化の最前線 メキシコ/アルゼンチンの崩壊/韓国/スウェーデン 地理的不均等発展のダイナミズム 第5章 「中国的特色のある」新自由主義 国内の変遷 対外関係の変遷 階級権力の再構築? 第6章 審判をうける新自由主義 新自由主義化のバランスシート あらゆるものの商品化 環境の悪化 権利の両義性 第7章 自由の展望 新自由主義の終焉 オルタナティブに向けて 付録 日本の新自由主義――ハーヴェイ『新自由主義』に寄せて 渡辺治 序 ハーヴェイ「新自由主義論」の問題提起と日本の位置 1 日本の新自由主義への動きは、いつ始まったのか? 2 日本の新自由主義の「敵」は誰か? 3 日本での新自由主義改革への合意は、いかなる特質を持つか? 4 新自由主義化と帝国主義化の併存 5 日本の新自由主義改革遂行過程のジグザグ 6 新自由主義国家の特殊性 7 新自由主義と新保守主義 8 日本の新自由主義の帰結と矛盾 訳者あとがき 森田成也 基本用語解説/参照文献一覧/事項索引/人名索引/地名索引
古代ギリシアにおけるデモクラシーの誕生から19世紀までの政治思想の流れを平易に説明したテキスト。 古代ギリシアにおけるデモクラシーの誕生以来の政治思想の流れを平易に説明したテキスト。政治的人文主義や共和主義といった,近年活発に議論されている考え方を盛り込み,グローバル・ヒストリーの時代にふさわしい新しい政治思想史を構想する。 はじめに 政治思想史とは何か 第1章 古代ギリシアの政治思想 第2章 ローマの政治思想 第3章 中世ヨーロッパの政治思想 第4章 ルネサンスと宗教改革 第5章 17世紀イングランドの政治思想 第6章 18世紀の政治思想 第7章 米仏二つの革命 第8章 19世紀の政治思想 結 章 20世紀の政治思想
ついに全面新改訂! 国と人を守る論理──初版刊行以来、読者の圧倒的な支持を得てきた定番が、11年目にして大改訂を施した。執筆陣も若返り、アップ・ツー・デートな問題意識で「いま問われるべき課題群」に切り込んだ。教科書に、討論の刺激剤に、そして安全保障的思考の訓練に使える一冊。 新訂第4版へのはしがき 初版へのはしがき 第1部 安全保障学入門 第1章 安全保障の概念 1 普遍的定義の欠如 2 伝統的な安全保障概念とその変容 3 新しい安全保障の諸概念 第2章 戦争と平和の理論 1 国際システムからみた国家間戦争の生起 2 二国間関係からみた国家間戦争の生起 3 国家からみた国家間戦争の生起 4 内戦の発生原因 第3章 国際安全保障体制論 1 国際安全保障体制とは 2 覇権モデル 3 勢力均衡モデル 4 集団安全保障モデル 5 集団防衛モデル 6 協調的安全保障モデル 7 「共通の安全保障」モデル 8 ポスト冷戦時代の安全保障体制 第4章 安全保障とパワー 1 ハードパワー・ソフトパワー・スマートパワー 2 パワー行使の諸形態 3 軍事力と安全保障 4 情報と安全保障 5 科学技術と安全保障 第5章 核と安全保障 1 核兵器国の核戦略 2 核拡散の動向 3 核兵器と国際政治 第6章 軍備管理・軍縮 1 軍縮と軍備管理の概念 2 軍備管理・軍縮の諸形態 3 「軍備管理・軍縮」から「軍縮・不拡散」へ 第7章 政軍関係論 ── シビリアン・コントロール 1 現代の軍事組織 2 軍事専門職主義 3 シビリアン・コントロール 第8章 現代紛争の管理 1 紛争の諸形態 2 紛争の予防と管理 3 人道的介入 4 信頼醸成措置 5 危機管理 6 紛争解決 第9章 安全保障の非軍事的側面 1 非軍事的安全保障の概念的枠組み 2 非軍事的安全保障の諸目的 3 安全保障の非軍事的手段 第10章 非伝統的脅威と安全保障 1 「非伝統的脅威」とは何か 2 テロリズム 3 海賊 4 越境組織犯罪 5 大量破壊兵器の拡散 第11章 国連と安全保障 1 集団安全保障機構としての国連 2 冷戦と国連の集団安全保障の空洞化 3 国連平和維持活動(PKO)の発達 4 冷戦の終結と国連の平和機能の活性化 5 『平和の課題』 6 ガリ構想の実践と挫折 7 『平和への課題への追補』 8 ブラヒミ・レポート 9 国連平和機能強化の限界 第12章 1 国際法の法的性質 2 集団安全保障 3 武力紛争法 第13章 ポスト九・一一の安全保障 1 冷戦の終結 2 秩序構想の不在と現実の先行 3 脅威の性格の変化と安全保障への二種類のアプローチ 4 安全保障環境の地域的不均質性 5 九・一一テロ・世界秩序・米国の役割 6 平和と軍事力に関する発送転換の進行 7 安全保障工具の新次元 第2部 日本の安全保障政策の基礎知識 Ⅰ 戦後日本の安全保障政策 Ⅱ 防衛計画の大綱 Ⅲ 日本の安全保障政策の原則 Ⅳ 日本の安全保障関連法制 Ⅴ 日米同盟 Ⅵ 集団的自衛権 Ⅶ 日本の国際平和協力活動 Ⅷ 日本の地域安全保障協力 Ⅸ 日本の軍縮・不拡散政策 Ⅹ 日本の危機管理体制 ⅩⅠ 日本のテロ対策 ⅩⅡ ミサイル防衛 ⅩⅢ 非伝統的安全保障への取り組み 参考文献 執筆者紹介
一九世紀ヨーロッパを代表する政治家、ビスマルクの業績は華々しい。一八七一年のドイツ帝国創建、三度にわたるドイツ統一戦争での勝利、欧州に同盟システムを構築した外交手腕、普通選挙や社会保険制度の導入-。しかし彼の評価は「英霊」から「ヒトラーの先駆者」まで揺れ動いてきた。「鉄血宰相」「誠実なる仲買人」「白色革命家」など数多の異名に彩られるドイツ帝国宰相、その等身大の姿と政治外交術の真髄に迫る。 第1章 「破天荒なビスマルク」として-ある若きユンカーの苦悩 第2章 代議士として-政治家ビスマルクの「修業時代」 第3章 外交官として-外交家ビスマルクの「遍歴時代」 第4章 プロイセン首相として-革命を起こされるよりは起こす 第5章 北ドイツ連邦宰相として-「プロイセンの政治家」から「ドイツの政治家」へ 第6章 ドイツ帝国宰相として-ビスマルク体制下のドイツ帝国 第7章 「誠実なる仲買人」として-ビスマルク体制下のヨーロッパ 第8章 カリスマ的存在へ-フリードリヒスルーでの晩年
E・H・カーから、ヴァンダナ・シヴァまで。変容し続ける国際関係の現実を批判的に乗り越え、オルタナティブを目指すための30冊。 第1部 「現実」をめぐって 第2部 法・規範と自由 第3部 資本と配分的正義 第4部 主権と権力 第5部 ヘゲモニーと複数性 第6部 「周辺」からの声と政治
現在の民主主義国の政治に焦点を絞り,議会や政党,宗教や文化,司法政治といった分野を扱う新しい比較政治学のテキスト。 現代の民主主義国の政治に焦点を絞って,議会や政党はもちろん,文化,宗教,司法など,さまざまな分野を取り上げて説明していく新しい比較政治学のテキスト。世界的に民主主義が後退していると言われる今こそ,民主主義国の政治のしくみをじっくりと考えてみよう。 第1章 国家形成 第2章 現代民主主義の定義と指標化 第3章 民主主義の多様性 第4章 選挙政治 第5章 政党政治 第6章 執政政治 第7章 議会政治 第8章 司法政治 第9章 地方政治 第10章 文化と政治 第11章 宗教と政治 第12章 政治経済 第13章 福祉政治 第14章 社会と政治
国連は創設60年を迎え改革論議が活発化し,EUは拡大と憲法の批准拒否に揺れ,他の地域的機構やNGOは多様な展開を見せるなど,国際機構は大きなうねりの中にある.国際機構の全体像を示し現代世界におけるその存在意義を問うテキスト,待望の全面改訂. 第1章 国際機構小史 第2章 国際連合 第3章 国連改革 第4章 地域的国際機構 第5章 国際機構創設の動因 第6章 構造・機能・意思決定 第7章 国際機構論の方法 第8章 国際機構の理論化
この書籍は、政治を身近な問題として理解できるように解説した入門書の改訂版で、イラストや図表を用いて概念を整理しています。内容は政治の基本概念から民主主義、福祉国家、選挙、世論、政党、地方自治まで幅広くカバーしています。著者はそれぞれ大学の准教授で、政治学に関する専門知識を持っています。
新興国の政治現象を理解する上で重要なテーマに絞って従来の研究を,構造,制度,アクターという3つの着眼点に分けて説明する。 ある政治現象を説明しようとするとき,どういった点に着目すればよいのか。新興国の政治現象を理解するうえで重要なテーマをとりあげ,これまでの研究成果を,構造,制度,アクターという3つの着眼点に分けて,体系的に説明する。 第1章 比較政治学の方法と着眼点 第2章 国 家 第3章 民主化 第4章 民主主義体制の持続 第5章 権威主義体制の持続 第6章 内 戦 第7章 執政制度 第8章 政党制度 第9章 軍 第10章 社会運動 第11章 民族集団 第12章 民主主義の質 第13章 新自由主義改革 第14章 比較政治学の方法と着眼点の活用法
「政治」に関するよくある質問
Q. 「政治」の本を選ぶポイントは?
A. 「政治」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「政治」本は?
A. 当サイトのランキングでは『政治学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで153冊の中から厳選しています。
Q. 「政治」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「政治」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。











![『国際政治学をつかむ 新版 (テキストブックス[つかむ])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41ziJ8jIRoL._SL500_.jpg)