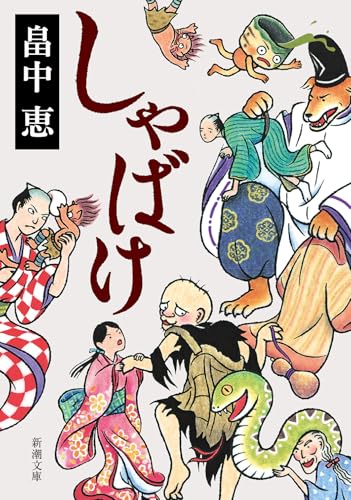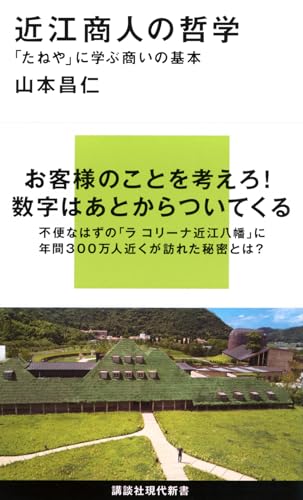【2026年】「江戸」のおすすめ 本 139選!人気ランキング
- 燃えよ剣(上) (新潮文庫)
- 関ケ原(上) (新潮文庫)
- 宮本武蔵(一) (新潮文庫)
- 孤宿の人(上) (新潮文庫)
- 風林火山 (新潮文庫)
- 村上海賊の娘(一)
- 壬生義士伝 上 (文春文庫 あ 39-2)
- 新装版 竜馬がゆく (1) (文春文庫)
- 八朔の雪―みをつくし料理帖 (ハルキ文庫 た 19-1 時代小説文庫)
- 新選組血風録 新装版 (角川文庫)
この作品は、幕末の動乱期に新選組副長として剣に生きた土方歳三の生涯を描いています。彼は武州石田村の百姓の子として生まれ、喧嘩好きと組織作りの才能を活かして、新選組を強力な集団へと成長させました。物語は、彼の影響が日本の歴史にどのような波紋を投げかけたかを探ります。著者は司馬遼太郎で、彼の作品は歴史小説の新たな地平を切り開き、多くの賞を受賞しています。
新選組の土方歳三の視点で、幕末を描いた小説。新選組の存在や土方歳三の存在はもちろん知っていたが、具体的にどんな人だったのか?は知らなかった。燃えよ剣を読んで強い組織の作り方や時流に乗る大切さや信念を貫き通すかっこよさなどを学べた。歴史が好きならぜひ読むべき1冊。
この作品は、豊臣政権の崩壊と家康による権力掌握を描いた歴史小説で、戦国時代の主要な武将たちの人間像を浮き彫りにしています。著者の司馬遼太郎は、戦闘の詳細や人物の苦闘を通じて、歴史の深い洞察を提供しています。
関ヶ原で生き延びた武蔵と又八は、お甲・朱実母娘の助けを受けた後、武蔵は故郷に戻るが追われる身となる。憎しみに満ちた武蔵は次々と敵を討つが、沢庵は「護るための剣」とは何かを問いかける。武蔵が二天一流の開祖に至るまでの成長を描いた物語。著者は吉川英治。
讃岐国・丸海藩で、九歳の少年が捨て子同然に置き去りにされ、藩医の井上家に引き取られる。しかし、井上家の琴江が毒殺され、領内では不審な毒死や謎の事件が続発する。著者は宮部みゆきで、多くの文学賞を受賞している。
大坂の南部藩蔵屋敷に満身創痍の侍、吉村貫一郎がたどり着く。彼は貧しさから脱藩し、新選組に入隊した“人斬り貫一”として恐れられながらも、困っている人々には優しさを示す男。元隊士や教え子たちが彼の非業の生涯を語る。浅田次郎の作品で、全日本人の心を揺さぶる文学の金字塔として評価され、第十三回柴田錬三郎賞を受賞している。
坂本竜馬の劇的な生涯を中心に、幕末維新期に活躍した若者たちを描いた長篇小説。竜馬は土佐の郷士の次男で浪人ながら、重要な歴史的出来事に大きな影響を与えた。
坂本龍馬の半生を綴った物語。坂本龍馬に対して歴史の教科書で学ぶくらいの知識しかなかったが、これを読むことで幕末の時代を駆け抜けた坂本龍馬という男に対する理解が深まる。激動の時代を生き抜く今の日本を形作った男の生き様を知ることで勇気をもらえる。
佐伯泰英の代表作「居眠り磐音」が全51巻の〈決定版〉として刊行開始。第一巻『陽炎の辻』では、豊後関前藩の若き武士3人が帰藩後に斬り合い、坂崎磐音が江戸・深川で浪人生活を始める様子が描かれる。彼は用心棒として働きながら、幕府を揺るがす陰謀に巻き込まれていく。著者は時代小説の新たなジャンルを確立し、多数の著作を持つ。2019年には松坂桃李主演の映画も公開予定。
応仁の乱前夜、孤独な少年・才蔵は、ならず者の頭目・骨皮道賢に見込まれ、市中警護役としての道を歩む。才蔵は蓮田兵衛に預けられ、彼から世の中を学び、厳しい棒術修業を経て生きる力を身につける。史実を基にしたこの小説は、混沌とした時代を描いた記念碑的な作品である。著者は垣根涼介。
織田信長が天下布武を掲げていた時期、陸奥の南部家では内紛が続いていた。九戸党の棟梁・政実は新たな時代を予見し、宗家を見切る。戦の天才「北の鬼」九戸政実が一族を率いて東北を駆け巡る物語が描かれた、著者の故郷を舞台にした歴史巨編「陸奥3部作」の最終章が文庫化された。著者は高橋克彦。
戦国時代の武田軍団が信長の侵攻からわずか一ヶ月で滅びた理由を探る歴史小説。信玄の死後、武田勝頼は内外の脅威や財政問題、家臣との対立に苦しむ中、同盟国の北条家から嫁いだ桂姫が彼の苦悩を理解し、両家の絆を深めようと奮闘する。著者の伊東潤は新鋭の歴史小説家として注目されている。
徳川家康は、戦国時代の混乱を収束させ、長期政権の基盤を築いた人物です。三河松平家の後継ぎとして生まれ、幼少期は今川家の人質として過ごしましたが、卓越した政治力で地位を確立しました。信長の急死後、秀吉が天下を狙う中での彼の活動が描かれています。著者の司馬遼太郎は、歴史小説の革新者として多くの賞を受賞し、明晰な歴史観で知られています。
戦国時代初頭、松波庄九郎は還俗し、美濃国を拠点に国盗りを目指す。彼は油商奈良屋の財産を奪い、斎藤道三の若き日の活躍と策略を描いた歴史物語。著者は司馬遼太郎で、彼は歴史小説の革新者として多くの賞を受賞した。
小間物問屋の若おかみ・おりんの水死体が発見され、同心・木暮信次郎は彼女の主人・清之助の不審な眼差しに気づく。事件はただの飛び込みと見られるが、信次郎は清之助に興味を持ち、岡っ引・伊佐治と共に真相を追う。男たちが“闇”と“乾き”の中で見つける救済の姿を描いた哀感溢れる時代小説。著者はあさのあつこ。
戦国時代、豊臣秀吉が関東の北条家に攻撃を仕掛ける中、難攻不落の「浮城」忍城を守る成田長親は、わずか500の兵で秀吉の約2万の大軍に立ち向かう。長親は従来の武将とは異なり、武・智・仁をもって領民の信頼を得ている。本作は新しい英傑像を描いた戦国エンターテインメント小説で、40万部を超え、本屋大賞で第2位を獲得した。著者は和田竜。
本書は、1945年の敗戦後、日本で一人の男、国岡鐡造が石油会社「国岡商店」を立ち上げ、困難を乗り越え再起を図る物語です。彼は全てを失いながらも、従業員を守りつつ、石油を武器に新たな戦いに挑む姿を描いています。著者は百田尚樹で、作品は経済歴史小説として感動的な内容が特徴です。
現代のヒーロー“光る君”として描かれた源氏物語の新たな解釈を通じて、平安時代の愛と葛藤を描いた長編小説。美貌と知性を持つ源氏が、許されぬ恋や苦しい恋を重ねる様子が描かれ、上巻には特定の巻が収められている。著者は田辺聖子で、受賞歴が豊富な作家。
豆腐職人の永吉が江戸に移り、妻おふみと共に店を開く物語。京と江戸の味覚の違いに悩みながらも、二人は成長し、子供たちの人生を通じて親子二代の物語が描かれる。著者は山本一力で、第126回直木賞を受賞した作品。
『天地明察』は、徳川四代将軍家綱の治世に、日本独自の暦を作るプロジェクトが立ち上がる物語です。従来の暦は正確さを失っており、改暦の実行者として選ばれた渋川春海が、算術に生き甲斐を見出しながら「天」との壮絶な勝負に挑む様子を描いています。この時代小説は日本文化に大きな影響を与えた計画を背景に、個人の成長物語としても感動的に展開され、第7回本屋大賞を受賞しました。著者は冲方丁です。
中国清朝末期、極貧の少年・春児は占い師の予言を信じ、幼なじみの文秀と共に都へ向かう。二人はそれぞれの志を胸に宿命に挑む。物語は希望と成長を描いたベストセラー作品であり、著者は浅田次郎。
『藤十郎の恋』は、元禄期の名優坂田藤十郎の偽りの恋を描いた作品を含む、歴史物の短編小説集です。収録されている作品には、仇討ちを否定する『恩讐の彼方に』や『忠直卿行状記』などがあり、著者の菊池寛は封建性の打破を目指し、多様な題材と独自のテーマで知られています。菊池寛は1888年に生まれ、作家としての地位を確立し、文壇の大御所と呼ばれました。
この作品は、下級武士から筆頭家老に昇進した勘一が、友人彦四郎の不遇の死の真相を追う物語です。二人の運命を変えた過去の事件や、勘一が負った「卑怯傷」の理由が明らかになり、友情と絆が描かれます。著者は百田尚樹で、代表作『永遠の0』に関連しています。また、巻末には未収録の「もう一つの結末」が含まれています。
平安時代を舞台に、陰陽師安倍晴明が親友の源博雅と共に死霊や鬼といった妖しの存在に立ち向かい、不思議な事件を解決する物語。彼は従四位下の地位にあり、天皇からの信任を受けている。
この作品は、下鴨神社の神職の家に生まれた長明の人生を描いています。彼は不運と挫折に満ちた人生を歩み、孤独や災禍に悩みながらも、歌の才能を認められ「新古今和歌集」に入撰します。晩年には一人で思索しながら、人生の意味や世の無常について深く考え続けます。著者の梓澤要は、歴史作家として評価されており、仏教史も学んでいます。
戦国時代の物語で、織田信長の家中にいる地味な武士・伊右衛門が、美しい妻・千代の励ましを受けて名を上げていく様子を描いています。最終的に、夫婦は土佐の大名の地位を手に入れる痛快なストーリーです。著者は司馬遼太郎で、彼は多くの文学賞を受賞した著名な作家です。
この作品は、仏師運慶の型破りな人生を描いた本格歴史小説です。運慶は「醜い顔」と嘲られながらも、美を追求し、女や武士の姿に魅了されます。快慶との確執や野心を抱きつつ、東大寺南大門の金剛力士像を完成させるも、病に倒れます。著者は梓澤要で、歴史文学賞を受賞した作家です。
天才絵師「写楽」をプロデュースする物語。関与者は少なく、世間を欺く大仕掛けが展開され、噂が広がるが、ある者が真実に気づく。仕掛人は窮地に陥り、禁じ手を使う。写楽が謎のまま消えた理由が「写楽事件」の鍵となる、傑作時代小説。著者は野口卓で、彼は多様な職業を経て時代小説作家として成功を収めた。
17歳のおちかは、実家での事件をきっかけに心を閉ざし、江戸の袋物屋「三島屋」で叔父夫婦と暮らしている。彼女は日々の仕事を通じて、訪れる客の不思議な話に引き込まれ、次第に心が癒されていく。物語は「三島屋百物語」として展開される。著者は宮部みゆき。
江戸時代の薬種問屋の一太郎は体が弱く外出できないが、ある夜人殺しを目撃してしまう。その後、猟奇的殺人事件が続き、妖怪たちと共に事件解決に挑む。物語は愉快で不思議な人情推理を描いており、著者は畠中恵である。
奈良県出身の今村勤三は、師の教えを胸に明治時代に大和の再独立を目指して立ち上がる。彼は廃藩置県後の屈辱的な地位に置かれた故郷の復興を目指し、議員として活動する。著者は植松三十里で、歴史文学賞や新田次郎文学賞などを受賞した経歴がある。
江戸・天明年間、シケに遭った男たちが無人の火山島に漂着し、仲間が次々と倒れる中、土佐の船乗り長平は12年間の苦闘を経て生還する。彼の生存の秘密と壮絶な生きざまを描いた感動的な長編ドキュメンタリー小説。著者は吉村昭で、周到な取材と緻密な構成が評価されている。
織田信長が甲斐の武田氏を滅ぼし、正親町帝に大坂遷都を迫る中、帝は不安から重大な勅命を下す。明智光秀や徳川家康など、信長を取り巻く人物たちの心理戦を描き、日本史上最大の謎を明らかにする歴史小説。著者は山本兼一。
天正10年(1582年)、織田・徳川連合軍により武田軍団が滅ぼされ、真田昌幸は孤立します。彼は武勇と知謀を駆使して天下の動向を探りつつ、織田信長に一時臣従しますが、さらなる驚くべき出来事が待ち受けています。著者は池波正太郎で、彼は多くの人気作品を残し、急性白血病で亡くなりました。
日本の卑弥呼の時代、中国では後漢の霊帝のもとで政治が腐敗し、民衆が苦しんでいた。そんな中、楼桑村の青年劉備は、同志関羽と張飛と共に桃園で義盟を結び、害賊を討つことを誓う。これにより、100年にわたる治乱興亡の壮大なドラマが展開される。
千利休は、緑釉の香合を持ち続け、自身の美学を貫いて権力者・秀吉に対峙し、天下一の茶頭に昇りつめる。しかし、その鋭い感性が仇となり、秀吉に疎まれ切腹を命じられる。利休の人生や恋がどのように彼の茶の道に影響を与えたのかを描く長編歴史小説で、第140回直木賞を受賞した作品。著者は山本兼一。
戦国末期、天下の傾奇者・前田慶次郎が主人公の時代小説。彼は豪快な戦士でありながら、自由を愛する風流人でもある。妻子を残し旅に出た彼の奔放な生き様が描かれている。著者は隆慶一郎で、短い作家活動の中で多くの賞を受賞した。
竹千代(家康)が生まれた年、信玄、謙信、信長がそれぞれ若い頃であった動乱期に、松平党にとっての希望の星として誕生。家康の生涯を通じて、剛毅と智謀で泰平の世を築く姿を描いた作品。
永井路子の代表作が大きな活字の新装版で登場。源頼朝の挙兵から鎌倉幕府の成立までを描き、武士たちの情熱と野望を鮮烈に表現した直木賞受賞の歴史小説。著者は東京女子大学卒業後、文筆業に入り、数々の文学賞を受賞している。
1789年。フランス王国は破産の危機に瀕していた。大凶作による飢えと物価高騰で、苦しむ民衆の怒りは爆発寸前。財政立て直しのため、国王ルイ16世は170余年ぶりに全国三部会を召集する。貴族でありながら民衆から絶大な支持を得たミラボーは、平民代表として議会に乗り込むが、想像もしない難題が待ち受けていた-。男たちの理想が、野望が、歴史を変える!一大巨編、ここに開幕。
本書は、前753年にロムルスと3千人のラテン人によってローマが建国され、前509年に共和政へ移行するまでのローマの歴史を描いています。ローマは王政の下で国家の形を整え、後にギリシア文明を視察し成文法の制定に取り組みます。著者は塩野七生で、ローマ帝国の興亡を一千年にわたって探求しています。
信玄の死後、武田軍を率いる勝頼は、信長や秀吉といった敵軍、さらには内部の敵とも戦いながら天下掌握を目指す。長篠の合戦を舞台に、男たちの熱いドラマと壮絶な戦闘を描いた歴史長編小説。著者は伊東潤で、数々の文学賞を受賞している。
これで あなたも 江戸通に!! 江戸の香りを今に伝える浅草の老舗どじょう屋が30年余にわたって開催してきた講演サロン「江戸文化道場」。200回を超えるその中から選りすぐりの江戸噺をまとめた入門書! ・永六輔(作家) ・坂東三津之助(歌舞伎役者) ・坂野比呂志(香具師) ・悠玄亭玉介(幇間) ・坂本五郎(刺青師) ・関岡扇令(木版画摺師) ・入船亭扇橋(噺家) ・米吉(呼出し) ・橘右近(橘流寄席文字家元) ・永山久夫(食文化史研究家) ・小山観翁(古典芸能評論家)など 各界の第一人者に訊いた江戸文化のあれこれを一冊に! 江戸っ子による江戸好きのための教養書。 【目次】 第一章 教養編――江戸の暮らしと知恵を知る 第二章 実践編――粋なおとなの愉しみ 第三章 江戸・東京お買い物帖――名所に名店あり
近世初頭の書物と読書瞥見 近世における出版と読書 近世庶民の学問とは何か 江戸初心者の勉学 日常生活の中の文事 江戸美人の読書 再説・浄瑠璃本の需要と供給 食事作法 貸本屋略史 名古屋の貸本屋大惣
この作品は、2022年の大河ドラマの主人公・北条義時の姉であり、源頼朝の妻である政子の物語です。政子は伊豆の豪族・北条時政の娘として生まれ、流人である源頼朝に恋をし、彼と共に平家に反旗を翻します。鎌倉幕府の成立や源平合戦を背景に、政子は実子や北条一族との愛憎に悩みながら乱世を生き抜く姿を描いています。著者は永井路子で、彼女は数々の文学賞を受賞した作家です。
九州高鍋の小藩から養子に入り、17歳で上杉家の藩主となった治憲は、米沢藩の再建に取り組む。彼は「藩主のために領民がいるのではない」という理念のもと、冷メシ派を登用し、改革を進めて人々に希望を与える。
近代はどこに向かうべきか、そのヒントは江戸にある。近代的評価にとらわれず江戸に即して眺めることで、江戸の本当の姿を理解する。 三百年をかけて文化を成熟させた江戸時代。行き詰まる現代社会が成熟するためのヒントがそこにある。社会・思想・書物・絵画ー従来の近代主義的な評価にとらわれず、江戸に即して眺めることで、「江戸の本当の姿」を理解する。 近代はどこに向かうべきか。 そのヒントは江戸にある。 泰平の世、三百年をかけて文化を成熟させた江戸時代。 歪み、行き詰まる現代社会が成熟するためのヒントがそこにある。 社会・思想・書物・絵画ー従来の近代主義的な評価にとらわれず、 江戸に即して眺めることで、「江戸の本当の姿」を理解する。 江戸文学研究の泰斗による講演会を収録! 【新しい世の中、新しい二十一世紀というものが始まっていくとすれば、そのときに一番大事なことは、江戸というものを江戸に即して眺めるという姿勢であろうと思います。戦後の日本は、江戸の中の近代主義的に評価できる部分だけをピンセットで摘まみ上げて、それだけを評価してきたんですね。それが、これまでの日本の近代であったわけです。(中略)江戸を、近代主義的に良かろうが悪かろうが、良いところは良いところで簡単に評価することはできますけれども、一番近代的ではない部分も全部ひっくるめて、それが江戸の文化の姿だというふうに考えて、その中で江戸は立派な文明を作りあげた。それをちゃんと理解する。そういう姿勢を持つべきではないか。それが、これからの江戸文化に対する我々の姿勢。まさにそこにあるんではないかというふうに思います。】…「第一章 大勢五転 近代人の江戸観について」より はじめに 第一章 大勢五転 近代人の江戸観について 高まる江戸ブーム/「大勢五転」とは/従来の江戸観/時代とともに移り変わる江戸観/明治の江戸観/大正の江戸観/昭和戦前の江戸観/敗戦後の江戸観/江戸の近代主義的再評価/平成の江戸観/近代は終わったのか?/文化成熟のモデルとしての江戸/江戸文化に対する姿勢/「和本リテラシー」とは/明治以前の書物の実態/和本を通して過去と対話する/消えていく江戸の書物/古典の精神を熟成させた江戸 第二章 雅と俗と 江戸文化理解の根本理念 前回のまとめ/江戸に対するスタンスのとり方/江戸の「雅」と「俗」と/近代主義的な江戸の見方/スタンスを変えてみる/江戸に即して江戸を眺める/「雅」・「俗」の内容と評価/「雅」の優位性 ハイカルチャーとサブカルチャー/浮世絵に見る「雅」・「俗」/変化する美人画/「雅」の絵画に見る十八世紀/江戸らしさとは 第三章 江戸モデル封建制 その大いなる誤解 誤解された江戸の封建制/西洋型学問摂取の弊害/江戸中期の浪人の生活/庶民の女性たちの生活/侍の生活と心構え/江戸の身分制の実態/江戸時代の武士道/自己犠牲の精神/外国人が見た江戸の社会/世界の中の日本/『国学正義編』を読む/江戸人の世界感覚 第四章 近世的自我 思想史再考 江戸思想史再考/雅俗のバランス/新しい仏教思想研究への期待/本当に朱子学中心なのか/陽明学を基本とした江戸儒学/江戸モデルの儒学という視点/江戸モデル封建制/近世的自我/本当の中華趣味/黄檗文化の受用/黄檗大名 黄檗貴族/色刷り略歴「大小」の流行/浮世絵の色目と箋譜の色目/「朱子学」と「陽明学」/仁斎学/徂徠学/狂者と畸人/近代的自我との相違点 第五章 和本リテラシーの回復 その必要性 出版物に関する江戸の常識/木版本と活版本/変体仮名と草書体漢字の問題/リテラシーの保有者/明治以前の書物の総数と活字本の総数/空間軸と時間軸/近世の出版史/出版の技術/江戸に即して/初刷りと後刷りの比較 参考資料集
寛永十三年〈一六三六〉時代の始まりの熱気と気品 万治三年〈一六六〇〉文化的インフラ整備期 寛文十三年〈延宝元年〉〈一六七三〉転換期の豊穣 元禄十四年〈一七〇一〉中世の終焉 享保十六年〈一七三二〉復古と革新 江戸時代の折り返し地点 元文三年〈一七三八〉大嘗会の再興と上方中心文化の終焉 宝暦十三年〈一七六三〉繋ぎ転換していく節目の年 明和五年〈一七六八〉上方の成熟、江戸の胎動 天明八年〈一七八八〉天変地異と文化の転換 寛政二年〈一七九〇〉社会の綻びへの対処と文芸の変質 文化五年〈一八〇八〉異国情報と尚古 知のダイナミズム 文政八年〈一八二五〉爛熟する庶民文化が示す江戸の深奥 嘉永六年〈一八五三〉内から外へとひらかれる視点 明治元年〈一八六八〉政治・文化の解体と再構築 明治二十年〈一八八七〉大量即製時代のはじまり
劇的な経済発展をした江戸時代。それを支える労働も多様になった。現代の働き方にも結びつくその変化を通し、江戸時代を捉えなおす。 戦国時代の終焉で、劇的な経済発展をした江戸時代。それを支える労働も多様になった。現代の働き方にも結びつくその変化を通して、江戸時代を捉えなおす。 戦国時代の終焉で、劇的な経済発展をした江戸時代。それを支える労働も多様になった。現代の働き方にも結びつくその変化を通して、江戸時代を捉えなおす。 現代の働き方、江戸に始まる ▼武士もダブルワークで才能開花 ▼武家奉公人は人材派遣で ▼自立?嫁入り修行?武家屋敷に雇われ働く女性たち ▼余業で稼いだ金銭で年貢を納める百姓たち (概要) 常に変化を求められながら、同時に変わらなさもあると感じる私たちの働き方。そもそも現代日本人の働き方の源流はどこにあるのだろうか。明治時代、産業革命以降の資本主義の流れのなかで形成されていったと見る向きもあるが、戦国時代の戦乱から解放され、おおいなる社会的・経済的発展や貨幣制度の成熟を背景に、多様化・細分化していった、江戸時代の労働事情が、その源にあると本書では考える。当時の社会を形作ったあらゆる階層の働き方を丁寧に掘り起こしながら、仕事を軸に江戸時代を捉えなおす。 第一章 「働き方」と貨幣制度 第二章 武家社会の階層構造と武士の「仕事」 第三章 旗本・御家人の「給与」生活 第四章 「雇用労働」者としての武家奉公人 第五章 専門知識をもつ武士たちの「非正規」登用 第六章 役所で働く武士の「勤務条件」 第七章 町人の「働き方」さまざま 第八章 「史料」に見る江戸の雇用労働者の実態 第九章 大店の奉公人の厳しい労働環境 第一〇章 雇われて働く女性たち 第一一章 雇用労働者をめぐる法制度 第一二章 百姓の働き方と「稼ぐ力」 第一三章 輸送・土木分野の賃銭労働 第一四章 漁業・鉱山業における働き手確保をめぐって
大好きだった兄の長太郎を亡くし たお瑛も、今は成次郎と夫婦にな り幸せに暮らしていた。そんな時、 圭太という男が現れる。料理茶屋 『柚木』の新しい奉公人だ。何く れとなくお瑛を助けてくれた女将 のお加津は、優しくて手際のよい 圭太を褒めちぎる。でも、何かお かしい……お瑛の胸はざわついた。 お加津さんは何を考えているの? お瑛は猪牙舟を大川に漕ぎだして いく。好評「みとや」シリーズ!
この書籍は、吉良邸討ち入りに関する詳細な会計記録を通じて、赤穂浪士の行動と心情を金銭面から分析しています。大石内蔵助が残した約700両の軍資金の使途を記した帳簿を基に、討ち入り計画の支出や収支決算を詳述し、歴史的事件の深層を解明しています。著者は近世政治史を専門とする山本博文で、江戸時代の新たな視点を提示しています。
「江戸でバイトやってみた。」は、令和の女子高生・七緒が江戸時代にタイムスリップし、さまざまな職業を体験する新感覚の時代劇です。彼女は江戸のハローワーク・口入れ屋でバイトをしながら、贋金事件に巻き込まれたり、江戸の人々と交流を深めたりします。物語は、江戸時代の職業や文化を解説しながら進行し、七緒の成長や心の変化も描かれています。著者は伝統芸能や歴史に詳しい櫻庭由紀子で、イラストはくろしまあきらが手がけています。
海坂藩の跡取り・文四郎の成長を描いた物語が、15歳の初夏から始まります。彼は隣家のふくとの淡い恋や友人たちとの絆を経験し、突然の悲運に直面しながらも成長していきます。この作品は藤沢周平の代表作であり、新装版として再登場しました。
江戸後期、淡路島の貧しい家庭に生まれた高田屋嘉兵衛は、困難な状況を乗り越え、海の男として成長し、最終的には北方の蝦夷・千島で成功した商人となる。彼の生涯は、閉ざされた日本と南下するロシアとの間での運命を描いている。
「江戸」に関するよくある質問
Q. 「江戸」の本を選ぶポイントは?
A. 「江戸」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「江戸」本は?
A. 当サイトのランキングでは『燃えよ剣(上) (新潮文庫)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで139冊の中から厳選しています。
Q. 「江戸」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「江戸」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。