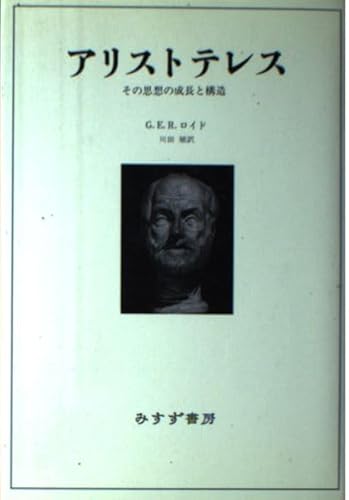【2025年】「存在論」のおすすめ 本 138選!人気ランキング
- 史上最強の哲学入門 (河出文庫)
- これからの「正義」の話をしよう (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)
- 哲学がわかる 形而上学 (A VERY SHORT INTRODUCTION)
- ワードマップ現代形而上学ー分析哲学が問う、人・因果・存在の謎
- 最強の成功哲学書 世界史
- 哲学の歴史 1 古代 1
- ハイデガー―すべてのものに贈られること:存在論 (入門・哲学者シリーズ)
- 古代アテネ旅行ガイド (ちくま学芸文庫)
- 哲学を知ったら生きやすくなった
- まんが!100分de名著 ハイデガー 存在と時間 (まんが!100分de名著)
この書籍は、哲学の歴史を強者たちの論争を通じてわかりやすく紹介した入門書です。ソクラテスやデカルト、ニーチェなどの哲学者の考えを基に、真理、国家、神、存在についての議論を展開しています。著者の飲茶は、難解な哲学や科学の知識を楽しく解説することで人気を博しています。
西洋文化・伝統の根幹をなす営み、ここに始まる-西洋哲学の全体像を描き出す日本初のシリーズ、第10弾。 総論 始まりとしてのギリシア 1 最初の哲学者たち 2 エレア学派と多元論者たち 3 ソフィスト思潮 4 ソクラテス 5 小ソクラテス学派 6 プラトン 7 アリストテレス 8 テオプラストスと初期ペリパトス学派
存在の頼りなさ ハイデガーが言うように薔薇の花は、その理由とも証拠とも無関係に咲いている。それどころか、われわれ自身の存在にもまた理由や証拠は必要ない。それでは存在とはいったいどういうことなのか、それを明らかにしようとしたのがハイデガーの生涯だった。 存在の頼りなさーーまえがき 第一章 存在への問い 1 伝統的ヨーロッパ哲学における「本質」と「存在」 (1) 「本質」「偶有性」 (2)「存在」 2 ハイデガーの問い (1) 「ある」とはどういうことか (2) 「存在の意味」への問い 第二章 非本来性:日常において見失われる自分 1 「現存在」 (1) 「道具連関」 (2) 「世界」 (3) デカルト主義の大略 (4) ハイデガーのデカルト批判 2 「世界-内-存在」のあり方 (1) 道具連関の最終目的 (2) 「ひと」:現存在の交換可能性 第三章 本来性:自分の完全なあり方 1 現存在の「かけがえのなさ」 (1) 現存在の交換不可能性 (2) 死へ向かう存在 (3) 現存在の全体性 (4) 死の忘却 (5) 死の忘却メカニズム (6) 死をめぐるヨーロッパ哲学 2 現存在の本来性 (1) 日常からの脱却:良心 (2)現存在の時間:非本来性 (3) 本来性における過去:被投性 (4) 現存在の将来:企投性 (5) 現存在の現在 (6) キルケゴールの実存思想 (7) 無をまえにした不安 3 実存主義と存在への問い (1) サルトルの実存主義 (2) サルトルとハイデガー 第四章 転回以後:存在の隠蔽 1 物、道具、芸術作品 (1) 認識活動と物 (2) デカルト批判再び (3) 芸術作品へ (4) 世界と大地 (5) 開示・現前と隠蔽・非現前の相互貫通 (6) 存在の真理 2 存在に聴き従うこと (1) デカルトと人間中心主義 (2) 存在の贈与 (3) おわりに あとがき
この書籍は、古代ギリシャを旅行する際のガイドブックで、名所や食文化、哲学者ソクラテスとの出会いなどの現地情報を豊富に紹介しています。特に紀元前5世紀半ばのアテネの日常生活や娯楽、著名人について詳しく描かれ、カラー図版も多数掲載されています。著者は古代ローマ史の専門家で、読者はアテネの魅力を深く理解できる内容となっています。
本書は、日経WOMANの人気連載を基にしたもので、現代の不安やモヤモヤを哲学的視点から解消するためのガイドです。哲学者小川仁志の監修のもと、マンガ形式で様々なテーマ(上司との関係、怒りのコントロール、孤独との向き合い方など)に対する哲学的なアプローチを紹介しています。全20話を通じて「哲学スイッチ」をオンにし、悩みを軽減する方法を学ぶことができます。
この書籍は、アリストテレスの哲学に関する論文を集めたもので、彼の思想が西洋哲学に与えた影響を探求しています。内容は、知識の追求や知恵の本質、四つの原因(形相因、質料因、始動因、目的因)についての考察を含み、古代哲学者たちの見解への批判を行っています。アリストテレスの分析方法や弁証法的思考は、今後の研究者にとっての模範となるものです。
全章を「問い」で構成し、難解な文章をほぐす――実力派による“はじめてのハイデガー”登場! 現代の硬直した世界観を解体する 類例のない究極の入門書 本書「序」のタイトルは「なぜ、『存在と時間』についてなおも書くのか」である。『存在と時間』やハイデガーの入門と謳う本はすでにいくるもあるからだ。 だが「なぜ、なおも書くのか」と問うには勇気がいる――正面から答えねばならないから。答えはこうだ; 「『存在と時間』は一度は読んだ方がいい。そして、『存在と時間』を読みたいとこころざした人にとって、この本がかつてなかった読み方と説得力を示しているから」。 哲学徒を引きつけてやまない“現代哲学の最高峰”の読解を、自分の読書体験としてモノにするための確かな道が本書だ。『存在と時間』の鮮烈な解釈で学界にデビューした新鋭による、問答無用のニュー・スタンダード! 序 なぜ『存在と時間』についてなおも書くのか 第1章 なぜ「存在の意味」を問うのに自分自身を問うのか 第2章 なぜ『存在と時間』の言葉遣いは普通の哲学書と違うのか 第3章 なぜ「主体」でも「心」でもなく「世界内存在」なのか 第4章 なぜハンマーと釘の分析が存在論になるのか 第5章 なぜ「世界は存在しない」なんて言えるのか 第6章 なぜ「手」を中心に考えるのか 第7章 「世人」とは誰のことなのか 第8章 「死への先駆」は無理な要求か 第9章 『存在と時間』に倫理学はあるのか 第10章 結局、『存在と時間』は何を成し遂げたのか 序 なぜ『存在と時間』についてなおも書くのか 第1章 なぜ「存在の意味」を問うのに自分自身を問うのか 第2章 なぜ『存在と時間』の言葉遣いは普通の哲学書と違うのか 第3章 なぜ「主体」でも「心」でもなく「世界内存在」なのか 第4章 なぜハンマーと釘の分析が存在論になるのか 第5章 なぜ「世界は存在しない」なんて言えるのか 第6章 なぜ「手」を中心に考えるのか 第7章 「世人」とは誰のことなのか 第8章 「死への先駆」は無理な要求か 第9章 『存在と時間』に倫理学はあるのか 第10章 結局、『存在と時間』は何を成し遂げたのか
学際化がすすむ社会諸学のロジックをいかにして身につけるか。日本で初めて認識論から説き起こし、多様な調査研究手法を明晰に整理して、メソドロジーの全体像を提示する。社会科学を実践するための要諦をつかみ、創造的研究を生み出すための最良のガイドブック。 はじめに 第I部 社会科学の認識論 第1章 認識論 1.1 存在論の2つの立場――基礎づけ主義と反基礎づけ主義 1.2 認識論のパラダイム――実証主義・批判的実在論・解釈主義 1.3 むすび 第II部 社会科学のリサーチ・デザイン 第2章 事例研究 2.1 事例研究とは――定義と特性 2.2 単一事例の選び方――3つの基準 2.3 複数事例の選び方――比較の論理 2.4 構成要素――問いと分析単位 2.5 一般化・理論的貢献・過程追跡――事例研究の論点 2.6 むすび Box2.1 歴史研究と事例研究 第3章 実験 3.1 実験とは――定義・要点・「無作為割り当て」 3.2 種類――実験室実験・フィールド実験と準実験 3.3 妥当性と問題点――実験における配慮事項 3.4 分析と方法論的位置づけ――アプローチと認識論 3.5 むすび Box3.1 自然実験 Box3.2 妥当性 Box3.3 ホーソン効果とピグマリオン効果 Box3.4 アクション・リサーチ 第4章 横断的・縦断的研究 4.1 横断的研究とは――定義・特性・方法論的位置づけ 4.2 縦断的研究とは――定義・類型・特性と方法論的位置づけ 4.3 標本抽出(サンプリング)——確率的/非確率的抽出とその論点 Box4.1 歴史研究と横断的/縦断的研究 Box4.2 非確率的抽出の限界 第III部 社会科学の手法 第5章 インタビュー 5.1 概要――類型(構造化・半構造化・非構造化)と認識論 5.2 個別インタビュー(1)基本的な考え方 5.3 個別インタビュー(2)オーラル&ライフ・ヒストリー 5.4 集団に対して行うインタビュー――フォーカス・グループ Box5.1 民俗学における半構造化・非構造化インタビュー 第6章 エスノグラフィー/参与観察 6.1 概要――定義・経緯・特性・認識論 6.2 手順/技法――アクセス・類型・書き方・再帰性・厚い記述 6.3 その他の注意点 Box6.1 歴史研究とエスノグラフィー 第7章 調査票調査 7.1 概要――要点・注意点・認識論 7.2 進め方――調査票の作成・調査の実施・データの処理 7.3 データの分析――集計表と解析 Box7.1 キャリー・オーバー効果 Box7.2 インターネットと調査 Box7.3 選挙の当確速報 第8章 言説分析 8.1 概要――定義と要点 8.2 類型と方法論的位置づけ――認識論とリサーチ・デザイン 8.3 批判的言説分析――フェアクラフを中心に 8.4 解釈主義系の言説分析――研究例を踏まえて 8.5 むすび Box8.1 歴史研究・縦断的研究と言説分析 第IV部 社会科学のルール 第9章 研究倫理と参照の方法 9.1 研究倫理 9.2 参照の方法――概要 9.3 ハーバード方式(括弧参照方式) 9.4 脚注方式 9.5 むすび Box9.1 修士論文を書く Box9.2 博士論文を書く(1) Box9.3 博士論文を書く(2) おわりに あとがき 索 引
その音‐映像を0.1秒オーダーで注視せよ。高解像度の分析によって浮かび上がる未聞のJLG的映画原理。映画史=20世紀史を一身に引き受けようとするゴダールは、映画に何を賭しているのか?そして21世紀のゴダールはどこへ向かうのか?映画論の「方法」を更新する新鋭の初単著。ゴダールとともに、知覚経験の臨界へ。 序章 新たなる視聴 第1章 結合 第2章 問いと非応答 第3章 見逃し、聴き逃し 第4章 類似 第5章 受苦と目撃
「どうして勉強しなければいけないの?」「どうしていじめはなくならないの?」「生きている意味はあるの?」 学校の… 「どうして勉強しなければいけないの?」 「どうしていじめはなくならないの?」 「生きている意味はあるの?」 学校の先生や親がなかなか答えられない、子どもが抱えるリアルな悩みや疑問を、哲学者の言葉をヒントに解決。 哲学を通して子どもの考える力を育てる、必読の一冊。 古代ギリシャから近代、現代の有名な哲学者の解説も。 ■第1章 自分について考える Q 運動が苦手 Q 勉強ができない Q 自分の言葉で上手く話せない Q 綺麗になりたい Q 自分のいいところがわからない Q 「自分らしさ」って何? ■第2章 友達について考える Q 友達ができない Q 友達が他の子と仲よくしているとムカムカしてしまう Q 友達グループの中で仲間外れにする子がいる Q ケンカをした友達に「ごめんなさい」が言えない Q 人を好きになるってどういうこと? ■第3章 悪について考える Q どうしてルールを守らなくちゃいけないの? Q 人にやさしくしなきゃいけないのはなぜ? Q どうしていじめはなくならないの? Q 悪いことをしている人には注意した方がいい? ■第4章 生き方について考える Q どうして勉強しなければいけないの? Q 苦手なことはあきらめちゃダメ? Q 「本をたくさん読みなさい」って言われたけどなぜ? Q 自分の夢を反対される Q 生きている意味はあるの? Q 幸せって何? ■第5章 命について考える Q 心はどこにあるの? Q 花や木に命はある? Q 死ぬのが怖い Q 人は死んだあとどうなるの? Q 人はどうして人を殺すの? ■岩村先生の哲学講座 人間の祖先「ホモ・サピエンス」が生き残れたわけ 物事の原因はすべて「目に見えない」 「ふたつの時間」を生きる 愛は「心を受ける」こと
本書は、アランの「プロポ」から選ばれた幸福に関する93の哲学断章を収めたもので、ルーアンの新聞に連載されたことが始まりです。独特なスタイルで「哲学を文学に、文学を哲学に」変える試みが評価され、フランス散文の傑作とされています。日本でも早くから親しまれています。
世界ゆるスポーツ協会代表理事が発見した、スポーツ、文化、働き方、社会、心のゆるめ方。ゆるめるとは、新しいルールをつくること… 老・若・男・女・健・障、すべての人が生きやすい世界を目指して--。世界ゆるスポーツ協会代表理事が発見した、スポーツ、文化、働き方、社会、心のゆるめ方。ゆるめるとは、新しいルールをつくること!! 老・若・男・女・健・障、すべての人が生きやすい世界を目指して--。 世界ゆるスポーツ協会代表理事が発見した、スポーツ、文化、働き方、社会、心のゆるめ方。 ゆるめるとは、新しいルールをつくること!! はじめに 第1章 スポーツをゆるめる 第2章 ゆるスポーツが生まれるまで 第3章 そもそも「ゆるめる」とは何か 第4章 「ゆるライズ」してみよう 第5章 “YURU”は日本独自のスタイル 第6章 ニューマイノリティをさがそう 第7章 働くをゆるめる 第8章 みんな普通で、みんな普通じゃない 第9章 ガチガチな世界からの脱出法 第10章 標準をゆるめる おわりに
この書籍は、幸福を得るためには自己中心的な考えを捨て、外界に目を向けて好奇心を持つことが重要であると説いています。著者ラッセルは、人生を豊かに生きるための知恵を提供し、不幸の原因や幸福をもたらす要素について詳述しています。内容は、不幸の原因を分析した第1部と、幸福を得るための要素を探る第2部に分かれています。
本書では、現代人が抱える「将来の不安」「お金への欲望」「死への恐怖」といった悩みを、哲学者たちの視点から解決に導く内容が紹介されています。アリストテレスやアンリ・ベルクソン、マックス・ウェーバーの考えを通じて、平易な言葉で哲学を学びながら悩みを解消することができる一冊です。
20世紀の哲学者による重要な講義の改訳版で、ナチズムとの関連についての「シュピーゲル対談(弁明)」も収録されています。内容は形而上学や存在の本質に関する問いを中心に構成されており、解説は木田元が担当しています。
主要トピックの理論と測定尺度を概観。経営学は実践の役に立つかを問い,実践家とともに理解を深め合える共同研究を模索する。 2020年現在の組織行動論領域において,学術的に確立された理論と測定尺度を概観。実際の経営現象を測定・研究する際,実践家とともに理解を深め合える協働を求め,経営学にとってのレリバンスとは何かを真摯に問う。研究者,ビジネスパーソン必読の書。 第1部 組織行動論の立ち位置 第1章 組織行動研究の俯瞰 第2章 「知っている」ということについて 第3章 概念と理論 第4章 組織行動の測定 第2部 組織行動論は何をどう測るか 第5章 リーダーシップ 第6章 組織の中の公正 第7章 欲求とモティベーション 第8章 人的資本,社会関係資本,心理的資本 第9章 組織と個人の心理的契約 第10章 組織コミットメント,ジョブ・エンベデッドネス 第11章 組織行動の成果 第3部 組織行動論の充実のために 第12章 2つの知のサイクルが共振する共同研究 第13章 組織行動研究のレリバンスを求めて
本書は、哲学の歴史を「魂の哲学」から「意識の哲学」、「言語の哲学」を経て「生命の哲学」へと展開するストーリーとして描いています。古代から21世紀までの人間の思考と精神の営みを探求し、ヘーゲルやシュペングラー、ローティを超えた新たな哲学史を提示します。著者は伊藤邦武で、京都大学で学び、教授を務めた経験があります。
プラトン、アリストテレス、孔子、デカルト、ルソー、カント、サルトル…… では、女性哲学者の名前を言えますか? 男性の名前ばかりがずらりと並ぶ、古今東西の哲学の歴史。 しかしその陰には、知的活動に一生をかけた数多くの有能な女性哲学者たちがいた。 ハンナ・アーレントやボーヴォワールから、中国初の女性歴史家やイスラム法学者まで。 知の歴史に大きなインパクトを与えながらも、見落とされてきた20名の思想家たち。 もう知らないとは言わせない、新しい哲学史へのはじめの一書。 【目次より】 ◆ディオティマ Diotima(紀元前400年ごろ) ◆班昭 Ban Zhao(西暦45~120年) ◆ヒュパティア Hypatia(西暦350年ごろ~415年) ◆ララ Lalla(1320~1392年) ◆メアリー・アステル Mary Astell(1666~1731年) ◆メアリ・ウルストンクラフト Mary Wollstonecraft(1759~1797年) ◆ハリエット・テイラー・ミル Harriet Taylor Mill(1807~1858年) ◆ジョージ・エリオット(メアリー・アン・エヴァンズ) George Eliot (Mary Anne Evans)(1819~1880年) ◆エーディト・シュタイン Edith Stein(1891年~1942年) ◆ハンナ・アーレント Hannah Arendt(1906~1975年) ◆シモーヌ・ド・ボーヴォワール Simone de Beauvoir(1908~1986年) ◆アイリス・マードック Iris Murdoch(1919~1999年) ◆メアリー・ミッジリー Mary Midgley(1919~2018年) ◆エリザベス・アンスコム Elizabeth Anscombe(1919~2001年) ◆メアリー・ウォーノック Mary Warnock(1924~2019年) ◆ソフィー・ボセデ・オルウォレ Sophie Bosede Oluwole(1935~2018年) ◆アンジェラ・デイヴィス Angela Davis(1944年~) ◆アイリス・マリオン・ヤング Iris Marion Young(1949~2006年) ◆アニタ・L・アレン Anita L. Allen(1953年~) ◆アジザ・イ・アルヒブリ Azizah Y. al-Hibri(1943年~) 明晰な思考、大胆な発想、透徹したまなざしで思想の世界に生きた、 20の知られざる哲学の女王たち(フィロソファー・クイーンズ)。 知の歴史をひっくり返す、新しい見取り図。 「……人々は相変わらずこう思っている。プラトンの時代から 思想の分野を担ってきたのはほとんどが男性だろうと。 まるで、女性も偉大な哲学者になれるというプラトンの予言を、 これまでだれも実現してこなかったかのように。」 (本書「はじめに」より) 【目次より】 ◆ディオティマ Diotima(紀元前400年ごろ) ◆班昭 Ban Zhao(西暦45~120年) ◆ヒュパティア Hypatia(西暦350年ごろ~415年) ◆ララ Lalla(1320~1392年) ◆メアリー・アステル Mary Astell(1666~1731年) ◆メアリ・ウルストンクラフト Mary Wollstonecraft(1759~1797年) ◆ハリエット・テイラー・ミル Harriet Taylor Mill(1807~1858年) ◆ジョージ・エリオット(メアリー・アン・エヴァンズ) George Eliot (Mary Anne Evans)(1819~1880年) ◆エーディト・シュタイン Edith Stein(1891年~1942年) ◆ハンナ・アーレント Hannah Arendt(1906~1975年) ◆シモーヌ・ド・ボーヴォワール Simone de Beauvoir(1908~1986年) ◆アイリス・マードック Iris Murdoch(1919~1999年) ◆メアリー・ミッジリー Mary Midgley(1919~2018年) ◆エリザベス・アンスコム Elizabeth Anscombe(1919~2001年) ◆メアリー・ウォーノック Mary Warnock(1924~2019年) ◆ソフィー・ボセデ・オルウォレ Sophie Bosede Oluwole(1935~2018年) ◆アンジェラ・デイヴィス Angela Davis(1944年~) ◆アイリス・マリオン・ヤング Iris Marion Young(1949~2006年) ◆アニタ・L・アレン Anita L. Allen(1953年~) ◆アジザ・イ・アルヒブリ Azizah Y. al-Hibri(1943年~)
本書は、出口治明氏が古代ギリシャから現代までの哲学と宗教の全史を体系的に解説した教養書で、特に日本人の苦手とするこのテーマに焦点を当てています。3000年の歴史を俯瞰し、100以上の哲学者・宗教家の肖像を用いて、知識の深まりを促します。著者はライフネット生命の創業者であり、立命館アジア太平洋大学の学長。多くの著名人から高く評価されており、教育や思索の重要性を強調しています。
この書籍は、ヘレニズム時代から古代後期にかけての科学的探求におけるギリシア的発想の特徴や方法、成果を解説しています。目次には、ヘレニズム時代の科学、アリストテレス以後のリュケイオン、エピクロス派とストア派、数学、天文学、生物学と医術、応用機械学、プトレマイオス、ガレノス、古代科学の衰退に関する章が含まれています。
経営学学習・研究の基本テキスト。共通に身につけておきたい知識が盛り込まれている。卒論作成や大学院進学を目指す際に役立つ。 東京大学大学院での経営学の方法論基礎の教科書。第Ⅰ部で実証研究の基礎、第Ⅱ部で具体的に各研究プロセスからそのエッセンスや留意点を学ぶ。専門が違っても共通に身につけておきたい知識が盛り込まれている。学部での卒論作成の準備や大学院進学を目指す際に役立つ。 第1部 リサーチ・サイクルを回す:経営学研究法の基礎 第1章 実証研究の方法論:Field-Based Research Method(FBRM)=藤本隆宏 研究の技法 1 アプローチの方法:ケース研究 1 ケース研究の妥当性=桑嶋健一 2 ケース研究のプロセス=桑嶋健一 2 データを集める 3 一次データの収集=藤田英樹 4 二次データの収集と活用=近能善範 5 インターネットを通じたデータ収集=山本 晶 6 インタビューメモの作り方=加藤寛之 7 アンケート調査の設計・実施=具 承桓 8 工場調査法=松尾 隆 9 資料の収集と分析=粕谷 誠 3 データを分析する 10 分析手法の見つけ方=清水 剛 11 因子分析と共分散構造分析=藤田英樹 12 重回帰分析におけるモデル選択=椙山泰生 13 文献情報と内容分析=宮崎正也 第2部 リサーチ・マインドを育む:研究プロセスに学ぶ 第2章 ぬるま湯体質の研究ができるまで 継続的調査からとらえた現象=高橋伸夫 第
倫理学の中心的な諸問題を深い学識と鋭い眼差しで再検討した現代における古典的名著。倫理学はいかに変貌すべきか、新たな方向づけを試みる。 倫理学の中心的な諸問題を深い学識と鋭い眼差しで再検討した現代における古典的名著。倫理学はいかに変貌すべきか、新たな方向づけを試みる。
初期自然学から,問う人ソクラテスを描いて新しい知の探求の道を開いたプラトン,諸学の礎を築いたアリストテレスへ.人間の「知」のあらゆる萌芽を秘めつつ,哲学そのものの成立の機微をうかがう待望の通史.
なんだか難しそうな哲学。しかし哲学することは特別なことではない。身近なテーマから、哲学するとはどんな行為なのかを解き明かす。 なんだか難しそうな哲学。中身は分からなくても、漠然と難しそうにみえる哲学。しかし、哲学することはなにも特別な行為ではない。哲学が扱うのはどれも実は身近な問題ばかりである。ニュースなどで見かける問題、人と話すときに話題にするようなこと、実はそこに哲学が隠れている。本書は、これを手がかりにさらに読者なりに考えを深めるための道具箱のようなものである。カントいわく、哲学は学べない。読者はこれをヒントに自分で考える。そこに哲学が存在する。 はじめに(戸田剛文) 第一部 身近なテーマから 第1章……いま芸術に何が期待されているのか(阿部将伸) はじめに 1 視線の向けかえ―古代 2 視線の落ち着き先の変容1―古代末から中世へ 3 視線の落ち着き先の変容2―近代 4 コミュニティ感覚 おわりに ❖おすすめ書籍 第2章……犬と暮らす(戸田剛文) はじめに 1 動物への道徳的配慮 2 具体的な問題 3 動物を食べることは正当化できるのか 4 幸福な社会 ❖おすすめ書籍 第3章……宗教原理主義が生じた背景とはどのようなものか(谷川嘉浩) はじめに 1 原理主義とはどのようなものか 2 近代化と、キリスト教原理主義 3 手のなかに収まらないものへ ❖おすすめ書籍 第4章……幸福の背後を語れるか(青山拓央) はじめに 1 幸福をめぐる三説 2 「私」の反事実的可能性 3 私的倫理と自由意志 4 『論考』と言語 5 『論考』と倫理 ❖おすすめ書籍 第二部 哲学の伝統 第5章……原因の探求(豊川祥隆) はじめに―「なぜ」という問いかけ 1 言葉の根―「アイティア」について 2 近代科学という営みと「目的」の瓦解 3 ドミノ倒し 4 現代の「原因」観―概念の多元主義にむけて 5 おわりに―人間の進歩と面白さ ❖おすすめ書籍 第6章……言葉と世界(佐野泰之) はじめに―言葉のない世界 1 言語論的転回 2 論理実証主義への批判 3 解釈学的転回 おわりに―私たちは言語の囚人なのか? ❖おすすめ書籍 第7章……知識と懐疑(松枝啓至) はじめに 1 古代懐疑主義 2 デカルトの「方法的懐疑」 3 「懐疑」について「懐疑」する―ウィトゲンシュタインの思索を手掛かりに ❖おすすめ書籍 第8章……存在を問う(中川萌子) はじめに 1 「存在とは何か」という問いの動機と必要性―ニーチェとハイデガーの時代診断 2 存在とは何か? 「存在とは何か?」と問うことはどのような営みか? 3 「存在とは何か」という問いの形式と歴史 4 「存在とは何か」と問うことの自由と責任―ハイデガーとヨナスの責任論 おわりに ❖おすすめ書籍 あとがき 索引(人名・事項)
本書は、古代ギリシア哲学の巨人アリストテレスの知の探求を再発見する試みである。彼は形式論理学の基礎を築き、近代自然科学の発展に寄与した。内容は、知への欲求や論理学の誕生、自然と原因、生命の意味、善の追求など多岐にわたり、アリストテレスの思考法が現代にどう影響しているかを探る。著者は大阪府立大学の教授、山口義久。
この文章は、プラトンの作品「ソクラテスの弁明」と「クリトン」を紹介しています。「ソクラテスの弁明」では法廷でのソクラテスの所信が描かれ、「クリトン」では彼が不正な死刑宣告を受けた後、脱獄を勧める友人クリトンとの対話が展開されます。両作品はソクラテスの偉大さを芸術的に表現しています。
世界遺産、人類の遺産、文化財に含まれる「遺産」とは何か。ノートル=ダムなど具体的な事例とともに紹介。文化に関わる必読文献。 世界遺産、人類の遺産、文化遺産/文化財に含む「遺産」とは何か。歴史的資料とともにノートル=ダムなど具体的な事例を紹介して論じる。文化に関わる必読文献。 世界遺産、人類の遺産、文化遺産/文化財に含まれる「遺産(patrimoine)」とは何か。老朽化や破壊という運命から免れ、特別な威光を与えられ、熱狂的な執着や、真の信仰を喚起してきた日用品、武具、宝飾品、建築物、さらに、これから新しい時代に生まれる遺産=文化財を守る、保存や修復には何が重要か。歴史的資料とともに、ノートル=ダムといった具体的な事例も紹介し、簡潔にして決定的に論じる。文化に関わるすべての人々の必読書。図版多数。 第一章 宗教的事象 聖遺物 聖像破壊 第二章 王政的事象 レガリア〔王の事物〕 図書館と公文書館 古代遺跡 王城 世論の目覚め 第三章 一族的事象 第四章 国家的事象 遺産の宮 第五章 行政的事象 第六章 科学的事象 参考資料 図版資料 訳者あとがき
この書籍は、哲学を学ぶ際の多様さと難解さに対処するための実用ガイドです。古代ギリシャから現代哲学、さらに西洋形而上学と東洋思想を網羅し、哲学者同士の関係を通じて思考の本質を理解する手助けをします。著者は専修大学の教授で、現象学や歴史理論を専門としています。
本書は、近代哲学の問題を明確に論じたもので、分析哲学の出発点とその将来を示しています。著者バートランド・ラッセルは、知識の認識や哲学の限界、価値について探求し、今日も読み継がれる哲学入門書の名著です。新訳版として登場しました。
哲学と哲学史をめぐって パルメニデス エンペドクレスとアナクサゴラス 古代ギリシアの数学 ソクラテスそしてプラトン アリストテレス ニーチェとギリシア ハイデガーと前ソクラテス期の哲学者たち 「哲学史」の作り方
本書は、図解を用いて哲学の歴史をわかりやすく解説した入門書です。ソクラテス以前から21世紀の思想まで幅広くカバーし、中世の普遍論争やハイデガーの『存在と時間』なども詳しく説明しています。哲学用語の理解を助けるための解説や、問題設定の背景を丁寧に説明し、視覚的な資料を多く用いることで直感的な理解を促進します。著者は専修大学の教授で、現代哲学や舞踊研究に精通しています。
この本は、子どもたちが「しあわせとは何か?」を考えるための6つの大きな問いを通じて、自分自身の答えを見つける手助けをする哲学絵本です。様々な視点を組み合わせながら、日常では見えない考えを探求し、子どもたちと大人が本気で対話することを促します。また、日本版監修の重松清による書き下ろしの短編も収録されています。シリーズ累計23万部の人気を誇ります。
この入門書は、古代から現代までの哲学の流れや近代日本の哲学、主要な哲学的テーマを網羅しています。見開き2ページで各トピックを解説しており、全体の流れを理解しつつ個別の学びが可能です。現代的なテーマとしてSTS(科学技術社会論)、子どもの哲学、クィア・LGBT、アフォーダンスなども取り上げています。著者は東京大学、阪大、慶應義塾大学の教授たちです。
本書はあえて時代に背を向けて、徹底的に自分の映像体験へと内的に遡行することにした。いったいなぜ私は映画オタクなのか。なぜ私は繰り返し繰り返し映画を見つづけてきたのか。そして写真はいかなる魅力でもって私を魅惑しつづけてきたのか。そのような映像経験に関する内的な問いを突き詰めて考えることが、本書の試みである。 (「あとがき」より) 序 第1部 写真という神秘と狂気 1 ベルグソン、あるいは写真としての現実 2 バルト、あるいは触覚的メディアとしての写真 3 バザン、あるいは痕跡としての写真 4 「人影」、あるいは写真としての原爆 5 べンヤミン、あるいは視覚的無意識としての写真 6 記憶痕跡としての写真---手塚治虫の『白い幻影』 7 ゴーリキー、あるいは単調な灰色の世界としての映像 8 戦時下のヴァーチャル・リアリティ---『南の島に雪が降る』 9 「まなざしなき視覚」とヴァーチャル・リアリティ 第2部 カメラという残酷と愛情 10 顔写真の政治学---「酒鬼薔薇聖斗」問題をめぐって 11 意味記憶とエピソード記憶---『記憶が失われたとき」 12 ドキュメンタリー映画における単独性 13 生命なき世界としての視覚的失認症 14 「具体の視線」としてのイディオ・サバン 15 バラージュ、あるいは相貌的知覚としてのカメラ 16 蓮實重彦、あるいはカメラの眼をもった男 17 子供の視線としてのカメラ---ロッセリーニからキアロスタミヘ 18 ピロピロ笛、あるいは存在の情けなさとしての神代辰巳 第3部 映画という反復の快楽 19 機械的反復の魅惑としての『どですかでん』 20 フロイト、あるいは映画カメラとしての人間的視線 21 快感原則の彼岸としてのリュミエール映画 22 アルコール先生、あるいはチャップリンの機械恐怖症 23 小津安二郎、あるいは単調な機械的反復 24 「空っぼ」の反復という快楽---黒沢清の『CURE』 25 北野武、あるいは「死」の快楽としての反復 26 アドルノとホルクハイマー、あるいは古典的ハリウッド映画における反復 27 映画観客の笑いと機械的反復 28 ドゥルーズ、あるいは世界を信じることとしての映画 あとがき
『ソクラテスの弁明』は、古代ギリシアの哲学者ソクラテスの裁判をプラトンが記録した作品で、彼の生き方や思想を明らかにする名著です。幸福を追求するためには、何が「善」であるかを理解することが重要であり、これは知恵や真実を求める意味でもあります。新訳と解説を通じて、ソクラテスの言動や哲学的概念(アレテーなど)を探求し、人生や哲学の本質に迫ります。著者は岸見一郎で、哲学やアドラー心理学を専門とする学者です。
映画に携わるあらゆる人々のために、そして映画それ自体のために紡がれた、映画批評の真の現在形 「それでもあなたはあなたの豊かな想像力のはけ口としてフィルムを作り続けるのか?」 蓮實重彦以来の「シネマ」概念をめぐり、その「大義」とは何かを問うべくして書かれた、2005~2017年までの廣瀬純による主要映画批評・論考を一挙収録。 「映画批評とは何をなすべきか」をめぐっての現代日本の最も果敢な実践がここにある ーーーーーーーーーーー 現代日本において最も先鋭的かつ実践的な映画批評を手がける廣瀬純による、現時点までのキャリアを総括した初の映画論集がここに完成。 単行本未収録論考はもちろん、国内未発表テクストほか、講演、討議、座談会まで、廣瀬純による「言葉」をめぐるパフォーマンスをこの一冊に凝縮した。 映画を見ること、映画をつくること、そして映画を思考することとは、いったいどのようにこの世界と関わるのか? 映画に携わるあらゆる人々のために、そして映画それ自体のために紡がれた、映画批評の真の現在形がここにある。 ●レヴィナス、ゴダール、小津安二郎──切り返しショットの系譜学 ●ロメール映画のなかの女たち――出来事を創造する ●クロード・シャブロル──『悪の華』と再生産 ●ポー、エプシュタイン、青山――ユリイカ対ユリイカ ●カトリーヌ・ドゥヌーヴ――脱性化されたモンロー ●エイゼンシュテイン、グレミヨン、ローシャ、ストローブ=ユイレ――地理映画(ジオ=シネマ)の地下水脈 ●『ダゲレオタイプの女』問題、あるいは、黒沢映画の唯物論的転回 ●ストローブ=ユイレ、フォード――そよ風の吹き抜けるサイエンス・フィクション ●若松孝二『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』──道程に終わりはない ●フーコー、イーストウッド――無理な芝居の一撃 ●クェンティン・タランティーノ――Shoot This Piece of Shit ●空族『サウダーヂ』――Outra vez…, mas! ●レオス・カラックス『ホーリー・モーターズ』──ルックス映画の極北 ●マルコ・べロッキオ『ポケットの中の握り拳』――暴力階級と垂直落下 ●高倉健追悼――客分として生きる ●ロべール・ブレッソン――不確かさと二階層構造 ●鈴木清順追悼――運命、恥辱、人民 and more……
本書『14歳からの哲学』の続編は、人生についての考察をエッセイ形式で柔らかく表現した「人生の教科書」です。著者は、幸福な人生を生きるために必要な16のテーマ(友愛、個性、社会、戦争、言葉など)を通じて、読者に自ら考える力を促します。池田晶子氏は、専門用語を使わず、日常の言葉で哲学を語る気鋭の哲学者です。
実体と属性 実体と付帯性 実体と本質 生成と質料 定義と質料 存在と形相 結合体の一性 普遍と形相 定義と形相 第一義的なデュナミス 能力と可能性 質料と可能態 エネルゲイアとエンテレケイア 現実態としての魂 本質・形相・現実態
戦後ばかりでなく戦前の数多くの映画作品を自由に踏査しながら、「運動イメージ」の詳細な分析を通して「映画的イメージにおける思考」にいたるドゥルーズの真に創造的な傑作。『シネマ2』にたいしてその必然的な前提である『シネマ1』は、物語的内容を論じる映画論や、たんなる映画史としてではなく、「映画に現れるかぎりでのイメージと記号の分類の試み」の原理を明確に提示する。 第1章 運動に関する諸テーゼ──第一のベルクソン注釈 第2章 フレームとショット、フレーミングとデクパージュ 第3章 モンタージュ 第4章 運動イメージとその三つの種類──第二のベルクソン注釈 第5章 知覚イメージ 第6章 感情イメージ──顔とクロースアップ 第7章 感情イメージ──質、力、任意空間 第8章 情動から行動へ──欲動イメージ 第9章 行動イメージ──大形式 第10章 行動イメージ──小形式 第11章 フィギュール、あるいは諸形式の変換 第12章 行動イメージの危機 用語解説 訳者あとがき 注・索引
戦前戦後の映画の流れを縦断しつつ「イメージと記号の分類」を試み,時間や運動をめぐる哲学の新たな概念を創造する。ドゥルーズの思考が多様に注入された結晶。 哲学者による単なる映画史・映画論ではなく、「映画に現れるかぎりでのイメージと記号の分類」の創造的な試み。映画芸術を思考することによって時間や運動をめぐる哲学の新たな概念を創出する。哲学と映画との唯一無二の出会いを記す書物であり、生、知覚、記憶、身体、言語、脳、集団、政治などのドゥルーズのあらゆる思考が多様に注入され、再編成され、結晶した現代の古典。 第1章 運動イメージを超えて 第2章 イメージと記号の再検討 第3章 回想から夢へ──第三のベルクソン注釈 第4章 時間の結晶 第5章 現在の諸先端と過去の諸層──第四のベルクソン注釈 第6章 偽なるものの力能 第7章 思考と映画 第8章 映画、身体と脳、思考 第9章 イメージの構成要素 第10章 結論 映画用語一覧 訳者あとがき 注・索引
アルバート・エリスが提唱する自己改善メソッドを紹介した本です。内容は、モヤモヤやイライラを解消するための思考法や行動法、自己受容の重要性、最悪の状況を想定することで動揺を減らす方法などを含んでいます。最終的には、幸せは自分自身で作り出すことができるというメッセージが伝えられています。
本書は、中世哲学がトリビアルな問題と見なされる理由を「普遍論争」に焦点を当てて探求します。「普遍は存在するのか?」という問いを通じて、中世哲学の豊かな可能性を明らかにし、哲学入門としても適した内容です。目次には、普遍論争の歴史、記号と事物の関係、代表理論についての議論、二十世紀における中世哲学の位置づけが含まれています。著者は山内志朗で、中世哲学を専門とし、幅広いテーマで研究・執筆を行っています。
◆哲学の究極の問いに挑む 世界にはいったい何が存在するのか。この哲学を代表する問いを扱う存在論は、いまや躍進を遂げています。古代・中世にあっては思弁と自然言葉を頼りに進められていた存在論ですが、現代では論理学を武器とすることで、高度に抽象的な概念を明晰に扱うことに成功し、工学などの分野にも影響を与えるような熱気のある学問へと新生しているのです。学生と教員との対話を織り交ぜ、存在論初心者から哲学愛好家まで、存在論の最先端へと招待する待望の本格教科書の登場です。著者は九州大学文学部准教授。 現代存在論講義 I 目次 序 文 本書の成立とスタイル 本書の主題 本書を世に問う理由─なぜ『現在論在論講義』なのか 著者の立場─暗黙の前提 第一講義 イントロダクション─存在論とは何か 1 何が存在するのか 1.1 「何が存在するのか」から「どのような種類のものが存在するのか」へ 1.2 性質と関係 1.3 物とプロセス 1.4 部分と集まり 1.5 種という普遍者 1.6 可能的対象および虚構的対象 2 存在論の諸区分 2.1 領域的存在論と形式的存在論 2.2 応用存在論と哲学的存在論 Box 1 表象的人工物としての存在論─存在論の可能な定義 2.3 形式的存在論と形式化された存在論 2.4 存在論の道具としての論理学 Box 2 同値、分析あるいは存在論的説明について 2.5 存在論とメタ存在論 まとめ 第二講義 方法論あるいはメタ存在論について 1 存在論的コミットメントとその周辺 1.1 世界についての語りと思考 1.2 存在論的コミットメントの基準 Box 3 すべてのものが存在する?!─存在の一義性について 1.3 パラフレーズ Box 4 “No entity without identity”─クワイン的メタ存在論の否定的テーゼ 2 理論的美徳─「適切な存在論」の基準について 2.1 単純性 2.2 説明力 2.3 直観および他の諸理論との整合性 3 非クワイン的なメタ存在論 3.1 虚構主義 3.2 マイノング主義 3.3 新カルナップ主義 Box 5 カルナップと存在論 まとめ 第三講義 カテゴリーの体系─形式的因子と形式的関係 1 カテゴリーと形式的因子 1.1 カテゴリーの個別化─形式的因子 1.2 存在論的スクエア 2 形式的関係 2.1 4カテゴリー存在論における形式的関係 2.2 存在論的セクステットと形式的関係 Table 1 主要な形式的関係のまとめ まとめ 第四講義 性質に関する実在論 1 ものが性質をもつということ 1.1 何が問われているのか 1.2 存在論的説明あるいは分析について 1.3 実在論による説明 2 実在論の擁護 2.1 分類の基礎 2.2 日常的な言語使用 2.3 自然法則と性質 3 ミニマルな実在論 3.1 述語と性質 3.2 否定的性質 3.3 選言的性質 3.4 連言的性質と構造的性質 3.5 付録:高階の普遍者について Box 6 アームストロングへの疑問 まとめ 第五講義 唯名論への応答 1 クラス唯名論 1.1 クラスによる説明 1.2 例化されていない性質および共外延的性質の問題 1.3 クラスの同一性基準と性質 1.4 すべてのクラスは性質に対応するのか 2 類似性唯名論 2.1 類似性の哲学 2.2 類似性唯名論への反論 3 述語唯名論 3.1 正統派の唯名論 3.2 述語唯名論への反論 4 トロープ唯名論 4.1 実在論の代替理論としてのトロープ理論 4.2 トロープの主要な特性とそれにもとづく「構築」 4.3 トロープ唯名論のテーゼとそれへの反論 Box 7 トロープへのコミットメントを動機づける理由 4.4 実在論との共存 まとめ 結語にかえて─存在の問いはトリヴァルに解決されるのか? 読書案内 あとがき 索引 装幀─荒川伸生
ついに、『シネマ』がわかる! 思想界に颯爽と現れた26歳の新鋭、衝撃のデビュー作! 「たんに見る」ことの難しさと創造性をめぐって書かれた画期的なドゥルーズ『シネマ』入門。 本書は、「見る」ことと「読む」ことの復権を同時に実現する。 20世紀最大の哲学者、ジル・ドゥルーズが著した芸術と哲学をめぐる二巻本『シネマ』。 本書は、『シネマ』にとって、映画は哲学の「フッテージ(footage)」、つまり「思考の素材=足場」であると捉えなおすことから議論を開始する。 その映画というフッテージに、もうひとりの重要な哲学者となるアンリ・ベルクソンの哲学が流しこまれる。そのとき映画はイメージ=映像による〈思考〉の実践として立ち現れてくるのだ。 『シネマ』と映画の関係、ドゥルーズとベルクソンの関係というふたつの問いは、哲学にとって「見る」ことと「読む」ことがいかにして概念の創造へと導かれるかということを指し示している。 映画という特殊な経験のシステムから立ちあがる、イメージがそれ以上でもそれ以下でもなく見たままで現れる地平、「眼がスクリーンになるとき」とはどのようなことか。 そのとき観客である私たちはどんな存在へと生成するのか。 また、「私は素朴な観客です」というドゥルーズの言葉どおり、「見たまま」を肯定する態度は、ドゥルーズの哲学の創造性とどのようなつながりがあるのだろうか。 映画から哲学へ、哲学から映画へ、まっすぐに『シネマ』の核心へとスリリングに論じぬく、新鋭のデビュー作 ! はじめに 第一章 映画と哲学、ベルクソンとドゥルーズ 1-1 『シネマ』と映画 1-2 ベルクソンにおけるイメージと運動 1-3 ベルクソンの「映画的錯覚」批判とベルクソニズムによるその解決 第二章 運動イメージ――感覚-運動的に思考する映画 2-1 運動イメージの分化――宇宙の構築 2-2 運動イメージの種別化――主観性の物質的アスペクト 2-3 映画的思考1――全体とフィギュールの思考、画面外と音声 第三章 運動と時間 3-1 運動から時間へ?――ランシエールの『シネマ』批判をめぐって 3-2 零次性としての知覚イメージ――物の知覚 3-3 眼がスクリーンになるとき――運動と時間 第四章 第一、第二の時間イメージ――視-聴覚的に思考する映画 4-1 結晶イメージの境位――知覚と記憶の同時性 4-2 過去の共存と現在の同時性――「脳」と「宇宙」の新しい意味 4-3 映画的思考2――〈外〉と定理の思考、視-聴覚的映画 補遺 ドゥルーズの「減算と縮約」 第五章 第三の時間イメージ――ひとつのおなじ結論の三つの異なるバージョン 5-1 私に身体を与えてください――瞬間に持続を導入する 5-2 偽なるものが力能になるとき――『シネマ』の物語論 5-3 ふたたび『シネマ』と映画、ベルクソンとドゥルーズ 文献一覧 あとがき
本書は「創造」と「狂気」の深い関係を2500年にわたる思想史を通じて探求する。プラトンやアリストテレスから始まり、デカルト、カント、ヘーゲルを経て、ラカン、デリダ、ドゥルーズに至るまでの哲学的議論を明快に描写。著者は、創造性を促進するためには「クレイジー」な人物を雇うべきだというビジネス界の見解を背景に、歴史的な視点からこのテーマを掘り下げている。著者は精神病理学の専門家であり、思想の展開を通じて新たな理解を提供することを目指す。
「考える」ためには何が重要か 多様性の時代の利他と利己 私はプロセスの途中にいる時間的存在 自分が自分であることの意味 民主主義とは何か わかりあえなさをつなぐということ
◆存在論の豊饒な沃野への招待 論理学を武器として“存在”の謎を解明する、現代存在論の本格入門書、待望の第2弾です。学生と教員との対話のかたちで存在論の基礎を明晰に論じて好評を博した1巻に続き、2巻は4つの主題を論じる各論編。目の前にある机のような「中間サイズの物質的対象」、生物・物質・人工物の「種」、現実世界と事物のあり方が異なる「可能世界」、そして小説のキャラクターといった「虚構的対象」について、現代哲学はどのように把握するのでしょうか。より身近な対象へと問いを広げた本書は、さらに読者の哲学的探究心を揺する1冊です。著者は九州大学文学部准教授。 現代存在論講義 Ⅱ 目次 序 文 I巻のおさらい II巻の内容について 第一講義 中間サイズの物質的対象 1 物質的構成の問題 1.1 二つの相反する直観 1.2 粘土の塊と像 1.3 ニヒリズムあるいは消去主義について 1.4 像と粘土の塊との非同一性を擁護する 1.5 構成関係の定義 2 通時的同一性の問題─変化と同一性 2.1 同一性とライプニッツの法則 2.2 四次元主義 Box 1 四次元主義と物質的構成の問題 2.3 三次元主義 2.4 通時的同一性の条件あるいは存続条件について まとめ 第二講義 種に関する実在論 1 種に関する実在論 1.1 種についての直観 1.2 普遍者としての種 Box 2 種の個体説について 1.3 性質と種(その一)─偶然的述定と本質的述定 1.4 性質と種(その二)─述語の共有 1.5 性質と種(その三)─タイプ的対象としての種 Box 3 種の例化を表現する“is”は冗長ではない 2 種と同一性 2.1 数え上げ可能性 2.2 種と同一性基準 3 種と法則的一般化 3.1 法則的言明 3.2 種と規範性 Box 4 HPC説と「自然種の一般理論」 4 付録─種的論理について まとめ 第三講義 可能世界と虚構主義 1 様相概念と可能世界 1.1 様相概念─可能性と必然性 1.2 可能世界─様相文が真であるとはいかなることか 1.3 付録─可能世界意味論の基本的アイディア 2 様相の形而上学 2.1 可能世界への量化と現実主義的実在論 2.2 ルイス型実在論 3 虚構主義 3.1 反実在論としての様相虚構主義 3.2 フィクションにおける「真理」とのアナロジー 3.3 背景とメタ理論的考察 3.4 虚構主義への反論1 3.5 虚構主義への反論2 まとめ 第四講義 虚構的対象 1 基本的構図 1.1 実在論か非実在論か 1.2 虚構と真理 1.3 記述の理論 2 現代の実在論的理論 2.1 マイノング主義(その1)─〈ある〉と〈存在する〉との区分 2.2 マイノング主義(その2)─述定の区分および不完全性 Box 5 非コミットメント型マイノング主義 2.3 理論的対象説 Box 6 虚構的対象についての虚構主義 2.4 人工物説 まとめ 結語にかえて──イージー・アプローチと実践的制約 読書案内 あとがき 索引 装幀─荒川伸生
不在の「現実」をスクリーンに映し出し一つの世界を魔術的に出現させる映画。そのメディア固有の美学的意味を探究した古典的名著。 不在の「現実」をスクリーンに映し出し、一つの世界を魔術的に出現させる映画。そのメディア固有の技術的・美学的・存在論的意味を探究した哲学的映画論の古典。 不在の「現実」をスクリーンに映し出し、一つの世界を魔術的に出現させる映画というメディアは、二十世紀の歴史と思考に何をもたらしてきたか。その物理的・技術的基盤に注目しつつ、絵画・写真・演劇とは異なる映画そのものの本質を、モダニズムの美学批判的眼差しのもとに探究した映画理論の古典。バザン以後の問いを受け継ぎ、ドゥルーズ『シネマ』と双璧をなす名著、待望の邦訳。 増補版への序 序 1 仲間たちをめぐる自叙伝 2 視覚と音 3 写真とスクリーン 4 観客、俳優、スター 5 類型的人物、シリーズ、ジャンル 6 起源についての諸説 7 ボードレールと映画の神話 8 軍人と女性 9 ダンディ 10 神話の終焉 11 映画のメディウムとメディア 12 死すべきものとしての世界──絶対的年齢と若さ 13 全体性としての世界──カラー 14 自動性 15 余論──いくつかのモダニズム絵画 16 展示と自己言及 17 カメラの介入 18 テクニックの言明 19 沈黙の認知 続・眼に映る世界 〈訳者解説〉なぜ映画が哲学の問題たり得るのか? 原注 訳注 人名・作品名索引
形而上学とは何か アリストテレス的形而上学を擁護する 存在と量化について考え直す 同一性・量化・数 存在論的カテゴリー 種は存在論的に基礎的か 四つのカテゴリーのうちふたつは余分か 四つのカテゴリー 新アリストテレス主義と実体 発生ポテンシャル 生命の起源と生命の定義 本質・必然性・説明 現実性なくして潜在性なし 新アリストテレス主義的実体存在論のひとつの形
この書籍は、対話形式と1コママンガを用いたニーチェ入門書で、わかりやすく哲学を紹介しています。内容は、哲学の意義やニーチェの思想(ニヒリズム、道徳、死の意味など)を通じて、前向きな生き方を提案しています。著者は飲茶で、哲学の学びが人生にどのように役立つかを探求しています。
数々の映画作品を分析することで「見る」という行為をめぐって展開される権力と欲望の闘争を抉り出し、来たるべき世界を予告する。 数々の映画作品を分析することで「見る」という行為をめぐって展開される権力と欲望の闘争を抉り出し、来たるべき世界を予告する。著者渾身の「映像の存在論」。 あらゆる映画はポルノグラフィである──。「見る」という行為を通して世界が所有される今日、映画は世界を容赦なく裸体にする。ポストモダンを代表する論客が『狼たちの午後』(シドニー・ルメット)、『シャイニング』(スタンリー・キューブリック)、『ディーバ』(ジャン=ジャック・ベネックス)など、数々の著名な映画作品を分析し、現代における権力と欲望の闘争を抉り出す。「映像の存在論」をなす著者渾身の論考群。 序論 第一部 第1章 大衆文化における物象化とユートピア 第2章 現代の大衆文化にみられる階級とアレゴリー──政治映画としての『狼たちの午後』 第3章 『ディーバ』とフランス社会主義 第4章 「破壊的要素に没入せよ」──ハンス=ユルゲン・ジーバーベルクと文化革命 第5章 『シャイニング』の語りと歴史主義 第6章 アレゴリーで読むヒッチコック 第7章 映画の魔術的リアリズム 第二部 第8章 イタリアの実存
フィルムアート社創立50周年記念復刊 映画の楽天性を慎ましく肯定する 明晰かつ挑発的。大胆かつ精細。 映画史を奔放に横断し咀嚼する蓮實流映画講義集、ついに復刊!! 「未だ現在進行形の「映画の死」。あなたは間に合ってしまった。とすれば、本書を読む以外の選択肢はない。」 ――濱口竜介(映画監督) わかりやすい言葉と魅力あふれる語り口で展開する「映画講義」。 レイ、ロージー、フラー、サーク、小津、トリュフォーなど、輝かしき饗宴を担った幾多の映画人たちへ深い追憶を捧げながら、大胆な省略と繊細な手さばきで、映画史の風土を滑走する鮮やかな一書。 第Ⅰ講 映画はいかにして死ぬか ハリウッドの五〇年代 第Ⅱ講 異邦人の饗宴 横断的映画史の試み 第Ⅲ講 放浪の音楽家 映画的健忘症を克服する 第Ⅳ講 三人の作家 小津安二郎1『麦秋』をめぐって 小津安二郎2『東京物語』をめぐって フランソワ・トリュフォー『恋のエチュード』をめぐって 鈴木清順『ツィゴイネルワイゼン』をめぐって 第Ⅴ講 ジブラルのタル鮫 わが映画遍歴 蓮實重彥ベスト10&ワースト5 十年史 あとがき 映画題名索引 初出誌(講演)一覧 新装版あとがき
この文章は、キルケゴールの晩年の思索を通じて、絶望という「死にいたる病」を分析し、キリスト教界の欺瞞を批判しながら、有限なる自己と無限なる神との関係を探求する内容です。現代人の自己疎外の問題に迫り、精神の教化と覚醒を促すことを目的としています。目次には、絶望の定義とその罪としての側面が示されています。
14歳からの「考える」のための教科書。「自分とは何か」「死」「家族」「恋愛と性」「メディアと書物」「人生」など30のテーマ。 今の学校教育に欠けている14歳からの「考える」の為の教科書。「言葉」「自分とは何か」「死」「家族」「社会」「理想と現実」「恋愛と性」「メディアと書物」「人生」等30のテーマ。 人には14歳以後、一度は考えておかなければならないことがある。 言葉、自分とは何か、死、心、他人、家族、社会、理想と現実、友情と愛情、恋愛と性、仕事と生活、本物と偽物、メディアと書物、人生、善悪、自由など、30のテーマを取り上げる。 Ⅰ 14歳からの哲学[A] 1 考える[1] 2 考える[2] 3 考える[3] 4 言葉[1] 5 言葉[2] 6 自分とは誰か 7 死をどう考えるか 8 体の見方 9 心はどこにある 10 他人とは何か Ⅱ 14歳からの哲学[B] 11 家族 12 社会 13 規則 14 理想と現実 15 友情と愛情 16 恋愛と性 17 仕事と生活 18 品格と名誉 19 本物と偽物 20 メディアと書物 Ⅲ 17歳からの哲学 21 宇宙と科学 22 歴史と人類 23 善悪[1] 24 善悪[2] 25 自由 26 宗教 27 人生の意味[1] 28 人生の意味[2] 29 存在の謎[1] 30 存在の謎[2]
著者ヨゼフ・ピーパーは、20世紀の著名なキリスト教哲学者であり、トマス・アクィナスの解釈を基にヨーロッパの伝統的な徳論を描いた名著を翻訳した。作品では、思慮、正義、勇気、節制という四つの枢要徳が、キリスト教の信仰、希望、愛とともに人々の行動規範を支える重要性が説かれている。特に思慮は他の徳の基盤であり、真実に基づく行動を促すものである。著者は、徳を人間存在全体と関連づける必要性を強調し、徳が切り離されると道徳主義に陥る危険性を警告している。
「モダニティとテクノロジーの経験」としての映像文化とは何か? 発展著しい英米圏の映画学の中核をなす記念碑的論文を本邦初めて翻訳・集成.気鋭の社会学者/映画研究者による充実した解題を付す.メディア,文化,社会の研究に必須となる基本論集. 序論 「想起」としての映像文化史(長谷正人) I 痕跡としての映像——テクノロジーとしてのカメラ 第1章 光(リュミエール)あれ ——リュミエール映画と自主性(ダイ・ヴォーン) 第2章 フロイト,マレー,そして映画 ——時間性,保存,読解可能性(メアリー・アン・ドーン) 第3章 個人の身体を追跡する ——写真,探偵,そして初期映画(トム・ガニング) II 循環する映像——資本主義と視覚文化 第4章 解き放たれる視覚 ——マネと「注意」概念の出現をめぐって(ジョナサン・クレイリー) 第5章 幽霊のイメージと近代的顕現現象 ——心霊写真,マジック劇場,トリック映画,そして写真における不気味なもの(トム・ガニング) 第6章 世紀末パリにおける大衆のリアリティ嗜好 ——モルグ,蝋人形館,パノラマ(ヴァネッサ・シュワルツ) III 映像のショック作用——大衆的身体感覚と初期映画 第7章 モダニティ,ハイパー刺激,そして大衆的センセーショナリズムの誕生(ベン・シンガー) 第8章 アトラクションの映画(トム・ガニング)
セネカの代表作3篇を収録した新訳本で、内容は以下の通りです。『生の短さについて』では、人生を浪費せずに活用する重要性を説き、『心の平静について』では心の安定を得る方法を探ります。『幸福な生について』では、快楽よりも徳が幸福の鍵であると主張しています。
論理学って、こんなに面白かったのか! 出来あいの論理学を天下り式に解説するのでなく、論理学の目的をはっきりさせた上で、それを作り上げていくプロセスを読者と共有することによって、考え方の「なぜ」が納得できるようにした傑作テキスト。初歩の論理学が一人でマスターできる。 はじめに 第I部 論理学をはじめる 第1章 What is THIS Thing called Logic ? 1.1 論理とは何か?そして論理学は何をするのか 1.2 論理の正しさをどこに求めたらよいか 第2章 論理学の人工言語をつくる 2.1 自然言語から人工言語へ 2.2 人工言語L 第3章 人工言語に意味を与える ――命題論理のセマンティクス 3.1 結合子の意味と真理表 3.2 論理式の真理値分析 3.3 トートロジー 3.4 「何だ、けっきょく同じことじゃない」を捉える――論理的同値性 3.5 真理表を理論的に反省する 3.6 矛盾とは何か 3.7 論証の正しさとは何か 3.8 論理的帰結という関係 3.9 真理関数という考え方 3.10 日本語の「ならば」と論理学の「→」 3.11 コンパクト性定理 3.12 メタ言語と対象言語をめぐって 第4章 機械もすなる論理学 4.1 意味論的タブローの方法 4.2 タブローの信頼性 第I部のまとめ 第II部 論理学をひろげる 第5章 論理学の対象言語を拡張する 5.1 なぜ言語の拡張が必要なのか 5.2 述語論理での命題の記号化 5.3 述語論理のための言語をつくる 5.4 タブローの方法を拡張する 第6章 おおっと述語論理のセマンティクスがまだだった 6.1 述語論理のセマンティクスをつくらなければ 6.2 セマンティクスとモデル 6.3 存在措定と会話の含意 6.4 伝統的論理学をちょっとだけ 第7章 さらに論理言語を拡張する 7.1 MPLの限界 7.2 PPLのセマンティクス 7.3 PPLにタブローを使ってみる 7.4 論理学者を責めないで――決定問題と計算の理論 第8章 さらにさらに論理言語を拡張する 8.1 同一性を含む述語論理IPL 8.2 個数の表現と同一性記号 第II部のまとめ 第III部 論理をもう1つの目で見る 第9章 自然演繹法を使いこなそう 9.1 自然演繹法をつくる 9.2 他の結合子のための推論規則 9.3 矛盾記号を導入した方がよいかも 9.4 述語論理への拡張 9.5 同一性記号を含む自然演繹 第10章 シンタクスの視点から論理学のゴールに迫る 10.1 公理系という発想 10.2 シンタクスとセマンティクス 10.3 命題論理の公理系の完全性証明 第III部のまとめ 第IV部 論理学はここから先が面白い! 進んだ話題のロードマップ 第11章 めくるめく非古典論理の世界にようこそ! 11.1 古典論理は神の論理である――2値原理と排中律のいかがわしさ 11.2 多値論理 11.3 直観主義論理 11.4 古典論理の拡張としての様相論理 第12章 古典論理にもまだ学ぶことがたくさん残っている 12.1 完全武装した述語論理の言語FOL 12.2 AFOLの完全性とそこから得られるいくつかの結果 12.3 第1階の理論 12.4 モデル同士の同型性 12.5 第2階の論理 第IV部のまとめ 付録 A. A little bit of mathematics B. 練習問題解答 C. ブックガイド
この書籍は、センター試験・倫理の形式で西洋思想を学ぶための内容で、ソクラテスからウィトゲンシュタインまでの重要な哲学的テーマを厳選した20問を通じて解説しています。著者は哲学の基本を楽しく理解できるように工夫しており、古代から近代、そして批判的な哲学の流れを網羅しています。著者は東京大学哲学科卒のライター・編集者、斎藤哲也氏です。
指針なき現代にこそ響く最強の古典!資本主義の本質を見抜き、日本実業界の礎となった渋沢栄一が、生涯を通じて貫いた経営哲学とは。 1番読みやすい現代語訳! 60万部突破!! いまこそ全ての日本人必読! 最強の古典 2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」主人公! 新1万円札の顔に決定! 指針なき現代においてわたしたちは「どう働き」「どう生きる」べきか? 迷ったとき、いつでも立ち返りたい原点がここにある!! 各界のトップ経営者も推薦! 岩瀬大輔氏 「あなたの仕事観を変える本。東洋の叡智がここにある! 」 佐々木常夫氏 「資本主義に対する彼の思想は、時代や国境を越えている」 新浪剛史氏 「“道徳に基づいた経営"という発想には学ぶべきことが多い」 資本主義の本質を見抜き、日本実業界の礎となった渋沢栄一。 「論語」とは道徳、「算盤」とは利益を追求する経済活動のことを指します。 『論語と算盤』は渋沢栄一の「利潤と道徳を調和させる」という経営哲学のエッセンスが詰まった一冊です。 明治期に資本主義の本質を見抜き、約480社もの会社設立・運営に関わった彼の言葉は、ビジネスに限らず、未来を生きる知恵に満ちています。 第1章:処世と信条 第2章:立志と学問 第3章:常識と習慣 第4章:仁義と富貴 第5章:理想と迷信 第6章:人格と修養 第7章:算盤と権利 第8章:実業と士道 第9章:教育と情誼 第10章:成敗と運命 なぜいま『論語と算盤』か(本書「はじめに」より抜粋) ここで現代に視点を移して、昨今の日本を考えてみると、その「働き方」や「経営に対する考え方」は、グローバル化の影響もあって実に多様化している。「金で買えないモノはない」「利益至上主義」から「企業の社会的責任を重視せよ」「持続可能性」までさまざまな価値観が錯綜し、マスコミから経営者、一般社員からアルバイトまでその軋轢の中で右往左往せざるを得ない状況がある。そんななかで、われわれ日本人が、「渋沢栄一」という原点に帰ることは、今、大きな意味があると筆者は信じている。この百年間、日本は少なくとも実業という面において世界に恥じない実績を上げ続けてきた。その基盤となった思想を知ることが、先の見えない時代に確かな指針を与えてくれるはずだからだ。 第1章:処世と信条 第2章:立志と学問 第3章:常識と習慣 第4章:仁義と富貴 第5章:理想と迷信 第6章:人格と修養 第7章:算盤と権利 第8章:実業と士道 第9章:教育と情誼 第10章:成敗と運命 十の格言 渋沢栄一小伝 『論語と算盤』注 参考図書
多くの経営者がバイブルとして挙げることの多い「論語と算盤」。明治維新後多くの企業を立ち上げて日本国を強くしてきた渋沢栄一の経営哲学が学べる。論語と算盤、すなわち今で言うとアートとサイエンス。この2つの両輪なくして経営は成り立たないしインパクトのある仕事はできない。常に渋沢栄一の経営哲学を頭に入れて日々過ごしていきたい。
写真映像の存在論 完全映画の神話 映画と探検 沈黙の世界 ユロ氏と時間 禁じられたモンタージュ 映画言語の進化 不純な映画のために 『田舎司祭の日記』とロベール・ブレッソンの文体論 演劇と映画 パニョルの立場 絵画と映画 ベルクソン的映画、『ピカソ天才の秘密』 ドイツ零年 最後の休暇
この書籍は、徳倫理学の入門書であり、善き生を求める古代から現代に至る倫理学の発展を解説しています。功利主義や義務論とは異なり、個々の行為ではなく人生全体を考察する視点を提供し、古代ギリシアや中世、西洋の哲学、中国の儒教、近現代の思想家を網羅しています。また、環境、医療、ビジネス、政治などの応用倫理についても触れています。著者は、各分野で活躍する研究者たちです。
本書は、徳倫理学を中心に、行為者の性格に焦点を当てた倫理的議論を展開する。アリストテレス以来の徳の概念を再評価し、フィリッパ・フットやロザリンド・ハーストハウスなどの主要論者の論文が収録されている。内容は、ニーチェの価値再評価から始まり、現代倫理理論、功利主義との関係、徳と正しさの相互作用など、多岐にわたるテーマを扱っている。著者は加藤尚武と児玉聡で、倫理学の専門家である。
映画前史からフィルムカルチャー全盛期、そしてデジタルが加速する2010年代まで。デジタル・グローバリズム時代に知っておきたい映画史キーワード!鑑賞・研究・批評にコンパクトに使える映画事典。 1895年まで-映画の誕生前夜、「動く映像」への試作期 1895…1900年代末-シネマトグラフの誕生、「驚き」から「物語」へ 1900年代末…1910年代-パテ社、MPPCなど産業システムの始動期 1920年代-夢の工場、アヴァンギャルド、モダニスムの高揚期 1930年代-無声映画からトーキーへ、夢と現実の交差 1940年代-戦争下のプロパガンダ、国策映画時代 1950年代-娯楽王国の変調、ハリウッド・システムの凋落期 1960年代-自由と新しい波の台頭、撮影所システムから離れて 1970年代-ニュー・ハリウッドの誕生、香港、インド映画の台頭 1980年代-マルチプレックス化と多様なヴィジュアライゼーションの実験 空前のインディーズ・ブーム、そして新しい世紀へ 情報社会の幕開けと液状化するリアリティ、ハリウッドの苦悩 立ち上がるソーシャルとクラウド、デジタル時代の新たな地平
「差別とはどういうものか」「差別はなぜ悪いのか」「差別はなぜなくならないのか」の3つの問いを通して、哲学的に考える入門書 本書は「差別とはどういうものか」「差別はなぜ悪いのか」「差別はなぜなくならないのか」の3つの問いを通して哲学的に考え、日常で起きている差別的な行為、発言、偏見について、どう考えていいのか手がかりを得る入門書 日常にある差別や偏見。どう考えれば、どうすればいいのかに応える待望の本! 差別的な行為、発言、あるいは偏見について、またハラスメントやいじめと差別との相違、アファーマティブ・アクションと逆差別、配慮しているつもりが差別になるというマイクロアグレッションなど、実際、日常で起きている差別や偏見について、どう考えていいのかわからなくなったら、立ち戻るところがようやく見つかった。 本書は「差別とはどういうものか」「差別はなぜ悪いのか」「差別はなぜなくならないのか」の3つの問いを通して、差別について哲学的に考えていきます。本書の基本的なスタンスは、悪質な差別をあたかも問題のない単なる区別かのように偽装しないこと、それと同時に、何でもかんでも差別と呼ぶような言葉のインフレに陥らないようにすること。 世界では盛んな差別の哲学だが、日本の哲学ではこれまで扱われてこなかった。本書は具体的な事例を使った日本では初めての差別の哲学入門書の決定版!! 序章 なぜ「差別の哲学」なのか 第1章 差別とはどういうものか 単なる区別と不当な差別はどう違うのか/区別か差別かの分類のむずかしさ/アファーマティブ・アクションと逆差別/ヘイトスピーチはどういう意味で差別か/中間考察ーー拾いすぎることと拾えないこと/ハラスメントは差別か/いじめは差別か/差別に歴史は必要か 第2章 差別はなぜ悪いのか 四つの答え/差別者の心や態度に問題があるのか(心理状態説) /害が大きいから悪いのか(害説) /自由を侵害するから悪いのか(自由侵害説) /被差別者を貶めるような社会的意味をもつから悪いのか?(社会的意味説) /結局、差別はなぜ悪いのか 第3章 差別はなぜなくならないのか なぜ嘘はなくならないのか/悪気はなくても差別は起こるーー事実による正当化/事実なのだから仕方がない、とはなぜ言えないのか/配慮しているつもりが差別になるーーマイクロアグレッション/差別されていると言えなくなる/反差別主義者も無自覚に差別している/科学との付き合い方/接触理論の着想/ためらいの好機 終章 差別の問題とこれからの哲学
「存在論」に関するよくある質問
Q. 「存在論」の本を選ぶポイントは?
A. 「存在論」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「存在論」本は?
A. 当サイトのランキングでは『史上最強の哲学入門 (河出文庫)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで138冊の中から厳選しています。
Q. 「存在論」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「存在論」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。