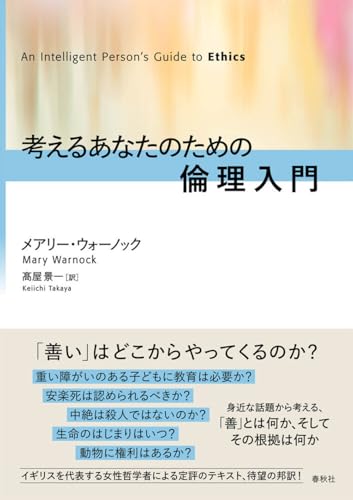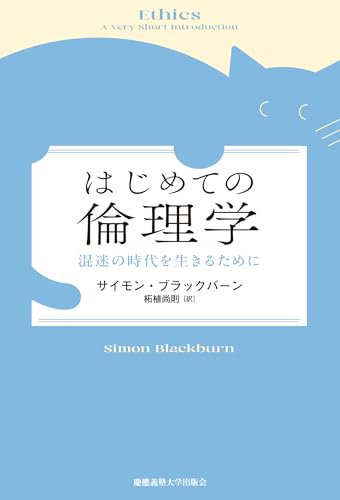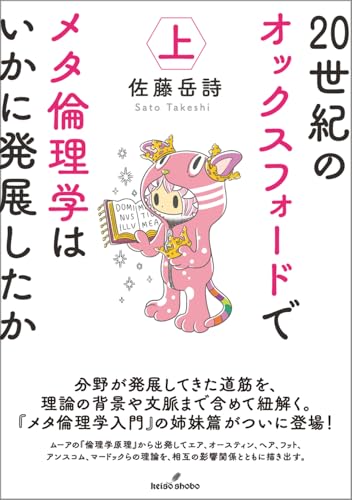【2025年】「倫理学」のおすすめ 本 156選!人気ランキング
- ニコマコス倫理学(アリストテレス) 上 (岩波文庫 青 604-1)
- 実践・倫理学 (けいそうブックス)
- 社会倫理学講義 (有斐閣アルマ)
- 倫理学入門-アリストテレスから生殖技術、AIまで (中公新書 2598)
- 動物の解放 改訂版
- 入門・倫理学の歴史 24人の思想家
- 安楽死・尊厳死の現在-最終段階の医療と自己決定 (中公新書)
- 入門・倫理学
- 蔭山の共通テスト倫理 (大学受験Nシリーズ)
- 動物からの倫理学入門
この文章は、古代ギリシアにおける倫理学の名著について紹介しています。著者は「幸福」を人生の究極の目的とし、その概念を詳細に分析しています。この考えは当時の市民に向けられ、ルネサンス以降の西洋思想や人間形成に大きな影響を与えました。目次では、善の追求、政治的活動の重要性、幸福の本質、習慣づけの役割などが論じられています。幸福は快楽や名誉、富とは異なるものであり、学習や習慣づけを通じて獲得されるとされています。
本書は倫理学の基本理論を紹介し、「善い」とは何か、助け合うべき理由や限界について考察します。アリストテレスやカントの理論を平易に解説し、現代の課題(医療、人工知能、戦争、環境問題など)を倫理学の視点から探求します。社会契約論や功利主義に関する図解や思想家のコラムも含まれています。著者は哲学・倫理学を専門とする品川哲彦です。
世界における動物福祉論の最大の画期となり、現在まで重要性を増し続ける革命的書物にしてシンガーの代表作。そのあまりに苛烈かつ論理的な倫理の要求は、われわれ全存在に向けられている。大幅な改稿を施された2009年版にもとづく決定版。 第1章 すべての動物は平等である 第2章 研究の道具 第3章 工場畜産を打倒せよ 第4章 ベジタリアンになる 第5章 人間による支配 第6章 現代のスピシーシズム
この文章は、哲学者の一覧と著者情報を提供しています。著者は柘植尚則で、倫理学を専門とし、慶應義塾大学の教授です。彼は1964年に大阪で生まれ、1993年に大阪大学大学院を退学しました。
本書は、21世紀初頭にオランダで合法化された安楽死について、年間6000人以上の実施が行われている現状を紹介し、自己決定意識の拡大や超高齢化社会の中で、ベルギー、スイス、カナダ、米国へと広がる流れを描く。一方、精神疾患や認知症の人々への適用に関する問題も浮上している。著者は、安楽死の実態や日本における尊厳死の問題、人類の自死に関する思想史を探求し、「死の医療化」の現状を考察する。
『入門・医療倫理』から倫理理論に関する章を抜粋し再編集した入門テキスト。倫理学の基礎、規範倫理学、メタ倫理学、政治哲学を体系的に学べる内容で、英米系倫理学理論をわかりやすく解説。倫理学を初めて学ぶ学生に最適な一冊。著者は東京大学と京都大学の教授陣。
現代倫理学の基本文献。利他性が生物学的な起源を超えて普遍的な倫理へと拡張していくプロセスを鮮やかに描きだす。 理性の力がひろげる〈利他の輪〉 倫理とはなにか? 謎を解く鍵はダーウィン進化論にある。家族や友人への思いやりは、やがて見知らぬ他人へ、さらに動物へと向かう──利他性が生物学的な起源を超えて普遍的な倫理へと拡張していくプロセスを鮮やかに描きだす現代倫理学の基本文献。日々の選択から地球規模の課題にいたるまで、よりよい世界を願うすべての人に。 二〇一一年版へのまえがき まえがき 第一章 利他性の起源 第二章 倫理の生物学的基盤 第三章 進化から倫理へ? 第四章 理性 第五章 理性と遺伝子 第六章 倫理の新しい理解 引用文献に関する注 二〇一一年版へのあとがき 訳者解説 索引
本書は倫理学を「倫理について批判的に考える学問」と位置づけ、特に「功利主義」に焦点を当てています。倫理学の意義や実用性を示し、社会の常識やルールを再考する技術を提供します。内容は、功利主義の基本からその批判、公共政策への応用、幸福の概念、道徳心理学との関連まで幅広く探求しています。著者は東京大学の専任講師で、倫理学と政治哲学を専門とし、現代の生命倫理についても考察しています。
私たちの身近な物事を通して、人間の弱さや卑しさに眼差しをむける、倫理学の超入門書。 欲望とは何か、なぜ過去の記憶に悩まされるのか、偶然性とは何か、人生に意味はあるのか、そして〈私〉とは何か。私たちの身近な物事を通して、人間の弱さや卑しさに眼差しをむける、倫理学の超入門書。 人間の弱さや卑しさに眼差しをむける小さくて深い倫理学の入門書 ▼愛とは何か、正義とは何か、欲望とは何か、なぜ過去の記憶に悩まされるのか、偶然性とは何か、人生に意味はあるのか、そして〈私〉とは何か。身近な物事を通して、人間の弱さや卑しさに眼差しをむける、倫理学の入門書。 三田哲学会は創立100年を機に、専門的な研究成果を「生きられる知」として伝え、 公共の中に行き渡らせる媒体として本叢書の発刊を企図した。 シリーズ名は、ars incognita アルス インコグニタ。 ラテン語で「未知の技法」を意味する。 単なる知識の獲得ではなく、新たな「生きる技法としての知」を作り出すという精神を表現している。 1 小さな倫理学のすすめ 2 欲望の倫理学 3 情念のない人間は倫理的なのか 4 〈私〉という苦しみ 5 世界の中心で〈私〉を叫ぶ 6 天使たちの倫理学 7 偶然性を問うこと 8 ハビトゥスを歌うこと 9 風や流れとしての〈私〉 10 過去が苦しめ続けること 11 〈私〉もまた暗闇の中にありき 12 傷つきやすさ 13 涙の中の倫理学 14 さらば、正義の味方 15 友達がいないこと 16 倫理学も真理へと強制されるのか 17 人生に目的はない 18 悪と暴力性、あるいはサディズムとは何か 19 〈私〉への救済と〈私〉からの救済 20 〈私〉とは何か 後書き
本書は、AIやロボット技術の進化に伴う倫理的問題を考察し、人間の道徳について探求する入門書です。著者たちは、ロボットやAIとの関係における倫理学の知恵を提供し、道徳的行為者性や責任、プライバシー、労働の未来などのテーマを扱っています。著者は名古屋大学や南山大学、金沢大学の教授陣で構成されています。
直感的な善悪の方が哲学的倫理学より正しいのではないか。学問としての倫理学が真に目指すべきものと倫理学的観点の面白さを伝える。 直感的な善悪の方が哲学的倫理学より正しいのではないか。倫理学を根底から問い直し、学問としての倫理学が真に目指すべきものと倫理学的観点の面白さを伝える。 直感的な善悪の方が哲学的倫理学より正しいのではないか。倫理学を根底から問い直し、学問としての倫理学が真に目指すべきものと倫理学的観点の面白さを伝える。
京都議定書の発効、「持続可能性」「エコロジカル・フットプリント」といった概念の登場を踏まえて、好評の初版を大幅に改訂。 京都議定書の発効,温暖化に伴う気候変動の再評価,世界規模での貧富の差の拡大,「持続可能性」「エコロジカル・フットプリント」「拡大された製造者責任」といった概念の登場など,環境をめぐる理論的な状況の変化に対応して,好評の初版を大幅に改訂。 第1章 環境問題を倫理学で解決できるだろうか 第2章 人間中心主義と人間非中心主義との不毛な対立 第3章 持続可能性とは何か 第4章 文明と人間の原存在の意味への問い 第5章 環境正義の思想 第6章 動物解放論 第7章 生態系と倫理学 第8章 自然保護 第9章 環境問題に宗教はどうかかわるか 第10章 消費者の自由と責任 第11章 京都議定書と国際協力 第12章 環境と平和
この書籍は、初心者向けの倫理学入門書で、専門用語を避けた平易な表現で倫理学の基礎から現代のテーマまでを解説しています。10年ぶりの改訂版では、AIやロボット技術の進展に伴う科学技術倫理に関する新章が追加され、巻末には最新の入門書の読書案内も更新されています。内容は13章に分かれており、幸福、義務、徳、道徳判断、正義、医療、環境、科学技術、ビジネスなど多岐にわたるテーマを扱っています。哲学に興味があるが難しいと感じる社会人にも適した一冊です。
この書籍は、女子高生の体験を通じて生殖医療やがん告知、中絶、安楽死、クローン技術などの生命倫理に関する問題を考察する入門書です。各章では、具体的な事例を挙げながら、倫理的な問いかけを行い、読者に深い思索を促します。著者は倫理学や生命倫理学の専門家で、漫画家も参加しています。
モラルなき現代に正義・愛・自由を問う、新しい倫理学! 社会も、経済も、政治も、科学も、倫理なしには成り立たない。 倫理がなければ、生きることすら難しい。 人生の局面で判断を間違わないために、正義と、愛と、自由の原理を押さえ、 自分なりの生き方の原則を作る! 道徳的混乱に満ちた現代で、 人生を炎上させずにエンジョイする、〈使える〉倫理学入門。 * * * * 科学はみんなが学ばなくても、科学者が研究してくれれば、それで進歩します。 でも、倫理は違います。 というのは、倫理に関する知識は放っておいてはちゃんと働かないからです。 そして、倫理がなければ、我々は生きることも難しくなる。 だから、一人ひとりが倫理について考えた方がよいのです。 倫理っていうのは、他人事じゃなくて、自分自身の人生の問題だからです。 ――「まえがき」より まえがき はじめに/最初で最後の倫理学の本/考える倫理学?/倫理学と自分たちを繫ぐ/数万人の著者がいる本/主人公は私 序章 この本の使い方 いきなりの抜き打ちテスト!/結局、この本で何ができるか/この本の読み方 パート0 倫理学とは何か 第1章 倫理とは何か 1 - 1 まずはざっくりと ざっくり言って、倫理学って?/で、倫理って?/人間だもの/人間がいて、何かして/だから善悪が生まれる/ルールというか、規範/まとめ 1 - 2 倫理が必要なわけ ふーん、それで?/ガリンペイロの世界/倫理、道徳の必要性 1 - 3 倫理、道徳が意識されないわけ なぜ道徳は意識されないか/言葉・文法と道徳・倫理学の類似/小学校の「道徳」の時間はなんだったのか/空気のような/倫理学の小道1:倫理学がますます必要に? 第2章 倫理学とは何か 2 - 1 残念! 倫理にも弱点が…… 道徳の弱点/善悪なんて人によって違う!?/倫理、道徳を整理する/仕方ないでは困る! 2 - 2 それは自由のために 「道徳は押しつけである」説/子どもは分かってくれない!/それを大人は教えてくれない/倫理学は人を自由にする/倫理学の小道2:科学と倫理学、原因と理由 2 - 3 最も役立つ知識 「倫理学は役立たない」説/役に立つのが分かりにくい/倫理学は独特の仕方で役に立つ/倫理のない医者、非道徳的な技術者/倫理学の小道3:技術と倫理の関係、ついでに職業倫理について 2 - 4 倫理学の答え 倫理学に答えは?/具体的な答えが欲しい!?/「倫理」と「倫理の原理」/そして、使うのは「私」/コラム1:倫理学と人生論 2 - 5 ちょこっと例題――運命のボタン ボタンを押して一億円/思考実験/二つのレベルを分ける/心理の原因、道徳の理由/相互性/正義の原理/道徳の基本原理と理由 インターミッション1 倫理の三つの領域 第3章 倫理の三つの領域 3 - 1 三つの関係 分かれ道/人間の関係としての倫理/個人と社会と、そして/噓とカント/友人より義務が大事!?/コラム2:カントと『ライアーゲーム』とインターネット/人間像の違い/コラム3:カントの定言命法(倫理学用語の難しさと便利さ)/三つの関係 3 - 2 三つの関係を確かめる 二つの極とその中間/ある倫理学者の一日/具体例の分析/重なり合う関係 3 - 3 マンガに応用する 三つの関係を応用する/『デスノート』の分析/『ウロボロス――警察ヲ裁クハ我ニアリ』の分析/『ワンピース』の分析 パート1 社会の倫理:正義 第4章 正義の正体 4 - 1 釣り合いとしての正義 夜神君は正義か?/意見をまとめる/罪と罰の釣り合い/天秤のイメージ 4 - 2 社会、正義、ジコチュー 一人では決められない/正義とジコチュー/みんな同等 4 - 3 生きている社会 生きて動いている社会/正義は自然には生まれない 第5章 正義を洗う 5 - 1 勝った方が正義? 「正義」にしては薄すぎる?/「勝った方が正義」?/「正義の味方」? 5 - 2 正義なんてない? 「正義は人によって違う」?/「正義なんて自分の都合」?/正義は自分たちで作るもの 5 - 3 正義の理念と方法 もう一つの「正義はない」/理念と方法、目的と手段/理念は一つ、方法はたくさん/本の読み方についての注意 第6章 正義のパターン 6 - 1 調整の正義 正義にもパターンがある/調整の正義と法/復讐と正義は違う 6 - 2 交換の正義 交換の正義と経済/調整と交換、法と経済/臓器売買はオッケーか/コラム4:回るお金を支える倫理の力 6 - 3 分配の正義 分配の正義と政治/二種の分配方法/二種の分配の使い分け 6 - 4 パターン分けの意味 一つの正義、三つのパターン/三つのパターンは決め方の違い/パターン分けの意味/序章の問一の答え 第7章 個人と社会 7 - 1 なぜ正義が大事なのか 正義はなぜ必要か/正義がないと「ズルい!」になる/正義がないと「ひどい!」のまま/正義と権利/倫理学の小道4:権利、正義、法/他人同士が傷つけ合わな/倫理学の小道5:正義は時代によって変化する?――権利拡張の歴史 7 - 2 正義を「私」に落とし込む 正義と「私」?/正義と義務/個人の自由/「自由」というと? パート2 個人の倫理:自由 第8章 二種類の自由 8 - 1 消極的自由 自由と制限/「無制限な自由」の罠/自由に制限が必要なわけ/愚行権/義務の範囲/消極的自由 8 - 2 積極的自由 積極的自由/『デスノート』から『バクマン。』へ/「自分」について/自律/自律と自立/「本当の自分」 第9章 自律と幸福 9 - 1 アリストテレス先生の幸福論 なぜ自分への制限が必要なのか/優先順位を決める/幸福/アリストテレスの幸福主義/お金と人気と快楽/幸福とは何か?/アリストテレスから離れて 9 - 2 幸福、目的、質 お金持ちか、幸せか?/質と量/目的と手段 9 - 3 幸福の正体 「質より量、目的より手段」の挙げ句に/例えば、安楽死/幸福の正体/コラム5:遊び、幸福、暇(アリストテレスとマルクス) 第10章 運命と出会い 10 - 1 運命と幸福 なぜ幸福になるのは難しいか/運命/運命と出会い 10 - 2 身近な関係と愛 幸福を成り立たせるもの/身近な関係で大事なもの?/ここは一丁「愛」ということで パート3 身近な関係の倫理:愛 第11章 愛とは何でないか 11 - 1 恋愛こそ愛である? 難しい愛/余計なイメージを取り除く/「愛=セックス」説/「恋愛中心」説/愛の伝統的な分類法 11 - 2 愛とは感情である? 「愛=感情」説/ストーカーは愛するか/不安定な愛?/愛の形 第12章 恋愛と友情 12 - 1 男女間に友情は成り立つか? アリストテレスの恋愛論?/男女間に友情は成り立つか/男女間では恋愛しかない?/男女間の友情?/友情型と恋愛型/相補性と共同性 12 - 2 愛する人は一人だけ? 愛する理由/愛する人は一人だけ?/愛と正義/オンリー・ワン 12 - 3 友達がよそよそしくなるとき 愛の強さの違い/友達がよそよそしくなるとき/愛は外からは分からない/不釣り合いなカップルの謎/愛の偏り/コラム6:嫁姑問題はなぜ難しいか(あるいはマスオさんはなぜ磯野家に同居しているか) 12 - 4 あなたがここにいてほしい 愛で大事なこと/共通のものを大事にする/「徳は孤ならず」/本当の友情?/大事なものを大事にする/あなたがここにいてほしい/序章の問二の答え 第13章 愛のパターン 13 - 1 家族をバラバラにする! 親子愛は?/親子愛は相補型/相補型にも二種類ある!/『サザエさん』はなぜ面白いか/それでも一つのまとまり 13 - 2 愛の内と外 二×二で、四種類/縦の共同性/身近な関係としての会社?/身近な関係の内と外/コラム7:ぼくのおじさん 13 - 3 会社は面白い! 会社は面白い!/会社は作られる/何を大事にする関係か/契約があるか、ないか/会社は組織される/会社が社会的に見える理由 第14章 身近な関係と個人、社会 14 - 1 身近な関係と個人 ブラック企業が生まれるわけ/身近な関係と個人/音楽とスポーツの比喩/スポーツと会社、音楽と恋愛 14 - 2 身近な関係と社会 身近な関係と個人、社会/児童虐待はなぜ防ぎにくいか?/親子と社会/上司の不正な命令に従うか?/会社と社会/身近な関係と社会/視野を広く/コラム8:内部告発は裏切りか? インターミッション2 倫理のケーススタディ 第15章 愛や正義の使い方 15 - 1 試験の採点 倫理の基本原理のまとめ/試験の採点をする1/試験の採点をする2/試験の採点をする3/直観と手続き/間違いを防ぐ/コラム9:税金の納め方 15 - 2 ジレンマの解決 道徳的ジレンマ/ハインツのジレンマ/人生の解釈学 第16章 人生の解釈学 16 - 1 マンガの解釈学 マンガの解釈学/『噓喰い』、『カイジ』などの場合/『逃げ恥』の場合/愛と契約/お金で愛は買えるか? 16 - 2 小説も読もう 小説も読もう/「半沢直樹」の原型/『火花』/自律からおじさんまで/活きた倫理学 16 - 3 ついでに映画も ついでに映画も/『ゴッドファーザー』、ドンの場合/序章の問三の答え/身内、社会、居場所/マイケルの場合/倫理学の小道6:カント対孔子/地味な物語 第17章 身近な話題に倫理学はいかが 17 - 1 ネットとかSNSとか インターネットの新しさ/SNSのSは何? 17 - 2 浮気とか不倫とか 友人と恋人の境目は?/どこからが浮気か?/浮気と不倫/三角関係は?/一夫多妻制の意味/『終末のハーレム』 パート4 攻めの倫理! 第18章 攻めの倫理、守りの倫理 今までを振り返ると/倫理、道徳の二つのイメージ/攻めの倫理と守りの倫理/必要条件と十分条件/「あれかこれか」と「あれもこれも」/やっぱり分けよう 第19章 身近な関係での攻めの倫理 19 - 1 縦の相補型(ついでにケア倫理) 身近な関係における守りと攻め/縦の相補型/ケアの倫理/ケアと正義/ケアと愛/倫理学も進歩する 19 - 2 横の相補型(ついでに医療倫理) 横の相補型/医療の社会性/医療の相補性/患者の権利とインフォームド・コンセント/問題が複雑になる理由 19 - 3 横の共同型(ついでのついでに共同体主義) 横の共同型/『3月のライオン』と『となりの怪物くん』/地域コミュニティ/倫理学の小道7:コミュニタリアニズム/実は私、町内会長です/守りであり、攻めであり 19 - 4 縦の共同型(おまけに経営倫理) 縦の共同型/会社は複雑な組織/攻めに出ると――横と縦の違い/自己目的化する組織/会社も主体である/経営倫理――コンプライアンスとCSR 第20章 社会における攻めの倫理 20 - 1 最大多数の最大幸福!? 社会における守りと攻め/社会改良のための功利主義/功利主義の弱点/倫理学の小道8:動物の権利/功利主義の弱点?/使える場合と使えない場合/倫理学の小道9:功利主義のあれこれ 20 - 2 倫理から政治へ みんなにとって何が大事かが決まる場合/人によって何が大事か違う場合?/不妊治療を健康保険で?/なぜ「政治」なんていうものが必要なのか/多数決とは何か 20 - 3 アファーマティブ・アクション! 攻めの正義?/税金の使い方/アファーマティブ・アクション/積極的正義? 20 - 4 神の正義、人の正義 完全な正義/人間だもの(悪い意味で)/宗教マンガとしての『デスノート』/神の正義、人の正義/コラム10:宗教と経済/倫理学の小道10:グローバリゼーションと正義 第21章 個人における攻めの倫理 21 - 1 自己への自由 個人における攻めと守り/攻めに出るのも難しい/困難な自由 21 - 2 不確定義務 四つの自由/法的義務と道徳的義務/完全義務と不完全義務/「親切」/なぜ親切が不完全なのか/権利を伴わない義務/倫理学の小道11:グローバル正義論 21 - 3 他者への自由 不確定義務は義務なのか?/カントの「義務」論/他者への自由/厄介な自由 21 - 4 自己からの自由 チョー義務!/自己犠牲否定論?/もう一つ自己犠牲否定論/無償の愛/自己からの自由/コラム11:道元の言葉「仏道をならふといふは……」 終章 全体のおさらい 1 倫理の基本原理とパターン 三×四で、合計一二個/段階を分ける 2 人間関係に関する注意 関係の複合/関係の多面性/関係の変化 3 広く見て柔軟にバランスを 幅広く考える/「主人公は私」再び/全体のバランス/自分でも倫理学を作る、自分の人生を作る あとがき 付録パート1 倫理学の内と外 I章 倫理学のアウトライン I - 1 倫理学の三分野 倫理学の中身/規範倫理学/応用倫理学/メタ倫理学/記述倫理学 I - 2 ざっくり倫理学の歴史 規範倫理学の三つの立場/まずはソクラテスから、倫理学の始まり/徳の倫理/義務論と功利主義/問題は? II章 倫理学のお隣さん 倫理学のお隣さん/社会・人間科学の基礎としての倫理学/法と倫理、二種の規範/法と道徳の違い/法に則って粛々と…/それぞれの強みと弱み/倫理学の小道12:倫理は文化によって違う?(相対主義の問題) 付録パート2 倫理学の方法 III章 倫理学の方法 III - 1 まとめる 倫理学者はどうやって研究しているか/やり方の基本/価値判断から規範へ/ノー・モア・ルールズ!/規範から基本原理へ/理由としての原理 III - 2 どーんと原理から考える 「まとめる」方法の難点1――手間がかかる!/「まとめる」方法の難点2――どこで止めたらいいの!?/発想の転換 付録パート3 倫理の基本原理 IV章 多すぎても少なすぎても IV - 1 基本は一つか ベンサムの場合/功利主義の弱点/ゴドウィンの場合 IV - 2 基本はたくさんか ほんのついでのアリストテレス/徳倫理学の利点/徳倫理学の弱点/多すぎても少なすぎても V章 基本原理の基盤を求めて 少数原理主義は倫理を狭く考えている/観点を定める/コラム12:道徳的柔軟性
この書籍は、哲学の歴史を強者たちの論争を通じてわかりやすく紹介した入門書です。ソクラテスやデカルト、ニーチェなどの哲学者の考えを基に、真理、国家、神、存在についての議論を展開しています。著者の飲茶は、難解な哲学や科学の知識を楽しく解説することで人気を博しています。
本書は、現代倫理学の主要な問題を日常の倫理的ジレンマを通じて明らかにし、読者が倫理学の議論に親しむことを目的としています。著者は、難解な理論よりも実生活に即した問題を通じて、21世紀の倫理の枠組みを描くことを目指しています。具体的なテーマとして、嘘や殺人、エゴイズム、幸福の計算、正義の原理など、さまざまな倫理的問いが扱われています。
本書は、出口治明氏が古代ギリシャから現代までの哲学と宗教の全史を体系的に解説した教養書で、特に日本人の苦手とするこのテーマに焦点を当てています。3000年の歴史を俯瞰し、100以上の哲学者・宗教家の肖像を用いて、知識の深まりを促します。著者はライフネット生命の創業者であり、立命館アジア太平洋大学の学長。多くの著名人から高く評価されており、教育や思索の重要性を強調しています。
世界ゆるスポーツ協会代表理事が発見した、スポーツ、文化、働き方、社会、心のゆるめ方。ゆるめるとは、新しいルールをつくること… 老・若・男・女・健・障、すべての人が生きやすい世界を目指して--。世界ゆるスポーツ協会代表理事が発見した、スポーツ、文化、働き方、社会、心のゆるめ方。ゆるめるとは、新しいルールをつくること!! 老・若・男・女・健・障、すべての人が生きやすい世界を目指して--。 世界ゆるスポーツ協会代表理事が発見した、スポーツ、文化、働き方、社会、心のゆるめ方。 ゆるめるとは、新しいルールをつくること!! はじめに 第1章 スポーツをゆるめる 第2章 ゆるスポーツが生まれるまで 第3章 そもそも「ゆるめる」とは何か 第4章 「ゆるライズ」してみよう 第5章 “YURU”は日本独自のスタイル 第6章 ニューマイノリティをさがそう 第7章 働くをゆるめる 第8章 みんな普通で、みんな普通じゃない 第9章 ガチガチな世界からの脱出法 第10章 標準をゆるめる おわりに
この書籍は、大学における倫理学の重要性を強調し、世界の問題に取り組むための人材育成を目的とした入門書です。善悪や正義、幸福に関する価値を他者と共に考える能力が求められる中、倫理学の主要理論や様々な視点(功利主義、道徳感情論、社会契約論、正義論、ケアの倫理、フェミニスト倫理学など)を学ぶための章立てがされています。
〈人間vs.自然〉では環境問題は解決できない.「自然」「生命」「精神」などの象徴的なテーマから,「持続可能性」「外来生物」,そして「地球温暖化」など現代の地球環境問題まで,すべての二項対立図式を超えて,私たちがこれから豊かに生きていくための環境倫理の新しい地平を拓く! 序章 環境倫理の現在——二項対立図式を超えて(鬼頭秀一) 第I部 環境倫理が語れること 1 人間・自然——「自然を守る」とはなにを守ることか(森岡正博) 2 自然・人為——都市と人工物の倫理(吉永明弘) 3 生命・殺生——肉食の倫理,菜食の論理(白水士郎) 4 公害・正義——「環境」から切り捨てられたもの/者(丸山徳次) 5 責任・未来——世代間倫理の行方(蔵田伸雄) 6 精神・豊かさ——生きものと人がともに育む豊かさ(福永真弓) 第II部 環境倫理のまなざしと現場 7 「外来対在来」を問う——地域社会のなかの外来種(立澤史郎) 8 「持続可能性」を問う——「持続可能な」野生動物保護管理の政治と倫理(安田章人) 9 「文化の対立」を問う——捕鯨問題の「二項対立」を超えて(佐久間淳子) 10 「自然の再生」を問う——環境倫理と歴史認識(瀬戸口明久) 11 「地球に優しい」を問う——自然エネルギーと自然「保護」の隘路(丸山康司) Box1 野生復帰を問う−野生復帰において人はどこまで操作可能か(池田 啓) Box2 政策からこぼれ落ちるローカル知——ウチダザリガニと人間の環境問題(二宮咲子) 第III部 環境倫理から生まれる政策 12 家庭から社会へ——持続可能な社会に続く道を地球温暖化問題から考える(井上有一) 13 知識から知慧へ——土着的知識と科学的知識をつなぐレジデント型研究機関(佐藤 哲) 14 政策から政/祭へ——熟議型市民政治とローカルな共的管理の対立を乗り越えるために(富田涼都) 15 安全から危険へ——生態リスク管理と予防原則をめぐって(松田裕之) 16 制御から管理へ——包括的ウェルネスの思想(桑子敏雄) 終章 恵みも禍も——豊かに生きるための環境倫理(鬼頭秀一)
本書は、哲学の歴史を「魂の哲学」から「意識の哲学」、「言語の哲学」を経て「生命の哲学」へと展開するストーリーとして描いています。古代から21世紀までの人間の思考と精神の営みを探求し、ヘーゲルやシュペングラー、ローティを超えた新たな哲学史を提示します。著者は伊藤邦武で、京都大学で学び、教授を務めた経験があります。
「食べるために動物を殺すことを可哀相と思ったり、屠畜に従事する人を残酷と感じる文化は、日本だけなの?」 屠畜という営みへの情熱を胸に、アメリカ、インド海外数カ国を回り、屠畜現場をスケッチ!! 国内では東京の芝浦屠場と沖縄をルポ。「動物が肉になるまで」の工程を緻密なイラストで描く。 もくじ 第1章 韓国 カラクトン市場の屠畜場 知らなかった白丁差別/韓国人は焼き肉が好き?/牛の脊髄の味/カラクトンの屠畜場へ/電気ショックで叫ぶ豚/ マジャンドンで働く ソウル最大の肉市場/韓国BSE騒動/マジャンドンで将来設計/結婚相手はエリートと/両班が編み出した宮廷料理/肉はために食べるだけ/恐るべしモンゴル軍/ 差別はあるのかないのか 差別は昔の話か/儒教と牛肉/牛を昇天させる「神の杖」/「今はない」ということば/朝鮮戦争で消えたなんて/ 第2章 バリ島 憧れの豚の丸焼き 屠畜なぞ「朝飯前」/バリヒンドゥー教徒と牛/バビグリン屋の仕事/ココナツの殻で剃毛/油垂らして回る豚/黄金豚は朝焼けに輝く 満月の寺院でみた生贄牛 どんどん豚へ着火/宗教タブーはあるけれど/「殺す」じゃなくて「切る」/祭りと生贄/トゥリマカシ・バビ/命をもらう責任/東京のマンションで鶏をつぶす/ 第3章 エジプト カイロのラクダ屠畜 胎児に遭遇/神様がくれた仕事/中東にも豚がいた/公務員と肉屋 ギザの大家族、羊を捌く 4階の部屋で「放牧」/エジプト人家庭の中で/血の手形は捌いた徴/兄嫁は頭料理が得意/異文化の溝を埋めるのは/ 第4章 イスラム世界 イスラム教徒と犠牲祭 「怖い」の違い/シーア派の屠畜方法/そもそも犠牲祭とは/イスラム世界で暮らす日本人/犠牲祭は残酷か/ 第5章 チェコ 屠畜と動物愛護 ヨゼフ・ラダが描いたザビヤチカ/社会主義と豚/「虐待リポート」番組/大規模屠畜場は残酷か/ ザビヤチカ・豊穣の肉祭り ロスチャの腕前/はじめて知った豚のアレ/肉屋はお金持ち/資本主義社会で生き残るために/ 第6章 モンゴル 草原に囲まれて 食べることは命をもらうこと/社会主義時代の遊牧民/凍った羊を背負って/草原が育てた感覚/とびきりの羊肉を世界へ/ モンゴル仏教と屠畜 羊を食わねば生きていけない土地で/殺生戒を超えて/転がる生首に驚きながら/羊は天からの贈り物/チャンサンマハ草原の香り/ 第7章 韓国の犬肉 Dr.ドッグミートの挑戦 虐待に負けるな/ネットで犬肉を販売/抗議にも負けず、売上倍増/世界に名だたるDr.ドッグミート/犬肉のダイエット効果/モラン市場で食肉犬と対面/「犬白丁」ということば/滋養あふれる犬料理 第8章 豚の屠畜 東京・芝浦屠場 肉は作られる 肉のジョーシキ/ストレスが味を落とす/頭の重み/ ラインに乗ってずんずん進め 種豚と去勢豚/と畜検査もまた重労働/ホッグマシンで皮を剥け/枝肉の完成/ それぞれの職人気質 ここに入ったら肉が食える/女性作業員に聞く/茶髪の職人魂/知らない奴にどう思われようが/ すご腕の仕事師世界 Hさんの修行時代/ショリショリとナイフ捌きが伝わって/「分け前」と「タダ働き」/今橋龍一さんの手技/「見て盗む」には早すぎる!/職人技と近代化の狭間で/屠場と差別/ 第9章 沖縄 ヤギの魔力に魅せられて 家畜をつぶしておもてなし/豚がつなげるトイレと屠畜/ヤギ食にまで抗議/甘くとろける睾丸の刺身/ヤギ屠畜は名護まで/ 海でつながる食肉文化 皮も食べる沖縄の豚/豚をつぶす啼き声が食欲をそそる/犬も猫も食べた/舟に乗った家畜/ 第10章 豚の内臓・頭 東京・芝浦屠場 豚の内臓と頭 ひとつながりの内臓から/赤モノと白モノ/食感にこだわる腸の仕上げ/頭捌きは丁寧かつ迅速に/ 第11章 革鞣し 東京・墨田 革鞣しは1日にしてならず 豚革に惚れ込んで/まちの中は皮革工場がたくさん/原皮が運び込まれて来た/革が青くなる、クロム鞣し/染色は緻密に粘り強く/全身筋肉痛のハードワーク/脂から油へ/木下川という土地で/ 第12章 動物の立場から おサルの気持ち? かわいそうと動物福祉/人間は肉を食べる生物である/動物の要求を知り、応える/感情はなくても情動はある/「丁寧」に食べる/決めるのは社会、つまり私たち/ 第13章 牛の屠畜 東京・芝浦屠場 超高級和牛肉、芝浦に結集 食の安全を言うなら/屠畜頭数日本一/係留所からノッキングへ/気合と技術のピッシング/中身を肉につけない工夫/頭の行方/ 枝肉ができるまで 自分の睫毛かと思ったら/重い牛を安全に吊るす/危険部位・脊髄をしっかり吸引/大型マシンで皮剥き/内臓がもりもり出てくる/牛の人工授精最前線/枝肉の誕生/ BSE検査と屠畜 食肉衛生検査/BSE検査、はじめから終わりまで/スクリーニング検査でふるいにかける/陽性が出た場合/ 第14章 牛の内臓・頭 東京・芝浦屠場 内臓業者の朝 内臓の熱気に包まれて/脂肪の中に渦巻く大腸/内臓にも番号をつけて/複雑多岐な白モノ処理/ほほ肉捌きにホレボレ/BSE検査に対応して/夜明け前から作業/ 第15章 インド ヒンドゥー教徒と犠牲祭 肉を忌避するヒンドゥー教徒/在日インド人と肉食論争/通訳はヒンドゥー教徒/牛の犠牲は禁止/着飾った羊の行く先は/祈りのことばとともに喉を切る/犠牲の羊はひっそりと/ さまよえる屠畜場 驚きの大屠畜場/8割が闇営業/貧乏ではないけれど/ガジプールへの移転/ゴミの丘のふもとに食べ物市場が!/IT大国に残る不浄観/ 第16章 アメリカ 屠畜場ブルース 大嫌いな国、アメリカへ/大屠畜場見学ツアー/最低の仕事/屠畜工程の衛生対策/安い、早いの裏側で/やさしく殺して/カスタムキル—店の裏で捌く/今も健在、カウボーイ/数万頭規模での個体管理/ 資本主義と牛肉 屠畜を英語で言うと/牛糞まみれ、太もも美人/一方、北部の消費者は/オーガニックビーフがある/貧者の肉/ 終章 屠畜紀行のその後 ヤンさんとの再会/屠殺と屠畜の間で/獲物と死体/ あとがき/主要参考文献一覧
この書籍は、ダーウィンの進化論の正誤を整理し、進化論の歴史を解明するものです。『種の起源』が出版されてから160年が経過し、ダーウィンの理論には今でも有効な部分と誤りがあるため、多くの人が進化論を誤解しています。著者の更科功は古生物学の専門家で、進化の過程やダーウィンの考え方について詳しく解説しています。目次では、ダーウィンの正当性や進化の誤解、生物の進化の具体例が取り上げられています。
プラトン、アリストテレス、孔子、デカルト、ルソー、カント、サルトル…… では、女性哲学者の名前を言えますか? 男性の名前ばかりがずらりと並ぶ、古今東西の哲学の歴史。 しかしその陰には、知的活動に一生をかけた数多くの有能な女性哲学者たちがいた。 ハンナ・アーレントやボーヴォワールから、中国初の女性歴史家やイスラム法学者まで。 知の歴史に大きなインパクトを与えながらも、見落とされてきた20名の思想家たち。 もう知らないとは言わせない、新しい哲学史へのはじめの一書。 【目次より】 ◆ディオティマ Diotima(紀元前400年ごろ) ◆班昭 Ban Zhao(西暦45~120年) ◆ヒュパティア Hypatia(西暦350年ごろ~415年) ◆ララ Lalla(1320~1392年) ◆メアリー・アステル Mary Astell(1666~1731年) ◆メアリ・ウルストンクラフト Mary Wollstonecraft(1759~1797年) ◆ハリエット・テイラー・ミル Harriet Taylor Mill(1807~1858年) ◆ジョージ・エリオット(メアリー・アン・エヴァンズ) George Eliot (Mary Anne Evans)(1819~1880年) ◆エーディト・シュタイン Edith Stein(1891年~1942年) ◆ハンナ・アーレント Hannah Arendt(1906~1975年) ◆シモーヌ・ド・ボーヴォワール Simone de Beauvoir(1908~1986年) ◆アイリス・マードック Iris Murdoch(1919~1999年) ◆メアリー・ミッジリー Mary Midgley(1919~2018年) ◆エリザベス・アンスコム Elizabeth Anscombe(1919~2001年) ◆メアリー・ウォーノック Mary Warnock(1924~2019年) ◆ソフィー・ボセデ・オルウォレ Sophie Bosede Oluwole(1935~2018年) ◆アンジェラ・デイヴィス Angela Davis(1944年~) ◆アイリス・マリオン・ヤング Iris Marion Young(1949~2006年) ◆アニタ・L・アレン Anita L. Allen(1953年~) ◆アジザ・イ・アルヒブリ Azizah Y. al-Hibri(1943年~) 明晰な思考、大胆な発想、透徹したまなざしで思想の世界に生きた、 20の知られざる哲学の女王たち(フィロソファー・クイーンズ)。 知の歴史をひっくり返す、新しい見取り図。 「……人々は相変わらずこう思っている。プラトンの時代から 思想の分野を担ってきたのはほとんどが男性だろうと。 まるで、女性も偉大な哲学者になれるというプラトンの予言を、 これまでだれも実現してこなかったかのように。」 (本書「はじめに」より) 【目次より】 ◆ディオティマ Diotima(紀元前400年ごろ) ◆班昭 Ban Zhao(西暦45~120年) ◆ヒュパティア Hypatia(西暦350年ごろ~415年) ◆ララ Lalla(1320~1392年) ◆メアリー・アステル Mary Astell(1666~1731年) ◆メアリ・ウルストンクラフト Mary Wollstonecraft(1759~1797年) ◆ハリエット・テイラー・ミル Harriet Taylor Mill(1807~1858年) ◆ジョージ・エリオット(メアリー・アン・エヴァンズ) George Eliot (Mary Anne Evans)(1819~1880年) ◆エーディト・シュタイン Edith Stein(1891年~1942年) ◆ハンナ・アーレント Hannah Arendt(1906~1975年) ◆シモーヌ・ド・ボーヴォワール Simone de Beauvoir(1908~1986年) ◆アイリス・マードック Iris Murdoch(1919~1999年) ◆メアリー・ミッジリー Mary Midgley(1919~2018年) ◆エリザベス・アンスコム Elizabeth Anscombe(1919~2001年) ◆メアリー・ウォーノック Mary Warnock(1924~2019年) ◆ソフィー・ボセデ・オルウォレ Sophie Bosede Oluwole(1935~2018年) ◆アンジェラ・デイヴィス Angela Davis(1944年~) ◆アイリス・マリオン・ヤング Iris Marion Young(1949~2006年) ◆アニタ・L・アレン Anita L. Allen(1953年~) ◆アジザ・イ・アルヒブリ Azizah Y. al-Hibri(1943年~)
障害者を考えることは健常者を考えることであり、同時に自分自身を考えること、なぜ人と人は支え合うかを「障害」を軸に解き明かす。 障害者を考えることは健常者を考えることであり、同時に自分自身を考えること、なぜ人と人は支え合うかを「障害」を軸に解き明かす。 『こんな夜更けにバナナかよ』から15年、渡辺一史最新刊! ほんとうに障害者はいなくなった方がいいですか? 今日、インターネット上に渦巻く次のような「問い」にあなたならどう答えますか? 「障害者って、生きてる価値はあるんでしょうか?」 「なんで税金を重くしてまで、障害者や老人を助けなくてはいけないのですか?」 「自然界は弱肉強食なのに、なぜ人間社会では弱者を救おうとするのですか?」 気鋭のノンフィクションライターが、豊富な取材経験をもとにキレイゴトではない「答え」を真摯に探究! あらためて障害や福祉の意味を問い直す。 障害者について考えることは、健常者について考えることであり、同時に、自分自身について考えることでもある。2016年に相模原市で起きた障害者殺傷事件などを通して、人と社会、人と人のあり方を根底から見つめ直す。
この書籍は、倫理学の基本を解説した入門書で、三つの主要な部に分かれています。第1部では規範倫理学として義務論、功利主義、徳倫理学を比較し、私たちが何をすべきかを探ります。第2部はメタ倫理学で、「善」の性質や非認知主義と認知主義の対立について論じます。第3部では応用倫理学として、環境倫理、動物倫理、生命倫理などの具体的な問題に対処します。著者は中村隆文で、哲学を専攻し、大学で教鞭を執っています。
倫理学の中心的な諸問題を深い学識と鋭い眼差しで再検討した現代における古典的名著。倫理学はいかに変貌すべきか、新たな方向づけを試みる。 倫理学の中心的な諸問題を深い学識と鋭い眼差しで再検討した現代における古典的名著。倫理学はいかに変貌すべきか、新たな方向づけを試みる。
14歳からの「考える」のための教科書。「自分とは何か」「死」「家族」「恋愛と性」「メディアと書物」「人生」など30のテーマ。 今の学校教育に欠けている14歳からの「考える」の為の教科書。「言葉」「自分とは何か」「死」「家族」「社会」「理想と現実」「恋愛と性」「メディアと書物」「人生」等30のテーマ。 人には14歳以後、一度は考えておかなければならないことがある。 言葉、自分とは何か、死、心、他人、家族、社会、理想と現実、友情と愛情、恋愛と性、仕事と生活、本物と偽物、メディアと書物、人生、善悪、自由など、30のテーマを取り上げる。 Ⅰ 14歳からの哲学[A] 1 考える[1] 2 考える[2] 3 考える[3] 4 言葉[1] 5 言葉[2] 6 自分とは誰か 7 死をどう考えるか 8 体の見方 9 心はどこにある 10 他人とは何か Ⅱ 14歳からの哲学[B] 11 家族 12 社会 13 規則 14 理想と現実 15 友情と愛情 16 恋愛と性 17 仕事と生活 18 品格と名誉 19 本物と偽物 20 メディアと書物 Ⅲ 17歳からの哲学 21 宇宙と科学 22 歴史と人類 23 善悪[1] 24 善悪[2] 25 自由 26 宗教 27 人生の意味[1] 28 人生の意味[2] 29 存在の謎[1] 30 存在の謎[2]
本書は、イスラーム文化の本質を探求し、宗教、法と倫理、内面の道を通じてその根底にある要素を明らかにします。著者は、顕教と密教の対立を考察し、イスラーム文化の深層に迫る内容となっています。
本書は倫理学が哲学の中心であることを強調し、古代ギリシアから20世紀までの思想家たちの倫理に対するアプローチを三つの潮流に分けて解説します。アリストテレスやエピクロス、ストア派から始まり、功利主義やカント、ヘーゲルに至るまでの人間性の探求を通じて、倫理が人間の行動や思索をどのように規定するかを明らかにします。著者は宇都宮芳明で、哲学・倫理学の専門家です。
本書は、道徳的な善悪について哲学的に探求する内容で、二人の大学生と猫のアインジヒト、M先生が対話を通じて「人は幸福を求めるのか」「社会契約は可能か」「なぜ道徳的であるべきか」といったテーマを議論します。プラトンやアリストテレス、ホッブズ、ルソー、カントなどの思想を紹介しながら、倫理学の新たな視点を提供する不道徳な教科書です。著者は永井均で、哲学・倫理学を専攻する教授です。
なんだか難しそうな哲学。しかし哲学することは特別なことではない。身近なテーマから、哲学するとはどんな行為なのかを解き明かす。 なんだか難しそうな哲学。中身は分からなくても、漠然と難しそうにみえる哲学。しかし、哲学することはなにも特別な行為ではない。哲学が扱うのはどれも実は身近な問題ばかりである。ニュースなどで見かける問題、人と話すときに話題にするようなこと、実はそこに哲学が隠れている。本書は、これを手がかりにさらに読者なりに考えを深めるための道具箱のようなものである。カントいわく、哲学は学べない。読者はこれをヒントに自分で考える。そこに哲学が存在する。 はじめに(戸田剛文) 第一部 身近なテーマから 第1章……いま芸術に何が期待されているのか(阿部将伸) はじめに 1 視線の向けかえ―古代 2 視線の落ち着き先の変容1―古代末から中世へ 3 視線の落ち着き先の変容2―近代 4 コミュニティ感覚 おわりに ❖おすすめ書籍 第2章……犬と暮らす(戸田剛文) はじめに 1 動物への道徳的配慮 2 具体的な問題 3 動物を食べることは正当化できるのか 4 幸福な社会 ❖おすすめ書籍 第3章……宗教原理主義が生じた背景とはどのようなものか(谷川嘉浩) はじめに 1 原理主義とはどのようなものか 2 近代化と、キリスト教原理主義 3 手のなかに収まらないものへ ❖おすすめ書籍 第4章……幸福の背後を語れるか(青山拓央) はじめに 1 幸福をめぐる三説 2 「私」の反事実的可能性 3 私的倫理と自由意志 4 『論考』と言語 5 『論考』と倫理 ❖おすすめ書籍 第二部 哲学の伝統 第5章……原因の探求(豊川祥隆) はじめに―「なぜ」という問いかけ 1 言葉の根―「アイティア」について 2 近代科学という営みと「目的」の瓦解 3 ドミノ倒し 4 現代の「原因」観―概念の多元主義にむけて 5 おわりに―人間の進歩と面白さ ❖おすすめ書籍 第6章……言葉と世界(佐野泰之) はじめに―言葉のない世界 1 言語論的転回 2 論理実証主義への批判 3 解釈学的転回 おわりに―私たちは言語の囚人なのか? ❖おすすめ書籍 第7章……知識と懐疑(松枝啓至) はじめに 1 古代懐疑主義 2 デカルトの「方法的懐疑」 3 「懐疑」について「懐疑」する―ウィトゲンシュタインの思索を手掛かりに ❖おすすめ書籍 第8章……存在を問う(中川萌子) はじめに 1 「存在とは何か」という問いの動機と必要性―ニーチェとハイデガーの時代診断 2 存在とは何か? 「存在とは何か?」と問うことはどのような営みか? 3 「存在とは何か」という問いの形式と歴史 4 「存在とは何か」と問うことの自由と責任―ハイデガーとヨナスの責任論 おわりに ❖おすすめ書籍 あとがき 索引(人名・事項)
自動運転車やケア・ロボット、自律型兵器などが引き起こしうる、もはや SF では済まされない倫理的問題を通し、人間の道徳を考える、知的興奮に満ちた入門書。「本書には、ロボットや AI という新しい隣人たちとつきあう上で参考となる倫理学の知恵がつまっている」 —— 伊勢田哲治。 はじめに Ⅰ ロボットから倫理を考える 第1章 機械の中の道徳 —— 道徳的であるとはそもそもどういうことかを考える 1-1 アシモフのロボット工学三原則 1-2 倫理はプログラム可能か? 1-3 道徳と感情 1-4 機械化された道徳は道徳なのか? 1-5 おわりに 第2章 葛藤するロボット —— 倫理学の主要な立場について考える 2-1 まず倫理に含めないものを除外しよう 2-2 倫理学を三つに分ける 2-3 規範倫理学の主要な二つの立場 : 帰結主義 (功利主義) と義務論 2-4 功利主義 2-5 義務論 2-6 第三の立場 : 徳倫理学 2-7 おわりに 第3章 私のせいではない、ロボットのせいだ —— 道徳的行為者性と責任について考える 3-1 「ロボットに責任を帰属する」 とは? 3-2 ロボットも責任主体になれるかも? : 両立論の考え 3-3 人は自己形成をコントロールできない : 非両立論の考え 3-4 ロボットへの帰責は可能か? 3-5 おわりに 第4章 この映画の撮影で虐待されたロボットはいません —— 道徳的被行為者性について考える 4-1 道徳的被行為者とは 4-2 道徳的被行為者としての人間 4-3 道徳的被行為者の範囲は? 4-4 ロボットを道徳的被行為者とみなす必要性はあるか? 4-5 おわりに Ⅱ ロボットの倫理を考える 第5章 AI と誠 —— ソーシャル・ロボットについて考える 5-1 ソーシャル・ロボットの普及 5-2 まやかしの関係? 5-3 ソーシャル・ロボットはユーザーを欺いていると言えるのか? 5-4 うそも方便 5-5 ソーシャル・ロボットが社会に与える影響 5-6 おわりに 第6章 壁にマイクあり障子にカメラあり —— ロボット社会のプライバシー問題について考える 6-1 ロボット利用に伴うプライバシー問題 6-2 プライバシー権とは 6-3 プライバシーの価値と情報化時代のプライバシー理論 6-4 ロボット共生社会における情報プライバシー 6-5 おわりに 第7章 良いも悪いもリモコン次第? —— 兵器としてのロボットについて考える 7-1 遠隔操作型兵器から自律型兵器へ 7-2 戦争にも倫理はある 7-3 自律型兵器をめぐる賛否両論 7-4 兵器開発競争への懸念 7-5 戦争の生態系 7-6 おわりに 第8章 はたらくロボット —— 近未来の労働のあり方について考える 8-1 創作物における 「はたらくロボット」 8-2 機械はなんでもできる 8-3 技術的失業と機械との競争 8-4 社会的な影響と対策 8-5 悪いことだけなのか? 8-6 ロボットにできるからといってロボットに任せたいとは限らない 8-7 労働者としてのロボットの責任と権利 8-8 おわりに
この書籍は、部屋や心、人生を浄化するための片づけ術を紹介しています。内容は、物を捨てる判断や自己認識、過去への執着を手放すこと、内面の整理が外面に影響することなど、多岐にわたります。著者はアメリカの片づけコンサルタント、ブルックス・パーマーで、家庭や職場の整理を手伝い、広く講演も行っています。
サイモン・ブラックバーンの著書は、倫理学を初めて学ぶ読者向けの超入門書であり、現代の陰謀論や政治不信に対処するための思考力を養うことを目的としています。内容は、倫理学の基本概念や脅威、倫理的な考え方を解説し、附録には人物解説や読書案内が充実しています。初版以来、「最初に読むべき一冊」として評価されており、基礎から応用までをコンパクトに学べる内容です。
この書籍は、人工知能(AI)に関する過大視や悪夢のシナリオを乗り越え、AIが引き起こす倫理的疑問に対して具体的な回答を提供し、受け入れ可能な統合的な視点を提示しています。技術的、哲学的、実践的な側面がバランスよく扱われ、AI社会の人間中心なデザインのためのアイデアも提案されています。著者はAI倫理の第一人者であり、専門的な背景を持つ教授たちです。
・20世紀を代表する哲学者、バーナード・ウィリアムズによるカリフォルニア大学の名講義。 ・西洋哲学が見落としていた「倫理」をギリシア古典に発見し、近代道徳の呪縛から解放する〈反道徳的な倫理学〉。 ・解説=納富信留(東京大学大学院教授) 近代以降の進歩主義的な見方では、古代ギリシア人は未開の心性をもち、より洗練された道徳が人間性を陶冶してきたと捉えられてきた。 ウィリアムズはこのような道徳哲学の提示する人間が、生きられた経験から切り離された、無性格な道徳的自己であるとして批判する。それとは対照的に、具体的な性格と来歴をもつ人々を描く、ホメロスの叙事詩やアイスキュロス、ソポクレスらの悲劇作品を読み解き、そこに流れる豊かな倫理的思考を明らかにする。 道徳哲学やプラトン、アリストテレスらの哲学を批判的に参照しながら、恥と罪、必然性(運命)と義務、運命と自由意思、責任と行為者性といった概念をめぐる議論を通して、古代と現代を通じてこの現実を生きる人間の生の姿を描き出す、カリフォルニア大学の名講義。 はじめに 二〇〇八年版への序文 A. A. ロング 第一章 古代の解放 第二章 行為者性のいくつかの中心 第三章 責任を認識すること 第四章 恥と自律 第五章 いくつかの必然的なアイデンティティ 第六章 可能性・自由・力 解説 古代ギリシアから私たちが学ぶこと 納富信留 訳者あとがき 古典文献一覧 参考文献一覧 附録1/附録2 注 索引
カント哲学の核心は、理性が持つ欺瞞性に対する挑戦にある。彼は理性の二面性を発見し、それを批判することで哲学の新たな道を切り開いた。本書では、カントの生涯や思想を探求し、特に『純粋理性批判』を通じてその哲学の核心を明確に解説する。各章では、理性のアイデンティティや批判哲学の背景、自由と道徳法則の関係などが論じられ、カントの新たな像が描かれる。
この書籍は、徳倫理学の入門書であり、善き生を求める古代から現代に至る倫理学の発展を解説しています。功利主義や義務論とは異なり、個々の行為ではなく人生全体を考察する視点を提供し、古代ギリシアや中世、西洋の哲学、中国の儒教、近現代の思想家を網羅しています。また、環境、医療、ビジネス、政治などの応用倫理についても触れています。著者は、各分野で活躍する研究者たちです。
本書は、近代哲学の問題を明確に論じたもので、分析哲学の出発点とその将来を示しています。著者バートランド・ラッセルは、知識の認識や哲学の限界、価値について探求し、今日も読み継がれる哲学入門書の名著です。新訳版として登場しました。
意見のすれ違う人と話し合うのは不毛か。「論破」したら勝ち、でいいのか。生産的議論のためのクリティカル・ディスカッション入門。 意見のすれ違う人と話し合うのは不毛か。「論破」したら勝ち、でいいのか。「価値観の壁」を越え、生産的に議論するためのクリティカル・ディスカッション入門。 意見のすれ違いの根底には「倫理問題」がある――。 「はい論破」ではなく、協力的で生産的な議論を。 わかり合えない人と話し合うための討論の技法! 物事の善し悪しを判断するのは難しい。社会のあるべき姿や幸せの形も人それぞれ。ならば意見のすれ違う人と対話するのは不毛なのだろうか。それでも私たちは他者と共に社会をつくるため、答えの出ない問題について話し合わなければいけないことがある。そんなとき、小手先の論理で相手を説き伏せようとする前に、対立の根本に遡って「そもそも倫理とは何か」と考えてみることがとても役に立つ。「価値観の壁」を越え、生産的に議論するためのクリティカル・ディスカッション入門。 はしがき 序章 哲学思考のその先へ SS0-1 唯一無二の食事1/クリティカル・シンキングとは/協力的クリティカル・シンキング/倫理的クリティカル・シンキング/倫理的思考における文脈主義/SS0-2 唯一無二の食事2/「そもそも倫理とは何か」を考える必要がでてくるのはどういうときか/本書の構成 ブックガイド 第一章 倫理を外から眺める SS1-1 エンケラドス生命たちの自衛1/自然主義的視点/モラル・サイコロジー/暴走路面電車という思考実験/倫理的判断ははらわたの感覚で決まっている/倫理は進化のプロセスで形成された?/道徳は簡単には進化に還元できない/運命共同体が生む道徳/SS1-2 エンケラドス生命たちの自衛2 ブックガイド 第二章 複視的に世界を眺める方法――中の人にしか見えない「社会」とは? SS2-1 見えるようになったもの1/拡張現実とは/「社会的な事実」とは/なぜ一万円札には価値があるか―制度的な規則と制度的事実/やりとりの中から浮かび上がる「社会」/社会的な存在としての「自己」/一貫性論争/コラム 平野啓一郎の分人主義/拡張現実としての「社会的事実」/「社会メガネ」は気の持ちよう?/一様ではない「社会メガネ」/二重写しに世界を見る/SS2-2 見えるようになったもの2/社会の存在論 ブックガイド 第三章 倫理とは何か――自由意志と倫理はどのように「見える」ようになるか 1 道徳的主体としての自分 SS3-1 丘に穴掘る部族の覚醒1/倫理メガネをかけて世界を眺める/「自由意志メガネ」のむこうに見える道徳的主体/自由意志は存在しないのか/道徳判断と行為はどうつながるか 2 善悪の客観性はどこからくるのか SS3-2 丘に穴掘る部族の覚醒2/「べき」には一貫性が求められる/客観主義と実在論/「客観性」や「実在性」は異星人にも見えるのか/「道徳的理由」に彩られた世界/コラム 非認知主義に対するアドバンテージ(ガチな人向けの補足)/人々はどのくらい道徳を客観的に捉えているか 3 善悪はフィクションか 「倫理メガネ」と錯誤理論/メガネをかける=感受性を研ぎ澄ます/SS3-3 丘に穴掘る部族の覚醒③/倫理とは半強制参加の拡張現実だ/自分のメガネは見えない/「倫理メガネ」の多層性と多様性 ブックガイド 第四章 倫理的思考の四つのものさし――善悪をどう測るか 1 倫理的思考のものさし SS4-1 旧友の依頼1/規範倫理学の考え方/四つのものさし 2 結果のものさし 幸せについての三つの考え方/功利主義という考え方/価値があるのは「幸福」だけか/コラム 生命の価値 3 ルールのものさし ルールの類型化/義務論1――一見自明の義務/義務論2――カント主義の場合/切り札としての権利/自己決定権とインフォームド・コンセント/誰の視点かで変わる答え/副次効果という考え方は有効か 4 性格のものさし 古代ギリシアから儒教まで/性格のものさしの特徴 5 関係のものさし ケアするものとされるものの関係/専門職倫理/関係のものさしはあくまで関係がある限りで働く/コラム 自分に対する責任 6 四つのものさしを使いこなす 四つのものさしの関係/ものさしへの感受性を研ぎ澄ます/SS4-2 旧友の依頼②/正当化的用法と発見的用法/倫理判断のクリームシチューモデル/コラム 未確定領域功利主義(ガチな人向けの補足) ブックガイド 第五章 なぜ意見が食い違うのか――倫理問題の難しさ 1 意見はどこで食い違っているか SS5-1 真空愛着1/すれ違いのパターン分類 2 言葉の意味についての食い違い SS5-2 真空愛着2/「定義」のずれ/言葉のネットワークのずれ/空を飛べないものは鳥ではない?――事例ベースで学んだ概念のずれ/言葉の使い方をどうすり合わせるか 3 事実関係についての食い違い SS5-3 真空愛着3/誰が何を言ったかの食い違い/調査が必要なことがらについての食い違い/調査結果の解釈のずれ/幅のある推定値/将来予測のずれ/誰が情報提供者として信頼できるか/バイアスが対立の溝を深める 4 価値についての食い違い SS5-4 真空愛着4/強制参加の中の自由度が生む考え方の違い/コラム とがめるほどでない過ち/社会メガネの食い違い 5 問題設定についての食い違い SS5-5 真空愛着5/問題の基本的枠組みについてのずれ/検討範囲のずれ/「次元数」の違い/誰に立証責任があるか/見え方の差を生む心理的背景/どれでもよいというわけではない 6 多対多の論争における食い違い SS5-6 真空愛着6/SNSが社会を分断する?/なぜネットはいつも揉めているのか――敵対的な討論状況/なぜ討論相手の主張をまじめに受けとれないか/一般化された欠如モデル/多対多討論状況/やっつける「敵」を特定する――「陣営」のイメージの危険性/わら人形論法の温床――多対多討論状況が生む討論のすれ違い/多対多敵対的討論状況というモデル ブックガイド 第六章 互いの論証をチェックする――協力的に討論をするための技法1 1 協力的討論のながれ SS6-1 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)1/協力的に討論するための五つのステップ/協力的態度は相互作用の中で作られる/「対立の解消」の二つのパターン 2 論証図をつくる 論証図における矢印の意味/コラム MECE(ミーシー)/消極的根拠と否定的根拠/論証構造の類型/論証図についてのよくある疑問 3 暗黙の前提と結論の明示化 暗黙の結論の明示化 4 前提と推論の予備チェック 事実関係をチェックする/価値主張をチェックする/誤謬推論になっていないかチェックする/文脈にあった推論になっているか ブックガイド 第七章 論破ではなく協力――協力的に討論をするための技法2 1 対論図をつくる SS7-1 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)2/対論図の基本的な考え方/対論になっていない討論/わら人形論法と論点ずらしの誤謬/コラム 食い違いのポイントをしぼりこむ方法/どういう場合に考えを変えるか訊いてみる/SS7-2 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)3 2 対立をどう解消するか 言葉遣いのすり合わせ/事実認識のすり合わせ/心理学的仕組みに注意をはらう/価値主張のずれの解消/メガネをすり合わせる/正解は発見されるのか発明されるのか/価値の大小についての食い違い/問題設定についての食い違い/地平の融合/SS7-3 メッセンジャー号の批判的討論(クリティカル・ディスカッション)4 3 多対多敵対的討論状況にどう対処するか 一般化された欠如モデルを避ける/「陣営」として捉えない/ゼロサム的に問題を捉えない/第三者にどう見えるかも気にかける/コラム ネガティブ・ケイパビリティ ブックガイド 第八章 批判的でいるのはいつでもよいことか──無理せずクリティカルに生きる SS8-1 エピローグ1/ここまでのおさらい/クリティカル・シンキングはどこまで合理的か/クリティカル・シンキングは騙されにくいか/SS8-2 エピローグ2/?つきとも協力すべきか/自分を傷つけようとしている相手ならどうか/SS8-3 エピローグ3/売られた喧嘩は買うしかないのか/当事者を傷つける心配はないか――二次被害の可能性と文脈の分業/SS8-4 エピローグ4/身の危険を感じたら考える前にまず逃げよ――緊急事態とクリティカル・シンキング/無理せずクリティカルに生きる ブックガイド 注/あとがき
本書は、図解を用いて哲学の歴史をわかりやすく解説した入門書です。ソクラテス以前から21世紀の思想まで幅広くカバーし、中世の普遍論争やハイデガーの『存在と時間』なども詳しく説明しています。哲学用語の理解を助けるための解説や、問題設定の背景を丁寧に説明し、視覚的な資料を多く用いることで直感的な理解を促進します。著者は専修大学の教授で、現代哲学や舞踊研究に精通しています。
この入門書は、古代から現代までの哲学の流れや近代日本の哲学、主要な哲学的テーマを網羅しています。見開き2ページで各トピックを解説しており、全体の流れを理解しつつ個別の学びが可能です。現代的なテーマとしてSTS(科学技術社会論)、子どもの哲学、クィア・LGBT、アフォーダンスなども取り上げています。著者は東京大学、阪大、慶應義塾大学の教授たちです。
〈入門編/実践篇〉とをキーワードに、適切な根拠に基いた論理的で、偏りのない思考へ導く。 信じるにたるとするものを見極め,自分の進むべき方向を決断し,問題を解決する生産的思考がクリティカル思考だ。メタ認知とマインドフルな態度を軸に学習,問題解決,議論の際の<クリシン>思考を身につける本。 好評の<入門篇>に続く<実践編>。たんに懐疑や批判のための思考ではなく,信じるにたるとするものを見極め,自分の進むべき方向を決断し,問題を解決する生産的な思考がクリティカル思考である。メタ認知とマインドフルな態度を支柱に,学習,問題解決,意志決定,議論の際の<クリシン>思考を身につける本。 6章 自分は何を知っているかを知る 1 はじめに 2 メタ認知 3 何を学ぶべきかについて考える 4 なぜ「わかったつもり」になってしまうのか 5 十分勉強したかどうかを知る 7章 問題を解決する 1 はじめに 2 「問題」とは何か 3 効果的な問題解決へのアプローチ 8章 意思決定をする 1 はじめに 2 システマティックな意思決定モデル 3 意思決定が間違っていたことがわかったとき 9章 良い議論と悪い議論 1 はじめに 2 「議論」の定義 3 二つの議論の形式を概観する 4 演繹的議論を評価する規準 5 帰納的議論を評価する規準 6 誤った論法 10章 エピローグ 1 省察的思考としてのクリティカル思考 2 アクティブな思考としてのクリティカル思考 3 問題解決の中でのクリティカル思考 クリティカルシンキングのための原則 【考えてみよう】の解説 推薦図書 事項索引 引用文献
この書籍は、現代医療とバイオテクノロジーの進展が「より健康に、より長く生きたい」という人々の願いをどのように実現しているかを探求しています。しかし、生命科学の進歩が「いのちをつくり変える」領域に踏み込む可能性についても警鐘を鳴らし、新しい倫理観を考える必要性を提起しています。目次では、治療を超えた身体の改造、出生前診断、再生医療、死生観など、多岐にわたるテーマが扱われています。著者は島薗進で、宗教や死生学の専門家です。
本書は、イェール大学で23年間人気を誇る講義を完全翻訳したもので、余命宣告を受けた学生が受講した伝説の授業を基にしています。死というテーマを通じて、人生の価値や生き方に焦点を当て、死への恐怖や孤独感、不死の可能性について考察します。内容は、死の本質、魂の存在、人格の同一性など多岐にわたり、読者に深い思索を促します。全体を通して、死を理解することで生がより輝くことを伝える名著です。
本書では、現代人が抱える「将来の不安」「お金への欲望」「死への恐怖」といった悩みを、哲学者たちの視点から解決に導く内容が紹介されています。アリストテレスやアンリ・ベルクソン、マックス・ウェーバーの考えを通じて、平易な言葉で哲学を学びながら悩みを解消することができる一冊です。
社会派ブロガー・ちきりんのベストセラーが大重版され、文庫化された本書は、自由で楽観的な生き方を提案しています。著者は、仕事やお金、人生設計について合理的に考えることで、今を楽しむ重要性を説いています。具体的なアドバイスとして、低い目標設定や自分基準での生き方、賢いお金の使い方、ストレスフリーな生活を推奨しています。著者は、過去に証券会社で働いた経歴を持ち、現在は執筆活動に専念しています。
この書籍は、人と動物の関係に関するさまざまな倫理的問題を探求しています。ペットのしつけや動物の殺処分、化粧品の動物実験、肉食、動物園、外来種、医療のための動物実験、野生動物の保護と駆除、イルカ・クジラの問題など、多岐にわたるテーマを扱っています。高校生の「生き物探偵」がこれらの問題に挑むマンガ形式で、読者に考える機会を提供します。著者は哲学者で、科学哲学や倫理学を専門としています。
著者ドミニク・オブライエンは、驚異的な記憶力を持つ世界記憶力選手権の優勝者であり、記憶力を向上させるための様々な方法を紹介しています。彼はジャーニー法やドミニク・システムなどの記憶術を解説し、脳の働きを解明しつつ、効果的なトレーニング方法を提供しています。目次には、記憶力の関連付けや連想結合法などのトピックが含まれています。
本書は、内向型人間の特性や強みを探求し、彼らが直面する社会的な問題を明らかにする内容です。ビル・ゲイツやガンジーなど多くの成功者が内向型であることを示し、アメリカ社会における外向型の優位性を批判します。内向型の人々が自分の特性を活かす方法や、外向型とのコミュニケーションの課題についても議論されています。全体を通して、内向型の魅力とその重要性が強調されています。
この書籍は、哲学をわかりやすく解説し、西洋と東洋の主要な哲学者50人の思想を紹介しています。内容は古代から現代までの哲学を網羅し、哲学の基本テーマや重要概念についても触れています。著者は哲学教授の貫成人で、哲学の面白さと実用性を伝えることを目的としています。
この文章は、ローマの哲人皇帝マルクス・アウレーリウスの著作についての紹介です。彼の内省的な言葉は多くの人々に影響を与えてきました。神谷美恵子による訳文に加え、新たな注釈が付されています。内容は複数の巻に分かれており、訳者の序や解説も含まれています。
この書籍は、哲学を学ぶ際の多様さと難解さに対処するための実用ガイドです。古代ギリシャから現代哲学、さらに西洋形而上学と東洋思想を網羅し、哲学者同士の関係を通じて思考の本質を理解する手助けをします。著者は専修大学の教授で、現象学や歴史理論を専門としています。
本書は、論理性よりも創造性・発想力が人生の成功に不可欠であることを説いています。現代の不確実性の中で、発想力が重要な要素となるとし、成功者の創造性や「ひらめき」を自分のものにする方法を紹介します。内容は、発想力を高める方法、アイデアを形にする技術、スランプ克服法、ネガティブな感情を活用した創造性向上の裏技など、多岐にわたります。著者はメンタリストDaiGoで、科学的アプローチから最高のアイデアを生む方法を提供しています。
この書籍は、ソクラテスからサルトルまでの2000年の哲学を基に、人生の問題解決に役立つ12の授業を提供します。著者は、哲学者の教えを現代に応用する方法を解説し、思考の革命や生き方の探求を促します。著者は白取春彦と冀剣制で、哲学的思考の重要性を若者に伝える活動を行っています。
現代社会の悩みを抱える人々が訪れる「哲学研究所」を舞台に、33人の哲学者が様々な問題に寄り添うマンガ形式の哲学入門書です。パワハラやSNSの承認欲求など、現代の課題に対する哲学的なヒントを提供し、読者が生きやすくなる手助けを目指します。著者は哲学者の平原卓とマンガ家の柚木原なりです。
本書は、フランスの高校生が必修とする哲学教育に焦点を当て、思考を深めるための「思考の型」を学ぶ実践的な哲学入門書です。著者は、哲学小論文の書き方を「知(概念・言葉の定義)」と「力(論述・表現)」の観点から解説し、具体的な問題を通じて考える力を養うことの重要性を説いています。バカロレア試験を通じ、異なる価値観を持つ人々が対話し共存するための哲学の意義も強調されています。著者は京都薬科大学の准教授で、フランス思想を専門としています。
指針なき現代にこそ響く最強の古典!資本主義の本質を見抜き、日本実業界の礎となった渋沢栄一が、生涯を通じて貫いた経営哲学とは。 1番読みやすい現代語訳! 60万部突破!! いまこそ全ての日本人必読! 最強の古典 2021年NHK大河ドラマ「青天を衝け」主人公! 新1万円札の顔に決定! 指針なき現代においてわたしたちは「どう働き」「どう生きる」べきか? 迷ったとき、いつでも立ち返りたい原点がここにある!! 各界のトップ経営者も推薦! 岩瀬大輔氏 「あなたの仕事観を変える本。東洋の叡智がここにある! 」 佐々木常夫氏 「資本主義に対する彼の思想は、時代や国境を越えている」 新浪剛史氏 「“道徳に基づいた経営"という発想には学ぶべきことが多い」 資本主義の本質を見抜き、日本実業界の礎となった渋沢栄一。 「論語」とは道徳、「算盤」とは利益を追求する経済活動のことを指します。 『論語と算盤』は渋沢栄一の「利潤と道徳を調和させる」という経営哲学のエッセンスが詰まった一冊です。 明治期に資本主義の本質を見抜き、約480社もの会社設立・運営に関わった彼の言葉は、ビジネスに限らず、未来を生きる知恵に満ちています。 第1章:処世と信条 第2章:立志と学問 第3章:常識と習慣 第4章:仁義と富貴 第5章:理想と迷信 第6章:人格と修養 第7章:算盤と権利 第8章:実業と士道 第9章:教育と情誼 第10章:成敗と運命 なぜいま『論語と算盤』か(本書「はじめに」より抜粋) ここで現代に視点を移して、昨今の日本を考えてみると、その「働き方」や「経営に対する考え方」は、グローバル化の影響もあって実に多様化している。「金で買えないモノはない」「利益至上主義」から「企業の社会的責任を重視せよ」「持続可能性」までさまざまな価値観が錯綜し、マスコミから経営者、一般社員からアルバイトまでその軋轢の中で右往左往せざるを得ない状況がある。そんななかで、われわれ日本人が、「渋沢栄一」という原点に帰ることは、今、大きな意味があると筆者は信じている。この百年間、日本は少なくとも実業という面において世界に恥じない実績を上げ続けてきた。その基盤となった思想を知ることが、先の見えない時代に確かな指針を与えてくれるはずだからだ。 第1章:処世と信条 第2章:立志と学問 第3章:常識と習慣 第4章:仁義と富貴 第5章:理想と迷信 第6章:人格と修養 第7章:算盤と権利 第8章:実業と士道 第9章:教育と情誼 第10章:成敗と運命 十の格言 渋沢栄一小伝 『論語と算盤』注 参考図書
多くの経営者がバイブルとして挙げることの多い「論語と算盤」。明治維新後多くの企業を立ち上げて日本国を強くしてきた渋沢栄一の経営哲学が学べる。論語と算盤、すなわち今で言うとアートとサイエンス。この2つの両輪なくして経営は成り立たないしインパクトのある仕事はできない。常に渋沢栄一の経営哲学を頭に入れて日々過ごしていきたい。
この本は、1000以上のフェルミ推定問題を解いた東京大学の学生たちが、その解法を体系化したものです。フェルミ推定の基本パターンと解法ステップを学ぶことで、効果的な思考トレーニングが可能になります。目次には、フェルミ推定の基本体系、コア問題、練習問題が含まれています。
吉野源三郎の名作「君たちはどう生きるか」が初のマンガ化され、80年経った今も多くの人々に支持されています。物語は、主人公コペル君と叔父さんが人間としての生き方を探求する姿を描き、いじめや貧困、格差などのテーマに真摯に向き合っています。このマンガ版は、原作のメッセージを保ちながら、読者に人生を見つめ直すきっかけを提供する一冊です。
著者ブライアン・R・リトルによる最新刊は、パーソナリティとウェルビーイングの関係を科学的に解明した内容で、ハーバード大学で人気教授に選ばれた実績があります。書籍では、自分の性格を理解し、人生を主体的に生きる方法や、性格が幸福や寿命に与える影響について探求しています。各章では、性格の変化やクリエイティビティ、生活の質に関するテーマが取り上げられています。
セネカの代表作3篇を収録した新訳本で、内容は以下の通りです。『生の短さについて』では、人生を浪費せずに活用する重要性を説き、『心の平静について』では心の安定を得る方法を探ります。『幸福な生について』では、快楽よりも徳が幸福の鍵であると主張しています。
この文章は、R・カーソンが化学薬品の乱用による自然破壊と人体への影響を告発した著作について紹介しています。彼女の警告は、初版から数十年経った今でも衝撃的であり、人類はこの問題の解決策を見出していないと述べています。また、作品は20世紀のベストセラーであり、新装版が待望されていることも触れています。目次には、自然や環境に関する多様なテーマが含まれています。
人気哲学作家・飲茶がニーチェの哲学を熱意をもって解説する入門書。著者の実体験を交え、ニーチェの思想(「神は死んだ」「奴隷道徳」「超人思想」など)をわかりやすく伝え、読む人の人生を幸福に変えることを目指している。目次では哲学の意義やニヒリズム、道徳、死の意味などが取り上げられ、哲学を学ぶことで生き方が変わる可能性を示唆している。
「どうして勉強しなければいけないの?」「どうしていじめはなくならないの?」「生きている意味はあるの?」 学校の… 「どうして勉強しなければいけないの?」 「どうしていじめはなくならないの?」 「生きている意味はあるの?」 学校の先生や親がなかなか答えられない、子どもが抱えるリアルな悩みや疑問を、哲学者の言葉をヒントに解決。 哲学を通して子どもの考える力を育てる、必読の一冊。 古代ギリシャから近代、現代の有名な哲学者の解説も。 ■第1章 自分について考える Q 運動が苦手 Q 勉強ができない Q 自分の言葉で上手く話せない Q 綺麗になりたい Q 自分のいいところがわからない Q 「自分らしさ」って何? ■第2章 友達について考える Q 友達ができない Q 友達が他の子と仲よくしているとムカムカしてしまう Q 友達グループの中で仲間外れにする子がいる Q ケンカをした友達に「ごめんなさい」が言えない Q 人を好きになるってどういうこと? ■第3章 悪について考える Q どうしてルールを守らなくちゃいけないの? Q 人にやさしくしなきゃいけないのはなぜ? Q どうしていじめはなくならないの? Q 悪いことをしている人には注意した方がいい? ■第4章 生き方について考える Q どうして勉強しなければいけないの? Q 苦手なことはあきらめちゃダメ? Q 「本をたくさん読みなさい」って言われたけどなぜ? Q 自分の夢を反対される Q 生きている意味はあるの? Q 幸せって何? ■第5章 命について考える Q 心はどこにあるの? Q 花や木に命はある? Q 死ぬのが怖い Q 人は死んだあとどうなるの? Q 人はどうして人を殺すの? ■岩村先生の哲学講座 人間の祖先「ホモ・サピエンス」が生き残れたわけ 物事の原因はすべて「目に見えない」 「ふたつの時間」を生きる 愛は「心を受ける」こと
この書籍は、現代の高度な医療において、生命に関する重要な決定権が誰にあるのかを探る内容です。著者は、様々な視点から「いのち」の判断についての対話を促し、終わり、始まり、質、優先順位などのテーマを扱っています。著者は小林亜津子で、生命倫理学の専門家です。
この文章は、デカルトの哲学書の内容を紹介しています。デカルトは「われ思う、ゆえにわれあり」という言葉で、外的権威を否定し、真理を求める思索を重ねました。この著作は近代精神の確立を示し、現代の学問の基盤となる新しい哲学の原理と方法を提供しています。
本書は、嫌いな自分を肯定し、自分らしさを理解するための新しい人間観を提供します。恋愛や職場、家族などの人間関係に悩む人々に向けて、自己と他者の距離の取り方を探求。内容は、自己の本質、分人の概念、他者との関係、愛と死、そして分断を超えることに焦点を当てています。著者は小説家の平野啓一郎で、芥川賞受賞歴があります。
本書『愛するということ』は、エーリッヒ・フロムによる愛の技術を探求する作品の改訳・新装版であり、愛は学べる技術であると説いています。著者は、現代人が愛よりも成功や権力にエネルギーを費やす中、愛が幸福な生活を送るための最も重要な技術であると強調しています。愛は能動的な行為であり、読者はその技術を習得することで、より充実した人生が得られるとされています。多くの著名人が本書の重要性を語り、愛の理解を深めることの価値を述べています。
『ソクラテスの弁明』は、古代ギリシアの哲学者ソクラテスの裁判をプラトンが記録した作品で、彼の生き方や思想を明らかにする名著です。幸福を追求するためには、何が「善」であるかを理解することが重要であり、これは知恵や真実を求める意味でもあります。新訳と解説を通じて、ソクラテスの言動や哲学的概念(アレテーなど)を探求し、人生や哲学の本質に迫ります。著者は岸見一郎で、哲学やアドラー心理学を専門とする学者です。
この書籍は、幸福を得るためには自己中心的な考えを捨て、外界に目を向けて好奇心を持つことが重要であると説いています。著者ラッセルは、人生を豊かに生きるための知恵を提供し、不幸の原因や幸福をもたらす要素について詳述しています。内容は、不幸の原因を分析した第1部と、幸福を得るための要素を探る第2部に分かれています。