【2025年】「大学院生」のおすすめ 本 119選!人気ランキング
- 創造的論文の書き方
- なぜあなたは論文が書けないのか?
- [改訂4版]グロービスMBAマーケティング
- Good Luck
- イシューからはじめよ[改訂版]――知的生産の「シンプルな本質」
- 社会科学の考え方―認識論、リサーチ・デザイン、手法―
- 最新版 論文の教室: レポートから卒論まで (NHKブックス 1272)
- 植木理恵のすぐに使える行動心理学
- マネジメント研究への招待
- 問題解決ができる! 武器としてのデータ活用術 高校生・大学生・ビジネスパーソンのためのサバイバルスキル
本書は、シリーズ累計150万部のビジネスパーソン向け定番テキストを改訂したもので、マーケティング理論の基礎から応用までを体系的に学べます。内容にはセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、コミュニケーション戦略、ブランド戦略、マーケティングリサーチ、顧客経験価値などが含まれ、新たに「顧客経験価値とカスタマージャーニー」の章が追加され、企業事例も刷新されています。
『イシューからはじめよ』の改訂版が発売され、累計58万部のロングセラーとしてビジネスパーソンや学生に支持されています。改訂版では「課題解決の2つの型」や「なぜ今この本が必要か」といった新しい内容が追加され、ページ数も増加しています。イシューとは、未解決の問題であり、価値のある仕事はこの設定から始まるとされています。本書は、空気や権威に頼らず、真に向き合うべき課題に取り組むことの重要性を訴えています。社会がイシュードリブンに移行するためには、個々の行動変容が必要だと強調しています。
学際化がすすむ社会諸学のロジックをいかにして身につけるか。日本で初めて認識論から説き起こし、多様な調査研究手法を明晰に整理して、メソドロジーの全体像を提示する。社会科学を実践するための要諦をつかみ、創造的研究を生み出すための最良のガイドブック。 はじめに 第I部 社会科学の認識論 第1章 認識論 1.1 存在論の2つの立場――基礎づけ主義と反基礎づけ主義 1.2 認識論のパラダイム――実証主義・批判的実在論・解釈主義 1.3 むすび 第II部 社会科学のリサーチ・デザイン 第2章 事例研究 2.1 事例研究とは――定義と特性 2.2 単一事例の選び方――3つの基準 2.3 複数事例の選び方――比較の論理 2.4 構成要素――問いと分析単位 2.5 一般化・理論的貢献・過程追跡――事例研究の論点 2.6 むすび Box2.1 歴史研究と事例研究 第3章 実験 3.1 実験とは――定義・要点・「無作為割り当て」 3.2 種類――実験室実験・フィールド実験と準実験 3.3 妥当性と問題点――実験における配慮事項 3.4 分析と方法論的位置づけ――アプローチと認識論 3.5 むすび Box3.1 自然実験 Box3.2 妥当性 Box3.3 ホーソン効果とピグマリオン効果 Box3.4 アクション・リサーチ 第4章 横断的・縦断的研究 4.1 横断的研究とは――定義・特性・方法論的位置づけ 4.2 縦断的研究とは――定義・類型・特性と方法論的位置づけ 4.3 標本抽出(サンプリング)——確率的/非確率的抽出とその論点 Box4.1 歴史研究と横断的/縦断的研究 Box4.2 非確率的抽出の限界 第III部 社会科学の手法 第5章 インタビュー 5.1 概要――類型(構造化・半構造化・非構造化)と認識論 5.2 個別インタビュー(1)基本的な考え方 5.3 個別インタビュー(2)オーラル&ライフ・ヒストリー 5.4 集団に対して行うインタビュー――フォーカス・グループ Box5.1 民俗学における半構造化・非構造化インタビュー 第6章 エスノグラフィー/参与観察 6.1 概要――定義・経緯・特性・認識論 6.2 手順/技法――アクセス・類型・書き方・再帰性・厚い記述 6.3 その他の注意点 Box6.1 歴史研究とエスノグラフィー 第7章 調査票調査 7.1 概要――要点・注意点・認識論 7.2 進め方――調査票の作成・調査の実施・データの処理 7.3 データの分析――集計表と解析 Box7.1 キャリー・オーバー効果 Box7.2 インターネットと調査 Box7.3 選挙の当確速報 第8章 言説分析 8.1 概要――定義と要点 8.2 類型と方法論的位置づけ――認識論とリサーチ・デザイン 8.3 批判的言説分析――フェアクラフを中心に 8.4 解釈主義系の言説分析――研究例を踏まえて 8.5 むすび Box8.1 歴史研究・縦断的研究と言説分析 第IV部 社会科学のルール 第9章 研究倫理と参照の方法 9.1 研究倫理 9.2 参照の方法――概要 9.3 ハーバード方式(括弧参照方式) 9.4 脚注方式 9.5 むすび Box9.1 修士論文を書く Box9.2 博士論文を書く(1) Box9.3 博士論文を書く(2) おわりに あとがき 索 引
この書籍は生化学の基礎から始まり、生体分子、酵素、代謝、遺伝子の発現と複製に関する内容を網羅しています。主要なトピックには、生命の化学、水の性質、ヌクレオチドやタンパク質の構造と機能、酵素の役割、代謝経路、DNAの複製や遺伝子発現の調節が含まれています。著者は生化学の専門家であり、教育と研究に長年従事しています。
村上春樹が自身の作家としての歩みや文学に対する思考を振り返る一冊。小説家としての寛容さ、オリジナリティ、長編小説の書き方、登場人物の選び方、海外への翻訳などについて具体的なエピソードを交えて語り、彼の生きる姿勢やアイデンティティが表現されています。作家としての成長や影響を受けた人物との出会いも紹介され、新たな視点を読者に提供する内容です。
この書籍は、仮説思考を用いることで作業効率を大幅に向上させる方法について解説しています。著者の内田和成は、BCGコンサルタントとしての経験を基に、仮説を立てることの重要性やその検証方法、思考力を高める方法を紹介しています。目次には、仮説思考の概念から始まり、実践的なステップが示されています。内田は東京大学卒で、経営戦略の専門家としての経歴を持っています。
1999年に発売され、シリーズ累計145万部を突破した経営戦略の教科書が全面改訂されました。本書では、経営戦略の基本概念から最新の分析・実行ツールまでを包括的に網羅しています。内容は、基本コンセプト、実務に役立つフレームワーク、経営戦略の応用に分かれており、事業創造やグローバル経営、競争優位についても触れています。
主要トピックの理論と測定尺度を概観。経営学は実践の役に立つかを問い,実践家とともに理解を深め合える共同研究を模索する。 2020年現在の組織行動論領域において,学術的に確立された理論と測定尺度を概観。実際の経営現象を測定・研究する際,実践家とともに理解を深め合える協働を求め,経営学にとってのレリバンスとは何かを真摯に問う。研究者,ビジネスパーソン必読の書。 第1部 組織行動論の立ち位置 第1章 組織行動研究の俯瞰 第2章 「知っている」ということについて 第3章 概念と理論 第4章 組織行動の測定 第2部 組織行動論は何をどう測るか 第5章 リーダーシップ 第6章 組織の中の公正 第7章 欲求とモティベーション 第8章 人的資本,社会関係資本,心理的資本 第9章 組織と個人の心理的契約 第10章 組織コミットメント,ジョブ・エンベデッドネス 第11章 組織行動の成果 第3部 組織行動論の充実のために 第12章 2つの知のサイクルが共振する共同研究 第13章 組織行動研究のレリバンスを求めて
この本は、日本一情報を発信する精神科医・樺沢紫苑が、脳科学に基づいた「アウトプット術」を紹介しています。読者が選ぶビジネス書グランプリ2025の特別賞を受賞し、シリーズ累計100万部を突破。内容は、伝え方、書き方、動き方に関する技術や方法論が含まれ、説明や雑談、プレゼンテーションなど多岐にわたるコミュニケーション能力を最大化することを目的としています。
アウトプットの重要性について語られて、具体的なアウトプット方法がたくさん学べる本。普通に過ごしているとどうしてもインプット過多になってしまうので、この本を読んでなるべくアウトプットする習慣を身につけていこう!
この文章は、心理学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、心理学の理論、感覚、記憶、言語、社会的認知、対人関係、発達、教育心理、感情、動機づけ、性格、臨床心理学などのトピックが含まれています。著者は、無藤隆、森敏昭、池上知子、福丸由佳の4名で、それぞれ異なる大学で教授を務めています。
この文章は、R・カーソンが化学薬品の乱用による自然破壊と人体への影響を告発した著作について紹介しています。彼女の警告は、初版から数十年経った今でも衝撃的であり、人類はこの問題の解決策を見出していないと述べています。また、作品は20世紀のベストセラーであり、新装版が待望されていることも触れています。目次には、自然や環境に関する多様なテーマが含まれています。
経営学学習・研究の基本テキスト。共通に身につけておきたい知識が盛り込まれている。卒論作成や大学院進学を目指す際に役立つ。 東京大学大学院での経営学の方法論基礎の教科書。第Ⅰ部で実証研究の基礎、第Ⅱ部で具体的に各研究プロセスからそのエッセンスや留意点を学ぶ。専門が違っても共通に身につけておきたい知識が盛り込まれている。学部での卒論作成の準備や大学院進学を目指す際に役立つ。 第1部 リサーチ・サイクルを回す:経営学研究法の基礎 第1章 実証研究の方法論:Field-Based Research Method(FBRM)=藤本隆宏 研究の技法 1 アプローチの方法:ケース研究 1 ケース研究の妥当性=桑嶋健一 2 ケース研究のプロセス=桑嶋健一 2 データを集める 3 一次データの収集=藤田英樹 4 二次データの収集と活用=近能善範 5 インターネットを通じたデータ収集=山本 晶 6 インタビューメモの作り方=加藤寛之 7 アンケート調査の設計・実施=具 承桓 8 工場調査法=松尾 隆 9 資料の収集と分析=粕谷 誠 3 データを分析する 10 分析手法の見つけ方=清水 剛 11 因子分析と共分散構造分析=藤田英樹 12 重回帰分析におけるモデル選択=椙山泰生 13 文献情報と内容分析=宮崎正也 第2部 リサーチ・マインドを育む:研究プロセスに学ぶ 第2章 ぬるま湯体質の研究ができるまで 継続的調査からとらえた現象=高橋伸夫 第
「MBAマネジメント・ブック1」は、シリーズ累計145万部を突破したビジネスパーソン向けの教科書で、経営分野の必須科目を網羅しています。続編では、アントレプレナーシップ、サービス、テクノロジー、グローバル経営、組織変革・事業再生、エコノミクスの6つの科目を収録し、現代のグローバル化や不確実性に対応する内容となっています。各分野は、ビジネスアイデアやマーケティング戦略、技術の事業化、グローバル戦略、企業の持続可能な経営、経済学の基礎などが含まれています。
現代の「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。人の頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解く。 永遠にかみ合わない議論、罵(ののし)り合う人と人。 その根底にあるのは「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。 動物にはない人間の知性を支える頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解きます。 具体的言説と抽象的言説のズレを新進気鋭の漫画家・一秒さんの四コマ漫画で表現しています。 序 章 抽象化なくして生きられない 第1章 数と言葉 人間の頭はどこがすごいのか 第2章 デフォルメ すぐれた物まねや似顔絵とは 第3章 精神世界と物理世界 言葉には二つずつ意味がある 第4章 法則とパターン認識 一を聞いて十を知る 第5章 関係性と構造 図解の目的は何か 第6章 往復運動 たとえ話の成否は何で決まるか 第7章 相対的 「おにぎり」は具体か抽象か 第8章 本質 議論がかみ合わないのはなぜか 第9章 自由度 「原作」を読むか「映画」で見るか 第10章 価値観 「上流」と「下流」は世界が違う 第11章 量と質 「分厚い資料」か「一枚の絵」か 第12章 二者択一と二項対立 そういうことを言ってるんじゃない? 第13章 ベクトル 哲学、理念、コンセプトの役割とは 第14章 アナロジー 「パクリ」と「アイデア」の違い 第15章 階層 かいつまんで話せるのはなぜか 第16章 バイアス 「本末転倒」が起こるメカニズム 第17章 理想と現実 実行に必要なのは何か 第18章 マジックミラー 「下」からは「上」は見えない 第19章 一方通行 一度手にしたら放せない 第20章 共通と相違 抽象化を妨げるものは何か 終 章 抽象化だけでは生きにくい
この本では、著者が自身の経験を基に「ブログで飯を食う」ための心構えや考え方を紹介しています。内容は、ブログ運営の実践的な方法や継続的な成果を出すための秘訣、個人での収入の仕組み、SNSの活用法、成功するための技術について触れています。著者は、非IT系出身のブロガーであり、現在はブログ運営やコンサルティングを通じて生計を立てています。
理系出身の記者が、理系学生の就職活動に関する悩みに答える本です。著者は業界誌記者としての経験を活かし、進路選びや企業研究、OB・OG訪問、履歴書や面接のポイントを解説しています。著者は日刊工業新聞社の論説委員であり、大学でも非常勤講師を務めています。
この書籍は、iPhoneやiPadなどの成功を収めたプレゼンテーションの極意を解説しています。著者カーマイン・ガロは、ストーリー作り、体験提供、仕上げと練習の三幕に分けて、効果的なプレゼンの技術を紹介します。著者はプレゼンテーションやコミュニケーションのコーチであり、さまざまなメディアで活躍しています。また、井口耕二と外村仁はそれぞれ翻訳者や経営コンサルタントとしての経歴を持つ専門家です。
この書籍は、心理学の発展に寄与した50の重要な実験を紹介し、人間心理の理解の歴史を探求しています。内容は、心理学の始まりから認知革命までの各時代を網羅しており、心の理解がどこまで進んだのかを考察しています。著者はアダム・ハート=デイヴィスで、科学書の編集やテレビ制作にも携わる経歴を持っています。翻訳は山崎正浩が担当しています。
この教科書は、生命科学と分子生物学の基本をストーリー性のある解説と美しい図版で学べる内容で、世界中で翻訳されています。改訂版では新しい知見が追加され、より深い理解が得られるようになっています。目次には細胞の基本単位、DNAの構造、遺伝子発現、細胞のシグナル伝達など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者は著名な研究者たちで構成されています。
この本は、宇宙の誕生から社会問題まで、子どもと大人が知りたい50の疑問に答える内容です。デンマークのSDGsに基づき、現代の世界を理解し、未来を見据える力を育むことを目的としています。親子での会話に役立つ情報が豊富に含まれており、科学や社会についての理解を深めることができます。著者はデンマークの科学ジャーナリストであり、翻訳者も参加しています。
この書籍は、思考の基本である「類推」に焦点を当て、戦略思考や仮説思考などの重要性を解説しています。著者は、アナロジーのメカニズムや抽象化思考力の必要性、さらに科学やビジネスでの応用例について述べています。著者の細谷功は、コンサルタントとして多様な業務改革や戦略策定に携わっています。
この文章は、シーナ・アイエンガーの著書についての目次と著者情報を紹介しています。目次では、選択に関する様々なテーマが取り上げられており、選択の本能や集団と個人の関係、選択の強制、影響要因、選択肢の豊富さ、代償、そして偶然や運命との関連が論じられています。著者のシーナ・アイエンガーはカナダ生まれで、全盲の社会心理学者としてコロンビア大学で教授を務めています。櫻井祐子は翻訳者としての経歴を持ち、経済学の学位を有しています。
この書籍は、時間を効率的に使う方法を提案し、1日4時間の自由な時間を生み出す方法を紹介しています。著者は「忙しい」と「やらなくていいこと」を見極め、時間をお金のように考えることや、発想を切り替えることで時間を増やす方法を解説。さらに、十分な休憩や睡眠を取ること、テクニックよりもルールを見直すことが重要だと述べています。著者は弁護士の谷原誠氏です。
本書は、行動理論やリーダーシップの各種理論、経験学習を含むリーダーシップ開発について網羅した内容で、理論を実践に移すためのコツを模擬授業形式で伝授しています。目次は理論編と実践編に分かれており、リーダーシップの変遷や組織行動、リーダーシップの磨き方と発揮方法を扱っています。
この本は、職場での平穏な日常を実現するための方法を紹介しています。成績や人気を追求するのではなく、「自分はここにいていい」と感じられる普通の生活を目指します。具体的には、仕事の先送り、ミス、集中力の欠如、整理整頓の苦手さ、コミュニケーションの悩みなど、様々な職場の悩みを抱える人々に役立つ内容が豊富なイラストと共に提供されています。著者は、実体験を基にした仕事術を共有し、ストレスの少ない働き方を実現しています。
社会科学を学ぶ人や一般的な統計ユーザーのための統計法テキスト。種々の分析法の基本的考え方や分析法が元々もつ問題点や分析された結果を解釈する際の留意点を重視して解説。一人で読んで十分に理解できる画期的な本。 統計の分析法の意味や考え方を感覚的に理解できるように, 図や表を多数使用しながら解説! 社会科学を学ぶ人たちや一般的な統計ユーザーのための「統計法」のテキスト。種々の分析法の基本的考え方やそれらの分析法がもともともっている問題点(いわば,統計の限界)および分析された結果を解釈する際の留意点を重視して解説した。ひとりで読んで十分に理解できる画期的な本。 まえがき 序章 統計について学ぶにあたって 1節 統計とは何か,そして,統計はなぜ必要か? 2節 変数とデータ 3節 Σの記号の意味 序章のまとめ 1章 1つひとつの変数についての分析1:図表を用いた度数分布のまとめ 1節 度数分布とは 2節 量的変数における度数分布の表し方 3節 質的変数における度数分布の表し方 2章 1つひとつの変数についての分析2:度数分布の特徴の数値要約 1節 量的変数に関するデータの数値要約 2節 質的変数に関するデータの数値要約 2章のまとめ 3章 2つの変数の関係についての分析1:量的変数どうしの場合 1節 相関図の作成 2節 相関係数による数値要約 3節 一方の変数の値によって分けた群間での他方の変数の代表値の比較 3章のまとめ 4章 2つの変数の関係についての分析2:質的変数どうしの場合 1節 クロス表の作成 2節 連関係数による数値要約 4章のまとめ 5章 変数の変換 1節 線形変換 2節 非線形変換 5章のまとめ 6章 統計的検定の基礎 1節 記述統計と推測統計 2節 無作為標本抽出 3節 推測統計の分類 4節 統計的検定の意義 5節 統計的検定の基本的考え方 6節 統計的検定に関する基本用語と統計的検定の一般的手続き 6章のまとめ 7章 適切な検定の選択 1節 基本用語 2節 適切な検定を選択する際の主な観点 7章のまとめ 8章 統計的検定の実際 1節 対応のない場合のt検定 2節 対応のある場合のt検定 3節 U検定 4節 対応のない1要因の分散分析 5節 2重クロス表についてのχ2検定 6節 ともに対応のない2要因の分散分析 7節 ピアソンの相関係数の有意性検定 8章のまとめ 9章 統計的検定の問題点・適用上の留意点 1節 問題点 2節 適用上の留意点 9章のまとめ 終章 統計に関する知識と日常の思考との関わり 引用文献 索引 別表 練習問題の解答
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
この書籍は、ポーターやブルー・オーシャン、破壊的イノベーションなどの主要な戦略理論を網羅し、混迷の時代における経営戦略の教科書として位置づけられています。内容は基本編と理論編に分かれており、経営戦略の基本や競争の経済性、伝統的な戦略理論、グローバル・ネットワーク時代の環境と戦略について解説しています。著者は相葉宏二氏で、豊富なコンサルティング経験と教育歴を持つ専門家です。
本書『エッセンシャル思考』は、無駄を排除し、本当に重要なことに集中する方法論を提案しています。著者グレッグ・マキューンは、重要な選択を見極め、瑣末な事柄を捨て、システム化することで、より少なく、しかしより良く生きることを目指します。この考え方は、単なるタイムマネジメントやライフハックを超えたものであり、現代において求められる生き方の変革を促しています。
普段の仕事や生活で自分の時間がなくて常に何かに追われている感覚があるのであれば是非読んで欲しい!本質的でないことは全て捨てて自分のやりたいことにフォーカスしよう!一度きりの人生、悩んでいる時間は無駄。社会人になりたてで四苦八苦している人がいたら是非読んで欲しい。
この本は、心理学の全体像を俯瞰できる入門書で、各分野を豊富なカラーイラストと写真を用いて解説しています。基礎から学べるステップアップ形式で構成されており、初学者に最適です。目次には心理学の歴史や学習、知覚、認知、社会、人格、臨床、発達、神経心理学などが含まれています。著者は心理学と工学的アプローチを融合させた研究を行う専門家です。
この書籍は、ビジネスに必要な論理的思考力を豊富な演習と事例を通じて学ぶことを目的としています。斬新な発想や機会の発見、効果的なコミュニケーション、集団意思決定、説得・交渉・コーチングのスキル向上を促し、成功をつかむための手助けをします。内容は論理の構造化や思考の基本姿勢、現状分析、因果関係、仮説検証などを含む構成になっています。
理解を促し楽しく学べる工夫が満載。基礎から応用まで心理学の世界の考え方・理論のエッセンスをコンパクトに解説。 誰もがもつ素朴な疑問から読み進められる構成で,WHITEBOARDやPOINTツール等,読んで・見て・考えながら学べる工夫が満載。基礎~応用まで広い心理学の世界を概観でき,それぞれの考え方・理論のエッセンスがつまったコンパクトな入門テキスト。 序 章 心は目に見えない─計量心理学 第1部 さまざまな心のとらえ方 第1章 目は心の一部である─知覚心理学 第2章 心は見えないが行動は見える ─学習心理学 第3章 ヒトの心の特徴 ─進化心理学 第4章 心は脳のどこにあるのか ─神経心理学 第5章 それぞれの人にそれぞれの心 ─個人差心理学 第2部 さまざまな心のメカニズム 第6章 心は機械で置き換えられるのか ─認知心理学 第7章 ヒトは白紙で生まれてくるのか ─発達心理学 第8章 感情はどのような役割を果たしているのか─感情心理学 第9章 いい人? 悪い人?─社会心理学 第3部 心の問題のとらえ方 第10章 なんだかいやな気持ち─ストレスと心の病気 第11章 発達の偏りと多様性─発達障害 第12章 心の問題へのアプローチ ─アセスメントと支援
この本は、アイデアを手に入れる方法についての究極の発想術を紹介しています。60分で読める内容でありながら、一生役立つ知識を提供します。目次には、経験や心の訓練、既存要素の組み合わせなど、アイデア創出に関するさまざまな考察が含まれています。
この書籍は、多様なメディアを活用し、文章を通じてビジネスを推進する方法を解説しています。具体的には、読者を引きつける文章の書き方や、説得力のある主張、印象に残る表現、目的に応じた構成やトーン、わかりやすいセンテンスの作成などを豊富な例を交えて紹介しています。著者の嶋田毅は、戦略系コンサルタントを経てグロービスで出版局長を務めており、ビジネス文章の重要性を強調しています。
この文章は、心理学に関する書籍の目次と著者情報を提供しています。目次では、心理学の基本的なテーマや概念(心理学の特徴、生物学的基礎、心理発達、感覚過程、知覚、意識、学習、記憶、言語、動機づけ、感情、知能、人格、ストレス、心理障害、治療、社会的影響など)が列挙されています。著者情報では、ノーレン・ホークセマ、フレデリックソン、ロフタス、ルッツ、内田一成の各専門家の経歴や研究分野が紹介されています。
この書籍は、エントリーシート(ES)の書き方を解説し、学生が書いた実例を多数収録しています。内容は、自己PRや志望動機の作成方法、業界別のよくある質問とその対策など多岐にわたり、特に難関企業やインターン選考に対応しています。著者はキャリアデザインの概念を導入した専門家で、就職活動における効果的な対策を提供しています。
この書籍は、相手の「しぐさ」を読み取ることで恋愛、友人関係、仕事、家族との関係を円滑にする方法を紹介しています。著者トルステン・ハーフェナーは、身体言語を通じて人の思考や感情を解釈する技術を持ち、さまざまな場面での「しぐさ」の読み取り方を具体的に解説しています。内容は、相手の気持ちを見抜く方法や、恋愛における「しぐさ」の暗号、職場や家族での人間関係の改善方法など多岐にわたります。翻訳は柴田さとみが担当しています。
この書籍では、ユニクロや京セラなどの成功事業の立ち上げに必要な要素を分析しています。具体的には、アイデアの発見からビジネスプランの作成、人材や組織の構築、資金調達、成長戦略の策定まで、事業を軌道に乗せるための方法を解説しています。著者は堀義人で、グロービス経営大学院の学長です。
本書は、経営環境の変化に対応して加筆・修正され、注目のビジネス・トピックスが増補されています。MBAコースで学ぶ経営理論とビジネス用語を体系的に網羅しており、内容は経営戦略、マーケティング、アカウンティング、ファイナンス、人・組織、IT、ゲーム理論・交渉術の7部構成です。
この書籍は、MBAシリーズの人気タイトルが14年ぶりに大幅改定されたもので、財務会計と管理会計の基礎知識を一冊で学べます。内容には収益認識会計基準や国際財務報告基準、ESG、税務会計などが含まれ、経営課題の理解を深めることができます。目次は財務会計と管理会計の2部構成です。
この書籍は、組織の目的を達成するための「人」と「組織」のマネジメントに焦点を当て、旧版『MBA人材マネジメント』を基に、個の活かし方や多様性、ワーク・ライフ・バランスといった新たな視点を取り入れている。内容は、組織設計や人材育成に関する章を含み、実践例も紹介されている。著者は慶應義塾大学の教授で、組織行動やイノベーションに関する研究を行っている。
本書は、現状を正しく認識し、意思決定の質とスピードを向上させるための方法を解説しています。思考や行動にメリハリをつけ、経営分析ツールを活用することを提案。目次は基礎編、指標編、ケーススタディの3部構成で、著者は東京大学修士課程修了の嶋田毅氏で、経営戦略や管理会計の講師も務めています。
この書籍は、企業の競争力を高めるための戦略とオペレーションの関係を探求しており、特に業務連鎖の視点から生産性を向上させる方法を提案しています。内容は、企業経営とオペレーションに関する基礎、オペレーションの5つのモジュール(CRMやSCMを含む)、およびオペレーション・エクセレンスへの取り組み方を紹介しています。著者は、戦略コンサルティングの専門家であり、実行支援を重視した結果を出すコンサルティングで評価されています。
この書籍は、変化の激しい時代において成果を上げ続けるミドルマネジャーの共通点と自己変革力について探求しています。グロービスの調査結果を基に、期待を超えるミドルマネジャーに必要なスキル、仕事への想い、周囲とのギャップを乗り越える力を解説。また、実際の成功事例を通じて、自己変革の方法や具体的な行動についても述べています。
この文章は、マーケティングとビジネス戦略に関する5つの章を要約しています。第1章では顧客視点の価値創造、第2章ではマーケティング戦略の練り上げ、第3章では潜在的ニーズの発掘、第4章ではIT時代のマーケティング手法、第5章では実行可能なビジネスモデルの構築について述べています。各章は、具体的な事例を通じてマーケティングの重要性と戦略を探求しています。
本書は、リーダーに必要な10のスキルを提示し、個人だけでなくチームとしての成果を重視する重要性を説いています。具体的なスキルには、環境理解、会計知識、組織文化の理解、目標設定、プランニング、段取り、伝達、セルフマネジメント、習慣づけ、メンバー育成が含まれ、これらを磨くことで、将来にわたって通用するリーダーシップを身につけることが目指されています。著者はグロービス経営大学院の専門家たちです。
この書籍は、正しいことを言っても人が動かない理由を探り、成果を出すための効果的なコミュニケーションや人脈づくりの方法を解説しています。具体的には、信頼の構築や根回しの重要性、プラン作成の手順、実行の継続方法、そして自己成長の必要性について述べています。著者は、ビジネスコンサルタントとしての経験を基に、実践的なアドバイスを提供しています。
この書籍は、仮説を活用することで生産性を向上させる方法を解説しています。内容は、仮説の定義、立て方、検証方法、進化させるプロセス、そしてリーダーシップにおける仮説検証の重要性について述べています。仮説を使うことで、スピードや説得力を高めることができるとしています。
この書籍は、ビジネスパーソンの成長を加速させるための基礎トレーニングとスキルチェックを提案しています。著者たちは、論理思考力やコミュニケーション力、情報収集力など、どこに行っても通用するスキルを10項目にわたって解説しています。著者陣はグロービス経営大学院の教授や研究者であり、各自が多様なバックグラウンドを持っています。
本書は、データ収集やグラフ作成、プレゼン資料の作成方法について、説得力を高める実践的なノウハウを紹介しています。目次は、数値分析の目的設定、データ加工の基本、解釈の重要性、分析結果の伝え方、マネジャーとしての数字の読み方に分かれており、各章で具体的な手法や注意点が解説されています。著者は慶應義塾大学出身で、グロービス経営大学院で教授を務めています。
この書籍は、個人が自らの環境の中でどのように生きるべきかを考察しており、グロービスの代表が生き方や働き方について語っています。内容は、人生の座標軸や個人、家庭、組織、日本人としての役割、さらにはアジア人・地球人としての視点を含む多様なテーマを扱っています。著者の堀義人は、グロービス経営大学院の学長であり、起業家支援や復興支援プロジェクトにも関与しています。
この書籍は、10年後に後悔しないためのキャリアマネジメントについての指南書です。内容は、キャリアの位置づけや自己満足度を分析し、自己実現に向けた戦略を立てる方法を解説しています。また、実際のキャリア事例を通じて学ぶことができます。著者は村尾佳子で、経営学の専門家として多くの講義やNPO活動にも関与しています。
本書は、2011年の東日本大震災後に自主的に復興支援を行った企業の事例を通じて、現場の力や経営のヒントを探る内容です。各章では、ヤマトホールディングスや富士フイルム、富士通、東邦銀行などの企業が地域支援や雇用維持に取り組む様子が紹介されており、現場主義や地域貢献の重要性が強調されています。著者は田久保善彦で、グロービス経営大学院の教授です。
この書籍は、タイム誌編集長リチャード・ステンゲルが、ネルソン・マンデラとの3年間の交流を通じて得た人生と勇気に関する洞察をまとめたものです。マンデラの人生論を2万語の日記から抽出し、多面的な視点や勇気、冷静さ、長期的視野など、彼の教えを具体的に示しています。著者は政治や文化に関する豊富な経験を持つ人物です。
この書籍は、論理的思考や説得力を高めるための基本的なルールやフレームワークの活用法を紹介しています。主な内容は、結論を明確にし、理由を考え、事実と意見を区別し、全体を見て漏れをなくすことです。また、思考を加速させる方法や、問題解決のステップも説明されています。著者はグロービスの教授で、ビジネス戦略や管理会計の専門家です。
著者はグロービス経営大学院の学長であり、本書では次世代のビジネスリーダーに必要な「能力」「人的ネットワーク」「志」の三要素を解説しています。ハーバードでの学びや起業経験を基に、具体的な学習法やネットワーク構築の方法、逆境に打ち勝つ志の育て方を紹介し、ビジネスパーソンに役立つ内容となっています。
著者堀義人の本は、ハーバード・ビジネス・スクールへの留学から始まり、グロービスの創業やビジネススクール、ベンチャー・キャピタル事業への挑戦を描いたケーススタディです。目次には、留学体験、使命の探求、グロービスの歴史、教育方針、MBAプログラムの創設などが含まれています。堀氏はグロービス経営大学院の学長であり、起業家育成に力を入れています。
本書は、ビジネスパーソンの人的ネットワーク構築をテーマに、800人以上の調査結果を基にした知見を提供します。ネットワーキングの重要性を理解し、5つのレベルを上げる方法を体系化しています。内容は、人的ネットワークの意味や価値、自分を知ること、具体的な行動方法、そして7人の実例を通じて学ぶネットワーク構築の方法に分かれています。著者は田久保善彦で、慶應義塾大学出身の経営学者です。
この本は、海外勤務における「4つの壁」(発展段階、ビジネス領域、組織の役割、文化の違い)を乗り越えるための実践的なフレームワークを提供します。著者は、異文化の理解よりも自己のバイアスを認識することが重要であると説き、自己理解やビジネススキル、リーダーシップの重要性を強調しています。海外駐在員にとっての新たな指南書として、自己成長の道標を示します。
本書は、エクセルをビジネスで効果的に活用する方法を解説しています。著者は、エクセルを単なる道具として捉え、知識よりもその活用法を重視しています。具体的には、定量分析を通じて経営判断に役立つ示唆を得る方法を紹介し、顧客理解、顧客セグメンテーション、因果関係の検証、投資判断、予算と実績のギャップ分析などのテーマを扱っています。また、基本的なエクセル操作法についても触れています。著者はグロービス経営大学院の准教授で、金融や経営戦略に関する豊富な経験を持っています。
本書は、成長を続ける人や組織の不変の方法論を解説しています。第1部では、創造と変革を導く「5つの原則」を紹介し、可能性の信念、人を巻き込む組織作り、戦略の構築と実行、変化への適応、リーダーの成長について述べています。第2部では、これらの技法を用いた実践例として、日本や地域、文化・スポーツの改善に向けた取り組みを紹介しています。
「大学院生」に関するよくある質問
Q. 「大学院生」の本を選ぶポイントは?
A. 「大学院生」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「大学院生」本は?
A. 当サイトのランキングでは『創造的論文の書き方』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで119冊の中から厳選しています。
Q. 「大学院生」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「大学院生」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



![『[改訂4版]グロービスMBAマーケティング』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41XMjaD44+L._SL500_.jpg)

![『イシューからはじめよ[改訂版]――知的生産の「シンプルな本質」』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41aKmV5fmyL._SL500_.jpg)

















![『[新版]グロービスMBA経営戦略』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41BPUX05CbL._SL500_.jpg)






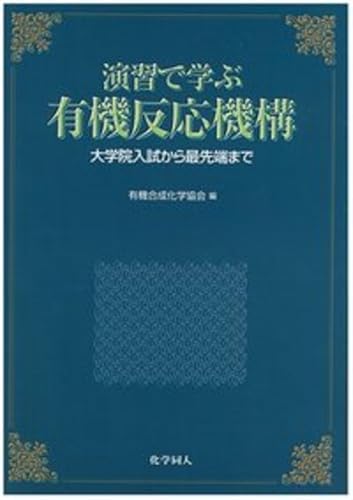




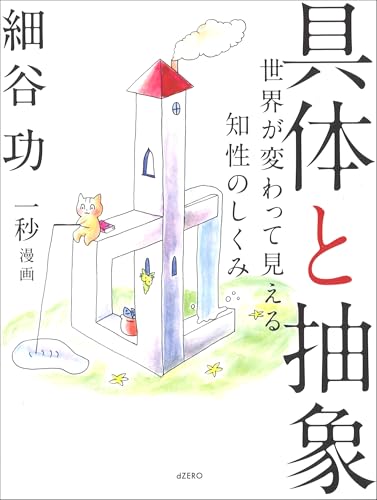







































![『[新版]グロービスMBAビジネスプラン』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41OdW6uijlL._SL500_.jpg)


![『[新版]グロービスMBAファイナンス』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41WvAJR-j4L._SL500_.jpg)

![『[改訂4版]グロービスMBAアカウンティング』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51eg3J+wmWL._SL500_.jpg)



















![『グロービスMBA集中講義 [実況]組織マネジメント教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41zGwQMaHFL._SL500_.jpg)

![『グロービスMBA集中講義 [実況]マーケティング教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZEha5QhZS._SL500_.jpg)
![『グロービスMBA集中講義 [実況]アカウンティング教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41oWjF865BL._SL500_.jpg)


![『グロービスMBA集中講義 [実況]経営戦略教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41+aVlZK03L._SL500_.jpg)
![『グロービスMBA集中講義 [実況]ロジカルシンキング教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51kjOsY1MmS._SL500_.jpg)

![『[実況]ファイナンス教室 (グロービスMBA集中講義)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41ito7cFLsL._SL500_.jpg)



![『[ポケットMBA]正しい意思決定のための「分析」の基礎技術 (PHPビジネス新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41-3qVfQZXL._SL500_.jpg)

















