【2025年】「金融政策」のおすすめ 本 157選!人気ランキング
- 21世紀の金融政策 大インフレからコロナ危機までの教訓
- 金融政策:理論と実践
- [新版]この1冊ですべてわかる 金融の基本
- 金融政策(第2版) (【ベーシック+】)
- 東大生が日本を100人の島に例えたら 面白いほど経済がわかった! (サンクチュアリ出版)
- 財政・金融政策の転換点-日本経済の再生プラン (中公新書 2784)
- 目からウロコが落ちる 奇跡の経済教室【基礎知識編】
- 世界の中央銀行/アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 [第2版]
- 経済評論家の父から息子への手紙
- お金の流れでわかる世界の歴史 富、経済、権力・・・・・・はこう「動いた」
インフレ、雇用、金融危機にどう対応すべきか。ノーベル経済学賞受賞の元FRB議長が歴史を通して展望する洞察に満ちた金融政策論。 中央銀行の使命を歴史から問い直すインフレ、雇用、金融危機――。経済の変化にどう対応すればよいのか。ノーベル経済学賞受賞の元FRB議長が歴史を通して未来を展望する。「本書では主に歴史のレンズを通して、今日(および明日の)連邦準備制度(Fed)を検証する。……それ以外の方法でFedの手段、戦略、コミュニケーションが現在の形に進化した経緯を完全に理解することはできないと考える」。(「序章」より)「日本銀行(日銀)は、他の主要中央銀行にかなり先駆けて、慢性的な低インフレと低金利という問題に直面した点で特筆すべき存在である。そして多くの場合、こうした問題に対する新たな政策立案においても先駆者であった。足元での(日本を除く)世界的なインフレの高騰はいずれ収束するだろうが、その暁には低インフレと低金利という課題が世界的に再浮上するだろう。その場合、日本の金融戦略が、再び世界の重要なモデルになる可能性がある」。(「日本語版への序文」より)■現代の経済をコントロールする最強の権能をもつ中央銀行。その目指すべき姿を探るには歴史の扉を叩くことが不可欠である。■なぜ1970年代、大インフレが生じたのか? ボルカーのインフレとの戦いを支えたアイデアとは? グリーンスパンをどう評価すべきか? バーナンキ時代の危機対応の真相は? イエレン議長の果たした重要な役割とは? パウエルの独自性とは?■大インフレ、バブル、世界金融危機、低インフレ・低金利、そして、ゼロ金利の解除、金融不安定化、インフレへの対応、中央銀行としての独立性の確保――。連邦準備制度(Fed)は雇用の最大化、物価の安定を二大責務としつつ、いかにして経済・金融の変化に対処し、現在の姿にたどり着いたのか? そして、これから先に何が待ち受けているのか?■連邦準備理事会(FRB)議長を務め、ノーベル経済学賞を受賞したベン・バーナンキが、自らの議長時代を含む過去70年間のFedの政策立案の歴史を解き明かす。あわせて経済環境が劇的に変化するなかで、21世紀におけるFedの金融政策の手段、枠組み、コミュニケーション戦略の劇的な変化、そして新たな課題を示す。■また、量的緩和、フォワード・ガイダンスなど、世界の中央銀行の中でイノベーティブな政策を次々と先駆的に打ち出した日本銀行の政策についての評価も行う。 日本語版への序文 序 章 第1部 20世紀の金融政策:インフレの上昇と低下 第1章 大インフレ 第2章 バーンズとボルカー 第3章 グリーンスパンと1990年代のブーム 第2部 21世紀の金融政策:世界金融危機と大不況 第4章 新しい世紀、新しい課題 第5章 世界金融危機 第6章 新たな金融政策の枠組み:QE1からQE2へ 第7章 金融政策の進化:QE3とテーパー・タントラム 第3部 21世紀の金融政策:解除から新型コロナパンデミックへ 第8章 解 除 第9章 パウエルとトランプ 第10章 パンデミック 第4部 21世紀の金融政策:待ち受けているもの 第11章 2008年以降のFedの政策手段:量的緩和とフォワード・ガイダンス 第12章 Fedの政策手段は十分か 第13章 政策の実効性を高める:新たな手段と枠組み 第14章 金融政策と金融の安定性 第15章 Fedの独立性と社会における役割 コメント歓迎 謝 辞 情報源について 原 注 参考文献 索引
実践力を養う。長年の中央銀行エコノミストとしての経験を基に、理論と実務の双方の視点からバランスのとれた金融政策論を講義。 金融政策分析の実践力を養う。金融理論に精通している(日銀金融研究所の所長を務めた)、中央銀行での政策現場経験がある、日銀支店長としての実務経験がある、の三拍子揃った強みを持つ著者による臨場感溢れるテキスト。 金融政策分析の実践力を養う 長年の中央銀行エコノミストとしての経験を基に、理論と実務の双方の視点からバランスのとれた金融政策論を講義。 通貨の信認の重要性、制度的要素の重視、新しい理論的手法の提示、非伝統的金融政策をめぐる扱いの四本を柱に、金融の役割や金融政策の目的、金融市場調節など基本項目を網羅しつつ、非伝統的金融政策やマクロプルーデンス政策など最新必須のトピックまでを余さず丁寧に解説する、著者の持ち味と独自性溢れるテキスト! 金融理論に精通している(日銀金融研究所の所長を務めた)、中央銀行での政策現場経験がある、日銀支店長としての実務経験がある、の三拍子揃った強みを持つ著者による臨場感溢れるテキスト。 金融政策の実務と理論の双方をバランスよく記述し、中央銀行が政策金利をコントロールするという、現実とより整合的なIS-MPモデルを用いるなどのオリジナリティも持つ。歴史観を伴った記述や金融政策をめぐる最新の展開も補記する。コラムも充実。 第1章 金融政策:概観 金融政策とは何か/金融政策分析の枠組み/金融政策分析の視点/金融政策分析の留意事項 第2章 金融の役割 「金融」とは/金融システム/金融政策をめぐる理論的基礎 第3章 貨幣と中央銀行 お金と中央銀行/貨幣の機能/貨幣経済/銀行券の発行/金融システムと通貨供給/中央銀行と通貨の信認/マクロ経済学の教科書の中での通貨発行益/為替レート制度の選択 第4章 金融政策の目標 インフレとデフレ/物価変動のコスト/インフレのコスト/デフレのコスト/物価安定の基本的な考え方 第5章 金融政策を運営する制度的枠組み 金融政策の失敗からの教訓/中央銀行の独立性/委員会制度/中央銀行のコミュニケーション/日銀の金融政策決定会合の運営/中央銀行の最適契約理論 第6章 金融政策と金利の期間構造 金融政策と金利の期間構造/債券価格と金利/金利の期待仮説とイールドカーブ/イールドカーブの変動メカニズム/イールドカーブに関するネルソン=シーゲルモデル/為替レートの決定理論/株価の決定理論 第7章 政策ルールとインフレ目標政策 政策金利の指針/ルールと裁量/テイラールールの基本形/テイラー原理/テイラールールの実践的な解釈/柔軟なインフレ目標政策 第8章 金融市場調節 金融市場調節とは/コール市場と金融市場調節/資金過不足の要因/金融市場調節/政策金利の安定化メカニズム/外国為替市場介入と金融市場調節 第9章 金融政策分析の基本モデル 総需要と潜在産出量/IS曲線/金融政策(MP)曲線/IS-MP分析/インフレ予想修正付きフィリップス曲線/テイラー原理の解釈/基本モデルの使い方 第10章 総需要=総供給分析への拡張 総需要曲線と総供給曲線/総需要=総供給分析/総需要=総供給ショックと政策対応/インフレ予想制御の重要性 第11章 非伝統的金融政策 非伝統的金融政策:概観/非伝統的金融政策の類型化/非伝統的金融政策の手段(1)金利政策の拡張/非伝統的金融政策の手段(2)量的緩和政策/非伝統的金融政策の効果:総需要=総供給分析の拡張 第12章 マクロプルーデンス政策 金融危機とシステミックリスク/マクロプルーデンス政策/中央銀行の政策運営への含意 第13章 金融政策の将来展望 二つの境界線の消滅/低体温症経済/政府債務の拡張と金融政策/当面の政策運営の枠組みを考えるうえでの課題/中央銀行の新たな課題
この書籍は、金融業界を目指す人や金融の基礎を学びたい人に向けて、金融の歴史と仕組みを解説しています。内容は、金融の重要性、コーポレート・ファイナンス、株式市場、債券市場、金利、外国為替市場、投資の基本、新しい金融の流れについての章で構成されています。著者は田渕直也で、金融業界での豊富な経験を持つ専門家です。
この本は、「日本がもしも100人の島だったら?」という視点から、経済の基本的な仕組みをわかりやすく解説しています。金利、国債、為替、インフレなどの難解な概念を簡潔に理解できるようにし、読者が自分の意見を持てるようになることを目指しています。目次には、経済の基礎から国家の役割、景気や物価、貿易と為替、そして未来の課題まで多岐にわたるトピックが含まれています。著者は経済評論家や学者で、一般向けに最新の経済学を解説することに定評があります。
この本は、経済学の常識を根本的に見直す内容で、日本経済の成長停滞やデフレの原因、経済政策の誤解を解説しています。第1部では、日本経済の現状やお金、税金、財政再建のシナリオについて詳述し、第2部では経済学者の誤りやその理論の限界を指摘しています。著者は、経済学がもはや宗教のようになっていると批判し、平成の過ちを繰り返さないための理解を促しています。
経済評論家・山崎元が著した本は、お金の稼ぎ方や増やし方についての実践的なアドバイスを提供し、資本主義経済の仕組みを理解することで有利に働く方法を示しています。著者は、世間の流れに流されず、自分の価値を見極めることの重要性を強調し、幸せな人生を送るための戦略や哲学を展開しています。本書は、人生の幸福を追求するための希望を与える内容となっています。また、著者の手紙も収録されています。
この書籍は、歴史を「お金の流れ」に焦点を当てて分析し、5000年の経済と権力の動きを追跡しています。著者は元国税調査官の大村大次郎で、歴史的な出来事や文明の興亡を脱税や金融破綻などの経済的要因から解説しています。各章では古代エジプトやローマ、ナポレオンの敗北、明治日本の成長など、さまざまな時代の事例を取り上げ、経済が歴史に与える影響を探ります。
著者は日銀審議委員として経済危機に対処し、量的緩和解除やデフレ克服の効果を検証した本書で、「時間軸政策」を中心に金融政策の影響を分析。各章ではマクロ経済や金融情勢、歴史的な金融政策、時間軸政策の導入とその効果について詳述しており、日銀の出口政策を理解するための重要な資料となっている。著者は経済学の専門家であり、豊富な経歴を持つ。
政策運営に暗雲が漂い始めているなか、日銀きっての論客と言われた筆者が日銀を退職後、ついに沈黙を破って持論を開陳する注目の書! 黒田日銀総裁の「異次元緩和」政策は、「マイナス金利」という奥の手を導入した。この先の政策運営に暗雲が漂い始めているなか、日銀きっての論客と言われた筆者が、日銀を退職後、ついに沈黙を破って持論を開陳する注目の書! 第57回(2016年度)エコノミスト賞を受賞しました。 ▼緩和一辺倒の政策手段から、いかに脱却するか 黒田東彦日銀総裁が遂行する「異次元緩和」政策は、目標に掲げたインフレ率2%の達成・維持と経済停滞からの脱却に至らないまま、「マイナス金利」という奥の手を導入した。この先の政策運営に暗雲が漂い始めているなか、日銀きっての論客と言われた筆者が、日銀を退職後、ついに沈黙を破って持論を開陳する注目の書! 日銀は何ができて、何ができないのか ―― 序 章 QQEの実験から見えてきたもの QQEは「短期決戦」だった / 長期戦の戦局は悪化していった / マ イナス金利導入:起死回生策も不発 / QQEが明らかにしたこと、 隠していること / 柔軟で透明な政策運営を 第1章 非伝統的金融政策:私論 1 「普遍化」する非伝統的金融政策 「全く次元のちがう金融緩和」の衝撃 / 非伝統的金融政策の分類 / 非伝統的金融緩和の歴史:日銀、FRB、ECBのイノベーション / リ ーマン・ショックとFRB / 欧州中央銀行(ECB)の苦悩 / マイナ ス金利というイノベーション / 「非伝統的金融政策=量的緩和」で はない 2 QQEの実験的性格 QQEの効果を理論的に考える / マネタリーベースの増量 / 信用緩 和 / 長期金利の押し下げ / 現実の金融市場はちがう? / 意味深 長なバーナンキ発言 3 非伝統的金融政策の倫理的側面 嘘をつくことは許されるか / 国民負担の問題 【コラム】 日銀の作戦:なぜQQEは「バズーカ」になったのか 第2章 QQEの成果と誤算 1 QQEがもたらした成果 (1)大幅な円安と株高 野党党首だったから許された円安誘導発言 / 反転上昇の兆しが あった株価 (2)デフレ脱却の実現 「デフレ脱却」未達感の理由 / デフレ脱却の条件はクリアできた か 2 QQE(アベノミクス)の誤算 (1)「2年で2%」の未達成 「インフレ目標2%」は妥当な水準 / 三つの留意点 (2)経済成長率の低迷 「長期低迷の主因はデフレ」とは限らない / 最大のサプライズは 輸出の伸び悩み / 公共投資と駆け込み需要による攪乱 (3)人手不足時代の到来 うれしい誤算 / 賃金上昇の実態 / 労働集約型産業で人手不足が 深刻化 3 QQEが明らかにした課題:潜在成長率の低下 上がらない生産性 / エレクトロニクス産業の不振が生産性押し下げ 要因か / 需給ギャップの推計をめぐって / 資本ストックの不稼働 問題 / デフレ脱却は潜在成長率低下のおかげ? 4 ハロウィン緩和の「誤射」 不可解な緩和決定 / 「誤射」の結末:トリクル・ダウン戦略の破 綻 / ハロウィン・バズーカはミッドウェー海戦だったのか 【コラム】 人口動態、過剰貯蓄とデフレ:「長期停滞論」再考 第3章 「リフレ派」の錯誤 1 「リフレ派」的思考法:主観主義・楽観主義・決断主義 「リフレ派」を定義する / 「リフレ派」の主張は整合的か / リフ レ派の困った議論①:後出しジャンケン / リフレ派の困った議論 ②:精神論 2 期待一本槍の政策論:主観主義の錯誤 リフレ派の大本はマネタリズム / 自然利子率の概念 / テイラー・ ルール / マネタリーベースを金融調節の軸に据えるのは的外れ / 資産価格への影響を考える 3 さまざまな「期待」:市場と企業・消費者の温度差 円安・株高のはじまりは外国人投資家 / 金融市場と実物経済の非対 称性 4 成長余力の過大評価:楽観主義の錯誤 「日本経済は強い」という主張の根拠はどこにある? / リフレ派の 空想的楽観論 5 「出口」なき大胆な金融緩和:決断主義の錯誤 「出口」をいつまでも意識しないでよいのか / 日本に潜む「出口」 までの困難 / ジリ貧かドカ貧か 【コラム】 マクロ政策で潜在成長率の引き上げは可能か 第4章 デフレ・マインドとの闘い 1 「デフレ・マインド」とは何か 企業や家計の消極的な行動様式 / 賃上げに及び腰の労働組合 / 「学習された悲観主義」という日本病 / 三度の金融危機が慎重化を 促進 2 「日本的雇用」とデフレ・マインド いまだ「世紀末の悪夢」から抜け出せず / メンバーシップ型雇用の 呪縛 / イノベーションの波に乗り遅れる日本企業 3 物価の「アンカー」 「錨」(アンカー)としての社会の基底に根づくもの / 安倍政権の 逆所得政策 4 マネタリーベースの誤解 マネタリーベースの意味が大きく変わった / 通貨発行益を考える / ヘリコプター・マネー? 5 QQEの行き詰まり 市場も怪しい雲行きに気づき始めた / 国債大量買入れの限界 6 短期決戦から持久戦へ:マイナス金利の導入 金利政策への回帰 / 政策の枠組み変更の意義 7 マイナス金利政策の功罪 マイナス金利政策の効果と副作用 / マイナス幅拡大の制約 / マイ ナス金利付きQQEの問題点 【コラム】 キャリー・トレードとしての量的緩和 第5章 「出口」をどう探るか 1 「出口」の必須条件:財政の維持可能性への市場の信認 出口で何が起こるのか / 長期金利上昇と金融システムの安定性 / 欧州債務危機の教訓 / 「出口」の成否を決めるもの 2 「成長頼み」の財政再建計画 あまりに遠い財政健全化 / 債務残高・名目GDP比率について / 税 収弾性値をめぐる議論 3 経済成長優先の幻想 潜在成長率の低下がネックとなる / 消費増税の影響評価 4 財政健全化の柱は社会保障改革 消費税率アップだけでは財政健全化は達成できない / 社会保障改革 の本丸は医療・介護分野 / 成長戦略の役割 5 QQEは市場を殺す政策 国債を国内貯蓄だけで吸収できなくなる日が近づいている / 市場か らの警告が聞こえない / マイナス金利政策への純化を 6 市場とのコミュニケーションの再建を 日銀の発信情報はもう信じられない / ピーターパンの誤解:「王様 は裸だ!」 【コラム】 金融抑圧は可能なのか あとがき 参考文献
本書は、経済を「たった1つの図」で説明し、経済の基本をシンプルに理解できるようにすることを目的としています。著者の高橋洋一氏は、ミクロ経済学やマクロ経済学、金融政策、財政政策について具体例を交えて解説し、読者が自分の頭で考えられるようになることを目指しています。特に最新の経済情報にも触れ、経済ニュースを理解する力を養う内容です。
半世紀近い日本の経済・金融環境を概観し、金融システムの機能と効果を丹念に解説。現代金融システムを総合的に捉えた決定版。 経済学の道具立てを総動員し、 過去半世紀の軌跡を検証! バブルとその崩壊から不良債権問題、世界金融危機など、アップダウンを繰り返しつつ、30年にわたる長期停滞からの脱出を模索してきたわが国の金融システム。 その半世紀を顧みることで、システムの何が機能し、何が足りなかったのかを明らかにする渾身の一書! ・1990年代以降、長期停滞に陥った日本経済。なかなかその不況感から脱出できなかった金融政策の背景には何があったのか。 ・バブル期(1980年代) から近年のマイナス金利解除までの半世紀近い日本の経済・金融環境を概観し、金融システムの機能と効果を丹念に解説する、わが国現代金融システムを総合的に捉えた決定版。 ・①資産価格バブル期(1980年代後半~90年代前半)、②バブル崩壊後の不良債権処理問題期(90年代後半~2000年代)、③「失われた30年」と長期停滞(1990年代~2020年代にかけて)、と、この半世紀近くの流れを区分ごとに丁寧かつ実証的に分析。 ・理論と実証の両面を兼ね備えつつ、解説書レベルの平易な解説を行う渾身の力作。 第1章 金融システムをどのように評価すべきか これまでの金融システム評価の問題/望ましい金融システム評価の方法/本書のアプローチ 第2章 金融システム評価のための道具立て(理論的枠組み) 日本の金融システムのパフォーマンスをどう評価するか/「金融」とは何か/金融「システム」とは何か:定義と目的/金融システムはどのような要素から成り立っているのか:構成要素/金融システムはどのような基準で評価すべきか:評価基準/金融システムはどのようなはたらきをするのか:機能/金融システムはどのような問題を起こすのか:問題/サブシステムとしての公的介入のシステム/本書における金融システム評価 第3章 経済環境と金融制度の変遷 マクロ経済指標の動きから見た日本経済の変化/金融制度の変化 第4章 金融構造とその変遷 金融資産の蓄積はどのように変化したか/資金循環構造はどのように変化したか/小括:日本の金融構造の評価 第5章 資産価格バブルの形成と崩壊(1980年代後半~1990年代初め) バブルと信用膨張の実態/バブルと信用膨張の相乗効果はみられたのか/金融自由化はバブルの遠因か/金融政策はバブルの遠因か/小括:資産価格バブルの形成と崩壊に関する金融システムの評価 第6章 不良債権問題と金融危機(1990年代~2000年代初め) 不良債権問題と金融危機の実態/不良債権問題・金融危機はなぜ発生したのか/世界金融危機から得られる示唆/小括:不良債権問題と金融危機に関する金融システムの評価 第7章 失われた30年と金融システム①――貸し渋りと追い貸し(1990年代~2010年代) 経済停滞の要因と金融システム/貸し渋り・貸しはがしが経済停滞を招いたのか/追い貸しとゾンビ企業は経済停滞を招いたのか 第8章 失われた30年と金融システム②――金融政策(1990年代~2010年代) 評価の難しさと本章の評価の視点/「失われた30年」における金融政策の変遷/非伝統的金融政策の理論的整理と期待される波及経路(理論的可能性)/金融政策は経済停滞を招いたのか/金融政策と経済停滞に関する検討結果と考察/小括:「失われた30年」に関する金融システムの評価 第9章 現代日本金融システムの評価と展望――これまでの金融システムとこれからの金融システム 各時代の日本の金融システムの評価/日本の金融構造をどう評価するか――「貯蓄から投資へ」の検討/四つの「貯蓄から投資へ」仮説/四つの仮説の妥当性を検討する/金融システム・制度評価と設計への示唆
この本は、行動経済学の視点から人間の不合理な行動を探求し、予測することでダイエット成功や新商品開発に役立つ可能性を示しています。著者ダン・アリエリーは行動経済学の専門家で、さまざまな実験を通じて人間の行動の背後にある心理を解明しています。文庫版は、彼のベストセラー作品であり、相対性や社会規範、価格の影響など多岐にわたるテーマを扱っています。翻訳は熊谷淳子が担当しています。
著者の翁邦雄が、日銀の金融政策を検証し、金利と経済成長の関係を探る内容の書籍。金利の基本概念から始まり、バブルやデフレ、マイナス金利政策、イールドカーブ・コントロール、財政政策の重要性などを論じている。翁は金融論の専門家で、数多くの著書を持つ。
元ギリシャ財務大臣ヤニス・バルファキスが、十代の娘の質問をきっかけに経済の仕組みを解説する本。彼は「格差」の歴史を1万年以上遡り、農業の発明から産業革命、仮想通貨、AI革命までを多様な視点で論じる。シンプルで響く言葉で経済と文明の本質を探求し、世界的に評価されている。著者は経済学教授であり、民主的ヨーロッパ運動の共同設立者でもある。
この書籍は、経済学の基本的な視点を養うために、戦後の日本経済の成長やバブル、アベノミクスに至るまでの歴史を解説し、ミクロ・マクロ経済学の理論やNPO、環境問題などの現代的課題にも触れています。著者は慶應義塾大学の教授で、経済学の専門家としての経歴を持っています。
複雑でわかりにくい金融の本質を,初学者にも理解できるように,図表や事例を用いて明快に解説した好評テキストの最新版。 複雑でわかりにくい金融の本質を,初学者にも理解できるように,図表や事例を用いて明快に解説した好評テキストの最新版。物価高,フィンテック,ソーシャル・ファイナンスなどの新しいトピックスを追加。初学者から専門家まで学習と実務の両面で役立つ一冊。 第Ⅰ部 貨幣と金融取引 第1章 貨幣と決済 第2章 金融とそのメリット 第3章 取引費用とリスク 第4章 情報の非対称性と返済のリスク 第Ⅱ部 取引費用に対処する金融の仕組み 第5章 金融の仕組み⑴:流動化,証券設計,情報生産 第6章 金融の仕組み⑵:担保,保証 第7章 金融の仕組み⑶:分散化 第Ⅲ部 金融機関と金融市場 第8章 金融機関⑴:金融仲介機関 第9章 金融市場 第10章 金融機関⑵:金融仲介機関以外の金融機関 第Ⅳ部 金融のマクロ的側面 第11章 資金循環と金融システム 第12章 金融政策と経済の実物面・金融面 第13章 金融システムの問題と金融危機 第14章 金融制度と公的介入・プルーデンス政策 終章 これからの金融:ソーシャル・ファイナンス
この文章は、著書の目次と著者情報を紹介しています。目次は4つの部から成り、ネクスト・ソサエティ、IT社会の未来、ビジネス・チャンス、社会と経済の関係について論じています。著者のピーター・F・ドラッカーは影響力のあるビジネス思想家で、マネジメント理論の発展に寄与しました。上田惇生は経済学の専門家で、教育と経済広報に関与しています。
本書は、日本経済の平成から令和への変遷を解説し、コロナ危機や脱炭素革命、デジタル化などの現代の課題に焦点を当てています。著者は長年の経験を持つベテラン記者で、難しい理論を使わずにわかりやすく説明しています。経済に興味がない人でも理解できる内容で、学生やビジネスパーソンにおすすめです。目次には、平成の30年、デジタル革命、人口問題、金融政策、国際経済などが含まれています。
本書は、1945年の敗戦後、日本で一人の男、国岡鐡造が石油会社「国岡商店」を立ち上げ、困難を乗り越え再起を図る物語です。彼は全てを失いながらも、従業員を守りつつ、石油を武器に新たな戦いに挑む姿を描いています。著者は百田尚樹で、作品は経済歴史小説として感動的な内容が特徴です。
本書は、マクロ経済学の基本を身近に感じられるよう解説した入門書です。著者の塩路悦朗氏は、具体的な事例やニュースを交えて、GDPや財政政策、金融政策などの経済の仕組みをわかりやすく説明します。学生や公務員を含む幅広い読者を対象に、マクロ経済学が日常生活や仕事にどのように関連しているかを理解できる内容となっています。短時間で基礎知識を学ぶことができる構成です。
著者が経済学の重要性を感じ、経済学を学ぶ必要性を伝えるために本書を執筆しました。テレビや新聞で経済に関する情報が常に流れている中、真の教養を得るためには経済学の思考枠組みを理解することが重要です。著者は東京大学での20年以上の教育経験を基に、ミクロ経済学とマクロ経済学のエッセンスを20項目にまとめ、1日30分で学べる内容にしています。主要なトピックには消費者行動、企業行動、市場機能、財政・金融政策、経済成長などが含まれています。
この書籍は、金融の歴史を通じて人間の欲望や知恵を探求するもので、シュメール人の文字の発明から始まり、ルネサンス期の銀行業や大航海時代、国家間の戦争が株式や債券の基礎を築いたことを解説しています。現代の国際市場では依然としてデフレ、インフレ、バブルが繰り返される様子を通史として俯瞰しています。著者は経済学の専門家で、証券業界での豊富な経験を持つ板谷敏彦です。
大阪西支店の融資課長・半沢は、支店長の命令で無理に融資を承認した会社が倒産し、責任を押し付けられそうになる。四面楚歌の状況で債権回収に追われる半沢は、辛い中間管理職の現実を描いた痛快なエンターテインメント小説。著者は池井戸潤。
「池井戸潤」の半沢直樹シリーズ。大ヒットしたドラマの原作であり本も非常に面白い。物語としても面白いながら、普通に銀行ビジネスや大組織での立ち回りなど勉強になる部分も多い。
本書はマクロ経済学の基本を解説し、GDPや経済政策の影響についての疑問に答えます。経済の動きを理解することが求められる人々や、短期間で基礎知識を習得したい学生に向けた内容です。著者は中谷巌で、経済学の専門家です。
本書は、現代経済学の多様な学派を網羅し、経済学の本質とその学び方を提案する内容です。日本の大学での経済学教育に対する批判を受け、主流派と異端派の理論を理解することで、経済学の意義を再評価しようとしています。著者は経済ジャーナリズムとアカデミズムを行き来する専門家であり、経済学の全体像を描き出しています。目次には、経済学者の類型、ミクロ・マクロ経済学、異端派経済学、現代の新潮流などが含まれています。
住宅ローン金利はどうなるか。なぜ低金利が円安を招くのか。株価暴落はどのように起きるのか。金融政策の第一人者が解き明かす。 住宅ローン金利はどうなるか。なぜ低金利が円安を招くのか。株価暴落はなぜ、どのように起きるのか。金融政策の第一人者が根本から解き明かす。 住宅ローンや消費者金融、銀行預金に個人向け国債。私たちの身の回りには「金利」があふれている。「低金利だから円安になる」「金利を上げると不景気になる」といったニュースも、毎日のように聞こえてくる。これらの「金利」は。お互いにどんな関係があって、それぞれの金利はなぜ/どうやって決まるのか。金利が動くと私たちの生活に何が起きるのか。金融政策の第一人者が、身近な事例をもとに根本から解き明かす。お金と社会を見る目が変わる、実践的経済学の書。 2024年8月に起きた史上最大の株価下落と金利の関係をひもとく「金利引き上げと株価暴落」を収録。 第一章 金利を上げ下げする力はどこから来るのか 1 プロローグ 2 「金利」とは何か・どう決まるのか 3 いろいろな金利はどう関連しているのか 補論 金利政策の理論的支柱としての現代マクロ経済学 第二章 金利はなぜ「特殊な価格」なのか 1 ミクロ経済学からみた金利の特殊性 2 家計にとっての金利はどう決まっているか 補論 社会規範からみた金利の位置づけ 第三章 消費者金融の金利は高すぎるのか低すぎるのか 1 消費者金融の金利 2 苛酷な取り立てがもたらした社会規範の変化 3 グレーゾーン金利解消の副作用は大きかったか? 補論 高利だが安全な質屋金融はなぜ衰退したのか 第四章 住宅ローンの金利は上がるのか下がるのか 1 日本における住宅ローン金利の選択肢 2 金利リスクが破滅的結果をもたらしたサブプライム・ローン問題 3 教訓 ―― 住宅ローンで家計の破綻を避けるために必要なこと 補論 ねずみ講・レッドライニング・略奪的貸出 第五章 金利はなぜ円高・円安を起こすのか 1 固定相場の時代 2 変動相場制と価格裁定・金利裁定 3 為替レートの予測はなぜ当たらないのか 4 為替レートと金利をめぐる不都合な真実 補論 円安・円高は将来の日本の人口構成を変える エピローグ ―― 金利引き上げと株価暴落
本書は、愛知県のトヨトミ自動車を舞台にした企業小説で、主人公の武田剛平が左遷から社長に昇りつめ、ハイブリッドカーの量産に挑む姿を描く。創業家出身の豊臣統一との確執や、自動車業界の経済戦争を通じて、フィクションと現実の境界が曖昧なストーリーが展開される。真偽のほどは不明だが、面白さは保証されている。
この本は、新NISA制度や暗号資産、キャッシュレス化などの金融の変化に対する知識を提供します。金融の基礎から市場、金利、金融政策、金融機関の役割、株や債券の仕組みまでをわかりやすく解説し、専門用語も丁寧に説明します。読み終える頃には、金融の世界が身近に感じられる内容です。著者は金融業界での豊富な経験を持つ伊藤亮太氏です。
現代金融の全体像を理論,歴史,現状からバランスよく解説。リーマン・ショックなどを踏まえて10年ぶりに大幅改訂。 現代金融の全体像を理論,歴史,現状からバランスよく解説したスタンダード・テキストを10年ぶりに大幅改訂。第Ⅰ部で金融の基礎的な概念や理論,メカニズムを,第Ⅱ部で日本の金融制度や政策を,第Ⅲ部でグローバル時代における現代金融の諸問題をわかりやすく解説。 第Ⅰ部 現代金融の基礎 第1章 貨幣と金融(川波洋一) 第2章 金融機関と銀行業(青山和司) 第3章 企業・家計と金融(前田真一郎) 第4章 金融市場と金融資産(三谷進) 第5章 管理通貨制と中央銀行(近廣昌志) 第Ⅱ部 現代金融と日本経済 第6章 景気変動と金融危機(川波洋一) 第7章 現代の金融業(掛下達郎) 第8章 国債膨張下の財政と金融(吉川哲生) 第9章 金融政策の新展開(森田京平) 第10章 金融規制と金融制度改革(山村延郎) 第11章 地域金融(齊藤正) 第Ⅲ部 グローバル化と現代金融 第12章 グローバル化と情報技術革新 (遠藤幸彦) 第13章 金融業の変貌とグローバル展開 (木村秀史) 第14章 グローバル化と主要国の金融システム(伊鹿倉正司) 第15章 金融のグローバル化と国際金融システム(上川孝夫) 第16章 グローバル化のなかの円(上川孝夫)
この本は、日露戦争時の戦費調達に奔走した高橋是清と深井英五の物語を描いています。彼らは、急速に進化する20世紀初頭の国際金融市場で、日本国債の発行を可能にするために奮闘しました。証券価格の動きを追いながら、外債募集の過程を詳細に再現し、新たな日露戦争像を提示しています。著者は、金融業界での経験を持つ板谷敏彦です。
この書籍は、日本の投資信託の問題点を指摘し、金融機関の巧妙な営業に騙されないための知識を提供します。投信の選び方や活用法を解説し、特に初心者からベテランまでの投資家に向けたアドバイスが含まれています。また、世代別の運用法やよくある疑問にも答えています。著者はファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子です。
本書は「教養としての○○」シリーズ第7弾で、金利についての基本をわかりやすく解説しています。著者の田渕直也氏が、金利の意義や歴史、計算方法、債券との関係、経済への影響などを幅広く深く取り上げ、金融緩和政策の変化の中で金利を学ぶ重要性を伝えています。読み応えがありながら面白い入門書です。
複雑でわかりにくい金融の理論や仕組みを,図表や事例を豊富に用いて丁寧に解説。学習にも実務にも使える決定版テキスト。 初学者には馴染みのない金融の専門用語から,証券化や投資信託といった複雑でわかりにくい金融の仕組み,マイナス金利やマクロプルーデンスなどの最新の金融政策までを幅広くカバーし,図表や事例を豊富に用いて丁寧に解説。学習にも実務にも使える決定版テキスト。 第Ⅰ部 貨幣と金融取引 第1章 貨幣と決済 第2章 金融とその機能 第3章 取引費用とリスク 第4章 情報の非対称性と返済のリスク 第Ⅱ部 取引費用に対処する金融の仕組み 第5章 金融の仕組み⑴:流動化,証券設計,情報生産 第6章 金融の仕組み⑵:担保,保証 第7章 金融の仕組み⑶:分散化 第Ⅲ部 金融機関と金融市場 第8章 金融機関⑴:金融仲介機関 第9章 金融市場 第10章 金融機関⑵:金融仲介機関以外の金融機関 第Ⅳ部 金融のマクロ的側面 第11章 資金循環と金融システム 第12章 金融政策と経済の実物面・金融面 第13章 金融システムの問題と金融危機 第14章 金融制度と公的介入・プルーデンス政策
この書籍は、経済学が理論重視から実証分析重視へと変化してきた経緯を探り、その過程で苦闘してきた経済学者たちの足跡を追っています。目次には、ノーベル経済学賞と計量経済学の関係、実証分析の重要性、因果推論の課題、RCTの位置付け、EBPMの可能性と限界、そして失われつつあるユートピアについての章が含まれています。著者は前田裕之で、経済学の研究や教育に従事しています。
この書籍は、経済学の入門書であり、現実経済や新たな経済学の動向を分かりやすく解説しています。内容はミクロ経済学とマクロ経済学に分かれ、需要と供給、消費者行動、市場の失敗、経済政策など幅広いテーマを扱っています。著者は東京大学の教授、伊藤元重氏です。
この書籍は、日常生活で必要なお金に関する基礎知識を解説しています。著者は、マネー知識がゼロの文系編集者で、元国税専門官に様々なお金の疑問を尋ねています。内容は金利、源泉徴収、税金、株、銀行、保険、年金など多岐にわたり、初心者にもわかりやすく説明されています。2時間で読める構成で、読者の金銭的不安を解消し、社会の仕組みを理解する手助けをします。
生活が苦しい国民と景気回復を発表する政府はいつも食い違う。データと実感が乖離する景気の仕組みを解明し日本経済に光をあてる。 「生活が苦しい」という国民と「景気回復」を発表する政府はいつも食い違う。どうしてデータと実感がズレるのか。景気の仕組みを紐解いて日本経済に光をあてる。 データと実感がズレる理由に迫る! 「給料が上がらず生活が苦しい」という国民の実感と「景気は緩やかに回復している」という政府の発表は食い違っている。テレビや本で紹介される経済学者の言うことは現実問題と関係が無いとすら思える。どうしてデータと実感がズレるのか。GDPや景気動向指数はどのような仕組みなのか。景気の問題と二百年以上向き合ってきた経済学の歴史から、現代の政策に至るまで「景気」の実相を究明し、不透明な日本経済に光をあてる。 はじめに 第1章 「景気」とは何か 第2章 政府の景気判断は正しいのか 第3章 1%成長時代の景況感 第4章 経済統計はどう誕生した? 第5章 大不況の中で生まれた経済理論 第6章 袋小路から抜け出すには おわりに
直木賞受賞作『下町ロケット』が文庫化されました。主人公の佃航平は町工場・佃製作所を継ぎ、製品開発で成功を収めますが、大手メーカーから特許侵害で訴えられ、窮地に立たされます。国産ロケットを開発する帝国重工が佃製作所の特許技術に目を付け、特許を売れば救われるが、その技術には佃の夢が込められていました。男たちの矜恃が交錯する感動の物語です。
本書は、戦後日本経済の歴史を67のトピックスを通じて解説する入門書です。財閥解体や石油危機、消費税導入などの重要な出来事を追い、復興から成長、停滞までの軌跡を示しています。著者は日本経済新聞の記者で、現代経済の流れを理解するためのエピソードを中心に構成されています。また、「失われた20年」に関する補論も含まれており、初心者にも分かりやすい内容となっています。
この書籍は、金融危機の原因と背景を国際金融の専門家が解説する内容です。ニクソン・ショックや中南米危機、プラザ合意、ブラック・マンデー、日本のバブル崩壊、アジア通貨危機、ITバブル崩壊、リーマン危機など、歴史的な金融危機を取り上げ、それぞれの影響や教訓を考察しています。また、次の震源地についても言及されており、金融システムの脆弱性を指摘しています。著者は東京大学卒業後、国際金融機関での経験を持つ倉都康行氏です。
社内の権力闘争に翻弄されながらも、義を貫き再生を果たした一人の男の物語。定年後の人生をどう生きるかを考えさせる小説。 「部長職を解き調査役を命ずる」という辞令を受けた主人公。社内の権力闘争に巻き込まれ翻弄されながらも、「人間としてやるべきことは何か」を貫いた一人の男の再生の物語。定年後の人生をどう生きるかを考えさせる小説。 「部長職を解き調査役を命ずる」という四月一日付の辞令を受けた主人公は、その日から机の配置も変わり部下のいない社員、いわゆる窓際族になった。しかし社内の権力闘争から再び表舞台へ上がるが……。権力闘争に巻き込まれるも同僚への思い遣りの心を大切にし、「義を見て為ざるは勇無きなり」と義を貫く主人公の生き方は、聖書の言葉「日は昇り、日は沈みあえぎ戻り、また昇る」のごとく転変を繰り返す。本作品は、組織の掟と、義や情の間に揺れ動き翻弄されながらも、「人間としてやるべきことは何か」を貫いた一人の男の再生の物語だが、定年後の人生をどう生きるか──という、誰もが抱える後半生の大きなテーマに光を当てた物語でもある。 第一章 止まって見えた大時計の針 第二章 抜け切れない会社人間 第三章 君は何を報告したのだ 第四章 あなたは運のいい人だ 第五章 言われたとおりにやれ 第六章 社長が行方不明です 第七章 今度は君が社長だ 第八章 賽は投げられた 第九章 最初に見せたのは誰だ 第十章 常務が自殺 終 章 夢、遙か あとがき
本書は、行動経済学を通じて人間の非合理的な意思決定を学び、ビジネスや生活に活かす方法を紹介する内容です。著者は東京大学の阿部誠教授で、行動経済学の基本概念をイラスト図解でわかりやすく解説し、実例を交えて応用法を提案しています。特に「ナッジ理論」やマーケティングへの活用事例が取り上げられ、ビジネスパーソンが戦略や企画を提案する際の参考になる一冊です。
本書は、全米で50万部以上のロングセラーを大幅改訂したもので、現代の投資家に向けた運用哲学のバイブルです。市場に勝つことが難しい今、インデックス・ファンドを活用することが最も効果的な投資方法とされています。内容は3部構成で、資産運用の基本、理論的な視点、個人投資家への具体的な助言が含まれています。著者は、投資の専門家としての経験を持つチャールズ・エリスと鹿毛雄二です。
2024年1月20日、JAXAは小型月面着陸実証機SLIMが月面に成功裏に着陸したと発表し、世界初のピンポイント着陸を実現したことが明らかになった。本書は、日本の宇宙開発の父である糸川英夫の生涯とイノベーションに焦点を当てた評伝であり、彼の影響を受けた事例として小惑星探査機「はやぶさ」の成功が紹介されている。内容は糸川の生い立ちから宇宙開発への道を辿り、彼の革新的なアイデアや業績を詳細に描いている。
本書は、金融エリートたちが実体経済を犠牲にして金融市場に資金を注ぎ込み、経済の二極化を引き起こしたことへの警鐘を鳴らしています。著者はウォール街の内幕を知るジャーナリストであり、経済の「永続的なゆがみ」とその恐怖について論じています。内容は、混乱、依存、過熱、変容の四部構成で、特にパンデミックやマネー供給の無制限化、暗号通貨の影響などが取り上げられています。
本書は、初学者向けの経済学入門テキスト『経済学入門(第3版)』の改訂版で、2007年に刊行された第2版から大幅に更新されています。主な変更点は、執筆陣の変更によりミクロ経済学とマクロ経済学がそれぞれ1人の著者によって担当され、内容が初歩から中級にわたるように整理されたことです。また、日本の事例を多く取り入れたコラムが刷新され、経済学の理解を深める内容になっています。目次はミクロ経済学とマクロ経済学の各章で構成され、今後の学習に向けた章も含まれています。著者は早稲田大学の教授陣です。
元ゴールドマン・サックスのベストセラー作家が描く、青春「お金」小説!子どもでも楽しめて大人の教養になる!ラストで泣ける物語! 話題沸騰!Amazonベストセラー総合1位!!大人も子どもも知っておきたい、経済教養小説!絶賛の声、続々!「こんな本が読みたかった!お金の常識がガラッと変わった」(20代、IT)「目から鱗で一気に読んだ。中学生の息子にも読ませたい」(40代、営業)「ハッとするような言葉の連続。ラストでは涙が溢れてきた」(50代、経営)所得、投資、貯金だけじゃない、人生も社会も豊かにするお金の授業、開講!今さら聞けない現代の「お金の不安や疑問」を物語で楽しく解説!・日本は借金まみれでつぶれるの?・少子化でもやっていける方法って?・物価が上がるのと下がるの、結局どっちがいい?・どうして格差が広がるの?・貯金をしても老後資金の問題は解決できない・貿易赤字が「本当にヤバい」理由は?「お金の本質」がわかると、人生の選択肢が増える! お金の不安がなくなる!「え、そうなの?」が「そうだったのか!」に!6つの謎で世界の見え方が変わる!・お金の謎1:お金自体には価値がない・お金の謎2:お金で解決できる問題はない・お金の謎3:みんなでお金を貯めても意味がない・格差の謎:退治する悪党は存在しない・社会の謎:未来には贈与しかできない・最後の謎:僕たちはひとりじゃない◆本書のあらすじ◆ある大雨の日、中学2 年生の優斗は、ひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海とともに、謎めいた屋敷へと入っていく。そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり、「この建物の本当の価値がわかる人に屋敷をわたす」と告げられる。その日からボスによる「お金の正体」と「社会のしくみ」についての講義が始まる 。 プロローグ 社会も愛も知らない子どもたち 第1章 お金の謎1:お金自体には価値がない 第2章 お金の謎2:お金で解決できる問題はない 第3章 お金の謎3:みんなでお金を貯めても意味がない 第4章 格差の謎:退治する悪党は存在しない 第5章 社会の謎:未来には贈与しかできない 最終章 最後の謎:ぼくたちはひとりじゃない エピローグ 6年後に届いた愛
中学生でお金について学べる主人公が、羨ましいと思った。大人になった今も、私はまだ分からない。でもこの本を通して、いろんな考え方があることに気づけた。もっと自分のお金観を育てたくなった。
本書は、カリスマ経営者たちが著した書籍のエッセンスを解説し、ビジネスに活用するための視点を提供します。取り上げられているのは、稲盛和夫や柳井正など10名の経営者の代表作で、彼らの卓越した知見が満載です。読者が実際の経営判断に役立てられるよう、エクササイズも挿入されており、マネジメント層や若手ビジネスパーソンにとって必読の内容となっています。
この本は、金利を通じて景気の動きを理解し、投資に成功する方法を解説しています。著者は現役ファンドマネージャーであり、実践的な内容が個人投資家から高く評価されています。日本の金利の変動や金融政策、投資戦略についての章があり、特に最近の経済状況の変化に焦点を当てています。
著者の実務経験を生かし、国際金融の基礎から為替制度、経済危機まで幅広く解説した書籍です。国際収支や為替レートの理論と実証研究、通貨危機や国家債務危機の特徴を分析し、グローバリゼーションの意義も考察しています。著者は経済学者であり、実務家としての経験も持つため、アカデミックな視点と実践的な視点が融合した内容となっています。
この書籍は、マネーの本質やその支配者を探求するエコノミストによるマネーの進化史を描いています。内容は、マネーの起源から権力の誕生、銀行の発明、経済学の観点まで多岐にわたります。著者のフェリックス・マーティンは、経済学の博士号を持ち、世界銀行での経験を経て、現在はロンドンでマクロエコノミストとして活動しています。
本書『現代の金融入門』は、金融ビジネスモデルの変革が求められる中、著者が金融の本質を再考し、情報や信用の創出について解説しています。金融危機を踏まえた全面改訂版で、アメリカのリスク取引や金融システムの安定に必要な規制について考察。また、資産価格バブルや非伝統的金融政策の影響も検討しています。著者は慶応義塾大学の池尾和人教授で、金融論の専門家です。
経済学の全体像を実践的に理解できる、最強の入門書を完全アップデート! 金融政策、物価、世界経済、キーワード索引などを増補。 経済学の全体像を実践的に理解できる、最強の入門書を完全アップデート! 金融政策の変遷、世界経済、キーワード索引を増補。ビジネスパーソンの学び直しにも! 全体像を一気につかむ! 最強の入門書、完全リニューアル? ▼キーワード索引で検索性UP↑ ▼ビジネスパーソンの学びなおしにも! 毎日の経済ニュースの捉え方や見方を高校生が理解できるように、経済学の考え方を徹底的に分かりやすく解説します。 需要と供給、市場メカニズム、金利、格差、効率と公平、景気、物価、GDP、人口減少と経済成長、インフレ、金融政策、税金と財政、社会保障、円高と円安、比較優位、貿易と世界経済…… ポイントやキーワードを押さえながら、経済学の全体像を一気につかみましょう。 ビジネスパーソンや大学生など、高校生以外の 学びなおしにもピッタリの最高の入門書。 知っているようで説明できない用語を、理解できる! 経済ニュースの見方や捉え方が、わかる! GDP/ GDPデフレーター/ FTA/大きな政府/ 異次元の金融緩和/金融引き締め/機会の平等/ インフレ/デフレ/物価/ CPI /景気/金利/ 市場メカニズム/市場の失敗/累進性 プライマリー・バランス/マネタリーベース…… (本書に登場するキーワードより) === はしがき 序 章 経済学を学ぶ前に 1 経済学はどのように学ばれているか 2 高校生にとっての経済学 第1章 需要と供給の決まり方 1 需要の大きさはどのように決まるか 2 価格と需要の奇妙な関係 3 供給の大きさはどのように決まるか 第2章 市場メカニズムの魅力 1 需要と供給を出合わせる 2 競争はいいことか悪いことか 第3章 なぜ政府が必要なのか 1 市場の「失敗」を補正する政府 2 高所得層から低所得層への所得再分配 3 経済を安定化するという役割 第4章 経済全体の動きをつかむ 1 経済全体の大きさを測る 2 景気の動きを捉える 3 物価と経済の関係を探る 4 経済成長のメカニズムを考える 第5章 お金の回り方を探る 1 お金の役割を考える 2 お金の動きを追ってみる 3 日本銀行の役割 ― 金融政策の話 第6章 税金と財政のあり方を考える 1「大きな政府」vs「小さな政府」 2 税金の納め方と使い方 3 財政赤字をめぐるさまざまな議論 4 世代と世代の利害対立 第7章 世界に目を向ける 1 なぜ外国と貿易取引をするのか 2 貿易収支は黒字が望ましいのか 3 円高と円安、どちらがよいか 4 深まる世界の結びつき おわりに 索引
本書は、さびれた商店街から「ユニクロ」を創り上げた柳井正の苦闘と成長を描いたノンフィクションです。青年の覚醒から始まり、東京進出やフリースブーム、海外展開の苦戦、ブラック企業批判を経て、ユニクロが情報製造小売業へと進化する過程をリアルに描写しています。著者は、柳井とその仲間たちの戦いを通じて、現代の企業や働く人々に希望を与える物語を提供しています。
本書『入門経済学』は、著者たちの『ミクロ経済学』と『マクロ経済学』から15章を選び、経済学の基本概念を学ぶために再構成されたテキストです。3部構成で、第1部は経済学の基本知識、第2部はミクロ経済学の基礎、第3部はマクロ経済学の基礎を扱います。著者は経済学のシンプルな考え方が現実の問題を理解し改善するのに役立つとし、最新のトピックを取り入れた「新しい」内容が特徴です。テキストには、経済学の原理や現実社会の問題を解決するためのコラムが含まれ、学生が経済を理解するための優先事項として位置づけられています。読後には、経済社会に対する見方が変わることが期待されています。
この書籍は、経済に不慣れな人でも理解しやすい形で最新の「お金の常識」を学べる内容です。目次には、お金の基本、稼ぎ方、将来のための蓄え方、最新の金融情報、そしてお金の流れについての章が含まれています。著者は金融教育ベンチャーのCEOであり、経済アナリストとしての豊富な経験を持つ森永康平氏です。
本書は、デフレに慣れた日本人に向けて、インフレ時代を乗り切るための経済指標の重要性を解説しています。近年の物価高騰や金利上昇などの影響で経済が不透明な中、適切な指標を理解することで資産を守り、増やす手助けとなる内容です。主な章では、重要な経済指標の解説や、米国の指標、景気を読む企業、コモディティの関係などが扱われています。著者はエミン・ユルマズで、経済の理解を深めたい人々に向けた指南書となっています。
本書は、金融機関の役割やマーケットの仕組みをわかりやすく解説した入門書の最新版です。銀行、証券、保険などの金融界の全体像や、金利、為替、株価に関する基本的な知識を提供し、マイナス金利やデジタル通貨といった最近のトピックスも取り上げています。金融の勉強を始める人や金融機関への就職を考える人に適した内容です。目次はお金の動きから金融市場、当局の役割、国際金融の挑戦まで多岐にわたります。
著者の川田修が伝説の営業マンと過ごした31日間の経験を通じて、営業テクニックだけでなく、仕事や人として大切なことを学んだ感動のストーリーを描いた本です。彼は外資系企業のトップセールスとして、営業目標を達成し続けており、現在は講演活動も行っています。
2022年から高校での投資教育が必須となり、経済教育への関心が高まっている。本書は、経済の基本やお金の流れ、投資の知識を初心者向けにわかりやすく解説する入門書で、著者のNobbyが「なぜ?」や「どうすればいい?」といった疑問に答える。内容は、世界情勢や日本経済、アジア経済、資源と情報の関係、投資の基礎に関する章で構成されている。
本書は、日本経済新聞の記者が執筆した投資の入門書で、株式、債券、投資信託、為替、貴金属などの金融商品についての基本知識を提供します。各章では、各金融商品の特性や取引方法、分析のコツ、注目すべき指標などを解説し、資産形成の手法を学ぶことができます。豊富な図表を用いて、投資の基礎をわかりやすく説明しています。初心者や投資を始めたい人に最適です。
本書は、金融業界の現状や仕組みを解説した業界研究の決定版です。フィンテックやAIの影響で変革が進む金融業界を、銀行、証券、保険、投資銀行、ノンバンクの5つに分類し、それぞれのビジネスモデルや動向を詳しく説明しています。業界の基本知識から最新のトピックまで幅広くカバーし、専門用語の解説も行っています。金融業界への就職や転職を考える人や、業界全体を理解したい人に適しています。著者は金融業界での豊富な経験を持つ専門家です。
イングランド銀行が提供する経済入門書で、経済に関する基本的な疑問を10の質問を通じてわかりやすく解説しています。景気や金利、インフレ・デフレ、GDPなどの用語や、経済危機や気候変動といった現代の問題を理解する手助けをします。高校生から一般のビジネスパーソンまで幅広い読者に向けた内容で、経済学の基本をシンプルに学べる一冊です。著者はイングランド銀行のエコノミストです。
桂木英一は、旧態依然とした日本の銀行を離れ、ウォール街の投資銀行で成長していく。彼は「伝説の男」竜神宗一と出会い、金融業界の変革期に直面する。1980年代の米国で、最先端の金融技術を駆使する中、複雑な取引や買収案件に挑むが、世界的な金融不安が彼を襲う。著者の黒木亮は、長年の金融業界の経験を持つ作家である。
若くして役員となった鹿子小穂は、父が招聘した大槻によって会社を追い出され、ヘッドハンティング会社に拾われる。新米ヘッドハンターとして、一流の経営者と接触しながら、仕事や経営、人情を学んでいく。著者の雫井脩介が新たな挑戦をしたビジネス小説で、緊迫感と感動が詰まった作品。
本書は、乱高下する為替相場や景気後退、株価下落などの世界経済の動向を理解するために、国際金融の理論、仕組み、歴史を解説する。旧版をアップデートしたもので、国際金融の基礎知識をコンパクトに学べる一冊。目次には、国際金融と外国為替、国際収支、為替相場制度、財政金融政策、為替リスクなどが含まれている。著者は岩田規久男。
中堅ゼネコン・一松組の若手社員、富島平太が異動したのは大口公共事業を受注する“談合課”。地下鉄工事の受注が迫る中、彼は技術力で入札に挑むが、談合の壁に直面する。組織に従うか正義を貫くかを問う人間ドラマが展開される。著者は池井戸潤で、吉川英治文学新人賞を受賞した作品。
常態化した「非伝統的」手段はどこに向かうのか 1998年の日銀法改正以来、日本の金融政策は「非伝統的金融政策」の導入と、黒田日銀総裁の指揮下での大胆な「異次元緩和」政策という二回の大きな変革を経験した。この間、FRBをはじめ主要国中銀がともに政策の枠組みを大転換させ、共通の新しい課題を抱える中、2023年に着任した植田和男新総裁はどのような舵取りで「出口」を模索するのか。本書はこれまでの経緯と今後の行方を理論・実証両面から分析する、金融市場関係者必読の一冊。 ◆ 筆者は、大学卒業後、銀行の調査部、金融為替市場関連部署に20年近く在籍し、エコノミストとして実体経済と日米中央銀行の政策を分析した。その後、大学に移籍してアカデミズムの世界に身を置き、マクロ・金融理論の展開に接しながら金融政策を論じるようになった。そうした経歴の中から、政策・実務の現場からの視点と経済理論からの視点を併せ持った分析を行うことで、金融政策論に新たな貢献をもたらす第一線の研究者。 ◆ 他の類書にみられない著者オリジナルの特色は、以下の通り。 ① 独自の「五分類法」で非伝統的政策手段を包括的に区分し、各手段の波及経路の分析、論争や誤解についての整理を行った。金融政策に対する誤解は、しばしば経済理論の通説的解釈から発生しているが、これを明らかにし、また金融実務の観点から理論と現実のギャップを浮彫りにした上で、アカデミズムの世界におけるモデルに沿った政策メカニズムの捉え方の現実にそぐわない点も指摘する。制度や政策枠組みの時系列的な変化の分析には、理論的な観点を取り込んでいる(1章、2章、3章)。 ② 中央銀行の「期待」に働きかける政策として、フォワードガイダンス、コミュニケーション戦略、インフレ目標政策という三つの政策の相互関係を、国際比較も含めて分析した(4章)。 ③ 日銀の異次元緩和の包括的な分析(6章)に加え、「新常態」の政策レジームを「超過準備保有型金融政策」として定式化した(5章)。さらに、コロナ危機が中央銀行に与えたインパクトの整理(5章)や、現代の中央銀行が抱える諸問題の整理・検討(7章)においても、金融政策論に一定の貢献を行っている。 第1章 短期金利誘導型金融政策とその形成 短期金利誘導型金融政策の理念型――メカニズムと波及経路/主要パーツとしての公開市場操作、信用創造、準備預金制度/短期金利誘導型金融政策とその形成過程――FRBと日銀の場合 (コラム1)信用創造メカニズムの通説的な説明 第2章 非伝統的金融政策の諸手段とそのメカニズム 非伝統的金融政策とは何か/大量資金供給/大量資産購入/フォワードガイダンス/貸出誘導資金供給/マイナス金利政策 (コラム2)非伝統的金融政策の分類学 第3章 主要国中央銀行の非伝統的金融政策と「正常化」の頓挫――大量資産購入を中心に 主要国中央銀行の政策展開――コロナ危機前まで/中央銀行界をリードしたFRBの大量資産購入/抑制的に運営されたBOEの大量資産購入/マイナス金利政策、TLTROと絡み合ったECBの大量資産購入/大量資金供給から大量資産購入に転じた日銀(異次元緩和前まで)/四中銀の大量資産購入「正常化」とその頓挫 (コラム3)大量資産購入の副作用―バーナンキの認識と究極の問題 第4章 フォワードガイダンスと「期待」 政策手段としてのフォワードガイダンス/中央銀行の情報発信あるいはコミュニケーション戦略の強化/インフレ目標政策/期待に働きかける政策と経済理論 (コラム4)二つのフォワードガイダンスの関連 第5章 コロナ危機のインパクトと金融政策の「新常態」 コロナ危機が中央銀行に与えたのインパクト/主要国中銀のコロナ危機対応/コロナ緩和の縮小と引締めへの急旋回/政府債務の拡大と中銀による財政ファイナンスの懸念/新常態としての「超過準備保有型」金融政策下の政策運営 (コラム5)「新常態」下における政策金利誘導の難しさ 第6章 日銀「異次元緩和」の特種性――長期化と変容、「出口」の難しさ 「異次元緩和」の全体像と特種性/「異次元緩和」の導入と展開/異次元緩和がもたらしたもの/コロナ危機を経て (コラム6)貸出促進利付制度による貸出誘導策の体系化 第7章 現代の中央銀行が抱える諸問題 自然利子率の低下と中央銀行―長期停滞論の中で/低インフレ時代の物価コントロール――供給インフレにどう対処するか/中央銀行のマンデートをめぐる議論/低金利下のバブルと金融システムの安定/財政ファイナンスと中央銀行/日銀はどう動くべきか――直近の円安、物価上昇と大局的なパースペクティブ (コラム7)日本のプライマリーバランス赤字は容認されるか
本書は、教育におけるデータ分析と経済学の視点を用いて、教育投資や政策の効果を論理的に解説しています。著者は、教育の効果を高めるための家庭や学校の役割、教育制度の設計について分析し、特にコロナ禍の影響や日本の事例を取り上げています。幅広い読者層を対象に、教育の最適化に向けた具体的な施策を提案しています。
この本は、金融や投資に関連する確率・統計の基本概念をわかりやすく解説しています。数式に不安がある人にも理解できるよう、実例を用いた説明がされており、各章の最後には数式による補足も提供されています。読みやすさと理解の深さを兼ね備えた一冊です。
この書籍は、金融を初めて学ぶ人向けの2023年改訂版で、日本の金融業の現状や制度、戦後の歴史を解説しています。ウクライナとコロナの影響、東京証券取引所の市場再編、フィンテック、デジタル通貨など最新の動向を含む内容です。数式を使用せず、数学が苦手な読者でも理解しやすいテキストで、講義にも適しています。目次は金融の基礎から国際金融まで幅広くカバーしています。著者は中島真志と島村高嘉です。
この書籍は、日本の男女平等の低さの原因を社会学的に分析し、さまざまなデータを用いて解明します。著者の山口一男氏は、企業が女性活用を妨げる思い込みや、長時間労働の文化が女性の職業進出を難しくしていることを指摘。また、女性の高学歴化が進んでも高賃金職に就く割合が低く、賃金格差が拡大している現状を説明します。全8章で、男女の所得格差や職業分離、企業のワークライフバランス推進の影響などを詳細に分析し、男女不平等の不合理性を論じています。
本書は、行動経済学の主要理論を体系化した入門書であり、「ナッジ理論」や「プロスペクト理論」などを扱っています。著者の相良奈美香は行動経済学の専門家で、コンサルティング会社を運営し、幅広い業界に行動経済学を導入しています。内容は、認知のクセ、状況、感情が意思決定に与える影響を探求し、日常生活における行動経済学の理解を深めることを目的としています。
本書は金融の基本をイラストを交えてわかりやすく解説しており、金融が経済全体に与える影響やお金と金利の役割を説明しています。金融教育の専門家である著者が、金融の仕組み、投資商品の種類、そして金融の未来について詳しく述べています。金融に関する知識を手軽に学びたい人に適した一冊です。
本書は、スタンフォード大学の“最優秀講義賞”を受賞した経済学の授業を再現し、経済政策のニュースを分かりやすく解説します。マクロ経済、GDP、失業率、インフレ、財政政策、国際貿易などのテーマを扱い、誰でも経済通になれる内容です。著者は経済学者のティモシー・テイラー、ジャーナリストの池上彰、翻訳家の高橋璃子です。
この文章は、最新改訂版のマクロ経済学テキストの内容を紹介しています。全7部、18章から構成され、世界金融危機後の金融規制やマクロ経済政策の変化を取り上げています。各部では、経済学の基本原理、データ、長期的な経済成長、貨幣と価格、開放経済、短期的な経済変動について解説されており、実際の経済の面白さを実感できる内容になっています。
田中辰夫は、大手不動産会社でリストラを実施した後、自らも解雇され、失業者となる。一方、息子の雅人は就職先を辞め、ネットビジネスを目指す。父と子はそれぞれの困難に立ち向かいながら、新たな不動産サービスを模索し、再建を目指す物語。著者は江波戸哲夫。
この本は、現代の経済の基本的な概念や仕組みをわかりやすく解説しています。内容は、「デジタル通貨」「仮想通貨」「電子マネー」の違いや、アメリカの銀行破綻の理由、中国の経済体制、物価上昇の原因、景気の良し悪し、日本の新しい経済の形など、多岐にわたります。著者の池上彰が、経済の基本的な質問に答えながら、現代の経済の動きを解明していきます。
「金融政策」に関するよくある質問
Q. 「金融政策」の本を選ぶポイントは?
A. 「金融政策」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「金融政策」本は?
A. 当サイトのランキングでは『21世紀の金融政策 大インフレからコロナ危機までの教訓』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで157冊の中から厳選しています。
Q. 「金融政策」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「金融政策」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。



![『[新版]この1冊ですべてわかる 金融の基本』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Gj20PvQzL._SL500_.jpg)




![『世界の中央銀行/アメリカ連邦準備制度(FRS)の金融政策 [第2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51nc+PldOlL._SL500_.jpg)


































![『図解即戦力 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51OThsXV9HL._SL500_.jpg)
















![『入門経済学[第4版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41dClUCUpEL._SL500_.jpg)






























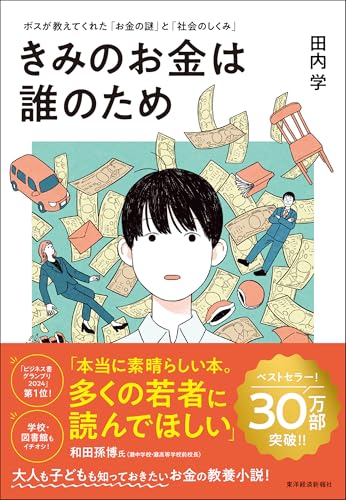




















![『現代の金融入門 [新版] (ちくま新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41la6aDpuIL._SL500_.jpg)
![『高校生のための経済学入門[新版] (ちくま新書 1779)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41BeOsvHSuL._SL500_.jpg)


















![『図解即戦力 金融業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書[改訂2版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51R7Ojpv9KL._SL500_.jpg)




































