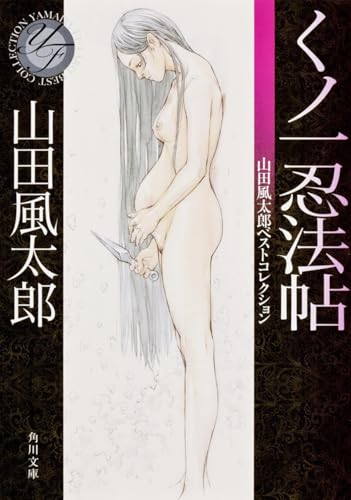【2025年】「法医学」のおすすめ 本 100選!人気ランキング
- 不自然な死因~イギリス法医学者が見てきた死と人生
- ユリイカ 2022年8月号 特集=現代語の世界 ―若者言葉から語用論まで―
- いまどきの死体 法医学者が見た幸せな死に方
- 解剖探偵 (角川文庫)
- 19番目のカルテ 徳重晃の問診 (1) (ゼノンコミックス)
- エッセンシャルシリーズ NEWエッセンシャル 法医学 第6版
- 標準法医学 第8版 (Standard textbook)
- ヒポクラテスの誓い
- 学生のための法医学
- 探偵ガリレオ
本書は、法医解剖医である著者が、解剖を通じて明らかになった死の真実や現代社会の課題について述べています。目次は6章から成り、法医学の役割や思いがけない死、解剖による事件の真相、孤独死や虐待死といった現代の問題、個々の人生を反映する遺体の物語、法医解剖医としての考え方が取り上げられています。著者は約3000体の解剖を行い、急増する孤独死に関する研究を進めています。
ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。
五分間の永遠 無人島と一冊の本 パン、買ってこい 電話が逃げていく 東京 蟹喰丸 背景の人々 カー・オブ・ザ・デッド 地球に磔にされた男 沈みかけの船より、愛をこめて 二つの顔と表面
手塚治虫の名作『BJ』の決定版が登場。天才外科医ブラック・ジャックが高額な治療費を提示しながら、不可能な治療を次々と成功させる物語。全集未収録の「ふたりの修二」も収められている。
老練な女用心棒バルサは、新ヨゴ皇国の二ノ妃から皇子チャグムを託され、精霊の卵を宿した彼を父帝や異界の魔物から守るために戦う。著者上橋菜穂子の緻密な世界構築が評価され、多くの受賞歴を持つロングセラーが文庫化された。新しい冒険シリーズが始まる。
現代の医者が、江戸時代にタイムスリップした医療系漫画です。薬がなかった時代に、現代で学んだ事を活かして、新しい薬を開発したり、疫病に立ち向かっていったりします。コミカルな、面白さもあります。
20 世紀ダブリンでなければ生まれなかった、 文豪・政治家たちの人物交流と名作。 20 世紀ダブリンでなければ生まれなかった、 文豪・政治家たちの人物交流と名作。 20 世紀ダブリンでなければ生まれなかった、 文豪・政治家たちの人物交流と名作。 W.B. イェイツ、ジェイムズ・ジョイス、G.W. ラッセル(Æ)、 オリヴァー・セント・ジョン・ゴガティ、ジョン・シング、グレゴリー夫人、 ショーン・オケイシー、マイケル・コリンズ…… アイルランド文芸復興、独立戦争など ダブリンの輝かしい時代を、人物の交流を通して見る一冊。 巻末には、本書に出てくる約270人の人物解説付き! 第一章 文化復興 第二章 アイルランド文芸復興 第三章 魅力的な個性を持った人びと 第四章 政治 第五章 ユーモア 第六章 成就 厳選した文献一覧 訳註 人物解説 年表 索引
国家福祉が主流を占める現代にあって,欧米,とくにイギリスはチャリティ大国としてその活力を保っている.公刊史料や手紙・広告などの非公刊史料によりつつ, 18世紀半ば以来の百年余にわたるチャリティ実践の歴史をはじめて活写し,救貧法史や福祉国家形成史,近代化論や帝国史からは知りえない,新しいイギリス像を掘り起こす. 序章 偽善・不合理・前近代?——フィランスロピとイギリス 第一章 さまざまなチャリティのかたち 第一節 遺産の半永久的な運用——信託型 第二節 寄付者の民主主義——結社型 第三節 貧者の相互扶助を管理下に——友愛組合支援型 第四節 コミュニティの記憶とアイデンティティ——慣習型 第五節 善意と浪費の相克——個人型 第六節 チャリティの近代的モザイク 第二章 近代国家とチャリティ 第一節 通史にチャリティを導入する 第二節 誰が誰をどのように救うのか——救貧法の再検討 第三節 難破船とイギリス近代——海難救助の歴史 第四節 慈悲深いイギリス——帝国とチャリティ 第三章 慈善社会で生きるということ 第一節 与える人、受け取る人——階級・ジェンダー・ネイション 第二節 日常と空間 第三節 チャリティのイデオロギー 第四節 転換と持続——一九世紀後半の「投票チャリティ」論争 第五節 チャリティの自然化した社会 終章 「チャリティの近代」のゆくえ
やろうと思ったけどできなかったこと、やる前に考えてしまったこと。考えすぎのプロ・武田砂鉄が紡ぐ不毛で豊かなエッセイ集。 やろうと思ったけどできなかったこと、やる前に考えてしまったこと。考えすぎのプロ・武田砂鉄が紡ぐ不毛で豊かなエッセイ集。 やろうと思ったけどできなかったこと、やる前に考えてしまったこと。不毛な考えが豊かに花開く、「日経MJ」連載から厳選したエッセイ123本詰め。
肥満の増加が社会問題となっているアメリカ。「肥満=悪」という反肥満イデオロギーが叫ばれるが、一体「太っている」とは誰のことを指し、それが意味するものは何なのか。気鋭の文化人類学者が肥満をめぐる問題から人間の多様なあり方を考える意欲的な著作。 はじめに――なぜ肥満/ファットに注目するのか? 序章 現代アメリカの「ファット/肥満」の民族誌に向けて はじめに Ⅰ.先行研究 1.人類学の対象としての肥満/ファット 2.フェミニズムのなかの太った女性 3.逸脱の医療化、社会問題論 Ⅱ.本書の視座 1.「肥満エピデミック」 2.「リスク社会」――「未来の操作可能性」と「未来の非決定性」の矛盾 3.「リスク社会」の新たな主体――「生物学的市民権」 4.新しい「人びとの種類(human kinds)」 5.ファット・アクセプタンス運動を理解するための本書の視座――「リスク社会」のアイデンティティ・ポリティクス? Ⅲ.フィールドワーク 1.本書の舞台――アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリア 2.フィールドワーク概要 3.本書の構成 4.用語の問題 第1部 肥満・リスク・制度 第1部導入 第1章 集合のリアリティ・個のリアリティ――アメリカの「小児肥満問題」から考えるリスクと個人 1.集合的事象としてのリスクと個人 2.錯綜する病因論と不確実性との対峙――「リスクの医学」の誕生と確率論的病因論 3.「肥満問題」とリスクの個人化 (1)「肥満エピデミック(Obesity Epidemic)」 (2)BMI小史 4.累積的リスクと「肥満になる」意思決定 (1)子どもの肥満をめぐる責任ゲーム――ジョージア州の小児肥満対策キャンペーンから (2)責任主体と累積的リスク (3)交錯する集合のリアリティと個人のリアリティ 第2章 空転するカテゴリー――福祉・公衆衛生政策から見る「貧困の肥満化」 1.リスクの犯人探し――「貧困の肥満化」という問題 2.貧困の肥満化 (1)貧困対策におけるアメリカ農務省による公的扶助の役割 (2)貧困の肥満化 3.公的扶助としての食料支援プログラムと肥満対策 (1)カリフォルニア州の「肥満の原因となる環境」への取り組み (2)WICプログラムの概要 (3)栄養カウンセリングの現場を中心に 4.引き受け手のないリスク (1)貧困層の肥満対策の複雑な構図 (2)引き受け手のないリスク 5.リスク・コンシャスなのは誰なのか――第2部に向けて 第2部 ファット・社会運動・科学 第2部導入 第3章 ファット・アクセプタンス運動の展開に見る「ファット」カテゴリーの特殊性 1.遅れをとるファット・アクセプタンス運動 2.ファット・カテゴリーを精査するために (1)社会運動とカテゴリー (2)マイノリティ・カテゴリーとしてのファット 3.ファット・アクセプタンス運動の歴史 (1)ファット・アクセプタンス運動の誕生――1969年 (2)第二波フェミニズムのなかの「ファット」――1970年代 (3)「障害」との連携――1980年代~1990年代 4.ファット・アクセプタンス運動のジレンマ (1)名乗りにおける齟齬 (2)公民権法が想定する個人観とADAが想定する個人観とその両立――「集合としての差異」と「集合のなかの差異」 5.「ファット」とインターセクショナリティ 第4章 ファット・アクセプタンス運動とフェミニズムの「ぎこちない」関係――ファットである自己、女である自己、その自己規定の困難 1.女であるからファットなのだ 2.フェミニズムを乗り越えようとする人びと (1)なぜフェミニズムは太った女性が受ける差別や抑圧に無関心なのか (2)美的・性的な身体としてのファット――1970年代から1990年代前半におけるフェミニズムからの影響、そして、フェミニズムとの距離 3.スージー・オーバックとの同盟をめぐる出来事 (1)フェミニズムとの同盟が招いた騒動――年次大会のゲスト・スピーカーをめぐって (2)フェミニストの「特権」 (3)小括――フェミニズムとファット・アクセプタンス運動の「ぎこちない関係」 4.ファットのなかの「多様性」――「ファット鶴プロジェクト(1000 Fat Cranes Project)」をめぐる人種差別批判 (1)「ファット鶴プロジェクト(1000 Fat Cranes Project)」 (2)「ファット鶴プロジェクト」に対する人種差別批判と文化的他者 (3)普遍主義と文化相対主義、ポジショナリティをめぐる問題 5.ファットであること、女であること、その自己規定の困難 第5章 「ファット」であることを学ぶ――情動的関係から生まれる共同性 1.なぜ集うのか? 2.共同性について考えるために (1)結果として生成する共同性 (2)社会運動の場において生成する情動的関係性 3.「ファット」であることを学ぶ (1)「ファット」から連想されるもの (2)年次大会の概要 (3)転倒する「ファット」と「痩せ」の意味 (4)「ファット」として生きることを語り合う (5)配慮の空間――身体実践から立ち現れてくる「ファット」 (6)ユーモラスな空間 (7)笑いの効果――言語使用実践から見る「ファット」 4.折り重なった矛盾の交渉、そして、笑いによる自他の跳躍 5.運動を持続させる力 第6章 ファット・アクセプタンス運動による対抗的な〈世界〉の制作 1.〈世界〉を制作するということ (1)公民権としての「ファット」の危機 (2)不確実性を生きる (3)〈世界〉という言葉と本章の目的 2.カテゴリーのもとに作られる〈世界〉 (1)生まれつきの「ファット」 (2)疫学理解の「誤謬」――相関関係と因果関係の混同 (3)対立するカテゴリー――「肥満」と「ファット」 3.「Health at Every Size」の組織化と事実作製 4.制作中の〈世界〉と既存の世界 (1)世界間の通じなさ (2)「パラダイム・シフト」、あるいは、同時にある二つの世界 5.〈世界〉制作と世界間の通約(不)可能性 (1)制作中の〈世界〉とすでにある世界の関係 (2)世界間の連続性と同一性について 6.「徹底した相対主義」――「リスク社会」とファット・アクセプタンス運動の世界 (1)部分的に通約(不)可能な存在として生きること (2)あらゆる視点から離れた世界はない 終章 多様性のために 1.本書で論じたこととファット・アクセプタンス運動のゆくえ (1)世界の概念化 (2)ファット・アクセプタンス運動のゆくえ 2.多様性のために (1)自然と文化の二分法的思考法から抜け出すこと (2)「普通」を相対化する (3)マークについて (4)「普通」であること 3.多様性のゆくえ おわりに 参考文献
『プラタナスの実』は、少子化やモンスターペアレントといった社会問題に直面する小児科医・鈴懸真心の物語です。彼は「子供が好き」だけでは乗り越えられない医療現場で、患者やその家族に寄り添いながら、温かく誠実に向き合います。作品は小児科医療の現状を描きつつ、家族の問題にも焦点を当てており、読者の心を温める感動的なストーリーです。
写真映像の存在論 完全映画の神話 映画と探検 沈黙の世界 ユロ氏と時間 禁じられたモンタージュ 映画言語の進化 不純な映画のために 『田舎司祭の日記』とロベール・ブレッソンの文体論 演劇と映画 パニョルの立場 絵画と映画 ベルクソン的映画、『ピカソ天才の秘密』 ドイツ零年 最後の休暇
本書は、エリックサウスの総料理長・稲田俊輔氏による、忙しいカレー好きのためのレシピ集です。疲れた夜でも簡単に本格的なインドカレーが約15分で作れる65の時短レシピと、休日にじっくり楽しむ本格南インド料理10レシピを収録。缶詰や肉、野菜を使ったアイデアも豊富で、カフェのメニュー開発にも役立ちます。
未知の物質によって太陽に異常が生じ、地球が氷河期に突入する中、男が宇宙に飛び立ち人類を救うミッションに挑む。『火星の人』のウィアーが描く、地球滅亡の危機をテーマにした極限のエンターテインメント。
21世紀後半、世界は「大災禍」を経て大規模な福祉社会を築いたが、そこに倦んだ3人の少女は餓死を選ぶ。しかし、死ねなかった少女・霧慧トァンは、13年後に混乱の中で亡くなったはずの少女の影を見る。著者は『虐殺器官』の伊藤計劃で、ユートピアの臨界点を描いている。
新米看護婦・似鳥ユキエが東京K病院での勤務を始め、先輩ナースたちの厳しい指導を受けながら、患者との関係や日常のトラブルに奮闘する様子を描いたホスピタル・コメディ。彼女は患者に心のこもった看護を提供しようと努力するが、中には苦手な患者もいる。物語はユキエの成長と騒動を中心に展開する。
ドラマ化された漫画です。病院内の薬剤師さんが患者さんに寄り添って、薬の説明をしたり、不安な事を聞いたり、とても優しくほっこりするような漫画です。ぜひ、手にとって読んで欲しいです。
公務員の沖らは、仮面の男・黒沼が所有する孤島での夏休みオフ会に参加する。初参加の赤毛の女子高生と共に孤島に着くと、翌日メンバーの二人が失踪し、続けて殺人事件が発生。さらに密室事件が続き、犯人探しが始まる。第50回メフィスト賞受賞作で、タイトル当てが読者への挑戦となっている。著者は早坂吝。
ドラマ化された漫画です。放射線技師が主役で、医者免許を持っている事を隠しています。レントゲン写真から、病気を見つけるのがおもしろいです。恋愛もあって、ドキドキします。
岸京一郎は病理医として病気の診断を行い、他の医師たちの診断をサポートする重要な役割を果たしています。彼は「強烈な変人だが、極めて優秀」と評されており、患者を密かに救う存在です。物語は彼の性格や助手との関係を描いた前後編の内容です。
本書は、孤島・古志木島で外科医として働く五島健助の物語を描いています。彼は東京の大学病院から赴任し、最初は受け入れられなかったものの、難手術を成功させることで島民の信頼を得て「コトー」と呼ばれるようになります。島には個性豊かな住民が約1000人おり、それぞれの病気や事情を抱えています。五島は彼らの命を守りながら、島の人々との絆を深めていきます。
大学生の種田静馬は、自殺を考え寒村の温泉宿を訪れた際、村の伝説に関わる少女の首切り事件に巻き込まれる。静馬は殺人犯と疑われるが、隻眼の少女探偵・御陵みかげの推理によって救われ、共に連続殺人事件を解決する。しかし、18年後、同じ場所で再び惨劇が起こる。著者の麻耶雄嵩は、この作品で日本推理作家協会賞と本格ミステリ大賞をダブル受賞した。
12歳の小夜は、亡き母から受け継いだ「聞き耳」の力を持つ少女。ある夕暮れ、犬に追われる子狐を助けたところ、その狐は霊狐・野火だった。隣国の争いに巻き込まれ、呪いを受けた少年・小春丸を救うため、小夜と野火は孤独な愛を育む。愛のために身を捨てた彼女たちは、恐れを克服していく。著者は上橋菜穂子で、作品は野間児童文芸賞を受賞している。
箱を祀る霊能者と箱詰めにされた少女たちを巡る事件が、美少女転落事件とバラバラ殺人を結びつける。探偵・榎木津、文士・関口、刑事・木場が事件に関与し、京極堂の元へ向かう。果たして憑物は落とせるのか?日本推理作家協会賞受賞のミステリー作品、妖怪シリーズ第2弾。
箱のなかの王国 吸血鬼の旅立ち スズとギンタの銀時計 静物平原 短時間接着剤 海田才一郎の朝 洞察者 ファンレター ナチュラロイド 円環の夜叉 最果てから未知へ
「法医学」に関するよくある質問
Q. 「法医学」の本を選ぶポイントは?
A. 「法医学」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「法医学」本は?
A. 当サイトのランキングでは『不自然な死因~イギリス法医学者が見てきた死と人生』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで100冊の中から厳選しています。
Q. 「法医学」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「法医学」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。