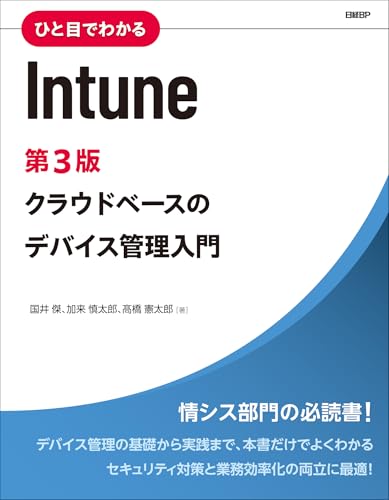【2025年】「要件定義」のおすすめ 本 130選!人気ランキング
- はじめよう! 要件定義 ~ビギナーからベテランまで
- はじめての上流工程をやり抜くための本~システム化企画から要件定義、基本設計まで (エンジニア道場)
- 図解即戦力 要件定義のセオリーと実践方法がこれ1冊でしっかりわかる教科書
- 図解まるわかり 要件定義のきほん
- はじめよう! プロセス設計 ~要件定義のその前に
- ユーザのための要件定義ガイド第2版
- はじめよう! システム設計 ~要件定義のその後に
- ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版]
- だまし絵を描かないための-- 要件定義のセオリー
- [改訂第2版] [入門+実践]要求を仕様化する技術・表現する技術 -仕様が書けていますか?
本書は、業務システムやアプリ開発における成功の鍵である「要件定義」の重要性を解説しています。要件定義は、ユーザーと開発者の合意を形成し、UIや機能、データを明確にするプロセスですが、しばしば軽視され、プロジェクトが迷走することがあります。豊富な図解を用いて、要件定義の知識をわかりやすく提供し、さらに「プロセス設計」や「システム設計」についても触れ、業務改善や最新技術の活用に向けた具体的な手法を示しています。読者は、システム設計を自信を持って進めるための理解を深めることができるでしょう。
本書は、システム化企画や要件定義、基本設計などの上流工程に必要なスキルや心構えについて解説しています。単に実装スキルだけでなく、議論をリードし、関係者の合意を得る能力、全体を見通す視点が求められます。上流工程を初めて行う際の準備やスキルアップ方法についても具体的なアドバイスが提供されています。著者は、システム開発の専門家であり、若手エンジニアの育成に力を入れています。
この書籍は、システム開発における重要なプロセス「要件定義」を豊富なイラストや具体例を用いて解説しています。エンジニアやビジネスパーソンが必要な知識を身につけるための内容が詰まっており、要件定義の基礎から各フェーズ(下調べ、業務要求、機能要求、非機能要求、合意と承認)に至るまで詳しく説明されています。著者は人材育成に携わる専門家で、実務に役立つスキルを広めることに努めています。
本書『はじめよう!プロセス設計』は、業務改革やITプロジェクトの効率を向上させるための「プロセス設計」の重要性を解説しています。日常の「モヤモヤ」を解消する鍵として、業務フローの見える化や仕組み化の方法をストーリー指向でわかりやすく紹介。システム開発においては、要件定義が成功の要であることを強調し、技術の選定やシステム設計のポイントについても触れています。幅広い読者に向けた実用的な内容で、業務の効率化を目指す人々に役立つ一冊です。
本書は、IT業界におけるシステム設計の重要性を解説し、特に「要件定義」の重要性を強調しています。システムを効果的に構築するための「UI・機能・データ」の三点セットを「クライアント・サーバ・DB」の三層構造に配置する方法を学びます。また、業務改善や最新技術の活用に向けたプロセス設計の重要性も取り上げ、具体的な手法や実務に役立つ知識を提供しています。システム設計の基礎から応用までを体系的に学べる内容です。
本書は、デザイナーでない人向けのデザイン基本書で、デザインの「4つの基本原則」(近接、整列、反復、コントラスト)を解説しています。プロでなくても、魅力的なデザインやプレゼン資料を作りたい人に最適で、具体的な作例とともに原則を適用する方法を紹介しています。また、日本語版では日本語を使ったデザインの適用方法も解説されています。18年間のロングセラーで、待望の第4版です。
デザインの基本原則をシンプルかつ実践的に解説する一冊です。デザインの経験がない人でもすぐに活用できる具体的なアドバイスが豊富に含まれており、特にレイアウトやフォントの使い方については実用的な例が満載です。デザイン初心者がプロのようなレイアウトを作り出すためのヒントが詰まっており、初心者から中級者まで幅広い層に役立つ内容です。
著者が前著に続き、要件定義の手順と成果物を定式化した本書は、ビジネス要求からシステム要件へのスムーズな移行を目指します。情報システム部門とSIベンダの両者に向けた内容で、要件定義の基本方針や実践方法、非機能要件の定義などを詳述しています。著者はSI業界とユーザー企業での豊富な経験を持ち、業務改革やデータ経営にも従事しています。
この書籍は、ソフトウェア開発における「要求」と「仕様」の重要性を解説し、要求仕様書の作成方法やプロセスを学ぶことを目的としています。内容は、要求仕様に関する問題、具体的な書き方、要件管理と測定技術に分かれており、仕様のトラブルを減らし開発をスムーズに進めるための技術が紹介されています。著者はソフトウェア開発の経験を持つ清水吉男氏で、要求の仕様化技法や派生開発のアプローチを確立した専門家です。
本書は、外資系コンサルタントが身につけるべーシックスキル30個を紹介し、職業や業界を問わず役立つ普遍的なスキルを提供します。新人からベテランまでが使える内容で、15年後にも通用する能力を身につけることを目的としています。著者は自身の経験と元コンサルタントへの取材を基に、実践的な技術や思考法、デスクワーク術、プロフェッショナルマインドを解説しています。
本書は、プロジェクトマネジメント(PM)の基本スキルを習得するためのガイドです。著者は22年の経験を持つプロジェクトマネージャーで、一般的なビジネススキルとしてのPMの重要性を強調し、失敗の原因として基本知識の不足を指摘しています。新規事業やDXに関わるマネージャーやビジネスパーソンに向けて、業種や規模を問わず再現性のあるPMスキルを詳しく解説しています。目次には、プロジェクトの基本から契約、要件定義、デザイン、リリースまでの各ステップが含まれています。
本書は、理解しやすいコードを書くための方法を紹介しています。具体的には、名前の付け方やコメントの書き方、制御フローや論理式の単純化、コードの再構成、テストの書き方などについて、楽しいイラストを交えて説明しています。著者はボズウェルとフォシェで、須藤功平氏による日本語版解説も収録されています。
本書は、システムに詳しくない業務担当者向けに、企業のDX推進に必要なノウハウを解説した教科書です。システムを自ら作れなくても、他者に作ってもらうための技術や判断力が求められる時代において、具体的なプロセスや注意点を示します。内容は、システム構築の計画から実施までの各ステップを網羅しており、著者の実践的な経験に基づく事例も紹介されています。
本書は、情報システムの設計手順を体系化し、ユーザーと開発チームをつなぐ方法を明示します。各工程の目的や作業内容を示しながら、データ、業務プロセス、画面UIの設計を「概要定義から詳細定義へ」「論理設計から物理設計へ」と進める手順を説明します。特定の開発手法に依存せず、実装技術や環境変化に左右されない原理原則を実践に即して解説しています。著者はシステム設計や業務改革に携わる専門家です。
本書は、UIデザインの基本から具体的な実践方法までを体系的に解説しています。デザインの目的や物理的・ソフトウェアの制約、人間の認知特性を考慮し、「わかりやすさ」と「使いやすさ」を追求する方法を示します。デザイナーやエンジニアなど、UI制作に関わるすべての人に役立つ内容です。また、2013年の『UIデザインの教科書』を基に最新の情報に更新されています。
本書は、サーバやインフラの運用・管理に必要な技術や知識を基礎から解説した教科書です。ネットワークやサーバの基本知識に加え、クラウド関連の知識やエンジニアとしての考え方、学習法、スキルアップ、業務知識、職業倫理も取り上げています。これからサーバ/インフラエンジニアを目指す人に適した内容となっています。目次には、エンジニアとしての生き方、ネットワーク、インターネット、サーバ、仮想化、ミドルウェア、Webサービス運用、セキュリティ、クラウド、法律・ライセンスの基礎知識が含まれています。著者は馬場俊彰氏で、豊富な実務経験を持つエンジニアです。
著者がエンジニアリングにおける課題解決のための思考整理法やメンタリング手法を解説する本です。コミュニケーションの不確実性、技術的負債、経営陣とエンジニア間の認識のずれを解消する方法について詳しく述べています。若手を育成し、成長する組織を設計・運営するための実践的なアプローチが紹介されています。著者は技術と経営の接続に関する豊富な経験を持つCTOです。
本書は、ダイレクトリクルーティングを活用したスカウト採用の手法を、プロの視点から解説した指南書です。中途・新卒採用担当者や経営者向けに、成功するためのテクニックやノウハウを紹介し、特にエンジニア採用に関する具体的なアドバイスも提供しています。著者は株式会社VOLLECTの代表で、500社以上のスカウト採用支援実績を持つ中島大志氏です。
本書は、JavaScriptの基礎から実践的な知識までを網羅しており、プログラミング初心者でも現場で役立つスキルを身につけられる内容です。目次には、導入編、基本編(変数、関数、オブジェクト指向など)、実践編(Webページ作成)、応用編(フレームワーク)などが含まれています。著者は技術書やゲーム開発に携わる柳井政和氏です。
この書籍は、Webマーケティングからデジタルマーケティングへの入門書で、ネット活用の基本を解説しています。目次には、ページビューの重要性や顧客理解、トラブル対応などが含まれています。著者はデジタルコンテンツ制作会社の創業者であり、複数の企業でマーケティングに携わった経験を持つ村上佳代と、漫画家の星井博文です。
この書籍は、UXデザインについて「知る」「理解する」「実践する」ことを体系的にまとめた初の日本語書です。内容は、UXデザインの背景や歴史、基礎知識、プロセス、手法に関する章で構成されています。著者は安藤昌也教授で、彼は人間中心設計の専門家として多くの学会に所属しています。
著者小野壮彦は、100社以上のグローバルカンパニーで約5000人のエグゼクティブを評価してきたヘッドハンターであり、人物プロファイリングのノウハウを初公開します。彼の著書では、「人を見る目」を鍛えることができ、適切な人材選びが人生を変える重要性が説かれています。内容は「人を選ぶ意義」から始まり、人の本質を見抜くメソッドや、選ぶ際の注意点などを詳述しています。
バーバラ・ミントが著した本は、コミュニケーション力を向上させるための文章の書き方を紹介しています。内容は、書く技術、考える技術、問題解決の技術、表現の技術の4部構成で、特にピラミッド構造を活用した文書作成法に焦点を当てています。また、構造がない状況での問題解決や重要ポイントのまとめも含まれています。
『独習Python』は、プログラミング初学者向けのPython入門書で、著者は山田祥寛氏です。本書は、手を動かして学ぶスタイルを重視し、Pythonの基本から応用までを体系的に学べる内容となっています。解説、例題、理解度チェックの3ステップで、基礎知識がない人でも理解しやすい構成です。プログラミング初心者や再入門者におすすめの一冊です。目次には、Pythonの基本、演算子、制御構文、標準ライブラリ、ユーザー定義関数、オブジェクト指向構文などが含まれています。
Pythonをしっかり学びたい人向けの本格的な入門書です。基礎から応用まで幅広いトピックをカバーしており、実際に手を動かしながら理解を深められるよう工夫されています。独習スタイルに特化しているため、自分のペースで着実に学びたい人におすすめ。豊富なコード例や練習問題もあり、プログラミングの実力を着実に高めることができます。
本書は、アジャイル開発の基本をストーリー形式で学べる内容で、特に過去にアジャイルに挫折した人にも適しています。主人公の相良真希乃が大手メーカーでの異動を通じて、問題だらけの現場をアジャイル手法で改善していく様子を描いています。アジャイルとウォーターフォールの共存を実現し、チームワークや部署間の連携を促進する方法が紹介されています。読者は、実践的なテクニックやキーワードを通じて、変化に対応し、競争力を高める手法を学ぶことができます。
この書籍は、システムエンジニア(SE)として成功するために必要な知識とスキルをまとめた必読書です。テクニカルスキルやマネジメントスキル、コミュニケーション術、炎上プロジェクトへの対処法などが解説されており、特にIoTやAIの活用に焦点を当てています。著者は、SEの活動領域が広がる中で求められる発想力や戦略立案術、柔軟性についても触れています。全体を通じて、SEとしての心構えや人間力の重要性が強調されています。
この書籍は、Webマーケティングの基本を理解できる内容で、人気のWebコンテンツにオリジナルの解説を加えています。目次には、SEO、Webデザイン、ライティング、SWOT分析、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディア運用など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者はWebライダーの松尾茂起と、イラストレーターの上野高史です。
Webマーケティングといえばこの書籍。ストーリ形式でWebマーケティングについて学べるのでサクサク読めてそれでいてWebマーケティングのエッセンスがギュッと詰まっている。それもそのはず超有名マーケターのWebライダー松尾氏が著者。Webマーケティングを学びはじめた初学者はまず手にとって欲しい書籍。ちなみにWebマーケティングの中でもかなりSEO・オウンドメディア運営にフォーカスしているので広告などについて学びたい人には向かない。
この本は、プログラミング初心者向けに、PHPとMySQLを楽しく学べる方法を提供しています。秋葉原での速習コースを基に、挫折しやすいポイントを分析し、1日でWeb画面と簡単なデータベースを作成できる内容です。目次には心の準備、パソコン設定、プログラミング、データベースの各章があり、著者は豊富な経験を持つ谷藤賢一氏です。
本書は、著者が過去に執筆したデータベース設計に関する人気記事を再編集し、さらに実際の題材を用いたERD作成のサンプルを8種類提供しています。内容は、データベース設計の基礎やRDBMSの重要性、実践的なERDレッスン、付録としてSQLの解説やボトルネック対策などが含まれています。著者の羽生章洋は、豊富な業務経験を持つIT業界の専門家で、現在は株式会社スターロジックのCEOを務めています。
この書籍は、上流工程の重要な局面である「基本設計」に焦点を当て、実用的なモデリングパターンや避けるべきアンチパターンを豊富な用例と共に解説しています。内容は、上流工程の困難、進め方、基本設計の概要、モデリングパターンの具体例などで構成されています。著者は新潟出身の渡辺幸三で、業務支援システムの設計・開発に従事しています。
本書は、サービスデザインを実践するための完全ガイドであり、リサーチから実装、組織への根付かせ方までの手法と事例を約600ページにわたって詳述しています。顧客体験の向上や持続可能なビジネスの創出に関心のあるビジネスパーソンに向けて、世界中の実践者の知見が詰め込まれています。目次には、サービスデザインの基本やプロセス、ワークショップのファシリテーションなどが含まれています。
本書『新人エンジニア向け教科書』第3版は、システム開発の基礎知識をゼロから解説する入門書です。新人エンジニアや学生を対象に、ウォータフォール型とアジャイル型の開発手法の特徴や違いを学べる内容となっており、アジャイル型開発の解説が大幅に加筆されています。また、開発過程での文書作成手順や演習課題も用意されており、現役エンジニアや研修担当者にも役立つ一冊です。
『デザインパターン』の23個のパターンをオブジェクト指向初心者向けに解説した書籍で、Javaのサンプルプログラムを掲載。新たに「デザインパターンQ&A」も追加されている。目次はデザインパターンの基本から、サブクラスの利用、インスタンス作成、構造管理など多岐にわたる。
この本は、45カ国のイノベーターによるビジネスモデルの革新を実践するためのガイドです。3Mやデロイトなどの一流企業で使用されるテクニックを紹介し、ビジネスモデルを9つの要素に分解して理解を深めます。豊富な事例とグラフィックを用いて、ビジネスモデルの設計や実行を系統的に学ぶことができ、戦略的思考を視覚化する「ビジネスモデルキャンバス」を活用した新しい発想法を提供します。著者は小山龍介で、彼の経験を基にした内容です。
本書は、システム開発における設計の基本知識を解説した14年ぶりのリニューアル版です。エンジニアが「はじめての設計」に挑戦する際の課題(アプリケーション設計、データベース設計、画面設計、外部システム接続、アーキテクチャ設計)を事例を交えて紹介し、実践的なノウハウを提供します。また、アジャイルやマイクロサービスに関する新しい情報も追加されています。若手エンジニアのステップアップやリーダーシップ向上を目指す一冊です。
本書は、新人や経験の浅いテストエンジニアが実務で「ソフトウェアテスト技法」を効果的に活用するための実践的な問題集です。各章では、同値分割法、境界値分析、デシジョンテーブル、状態遷移テスト、組合せテストをテーマにした具体的なシチュエーションが取り上げられ、テスト技法の理解を深めることを目的としています。企業の新人研修や個々のスキルアップにも利用可能です。
本書は、急成長中の採用・人事業務代行会社の社長が、ベンチャー企業や中小企業向けに「本当にほしい人材」を集めるための実践的メソッドを解説しています。著者は350社以上の採用活動を支援し、自社も急成長を遂げた経験を基に、中途採用の戦略を紹介。具体的には、採用広報、スカウト文の作成、面接方法など、戦略的なアプローチが必要であると強調し、採用に悩む企業に有益な手法を提供しています。
本書は、Webサイトの運営や成長に悩む人々に向けて、データの見方や施策の打ち方を解説した指南書です。内容は、ゴール設定やデータ分析の基礎から、具体的な施策(自然検索、メールマガジン、ソーシャルメディアなど)の改善方法、分析結果の活用法、Googleアナリティクスの設定・操作方法まで幅広くカバーしています。著者はウェブアナリストの小川卓氏で、実践的なスキルを身につけるための必携書です。
本書では、著者の西口一希氏が「顧客起点マーケティング」の重要性を説き、特に一人の顧客(N1)の分析を通じて効果的なマーケティングアイデアを導き出す方法を紹介しています。著者はP&Gやロート製薬、スマートニュースでの成功経験を基に、顧客ピラミッドや9セグマップといったフレームワークを用いて、ターゲット顧客の可視化や競合分析を行う手法を解説します。具体的には、未購買顧客を顧客化し、ロイヤル顧客に育てるための戦略や、デジタル時代における顧客分析の重要性についても触れています。
期待度が高かっただけあって、それほど学びがなく残念だった。顧客一人にフォーカスしたN1分析は確かにデータ分析の初期シーンでよく使うので考え方としては分かるが、そこからマーケティングに転化していくイメージがあまり湧かなかった。
『プリンシプル オブ プログラミング』は、プログラマーが3年目までに身につけるべき101の原理原則を紹介するガイドブックです。KISSやブルックスの法則など、古今東西の知恵を集約し、質の高いプログラミングを実現するための基本的な考え方や手法をわかりやすく解説しています。初心者から脱却したいプログラマーに最適な一冊です。著者は上田勲で、キヤノンITソリューションズでの豊富な経験を持っています。
本書は、リファラル採用の成功法則を提唱する鈴木貴史氏によるもので、企業が競争を避け、採用活動の効率を高める方法を紹介しています。著者は、日本でリファラル採用の概念を創出した起業家であり、企業が従来の手法に頼らず、社員を巻き込んだ採用戦略を実現することを目指しています。具体的には、企業ブランドへの共感を呼び起こし、採用コストを削減し、従業員のエンゲージメントを高めることが可能です。本書は、戦わない採用の実践方法や成功事例を通じて、企業の変革を促す内容となっています。
本書は、経営計画と整合した情報システムの構築方法を紹介し、経営効果を高める手段としての重要性を強調しています。目次では、経営計画の実現から情報システム要件の立案、全体推進計画の策定までの具体的なフェーズが示されています。著者の柴崎知己は、システム戦略やITマネジメントに関する豊富な経験を持つ専門家です。
先を制してライバル企業に勝つためのポイントとは?決算を早期化して利益を稼ぎだすには?業務改革で会社をよみがえらせるには?最高のシステムをつくるための「亀のコウラ」とは?ベンチャーから中堅企業まで50社以上、業務設計・改善から会計監査さらにIPO支援まで20年近いコンサルティング実績を誇る「公認会計士兼システムコンサルタント」という異色の著者だからこそ書ける成功のノウハウが満載! 第1章 「稼げるシステム」と「稼げないシステム」の分かれ道はどこにあるのか? 第2章 先を制してライバル企業に勝つ"経営の視点" 第3章 決算を早期化して利益を稼ぎ出す"会計の視点" 第4章 業務改革で会社をよみがえらせる"業務の視点" 第5章 正しい知識で最高のシステムをつくる"システムの視点" 第6章 プロジェクトを成功に導き、会社を飛躍させよう
本書は、Webアプリケーション開発におけるフロントエンドエンジニア向けに、テストの基本知識と実践手法を解説したものです。自動テストの重要性を強調し、具体的なテストコードの書き方や手法、ツールの使い分けを学べます。UIコンポーネントテストやビジュアルリグレッションテストなど、フロントエンド特有の課題に焦点を当て、サンプルアプリケーション(Next.js)を使ったハンズオン形式で進められます。テストを始めたいが方法がわからないエンジニアに最適な内容です。
本書は、ソフトウェアアーキテクチャの重要性と、効果的なアーキテクチャを設計・構築・維持するためのスキルや知識を現代的視点から解説しています。内容は、アーキテクチャの基礎、アーキテクトの役割、アーキテクチャスタイル、チームとのコラボレーションに必要なソフトスキルなど多岐にわたり、実践的な例を交えて説明されています。著者は経験豊富なアーキテクトたちで、読者がソフトウェアアーキテクトとして成長するための道筋を示しています。
本書は、Webサイトのデザイン改善に関する実際の事例やTipsを提供し、継続的な改善のためのヒントを集めています。著者たちは、Before&Afterのデザイン事例や汎用的な改善策を解説し、様々なサイトで再現可能なポイントを紹介しています。最後の章では、プロが行う改善プロセスとその考え方についてまとめています。内容は初心者から上級者まで幅広く役立つ情報が含まれています。
この書籍は、ITインフラの基礎知識を包括的に解説しており、サーバー、OS、ネットワーク、ストレージ、仮想化、クラウド、データセンター、セキュリティ、運用などの最新情報が含まれています。新入社員やインフラエンジニアを目指す人に推奨される入門書です。著者は富士通やLINEでの豊富な経験を持つ佐野裕氏です。
本書は、Googleで発展した「サイトリライアビリティエンジニアリング(SRE)」の手法について解説しています。SREは大規模なサイトの運用と構築に関する方法論で、リスク管理やサービスレベル目標、インシデント管理などを通じて、高い信頼性を持つサービスの運用方法を示します。著者はGoogleのSREチームのメンバーで、実践的なストーリーを通じて、ソフトウェアのライフサイクル全体をカバーしています。エンジニアにとって必携の一冊です。
学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。
本書は、AI時代に必要な「プロジェクトマネジメント」のスキルを小中学生向けに解説しています。身近なプロジェクト(自由研究やサプライズなど)を通じて、目標設定、計画立案、実行、リーダーシップの重要性を学びます。ストーリー漫画、図解、体験ワークを用いて、子どもたちが未知の課題に挑む力を育成する内容です。著者はプロジェクトマネジメントの専門家で、実践的なスキルを身につけることの重要性を強調しています。
新規事業・DXなどどんなプロジェクトでも成功に導く本物のプロジェクトマネジメント力を身につけようあらゆるビジネスを円滑に進めるうえでは欠かせないプロジェクトマネジメント(PM)。そこで求められるのは組織力・コミュニケーション能力・リーダーシップの3つです。PMの世界ならではこれらの能力を高めるコツがあるのですが、多くの人がそれを知らずにプロジェクトのリスクを高めてしまったり、炎上したりしてしまうことが後を絶ちません。そこで本書では、だれでも組織力・コミュニケーション能力・リーダーシップを高められる考え方と行動を丁寧に解説します。プロジェクトマネージャー一筋23年の著者がこれまでに経験した失敗から学び得たあらゆる知見を注ぎ込み、まとめました。さらに本書ではPMとしてキャリアを高めていく方法についても詳しく紹介しています。著者の第一作『プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本』ではPMスキルの全体像を見渡しました。本書ではプロジェクトを実際に推進する「本物の実力」を身につけるための神髄が詰まっていますとくに次のような方々にとっては手元に置いておきたい一冊です。・新規事業やDXに携わるマネージャー・受託プロジェクトのマネージャー・キャリアアップを図りたいプロジェクトメンバー・プロダクト開発に挑戦するスタートアップの経営者、エンジニア、デザイナー・PMの基本を学び直したいビジネスパーソン●目次概要序章 本物の実力をつけるための基礎知識第1章 不安を乗り越える第2章 組織力を鍛える――「プロジェクト的な働き方」を実現するための考え方第3章 コミュニケーション能力を鍛える――チーム・組織と信頼関係を構築するための考え方第4章 リーダーシップを鍛える――長期にわたって自身のメンタルを維持するための考え方第5章 キャリア構築力を鍛える――プロジェクトの点と線をつないで仕事を社会に広げていく考え方●著者略歴橋本将功(はしもと・まさよし)。パラダイスウェア株式会社 代表取締役。早稲田大学第一文学部卒業。文学修士(MA)。Webサイト/Webツール/業務システム/アプリ/組織改革など、500件以上のプロジェクトのリードとサポートを実施。世界中のプロジェクトの成功率を上げて人類をよりハッピーにすることが人生のミッション。著書に『プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本』(翔泳社、2022)。 はじめに序章 本物の実力をつけるための基礎知識 本章のテーマ なぜ日本は行き詰まっているのか 「失われた30年」と IT革命 人材・ITへの投資が行われなかった なぜ日本は労働生産性が低いのか ルーチンワーク型の考え方が企業・教育に浸透している IT人材がIT業界に偏っている 経験の浅いクライアントが決定権をもちがちな業界構造 プロジェクト的な働き方がこれからの社会の生命線 メタ認知は個人だけではなく組織にも欠かせない プロジェクトに必要な5つのメタ認知 Q&A 若い世代と働き方の感覚が違い、どのように育成すればよいかわかりません第1章 不安を乗り越える 本章のテーマ プロジェクトマネージャーが抱える不安 不安なのはプロジェクトマネージャーだけではない 不安を誰かに押し付けると失敗する 不安を無視すると失敗する どうやって不安と戦うか 集団思考のリスクを回避する プロジェクトマネージャーとまわりの関係者との認識のギャップ 認識のギャップへの対策 燃え尽きないための時代のとらえ方 羅針盤をもつ プロジェクトにおける功利主義 Q&A 1人で任せれたプロジェクトが不安でたまりません第2章 組織力を鍛える――「プロジェクト的な働き方」を実現するための考え方 本章のテーマ シリコンバレー企業のまねは無理がある トレンドに翻弄されない 強引な組織変革がもたらす弊害 プロジェクトが得意な組織の3つの考え方 ルーチンワークとプロジェクトの違い ルーチンワークとプロジェクトの違いによる組織内対立 組織変革成功のヒント1 組織とプロジェクトのマネジメントを切り分ける――業務量の観点 組織変革成功のヒント1 組織とプロジェクトのマネジメントを切り分ける――人材適正の観点 組織とプロジェクトのマネジメントの理想的な関係 組織とプロジェクトのマネジメントの相補的な関係 組織とプロジェクトのマネジメントバランスの取り方 ルーチンワーク型企業にプロジェクトを取り入れるパターン プロジェクト型企業に組織マネジメントを拡大するパターン 組織変革成功のヒント2 人材評価の考え方を変える 評価軸を設定する 受託開発のプロジェクトの評価軸 新規事業・サービス開発のプロジェクトの評価軸 DX(業務改革・組織改革)のプロジェクトの評価軸 組織変革成功のヒント3 適切な育成とモニタリングの環境を整える 人材の育成環境を整備する際の注意点 体系的な知識と現場での習得をセットにする ドキュメントのテンプレート化を促進する メンタリングの仕組みを整備する モニタリングを整備する際のポイント 適性と経験を見極める 適性の見極め方 行動特性の4つの評価軸 経験の見極め方 Q&A プロジェクトを任せている有望な若手から転職したいと申し出され困っています第3章 コミュニケーション能力を鍛える――チーム・組織と信頼関係を構築するための考え方 本章のテーマ なぜ正しいコミュニケーションがとれないのか ブリリアント・ジャークにならない コミュニケーションには機能と目的がある コミュニケーションの機能と目的1 目的・目標・計画の明確化と共有 コミュニケーションの機能と目的2 進捗確認と共有 コミュニケーションの機能と目的3 発生した課題やトラブルの解決 コミュニケーションの機能と目的4 情報の共有 コミュニケーションの機能と目的5 チームの雰囲気の向上と維持 「強い言葉」が物事をよくすることはない エビデンスとファクトで冷静かつ論理的に話す 「信用ポイント」を貯める 「信用ポイント」が貯まる4つの観点 Q&A新しい会社にプロジェクトマネージャーとして入社しましたが、コミュニケーションスタイルの違いに困惑しています第4章 リーダーシップを鍛える――長期にわたって自身のメンタルを維持するための考え方 本章のテーマ プロジェクトにおけるリーダーシップとは リーダーが果たすべき役割 適切なリーダー像をもつ 「リーダーの孤独」に対処する 孤独感への対策1 孤独感に対する覚悟を決める 孤独感への対策2 「横のつながり」をつくる 孤独感への対策3 メンターを探す 防衛戦や撤退戦への4つの取り組み方 防衛戦・撤退戦の取り組み方1 防衛戦・撤退戦であることを周囲と共有する 防衛戦・撤退戦の取り組み方2 勝利条件と防衛ラインを決める 防衛戦・撤退戦の取り組み方3 計画を立てて粛々と実行する 防衛戦・撤退戦の取り組み方4 振り返りを組織にフィードバックする リーダーのストレスマネジメント ストレスマネジメントのコツ1 ストレスの性質を知る ストレスマネジメントのコツ2 手の抜き方を覚える ストレスマネジメントのコツ3 ONとOFFを切り替える ストレスマネジメントのコツ4 働く環境を変える Q&A プロジェクトマネジメント業務でたまったストレスをうまく発散できておらず、健康面での不安がつのっています第5章 キャリア構築力を鍛える――プロジェクトの点と線をつないで仕事を社会に広げていく考え方 本章のテーマ ハイリスク・ハイリターンな仕事であることを知っておく キャリアは環境選びが大切 プロジェクトを軸としたキャリア設計の歴史は浅い キャリアを考える際の3つの観点 キャリアを考える観点1 安定性と柔軟性 キャリアを考える観点2 カルチャーとモラル キャリアを考える観点3 報酬と利益の分配 プロジェクトを軸に据えたキャリア形成のための考え方 プロジェクトマネジメントの習熟レベル 4タイプのプロジェクト環境Q&A いずれはプロジェクトマネージャーやプロダクトマネージャーになりたいと思っていますおわりに 著者略歴
本書は、組織内の問題を「わかりあえないこと」から解決するためのアプローチを提案しています。著者は、対話を通じて新たな関係性を築くことが重要であるとし、組織の複雑な問題に対する実践的な手法を示しています。特に、ナラティヴ・アプローチを用いて、権力や対立を超えたコミュニケーションを促進する方法を解説。経営学者である著者のデビュー作であり、多くの読者から高い評価を受けています。
本書は、企業が直面する「変革を担う人材がいない」という課題に対し、リーダー育成とビジネス変革を同時に進める「育つ変革プロジェクト」を提案しています。著者は具体的な事例を交え、プロジェクトの立ち上げや推進方法、人材育成のノウハウを詳細に解説。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業に向けた実践的な内容となっており、組織全体での学びの拡大も強調されています。
本書は、ハーバード・ロースクールの交渉学を基に、日本人向けに実践的にアレンジされた入門書です。交渉の成功に必要な原則や、感情や心理バイアスの影響、パワープレーへの対処法、事前準備の方法論、交渉の進め方、コンフリクト・マネジメントについて具体的に解説しています。著者は田村次朗と隅田浩司で、いずれも法学の専門家です。
バグの分類 フローグラフとパステスト法 トランザクションフローテスト法 データフローテスト ドメインテスト メトリックスと複雑性 パス、パス積、正規表現〔ほか〕
著者は外資系コンサルタントとして12年間の経験を持つ元バンドマンで、初の著書を通じて「最速仕事術」を紹介しています。内容は、仕事のスピードや論点思考、説得力のある品質の重要性、会社の集合知の活用法など、幅広い業界で役立つ秘訣が盛り込まれています。特に、社会人1年目に知っておきたい実践的な知識が詰まった一冊です。
この図解入門書は、システム開発における要求定義の手順やスキルを豊富な図解と事例で解説しています。要求定義はシステムの品質を決定づける重要な工程であり、国内外の開発手法の違いも考慮されています。著者はコミュニケーションを重視し、要求定義のノウハウを技術者やエンジニアに伝えることを目的としています。内容は、要求定義の位置づけ、事前情報、要求の獲得・分析・取りまとめ、検証と変更管理、実例の紹介に分かれています。著者は豊富な経験を持つコンサルタントで、システム開発に関する研修や講演も行っています。
本書は、UNIXのユニークなコマンド組み合わせ技術を学ぶためのガイドで、初心者から上級者まで多様な内容を含んでいます。各章では、ファイルシステム、シェルの利用、プログラミング、文書作成など、UNIXの基本から応用までを網羅しています。著者は、UNIXの知られざる機能に驚かされ、自身の知識を深めることができたと述べています。付録にはエディタの要約や関連マニュアルも含まれています。
日本語の「採用」と英語の「リクルートメント」の定義のちがいを手がかりに考察を展開。採用の戦略を多面的に分析した包括的研究。 日本語の「採用」と英語の「リクルートメント」の定義のちがいを手がかりに考察を展開。日本的雇用の特殊性を考慮した「採用のホィールモデル」を構築し、採用の戦略を多面的に分析した包括的研究。 人材の“Buy and Make”の新たな戦略モデル! 未曾有の人材獲得難を突破するには、新たな方法論が必要だ。分断された日本の外部労働市場と内部労働市場を「ホィール」によって結合し、繰り返しの中で採用力を高めていく。 新卒、中途、パート採用からアメリカ企業・フランス企業のタレント獲得までを網羅した総合研究。 ▼「新卒採用」への過度な偏重から脱却し、働き方改革やタレントマネジメントなど新たなパラダイム取り込んだ画期的な採用論。 ▼日本語の「採用」と英語の「リクルートメント」の定義のちがいを手がかりに考察を展開。日本的雇用の特殊性を考慮した「採用のホィールモデル」を構築し、採用の戦略を多面的に分析した包括的研究。 人口減少やデジタライゼ―ションにより、空前の「売り手市場」が発生し、いまや熾烈な人材獲得競争に勝ち抜くことが企業にとっての生命線となっている。今後、採用の戦略は、中途採用、パート採用、ときには海外でのタレント獲得も含めて立案しなければならない。その際、新卒や中途といった採用対象による分類から「攻めの採用」「守りの採用」という採用目的による分類へ、さらには外部労働市場の募集・選考プロセスに限った「小さな採用」論から、企業内部の雇用の仕組みも考慮した「大きな採用」論へと発想を切り替える必要があることを、本書では提示する。 第1章 二つの「戦略」 第2章 人材獲得競争の激化 第3章 日本企業の採用行動 第4章 採用のパターン 第5章 採用の成果 第6章 「採用のホィールモデル」の構築 第7章 「採用のホィールモデル」の検証 第8章 次世代リーダーの獲得――グローバルメーカーA社の変革事例 第9章 新卒・中途・有期雇用の採用はどう異なるのか 第10章 日本・フランス・アメリカ企業のタレント獲得 第11章 採用活動のフィードバックループ――日米企業の比較から 第12章 過去と未来 おわりに 参考文献 事項索引 人名索引
本書は、企業のIT担当者が必要とする基礎知識を解説しています。内容は、パソコンや周辺機器の調達、社内インフラの整備、情報セキュリティの強化、業務システムの導入、システム開発の外部委託に関する5章から構成されています。各章では、専門的な知識が求められるテーマを取り上げ、IT業務に携わる初心者向けに必要最低限の情報を提供しています。著者は、豊富な経験を持つエンジニアたちです。
この書籍は、プロジェクトの立ち上げ期に焦点を当て、「反常識のプロジェクト成功法」を解説しています。実際の企業事例やツール、当事者の声を交えて、視覚的に理解しやすく説明しています。内容は、変革の概要、現状調査・分析、将来のビジョンの構築、計画の価値を示すためのステップに分かれており、著者は両名ともコンサルタントとして多様な業界での改革に関与しています。
本書は、体系的かつシンプルなロジカル・コミュニケーション技術を習得することを目的としています。著者たちは、訓練を通じて誰でもこの技術を身につけられると確信しています。内容は、伝えることの重要性や論理的思考の整理、構成技術に関する具体的な方法を提供しています。著者は共にマッキンゼーでの経験を持ち、コミュニケーション戦略やトレーニングに従事しています。
本書は、効果的な採用を実現するための新しいアプローチを提案しています。採用担当者が直面する課題—人材が集まらない、選考がうまくいかない、離職が多い—を解決するために、リクルートメント・マーケティングを基にした戦略的な採用プロセスを紹介します。具体的には、候補者との接触を重視した「ソフトな選考」や、採用後のフォローアップを強調し、採用の好循環を築く方法を探ります。特に新卒一括採用が主流の日本において、現代的な採用手法を学ぶことができる内容です。
この書籍は、テクノロジーの進化に伴う世界の変化を捉え、デザインにおける「自己帰属感」を中心に据えた設計手法を探求しています。UXやIoTの本質を理解したい人に向けて、情報を基盤としたデザインの考え方を解説しています。著者の渡邊恵太は、インタラクションデザインや身体性を活かした手法の研究を行っている専門家です。
この本は、iOSプログラミング初心者向けの詳細な入門書であり、プログラミング経験がゼロでも理解できるように丁寧に解説されています。Swiftとアプリ開発の基本を習得できる内容で、Xcode 11やiOS 13.5、SwiftUIに対応しています。アプリ開発は副業にも最適で、リスクなく始められ、収益を上げる方法も紹介されています。著者はiPhoneアプリ開発の経験が豊富で、数々の成功作を持っています。
『要点で学ぶ、デザインの法則150』シリーズの新刊は、複雑な問題を解決するための100の手法を簡潔に学べる一冊です。人間中心設計に必要なリサーチ手法やデータ分析法を、見開きでわかりやすく解説。マーケティングやデザインの現場で役立つ内容で、説得力のある提案やユーザーに役立つサービスを生み出すために活用できます。
「はじめて「スクラム」をやることになったら読む本」は、スクラムを実践するための手引きとして増補改訂されました。スクラムの基本概念やルールをわかりやすく解説し、架空の開発現場を題材に実践的なプラクティスを紹介しています。2017年版のスクラムガイドに対応し、最近の開発現場に向けた内容に更新されています。これからスクラムを始める人や導入に苦労している人に適した一冊です。
本書は、日本の著名なITアーキテクトである著者が、30年の経験を基にエンタープライズアーキテクチャ(EA)の実践手法を解説しています。特に「EAの中心に全社データHUBを据える」という考え方が中心テーマで、ITマネジメント賞を受賞したアーキテクチャの全貌が紹介されています。内容は、問題の所在や課題、アーキテクチャの各要素、戦略・戦術ソリューションに分かれており、ユーザ企業やITベンダにとって貴重な知識となるでしょう。著者は協和発酵キリンでの豊富な経験を持ち、システム構築に貢献してきました。
この書籍は、プロフェッショナルな情報アーキテクチャ(IA)を活用した問題解決アプローチを紹介しており、著者の坂本貴史が「坂本式」思考プロセスを通じて解説しています。内容は、IAの基本スキルや情報分類、サイト構造、ナビゲーションパターン、ユーザー行動、ワイヤーフレーム設計、ケーススタディなど多岐にわたります。坂本はネットイヤーグループでIA/UXデザイナーとして活動しており、コンサルティングやWebサイト構築の専門家です。
この書籍は、デジタル広告市場におけるGoogleとFacebookの重要性を強調し、それに基づく広告戦略の構築を提案しています。内容は、広告の準備と計画、検索広告の機械学習活用、ディスプレイ広告のクリエイティブの重要性、Facebook広告のコンバージョン学習、そして評価と改善のプロセスに分かれています。著者は、SEMの専門家であり、実務経験を基にした実践的なアドバイスを提供しています。
本書は、ビジネスプロセスマネジメント(BPM)の重要性を解説し、業務理解の入門書としての役割を果たしています。前著『ビジネスプロセスの教科書』を基に、デジタル化や経営環境の変化に対応した内容を提供し、全体の7割をアップデートした大改訂版です。各章では、顧客の期待に基づくプロセスの重要性、問題解決のポイント、ビジネス構造の理解、デジタル化の影響、業務の詳細な分析、仕事の価値の明確化、プロセス変革の方法、ネットワークによる共創について述べています。著者は、ビジネスプロセスマネジメントの実践的な知識を提供し、経営者や業務担当者の疑問に応えています。
この書籍は、雑談の技術を通じて人間関係を深める重要性を説いています。雑談力を身につけることが、現代社会で生き抜く力になると強調し、学校や職場で役立つ50のアイデアを提供しています。内容は、雑談のルールやマナー、鍛え方、ビジネスでの活用法、達人からの学びなど多岐にわたります。著者は明治大学の齋藤孝教授で、教育学やコミュニケーション論を専門としています。
「日本インタラクティブ広告協会(JIAA)」がまとめたこの手引書は、インターネット広告の歴史、業界構造、最新技術、効果指標、広告品質向上の取り組みなどを詳しく解説し、プロフェッショナルに必要な知識を提供します。戦略立案に役立つ内容で、ネット広告の理解を深めることができます。
この書籍は、デジタルマーケティングにおける「定石」を整理し、成果を上げるための施策パターンを詳しく解説しています。内容は、デジタルの特性や限界、各フェーズにおける定石の理解、そしてそれをビジネスモデルに適用する実践方法に分かれています。著者は、デジタルマーケティングの専門家であり、AIを活用した分析ツールの開発にも携わっています。
この書籍は、初めてSNSを運用する人向けに、予算をかけずに効果的なソーシャルメディアマーケティングの方法を解説しています。内容は、SNSマーケティングの基本から、各プラットフォーム(Facebook、Twitter、Instagramなど)の活用法、マーケティングの分析と改善、成功事例まで多岐にわたります。著者はIT企業での経験を持つ清水将之氏です。
この入門書は、Webアプリケーション開発の基礎を学ぶためのもので、通信技術とソフトウェア開発技術の両方からWebシステムの仕組みを詳しく解説しています。内容は、Webアプリケーションの定義、発展の歴史、HTTPの理解、CGIからの進化、構成要素、効率的な開発手法、セキュリティ対策などが含まれています。著者はウルシステムズのシニアコンサルタントで、オープンソースソフトウェア開発にも関与しています。
本書は、Laravelフレームワークの入門書で、最新バージョンに対応して改訂されています。内容は、Laravelのインストール、MVCの使い方、各種機能の解説を含み、新しいディレクティブやバリデーションルール、Bootstrapによるページネーション、認証機能などが追加されています。著者は、さまざまなプラットフォーム向けにプログラミング初心者向けの書籍を執筆している掌田津耶乃です。
本書は、高橋寿一氏による「開発者テスト」の実践ガイドで、ウォーターフォールやアジャイル開発における上流品質の向上を目指します。開発者が行うべきテスト手法(単体テスト、リファクタリング、テストの自動化など)を実例を交えて解説し、アジャイル開発に特化した内容も強化されています。著者の豊富な経験を基に、現場で必要な手法と学術的な根拠を提供する一冊です。
「要件定義」に関するよくある質問
Q. 「要件定義」の本を選ぶポイントは?
A. 「要件定義」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。
Q. 初心者におすすめの「要件定義」本は?
A. 当サイトのランキングでは『はじめよう! 要件定義 ~ビギナーからベテランまで』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで130冊の中から厳選しています。
Q. 「要件定義」の本は何冊読むべき?
A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。
Q. 「要件定義」のランキングはどのように決めていますか?
A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。








![『ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51HKaOqL-RL._SL500_.jpg)

![『[改訂第2版] [入門+実践]要求を仕様化する技術・表現する技術 -仕様が書けていますか?』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51hV6os4M5L._SL500_.jpg)







![『UIデザインの教科書[新版] マルチデバイス時代のインターフェース設計』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51cob3qUaTL._SL500_.jpg)






![『JavaScript[完全]入門』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51X+EGiSlYL._SL500_.jpg)